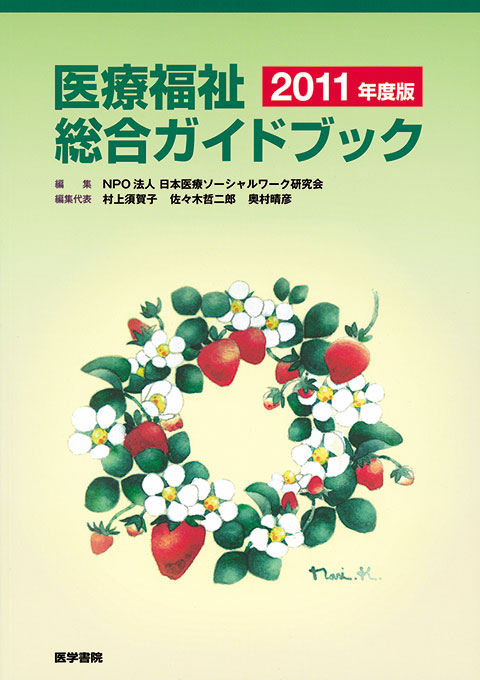医療福祉総合ガイドブック 2011年度版
めまぐるしい現場レベルでの変化をフォロー。医療福祉サービス一覧の2011年度版
もっと見る
医療・福祉サービスの社会資源を、利用者の視点で一覧できるガイドブックの2011年度版。法律や省令レベルでの制度枠組みの解説にとどまらず、通知レベルの最新情報を従来通りフォロー。毎年の内容見直しに加え、配列の変更や相互参照の充実を図り、利用者からの相談により素早く、確実に対応できるよう配慮した。保健・医療・福祉関係者必携の1冊。
本書は2011年2月末日(一部、3月15日)までに把握できた情報をもとに構成しております。本書の発行後にも法律の改正や制度の変更が行われる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
本書は2011年2月末日(一部、3月15日)までに把握できた情報をもとに構成しております。本書の発行後にも法律の改正や制度の変更が行われる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
| 編集 | NPO法人 日本医療ソーシャルワーク研究会 |
|---|---|
| 編集代表 | 村上 須賀子 / 佐々木 哲二郎 / 奥村 晴彦 |
| 発行 | 2011年04月判型:A4頁:312 |
| ISBN | 978-4-260-01320-8 |
| 定価 | 3,520円 (本体3,200円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
はじめに
「格差社会」―─時代と世の中のありようを言いあらわすキーワードとして,ひと頃盛んに使われたこの形容は,昨2010年は「無縁社会」へと改められた感があります.
「格差社会」―─それは,大多数を占めた中流層の崩壊と貧富の差の拡大,すなわち「努力するものが報われる」という意識が人々から消失したことを意味します.それは,労働の報酬が生活保護基準にも満たない「ワーキングプア」や,職と住居を失った人びとのための「年越し派遣村」に象徴されます.旧来の社会保障のしくみが機能しなくなった脆い社会が映し出されています.ここでは,働く人がいとも容易に雇用・所得・居住を奪われる事態に直面する様が,他人ごととは思えない切迫感を伴って露呈してきました.
そして,「無縁社会」が2010年を表すキーワードにあげられました.3万人を超す自殺者が13年間連続し,虐待,そして所在不明の高齢者の続出,孤独死など…….希薄になったといわれてきた人びとの結びつきや相互扶助の関係が,すでに断ち切られたかの衝撃を与える事件・事故の報が相次ぎました.さまざまなセイフティネットが機能しなくなっているといえます.「格差社会」では社会保障のしくみが機能不全に陥っていることを,「無縁社会」ではインフォーマルな相互扶助さえも希薄化したことをあらわにしました.
自殺は,失業・失職・無収入・債務・住居・疾病・うつといった生活問題が連動した結果であると考えられます.それゆえ2009年にはハローワークに仕事・多重債務・健康問題に対応する総合的相談窓口である「ワンストップ・サービス・デイ」が設けられました.思いもよらない生活上のつまずきが“死に至るまでの連鎖”となることを断ち切るために,このワンストップ相談対応は有効です.しかし,残念ながら2010年は本格的に実施されることはありませんでした.無縁社会からの再生に向け,社会・経済をはじめさまざまなシステムの見直しが今後求められるでしょうが,早急な方策はワンストップの相談・支援のしくみが重層的に設けられることであると考えます.
本書の執筆を担った医療ソーシャルワーカーたちは,病院などで生活問題を中心に患者さんや家族の相談に当たっています.「それは,私の管轄外です」とたらい回しにすることなく,保健・医療・福祉制度全般にわたって幅広く情報収集したものを,患者さんや家族のよりよい問題解決のために活用します.ワンストップの相談・支援を日々実践しているのです.制度そのものの枠組みさえも改変されつつあるこの時代,その情報の正確さを保つためには,日々の絶え間ない努力が要求されます.
若いソーシャルワーカーたちから「この本は私のバイブルです」と言われ,読者からは「『家庭の医学』みたいな本だね」と言われれば,本書を編集した医療ソーシャルワーカーたちは,出版継続のための自らの責務を実感せざるを得ません.
2007年度版から,身体・知的・精神障害の3つの障害を統合した障害者自立支援法に沿って精神科医療を「医療サービス」の章に統合しました.総合的なわかりやすい医療サービスガイドとして,第II章に位置づけました.また,2010年度版からは,コラムを毎年更新し,利用者の声や医療ソーシャルワーカーの意見表明も加え,バラエティ豊かなものとしています.そして,この2011年度版では,従来「お金のこと」としていた第III章を「生活費と仕事」と,新しく位置づけています.これまでも生活費と雇用の問題を1つの章に収めてはいましたが,雇用と所得は不可分の生活課題であるとの認識をより明確にして,内容を見直しています.それは,このガイドブックにおいても「ワンストップ相談対応」を具現したいという想いからです.ともすれば堅苦しくなりがちな本文に,ところどころ配したイラストが好評でした.医療現場に従事しているイラストの書き手が伝えるリアルな温もりが,ホッとさせてくれます.毎年のリピーター読者に感謝して,今回は大幅にリニューアルしました.
日本社会の地域間格差が,生活への深刻な影響を与えています.ある障害児のお母さんから寄せられた声を紹介します.このガイドブックに掲載されている制度について役所に問い合わせたところ,「うちの市ではやってません」との答えで,ほかの地域には存在する制度がわが市にはないことが確認できた,とのことでした.このように,社会資源にも「地域間格差」があることを明確にするために,2008年度版からは法的な根拠を掲載することに努めました.各地で格差是正を求める活動が進められ,本書がそれを応援する力になり得れば,執筆者たちの大いなる喜びです.
このガイドブックを利用してくださった読者の方々から,ご意見や新しい情報をお寄せいただければ幸いです.次年度版に反映いたします.
本書前身の初版発行より,本書のもつ社会的使命を共有してくださり,プロとしての情熱を傾け続けてくださった医学書院看護出版部の故・川中幸子さんと,前制作部の武田誠さんの志を継承していきたいと思います.
また,年度版発行に向けて持続可能な編集システムの編成のために尽力してくださった看護出版部の北原拓也さんに深謝申し上げます.それにより,毎年新たな本を出版し続けるという苦難に満ちた作業の負担が格段に軽減されました.
初版発行より10年を数え,読者の方々をはじめ,各地の執筆者のチームワークなど,多くの方々の支えによって版を重ね続けられていることを改めて実感し感謝申し上げます.
なお,本書編集の「NPO法人 日本医療ソーシャルワーク研究会」では,本書の印税を医療福祉の広報,普及活動や医療ソーシャルワーカーの研修に役立てておりますことをご報告しておきます.
2011年3月
編集代表 村上須賀子 佐々木哲二郎 奥村晴彦
「格差社会」―─時代と世の中のありようを言いあらわすキーワードとして,ひと頃盛んに使われたこの形容は,昨2010年は「無縁社会」へと改められた感があります.
「格差社会」―─それは,大多数を占めた中流層の崩壊と貧富の差の拡大,すなわち「努力するものが報われる」という意識が人々から消失したことを意味します.それは,労働の報酬が生活保護基準にも満たない「ワーキングプア」や,職と住居を失った人びとのための「年越し派遣村」に象徴されます.旧来の社会保障のしくみが機能しなくなった脆い社会が映し出されています.ここでは,働く人がいとも容易に雇用・所得・居住を奪われる事態に直面する様が,他人ごととは思えない切迫感を伴って露呈してきました.
そして,「無縁社会」が2010年を表すキーワードにあげられました.3万人を超す自殺者が13年間連続し,虐待,そして所在不明の高齢者の続出,孤独死など…….希薄になったといわれてきた人びとの結びつきや相互扶助の関係が,すでに断ち切られたかの衝撃を与える事件・事故の報が相次ぎました.さまざまなセイフティネットが機能しなくなっているといえます.「格差社会」では社会保障のしくみが機能不全に陥っていることを,「無縁社会」ではインフォーマルな相互扶助さえも希薄化したことをあらわにしました.
自殺は,失業・失職・無収入・債務・住居・疾病・うつといった生活問題が連動した結果であると考えられます.それゆえ2009年にはハローワークに仕事・多重債務・健康問題に対応する総合的相談窓口である「ワンストップ・サービス・デイ」が設けられました.思いもよらない生活上のつまずきが“死に至るまでの連鎖”となることを断ち切るために,このワンストップ相談対応は有効です.しかし,残念ながら2010年は本格的に実施されることはありませんでした.無縁社会からの再生に向け,社会・経済をはじめさまざまなシステムの見直しが今後求められるでしょうが,早急な方策はワンストップの相談・支援のしくみが重層的に設けられることであると考えます.
本書の執筆を担った医療ソーシャルワーカーたちは,病院などで生活問題を中心に患者さんや家族の相談に当たっています.「それは,私の管轄外です」とたらい回しにすることなく,保健・医療・福祉制度全般にわたって幅広く情報収集したものを,患者さんや家族のよりよい問題解決のために活用します.ワンストップの相談・支援を日々実践しているのです.制度そのものの枠組みさえも改変されつつあるこの時代,その情報の正確さを保つためには,日々の絶え間ない努力が要求されます.
若いソーシャルワーカーたちから「この本は私のバイブルです」と言われ,読者からは「『家庭の医学』みたいな本だね」と言われれば,本書を編集した医療ソーシャルワーカーたちは,出版継続のための自らの責務を実感せざるを得ません.
2007年度版から,身体・知的・精神障害の3つの障害を統合した障害者自立支援法に沿って精神科医療を「医療サービス」の章に統合しました.総合的なわかりやすい医療サービスガイドとして,第II章に位置づけました.また,2010年度版からは,コラムを毎年更新し,利用者の声や医療ソーシャルワーカーの意見表明も加え,バラエティ豊かなものとしています.そして,この2011年度版では,従来「お金のこと」としていた第III章を「生活費と仕事」と,新しく位置づけています.これまでも生活費と雇用の問題を1つの章に収めてはいましたが,雇用と所得は不可分の生活課題であるとの認識をより明確にして,内容を見直しています.それは,このガイドブックにおいても「ワンストップ相談対応」を具現したいという想いからです.ともすれば堅苦しくなりがちな本文に,ところどころ配したイラストが好評でした.医療現場に従事しているイラストの書き手が伝えるリアルな温もりが,ホッとさせてくれます.毎年のリピーター読者に感謝して,今回は大幅にリニューアルしました.
日本社会の地域間格差が,生活への深刻な影響を与えています.ある障害児のお母さんから寄せられた声を紹介します.このガイドブックに掲載されている制度について役所に問い合わせたところ,「うちの市ではやってません」との答えで,ほかの地域には存在する制度がわが市にはないことが確認できた,とのことでした.このように,社会資源にも「地域間格差」があることを明確にするために,2008年度版からは法的な根拠を掲載することに努めました.各地で格差是正を求める活動が進められ,本書がそれを応援する力になり得れば,執筆者たちの大いなる喜びです.
このガイドブックを利用してくださった読者の方々から,ご意見や新しい情報をお寄せいただければ幸いです.次年度版に反映いたします.
本書前身の初版発行より,本書のもつ社会的使命を共有してくださり,プロとしての情熱を傾け続けてくださった医学書院看護出版部の故・川中幸子さんと,前制作部の武田誠さんの志を継承していきたいと思います.
また,年度版発行に向けて持続可能な編集システムの編成のために尽力してくださった看護出版部の北原拓也さんに深謝申し上げます.それにより,毎年新たな本を出版し続けるという苦難に満ちた作業の負担が格段に軽減されました.
初版発行より10年を数え,読者の方々をはじめ,各地の執筆者のチームワークなど,多くの方々の支えによって版を重ね続けられていることを改めて実感し感謝申し上げます.
なお,本書編集の「NPO法人 日本医療ソーシャルワーク研究会」では,本書の印税を医療福祉の広報,普及活動や医療ソーシャルワーカーの研修に役立てておりますことをご報告しておきます.
2011年3月
編集代表 村上須賀子 佐々木哲二郎 奥村晴彦
目次
開く
ガイドブック活用の前に
I 社会保障のしくみ
社会保障のしくみ
II 医療サービス
病院選びに困ったとき
医療費に困ったとき
III 生活費としごと
生活費
しごと
IV 高齢者サービス
介護保険のしくみ
高齢者サービスの実際
V 障害者サービス
障害者サービスのガイド
障害者サービスの実際
住まい
暮らすところで利用するサービス
出向いて利用するサービス
おでかけ
しごと
VI 難病
難病患者のために
VII 母子(ひとり親)・乳幼児・児童のために
母子(ひとり親)・乳幼児・児童のために
VIII 権利擁護と利用者支援
権利を擁護するということ
権利行使を支援するシステム
権利侵害があった場合の救済システム
IX 相談・支援とピア・サポート
支援する人
サービス利用の窓口
自助グループ(セルフヘルプグループ)
資料編
1.労働者災害補償保険法障害等級表
2.自動車損害賠償保障法後遺障害等級表
3.重度心身障害者医療費助成制度
4.生活保護における地域の級地区分
5.国民年金障害等級表,厚生年金障害等級表,厚生年金障害手当金
6.特別障害者手当障害程度
7.身体障害者障害程度等級表
8.精神障害者保健福祉手帳障害等級表
9.高次脳機能障害診断基準
10.厚生労働省科学研究 難治性疾患克服研究事業対象疾患
11.こども医療費助成制度,乳幼児医療費助成制度
12.ひとり親家庭等医療費助成制度
13.都道府県における医療ソーシャルワーカーに関する問合せ先
14.無料低額診療施設
索引
I 社会保障のしくみ
社会保障のしくみ
II 医療サービス
病院選びに困ったとき
医療費に困ったとき
III 生活費としごと
生活費
しごと
IV 高齢者サービス
介護保険のしくみ
高齢者サービスの実際
V 障害者サービス
障害者サービスのガイド
障害者サービスの実際
住まい
暮らすところで利用するサービス
出向いて利用するサービス
おでかけ
しごと
VI 難病
難病患者のために
VII 母子(ひとり親)・乳幼児・児童のために
母子(ひとり親)・乳幼児・児童のために
VIII 権利擁護と利用者支援
権利を擁護するということ
権利行使を支援するシステム
権利侵害があった場合の救済システム
IX 相談・支援とピア・サポート
支援する人
サービス利用の窓口
自助グループ(セルフヘルプグループ)
資料編
1.労働者災害補償保険法障害等級表
2.自動車損害賠償保障法後遺障害等級表
3.重度心身障害者医療費助成制度
4.生活保護における地域の級地区分
5.国民年金障害等級表,厚生年金障害等級表,厚生年金障害手当金
6.特別障害者手当障害程度
7.身体障害者障害程度等級表
8.精神障害者保健福祉手帳障害等級表
9.高次脳機能障害診断基準
10.厚生労働省科学研究 難治性疾患克服研究事業対象疾患
11.こども医療費助成制度,乳幼児医療費助成制度
12.ひとり親家庭等医療費助成制度
13.都道府県における医療ソーシャルワーカーに関する問合せ先
14.無料低額診療施設
索引
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。