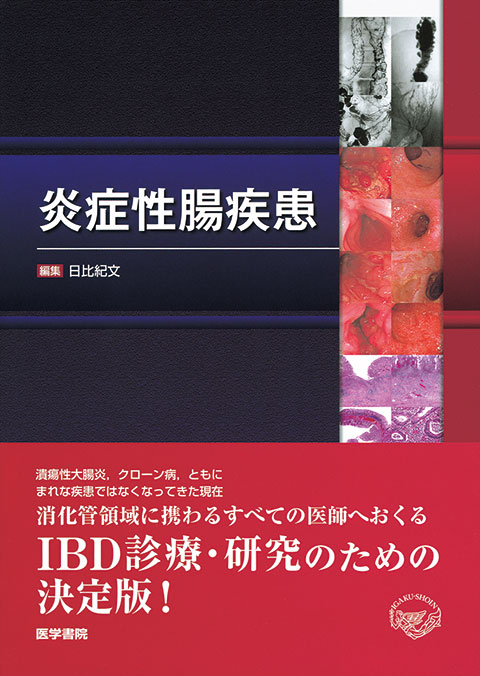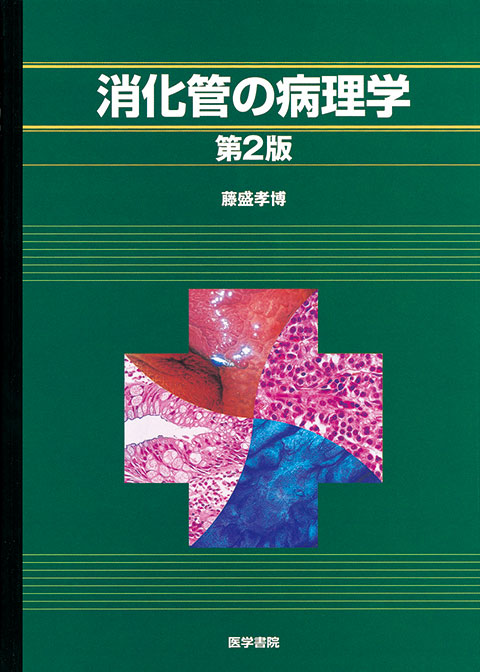炎症性腸疾患
炎症性腸疾患の知見を集大成!
もっと見る
炎症性腸疾患(IBD:潰瘍性大腸炎とクローン病)は、近年患者数が増加の一途をたどっており、いまや専門医のみならず、消化管領域に携わるすべての医師にとってその全体像を正しく知っておくことが必須の状況となってきている。本書は、本邦のIBD研究をリードしてきた厚労省研究班(日比班)のメンバーにより、基礎から臨床まで今現在におけるすべての知見を集大成した決定版。
| 編集 | 日比 紀文 |
|---|---|
| 発行 | 2010年10月判型:B5頁:352 |
| ISBN | 978-4-260-01007-8 |
| 定価 | 14,300円 (本体13,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease : IBD)と総称される潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis : UC)とクローン病(Crohn's disease : CD)は,原因不明の難治性慢性の炎症をきたす腸疾患である。原因が不明であるため根本的治療法はいまだ確立されていない。以前は欧米にみられる疾患であり,アジアではまれな疾患と考えられてきた。しかし,近年生活習慣や食事習慣の欧米化に伴って患者数が増加し,わが国ばかりでなく韓国や中国でも患者数が急増している。UCは約10万5,000人を超える医療受給者証交付件数があり,CDも約3万人を超えて,ともにまれな疾患ではなくなってきている。若年層に発症することが多いため,根治療法のない現在においては患者の病悩期間は長く,QOLは低下している。しかし,大部分の患者は適切な治療を受けることによって日常生活,社会生活を送ることが可能となり,基本的には生命予後への影響も少なく,長期的なQOLも改善されてきた。わが国ではIBDにかぎらず患者の専門医・大病院志向が強いが,本疾患もprimary care physicianによって診療・治療することが要求される時代になってきている。欧米では,通常の診療はprimary care physicianが行い,特殊な状況下でのみ専門医への紹介や入院が行われている。消化管領域にたずさわる医師として,IBDに関する正しい知識を持ち,標準化した治療を知り,専門医への紹介のタイミングなどについて十分理解しておくことは必須の状況となってきている。
わが国における本疾患の研究は,37年前の1973年から,厚生労働省(旧厚生省)による「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究班」(以下,研究班)を中心として進められてきた。医学書院では過去に主任研究者を務められた武藤徹一郎先生を中心に,1999年に『炎症性腸疾患─潰瘍性大腸炎とクローン病のすべて』を発行している。それから約10年が経ち,研究班では病態解明に関する基礎研究,疫学研究,診療ガイドラインの整備,新しい治療法の開発など数多くの研究プロジェクトで成果が達成され,研究報告書によって公表されているが,最新の研究成果や臨床情報が幅広く普及しているとは言いがたい。さらに,抗TNF-α抗体などの生物製剤や白血球除去療法,アザチオプリン(AZA)やタクロリムス(FK506)など免疫調節療法が確立してきた。
このたび,2002年から2007年まで主任研究者をつとめさせていただいたのを機に,厚生労働省研究班の研究成果をまとめ,IBDにおける知見を集大成させていただいた。研究班(日比班)の班員の先生方を中心に執筆をお願いし,わが国における現時点での最新の知見を網羅している。多くの研究会が行われ,多くの出版物が出されているが,IBDに関してバイブルにも近い必携の書となるものと確信している。IBDを診療している若い研修医や消化器系,内科系,外科系の臨床医を含むすべての方々にとって,本書が適切な診断と治療さらには研究を進めていくための一助となることを期待している。
2010年9月
日比紀文
炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease : IBD)と総称される潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis : UC)とクローン病(Crohn's disease : CD)は,原因不明の難治性慢性の炎症をきたす腸疾患である。原因が不明であるため根本的治療法はいまだ確立されていない。以前は欧米にみられる疾患であり,アジアではまれな疾患と考えられてきた。しかし,近年生活習慣や食事習慣の欧米化に伴って患者数が増加し,わが国ばかりでなく韓国や中国でも患者数が急増している。UCは約10万5,000人を超える医療受給者証交付件数があり,CDも約3万人を超えて,ともにまれな疾患ではなくなってきている。若年層に発症することが多いため,根治療法のない現在においては患者の病悩期間は長く,QOLは低下している。しかし,大部分の患者は適切な治療を受けることによって日常生活,社会生活を送ることが可能となり,基本的には生命予後への影響も少なく,長期的なQOLも改善されてきた。わが国ではIBDにかぎらず患者の専門医・大病院志向が強いが,本疾患もprimary care physicianによって診療・治療することが要求される時代になってきている。欧米では,通常の診療はprimary care physicianが行い,特殊な状況下でのみ専門医への紹介や入院が行われている。消化管領域にたずさわる医師として,IBDに関する正しい知識を持ち,標準化した治療を知り,専門医への紹介のタイミングなどについて十分理解しておくことは必須の状況となってきている。
わが国における本疾患の研究は,37年前の1973年から,厚生労働省(旧厚生省)による「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究班」(以下,研究班)を中心として進められてきた。医学書院では過去に主任研究者を務められた武藤徹一郎先生を中心に,1999年に『炎症性腸疾患─潰瘍性大腸炎とクローン病のすべて』を発行している。それから約10年が経ち,研究班では病態解明に関する基礎研究,疫学研究,診療ガイドラインの整備,新しい治療法の開発など数多くの研究プロジェクトで成果が達成され,研究報告書によって公表されているが,最新の研究成果や臨床情報が幅広く普及しているとは言いがたい。さらに,抗TNF-α抗体などの生物製剤や白血球除去療法,アザチオプリン(AZA)やタクロリムス(FK506)など免疫調節療法が確立してきた。
このたび,2002年から2007年まで主任研究者をつとめさせていただいたのを機に,厚生労働省研究班の研究成果をまとめ,IBDにおける知見を集大成させていただいた。研究班(日比班)の班員の先生方を中心に執筆をお願いし,わが国における現時点での最新の知見を網羅している。多くの研究会が行われ,多くの出版物が出されているが,IBDに関してバイブルにも近い必携の書となるものと確信している。IBDを診療している若い研修医や消化器系,内科系,外科系の臨床医を含むすべての方々にとって,本書が適切な診断と治療さらには研究を進めていくための一助となることを期待している。
2010年9月
日比紀文
目次
開く
序
第1章 臨床像
I 症状および経過
II 血液・生化学所見
III 分類(病型,重症度など)
IV 腸管外合併症
V 長期予後
VI 炎症性腸疾患とQOL
第2章 診断
I 診断基準
II 診断手順
III X線診断
IV 内視鏡診断
V CT・MRI診断
VI 新しい診断手技
VII 鑑別診断
VIII 癌化・dysplasiaのサーベイランス
IX 潰瘍性大腸炎関連腫瘍における拡大内視鏡検査
第3章 内科的治療
I 重症度・病勢の把握,評価
II 治療のストラテジー,治療指針
III 内科的治療に用いられる薬物,治療法(特徴と副作用)
IV 潰瘍性大腸炎に対する内科的治療の実際
V クローン病に対する内科的治療の実際
VI 診療ガイドラインの開発と適用
VII 小児に対する治療,治療指針
VIII 妊娠に対する指導と治療の実際
IX 合併症に対する治療
X 新しい治療薬
XI 患者に対する栄養・生活指導
第4章 外科的治療
I 手術適応
II 潰瘍性大腸炎に対する手術
III 術後pouchitisの診断と治療
IV クローン病に対する手術
V 腹腔鏡下手術
VI クローン病肛門病変の治療
VII 癌化例に対する外科治療
VIII 外科的治療の合併症と問題点
第5章 病理
I 病理所見と病理診断
II 生検所見と生検診断
III 鑑別診断
IV 癌化
第6章 疫学
I 有病率・発病率・死亡率
II 年齢・臨床経過別頻度
III 地域別発病率
IV 家族内発病頻度
V 発症因子としての生活因子
VI 小児の疫学
第7章 病因・病態
I 総論,歴史的経緯
II 病原微生物による感染論
III 免疫学的異常
IV 神経・内分泌的因子
V 血流障害,微小循環障害の関与
VI 疾患関連遺伝子
VII IBDの動物実験モデル
VIII 発症機序に関する集学的考察
IX 炎症性腸疾患と粘膜上皮再生
X 炎症性腸疾患における癌化機序
索引
第1章 臨床像
I 症状および経過
II 血液・生化学所見
III 分類(病型,重症度など)
IV 腸管外合併症
V 長期予後
VI 炎症性腸疾患とQOL
第2章 診断
I 診断基準
II 診断手順
III X線診断
IV 内視鏡診断
V CT・MRI診断
VI 新しい診断手技
VII 鑑別診断
VIII 癌化・dysplasiaのサーベイランス
IX 潰瘍性大腸炎関連腫瘍における拡大内視鏡検査
第3章 内科的治療
I 重症度・病勢の把握,評価
II 治療のストラテジー,治療指針
III 内科的治療に用いられる薬物,治療法(特徴と副作用)
IV 潰瘍性大腸炎に対する内科的治療の実際
V クローン病に対する内科的治療の実際
VI 診療ガイドラインの開発と適用
VII 小児に対する治療,治療指針
VIII 妊娠に対する指導と治療の実際
IX 合併症に対する治療
X 新しい治療薬
XI 患者に対する栄養・生活指導
第4章 外科的治療
I 手術適応
II 潰瘍性大腸炎に対する手術
III 術後pouchitisの診断と治療
IV クローン病に対する手術
V 腹腔鏡下手術
VI クローン病肛門病変の治療
VII 癌化例に対する外科治療
VIII 外科的治療の合併症と問題点
第5章 病理
I 病理所見と病理診断
II 生検所見と生検診断
III 鑑別診断
IV 癌化
第6章 疫学
I 有病率・発病率・死亡率
II 年齢・臨床経過別頻度
III 地域別発病率
IV 家族内発病頻度
V 発症因子としての生活因子
VI 小児の疫学
第7章 病因・病態
I 総論,歴史的経緯
II 病原微生物による感染論
III 免疫学的異常
IV 神経・内分泌的因子
V 血流障害,微小循環障害の関与
VI 疾患関連遺伝子
VII IBDの動物実験モデル
VIII 発症機序に関する集学的考察
IX 炎症性腸疾患と粘膜上皮再生
X 炎症性腸疾患における癌化機序
索引
書評
開く
厚労省研究班の成果を結集した,最高かつ最新の内容
書評者: 浅香 正博 (北大大学院教授・消化器内科学)
潰瘍性大腸炎とクローン病は併せて炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease : IBD)と総称されており,どちらも原因不明で難治性の慢性炎症の所見を呈する腸疾患である。生命予後はよいが,再発を繰り返すため,社会復帰が困難になるケースが多く,きわめて厄介な病気である。
わが国においてここ30~40年くらいの間に,信じられないスピードで両疾患の発生数が急増している。潰瘍性大腸炎,クローン病ともに70年代に比して30~50倍の増加を示しており,特定疾患医療受給者数でみると,潰瘍性大腸炎は11万人を超え,クローン病はほぼ3万人である。このような極端な増加を示す疾患は消化管疾患では見あたらないし,消化器以外の疾患でもきわめてまれなケースである。その原因については生活習慣の変化といった漠然とした理由でしか説明されていない。感染,生活習慣さらには遺伝子レベルに至るまでの詳細な研究がなされているが,いまだ成因は不明のままである。
30年前には炎症性腸疾患と同じく原因不明で治療法が確立されていなかった消化性潰瘍は,80年代にH2ブロッカーやPPIのような酸分泌抑制剤の開発により劇的に治癒する疾患になり,90年代後半にはその原因が同定され,ヘリコバクター・ピロリの除菌により,再発はほぼ抑制されるようになった。私が医学部を卒業した当時は同じスタートラインにいた炎症性腸疾患と消化性潰瘍の治療は,現在このように大きな差が生まれてしまった。現在の炎症性腸疾患の治療は消化性潰瘍の治療の進歩にたとえるとどこまで来ているのであろうか? 白血球除去療法やインフリキシマブのような生物製剤の開発により,確かに治療は進歩したが,消化性潰瘍の治療で画期的な変化をもたらしたH2ブロッカーの時代にも達していないのが現状であり,比較的効率のよい制酸剤や抗コリン剤の役割しか果たしていないと考えられる。
本書は,慶應義塾大学医学部消化器内科の日比紀文教授が2002年から2007年まで班長を務めた厚生労働省による“難治性炎症性腸管障害に関する調査研究班”の成果の結集である。これまで炎症性腸疾患に関する書物は数多く出版されているが,わが国の炎症性腸疾患の研究者が5年間にわたって継続的にテーマを持って研究を行い,十分な討論を行った上で刊行された本書は,厚生労働省の班会議の成果という権威のみならず,実質を伴った現時点における最高の品質で最新の内容を提供していると考えてよい。この本をベースにしながら,炎症性腸疾患の成因や病態生理を追求し,大きな成果を上げてほしいと心から願っている。もちろん世界中が総力を挙げて研究しているのにいまだ本質に迫れない手強い病気であることは十分承知のうえであるが,わが国から画期的な成果が報告されることを期待している。
IBD診療の大集積
書評者: 武藤 徹一郎 (財団法人 癌研有明病院名誉院長/メディカルディレクター・消化器外科学)
今にして思えば,1973年はわが国の炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease : IBD)元年であった。この年,厚生労働省(旧厚生省)による「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究班」(以下,研究班)が発足し,わが国におけるIBDの調査研究が本格的にスタートした。当時,IBDは国内ではほとんど知られておらず,特にクローン病は未知の疾患であった。しかし,現在も存続しているこの研究班の継続的な活動のおかげで,今やIBDはふつうの疾患(common disease)になった。消化管の専門家がいる医療機関なら,日本中どこでもIBDの診断が可能で,ガイドラインに基づいた均一な治療が行われるようになったのは,ひとえにこの研究班の活動の賜物であると言ってよい。厚労省からは班員,班協力者を選ぶ際に,できるだけ全国からまんべんなく選んで,研究よりは勉強の機会を多くの医師に与えてほしいという要望があった。研究会は全国から集まった消化管専門の医師であふれていたが,そのほとんどはIBDに関しては素人同然であった。もっとも,教える側(?)の班員のレベルも今から比べると大したことはなかったのだが。しかし,厚労省のこの方針はIBDの診断・治療の均てん化の推進に大いに役立った。研究班の大きな課題の1つはIBDの診断基準と治療ガイドラインの作成であったが,この仕事は着々と改訂が進められ今やほぼ定着したと言ってよい。病態の解明も著しく進展したが,病因の解明は核心により接近したとはいえ,残念ながらいまだ解決に至っていない。手術適応,手術法についても研究班の努力でほぼ一定の見解が得られている。数ある難病研究班の中で,IBD研究班は最も成功を収めた班の1つとして言ってよいと思う。
班研究の成果は毎年報告書として提出され,全国の主たる医療機関に配布されるが,一般病院にその情報が伝達されるのはさらに2~3年のタイムラグがあるのがふつうである。多くの場合,医学的商業雑誌の特集がその役割を果たしていた。このタイムラグを短縮するために筆者がIBD班長期間(1991~1995)の成果をまとめて成書にしたのは1999年のことであり,それなりの役割を果たしたと思う。本書は日比班(2002~2007)の成果を同様の主旨でまとめたもので,“IBD診療・研究のための決定版”と銘打っただけあって,大変よくまとめられた有用な成書であり,前書から10年の進歩の跡がよくわかる。治療法として6MP,アザチオプリン,シクロスポリン,白血球除去療法,抗TNF-α抗体(レミケード®)などが日常診療の中に登場し定着したのは大きな進歩である。また,手術療法が特に潰瘍性大腸炎において,病気との決別の最後の手段として確固たる地位を占めるようになったことは大きな意味がある。生体の免疫異常が病因・病態に関与していることは明白であり,最後の詰めができていないことは残念であるが,今後の班研究の成果を待つことにしよう。日比班を継ぐ渡辺班の粘膜上皮再生をターゲットにした研究に大いに期待したい。
本書にはIBDに関する最新の診断・治療のエッセンスが満載されており,すべての消化管専門家に一読をお勧めしたい。
IBDの臨床から基礎まで,最近の進歩をすべて網羅
書評者: 八尾 恒良 (福岡大名誉教授・消化器内科学)
日比紀文先生編集による本書『炎症性腸疾患』は厚生労働省「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究班」(以下,班研究)の2002年から2007年までの研究成果の集大成である。同様の成書は1999年,11年前に,当時班研究の班長を勤められた武藤徹一郎先生がまとめられ,私もそのお手伝いをした経緯があり,今回の書評を仰せつかったものと思う。
班研究の業績は毎年まとめられ,コンセンサスが得られた診断・治療方針などその年の業績集に記載されている。しかし,業績集は班員には配布されるものの一般の医師の目に触れる機会は少ない。また,その一部が専門誌で解説されることはあるが業績の全体に目を通す機会はない。消化器専門医は診療や学会の研究発表を正確に理解するために班研究で決められたことを理解しておく必要がある。
本書によると11年前に約5万人であった潰瘍性大腸炎(UC)患者は10万人を超え,1万人であったクローン病(CD)患者は3万人を超えたという。炎症性腸疾患の患者さんは,一時点の治療で決着がつく訳ではなく,患者さんの一生にわたる長期の管理と治療が必要である。とても消化器専門医だけですべての患者さんの診療ができるわけがなく,一般臨床医と協力した診療体制が必要となる。
診療には疾病に対する包括的な知識が必要で,一般臨床医,消化器専門医を問わず,本書は炎症性疾患に関与する医師にとって,必要不可欠な座右の書となるであろう。
本書にはUC,CDの臨床的事項から基礎研究まで,最近11年間の進歩がすべて網羅されている。すべてを論じることはできないが進歩の要点は以下の点であろう。
1)診断・他:
①CT,MR,USの役割が明らかにされている。②新しい診断方法,CT・MR-enterography,カプセル内視鏡,バルーン内視鏡などが記載されている。③全大腸炎型は脾彎曲部を越えるものと変更されている。
2)内科的治療:
A. UC:ステロイドの反応性(抵抗性,依存性)によって治療方法を考えるという方針が確立されている。そのほか,①難治例の定義が定められその対処方法が記載されている。②免疫調節薬の役割が明らかにされ,アサコール®,シクロスポリン,タクロリムスなど新しい薬剤・治療法が記載され,CMV感染例に対する抗ウイルス剤の治療効果も(少し)述べられている。③直腸炎型は他の型の重症度分類とは別に治療指針が立てられている。
B. CD:治療にインフリキシマブ(レミケード®)が導入され,本症の治療に大きな変革をもたらしている。また,免疫調節薬の役割が明らかにされ,狭窄に対するバルーン拡張術の適応も確立されている。
特記すべきは「診療ガイドライン」の項目が設けられ詳述されていることである。今後,製薬会社が関与しないエビデンスの積み上げに専門家の一層の努力が必要であろう。
3)外科治療
①CDに対する腹腔鏡下手術:可能な症例では癒着の減少による長期予後の改善が期待される。②術後再発防止のレミケード®の効果が検討し始められている。
4)病因・病態
TLRの役割をはじめ,この10年間の進歩はすごい。引用文献のほとんどが2005年以降である。基礎研究の臨床へのフィードバックが望まれる。
なお,「班研究のまとめ」は進歩の要点だけでも3~4年に1回くらいの間隔で出版して欲しい。
書評者: 浅香 正博 (北大大学院教授・消化器内科学)
潰瘍性大腸炎とクローン病は併せて炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease : IBD)と総称されており,どちらも原因不明で難治性の慢性炎症の所見を呈する腸疾患である。生命予後はよいが,再発を繰り返すため,社会復帰が困難になるケースが多く,きわめて厄介な病気である。
わが国においてここ30~40年くらいの間に,信じられないスピードで両疾患の発生数が急増している。潰瘍性大腸炎,クローン病ともに70年代に比して30~50倍の増加を示しており,特定疾患医療受給者数でみると,潰瘍性大腸炎は11万人を超え,クローン病はほぼ3万人である。このような極端な増加を示す疾患は消化管疾患では見あたらないし,消化器以外の疾患でもきわめてまれなケースである。その原因については生活習慣の変化といった漠然とした理由でしか説明されていない。感染,生活習慣さらには遺伝子レベルに至るまでの詳細な研究がなされているが,いまだ成因は不明のままである。
30年前には炎症性腸疾患と同じく原因不明で治療法が確立されていなかった消化性潰瘍は,80年代にH2ブロッカーやPPIのような酸分泌抑制剤の開発により劇的に治癒する疾患になり,90年代後半にはその原因が同定され,ヘリコバクター・ピロリの除菌により,再発はほぼ抑制されるようになった。私が医学部を卒業した当時は同じスタートラインにいた炎症性腸疾患と消化性潰瘍の治療は,現在このように大きな差が生まれてしまった。現在の炎症性腸疾患の治療は消化性潰瘍の治療の進歩にたとえるとどこまで来ているのであろうか? 白血球除去療法やインフリキシマブのような生物製剤の開発により,確かに治療は進歩したが,消化性潰瘍の治療で画期的な変化をもたらしたH2ブロッカーの時代にも達していないのが現状であり,比較的効率のよい制酸剤や抗コリン剤の役割しか果たしていないと考えられる。
本書は,慶應義塾大学医学部消化器内科の日比紀文教授が2002年から2007年まで班長を務めた厚生労働省による“難治性炎症性腸管障害に関する調査研究班”の成果の結集である。これまで炎症性腸疾患に関する書物は数多く出版されているが,わが国の炎症性腸疾患の研究者が5年間にわたって継続的にテーマを持って研究を行い,十分な討論を行った上で刊行された本書は,厚生労働省の班会議の成果という権威のみならず,実質を伴った現時点における最高の品質で最新の内容を提供していると考えてよい。この本をベースにしながら,炎症性腸疾患の成因や病態生理を追求し,大きな成果を上げてほしいと心から願っている。もちろん世界中が総力を挙げて研究しているのにいまだ本質に迫れない手強い病気であることは十分承知のうえであるが,わが国から画期的な成果が報告されることを期待している。
IBD診療の大集積
書評者: 武藤 徹一郎 (財団法人 癌研有明病院名誉院長/メディカルディレクター・消化器外科学)
今にして思えば,1973年はわが国の炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease : IBD)元年であった。この年,厚生労働省(旧厚生省)による「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究班」(以下,研究班)が発足し,わが国におけるIBDの調査研究が本格的にスタートした。当時,IBDは国内ではほとんど知られておらず,特にクローン病は未知の疾患であった。しかし,現在も存続しているこの研究班の継続的な活動のおかげで,今やIBDはふつうの疾患(common disease)になった。消化管の専門家がいる医療機関なら,日本中どこでもIBDの診断が可能で,ガイドラインに基づいた均一な治療が行われるようになったのは,ひとえにこの研究班の活動の賜物であると言ってよい。厚労省からは班員,班協力者を選ぶ際に,できるだけ全国からまんべんなく選んで,研究よりは勉強の機会を多くの医師に与えてほしいという要望があった。研究会は全国から集まった消化管専門の医師であふれていたが,そのほとんどはIBDに関しては素人同然であった。もっとも,教える側(?)の班員のレベルも今から比べると大したことはなかったのだが。しかし,厚労省のこの方針はIBDの診断・治療の均てん化の推進に大いに役立った。研究班の大きな課題の1つはIBDの診断基準と治療ガイドラインの作成であったが,この仕事は着々と改訂が進められ今やほぼ定着したと言ってよい。病態の解明も著しく進展したが,病因の解明は核心により接近したとはいえ,残念ながらいまだ解決に至っていない。手術適応,手術法についても研究班の努力でほぼ一定の見解が得られている。数ある難病研究班の中で,IBD研究班は最も成功を収めた班の1つとして言ってよいと思う。
班研究の成果は毎年報告書として提出され,全国の主たる医療機関に配布されるが,一般病院にその情報が伝達されるのはさらに2~3年のタイムラグがあるのがふつうである。多くの場合,医学的商業雑誌の特集がその役割を果たしていた。このタイムラグを短縮するために筆者がIBD班長期間(1991~1995)の成果をまとめて成書にしたのは1999年のことであり,それなりの役割を果たしたと思う。本書は日比班(2002~2007)の成果を同様の主旨でまとめたもので,“IBD診療・研究のための決定版”と銘打っただけあって,大変よくまとめられた有用な成書であり,前書から10年の進歩の跡がよくわかる。治療法として6MP,アザチオプリン,シクロスポリン,白血球除去療法,抗TNF-α抗体(レミケード®)などが日常診療の中に登場し定着したのは大きな進歩である。また,手術療法が特に潰瘍性大腸炎において,病気との決別の最後の手段として確固たる地位を占めるようになったことは大きな意味がある。生体の免疫異常が病因・病態に関与していることは明白であり,最後の詰めができていないことは残念であるが,今後の班研究の成果を待つことにしよう。日比班を継ぐ渡辺班の粘膜上皮再生をターゲットにした研究に大いに期待したい。
本書にはIBDに関する最新の診断・治療のエッセンスが満載されており,すべての消化管専門家に一読をお勧めしたい。
IBDの臨床から基礎まで,最近の進歩をすべて網羅
書評者: 八尾 恒良 (福岡大名誉教授・消化器内科学)
日比紀文先生編集による本書『炎症性腸疾患』は厚生労働省「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究班」(以下,班研究)の2002年から2007年までの研究成果の集大成である。同様の成書は1999年,11年前に,当時班研究の班長を勤められた武藤徹一郎先生がまとめられ,私もそのお手伝いをした経緯があり,今回の書評を仰せつかったものと思う。
班研究の業績は毎年まとめられ,コンセンサスが得られた診断・治療方針などその年の業績集に記載されている。しかし,業績集は班員には配布されるものの一般の医師の目に触れる機会は少ない。また,その一部が専門誌で解説されることはあるが業績の全体に目を通す機会はない。消化器専門医は診療や学会の研究発表を正確に理解するために班研究で決められたことを理解しておく必要がある。
本書によると11年前に約5万人であった潰瘍性大腸炎(UC)患者は10万人を超え,1万人であったクローン病(CD)患者は3万人を超えたという。炎症性腸疾患の患者さんは,一時点の治療で決着がつく訳ではなく,患者さんの一生にわたる長期の管理と治療が必要である。とても消化器専門医だけですべての患者さんの診療ができるわけがなく,一般臨床医と協力した診療体制が必要となる。
診療には疾病に対する包括的な知識が必要で,一般臨床医,消化器専門医を問わず,本書は炎症性疾患に関与する医師にとって,必要不可欠な座右の書となるであろう。
本書にはUC,CDの臨床的事項から基礎研究まで,最近11年間の進歩がすべて網羅されている。すべてを論じることはできないが進歩の要点は以下の点であろう。
1)診断・他:
①CT,MR,USの役割が明らかにされている。②新しい診断方法,CT・MR-enterography,カプセル内視鏡,バルーン内視鏡などが記載されている。③全大腸炎型は脾彎曲部を越えるものと変更されている。
2)内科的治療:
A. UC:ステロイドの反応性(抵抗性,依存性)によって治療方法を考えるという方針が確立されている。そのほか,①難治例の定義が定められその対処方法が記載されている。②免疫調節薬の役割が明らかにされ,アサコール®,シクロスポリン,タクロリムスなど新しい薬剤・治療法が記載され,CMV感染例に対する抗ウイルス剤の治療効果も(少し)述べられている。③直腸炎型は他の型の重症度分類とは別に治療指針が立てられている。
B. CD:治療にインフリキシマブ(レミケード®)が導入され,本症の治療に大きな変革をもたらしている。また,免疫調節薬の役割が明らかにされ,狭窄に対するバルーン拡張術の適応も確立されている。
特記すべきは「診療ガイドライン」の項目が設けられ詳述されていることである。今後,製薬会社が関与しないエビデンスの積み上げに専門家の一層の努力が必要であろう。
3)外科治療
①CDに対する腹腔鏡下手術:可能な症例では癒着の減少による長期予後の改善が期待される。②術後再発防止のレミケード®の効果が検討し始められている。
4)病因・病態
TLRの役割をはじめ,この10年間の進歩はすごい。引用文献のほとんどが2005年以降である。基礎研究の臨床へのフィードバックが望まれる。
なお,「班研究のまとめ」は進歩の要点だけでも3~4年に1回くらいの間隔で出版して欲しい。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。