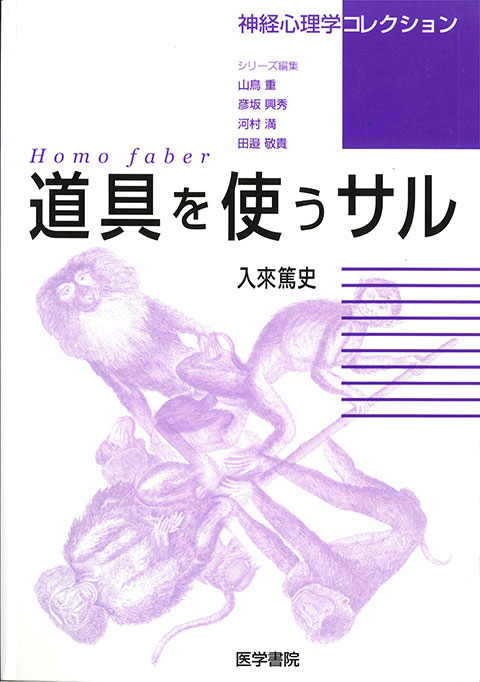Homo faber
道具を使うサル
気鋭の生理学者が書下ろした世界初の「ホモ・ファベル」論
もっと見る
二足歩行や火の使用とともに,道具の使用はヒトと動物を分つ指標であった。本書は道具使用をニホンザルで研究してきた気鋭の生理学者が書下ろした世界で最初の「ホモ・ファベル(工作人)」論。内容は生物進化から分子遺伝学と多岐にわたり,ダイナミックな道具論を展開するとともに,著者の絶えざる思考実験の軌跡とサイエンティストの遊び心が感じられる。
*「神経心理学コレクション」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | 神経心理学コレクション |
|---|---|
| 著 | 入來 篤史 |
| シリーズ編集 | 山鳥 重 / 彦坂 興秀 / 河村 満 / 田邉 敬貴 |
| 発行 | 2004年07月判型:A5頁:236 |
| ISBN | 978-4-260-11893-4 |
| 定価 | 3,300円 (本体3,000円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 目次
- 書評
目次
開く
序章 道具―「想い」のかたち
第1章 道具を使うニホンザル
第2章 道具使用を可能にする脳機能
第3章 「心の内」を計測する
第4章 脳内表象の発達とその進化
第5章 テレビゲームを楽しむニホンザル
第6章 サルに象徴的表象を教える
第7章 道具を通して迫る「知性」の研究戦略
第8章 「道具」の向こうに望む「想い」
参考文献
索引
あとがき
第1章 道具を使うニホンザル
第2章 道具使用を可能にする脳機能
第3章 「心の内」を計測する
第4章 脳内表象の発達とその進化
第5章 テレビゲームを楽しむニホンザル
第6章 サルに象徴的表象を教える
第7章 道具を通して迫る「知性」の研究戦略
第8章 「道具」の向こうに望む「想い」
参考文献
索引
あとがき
書評
開く
「サルの道具使用」の研究の軌跡を詳述した,ユニークな科学読み物
書評者: 岩村 吉晃 (川崎医療福祉大教授・感覚矯正学科)
本書の著者,入來篤史氏は私のかつての共同研究者である。彼は私のライフワーク,サル体性感覚野における階層的情報処理の仕事が終盤にさしかかった1993年ごろ,この研究プロジェクトに参加,中心後回後方における両手統合の発見,第二体性感覚野研究の開始など,高次感覚情報統合の仕組み解明に大いに貢献した。私は中心後回の後方,頭頂間溝領域に研究の初期より電極を刺入,不思議なニューロン活動をいろいろ記録していた。その多くが再現性に乏しい逸話的観察であったが,その中に体性感覚野なのに視覚刺激に応答するニューロンがあった。これは1993年にそれまでの研究を総括した論文に軽く記載しただけで,深くは追求しないまま放置しておいた。入來氏が参加してまもなく,私はこれまでの頭頂間溝領域の面白いニューロンと,これと同時記録した行動ビデオを彼に見せた。彼はこれに深く印象づけられた様子であったが,まもなくまったく新しい実験パラダイムを考案し実行に移した。これが「サルの道具使用」の研究であり,本書のテーマ,なのである。
本書はこの実験の着想を得てから,その発展にいたる経緯を詳細に述べている。私にとって特に印象的だったのは,この実験結果を北米の神経科学学会で最初に報告した時のことである。エンドレスビデオテープを写すテレビをポスターの前に置いた。これは前を通る観客の注意をひき,大きな人だかりができた。この研究はその後も国際的に(もちろん国内でも)評判となり,入來氏は人気者になった。2001年にはNeuroscience Research誌のExcellent Paper Awardを受賞,2004年の秋には,Minerva Foundation in CaliforniaからGolden Brain Awardを受賞した。本書はそのような彼の10年にわたる研究の成功物語である。本書には著者の見せる才能が遺憾なく発揮され,演出的配慮がいたるところになされている。たとえば,前書きにおける,幼少時アメリカ生活でのベンジャミン・フランクリンとの出会いであり,ベルクソンやカッシラーなど20世紀西欧哲学者の業績への言及であり,2種類のコラムのシリーズに書かれた,世界の有名美術館での哲学的思索の表出などである。
本書の思想的な柱はいくつかあるが,その1つは進化論である。サルとヒトの知的能力を連続的と見るのか不連続と見るのかはっきりしないところがあるが,これはいましばらく結論が出ない問題である。進化論への傾倒は生物学者であった著者の祖父の強い影響らしい。もう1つは西欧文明への憧憬である。ボディイメージという主観的現象を扱うとき,哲学的思索は避けることはできない。ただ,いうまでもなく哲学用語は特に翻訳されて紹介されると難解であり,定義された用語を使う実験科学としての生理学の枠からはずれ,著者が自分の思索のあとを哲学的に語るときにも,その意図が伝わりにくいところが多い。心理学や言語学の世界にも日常的に同じ悩みがある。一方,哲学に限らず,著者の芸術,学術,科学技術などにおける西欧文明への強い憧れがうかがえるが,彼の仕事がヨーロッパで高く評価されているのも,著者が西欧的文化基盤を並みの日本人以上に彼らと共有しているためであろうか。いずれにせよ,最初の発見から10年ほどで,遺伝子技法から脳イメージングまでさまざまな実験手法を駆使しての研究の展開ぶりがよくわかり,大変感銘を受けた。挿図や写真も適切である。本書はこれまでの殻を破ったユニークな科学読み物であり,若い研究者に研究の仕方を教え,勇気づける内容であると思われる。
書評者: 岩村 吉晃 (川崎医療福祉大教授・感覚矯正学科)
本書の著者,入來篤史氏は私のかつての共同研究者である。彼は私のライフワーク,サル体性感覚野における階層的情報処理の仕事が終盤にさしかかった1993年ごろ,この研究プロジェクトに参加,中心後回後方における両手統合の発見,第二体性感覚野研究の開始など,高次感覚情報統合の仕組み解明に大いに貢献した。私は中心後回の後方,頭頂間溝領域に研究の初期より電極を刺入,不思議なニューロン活動をいろいろ記録していた。その多くが再現性に乏しい逸話的観察であったが,その中に体性感覚野なのに視覚刺激に応答するニューロンがあった。これは1993年にそれまでの研究を総括した論文に軽く記載しただけで,深くは追求しないまま放置しておいた。入來氏が参加してまもなく,私はこれまでの頭頂間溝領域の面白いニューロンと,これと同時記録した行動ビデオを彼に見せた。彼はこれに深く印象づけられた様子であったが,まもなくまったく新しい実験パラダイムを考案し実行に移した。これが「サルの道具使用」の研究であり,本書のテーマ,なのである。
本書はこの実験の着想を得てから,その発展にいたる経緯を詳細に述べている。私にとって特に印象的だったのは,この実験結果を北米の神経科学学会で最初に報告した時のことである。エンドレスビデオテープを写すテレビをポスターの前に置いた。これは前を通る観客の注意をひき,大きな人だかりができた。この研究はその後も国際的に(もちろん国内でも)評判となり,入來氏は人気者になった。2001年にはNeuroscience Research誌のExcellent Paper Awardを受賞,2004年の秋には,Minerva Foundation in CaliforniaからGolden Brain Awardを受賞した。本書はそのような彼の10年にわたる研究の成功物語である。本書には著者の見せる才能が遺憾なく発揮され,演出的配慮がいたるところになされている。たとえば,前書きにおける,幼少時アメリカ生活でのベンジャミン・フランクリンとの出会いであり,ベルクソンやカッシラーなど20世紀西欧哲学者の業績への言及であり,2種類のコラムのシリーズに書かれた,世界の有名美術館での哲学的思索の表出などである。
本書の思想的な柱はいくつかあるが,その1つは進化論である。サルとヒトの知的能力を連続的と見るのか不連続と見るのかはっきりしないところがあるが,これはいましばらく結論が出ない問題である。進化論への傾倒は生物学者であった著者の祖父の強い影響らしい。もう1つは西欧文明への憧憬である。ボディイメージという主観的現象を扱うとき,哲学的思索は避けることはできない。ただ,いうまでもなく哲学用語は特に翻訳されて紹介されると難解であり,定義された用語を使う実験科学としての生理学の枠からはずれ,著者が自分の思索のあとを哲学的に語るときにも,その意図が伝わりにくいところが多い。心理学や言語学の世界にも日常的に同じ悩みがある。一方,哲学に限らず,著者の芸術,学術,科学技術などにおける西欧文明への強い憧れがうかがえるが,彼の仕事がヨーロッパで高く評価されているのも,著者が西欧的文化基盤を並みの日本人以上に彼らと共有しているためであろうか。いずれにせよ,最初の発見から10年ほどで,遺伝子技法から脳イメージングまでさまざまな実験手法を駆使しての研究の展開ぶりがよくわかり,大変感銘を受けた。挿図や写真も適切である。本書はこれまでの殻を破ったユニークな科学読み物であり,若い研究者に研究の仕方を教え,勇気づける内容であると思われる。