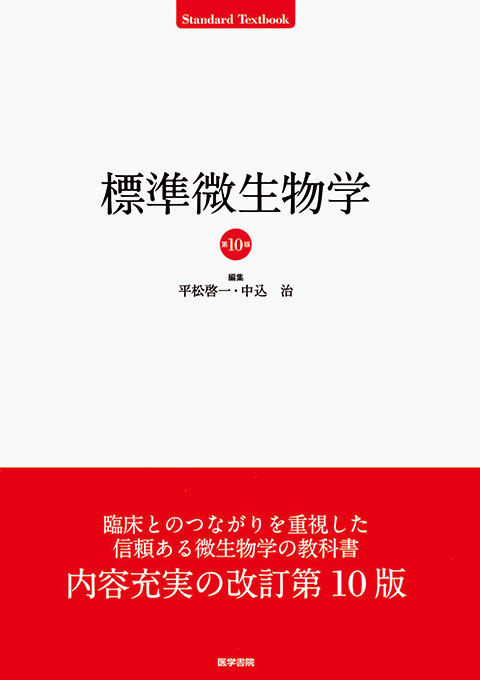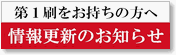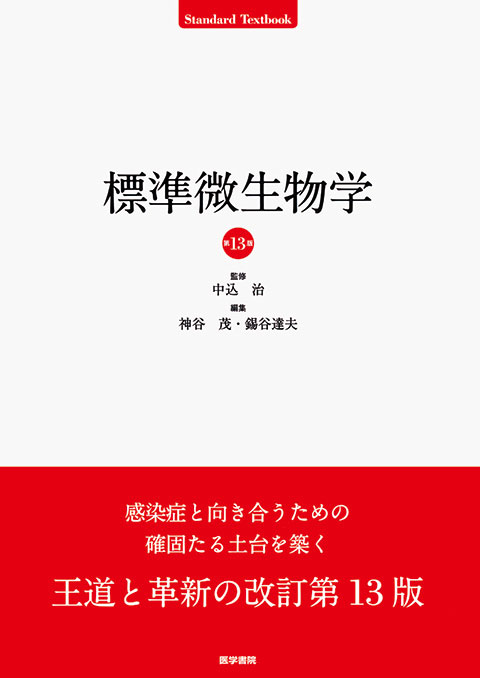標準微生物学 第10版
臨床とのつながりをいっそう重視した構成に、最新知見を盛り込み改訂
もっと見る
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
第10版 序
第10版編集の最終段階にあった2008年の晩秋に,ノーベル生理学・医学賞が「子宮頸癌を引き起こすヒトパピローマウイルスの発見」と「ヒト免疫不全ウイルスの発見」に対して授与されたというニュースが飛び込んできた。いずれも現代微生物学の人類に対する画期的貢献である。一方,新型インフルエンザのパンデミックが間近にも起こりうるという現状認識がわれわれに脅威を与えている。20世紀において新型インフルエンザウイルスの流行は3度あったが,1968年の香港かぜの流行を最後に,過去40年以上大流行を経験していない。現代のウイルス学が明らかにしたことによれば,1918年に大流行を起こしたスペインかぜのインフルエンザウイルスのゲノムは,そのすべてがトリインフルエンザウイルスに由来している。世界が,東南アジアにおけるトリインフルエンザのヒトへの感染に神経をとがらせている所以である。
われわれに脅威を与えているのは,このような新興感染症の世界的大流行ばかりではない。現代の高度先進医療は,かつて不可能だった臓器移植やさまざまな複雑・長時間にわたる外科手術を可能にした。これは,とりもなおさず免疫学的な弱者,すなわち易感染宿主が現代の病院にあふれていることを意味している。平素無害な日和見病原体はもとより,高度に耐性化したメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)が現代医療を根底からないがしろにしようとしている。
このような状況下にあって,感染症学およびその基礎となる病原微生物学をしっかり学ぶ意義は大きい。『標準微生物学』は初版からこの第10版に至るまで,医学における微生物学はいかにあるべきかという理念を求め時代の要請に応えるとともに,時代のゆく先に指針を与えるべく改訂を重ねてきた。特に前版では,医学教育における本書の利用価値を向上させるべく大改訂を試みたが,さらに使いやすくなるよう,この第10版においては次の3つの改良を試みた。
① 基礎医学である病原微生物学を学ぶことが,臨床医学における感染症学にどのように展開していくのか。病原微生物学の学習は,この感染症学への応用という視点を欠けばその意味を失いかねない。一方,感染症学の理解も,個々の病原微生物の生物学的特徴を知るという努力を欠けば危うい。このことを学生諸君に強く意識してもらうため,前版で「感染症の疫学」と「感染症と病原微生物学」の章を新設したが,第10版ではそれをより充実させるため,両章を統合し,さらに全身性炎症性反応症候群(SIRS)と新興感染症の項目を新たに加えて,「感染症の臨床へのアプローチ」という章を設けた。これは臨床の観点から病原微生物学の知識を再構成する試みである。学生諸君は,クロスリファレンスの労をいとわず各病原微生物の該当頁に目を通し,学んだ知識を有機的に結びつけてほしい。将来感染症と向き合う際に,ここで身につけた知識が必ず役に立つことだろう。
② 本書は,はじめて微生物学を学ぶ医学部の学生諸君を念頭に置いて書かれた教科書である。そのためカラー写真の点数を増やし,ビジュアルな理解の手助けとなるようにした。さらに,全体にわたり細かな見出しや内容構成,本文の記載などをあらため,より読みやすく・わかりやすくなるよう工夫した。また,初学者にとって使いやすい教科書となるよう,略語一覧と索引を充実させた。ふだんの学習において気になる用語やわからない用語があった際など,大いに活用して本書を使いこなしてもらいたい。
③ 学生諸君の学習の利便をはかるため,巻末付録として「細菌学・真菌学・ウイルス学の要点」を掲載した。これは本書第III章~第VII章の重要事項の記載を,おおむねそのまま抜き出して(一部は改変して)まとめたもので,いわば本書のエッセンスを凝縮したものである。ここを参照することで微生物学の重要事項を理解し,さらに本文の該当頁を再復習することで,知識に厚みを持たせてほしい。時に応じて復習すれば,学習者に大きな自信を与えるであろう。また,ポイントとなる語句は色文字とし,市販の赤いシートをかぶせることで消えるようにしてある。穴埋め問題集として繰り返しチェックを行うことで,医学生が最低限学ばねばならない微生物学の知識が身につくであろう。効率のよい学習のために,ぜひ活用してもらいたい。
上記のような改訂を行ったことで,まだまだ至らぬ点はあるにせよ,詳しいながらもわかりやすく,使い勝手のよい教科書となったと自負している。本書を活用することで,学生諸君が病原微生物学の生きた知識を身につけてくれることを望む。
最後に,改訂の趣旨を了解し,編集者からの少なからぬ無理な要求に快く応じられ執筆に協力してくださった分担執筆者に御礼申し上げる。また,校正は細心の注意をもって繰り返したが,なお意を尽くさぬところを懼れる。この点に関し,ぜひとも読者からの御叱正を賜りたい。お気づきの点があれば,ぜひ医学書院『標準微生物学』編集室宛にご連絡いただければ幸いである。
2009年3月
平松啓一
中込 治
第10版編集の最終段階にあった2008年の晩秋に,ノーベル生理学・医学賞が「子宮頸癌を引き起こすヒトパピローマウイルスの発見」と「ヒト免疫不全ウイルスの発見」に対して授与されたというニュースが飛び込んできた。いずれも現代微生物学の人類に対する画期的貢献である。一方,新型インフルエンザのパンデミックが間近にも起こりうるという現状認識がわれわれに脅威を与えている。20世紀において新型インフルエンザウイルスの流行は3度あったが,1968年の香港かぜの流行を最後に,過去40年以上大流行を経験していない。現代のウイルス学が明らかにしたことによれば,1918年に大流行を起こしたスペインかぜのインフルエンザウイルスのゲノムは,そのすべてがトリインフルエンザウイルスに由来している。世界が,東南アジアにおけるトリインフルエンザのヒトへの感染に神経をとがらせている所以である。
われわれに脅威を与えているのは,このような新興感染症の世界的大流行ばかりではない。現代の高度先進医療は,かつて不可能だった臓器移植やさまざまな複雑・長時間にわたる外科手術を可能にした。これは,とりもなおさず免疫学的な弱者,すなわち易感染宿主が現代の病院にあふれていることを意味している。平素無害な日和見病原体はもとより,高度に耐性化したメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)が現代医療を根底からないがしろにしようとしている。
このような状況下にあって,感染症学およびその基礎となる病原微生物学をしっかり学ぶ意義は大きい。『標準微生物学』は初版からこの第10版に至るまで,医学における微生物学はいかにあるべきかという理念を求め時代の要請に応えるとともに,時代のゆく先に指針を与えるべく改訂を重ねてきた。特に前版では,医学教育における本書の利用価値を向上させるべく大改訂を試みたが,さらに使いやすくなるよう,この第10版においては次の3つの改良を試みた。
① 基礎医学である病原微生物学を学ぶことが,臨床医学における感染症学にどのように展開していくのか。病原微生物学の学習は,この感染症学への応用という視点を欠けばその意味を失いかねない。一方,感染症学の理解も,個々の病原微生物の生物学的特徴を知るという努力を欠けば危うい。このことを学生諸君に強く意識してもらうため,前版で「感染症の疫学」と「感染症と病原微生物学」の章を新設したが,第10版ではそれをより充実させるため,両章を統合し,さらに全身性炎症性反応症候群(SIRS)と新興感染症の項目を新たに加えて,「感染症の臨床へのアプローチ」という章を設けた。これは臨床の観点から病原微生物学の知識を再構成する試みである。学生諸君は,クロスリファレンスの労をいとわず各病原微生物の該当頁に目を通し,学んだ知識を有機的に結びつけてほしい。将来感染症と向き合う際に,ここで身につけた知識が必ず役に立つことだろう。
② 本書は,はじめて微生物学を学ぶ医学部の学生諸君を念頭に置いて書かれた教科書である。そのためカラー写真の点数を増やし,ビジュアルな理解の手助けとなるようにした。さらに,全体にわたり細かな見出しや内容構成,本文の記載などをあらため,より読みやすく・わかりやすくなるよう工夫した。また,初学者にとって使いやすい教科書となるよう,略語一覧と索引を充実させた。ふだんの学習において気になる用語やわからない用語があった際など,大いに活用して本書を使いこなしてもらいたい。
③ 学生諸君の学習の利便をはかるため,巻末付録として「細菌学・真菌学・ウイルス学の要点」を掲載した。これは本書第III章~第VII章の重要事項の記載を,おおむねそのまま抜き出して(一部は改変して)まとめたもので,いわば本書のエッセンスを凝縮したものである。ここを参照することで微生物学の重要事項を理解し,さらに本文の該当頁を再復習することで,知識に厚みを持たせてほしい。時に応じて復習すれば,学習者に大きな自信を与えるであろう。また,ポイントとなる語句は色文字とし,市販の赤いシートをかぶせることで消えるようにしてある。穴埋め問題集として繰り返しチェックを行うことで,医学生が最低限学ばねばならない微生物学の知識が身につくであろう。効率のよい学習のために,ぜひ活用してもらいたい。
上記のような改訂を行ったことで,まだまだ至らぬ点はあるにせよ,詳しいながらもわかりやすく,使い勝手のよい教科書となったと自負している。本書を活用することで,学生諸君が病原微生物学の生きた知識を身につけてくれることを望む。
最後に,改訂の趣旨を了解し,編集者からの少なからぬ無理な要求に快く応じられ執筆に協力してくださった分担執筆者に御礼申し上げる。また,校正は細心の注意をもって繰り返したが,なお意を尽くさぬところを懼れる。この点に関し,ぜひとも読者からの御叱正を賜りたい。お気づきの点があれば,ぜひ医学書院『標準微生物学』編集室宛にご連絡いただければ幸いである。
2009年3月
平松啓一
中込 治
目次
開く
序論 近年の微生物感染症の動向
第I章 微生物学の歴史
第II章 環境と微生物
1 微生物の種類と微生物学の範囲
2 生体防御と感染
3 compromised hostと日和見感染
4 病原微生物の取り扱い
5 バイオセーフティー
第III章 細菌学総論
1 細菌の構造と機能
2 細菌の物質代謝の特徴
3 細菌遺伝学
4 細菌の病原性
細菌の病原因子/毒素1:内毒素(エンドトキシン)/毒素2:外毒素
5 細菌の分類と同定
6 細菌の化学療法
第IV章 細菌学各論
1 グラム陰性通性嫌気性桿菌
腸内細菌科/ビブリオ科/その他のグラム陰性通性嫌気性桿菌
2 グラム陰性好気性桿菌
3 無芽胞偏性嫌気性グラム陰性桿菌
4 グラム陰性球菌および球桿菌
5 グラム陰性嫌気性球菌
6 スピロヘータ科細菌,レプトスピラ科細菌およびらせん菌
スピロヘータ科/レプトスピラ科/らせん菌
7 グラム陽性球菌
8 有芽胞菌
9 グラム陽性無芽胞桿菌
10 放線菌とその関連細菌
11 口腔細菌
12 マイコプラズマ
13 リケッチア
14 クラミジア
第V章 真菌学
第VI章 ウイルス学総論
1 ウイルスの形態・構造・組成
2 ウイルスの分類と命名
3 ウイルスの増殖
4 ウイルスの遺伝・進化
5 ウイルスの病原性
6 ウイルスの検査室診断
7 ウイルス病の治療
第VII章 ウイルス学各論
1 RNA型ウイルス
2 DNA型ウイルス
3 肝炎ウイルス
4 プリオンと遅発性ウイルス感染症
第VIII章 感染症の臨床へのアプローチ
1 集団レベルでの感染論
2 院内感染
3 感染症の制圧と予防
4 人獣共通感染症(zoonoses):感染症理解へのもうひとつの視点
5 全身性炎症反応症候群(SIRS)
6 新興感染症(emerging infectious diseases)
7 臨床症状から病原診断へ:syndromic approach
付録 細菌学・真菌学・ウイルス学の要点
本書で用いた略語一覧
和文索引
欧文索引
第I章 微生物学の歴史
第II章 環境と微生物
1 微生物の種類と微生物学の範囲
2 生体防御と感染
3 compromised hostと日和見感染
4 病原微生物の取り扱い
5 バイオセーフティー
第III章 細菌学総論
1 細菌の構造と機能
2 細菌の物質代謝の特徴
3 細菌遺伝学
4 細菌の病原性
細菌の病原因子/毒素1:内毒素(エンドトキシン)/毒素2:外毒素
5 細菌の分類と同定
6 細菌の化学療法
第IV章 細菌学各論
1 グラム陰性通性嫌気性桿菌
腸内細菌科/ビブリオ科/その他のグラム陰性通性嫌気性桿菌
2 グラム陰性好気性桿菌
3 無芽胞偏性嫌気性グラム陰性桿菌
4 グラム陰性球菌および球桿菌
5 グラム陰性嫌気性球菌
6 スピロヘータ科細菌,レプトスピラ科細菌およびらせん菌
スピロヘータ科/レプトスピラ科/らせん菌
7 グラム陽性球菌
8 有芽胞菌
9 グラム陽性無芽胞桿菌
10 放線菌とその関連細菌
11 口腔細菌
12 マイコプラズマ
13 リケッチア
14 クラミジア
第V章 真菌学
第VI章 ウイルス学総論
1 ウイルスの形態・構造・組成
2 ウイルスの分類と命名
3 ウイルスの増殖
4 ウイルスの遺伝・進化
5 ウイルスの病原性
6 ウイルスの検査室診断
7 ウイルス病の治療
第VII章 ウイルス学各論
1 RNA型ウイルス
2 DNA型ウイルス
3 肝炎ウイルス
4 プリオンと遅発性ウイルス感染症
第VIII章 感染症の臨床へのアプローチ
1 集団レベルでの感染論
2 院内感染
3 感染症の制圧と予防
4 人獣共通感染症(zoonoses):感染症理解へのもうひとつの視点
5 全身性炎症反応症候群(SIRS)
6 新興感染症(emerging infectious diseases)
7 臨床症状から病原診断へ:syndromic approach
付録 細菌学・真菌学・ウイルス学の要点
本書で用いた略語一覧
和文索引
欧文索引
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。