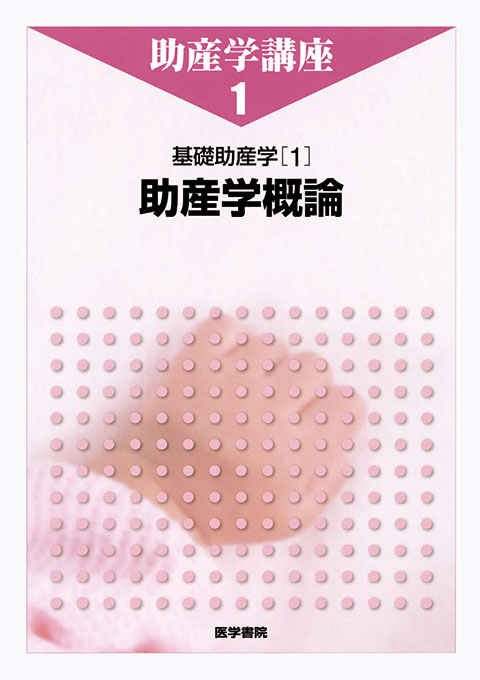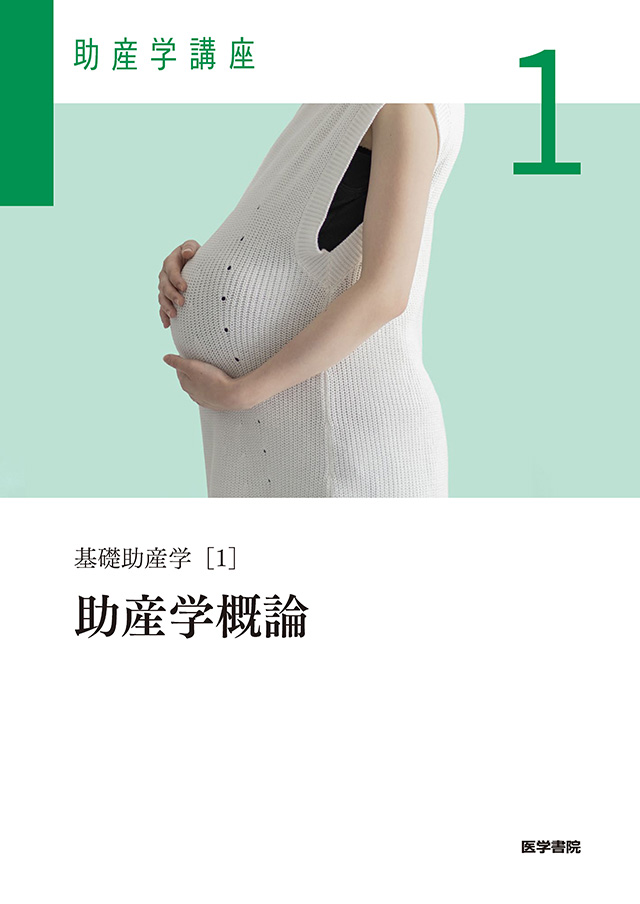基礎助産学[1]
助産学概論 第4版
本書の特長
もっと見る
執筆者全員交代による全面改訂を行い、助産学を学ぶうえで最初の導入となるべき基本的な概念や理論を解説。国家試験出題基準と照らし合わせ、助産の考え方、対象の特性、助産活動に必要な基礎知識を包含した内容となっています。また第4版では、新たにジェンダー、性差医療といった最新の話題、助産・助産師の歴史についても追加してあります。
*2013年版より表紙が新しくなりました。
| シリーズ | 助産学講座 1 |
|---|---|
| 編集 | 我部山 キヨ子 / 武谷 雄二 |
| 著 | 我部山 キヨ子 / 遠藤 俊子 / 大久保 功子 / 江角 二三子 / 石村 由利子 / 田母神 裕美 / 今関 節子 / 永山 くに子 |
| 発行 | 2008年03月判型:B5頁:248 |
| ISBN | 978-4-260-00547-0 |
| 定価 | 4,180円 (本体3,800円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
第4版の序
改訂の背景
平成8年の看護職員養成に関するカリキュラム改正から,はや11年が経過した。この間の母子を取り巻く社会情勢は大きく変化した。すなわち,家族規模の縮小化と養育機能の低下,離婚率の増加など,母子・親子関係の根幹が揺らぎ,家族機能は急速に弱体化しつつある。また,晩婚化・晩産化・少子化が進行し,次のような変化も起きてきた。従来にも増してハイリスク妊娠や妊婦の重症ケースが増え,医療の高度化が求められている。生殖補助医療は日々進歩,普及している。育児不安・子どもの虐待など育児をめぐる問題が多様化・深刻化している。さらには思春期の若者の性・生活・社会環境の変化から派生する性感染症・薬物依存・栄養障害などの健康問題,在日外国人の母子保健問題,女性へのドメスティック・バイオレンスやリプロダクティブ・ヘルス/ライツの問題,受精卵のES細胞や胎児組織の再生・移植医療への応用にあたっての問題など,母子や性と生殖に関する多くの課題が浮き彫りになり,大きな社会的問題となっている。
助産師業務も,このような母子(及び女性)とその家族の多種多様なニーズと急速な変化に対応するべく,変革をしてきた。ICMオーストラリア・ブリスベン大会(2005年7月)において改定された助産師の定義を見てみよう。まず助産師の責任や女性とのパートナーシップが強調されている。具体的なケアとして,正常分娩の推進,母子の合併症の発見,医療あるいはその他の適切な支援を利用すること,救急処置の実施から,女性の健康,性と生殖に関する健康,育児まで,女性とその家族・地域をも含めた生涯に渡るリプロダクティブ・ヘルス/ライツへの支援を明瞭に打ち出した。
助産師の活動する範囲や業務は拡大したにもかかわらず,助産師教育には次のような問題がある。近年,看護系大学の増加に伴い,4年制大学の中で助産師教育を行う教育機関が増加する一方,従来の1年課程の助産師教育機関は減少している。また,現行の保健師助産師看護師学校養成所指定規則(以下,指定規則)で定められた助産師教育に必要な単位数は22単位であるが,大学における助産師教育の平均卒業単位数は15.5±3.7単位である。これは従来の1年課程の助産師教育機関で行っていた単位数(多くは30単位前後)よりも大幅に下回っている(全国助産師教育協議会:看護大学における助産師教育の実際,p28,平成14年度事業活動報告書)。また,教育制度の変化や少子化の影響で,助産師学生の卒業時技術到達度として指定規則で定める出産介助例数(10例程度)を下回るなど,臨床技術が未熟なまま助産師資格を得てしまう問題も生じている。
このような現状に対し,平成13年の保健師助産師看護師法改正案の審議過程で,衆参両院で助産師教育の状況に関して多くの議論がなされ,助産師教育の充実を図るための附帯決議として,(1)出産に関するケアを受ける者の意向が尊重され,それぞれの者にあったサービスの提供が行われるよう,情報提供の促進を含め必要な環境の整備に努めること,(2)助産師教育については,学校養成所指定規則に定める十分な出産介助実習が経験できるようにする等,その充実に努めること(以下省略),と付記された。平成19(2007)年4月には「厚生労働省:看護基礎教育の充実に関する検討会」から,看護基礎教育におけるカリキュラム改正案や,実施にあたる教員・実習指導者等に関する報告書がまとめられ,平成20(2008)年4月に指定規則が一部改正,施行されることとなった〔平成21(2009)年度入学生から新カリキュラムを適用〕。
改訂の趣旨
本講座は第一義には助産師学生の基礎教育テキストである。助産師国家試験出題基準で示された内容を網羅するよう,改訂第4版を企画した。現行カリキュラムの基本的枠組みを踏襲しつつ,EBMを踏まえた基礎的内容と発展的内容を押さえるように再編成している。そのねらいは,助産学教育の水準を向上させ,助産学の発展・確立に寄与することで,具体的には改訂の背景で前述したような状況にも対応できる助産師を養成することである。
2008年版では,「助産診断・技術学」の改訂にひきつづき,「基礎助産学」全4巻を全面改訂した。今回の改訂では,(1)正常な妊娠,分娩,産褥経過をたどる女性と新生児の健康水準を診断し,継続的なケアを独立して行うことができる,(2)正常からの逸脱を識別することができる,(3)変動する社会の要請や関連諸科学・技術の進歩に対応できる,という3つの大きな学習目標を意識し,助産学の確立および助産実践の基礎的・科学的基盤となる知識を体系的にまとめた。特に女性のライフサイクルを通じた性と生殖の健康問題という視点を重視している。また健康科学関連の知識は大幅に拡充して,第3巻「母子の健康科学」として新たにラインナップした。いずれの巻も最新の知見をもとにデータを刷新するとともに,最近の動向を反映した内容となっている。平成20(2008)年4月施行予定の新カリキュラム(改正案)で示されている教育内容にも十分に配慮している。
助産師学生のための教科書としてのみならず,臨床や地域で活躍する助産師の皆様の指導書として,本書を広く活用していただければと,切に願っている。
2007年12月
編者ら
改訂の背景
平成8年の看護職員養成に関するカリキュラム改正から,はや11年が経過した。この間の母子を取り巻く社会情勢は大きく変化した。すなわち,家族規模の縮小化と養育機能の低下,離婚率の増加など,母子・親子関係の根幹が揺らぎ,家族機能は急速に弱体化しつつある。また,晩婚化・晩産化・少子化が進行し,次のような変化も起きてきた。従来にも増してハイリスク妊娠や妊婦の重症ケースが増え,医療の高度化が求められている。生殖補助医療は日々進歩,普及している。育児不安・子どもの虐待など育児をめぐる問題が多様化・深刻化している。さらには思春期の若者の性・生活・社会環境の変化から派生する性感染症・薬物依存・栄養障害などの健康問題,在日外国人の母子保健問題,女性へのドメスティック・バイオレンスやリプロダクティブ・ヘルス/ライツの問題,受精卵のES細胞や胎児組織の再生・移植医療への応用にあたっての問題など,母子や性と生殖に関する多くの課題が浮き彫りになり,大きな社会的問題となっている。
助産師業務も,このような母子(及び女性)とその家族の多種多様なニーズと急速な変化に対応するべく,変革をしてきた。ICMオーストラリア・ブリスベン大会(2005年7月)において改定された助産師の定義を見てみよう。まず助産師の責任や女性とのパートナーシップが強調されている。具体的なケアとして,正常分娩の推進,母子の合併症の発見,医療あるいはその他の適切な支援を利用すること,救急処置の実施から,女性の健康,性と生殖に関する健康,育児まで,女性とその家族・地域をも含めた生涯に渡るリプロダクティブ・ヘルス/ライツへの支援を明瞭に打ち出した。
助産師の活動する範囲や業務は拡大したにもかかわらず,助産師教育には次のような問題がある。近年,看護系大学の増加に伴い,4年制大学の中で助産師教育を行う教育機関が増加する一方,従来の1年課程の助産師教育機関は減少している。また,現行の保健師助産師看護師学校養成所指定規則(以下,指定規則)で定められた助産師教育に必要な単位数は22単位であるが,大学における助産師教育の平均卒業単位数は15.5±3.7単位である。これは従来の1年課程の助産師教育機関で行っていた単位数(多くは30単位前後)よりも大幅に下回っている(全国助産師教育協議会:看護大学における助産師教育の実際,p28,平成14年度事業活動報告書)。また,教育制度の変化や少子化の影響で,助産師学生の卒業時技術到達度として指定規則で定める出産介助例数(10例程度)を下回るなど,臨床技術が未熟なまま助産師資格を得てしまう問題も生じている。
このような現状に対し,平成13年の保健師助産師看護師法改正案の審議過程で,衆参両院で助産師教育の状況に関して多くの議論がなされ,助産師教育の充実を図るための附帯決議として,(1)出産に関するケアを受ける者の意向が尊重され,それぞれの者にあったサービスの提供が行われるよう,情報提供の促進を含め必要な環境の整備に努めること,(2)助産師教育については,学校養成所指定規則に定める十分な出産介助実習が経験できるようにする等,その充実に努めること(以下省略),と付記された。平成19(2007)年4月には「厚生労働省:看護基礎教育の充実に関する検討会」から,看護基礎教育におけるカリキュラム改正案や,実施にあたる教員・実習指導者等に関する報告書がまとめられ,平成20(2008)年4月に指定規則が一部改正,施行されることとなった〔平成21(2009)年度入学生から新カリキュラムを適用〕。
改訂の趣旨
本講座は第一義には助産師学生の基礎教育テキストである。助産師国家試験出題基準で示された内容を網羅するよう,改訂第4版を企画した。現行カリキュラムの基本的枠組みを踏襲しつつ,EBMを踏まえた基礎的内容と発展的内容を押さえるように再編成している。そのねらいは,助産学教育の水準を向上させ,助産学の発展・確立に寄与することで,具体的には改訂の背景で前述したような状況にも対応できる助産師を養成することである。
2008年版では,「助産診断・技術学」の改訂にひきつづき,「基礎助産学」全4巻を全面改訂した。今回の改訂では,(1)正常な妊娠,分娩,産褥経過をたどる女性と新生児の健康水準を診断し,継続的なケアを独立して行うことができる,(2)正常からの逸脱を識別することができる,(3)変動する社会の要請や関連諸科学・技術の進歩に対応できる,という3つの大きな学習目標を意識し,助産学の確立および助産実践の基礎的・科学的基盤となる知識を体系的にまとめた。特に女性のライフサイクルを通じた性と生殖の健康問題という視点を重視している。また健康科学関連の知識は大幅に拡充して,第3巻「母子の健康科学」として新たにラインナップした。いずれの巻も最新の知見をもとにデータを刷新するとともに,最近の動向を反映した内容となっている。平成20(2008)年4月施行予定の新カリキュラム(改正案)で示されている教育内容にも十分に配慮している。
助産師学生のための教科書としてのみならず,臨床や地域で活躍する助産師の皆様の指導書として,本書を広く活用していただければと,切に願っている。
2007年12月
編者ら
目次
開く
第1章 助産の概念
A 助産の概念
B 助産に関係する概念
第2章 助産師の職制と業務
A 助産師と法律
B 助産師の職制としての推移と国際的な職制
C 保健師助産師看護師法からみた助産師の身分
D 助産師の業務・責務と今後の展望
第3章 助産学を支える理論
A 助産学を構成する理論
B 研究と助産師
第4章 助産師と倫理
A 助産師と倫理
第5章 母子保健の動向
A 母子保健の歴史
B 現代の母子保健
C 母子保健の動向と諸制度
第6章 助産の歴史
A 古代から江戸時代までの助産の変遷推移
B 明治~昭和初期(第2次世界大戦まで)の助産の変遷
第7章 助産師教育の変遷
A わが国における助産師教育の歴史
B 諸外国における助産師教育
付章 関係法規
索引
A 助産の概念
B 助産に関係する概念
第2章 助産師の職制と業務
A 助産師と法律
B 助産師の職制としての推移と国際的な職制
C 保健師助産師看護師法からみた助産師の身分
D 助産師の業務・責務と今後の展望
第3章 助産学を支える理論
A 助産学を構成する理論
B 研究と助産師
第4章 助産師と倫理
A 助産師と倫理
第5章 母子保健の動向
A 母子保健の歴史
B 現代の母子保健
C 母子保健の動向と諸制度
第6章 助産の歴史
A 古代から江戸時代までの助産の変遷推移
B 明治~昭和初期(第2次世界大戦まで)の助産の変遷
第7章 助産師教育の変遷
A わが国における助産師教育の歴史
B 諸外国における助産師教育
付章 関係法規
索引
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。