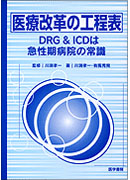医療改革の工程表
DRG & ICDは急性期病院の常識
病院経営のための道しるべ
もっと見る
医療制度改革が急スピードで押し進められるなか,医療情報は日々錯綜し,病院経営事業においても,その取捨選択に難渋しているのが現状である。本書は医療改革の救世主となるDRG,さらにはICDについて,詳細な解説から具体的手法に到るまでの全てを網羅した,病院経営に携わる者の「道しるべ」となる必携の書である。
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 目次
- 書評
目次
開く
第1章 いま何故DRGか-聖域なき構造改革が医療界に突きつけたもの
第2章 DRGをいかに使うか
第3章 DRG事業にどうすれば参加できるか
第4章 ICDに関する演習問題
第2章 DRGをいかに使うか
第3章 DRG事業にどうすれば参加できるか
第4章 ICDに関する演習問題
書評
開く
キラリ輝く医療改革に向けた具体論
書評者: 飯野 奈津子 (NHK解説委員)
増え続ける医療費をどう抑制するか,質の高い医療を望む国民の声にどう応えるか。来年度に予定されている医療制度の抜本改革に向けた議論が本格化している。
これまで,厚生労働省や各関連団体から改革案が示されているが,どれも具体性に欠け,これぞ抜本改革と思われるものが見当たらない。その中で,本書が示す医療改革の工程表はキラリと輝いている。
◆DRG手法をいかに医療改革に生かすか
本書のテーマは,DRGという手法をいかに日本の医療改革に生かしていくかという点だ。DRGというと,すぐに医療費の支払い方法と結びつけて考えてしまうが,そもそも病院の運営の無駄を省いて,生産性を上げるためのマネジメント手法として開発されたものだ。患者に使ったマンパワーや薬剤,医療材料,入院日数,コストなどのデータをできるだけ多くの病院から集めて,一定の疾患ごとに分析することで,それぞれの病院の改善点を明確にすることだという。
本書では,DRGを使って,著者が試みてきた病院ベンチマーク事業が紹介されている。病院から集めたデータをもとに,疾患ごとに患者1人あたりのコストや,死亡率や再入院率,それに入院日数などを比較して,それぞれの病院が全体の中でどの位置にあるのか,一目でわかるよう分析されている。こうした情報があれば,医療提供側みずからコスト管理や医療の質を改善するきっかけとなり,また,患者の側にも情報が提供されれば,医療機関を選択するのに大いに役立つはずである。
◆必要な科学的根拠に基づく病院機能分析
今,日本の医療界に必要なのは,こうした科学的根拠に基づく病院機能の分析ではないだろうか。どの病院がどれだけの症例数をこなし,どれだけコストをかけて,どのような治療成果をあげているのか。こうした情報分析があってこそ,「医療の効率化」と「医療の質の向上」に向けた具体的な改革が進んでいくのではないだろうか。
総論ばかりの医療制度の改革案が目立つ中で,本書がキラリと輝いているのは,改革に向けた具体論が提示されているからに違いない。医療制度改革を考える人たちや病院を経営する人たちに,ぜひ読んでほしい1冊である。
予想される医療改革に向けての病院経営行動指針
書評者: 堺 常雄 (聖隷浜松病院長)
◆公表された「医療制度改革試案」への対処
「聖域なき構造改革」が言われ,一方で日本の医療が制度疲労をきたしているという認識が持たれている中で,これからの医療制度がどうあるべきか,厚生労働省は2001年(平成13)年9月25日に「医療制度改革試案」を公表した。これに対して,財務省からは医療制度改革の論点が公表され,経済財政諮問会議でも議論がなされている。
総じて厚生労働省への風当たりは強くなっているが,ひるがえって実際に医療を提供している現場は,どのように対処すべきであろうか。物事を受身にとらえるのではなく,自分たちから積極的に行動を起こす以外ないというのが実状であろう。そのような時期にタイムリーに出版されたのが,この『医療改革の工程表』である。監修・著者の川渕孝一氏は,すでに前著『DRG/PPSの全貌と問題点』,『DRG/PPS導入の条件と環境』(ともにじほう社)でおなじみであるが,今回は,DRG関連書の3冊目として東京医科歯科大学大学院医療経済学分野の有馬秀晃氏と共著での出版となった。
◆新しい病院経営ツールとしてのDRGへの理解
本書は,DRGの基礎的な部分に言及した第1-2章と実践的な第3-4章からなっている。
「第1章 いま何故DRGか」では,医療制度改革の中味が説明され,良質かつ効率的な医療の提供がなされなければならず,そのためには,「選択と集中」が必要であるという著者の持論が述べられている。DRGは,医療資源の利用状況やコストを「プロダクトライン」の観点から見ることができるため,「選択と集中」のツールとして適している。また,この章では,ICDコーディングの重要性についても言及されている。
「第2章 DRGをいかに使うか」では,DRGのマネジメントツール,政策提言としての2つの役割について述べられている。ここでは,日医総研の第2次定点観測事業(病院ベンチマーク事業)の結果が紹介され,科学的根拠に基づく病院機能の分析がDRGによって可能であり,医療現場でDRGに積極的に取り組むべきであるという示唆がなされている。
「第3章 DRG事業にどうすれば参加できるか」では,ICDコーディングの解説をとおして,コーディングがDRGにとっては,「命」であることが述べられ,ICDからDRGに転換する具体例が示されている。章末資料として,「第4次病院ベンチマーク事業」調査票が添付されており,各病院の積極的な参加を望むところである。
「第4章 ICDに関する演習問題」では,実際の患者カルテから抜粋したケースをもとに,診療情報管理士が行なうコーディングについて臓器別に例題,解答,解説の順で述べられ,非常に理解しやすいものとなっている。また,ITを活用したコーディングの実践例も示され有益である。
◆深めたい「病院運営も科学」という認識
医療制度改革に対して多くの医療機関は消極的であったし,なるべくなら自分たちの既得権を守り,影響が少なければよいという自分中心のとらえ方であったと思われる。しかし,本書で述べられているように「医療も聖域」ではなくなったのであり,医療の中心は,それを受ける利用者であるということを再確認する必要があるだろう。
本書では,そのための「医療改革の工程表」が明確に示されており,医療機関のパフォーマンスを示すツールとしてのDRGの役割がよく理解できる。今まで病院の片隅で行なわれていた診療情報管理が,医療の質と効率の面から病院運営の表舞台に登場してきたと言えよう。その意味でも,本書は急性期病院をめざす医療機関の経営担当者のみならず,診療情報管理士にも必読の書である。まさに「選択と集中」が行なわれようとしている現在,行動の有無で医療機関の存亡が決まろうとしているのであり,本書を参考に速やかに行動を開始したいものである。さらには,今までの伝統的な病院経営指標ではない新しいツールとしてのDRGを理解して,病院運営も科学であるという認識を深めていただきたいものである。
書評者: 飯野 奈津子 (NHK解説委員)
増え続ける医療費をどう抑制するか,質の高い医療を望む国民の声にどう応えるか。来年度に予定されている医療制度の抜本改革に向けた議論が本格化している。
これまで,厚生労働省や各関連団体から改革案が示されているが,どれも具体性に欠け,これぞ抜本改革と思われるものが見当たらない。その中で,本書が示す医療改革の工程表はキラリと輝いている。
◆DRG手法をいかに医療改革に生かすか
本書のテーマは,DRGという手法をいかに日本の医療改革に生かしていくかという点だ。DRGというと,すぐに医療費の支払い方法と結びつけて考えてしまうが,そもそも病院の運営の無駄を省いて,生産性を上げるためのマネジメント手法として開発されたものだ。患者に使ったマンパワーや薬剤,医療材料,入院日数,コストなどのデータをできるだけ多くの病院から集めて,一定の疾患ごとに分析することで,それぞれの病院の改善点を明確にすることだという。
本書では,DRGを使って,著者が試みてきた病院ベンチマーク事業が紹介されている。病院から集めたデータをもとに,疾患ごとに患者1人あたりのコストや,死亡率や再入院率,それに入院日数などを比較して,それぞれの病院が全体の中でどの位置にあるのか,一目でわかるよう分析されている。こうした情報があれば,医療提供側みずからコスト管理や医療の質を改善するきっかけとなり,また,患者の側にも情報が提供されれば,医療機関を選択するのに大いに役立つはずである。
◆必要な科学的根拠に基づく病院機能分析
今,日本の医療界に必要なのは,こうした科学的根拠に基づく病院機能の分析ではないだろうか。どの病院がどれだけの症例数をこなし,どれだけコストをかけて,どのような治療成果をあげているのか。こうした情報分析があってこそ,「医療の効率化」と「医療の質の向上」に向けた具体的な改革が進んでいくのではないだろうか。
総論ばかりの医療制度の改革案が目立つ中で,本書がキラリと輝いているのは,改革に向けた具体論が提示されているからに違いない。医療制度改革を考える人たちや病院を経営する人たちに,ぜひ読んでほしい1冊である。
予想される医療改革に向けての病院経営行動指針
書評者: 堺 常雄 (聖隷浜松病院長)
◆公表された「医療制度改革試案」への対処
「聖域なき構造改革」が言われ,一方で日本の医療が制度疲労をきたしているという認識が持たれている中で,これからの医療制度がどうあるべきか,厚生労働省は2001年(平成13)年9月25日に「医療制度改革試案」を公表した。これに対して,財務省からは医療制度改革の論点が公表され,経済財政諮問会議でも議論がなされている。
総じて厚生労働省への風当たりは強くなっているが,ひるがえって実際に医療を提供している現場は,どのように対処すべきであろうか。物事を受身にとらえるのではなく,自分たちから積極的に行動を起こす以外ないというのが実状であろう。そのような時期にタイムリーに出版されたのが,この『医療改革の工程表』である。監修・著者の川渕孝一氏は,すでに前著『DRG/PPSの全貌と問題点』,『DRG/PPS導入の条件と環境』(ともにじほう社)でおなじみであるが,今回は,DRG関連書の3冊目として東京医科歯科大学大学院医療経済学分野の有馬秀晃氏と共著での出版となった。
◆新しい病院経営ツールとしてのDRGへの理解
本書は,DRGの基礎的な部分に言及した第1-2章と実践的な第3-4章からなっている。
「第1章 いま何故DRGか」では,医療制度改革の中味が説明され,良質かつ効率的な医療の提供がなされなければならず,そのためには,「選択と集中」が必要であるという著者の持論が述べられている。DRGは,医療資源の利用状況やコストを「プロダクトライン」の観点から見ることができるため,「選択と集中」のツールとして適している。また,この章では,ICDコーディングの重要性についても言及されている。
「第2章 DRGをいかに使うか」では,DRGのマネジメントツール,政策提言としての2つの役割について述べられている。ここでは,日医総研の第2次定点観測事業(病院ベンチマーク事業)の結果が紹介され,科学的根拠に基づく病院機能の分析がDRGによって可能であり,医療現場でDRGに積極的に取り組むべきであるという示唆がなされている。
「第3章 DRG事業にどうすれば参加できるか」では,ICDコーディングの解説をとおして,コーディングがDRGにとっては,「命」であることが述べられ,ICDからDRGに転換する具体例が示されている。章末資料として,「第4次病院ベンチマーク事業」調査票が添付されており,各病院の積極的な参加を望むところである。
「第4章 ICDに関する演習問題」では,実際の患者カルテから抜粋したケースをもとに,診療情報管理士が行なうコーディングについて臓器別に例題,解答,解説の順で述べられ,非常に理解しやすいものとなっている。また,ITを活用したコーディングの実践例も示され有益である。
◆深めたい「病院運営も科学」という認識
医療制度改革に対して多くの医療機関は消極的であったし,なるべくなら自分たちの既得権を守り,影響が少なければよいという自分中心のとらえ方であったと思われる。しかし,本書で述べられているように「医療も聖域」ではなくなったのであり,医療の中心は,それを受ける利用者であるということを再確認する必要があるだろう。
本書では,そのための「医療改革の工程表」が明確に示されており,医療機関のパフォーマンスを示すツールとしてのDRGの役割がよく理解できる。今まで病院の片隅で行なわれていた診療情報管理が,医療の質と効率の面から病院運営の表舞台に登場してきたと言えよう。その意味でも,本書は急性期病院をめざす医療機関の経営担当者のみならず,診療情報管理士にも必読の書である。まさに「選択と集中」が行なわれようとしている現在,行動の有無で医療機関の存亡が決まろうとしているのであり,本書を参考に速やかに行動を開始したいものである。さらには,今までの伝統的な病院経営指標ではない新しいツールとしてのDRGを理解して,病院運営も科学であるという認識を深めていただきたいものである。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。