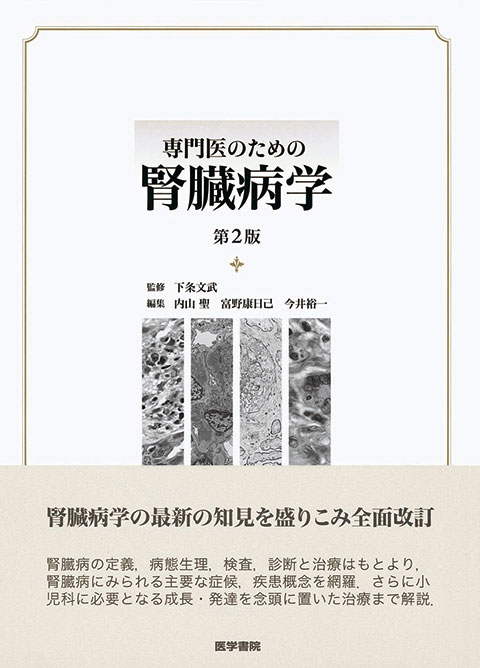専門医のための腎臓病学
第一線の臨床家に贈る臨床志向の実践書
もっと見る
内科・小児科を問わず,腎臓病を専門とする第一線臨床家を対象とした実践書。〔症候編〕と〔疾患編〕で構成。症候編では腎の構造と機能をベースにおいた診断の進め方を,疾患編では高頻度に認められる疾患の病態生理・診断・治療をまとめた。あえて〔基礎編〕は作らず,項目ごとに必要事項を織り込んで解説した臨床志向の1冊。
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 目次
- 書評
目次
開く
I. 症候編
1. 蛋白尿
2. 血尿
3. 膿尿
4. 糖尿
5. 乏尿・無尿・多尿
6. 浮腫
7. 頻尿
8. 排尿痛
9. 夜間尿と尿濃縮
10. 高血圧
11. 電解質異常
12. 酸・塩基平衡障害
II. 疾患各論
1. 急性腎不全
2. 慢性腎不全
3. 急性糸球体腎炎
4. 急速進行性糸球体腎炎
5. ネフローゼ症候群
6. メサンギウム増殖性糸球体腎炎-IgA腎症
7. 膜性腎症
8. 膜性増殖性糸球体腎炎
9. 家族性・遺伝性疾患
10. 膠原病と類縁疾患による腎障害
11. 紫斑病性腎炎
12. 肝疾患と腎糸球体病変
13. クリオグロブリン血症に伴う腎病変
14. アミロイド腎症
15. 多発性骨髄腫における腎障害
16. Immunotactoid glomerulopathy/Fibrillary glomerulonephritis
17. リポ蛋白糸球体症
18. 腎硬化症
19. 糖尿病性腎症
20. 妊娠中毒症
21. 痛風腎
22. 溶血性尿毒症症候群
23. 尿細管間質性腎炎(急性・慢性)
24. 尿細管機能異常
25. 中毒性腎症(薬物,重金属)
26. 尿路感染症
27. 尿路結石症
28. 血液浄化療法
29. 腎移植
1. 蛋白尿
2. 血尿
3. 膿尿
4. 糖尿
5. 乏尿・無尿・多尿
6. 浮腫
7. 頻尿
8. 排尿痛
9. 夜間尿と尿濃縮
10. 高血圧
11. 電解質異常
12. 酸・塩基平衡障害
II. 疾患各論
1. 急性腎不全
2. 慢性腎不全
3. 急性糸球体腎炎
4. 急速進行性糸球体腎炎
5. ネフローゼ症候群
6. メサンギウム増殖性糸球体腎炎-IgA腎症
7. 膜性腎症
8. 膜性増殖性糸球体腎炎
9. 家族性・遺伝性疾患
10. 膠原病と類縁疾患による腎障害
11. 紫斑病性腎炎
12. 肝疾患と腎糸球体病変
13. クリオグロブリン血症に伴う腎病変
14. アミロイド腎症
15. 多発性骨髄腫における腎障害
16. Immunotactoid glomerulopathy/Fibrillary glomerulonephritis
17. リポ蛋白糸球体症
18. 腎硬化症
19. 糖尿病性腎症
20. 妊娠中毒症
21. 痛風腎
22. 溶血性尿毒症症候群
23. 尿細管間質性腎炎(急性・慢性)
24. 尿細管機能異常
25. 中毒性腎症(薬物,重金属)
26. 尿路感染症
27. 尿路結石症
28. 血液浄化療法
29. 腎移植
書評
開く
よりレベルの高い腎臓専門医をめざすための座右の書
書評者: 酒井 糾 (北里大名誉教授)
このたび,医学書院から発刊された,『専門医のための腎臓病学』は,日本の腎臓学会でご活躍中の先生方によって執筆されたもので,実にバランスよくしかもアップデートの知見をも網羅した内容となっており,読む者にとっては,まさにこれこそ座右の書となるものである。下条文武教授,内山聖教授,富野康日己教授,お三方の見事な編集に敬意を表したい。
◆医学・医療の視点から将来を見据えた内容
本書は,企画から発行までわずか13か月という稀に見るスピードで作られた本と聞いているが,内容的にはすばらしいものとなっており,腎臓病学の全般を医学・医療の視点はもとより,各々の将来を見据えた内容でまとめられている。これぞまさしく21世紀初頭を飾るにふさわしい専門書として,きわめて意義深いものを感じている。20世紀終盤の四半世紀から21世紀にかけての腎臓病学の基礎的進歩が,どれほど臨床医学のありようをエキサイティングにしたかはどの切り口を見ても明らかであるが,そうした時代背景を持つ学問領域をそれぞれの執筆者がわかりやすく記述されている。
本書の特徴は,大項目として「症候編」と「疾患各論」の2部構成でまとめられている点である。編集の熱のこもった序文からうかがい知れるところであるが,腎臓病学の新しい知識をどのように患者の診療に生かすか,特にそれらを踏まえて臨床医に求められる新しい知識の増幅をいかにして求めやすくするか,こうしたきわめて高いレベルの要求を満たそうとする姿勢が随所に見られる。一節を借りれば,「腎臓専門医には,蛋白尿・血尿など尿異常の解析から,腎生理学と水・電解質代謝の理解,腎生検などによる一次性・二次性腎疾患の診断と治療管理,末期腎不全に対する透析治療と腎移植まできわめて広範囲にわたり,かつ高度のものが要求されるようになっている」とした文言で編集の思いが綴られており,読者に対するメッセージがその通り伝わってくる。
◆プロ中のプロをめざすために最適
今や腎臓病学は内科,小児科,泌尿器科はもとより周辺医科学のプロフェッショナルに対しても共創の場が提供されており,まさしく基礎医学から臨床医学におよぶ相互連関が広がりをみせている学問領域である。しかし何としても臨床の場で腎臓病患者を診療する臨床医はもちろん,これから腎臓病専門医をめざそうとする若い医師にとっては,本書がプロフェッショナルとしての力をつける上に最適の書となることは,間違いないものと信じる。特筆すべきは,小児科の視点を数多く取り入れたこと,そして随所に小児科医の追記がある点もネフロロジーをトータルにとらえるとした狙いが感じられる。また,血液浄化療法,腎移植といった20世紀治療医学の双璧をそれぞれ独立して取り入れたのは,腎臓病学とした書名にあっても治療医学の重要性を加味されたものとしてきわめて意義深く感じられる。
本書は,21世紀のわが国の腎臓専門医と,それをめざす先生方の座右の書であると確信するとともに,本書が広く活用されることを祈念してやまない。
腎臓病を専門とする第一線臨床家を対象とした実践書
書評者: 浅野 泰 (自治医大教授・腎臓内科学/日本腎臓学会理事長)
◆明確な目的をもった編集
腎臓病に関する書籍は多数あるが,対象読者を研修医にしているのか,一般実地医家か,それとも腎臓病を専門とする医師にしているのか明確でないものが多い。それぞれの立場からすれば,「帯に短し襷に長し」である。そんな中で,本書は第一線の腎臓病患者を診察している腎臓専門医や,それをめざしている研修医を対象とするという明確な目的をもって編集されたものである。
それだけに,本書の内容も最新の情報や治療指針のみならず一部進行中の研究内容まで披露されており,かつよく整理記載されている。
◆臨床と密着した充実した内容
一方,一般的な書籍とは異なり臨床と密着した内容とする編集方針もあって,腎臓の構造や生理学的な基礎事項を記載する章はなく,研修医には若干もの足りなさを感じるかもしれない。しかし,このことに関しては,他にいくらでも見るべき書籍はあり,本書の目的とした臨床に密着した内容の充実がなされているので,読者も満足してくれるものと思われる。特に小児から成人にまたがる疾患については,それぞれの項で「小児科の視点」を加えたことは他に類を見ない優れた視点となっている。患者側からすれば,乳幼児,小児,成人と連続してかかわってきた同一疾患にかかわらず,そのつど主治医が変更となり,また時には治療方針の変化から不安となるのは当然のことである。小児科医と内科医との間の連携をもっと深めるべきであると日本腎臓学会でも長らく叫ばれてきたが,この点に着目されて計画されたことも,本書の優れたところと言えよう。
なお,執筆者には新進の次世代の腎臓病学を担う若手も目立ち,それはそれで頼もしい限りであるが,細部まで見証すると,使用された図表の出典が明らかとなっていないものがある。往々にして若手の,また日本人の疑りやすい点であるが,まったくのオリジナルの図表でない限り(以前に用いた自著の図表であっても),許諾も含めて出典を明らかにしなければならないことは,ぜひともシニアの先生方から指導していただきたい。
以上を除けば,本書はこれまでにない編集方針と内容で作製されたものであり,腎臓病の専門医,またそれをめざす研修医に良書としてぜひともお勧めしたい書である。
書評者: 酒井 糾 (北里大名誉教授)
このたび,医学書院から発刊された,『専門医のための腎臓病学』は,日本の腎臓学会でご活躍中の先生方によって執筆されたもので,実にバランスよくしかもアップデートの知見をも網羅した内容となっており,読む者にとっては,まさにこれこそ座右の書となるものである。下条文武教授,内山聖教授,富野康日己教授,お三方の見事な編集に敬意を表したい。
◆医学・医療の視点から将来を見据えた内容
本書は,企画から発行までわずか13か月という稀に見るスピードで作られた本と聞いているが,内容的にはすばらしいものとなっており,腎臓病学の全般を医学・医療の視点はもとより,各々の将来を見据えた内容でまとめられている。これぞまさしく21世紀初頭を飾るにふさわしい専門書として,きわめて意義深いものを感じている。20世紀終盤の四半世紀から21世紀にかけての腎臓病学の基礎的進歩が,どれほど臨床医学のありようをエキサイティングにしたかはどの切り口を見ても明らかであるが,そうした時代背景を持つ学問領域をそれぞれの執筆者がわかりやすく記述されている。
本書の特徴は,大項目として「症候編」と「疾患各論」の2部構成でまとめられている点である。編集の熱のこもった序文からうかがい知れるところであるが,腎臓病学の新しい知識をどのように患者の診療に生かすか,特にそれらを踏まえて臨床医に求められる新しい知識の増幅をいかにして求めやすくするか,こうしたきわめて高いレベルの要求を満たそうとする姿勢が随所に見られる。一節を借りれば,「腎臓専門医には,蛋白尿・血尿など尿異常の解析から,腎生理学と水・電解質代謝の理解,腎生検などによる一次性・二次性腎疾患の診断と治療管理,末期腎不全に対する透析治療と腎移植まできわめて広範囲にわたり,かつ高度のものが要求されるようになっている」とした文言で編集の思いが綴られており,読者に対するメッセージがその通り伝わってくる。
◆プロ中のプロをめざすために最適
今や腎臓病学は内科,小児科,泌尿器科はもとより周辺医科学のプロフェッショナルに対しても共創の場が提供されており,まさしく基礎医学から臨床医学におよぶ相互連関が広がりをみせている学問領域である。しかし何としても臨床の場で腎臓病患者を診療する臨床医はもちろん,これから腎臓病専門医をめざそうとする若い医師にとっては,本書がプロフェッショナルとしての力をつける上に最適の書となることは,間違いないものと信じる。特筆すべきは,小児科の視点を数多く取り入れたこと,そして随所に小児科医の追記がある点もネフロロジーをトータルにとらえるとした狙いが感じられる。また,血液浄化療法,腎移植といった20世紀治療医学の双璧をそれぞれ独立して取り入れたのは,腎臓病学とした書名にあっても治療医学の重要性を加味されたものとしてきわめて意義深く感じられる。
本書は,21世紀のわが国の腎臓専門医と,それをめざす先生方の座右の書であると確信するとともに,本書が広く活用されることを祈念してやまない。
腎臓病を専門とする第一線臨床家を対象とした実践書
書評者: 浅野 泰 (自治医大教授・腎臓内科学/日本腎臓学会理事長)
◆明確な目的をもった編集
腎臓病に関する書籍は多数あるが,対象読者を研修医にしているのか,一般実地医家か,それとも腎臓病を専門とする医師にしているのか明確でないものが多い。それぞれの立場からすれば,「帯に短し襷に長し」である。そんな中で,本書は第一線の腎臓病患者を診察している腎臓専門医や,それをめざしている研修医を対象とするという明確な目的をもって編集されたものである。
それだけに,本書の内容も最新の情報や治療指針のみならず一部進行中の研究内容まで披露されており,かつよく整理記載されている。
◆臨床と密着した充実した内容
一方,一般的な書籍とは異なり臨床と密着した内容とする編集方針もあって,腎臓の構造や生理学的な基礎事項を記載する章はなく,研修医には若干もの足りなさを感じるかもしれない。しかし,このことに関しては,他にいくらでも見るべき書籍はあり,本書の目的とした臨床に密着した内容の充実がなされているので,読者も満足してくれるものと思われる。特に小児から成人にまたがる疾患については,それぞれの項で「小児科の視点」を加えたことは他に類を見ない優れた視点となっている。患者側からすれば,乳幼児,小児,成人と連続してかかわってきた同一疾患にかかわらず,そのつど主治医が変更となり,また時には治療方針の変化から不安となるのは当然のことである。小児科医と内科医との間の連携をもっと深めるべきであると日本腎臓学会でも長らく叫ばれてきたが,この点に着目されて計画されたことも,本書の優れたところと言えよう。
なお,執筆者には新進の次世代の腎臓病学を担う若手も目立ち,それはそれで頼もしい限りであるが,細部まで見証すると,使用された図表の出典が明らかとなっていないものがある。往々にして若手の,また日本人の疑りやすい点であるが,まったくのオリジナルの図表でない限り(以前に用いた自著の図表であっても),許諾も含めて出典を明らかにしなければならないことは,ぜひともシニアの先生方から指導していただきたい。
以上を除けば,本書はこれまでにない編集方針と内容で作製されたものであり,腎臓病の専門医,またそれをめざす研修医に良書としてぜひともお勧めしたい書である。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。