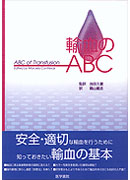輸血のABC
安全な輸血のための知識をコンパクトにまとめた入門書
もっと見る
安全・適切な輸血を行うために知っておくべき事項をコンパクトにまとめた入門書。最近の輸血医療の進展を踏まえた簡明な解説は,初学者はもとより,日常的に輸血を行っている医師,検査技師,看護婦等の知識の整理にも有用。豊富に収載されたカラー写真・図が理解を助ける。輸血業務に携わる医療関係者必読の自己研修用テキスト。
| 原著 | Marcela Contreras |
|---|---|
| 監訳 | 池田 久實 |
| 訳 | 霜山 龍志 |
| 発行 | 2001年08月判型:B5頁:120 |
| ISBN | 978-4-260-24401-5 |
| 定価 | 4,180円 (本体3,800円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 目次
- 書評
目次
開く
第1章 献血者と献血血液の検査
第2章 輸血前検査および血液注文の指針
第3章 赤血球輸血
第4章 血小板と白血球の輸血
第5章 自己血輸血
第6章 新生児溶血性疾患とその予防
第7章 胎児および新生児の輸血
第8章 血漿,血漿分画製剤およびその適応
第9章 ヒトアルブミン液
第10章 大量輸血
第11章 輸血の免疫学的副作用
第12章 輸血の感染性副作用-細菌と寄生虫
第13章 輸血感染-ウイルス
第14章 治療的アフェレシス
第15章 赤血球代替物
第16章 血液成分,血液製剤の供給と需要
第2章 輸血前検査および血液注文の指針
第3章 赤血球輸血
第4章 血小板と白血球の輸血
第5章 自己血輸血
第6章 新生児溶血性疾患とその予防
第7章 胎児および新生児の輸血
第8章 血漿,血漿分画製剤およびその適応
第9章 ヒトアルブミン液
第10章 大量輸血
第11章 輸血の免疫学的副作用
第12章 輸血の感染性副作用-細菌と寄生虫
第13章 輸血感染-ウイルス
第14章 治療的アフェレシス
第15章 赤血球代替物
第16章 血液成分,血液製剤の供給と需要
書評
開く
きわめて実践的かつ実用的な輸血医療の入門書
書評者: 佐川 公矯 (久留米大附属病院教授・臨床検査部)
本書『輸血のABC』は,英国で輸血医療の第一線で活躍している人々によって分担執筆された『ABC of Transfusion, 3rd ed』(edited by Marcela Contreras, BMJ Books, 1998)の邦訳である。タイトルからわかるように,輸血医療の実践を学ぼうとする,英国の医師,看護職,検査技師のために編まれた入門書である。
◆輸血現場の要求に応え具体的にていねいに記述
内容は,きわめて実践的かつ実用的である。理論的な説明は,むしろ意図して省略されていると思われる。「献血」から説き始めて,「輸血前の検査」,「赤血球輸血」,「血小板と白血球輸血」,「新鮮凍結血漿と血漿分画製剤の輸血」,「アルブミン投与」,「自己血輸血」,「新生児溶血性疾患の予防」,「輸血の免疫学的副作用」,「輸血の感染性副作用」,さらには「治療的アフェレシス」などまで,実際の輸血の臨床現場で必要になるであろうこと,また,疑問を抱くであろうことについて,具体的にそしてていねいに記述されている。
カラー写真やカラーの図表が数多く,かつ適切に使われており,読者が理解しやすいように編集されている。また,本文中に適宜,重要事項を箇条書きにまとめたものが赤の囲みで示されており,読者の知識の整理に役立つよう配慮されている。時間の制約のある人は,このまとめだけ通読しても,輸血医療のおおよその流れは,把握できるであろう。
本書は本来,英国の医師,看護職,検査技師を対象として書かれたものなので,当然のことながら英国の輸血医療体制を基盤にして記述されており,英国と日本との差異も散見されるが,訳者は,そのような英国と日本の違いについて訳者注を挿入して注意深く説明を加えているため,違和感はまったく感じられない。
◆さらに深まる日本の輸血医療への理解度
日本における本書の対象読者としては,日本の輸血医療体制について基礎的な知識とある程度の実践経験を持った医師,看護職,検査技師が適当であると思う。そのような医療従事者が本書を読み進めば,英国の輸血医療事情が学べると同時に,英国と日本の違いがほとんどないことも知るであろう。またそのことを通じて,日本の輸血医療への理解度がさらに深まることになると思う。
本書を読むことの楽しみの1つに,はたと膝を打つ記述にしばしば出会えることをつけ加えておきたい。1例をあげると,薬物摂取中の人が献血できない理由として,献血者血液中の薬物が受血者に有害な影響を与える可能性は,実際的というよりむしろ理論的な問題であり,薬物摂取は病気の存在を示すので,病気そのものが献血者を除外するのだと説明しており,言われてみればあたり前のことながら深く感心した次第である。
求められる輸血医療の安全向上に寄与
書評者: 星 順隆 (慈恵医大附属病院・輸血部/造血細胞治療センター/小児科)
交通手段,通信手段の発展により,国際的基準で考えることの重要性が強調されている今日,多くの分野でグローバル・スタンダードが構築されつつある。輸血および血液製剤の供給もその1つであるが,輸血医療は国の事情によって異なる発展をしてきた。わが国では,長年輸血は主治医の裁量権で行なわれてきた。血液製剤によるエイズ感染を契機に全世界的に輸血および血漿分画製剤の見直しがなされ,基準にしたがった医療が重視されている。わが国においても,1989(平成1)年に「輸血療法の適正化に関するガイドライン」が厚生省より提示され,方向性の修正が行なわれた。さらに1999(平成11)年には,「輸血療法の実施に関する指針」と改定されて,輸血医療の基本的ルールとなっている。
◆参考になる英国の輸血ガイドライン
40年以上前から整備されてきた米国の輸血システムを,ただちにわが国に導入することには多少無理がある。米国ほど厳格でなく,さらに狂牛病でもっとも苦しんだ当事国である英国の輸血ガイドラインは,われわれにとって大変参考になる。
本書は,英国の輸血臨床家向けの手引書である。内容は,16章に輸血のすべてを網羅している。献血での血液の収集から,献血血液の安全を保証する検査,輸血を実施する場合の注文の指針,各成分の輸血指針が示されている。続いて,血液成分による副作用とその対策について簡潔に述べられている。さらに治療的アフェレーシス,赤血球代替物など新しい分野の解説が続き,最後は供給と需要について,将来的問題点を示すことで締めくくっている。
◆身近に置いて活用すべき参考書
本書は,教科書でもなければハンドブックでもない。あえて言えば,参考書(アンチョコ)である。これを訳者の霜山先生が,わが国と異なる部分には注釈をつけて理解しやすいように表現している。さらに重点は,「囲み」にきわめて簡潔に記載され,本文を読まなくても重点を確認できるように工夫されている。カラー写真が多用され,説明も明確である。訳者の注釈も適切である。
難を言えば,もう少し字と写真が大きければ見やすいと思われるが,これだけの内容を約120頁に抑えて,価格を下げるためにはやむを得ないのかもしれない。内容・価格からみると大変価値のある参考書である。輸血を実施する臨床医の身近に置いて活用すべき参考書であり,わが国の輸血医療の安全向上に寄与する書物であると確信する。
書評者: 佐川 公矯 (久留米大附属病院教授・臨床検査部)
本書『輸血のABC』は,英国で輸血医療の第一線で活躍している人々によって分担執筆された『ABC of Transfusion, 3rd ed』(edited by Marcela Contreras, BMJ Books, 1998)の邦訳である。タイトルからわかるように,輸血医療の実践を学ぼうとする,英国の医師,看護職,検査技師のために編まれた入門書である。
◆輸血現場の要求に応え具体的にていねいに記述
内容は,きわめて実践的かつ実用的である。理論的な説明は,むしろ意図して省略されていると思われる。「献血」から説き始めて,「輸血前の検査」,「赤血球輸血」,「血小板と白血球輸血」,「新鮮凍結血漿と血漿分画製剤の輸血」,「アルブミン投与」,「自己血輸血」,「新生児溶血性疾患の予防」,「輸血の免疫学的副作用」,「輸血の感染性副作用」,さらには「治療的アフェレシス」などまで,実際の輸血の臨床現場で必要になるであろうこと,また,疑問を抱くであろうことについて,具体的にそしてていねいに記述されている。
カラー写真やカラーの図表が数多く,かつ適切に使われており,読者が理解しやすいように編集されている。また,本文中に適宜,重要事項を箇条書きにまとめたものが赤の囲みで示されており,読者の知識の整理に役立つよう配慮されている。時間の制約のある人は,このまとめだけ通読しても,輸血医療のおおよその流れは,把握できるであろう。
本書は本来,英国の医師,看護職,検査技師を対象として書かれたものなので,当然のことながら英国の輸血医療体制を基盤にして記述されており,英国と日本との差異も散見されるが,訳者は,そのような英国と日本の違いについて訳者注を挿入して注意深く説明を加えているため,違和感はまったく感じられない。
◆さらに深まる日本の輸血医療への理解度
日本における本書の対象読者としては,日本の輸血医療体制について基礎的な知識とある程度の実践経験を持った医師,看護職,検査技師が適当であると思う。そのような医療従事者が本書を読み進めば,英国の輸血医療事情が学べると同時に,英国と日本の違いがほとんどないことも知るであろう。またそのことを通じて,日本の輸血医療への理解度がさらに深まることになると思う。
本書を読むことの楽しみの1つに,はたと膝を打つ記述にしばしば出会えることをつけ加えておきたい。1例をあげると,薬物摂取中の人が献血できない理由として,献血者血液中の薬物が受血者に有害な影響を与える可能性は,実際的というよりむしろ理論的な問題であり,薬物摂取は病気の存在を示すので,病気そのものが献血者を除外するのだと説明しており,言われてみればあたり前のことながら深く感心した次第である。
求められる輸血医療の安全向上に寄与
書評者: 星 順隆 (慈恵医大附属病院・輸血部/造血細胞治療センター/小児科)
交通手段,通信手段の発展により,国際的基準で考えることの重要性が強調されている今日,多くの分野でグローバル・スタンダードが構築されつつある。輸血および血液製剤の供給もその1つであるが,輸血医療は国の事情によって異なる発展をしてきた。わが国では,長年輸血は主治医の裁量権で行なわれてきた。血液製剤によるエイズ感染を契機に全世界的に輸血および血漿分画製剤の見直しがなされ,基準にしたがった医療が重視されている。わが国においても,1989(平成1)年に「輸血療法の適正化に関するガイドライン」が厚生省より提示され,方向性の修正が行なわれた。さらに1999(平成11)年には,「輸血療法の実施に関する指針」と改定されて,輸血医療の基本的ルールとなっている。
◆参考になる英国の輸血ガイドライン
40年以上前から整備されてきた米国の輸血システムを,ただちにわが国に導入することには多少無理がある。米国ほど厳格でなく,さらに狂牛病でもっとも苦しんだ当事国である英国の輸血ガイドラインは,われわれにとって大変参考になる。
本書は,英国の輸血臨床家向けの手引書である。内容は,16章に輸血のすべてを網羅している。献血での血液の収集から,献血血液の安全を保証する検査,輸血を実施する場合の注文の指針,各成分の輸血指針が示されている。続いて,血液成分による副作用とその対策について簡潔に述べられている。さらに治療的アフェレーシス,赤血球代替物など新しい分野の解説が続き,最後は供給と需要について,将来的問題点を示すことで締めくくっている。
◆身近に置いて活用すべき参考書
本書は,教科書でもなければハンドブックでもない。あえて言えば,参考書(アンチョコ)である。これを訳者の霜山先生が,わが国と異なる部分には注釈をつけて理解しやすいように表現している。さらに重点は,「囲み」にきわめて簡潔に記載され,本文を読まなくても重点を確認できるように工夫されている。カラー写真が多用され,説明も明確である。訳者の注釈も適切である。
難を言えば,もう少し字と写真が大きければ見やすいと思われるが,これだけの内容を約120頁に抑えて,価格を下げるためにはやむを得ないのかもしれない。内容・価格からみると大変価値のある参考書である。輸血を実施する臨床医の身近に置いて活用すべき参考書であり,わが国の輸血医療の安全向上に寄与する書物であると確信する。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。