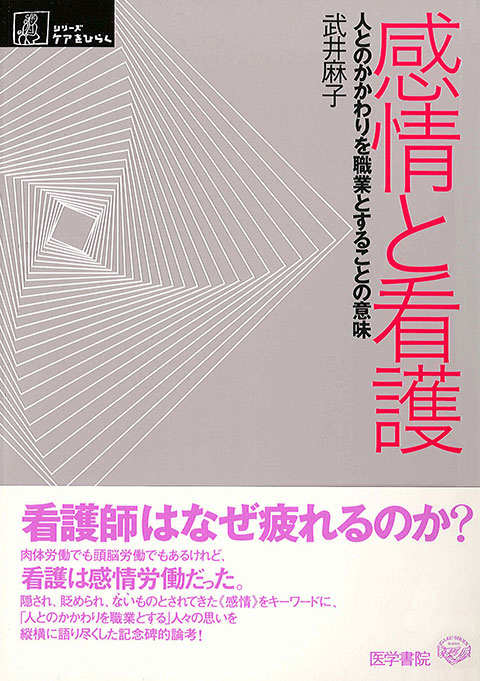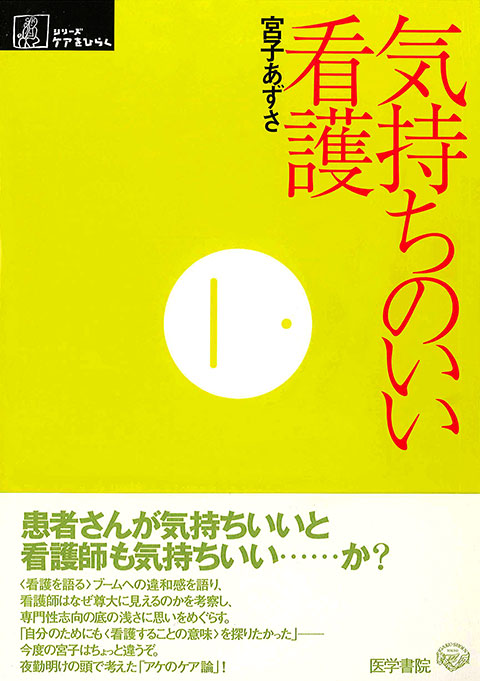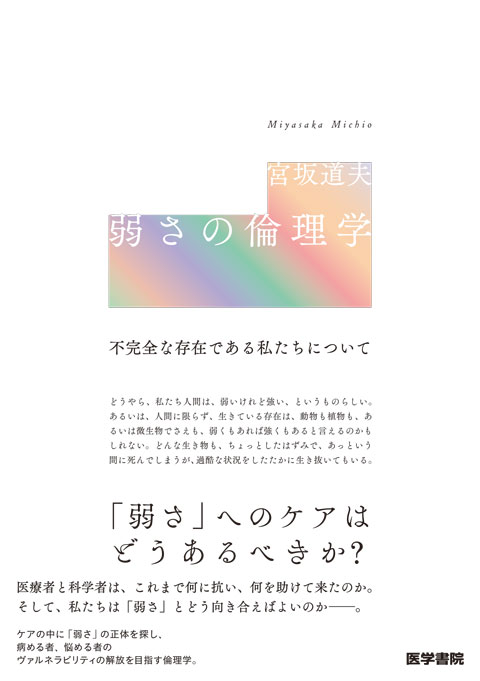感情と看護
人とのかかわりを職業とすることの意味
「科学性」「専門性」「主体性」といったことばだけでは語りきれない地点から<ケア>の世界を探ります。
もっと見る
看護婦はなぜ疲れるのか。「巻き込まれずに共感せよ」「怒ってはいけない!」「うんざりするな!!」――看護は肉体労働でも頭脳労働でもあるが、なにより感情労働だ。どう感じるべきかが強制され、やがて自分の気持ちさえ見えなくなってくる。隠され、貶められ、ないものとされてきた<感情>をキーワードに、「看護とは何か」を縦横に論じた記念碑的論考!
| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |
|---|---|
| 著 | 武井 麻子 |
| 発行 | 2001年03月判型:A5頁:284 |
| ISBN | 978-4-260-33117-3 |
| 定価 | 2,640円 (本体2,400円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- TOPICS
- 目次
- 書評
TOPICS
開く
●『シリーズ ケアをひらく』が第73回毎日出版文化賞(企画部門)受賞!
第73回毎日出版文化賞(主催:毎日新聞社)が2019年11月3日に発表となり、『シリーズ ケアをひらく』が「企画部門」に選出されました。同賞は1947年に創設され、毎年優れた著作物や出版活動を顕彰するもので、「文学・芸術部門」「人文・社会部門」「自然科学部門」「企画部門」の4部門ごとに選出されます。同賞の詳細情報はこちら(毎日新聞社ウェブサイトへ)。
目次
開く
1 看護の仕事
2 感情労働としての看護
3 看護婦のイメージ
4 「共感」という神話
5 身体が語る言葉
6 看護における無意識のコミュニケーション
7 死との出会い
8 傷つく看護婦、傷つける看護婦
9 看護婦という生き方
10 組織のなかの看護婦
終章 看護の行方
書評
開く
「そうかーーー!」と呆然。医師が読むべき看護の本
書評者:長廻 紘(群馬県立がんセンター院長)
書評を見る閉じる
評者は長らく東京の私大病院(A)に,次いで8年前から県立のがんセンター(B)に勤務している者です。いきなり私事,しかも自慢できないことを白状しなければなりません。
まずは回心篇
Aでは,患者は「病気をもって馳せ参じる人」であり,したがって珍しい病気の人が医者にとっては良い患者,そして看護師は,「よく仕えてくださる方」でした。
Bでは,患者さん(患者様という人もいる)は「肉体のみならず精神的にも苦しんでいる人」,看護師は「尊敬すべき同僚」となりました。こんなふうに,時間をかけて見る目が変わってきたような気がします。まるで『罪と罰』の回心篇のような具合です。
そういうところへ,ある偶然から本書『感情と看護』に出会い,目から鱗というか,これまでよくわからなく,もどかしく感じていた諸々のことが大変よく理解できました。
なるほど,看護は感情労働だ
まず文章がよい。そして導入がすばらしい。『女たちは,いま』という本が紹介され,「主婦まで含めてありとあらゆる職業の女性が登場するのに,看護婦は出てこない。なぜか」などといわれると,つい読み進んでみたくなるではありませんか。
そして,内容がよいのは言うまでもありません。筋が通って淀みがありません。専門分野外の本は,文章が読みづらいとまず投げ出してしまうものですが,重い内容なのにすらすらと進むことができます。
最も力を注いだと思われる第2章「感情労働としての看護」では,次のように述べられています。
《患者が体験しているのは生理的現象としての「疾患disease」ではなく,その人の人生のなかで意味づけられた「病いillness」なのです。そこには,さまざまな感情と意味がつきまとっています》そして,《患者とかかわることは,こうしたさまざまな感情にさらされることでもあるのです。……看護が感情労働だと思うのは,こんなときです》
なるほど,看護の仕事はそんな面も含むのか。
しかし現実の看護師は過労で,そんな余裕はなさそうで可愛そうだ。そのうえ,《患者の気持ちをケアするのはもっぱら看護婦の仕事ということになり,医師の思いやりのない言葉や態度に傷ついた患者をなぐさめるという仕事まで看護婦に任されてしまう》(第3章)のですから。
病棟という戦場での救援者
また別の章にはこんな文章もあります。
《このように患者に共感し,援助しようとしている人のなかに生じる独特の心理的疲労を「共感疲労compassion fatigue」といいます》 《告知されない患者とのかかわりでいちばん看護婦が悩むのは,患者に嘘をついているという思いです。誠心誠意ケアをしたいと思っている当の患者を裏切っているというこころの痛みは,患者のもとへの足を重く鈍らせます》
このあたりまでは了解可能の領域ですが,《看護婦は病棟という戦場での救援者です。看護婦に二次的PTSDの症状が出てくるのは,必然といえるでしょう》(第7章「死との出会い」)となると,「そうかーーー!」といって呆然とするしかありません。
内容紹介はこれぐらいにしますが,「看護婦のパーソナリティと共依存」「強迫的世話やきとアダルトチルドレン」「春名ちゃん事件について」「外傷体験と看護という職業選択」「看護婦の規律はなぜ厳しいか」といった項目が目白押しです。どうです? もっと読みたくなりませんか。
燃えつきを防ぐのも医師の務め
看護という仕事は打ち込めば打ち込むほどきついものです。しかし本書を読むと,そこに精神的向上の契機が他の仕事(どんな仕事でも打ち込めば精神的向上はついてくる)以上に散りばめられていることがわかります。しかし,現実はなかなかそれを許さず,中途で転職したり,燃えつきる人が少なくありません。そうならないようにするのは看護部の幹部であるとともに,医者の務めということも肝に銘じました。
評者のキャリアからいって本書を本格的に論ずる資格はありませんし,論ずれば失礼になるような格調高い内容です。下手をすると深みにはまりそうな世界ですが,決していやみはなく率直に共感できる本です。
本書は看護師のための,看護師にエールを送っている本だとは思いますが,医者にも,いや医者にこそ読んでほしいし,また読むべき書と思います。
看護を感情労働としての視点で論求
書評者:李 啓充(ハーバード大学医学部助教授/MGH・内分泌部門)
書評を見る閉じる
感情労働としての看護
「看護は典型的な感情労働である」,と著者は言う。感情労働とは,肉体労働・頭脳労働に対する言葉であるが,サービスの提供者(看護婦)が顧客(患者)とやりとりする感情に商品価値があることを強調する概念であり,(1)顧客との直接の接触が不可欠である,(2)顧客に安心など何らかの感情変化を起こさなければならない,(3)雇用者が労働者の感情活動をある程度支配する,という3つの特質を持つ。感情労働においてやりとりされる感情には,その適切性について基準(感情規則)があり,その基準からはずれる感情の表出は許されない(感情管理)。日常の業務で悲しみや怒りといった強い感情を抱いた場合でも,患者の目の前で泣いたり,怒鳴ったりするような「感情的な」態度を顕にすることは許されない。悲しみや怒りなどの感情の処理(感情作業)は,看護という仕事には不可欠の部分であり,この処理に失敗すると,「自己欺瞞やうつ,バーンアウト,アイデンティティの危機」などに陥る危険があり,これが感情労働のリスクなのだ,という。
著者は,看護を感情労働という視点から捉えることの重要性を強調し,感情労働に伴うリスク(感情を押し殺している間に本当の自分を見失ってしまう,など)をいかに防ぐかを論じている。
評者がこの本を読んで真っ先に思い出したことは,マサチューセッツ・ジェネラル・ホスピタル(MGH)の「ケネス・B・シュワルツ研究所」が行なっている活動であった。
ケネス・B・シュワルツ氏は,『ある癌患者の手記』(拙著『市場原理に揺れるアメリカの医療』医学書院刊に収載)の著者であるが,進行期肺癌の闘病体験から「医療においてもっとも大切なことは,ハイテク器機とか先進治療とかではなく,医療者と患者の人間的触れ合い」であることを強調した。シュワルツ氏は亡くなる数日前に「よりよい患者―医療者関係を構築するための活動をする機関」の設立を思い立ち,未亡人のエレン・コーヘン女史が氏の遺志を継いで,MGH内にシュワルツ研究所を設立した。コーヘン女史は,同研究所の活動を開始した直後に「患者だけでなく,ケアをする側も悩み苦しんでいる」ということに気が付き,ケアをする側の心の負担をどう軽減するかという研究プログラムを同研究所の活動目標の1つとした。「よりよい患者―医療者関係」を追究しようとする患者の側からの努力が,「ケアをする側の感情労働のリスクを軽減する」ことを主要目標の1つとしていたのだということを,評者は,本書を読んで初めて明瞭に理解したのである。
医師・医学教育関係者も一読を
また,著者をはじめ,看護教育に携わる方々が「患者との接し方」に関する教育について多大の努力を傾注していることに比較すると,医学部における「患者接遇学」の教育努力は,「限りなくゼロに近い」と言わなければならない。感情労働としての看護のストレスは,「鈍感」な医師たちによってもたらされる部分が大きいだけでなく,医師もまた感情労働に従事していることに変わりはない。看護に携わる方々は元より,医師・医学教育関係者にも本書を一読されることを強く勧めたい。
看護する心の診断学
書評者:帚木 蓬生(作家,精神科医)
書評を見る閉じる
精神科医になって丸23年である。患者とのつきあいをのぞくと,一番やりとりが多かったのは看護職だったと改めて気づく。
この4半世紀で精神科医療は大きく変わった。おしなべてそれは進歩だったと言える。ところが看護の世界を眺めると,停滞はおろか退化しているのではないかという気がする。
「詰所看護婦」に成り下がった
確かに各地に看護大学が新設され,受持ち看護制になり,看護診断や看護過程などの手順も導入された。しかし看護婦(士)が患者と接する時間は確実に減り,私の勤める病院でも,患者に尻向けて,パソコンを前に指ばかり動かして記録の作成に精を出している姿が目につく。代わりに患者の中で立ち働いているのは,看護助手や介護士,作業療法士,臨床心理士,薬剤師である。仕事の最もおいしいところを他職種に奪われ,看護職はおしなべて詰所看護婦(士)に成り下がってしまった観がある。
この現象が精神科だけかというとそうでもないらしい。糖尿病で総合病院の内科に入院した知人は,初日に受持ち看護婦の自己紹介を受けたきり,1週間後の退院まで看護婦から話しかけられなかったとぼやいた。看護婦不足かと思って詰所をのぞくと,そこにはうじゃうじゃたむろしていたそうである。
私の母校の大学病院でも検温が全廃されて久しい。唯一心療内科だけに残っている。とはいえ1日1回の測定だから,まっすぐな青線が伸びているだけである。体温測定こそまたとない患者との対話の機会であり,体調観察の好機なのに,惜しいことこの上ない。
看護診断の前にやるべきこと
最近の看護職がバイブルのようにあがめている「看護診断」の教科書を見て,仰天した。ハイリスクやペアレンティング,コーピングといった片仮名の氾濫と訳語の生硬さも噴飯ものだが,1つの疾患に診断が12や13もつく煩雑さ,それに対する治療的側面の記述の貧困さは目を覆うばかりである。例えば,抑うつの項の看護目標には,「信頼関係を築く」とか「抑うつの感情を緩和する」など,いとも簡単な言挙げがなされている。しかしこれを実行するには,どれほど深い看護技術の修練が必要か。詰所看護婦(士)では20年30年たっても身につかないことだけは確かである。
看護診断や看護過程を導入するなら,それに見合う分,患者を看護する側の心理の深化も当然要請されなければなるまい。
看護の内と外をあますところなく描写
武井麻子著『感情と看護』は,その空白の部分,未開拓の領域に初めて鍬を入れた待望の書である。そこでは,看護過程で生じるさまざまな心の動きは無論のこと,看護に対する当事者が抱くイメージと世間のそれとの落差,看護職の集団としての構造と軋みなど,看護の内と外があますところなく描出され,解析される。
さらに,看護職やソーシャルワーカー,保母や調理師,大学教官など,人とのかかわりを職業としてこられた著者のさまざまな経験が縦横に織り込まれて,説得力に彩りを添える。
私は本書で,日常何気なく使っているケアが「思いやること」「関心を示すこと」であり,ケアリングが「何かを大事に思うこと」「人が何かにつなぎとめられていること」であると,初めて教えられた。まさしくこれこそ「看護」の本質を衝く言葉である。現在ほとんどの病院が採用し,現場を席巻しているSOAP形式の記録法によって,看護婦(士)の感情が行き場を失っているという指摘も,大いにうなずける。また,看護婦(士)を自縄自縛している「受容」や「共感」の功罪については,さもありなんと思う。
死にゆくもの同士のつながりの場として
確かに看護の場は戦場である。弾丸が頭上を飛び交い,足元は泥でぬかるむ。しかし,いずれ死にゆく身が,同じように死にゆく人々と数瞬の光り輝くつながりを持つ,支え合うかけがいのない場である。そこで働けることこそ生まれ甲斐があるというものである。
この本は,詰所看護婦(士)に自らの土俵に立ち戻っていく勇気を与え,人を援助したいすべての人に,人間として成長していくための知恵と指針を提示してくれる。
開かれたパンドラの箱――看護婦は感情労働者である
書評者:石川 准(静岡県立大教授・社会学)
書評を見る閉じる
看護婦は酷使されている。そのことを,劣悪な労働条件から説明するのではなく,「感情」という「看護のなかでもこれまでもっとも光の当てられてこなかった領域」を切り口に,豊富な事例・引用に基づいて分析を試みる本書は,画期的な取り組みであると同時に,なぜこれまでそのような論考がなかったのかという疑念をも誘発する。
実はそのような看護をめぐる言説空間のありようこそが,何かを物語ってはいないだろうか。そのことを明らかにするには,看護労働と,「感情労働」という感情社会学によって提出された概念との関係を考える必要がある。
感情労働とは何か
感情労働とは,「公的に観察可能な表情と身体的表現を作るために行なう感情の管理という意味」(ホックシールド『管理される心』2000: 7)である。この意味で,看護労働が感情労働であることは自明であるが,本書の触発的なところは,単純に感情労働としての看護労働の分析にとどまるのではなく,むしろ他の感情労働との差異を語るための端緒を開く役割を果たしている点にあると,私は思う。
感情社会学において,特にその嚆矢であるホックシールドが,フライト・アテンダントのような接客業に焦点を当てたのは,ジェンダーと労働という関心からであった。
感情社会学は,女性というジェンダーに感情労働を強いている感情政治のありようを批判し,またそこから導出された表層演技,あるいは深層演技といった概念によって達成される感情の脱自然化は,フライト・アテンダントの実存的苦悩を緩和するものとして機能した。なぜなら感情労働という考え方は,演技によって表示される「偽りの自己」と,それをコントロールする「本当の自己」という切り分けを可能にしたうえで,そのような切り分けは,フライト・アテンダントの感情管理能力,つまりは職能の高さとして誇ってよいのだと述べたからだ。
「感情消去」が看護婦を守る
「玄人はだし」の趣味を持ったり,職場とはまるで別人格の私生活を送ったりというように,そのような切り分けをしている看護婦は多いとも,本書には記述されている。しかし,そうした「割り切り」が看護労働でも有効なのであろうか。
表層演技や深層演技では,「自分は本物の『良い看護婦』ではない,患者に不誠実な『悪い看護婦』」(51頁)という自責の念が生じやすく,そのような気持ちを避けるためには,「演じているという意識そのものをなくしてしまうしかありません」(同頁)と著者は述べる。つまり「割り切り」ではなく,ある種の感情消去こそが看護労働の職能の高さを保証すると同時に,極度の「共感疲労」や自己への幻滅感によってバーンアウトすることからかろうじて看護婦を守っている。
このような事情が,看護をめぐる言説空間で,感情,特にネガティヴな感情について語ることをタブーにしてきたのであり――なぜならそれは感情消去していることを再想起させてしまうからだ――,同様に感情社会学的言説も,フライト・アテンダントを励ますことはできても,看護婦に対してはいっそう複雑で困難な状況をもたらしてしまう。
アンビバレントな要求に引き裂かれる看護婦
看護という労働において職業人としての自己とプライベートな自己を区別するのが著しく困難なのは,それが死や病や痛みという人の根元的な苦悩と至近距離で向き合う仕事だからである。そもそも看護が目的とする「ケア」は,患者との全人格的なかかわりを要求する。他者への自己のかかわり方の深さや浅さは自分が抱いている感情の質や強さによって自覚される。
だがその一方で,看護婦は,特定の患者に感情移入してはならないこと,冷静沈着であることもたたき込まれる。個々の患者の苦悩に同情しすぎたり,罪悪感や無力感を感じたり動揺したりして,医療という戦場から戦線離脱してはならないのだ。
それぞれ十分適切に同調することは困難であると同時に,両立させることはさらに至難の業であるような2つの感情規則は,看護婦を追い詰め,それは時に「共感疲労」や「援助職症候群」といった病理的な状態にまで陥れる。
「負の能力」という希望
そうした背景を考えた時,本書に紹介されている,看護婦たちが自分の感情を語り「本当の自分」を取り戻そうとする取り組みは,貴重である。しかしながら著者も述べるように,「看護婦みずからによる自分たちの本当の姿を受け入れる努力」だけでは問題は解決しない。看護社会学者のジェームズは「ケア=組織+肉体労働+感情労働」(258頁)と定義しているが,当然のことながら,看護労働を必要とする医療という制度や病院という組織のあり方を再構築していく必要があるし,それによって,看護労働における感情政治は緩和されることもあろう。
だがそれでも,われわれの社会が看護を担う人々に,他者への「本当の思いやり」を要請し続ける限り,看護婦の苦悩はなくならないようにも思える。そして,おそらくわれわれの社会,否,われわれは,どれほど看護婦たちの苦悩を聞かされても,この要請を控えることはできないだろう。だからこそ「何かができる能力ではなく,何もできない無力感や空しさに耐える能力」である「負の能力negative capability」こそが,「希望とつながっている」(264頁)と著者は述べるのである。