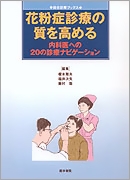花粉症診療の質を高める
内科医への20の診療ナビゲーション
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 目次
- 書評
目次
開く
花粉症(鼻アレルギー)診療ベストプラクティス
Introduction 花粉症(鼻アレルギー)診療にEBM(Evidence-based Medicine)を
診断編
Navigation
1 鼻粘膜を観察しよう
2 花粉症の問診のコツ
3 春先の鼻炎は花粉症とは限らない:鑑別診断のコツ
4 血液検査のみで抗原を同定してはいけない
5 早い,安い,見て納得,皮膚試験を見直そう
6 花粉症だと思っても通年性の抗原を検査する
7 初診の患者には副鼻腔のX線撮影をする
8 くしゃみ,鼻水,鼻づまりだけが花粉症の症状とは限らない
治療編
9 経口薬処方のポイント
10 点鼻薬処方のポイント
11 点眼薬処方のポイント
12 初期療法のポイント
13 妊婦,授乳婦,妊娠が疑われる人の治療法
14 幼児・小児の治療法
15 めがね,マスクの効用
16 イラストで見るダニ・ハウスダスト対策
17 イラストで見る花粉症対策
18 なぜ花粉症(鼻アレルギー)が増加したのか―21世紀の夢の治療に向けて
19 花粉症の遺伝
20 花粉症(鼻アレルギー)とQOL
Appendix 1 花粉症(鼻アレルギー)の問診表
Appendix 2 アレルゲン
Introduction 花粉症(鼻アレルギー)診療にEBM(Evidence-based Medicine)を
診断編
Navigation
1 鼻粘膜を観察しよう
2 花粉症の問診のコツ
3 春先の鼻炎は花粉症とは限らない:鑑別診断のコツ
4 血液検査のみで抗原を同定してはいけない
5 早い,安い,見て納得,皮膚試験を見直そう
6 花粉症だと思っても通年性の抗原を検査する
7 初診の患者には副鼻腔のX線撮影をする
8 くしゃみ,鼻水,鼻づまりだけが花粉症の症状とは限らない
治療編
9 経口薬処方のポイント
10 点鼻薬処方のポイント
11 点眼薬処方のポイント
12 初期療法のポイント
13 妊婦,授乳婦,妊娠が疑われる人の治療法
14 幼児・小児の治療法
15 めがね,マスクの効用
16 イラストで見るダニ・ハウスダスト対策
17 イラストで見る花粉症対策
18 なぜ花粉症(鼻アレルギー)が増加したのか―21世紀の夢の治療に向けて
19 花粉症の遺伝
20 花粉症(鼻アレルギー)とQOL
Appendix 1 花粉症(鼻アレルギー)の問診表
Appendix 2 アレルゲン
書評
開く
プラクティカルな花粉症診療のガイドライン
書評者: 木川 和彦 (熊本大附属病院・総合診療部)
◆求められる非専門外来での患者教育
花粉症患者さんの受診は,近年の患者数の増加に伴い,耳鼻科などの専門外来のみならず,一般内科やいわゆるプライマリ・ケアの外来への受診増や,さらには内科の他の専門外来においても,受診中の患者さんへの初期診療が求められるなど,非専門外来における対応への需要が増してきている。
当然ながら非専門外来においても,きちんとした診断,治療そして適切な患者教育が求められている。また症例によっては主治医として,患者さんへのベストな診療を模索するために,専門医とのディスカッションや的確なコンサルテーションが必要になる。その際,総合診療ブックス・シリーズの1冊でもある本書は,多忙な第一線の臨床医にとって,きわめてプラクティカルで,良質な診療ガイドラインとして有用である。
◆研修医にとっても最適な参考書
本書の特徴は,(1)第一線の医療現場の状況を把握している総合診療医が,非専門外来での診療に対応していくために何が必要かを熟慮した上で,専門医とともに執筆していること,(2)構成上にもさまざまな工夫がされており,大きく20項目に分け,非常に読みやすく,理解しやすいものであること,(3)病歴や身体診察で注意すべき点,診断,治療,さらに患者教育という視点からのアドバイスなど,単なる診断や,治療のための,いわゆるマニュアル本ではなく,筋道を立ててのアプローチの仕方,考え方が示されていること,(4)コンパクトな仕上げにもかかわらず,引用された最新の文献欄もあり,自己学習によりさらに質を高めることができること,(5)使い方が最初に,Map of the book=本書の使い方として示してあるなど,使いやすさへの配慮がなされていることなどである。したがって,日曜や夜間の時間外の外来診療にあたる研修医にとっても最適な参考書であると思う。
余談だが,11のコラムに名づけられたClinical pearlsという表現は,27年前のアメリカでのレジデント時代を,懐かしく思い出させてくれた。
毎日の診療の場で活用してほしい1冊
書評者: 大滝 純司 (北大助教授・総合診療部)
「総合診療ブックス」シリーズは,generalな診療に役立つポイントを,第一線の臨床医がわかりやすく紹介することをめざしているとのことで,今回のテーマは花粉症である。鼻腔の診察,問診,鑑別診断,薬剤(経口・点鼻・点眼)の使い方,妊婦や小児の花粉症への対応,眼鏡やマスクから始まり掃除や寝具にまで至るセルフケアの指導,そして病態に迫る研究のトピックスと,幅広くかつ実用的な内容が具体的な記述でまとめられている。執筆者の多くは耳鼻咽喉科医である。それぞれの執筆者が経験的に行なっている診療内容を紹介しているのではなく,重症度の分類,鼻腔内所見の記載方法,治療法の選択,セルフケアの指導などは「鼻アレルギー診療ガイドライン」に基づいた内容になっている。
◆耳鼻科医以外も鼻粘膜の観察を
特筆すべきは,耳鼻咽喉科以外の医師に,鼻粘膜の観察を強く勧めている点である。私は身体診察が(へたの横好きであるが)大好きで,風邪の患者をはじめ,鼻症状のある患者では必ず鼻鏡(後述)で鼻粘膜の視診を行ない,副鼻腔の触診や透光性の観察なども積極的に行なうように心がけているが,日本の教科書で耳鼻科以外の医者に鼻腔の観察の重要性をこれほど強調している本を読んだことがない。その点で画期的な本だと思う。診察だけでなく,エオジノステインやプリックテストなど,簡易で安価で短時間で結果が出る検査を重視し,患者の負担を減らし医療費を少なくしようという姿勢も随所にうかがえる。
通読してみて,気になった点もいくつかあった。中でも鼻粘膜の観察のところでは,検眼鏡のヘッドを耳・鼻鏡用ヘッドと付け替える方式の,手持ち式の光源つき鼻鏡を用いる方法も,ぜひ紹介していただきたかった。日本の医学教育でようやく普及しはじめた,いわゆる「基本的身体診察」の教育の中では,この種の用具を用いることを勧める場合が多いし,ペンライトや額帯鏡を使うよりも簡便で確実に観察できると思う。さらに,せっかくのカラーページをもっと生かして,正常とアレルギーだけでなく,肥厚性鼻炎やポリープなど,頻度の高い鼻粘膜異常所見をもう少し多く示していただけるとありがたい。
このシリーズは,コンパクトなのに価格が高目だという事と,それにも関わらず,役に立つのでどんどん買ってしまうということで,総合診療の仲間うちでは知られている。耳鼻科医以外のすべての臨床医に(厚さの割に値段がちょっと高いなと思っても),ぜひ一度,手にとって読んでみていただきたい。
花粉症診療に必読のテキスト
書評者: 吉田 修 (日赤和歌山医療センター院長・京大名誉教授)
◆増加著しい「第2の国民病」
近年,花粉症(スギ花粉症)や鼻アレルギー患者の増加は著しく,日本人の17%にみられ,「第2の国民病」とさえ言われている。また先頃開かれた国際シンポジウムにおいても,アレルギー性鼻炎患者の4割に気管支喘息のあることが,世界保健機構と関連研究組織(ARIA)の協同研究で明らかにされ,世界的な注目を集めている。
花粉症の治療には,いろいろな問題がある。患者はどの診療科で治療を受けたらよいのか迷う場合が多く,耳鼻科,内科,時には眼科などを訪れる。また,それぞれの診療科での治療もさまざまである。さらに,Evidenceに基づいた治療が行なわれているかは,はなはだ疑問である。
本書は花粉症に対する診療の質を高めるために,専門家のためではなく,一般医や看護職のための実践書として書かれている。
◆保険診療のもとに医療の質も考慮
また本書は,20の診療ナビゲーションからなるが,まず診断について,鼻粘膜の観察,問診のコツ,鑑別診断,特異的IgE抗体検査,皮膚検査,抗原の検査,副鼻腔のX線検査,鼻症状以外症状などの項目につき詳しく述べられている。特に,鼻粘膜の観察の重要性が強調されているが,内科医も花粉症の検査には鼻鏡を用いるべきであろう。
治療については,経口薬処方,点鼻薬処方,点眼薬処方,初期治療それぞれのポイント,また妊婦,授乳婦,妊娠が疑われる人の治療,乳児・小児の治療,めがね・マスクの効用,ダニ・ハウスダスト対策などについて述べ,さらにトピックスとして増加の原因,遺伝そしてQOLにも言及している。
全体を通じて,新しい電子メディア時代に相応しい,インターネット感覚の構成である。また保険診療のもとにいかに質のよい医療を行なうかを考慮しており,血清中特異的IgE検出の保険点数になどにも及んでいる。一般医にとってこれ以上懇切丁寧な実践書はあるまい。
内容も豊富であり,花粉症診療の必読の書として推薦するにやぶさかではない。
ただ,重複,説明不足,専門的すぎて難解な箇所などもある。次回の改訂時に修正することにより,さらに高い評価を得,また長く読まれる良書となることを信じている。
知りたい花粉症診療のコツがいっぱい!
書評者: 木戸 友幸 (木戸医院)
◆すっと頭に入り,肩の凝らない内容
本書は,一般医の診療のためにと企画された『総合診療ブックス』の第9冊目になるものである。内容は,「内科医への20のナビゲーション」と名づけられた20の章からなっている。これらの章の内訳は診断編8章,治療編9章,トピックス3章である。各章には,まずチェックリストでまとめが示され,その後,すぐ症例が提示される。それに続きイラスト豊富な本文があり,最後に提示された症例の解説と教訓が示されるという,かなり凝った構成になっている。しかし,プライマリ・ケアに従事する医師が患者を診る思考過程に沿って書かれているので,すっと頭に入り,決して肩は凝らない!
◆効果的なマスクの使用まで記載
執筆者はすべて臨床家で,日頃コンサルテーションを受ける立場の先生方である。したがって,プライマリ・ケア医が何を知りたいかを熟知しておられる。おそらく執筆メンバーは,他科の医師から人気の高い先生方なのだろうと察せられる。書かれていることは,日頃われわれプライマリ・ケア医が知りたいことばかりである。また記載が抽象的または一般的な記述ではなく,非常に具体的である。これもわれわれの日常診療に非常に役立つ点である。
例えば,「花粉症にマスクが効果的」と書くだけでなく,「高価なマスクを大切に長く使用するより,安価なものを毎日使い捨てで使用するほうが,衛生面も考えるとお勧めである」と書いてくれている。また,検査法もその信頼度と保険点数の両方の観点から見て,どの方法が好ましいかが記載されている。また,表現,述語も平易なもので統一されているので,医師だけでなく,看護婦,薬剤師,検査技師など同じ職場のコメディカルの人たちにも十分利用してもらえる著書である。
さて,最後にこの『総合診療ブックス』シリーズへの希望であるが,ぜひ精神科関係のものを企画してほしい。最近,薬物療法の進化に伴い,一般医がうつを中心に,精神科疾患の患者を多く診ているが,それに対する信頼のおけるガイドをぜひお願いしたい。
書評者: 木川 和彦 (熊本大附属病院・総合診療部)
◆求められる非専門外来での患者教育
花粉症患者さんの受診は,近年の患者数の増加に伴い,耳鼻科などの専門外来のみならず,一般内科やいわゆるプライマリ・ケアの外来への受診増や,さらには内科の他の専門外来においても,受診中の患者さんへの初期診療が求められるなど,非専門外来における対応への需要が増してきている。
当然ながら非専門外来においても,きちんとした診断,治療そして適切な患者教育が求められている。また症例によっては主治医として,患者さんへのベストな診療を模索するために,専門医とのディスカッションや的確なコンサルテーションが必要になる。その際,総合診療ブックス・シリーズの1冊でもある本書は,多忙な第一線の臨床医にとって,きわめてプラクティカルで,良質な診療ガイドラインとして有用である。
◆研修医にとっても最適な参考書
本書の特徴は,(1)第一線の医療現場の状況を把握している総合診療医が,非専門外来での診療に対応していくために何が必要かを熟慮した上で,専門医とともに執筆していること,(2)構成上にもさまざまな工夫がされており,大きく20項目に分け,非常に読みやすく,理解しやすいものであること,(3)病歴や身体診察で注意すべき点,診断,治療,さらに患者教育という視点からのアドバイスなど,単なる診断や,治療のための,いわゆるマニュアル本ではなく,筋道を立ててのアプローチの仕方,考え方が示されていること,(4)コンパクトな仕上げにもかかわらず,引用された最新の文献欄もあり,自己学習によりさらに質を高めることができること,(5)使い方が最初に,Map of the book=本書の使い方として示してあるなど,使いやすさへの配慮がなされていることなどである。したがって,日曜や夜間の時間外の外来診療にあたる研修医にとっても最適な参考書であると思う。
余談だが,11のコラムに名づけられたClinical pearlsという表現は,27年前のアメリカでのレジデント時代を,懐かしく思い出させてくれた。
毎日の診療の場で活用してほしい1冊
書評者: 大滝 純司 (北大助教授・総合診療部)
「総合診療ブックス」シリーズは,generalな診療に役立つポイントを,第一線の臨床医がわかりやすく紹介することをめざしているとのことで,今回のテーマは花粉症である。鼻腔の診察,問診,鑑別診断,薬剤(経口・点鼻・点眼)の使い方,妊婦や小児の花粉症への対応,眼鏡やマスクから始まり掃除や寝具にまで至るセルフケアの指導,そして病態に迫る研究のトピックスと,幅広くかつ実用的な内容が具体的な記述でまとめられている。執筆者の多くは耳鼻咽喉科医である。それぞれの執筆者が経験的に行なっている診療内容を紹介しているのではなく,重症度の分類,鼻腔内所見の記載方法,治療法の選択,セルフケアの指導などは「鼻アレルギー診療ガイドライン」に基づいた内容になっている。
◆耳鼻科医以外も鼻粘膜の観察を
特筆すべきは,耳鼻咽喉科以外の医師に,鼻粘膜の観察を強く勧めている点である。私は身体診察が(へたの横好きであるが)大好きで,風邪の患者をはじめ,鼻症状のある患者では必ず鼻鏡(後述)で鼻粘膜の視診を行ない,副鼻腔の触診や透光性の観察なども積極的に行なうように心がけているが,日本の教科書で耳鼻科以外の医者に鼻腔の観察の重要性をこれほど強調している本を読んだことがない。その点で画期的な本だと思う。診察だけでなく,エオジノステインやプリックテストなど,簡易で安価で短時間で結果が出る検査を重視し,患者の負担を減らし医療費を少なくしようという姿勢も随所にうかがえる。
通読してみて,気になった点もいくつかあった。中でも鼻粘膜の観察のところでは,検眼鏡のヘッドを耳・鼻鏡用ヘッドと付け替える方式の,手持ち式の光源つき鼻鏡を用いる方法も,ぜひ紹介していただきたかった。日本の医学教育でようやく普及しはじめた,いわゆる「基本的身体診察」の教育の中では,この種の用具を用いることを勧める場合が多いし,ペンライトや額帯鏡を使うよりも簡便で確実に観察できると思う。さらに,せっかくのカラーページをもっと生かして,正常とアレルギーだけでなく,肥厚性鼻炎やポリープなど,頻度の高い鼻粘膜異常所見をもう少し多く示していただけるとありがたい。
このシリーズは,コンパクトなのに価格が高目だという事と,それにも関わらず,役に立つのでどんどん買ってしまうということで,総合診療の仲間うちでは知られている。耳鼻科医以外のすべての臨床医に(厚さの割に値段がちょっと高いなと思っても),ぜひ一度,手にとって読んでみていただきたい。
花粉症診療に必読のテキスト
書評者: 吉田 修 (日赤和歌山医療センター院長・京大名誉教授)
◆増加著しい「第2の国民病」
近年,花粉症(スギ花粉症)や鼻アレルギー患者の増加は著しく,日本人の17%にみられ,「第2の国民病」とさえ言われている。また先頃開かれた国際シンポジウムにおいても,アレルギー性鼻炎患者の4割に気管支喘息のあることが,世界保健機構と関連研究組織(ARIA)の協同研究で明らかにされ,世界的な注目を集めている。
花粉症の治療には,いろいろな問題がある。患者はどの診療科で治療を受けたらよいのか迷う場合が多く,耳鼻科,内科,時には眼科などを訪れる。また,それぞれの診療科での治療もさまざまである。さらに,Evidenceに基づいた治療が行なわれているかは,はなはだ疑問である。
本書は花粉症に対する診療の質を高めるために,専門家のためではなく,一般医や看護職のための実践書として書かれている。
◆保険診療のもとに医療の質も考慮
また本書は,20の診療ナビゲーションからなるが,まず診断について,鼻粘膜の観察,問診のコツ,鑑別診断,特異的IgE抗体検査,皮膚検査,抗原の検査,副鼻腔のX線検査,鼻症状以外症状などの項目につき詳しく述べられている。特に,鼻粘膜の観察の重要性が強調されているが,内科医も花粉症の検査には鼻鏡を用いるべきであろう。
治療については,経口薬処方,点鼻薬処方,点眼薬処方,初期治療それぞれのポイント,また妊婦,授乳婦,妊娠が疑われる人の治療,乳児・小児の治療,めがね・マスクの効用,ダニ・ハウスダスト対策などについて述べ,さらにトピックスとして増加の原因,遺伝そしてQOLにも言及している。
全体を通じて,新しい電子メディア時代に相応しい,インターネット感覚の構成である。また保険診療のもとにいかに質のよい医療を行なうかを考慮しており,血清中特異的IgE検出の保険点数になどにも及んでいる。一般医にとってこれ以上懇切丁寧な実践書はあるまい。
内容も豊富であり,花粉症診療の必読の書として推薦するにやぶさかではない。
ただ,重複,説明不足,専門的すぎて難解な箇所などもある。次回の改訂時に修正することにより,さらに高い評価を得,また長く読まれる良書となることを信じている。
知りたい花粉症診療のコツがいっぱい!
書評者: 木戸 友幸 (木戸医院)
◆すっと頭に入り,肩の凝らない内容
本書は,一般医の診療のためにと企画された『総合診療ブックス』の第9冊目になるものである。内容は,「内科医への20のナビゲーション」と名づけられた20の章からなっている。これらの章の内訳は診断編8章,治療編9章,トピックス3章である。各章には,まずチェックリストでまとめが示され,その後,すぐ症例が提示される。それに続きイラスト豊富な本文があり,最後に提示された症例の解説と教訓が示されるという,かなり凝った構成になっている。しかし,プライマリ・ケアに従事する医師が患者を診る思考過程に沿って書かれているので,すっと頭に入り,決して肩は凝らない!
◆効果的なマスクの使用まで記載
執筆者はすべて臨床家で,日頃コンサルテーションを受ける立場の先生方である。したがって,プライマリ・ケア医が何を知りたいかを熟知しておられる。おそらく執筆メンバーは,他科の医師から人気の高い先生方なのだろうと察せられる。書かれていることは,日頃われわれプライマリ・ケア医が知りたいことばかりである。また記載が抽象的または一般的な記述ではなく,非常に具体的である。これもわれわれの日常診療に非常に役立つ点である。
例えば,「花粉症にマスクが効果的」と書くだけでなく,「高価なマスクを大切に長く使用するより,安価なものを毎日使い捨てで使用するほうが,衛生面も考えるとお勧めである」と書いてくれている。また,検査法もその信頼度と保険点数の両方の観点から見て,どの方法が好ましいかが記載されている。また,表現,述語も平易なもので統一されているので,医師だけでなく,看護婦,薬剤師,検査技師など同じ職場のコメディカルの人たちにも十分利用してもらえる著書である。
さて,最後にこの『総合診療ブックス』シリーズへの希望であるが,ぜひ精神科関係のものを企画してほしい。最近,薬物療法の進化に伴い,一般医がうつを中心に,精神科疾患の患者を多く診ているが,それに対する信頼のおけるガイドをぜひお願いしたい。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。