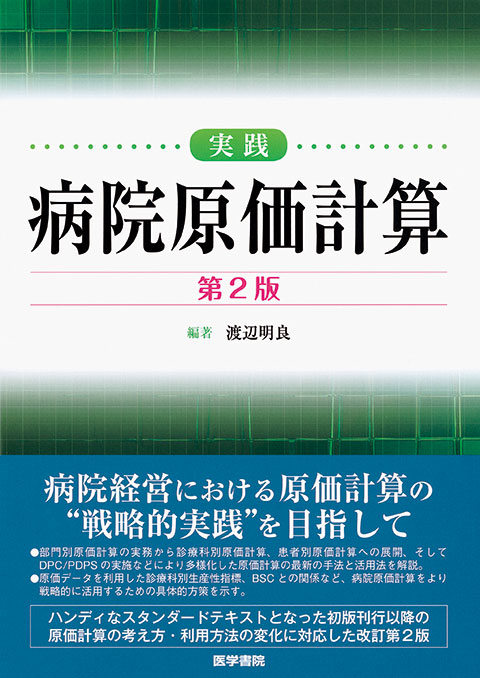実践 病院原価計算
従来の財務分析に加え,新機軸に立った原価計算方法論を開陳した病院経営者の必携書
もっと見る
病院経営者にとって、いまや具体的な増収策やコスト削減が不可欠な時代となってきた。そのためには従来の財務分析にとどまらない、部門別・科別・行為別・疾病別の原価計算が要求される。本書は、その方法論を豊富な図表とともに、DRG/PPSやクリティカルパスの導入まで視野に入れて解説した。これからの病院経営に必須の1冊。
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 書評
書評
開く
病院の経営意思決定に悩む病院関係者にお勧めの一品
書評者: 武藤 正樹 (国立長野病院副院長)
◆原価計算は病院の重要な計器(インディケーター)
本書にもあるように,平成2年(1990年)には1万を超えていた病院数が今や,9300あまり,9000を割り込むのも時間の問題だろう。いよいよ病院の本格的な淘汰と選別の時代が始まろうとしている。また,この4月の診療報酬の改訂や第4次医療法改正など,医療をとりまく環境が激変している。この変革の時期に意思決定を迫られる病院の病院長は,乱気流の中,視界ゼロの雲の中を飛ぶジャンボジェットの機長のようなものだ。一歩,判断を誤ればジャンボジェットは墜落しかねない。こうした視界ゼロのコックピットで唯一頼りになるのは種々の計器(インディケーター)だ。本書で扱っている,原価計算もこうした病院のコックピットでの重要な計器の1つといえる。
原価とは,医療サービスを提供するにあたって,消費されたあるいはこれから消費する予定の資源(人,モノ)を金銭に換算して得られる指標である。また,原価計算から導かれる損益分岐点は,コックピットに鳴り響くアラーム音とも言える。このように原価を計算することで,見えてくることがたくさんある。
実際に本書では,原価計算の方法とそれによる経営意思決定の過程を,著者らが勤務する聖路加国際病院の実例をあげながら,わかりやすく解説している。いくつかの事例の中で,同病院の栄養科の原価計算が読む者をひきつける。栄養科を部門別原価計算したところ,単月で2000万の赤字であることがわかり,コスト構造の見直しの結果,最終的には栄養科をアウトソーシングするに至った意思決定の過程が生々しく描かれている。
◆クリティカルパスによる原価計算
また,本書ではクリティカルパスによる原価計算についても言及している。白内障のクリティカルパスを例にとりながら,クリティカルパス上で基本タスクを同定してタスクごとの標準原価計算を行なう方法を提案している。ちなみに,白内障のクリティカルパスで同定された基本タスクは「アナムネとり」や,「点眼薬の投与」など,全部で21あったと言う。こうしたタスクごとの標準原価がわかれば,あとはタスクの組み合わせで別のクリティカルパスの原価計算を行なえることになる。
さて,病院ほど複雑なマネジメント組織は地球上にないと言われる。提供するサービス商品数は国際疾病分類で1万種以上,参加する専門職種数は20以上,部門の数は診療科数で30以上,しかも多品種少量生産のサービスラインがジャングルのように絡み合ってできているのが病院だ。こうした複雑な組織こそ,その絡み合ったサービス生産ラインを切り分けしてコスト構造を分析する,原価計算の手法が必要と言える。本書はそうした複雑な病院の原価計算をわかりやすく,また演習問題も交えながら解説している。病院の経営意思決定に悩むすべての病院関係者にお勧めの一品と言える。
原価計算から得たデータを経営改善に結びつける
書評者: 竹田 秀 (竹田綜合病院理事長)
◆名マネージャーと気鋭のシェフによる一品
著者の中村彰吾氏は,聖路加国際病院の名事務長として病院経営に腕をふるっておられることはご承知のとおりである。また,長年にわたって病院の部門別原価計算を実践され,この分野の第一人者であることも改めてご紹介するまでもない。
共著者の渡辺明良氏は,企画室チーフとして聖路加国際病院の経営戦略を担当されている若手であるが,経営管理に関する卓越した知識とセンスの持ち主でまさに俊英である。名マネージャーと気鋭のシェフにも例えられるこのお二人の師弟コンビが,聖路加国際病院の伝統である原価計算をどのように調理して読者に提供するか期待をもって頁を開いたが,期待にたがわない一品に仕上がったと言える。
第1章は「病院経営環境の変化と原価計算」と題されているが,財務分析による費用の比率の見方と財務会計と管理会計の役割の違いが述べられている。第2章は原価の概念や損益分岐点の説明がなされている。ここまでは前菜にあたるが要領よく説明されており,原価計算に直接たずさわらない部門でも,管理職であれば理解しておくべき内容である。
第3章の「原価計算の実務」は主菜の一皿であり,約3分の1の60頁を占める。ここは聖路加国際病院における長年の経験とノウハウが凝縮されていて,原価計算の担当者にとっては大変に貴重であり参考になるであろう。第4章は,第3章の部門別原価計算をいかに病院経営管理へ活用するかが述べられている。各科や各病棟の責任者が理解しておくべき内容である。
第5章から第7章は応用編で,科別や疾病別の原価計算に触れている。
第8章は原価計算の今後の展望としてABC(activity based costing)に触れられている。第9章は聖路加国際病院における経営戦略の具体的な事例がとりあげられていて,美味しいデザートである。
◆病院経営管理の参考書としても有用
本書は全体としてコンパクトな中に,要点が盛り込まれており,原価計算のみならず病院経営管理の参考書としても有用である。
原価計算の実務もさることながら,そのデータをいかに経営改善に結びつけるかという視点から記述されている点は,大きく評価したい。原価計算はそれ自体が目的ではなく,経営改善の手段だからである。
各節にチェックポイントやキーワードがつけられているのも親切で丁寧である。また少しであるが演習問題があるので,学生や若い読者はおっくうがらずに手を動かして解くことで理解を深めてほしい。
このコンビによる次書を期待したい。
書評者: 武藤 正樹 (国立長野病院副院長)
◆原価計算は病院の重要な計器(インディケーター)
本書にもあるように,平成2年(1990年)には1万を超えていた病院数が今や,9300あまり,9000を割り込むのも時間の問題だろう。いよいよ病院の本格的な淘汰と選別の時代が始まろうとしている。また,この4月の診療報酬の改訂や第4次医療法改正など,医療をとりまく環境が激変している。この変革の時期に意思決定を迫られる病院の病院長は,乱気流の中,視界ゼロの雲の中を飛ぶジャンボジェットの機長のようなものだ。一歩,判断を誤ればジャンボジェットは墜落しかねない。こうした視界ゼロのコックピットで唯一頼りになるのは種々の計器(インディケーター)だ。本書で扱っている,原価計算もこうした病院のコックピットでの重要な計器の1つといえる。
原価とは,医療サービスを提供するにあたって,消費されたあるいはこれから消費する予定の資源(人,モノ)を金銭に換算して得られる指標である。また,原価計算から導かれる損益分岐点は,コックピットに鳴り響くアラーム音とも言える。このように原価を計算することで,見えてくることがたくさんある。
実際に本書では,原価計算の方法とそれによる経営意思決定の過程を,著者らが勤務する聖路加国際病院の実例をあげながら,わかりやすく解説している。いくつかの事例の中で,同病院の栄養科の原価計算が読む者をひきつける。栄養科を部門別原価計算したところ,単月で2000万の赤字であることがわかり,コスト構造の見直しの結果,最終的には栄養科をアウトソーシングするに至った意思決定の過程が生々しく描かれている。
◆クリティカルパスによる原価計算
また,本書ではクリティカルパスによる原価計算についても言及している。白内障のクリティカルパスを例にとりながら,クリティカルパス上で基本タスクを同定してタスクごとの標準原価計算を行なう方法を提案している。ちなみに,白内障のクリティカルパスで同定された基本タスクは「アナムネとり」や,「点眼薬の投与」など,全部で21あったと言う。こうしたタスクごとの標準原価がわかれば,あとはタスクの組み合わせで別のクリティカルパスの原価計算を行なえることになる。
さて,病院ほど複雑なマネジメント組織は地球上にないと言われる。提供するサービス商品数は国際疾病分類で1万種以上,参加する専門職種数は20以上,部門の数は診療科数で30以上,しかも多品種少量生産のサービスラインがジャングルのように絡み合ってできているのが病院だ。こうした複雑な組織こそ,その絡み合ったサービス生産ラインを切り分けしてコスト構造を分析する,原価計算の手法が必要と言える。本書はそうした複雑な病院の原価計算をわかりやすく,また演習問題も交えながら解説している。病院の経営意思決定に悩むすべての病院関係者にお勧めの一品と言える。
原価計算から得たデータを経営改善に結びつける
書評者: 竹田 秀 (竹田綜合病院理事長)
◆名マネージャーと気鋭のシェフによる一品
著者の中村彰吾氏は,聖路加国際病院の名事務長として病院経営に腕をふるっておられることはご承知のとおりである。また,長年にわたって病院の部門別原価計算を実践され,この分野の第一人者であることも改めてご紹介するまでもない。
共著者の渡辺明良氏は,企画室チーフとして聖路加国際病院の経営戦略を担当されている若手であるが,経営管理に関する卓越した知識とセンスの持ち主でまさに俊英である。名マネージャーと気鋭のシェフにも例えられるこのお二人の師弟コンビが,聖路加国際病院の伝統である原価計算をどのように調理して読者に提供するか期待をもって頁を開いたが,期待にたがわない一品に仕上がったと言える。
第1章は「病院経営環境の変化と原価計算」と題されているが,財務分析による費用の比率の見方と財務会計と管理会計の役割の違いが述べられている。第2章は原価の概念や損益分岐点の説明がなされている。ここまでは前菜にあたるが要領よく説明されており,原価計算に直接たずさわらない部門でも,管理職であれば理解しておくべき内容である。
第3章の「原価計算の実務」は主菜の一皿であり,約3分の1の60頁を占める。ここは聖路加国際病院における長年の経験とノウハウが凝縮されていて,原価計算の担当者にとっては大変に貴重であり参考になるであろう。第4章は,第3章の部門別原価計算をいかに病院経営管理へ活用するかが述べられている。各科や各病棟の責任者が理解しておくべき内容である。
第5章から第7章は応用編で,科別や疾病別の原価計算に触れている。
第8章は原価計算の今後の展望としてABC(activity based costing)に触れられている。第9章は聖路加国際病院における経営戦略の具体的な事例がとりあげられていて,美味しいデザートである。
◆病院経営管理の参考書としても有用
本書は全体としてコンパクトな中に,要点が盛り込まれており,原価計算のみならず病院経営管理の参考書としても有用である。
原価計算の実務もさることながら,そのデータをいかに経営改善に結びつけるかという視点から記述されている点は,大きく評価したい。原価計算はそれ自体が目的ではなく,経営改善の手段だからである。
各節にチェックポイントやキーワードがつけられているのも親切で丁寧である。また少しであるが演習問題があるので,学生や若い読者はおっくうがらずに手を動かして解くことで理解を深めてほしい。
このコンビによる次書を期待したい。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。