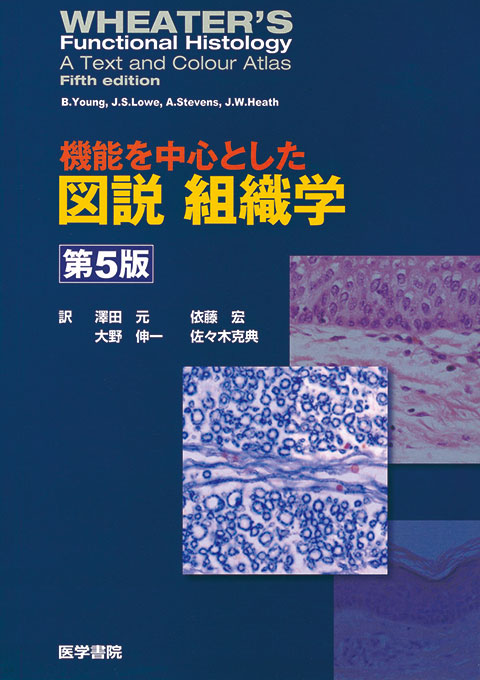機能を中心とした図説組織学 第4版
豊富なカラー図版で贈る実習用組織学アトラス
もっと見る
ヒト組織材料のきれいな光学顕微鏡写真がそろっていることで定評のある“Wheaterの組織学”日本語訳の第4版。今回からA4判に判型を拡大し,線画もすべてカラー図版となり,より見やすく分かりやすい図譜となった。医学部,歯学部,獣医学部の学生の実習用のアトラスに最適。図版の説明も新しい知識を加え,より一層充実。
| 原著 | Barbara Young / John W. Heath |
|---|---|
| 監訳 | 山田 英智 |
| 訳 | 石川 春律 / 廣澤 一成 / 澤田 元 |
| 発行 | 2001年07月判型:A4頁:448 |
| ISBN | 978-4-260-10072-4 |
| 定価 | 10,450円 (本体9,500円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 目次
- 書評
目次
開く
第I部 細胞
1. 細胞の構造と機能
2. 細胞周期と細胞複製
第II部 基本となる組織
3. 血液
4. 結合(支持)組織
5. 上皮組織
6. 筋
7. 神経組織
第III部 器官系
8. 循環器系
9. 皮膚
10. 骨格系組織
11. 免疫系
12. 呼吸器系
13. 口腔内組織
14. 消化管
15. 肝臓と膵臓
16. 泌尿器系
17. 内分泌腺
18. 男性生殖器系
19. 女性生殖器系
20. 中枢神経系
21. 感覚器
染色法ノート
1. 細胞の構造と機能
2. 細胞周期と細胞複製
第II部 基本となる組織
3. 血液
4. 結合(支持)組織
5. 上皮組織
6. 筋
7. 神経組織
第III部 器官系
8. 循環器系
9. 皮膚
10. 骨格系組織
11. 免疫系
12. 呼吸器系
13. 口腔内組織
14. 消化管
15. 肝臓と膵臓
16. 泌尿器系
17. 内分泌腺
18. 男性生殖器系
19. 女性生殖器系
20. 中枢神経系
21. 感覚器
染色法ノート
書評
開く
「洛陽ノ紙価ヲ高メ」てきた組織学の名著
書評者: 猪口 哲夫 (久留米大教授・解剖学)
本書は,英国のノッティンガム大学のWheaterが著した『Functional Histology A Text and Colour Atlas』(初版は1979年)の第4版(2000年刊)の翻訳で,1979年に第1版が出版されて以来,「洛陽ノ紙価ヲ高メ」てきた名著である。その第1版の日本語訳(1981年刊,医学書院)が,東京大学医学部解剖学教室の山田英智教授(当時,現同大名誉教授)監修の下に当時同大解剖学教育関係の方々の分担により訳出され,その後,原著が改版されるたびに同一の担当者(今回から澤田教授が参加)による速やかな和訳の作業が,責任ある態度をもって行なわれてきたものである。
◆はかられた執筆者の世代交代
今回の原著は,その第1,2版の中心的著者であったノッティンガム大学のPaul R. Wheaterの死去(1989年)後,第3版の執筆者の1人Barbara Young(オーストラリア・シドニー大学)が,John W. Heath(同・ニューカッスル大学)とともに改訂作業を行なっている。原著の執筆者が,一人ずつ入れ替わって版を重ねるうち,内容,図版・写真の更新が図られつつ,主体が英国のノッティンガム,ケンブリッジからオーストラリアの次世代の担い手たちへ引き継がれている様子がうかがわれる。
さて,この第4版では,(1)A4判に大型化した,(2)第3版の内容に加えて,その後の分子・細胞生物学分野での新しい知見を取り入れた,(3)図を増やし,かつカラー化した,(4)第1部冒頭に「顕微鏡法の手引き」が入れられた,などの変更がみられる。
◆きわめてオーソドックスな組織学教科書
本書を類書と見比べてみると解ることは,きわめてオーソドックスな組織学教科書のスタイルを一貫していることである。内容は,細部にわたり過ぎず,重点が明示され,章の配列はやや伝統的とも見える構成ながら,新しい知見を教育的観点より適宜取り入れている。また,記載内容の深さ,光顕写真・電顕写真の位置づけと取り扱い方はバランスがとれ,厳密に選択されたそれらの写真・図版は美しく,医学教育を受ける学生にとって妥当なものとなっている。
本書の持つ特色をさらにあげると,人体から得られた材料が努めて使われている点がある。これは,医学教育のテキストとしてきわめて望ましいことである。もう1つは,用語と訳注に関する訳者らの配慮が行き届いていることも指摘されねばならない。すなわち,本書の用語(和訳)は,日本解剖学会の「解剖学用語」,「組織学用語」,「発生学用語」に準拠しているほか,日常頻用されている,いわゆる「日本式カタカナ語」表記が採用されている。さらに,訳注が適宜につけられていて,用語の人名や原著自身の持つ記載内容の誤記にまで率直に触れているなど,日本語版読者のために十分に意を尽くしたものとされていることは,誠にありがたいと思う。訳文は平易な日本語文になっており,読みやすい。教育的によく配慮された,優れた組織学書として,広く推薦したい。
学習者本位に企画された組織学の図譜兼教科書
書評者: 依藤 宏 (防衛医大教授・解剖学)
◆判型が大型化し,学習者の理解を助ける手だてがいっぱい
B. Young,J. W. Heath著,山田英智監訳による『機能を中心とした図説組織学』の改訂第4版が出た。この本は図説とあり,原著にもText and Colour Atlasとあるように単なる図譜ではなく,光学顕微鏡写真,電子顕微鏡写真および理解を助ける模式図にはそれぞれ要を得た適切な長さの説明がついている。また各章の始めには,その章の内容の理解に必要な事項の説明があり,細部にとらわれて全体を見失わないための配慮もなされている。そしてさらには「機能を中心とする」とあるように各部位の解説も形態のみの説明だけではなく,機能から構造を理解させようという試みが随所に盛られている。この本が今回改訂になって大きく変わった点は,まず,判型がB5からA4判へと大きくなったことである。これにより頁にゆとりができ,見出しも網掛けや線で囲むなどの工夫がなされ,大変見やすくなっている。加えて,説明文中のキーワードが太字に変わり,ある術語を索引から検索する場合にも短時間で探し当てることが可能となった。さらには模式図がカラー化されて一段と理解しやすくなり,また組織切片だけではわかりづらいところには,新たに概念図を挿入したり,まとめの表を追加するなど,いろいろの学習者の理解を助ける手だてが加わっている。
◆「組織学を機能とからめて楽しく理解」をモットーに
第1部「細胞」の章では,総合的理解のため,以前章末にあった光学顕微鏡写真を電子顕微鏡写真と組み合わせて配慮しているほか,アポトーシスの機構など新たな分野の解説も取り入れている。このような学問の進歩も進んで取り入れる姿勢は,この種の本としては頻繁な改訂(原著で6-8年ごと)に現れている。もともとこの本は,組織学を機能とからめて楽しく理解できるようにとの意図の元に書かれた本であるが,今回の改訂で学習者にとりさらに使いやすい本となっている。
ところで,医学教育は現在大きな転換点を迎えている。解剖学は従来のカリキュラムから大幅に時間数が削減される大学が多く,組織学も要点を要領よく短時間で身につけさせる必要がでてきているほか,器官別に病理学,臨床の科目と組み合わせた統合型のカリキュラムとなるところも多い。このような解剖学教育の現状からこの本を見てみると,本書は機能面を重視しながら構造を理解しようとしているので,統合型の学習にも向いており,さらには索引がこの種の本としては他に比肩するものがないほど充実している――項目数は和文,英文ともにそれぞれ2000以上――ので,学習の途中で疑問のでた項目を探したいという,例えばチュートリアルシステムのようなタイプの学習においても大いに役立つことを意味している。この本は,著者が学習者の理解を第1にして書き著し改訂した優れた組織学の図譜兼教科書であり,内耳などの特殊な部分を除いて光学顕微鏡写真は,すべてヒトを材料としていることから,学生のみならず組織学を再度見直そうという人には,ぜひ1度手に取っていただきたい本である。
書評者: 猪口 哲夫 (久留米大教授・解剖学)
本書は,英国のノッティンガム大学のWheaterが著した『Functional Histology A Text and Colour Atlas』(初版は1979年)の第4版(2000年刊)の翻訳で,1979年に第1版が出版されて以来,「洛陽ノ紙価ヲ高メ」てきた名著である。その第1版の日本語訳(1981年刊,医学書院)が,東京大学医学部解剖学教室の山田英智教授(当時,現同大名誉教授)監修の下に当時同大解剖学教育関係の方々の分担により訳出され,その後,原著が改版されるたびに同一の担当者(今回から澤田教授が参加)による速やかな和訳の作業が,責任ある態度をもって行なわれてきたものである。
◆はかられた執筆者の世代交代
今回の原著は,その第1,2版の中心的著者であったノッティンガム大学のPaul R. Wheaterの死去(1989年)後,第3版の執筆者の1人Barbara Young(オーストラリア・シドニー大学)が,John W. Heath(同・ニューカッスル大学)とともに改訂作業を行なっている。原著の執筆者が,一人ずつ入れ替わって版を重ねるうち,内容,図版・写真の更新が図られつつ,主体が英国のノッティンガム,ケンブリッジからオーストラリアの次世代の担い手たちへ引き継がれている様子がうかがわれる。
さて,この第4版では,(1)A4判に大型化した,(2)第3版の内容に加えて,その後の分子・細胞生物学分野での新しい知見を取り入れた,(3)図を増やし,かつカラー化した,(4)第1部冒頭に「顕微鏡法の手引き」が入れられた,などの変更がみられる。
◆きわめてオーソドックスな組織学教科書
本書を類書と見比べてみると解ることは,きわめてオーソドックスな組織学教科書のスタイルを一貫していることである。内容は,細部にわたり過ぎず,重点が明示され,章の配列はやや伝統的とも見える構成ながら,新しい知見を教育的観点より適宜取り入れている。また,記載内容の深さ,光顕写真・電顕写真の位置づけと取り扱い方はバランスがとれ,厳密に選択されたそれらの写真・図版は美しく,医学教育を受ける学生にとって妥当なものとなっている。
本書の持つ特色をさらにあげると,人体から得られた材料が努めて使われている点がある。これは,医学教育のテキストとしてきわめて望ましいことである。もう1つは,用語と訳注に関する訳者らの配慮が行き届いていることも指摘されねばならない。すなわち,本書の用語(和訳)は,日本解剖学会の「解剖学用語」,「組織学用語」,「発生学用語」に準拠しているほか,日常頻用されている,いわゆる「日本式カタカナ語」表記が採用されている。さらに,訳注が適宜につけられていて,用語の人名や原著自身の持つ記載内容の誤記にまで率直に触れているなど,日本語版読者のために十分に意を尽くしたものとされていることは,誠にありがたいと思う。訳文は平易な日本語文になっており,読みやすい。教育的によく配慮された,優れた組織学書として,広く推薦したい。
学習者本位に企画された組織学の図譜兼教科書
書評者: 依藤 宏 (防衛医大教授・解剖学)
◆判型が大型化し,学習者の理解を助ける手だてがいっぱい
B. Young,J. W. Heath著,山田英智監訳による『機能を中心とした図説組織学』の改訂第4版が出た。この本は図説とあり,原著にもText and Colour Atlasとあるように単なる図譜ではなく,光学顕微鏡写真,電子顕微鏡写真および理解を助ける模式図にはそれぞれ要を得た適切な長さの説明がついている。また各章の始めには,その章の内容の理解に必要な事項の説明があり,細部にとらわれて全体を見失わないための配慮もなされている。そしてさらには「機能を中心とする」とあるように各部位の解説も形態のみの説明だけではなく,機能から構造を理解させようという試みが随所に盛られている。この本が今回改訂になって大きく変わった点は,まず,判型がB5からA4判へと大きくなったことである。これにより頁にゆとりができ,見出しも網掛けや線で囲むなどの工夫がなされ,大変見やすくなっている。加えて,説明文中のキーワードが太字に変わり,ある術語を索引から検索する場合にも短時間で探し当てることが可能となった。さらには模式図がカラー化されて一段と理解しやすくなり,また組織切片だけではわかりづらいところには,新たに概念図を挿入したり,まとめの表を追加するなど,いろいろの学習者の理解を助ける手だてが加わっている。
◆「組織学を機能とからめて楽しく理解」をモットーに
第1部「細胞」の章では,総合的理解のため,以前章末にあった光学顕微鏡写真を電子顕微鏡写真と組み合わせて配慮しているほか,アポトーシスの機構など新たな分野の解説も取り入れている。このような学問の進歩も進んで取り入れる姿勢は,この種の本としては頻繁な改訂(原著で6-8年ごと)に現れている。もともとこの本は,組織学を機能とからめて楽しく理解できるようにとの意図の元に書かれた本であるが,今回の改訂で学習者にとりさらに使いやすい本となっている。
ところで,医学教育は現在大きな転換点を迎えている。解剖学は従来のカリキュラムから大幅に時間数が削減される大学が多く,組織学も要点を要領よく短時間で身につけさせる必要がでてきているほか,器官別に病理学,臨床の科目と組み合わせた統合型のカリキュラムとなるところも多い。このような解剖学教育の現状からこの本を見てみると,本書は機能面を重視しながら構造を理解しようとしているので,統合型の学習にも向いており,さらには索引がこの種の本としては他に比肩するものがないほど充実している――項目数は和文,英文ともにそれぞれ2000以上――ので,学習の途中で疑問のでた項目を探したいという,例えばチュートリアルシステムのようなタイプの学習においても大いに役立つことを意味している。この本は,著者が学習者の理解を第1にして書き著し改訂した優れた組織学の図譜兼教科書であり,内耳などの特殊な部分を除いて光学顕微鏡写真は,すべてヒトを材料としていることから,学生のみならず組織学を再度見直そうという人には,ぜひ1度手に取っていただきたい本である。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。