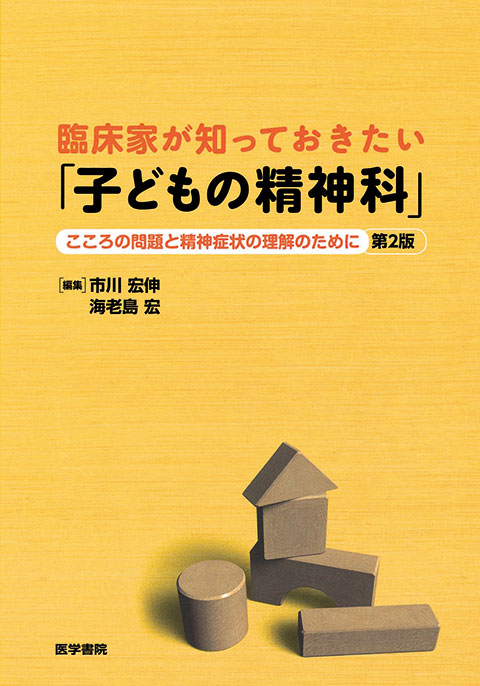臨床家が知っておきたい「子どもの精神科」
こころの問題と精神症状の理解のために
子どもの精神症状の診かたと対応を解説した全医療者必携の実践的入門書
もっと見る
子どもの心の問題,精神症状への理解を深め,医療者として適切に対応するために,知っておくべき児童精神科の知識・手法から福祉との連携,家族との接し方まで,専門医がわかりやすく解説した実践的入門書。子どもの精神科医の不足・誤解により,必要な医療の介入がなされているとは言えない今,子どもをみる,すべての臨床家必読の書。
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 目次
- 書評
目次
開く
診断にあたって
子どもの精神医学的診断のしかた
小児精神科における諸検査
治療的対応について
治療の考え方
具体的な対応のしかた
子どもによくみられる精神症状のみかた
子どもによくみられる精神症状
代表的症状のみかた
子どもによくみられる精神疾患とそれらへの対応
児童青年期の精神疾患と診断基準
各論
「子どもの精神科」におけるいくつかの問題
家族と治療
教育との連携
福祉・司法・保健との連携
小児科からみた子どもの精神科との連携
子どもの精神科からみた他科との連携
成人の精神科からみた子どもの精神科との連携
子どもの精神医学的診断のしかた
小児精神科における諸検査
治療的対応について
治療の考え方
具体的な対応のしかた
子どもによくみられる精神症状のみかた
子どもによくみられる精神症状
代表的症状のみかた
子どもによくみられる精神疾患とそれらへの対応
児童青年期の精神疾患と診断基準
各論
「子どもの精神科」におけるいくつかの問題
家族と治療
教育との連携
福祉・司法・保健との連携
小児科からみた子どもの精神科との連携
子どもの精神科からみた他科との連携
成人の精神科からみた子どもの精神科との連携
書評
開く
子どもの精神科のアウトラインを知るために絶好
書評者: 中根 晃 (都精神研)
児童・思春期の精神的問題は,成人の精神疾患をモデルとした精神医学の体系では対応できないことはよく知られている。例えば,思春期のうつ状態は従来型の抗うつ薬は奏効しきれない。そこに児童青年精神医学の存在意義があるわけであるが,ここで注意したいのは,親は自分の子どもを精神疾患だと思って受診させるのではないことである。そのため,全国各地の小児医療センターに精神科クリニックが開設され,小児医療の一環として運営されている。しかし,スペースやスタッフ機能が十分でなく,全方位の精神科診療を提供しにくいという難点を持っている。本書の執筆者の多くが所属している東京都立梅ケ丘病院は長年,広範囲にわたる子どもの精神科の臨床を実践している。本書は,その実績に立って書かれた臨床家のための手引きである。
◆日常の臨床の中で編集,洗練された懐の深い記述内容
どの教科書でも総論ではそのあるべき姿が書かれているが,それはすでに年月を経てしまって,現実とはかけ離れたものになっていることが多い。本書は,それを日常の臨床の中で編集し直して,洗練された形で記述している。「治療的対応について」の章では,年齢や発達段階に応じた個所プログラムの提供や医療体制の中での教育についても言及している。
「具体的対応の仕方」の章の「精神療法的対応」の項はユニークである。子どもの精神科での作業療法士の多岐にわたる活動についての記述は,わが国ではおそらく本書が最初であろう。また,「子どもによく見られる精神症状の見方」の各章では,代表的なものについて年齢ごとの特徴が書かれている点は精神科医にとっても,小児科医にとっても大いに参考になる個所である。
各論にあたる「子どもによく見られる精神疾患とそれらへの対応」の章は,ICD-10に沿って記述した関係上,年齢による細かい特徴は記されていないが,つぎの「子どもの精神科におけるいくつかの問題」の章の「家族と治療」の項は,受診に際して,入院に際して,家族の受けとめ方などと,具体的に述べながら家族の窮地の救いへと論を進めていく手法は本書の圧巻である。また,連携に関する各項目では,教育との連携が詳しく述べられ,司法との連携にも触れているのも本書の懐の深さを示している。
本書の各章は,要点がよくまとめられているので,子どもの精神科のアウトラインを知るための絶好の書に違いない。
子どものこころへの対応を児童精神科医が見事に解説
書評者: 小島 卓也 (日大教授・精神神経科学)
◆緊急対応が求められる子どものこころの問題解決にピッタリ
子どものこころの問題は,多動,不登校,いじめ,校内暴力,学級崩壊,ひきこもり,自殺,非行,社会的逸脱行動などとして増加しており,教育,福祉,医療,司法の分野で緊要な問題となっている。しかし日本では児童精神医学の専門家は少なく,この領域からの対応が不十分なのが現状である。
本書は,日本において数少ない児童専門精神病院でのチーム医療を中心にした成果のエッセンスを,関連の診療科や関連領域の方々に役立つようにとわかりやすくまとめたものである。発達を基盤にした子供に対する関わり方の基本と,症例や状況に応じた具体的な対応の仕方がすぐにわかるようにまとめられている。分担執筆者が自らの経験に基づいて,ていねいに記載しており,しかも読者がわかりやすいように,さまざまな工夫がなされている。一読した後も診療室において利用したくなる本である。
◆要領よく利用しやすい内容
内容について触れると,「診断にあたって」,「治療的対応について」,「子どもによくみられる精神症状のみかた」,「子どもにみられる精神疾患とそれらへの対応」,「「子どもの精神科」におけるいくつかの問題」に分かれている。「診断にあたって」についてみると,診察場面の設定では待合い室および,診察室の工夫,診察のきわめて困難な子どもに対する工夫から,診察場面では円滑な問診を妨げるファクターとその対処方法として,受診にいたるまでの子ども・親の心理,受診時の子ども・親の過剰な期待,問診時の子ども・親の心理,問診時の情報の客観性までが説明されている。
また実際の問診の進め方では,一般的な面接の仕方,小学校入学以前,小学校低学年,小学校高学年以降,特殊な場合の問診の進め方というように,発達に応じた対応の仕方が記されている。そして「子どもによくみられる精神症状のみかた」では,家庭医学書のようにその項目を見ると発達の面からの解説,考えられる疾患,鑑別診断,治療,対応の問題点などが書かれていて利用しやすい。
詳しすぎず,簡単すぎず,要領よくポイントが記されている。本書の編集方針がいきわたっているように思う。成人の精神科で治療する方々,小児科で児童青年期の精神障害に対応している方々,児童青年精神科医療の関連領域で働く方々にぜひ一読していただき,日常の活動に役立てていただきたいと思う。
書評者: 中根 晃 (都精神研)
児童・思春期の精神的問題は,成人の精神疾患をモデルとした精神医学の体系では対応できないことはよく知られている。例えば,思春期のうつ状態は従来型の抗うつ薬は奏効しきれない。そこに児童青年精神医学の存在意義があるわけであるが,ここで注意したいのは,親は自分の子どもを精神疾患だと思って受診させるのではないことである。そのため,全国各地の小児医療センターに精神科クリニックが開設され,小児医療の一環として運営されている。しかし,スペースやスタッフ機能が十分でなく,全方位の精神科診療を提供しにくいという難点を持っている。本書の執筆者の多くが所属している東京都立梅ケ丘病院は長年,広範囲にわたる子どもの精神科の臨床を実践している。本書は,その実績に立って書かれた臨床家のための手引きである。
◆日常の臨床の中で編集,洗練された懐の深い記述内容
どの教科書でも総論ではそのあるべき姿が書かれているが,それはすでに年月を経てしまって,現実とはかけ離れたものになっていることが多い。本書は,それを日常の臨床の中で編集し直して,洗練された形で記述している。「治療的対応について」の章では,年齢や発達段階に応じた個所プログラムの提供や医療体制の中での教育についても言及している。
「具体的対応の仕方」の章の「精神療法的対応」の項はユニークである。子どもの精神科での作業療法士の多岐にわたる活動についての記述は,わが国ではおそらく本書が最初であろう。また,「子どもによく見られる精神症状の見方」の各章では,代表的なものについて年齢ごとの特徴が書かれている点は精神科医にとっても,小児科医にとっても大いに参考になる個所である。
各論にあたる「子どもによく見られる精神疾患とそれらへの対応」の章は,ICD-10に沿って記述した関係上,年齢による細かい特徴は記されていないが,つぎの「子どもの精神科におけるいくつかの問題」の章の「家族と治療」の項は,受診に際して,入院に際して,家族の受けとめ方などと,具体的に述べながら家族の窮地の救いへと論を進めていく手法は本書の圧巻である。また,連携に関する各項目では,教育との連携が詳しく述べられ,司法との連携にも触れているのも本書の懐の深さを示している。
本書の各章は,要点がよくまとめられているので,子どもの精神科のアウトラインを知るための絶好の書に違いない。
子どものこころへの対応を児童精神科医が見事に解説
書評者: 小島 卓也 (日大教授・精神神経科学)
◆緊急対応が求められる子どものこころの問題解決にピッタリ
子どものこころの問題は,多動,不登校,いじめ,校内暴力,学級崩壊,ひきこもり,自殺,非行,社会的逸脱行動などとして増加しており,教育,福祉,医療,司法の分野で緊要な問題となっている。しかし日本では児童精神医学の専門家は少なく,この領域からの対応が不十分なのが現状である。
本書は,日本において数少ない児童専門精神病院でのチーム医療を中心にした成果のエッセンスを,関連の診療科や関連領域の方々に役立つようにとわかりやすくまとめたものである。発達を基盤にした子供に対する関わり方の基本と,症例や状況に応じた具体的な対応の仕方がすぐにわかるようにまとめられている。分担執筆者が自らの経験に基づいて,ていねいに記載しており,しかも読者がわかりやすいように,さまざまな工夫がなされている。一読した後も診療室において利用したくなる本である。
◆要領よく利用しやすい内容
内容について触れると,「診断にあたって」,「治療的対応について」,「子どもによくみられる精神症状のみかた」,「子どもにみられる精神疾患とそれらへの対応」,「「子どもの精神科」におけるいくつかの問題」に分かれている。「診断にあたって」についてみると,診察場面の設定では待合い室および,診察室の工夫,診察のきわめて困難な子どもに対する工夫から,診察場面では円滑な問診を妨げるファクターとその対処方法として,受診にいたるまでの子ども・親の心理,受診時の子ども・親の過剰な期待,問診時の子ども・親の心理,問診時の情報の客観性までが説明されている。
また実際の問診の進め方では,一般的な面接の仕方,小学校入学以前,小学校低学年,小学校高学年以降,特殊な場合の問診の進め方というように,発達に応じた対応の仕方が記されている。そして「子どもによくみられる精神症状のみかた」では,家庭医学書のようにその項目を見ると発達の面からの解説,考えられる疾患,鑑別診断,治療,対応の問題点などが書かれていて利用しやすい。
詳しすぎず,簡単すぎず,要領よくポイントが記されている。本書の編集方針がいきわたっているように思う。成人の精神科で治療する方々,小児科で児童青年期の精神障害に対応している方々,児童青年精神科医療の関連領域で働く方々にぜひ一読していただき,日常の活動に役立てていただきたいと思う。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。