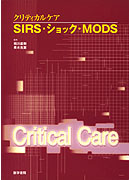クリティカルケア
SIRS・ショック・MODS
最先端のショックに関する病態生理から治療までを解説した救急医の必携書
もっと見る
近年ショックの分類は、循環動態を中心とした機能的分類に変わり、より治療に直結したものに整理された。本書では、この新しい分類に基づいたショックの病態生理を臨床的な視点から詳述し、ショック後の臓器障害をSIRS・MODSという疾病概念とのかかわりで新たに構築するとともに、最先端のショック治療の実際までを豊富な図表を駆使してわかりやすく解説した。
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 目次
- 書評
目次
開く
第1章 SIRS・ショック・MODSの歴史的概観
第2章 SIRS・ショック・MODSの病態
I サイトカイン
II ケミカルメディエータ
III 血管内皮と微小循環障害
IV 虚血再灌流障害
V 組織酸素代謝障害
第3章 SIRS・ショック・MODSの診断と初療
I SIRS・ショック・MODS;定義、分類および診断基準
II SIRS患者のトリアージ
III ショックの診断と緊急処置
第4章 SIRS・ショック・MODSの治療
I 呼吸管理
II 輸液・輸血・栄養管理
III 血管作動薬
IV 蛋白分解酵素阻害薬と抗メディエータ療法
V 血液浄化法
第5章 各種ショックの治療の実際
I 血液分布異常性ショック
II 循環血液量減少性ショック
III 心原性ショック
IV 心外閉塞・拘束性ショック
第6章 臓器サポートの実際
I 呼吸不全
II 心不全
III 腎不全
IV 肝不全
V 消化管出血とDIC
VI 中枢神経障害
第2章 SIRS・ショック・MODSの病態
I サイトカイン
II ケミカルメディエータ
III 血管内皮と微小循環障害
IV 虚血再灌流障害
V 組織酸素代謝障害
第3章 SIRS・ショック・MODSの診断と初療
I SIRS・ショック・MODS;定義、分類および診断基準
II SIRS患者のトリアージ
III ショックの診断と緊急処置
第4章 SIRS・ショック・MODSの治療
I 呼吸管理
II 輸液・輸血・栄養管理
III 血管作動薬
IV 蛋白分解酵素阻害薬と抗メディエータ療法
V 血液浄化法
第5章 各種ショックの治療の実際
I 血液分布異常性ショック
II 循環血液量減少性ショック
III 心原性ショック
IV 心外閉塞・拘束性ショック
第6章 臓器サポートの実際
I 呼吸不全
II 心不全
III 腎不全
IV 肝不全
V 消化管出血とDIC
VI 中枢神経障害
書評
開く
重症患者の評価,治療を新たな概念から詳述
書評者: 小川 龍 (日医大教授・麻酔科学)
◆重症患者管理医学の課題
このたび医学書院より,慶応義塾大学医学部救急部の相川直樹,青木克憲両氏の編集になる『クリティカルケア-SIRS・ショック・MODS』と題する書籍が刊行された。
近時,呼吸管理や循環管理などから発展してきた集中治療医学(intensive care medicine)と外傷,熱傷,中毒の蘇生・治療から成長してきた救急医学(emergency medicine)がしだいに接近して,重症患者管理医学(critical care medicine)ともいうべき分野を形成している。重症患者管理医学が取り組んでいる最大の問題は,重症患者に合併し,死の直接の原因となる多臓器複合不全である。
1991年,米国の胸部疾患学会と救急医学会との合同討議で産まれたSIRS(全身性炎症反応症候群)の概念は,非感染性炎症性ショック(SIRSショック)や機能面を重視した多臓器不全(MODS)の新しい考え方を導いた。このSIRSの概念は,細菌感染と非細菌感染とを明確に区別して,敗血症性ショック(septic shock)の治療に対する評価を明確にするためである。
◆感染症の有無を基本に(SIRS・ショック・MODS)
SIRSの病態を子細に分析すると,体内でサイトカインが動員されているcytokine stormがあることが知られ,循環動態の抑制によるショックの発生には非酸素ラディカル(窒素ラディカル・炭素ラディカル)が重要な役割を果していることが明らかとなった。また非酸素ラディカルの細胞の計画死(apoptosis)の誘導も知られるに至り,編集者の相川氏が第1章で述べているように自己破壊的生体反応症候群(antodestructive host-response syndrome)の側面も顕わになった。
このような基調のもとで第2章の病態へと進む。病態ではサイトカインその他のメディエータの役割が詳しく解説されている。また血管内皮,虚血再灌流,組織酸素代謝の問題も詳しく論じられている。
第3章は,診断と初療である。まずショックの分類について,最近採用されている,血液分布異常性,循環血液量減少性,心原性,心外閉塞・拘束性ショックを用いた点に新味がある。しかし心外閉塞・拘束性ショックは,extracardiac obstructive shockの訳であろうが,理解しにくい。心帰流障害性ショックのほうが理解しやすい。診断は前述の米国2学会の共同提案に従っており,感染の有無で厳格に区分している。またショック診断の主項目(血圧)と小項目(臓器血流不全)は誠に要を得ている。
第4章以降は,治療の問題を取り上げている。特に第6章の臓器サポートの実際は,臨床の最先端を余すところなく記述している。
総体として本書は,新しい概念であるSIRS・ショック・MODSを十分に描きつくしている。本書を熟読することにより,感染症の有無を基本とした重症患者の評価,治療の全貌が理解できると考える。
クリティカルケアに従事するすべての人に本書を勧めたい
書評者: 劔物 修 (北大大学院教授・侵襲制御医学)
◆最新のクリティカルケアの全貌
クリティカルケアの対象疾患の共通病態として,感染性ショックと多臓器機能障害症候群(MODS)があり,これらの病態の基礎には全身性炎症反応症候群(SIRS)がある。本書では,最新のクリティカルケアの理解に必要なSIRS,ショック,そしてMODSの病態について新進気鋭の執筆者を得て,わかりやすく解説されている。本書は6章から構成されており,第1章から4章では,SIRS・ショック・MODSの歴史的概観,病態,診断と初療,そして治療がそれぞれ具体的にまとめられている。
第1章では,SIRS・ショック・MODSの概念が発生機序とともに理解しやすく整理されている。SIRS・ショック・MODSには,サイトカインストームで代表される各種のメディエータを介する宿主の自己破壊的な生体反応が共通の病態と捉え,編者の相川直樹教授は,自己破壊的生体反応症候群:autodestructive host-response syndrome(AHRS)という新しい症候群を提唱している。これは編者の永年にわたるこの分野における基礎的研究と臨床経験からの発想と理解され,説得力がある。
第2章では,サイトカイン,ケミカルメディエータ,血管内皮と微小循環障害,虚血再灌流障害,組織酸素代謝障害がキーワードとなり,SIRS・ショック・MODSの病態を詳細に解説している。
第3章では,ショックを「急性全身性循環障害で,重要臓器機能を維持するのに十分な血液循環が得られない結果発生する生体機能異常を呈する症候群」と定義している。従来は不十分であったショックの定義を端的に表現しており,含蓄のあるものである。ショックの分類も I.血液分布異常性(A.感染性,B.アナフィラキシー,C.心原性),II.循環血液量減少性(A.出血性,B.体液喪失),III.心原性(A.心筋性,B.機械性,C.不整脈),IV.心外閉塞・拘束性(A.心タンポナーデ,B.収縮性心膜炎,C.重症肺塞栓症,D.緊張性気胸)と,新しいものを採択している。この分類に最初は多少の戸惑いを覚えるが,内容を吟味すると納得のいくものと理解できる。この章では新しい分類に基づき,SIRS患者のトリアージ,ショックの診断と初療が順序よく記述されており,次の第4章のSIRS・ショック・MODSの治療に引き継がれている。
第4章では,呼吸管理,輸液・輸血・栄養管理,血管作動薬,蛋白分解酵素阻害薬と抗メディエータ治療,血流浄化法が総論的にまとめられている。
第5章では,新分類による各種ショックごとに,A.病態生理,B.検査・診断のポイント,C.治療の実際がコンパクトにまとめられている。
第6章では,臓器サポートを呼吸不全,心不全,腎不全,肝不全,消化器出血とDIC,中枢神経障害に分けて,病態生理,鑑別診断,早期診断そして治療の実際を,治療を行なう立場から小気味よく記述している。
◆心憎いほど伝わる編者の意気込み
本書では,各項のあとに3編ずつの文献抄録が付され,ショックに対する古典的なものから最新の考え方まで紹介されている。頁をめくるにつれてSIRS・ショック・MODSの知識が深まっていき,編者の本書に託す意気込みが心憎いほど伝わってくる。本書は,クリティカルケアに関与するすべての医師,看護婦(士)に推薦できるSIRS・ショック・MODSに関するガイドブックであると同時に,各科の研修医あるいは医学生にもぜひ一読を勧めたい良書である。
書評者: 小川 龍 (日医大教授・麻酔科学)
◆重症患者管理医学の課題
このたび医学書院より,慶応義塾大学医学部救急部の相川直樹,青木克憲両氏の編集になる『クリティカルケア-SIRS・ショック・MODS』と題する書籍が刊行された。
近時,呼吸管理や循環管理などから発展してきた集中治療医学(intensive care medicine)と外傷,熱傷,中毒の蘇生・治療から成長してきた救急医学(emergency medicine)がしだいに接近して,重症患者管理医学(critical care medicine)ともいうべき分野を形成している。重症患者管理医学が取り組んでいる最大の問題は,重症患者に合併し,死の直接の原因となる多臓器複合不全である。
1991年,米国の胸部疾患学会と救急医学会との合同討議で産まれたSIRS(全身性炎症反応症候群)の概念は,非感染性炎症性ショック(SIRSショック)や機能面を重視した多臓器不全(MODS)の新しい考え方を導いた。このSIRSの概念は,細菌感染と非細菌感染とを明確に区別して,敗血症性ショック(septic shock)の治療に対する評価を明確にするためである。
◆感染症の有無を基本に(SIRS・ショック・MODS)
SIRSの病態を子細に分析すると,体内でサイトカインが動員されているcytokine stormがあることが知られ,循環動態の抑制によるショックの発生には非酸素ラディカル(窒素ラディカル・炭素ラディカル)が重要な役割を果していることが明らかとなった。また非酸素ラディカルの細胞の計画死(apoptosis)の誘導も知られるに至り,編集者の相川氏が第1章で述べているように自己破壊的生体反応症候群(antodestructive host-response syndrome)の側面も顕わになった。
このような基調のもとで第2章の病態へと進む。病態ではサイトカインその他のメディエータの役割が詳しく解説されている。また血管内皮,虚血再灌流,組織酸素代謝の問題も詳しく論じられている。
第3章は,診断と初療である。まずショックの分類について,最近採用されている,血液分布異常性,循環血液量減少性,心原性,心外閉塞・拘束性ショックを用いた点に新味がある。しかし心外閉塞・拘束性ショックは,extracardiac obstructive shockの訳であろうが,理解しにくい。心帰流障害性ショックのほうが理解しやすい。診断は前述の米国2学会の共同提案に従っており,感染の有無で厳格に区分している。またショック診断の主項目(血圧)と小項目(臓器血流不全)は誠に要を得ている。
第4章以降は,治療の問題を取り上げている。特に第6章の臓器サポートの実際は,臨床の最先端を余すところなく記述している。
総体として本書は,新しい概念であるSIRS・ショック・MODSを十分に描きつくしている。本書を熟読することにより,感染症の有無を基本とした重症患者の評価,治療の全貌が理解できると考える。
クリティカルケアに従事するすべての人に本書を勧めたい
書評者: 劔物 修 (北大大学院教授・侵襲制御医学)
◆最新のクリティカルケアの全貌
クリティカルケアの対象疾患の共通病態として,感染性ショックと多臓器機能障害症候群(MODS)があり,これらの病態の基礎には全身性炎症反応症候群(SIRS)がある。本書では,最新のクリティカルケアの理解に必要なSIRS,ショック,そしてMODSの病態について新進気鋭の執筆者を得て,わかりやすく解説されている。本書は6章から構成されており,第1章から4章では,SIRS・ショック・MODSの歴史的概観,病態,診断と初療,そして治療がそれぞれ具体的にまとめられている。
第1章では,SIRS・ショック・MODSの概念が発生機序とともに理解しやすく整理されている。SIRS・ショック・MODSには,サイトカインストームで代表される各種のメディエータを介する宿主の自己破壊的な生体反応が共通の病態と捉え,編者の相川直樹教授は,自己破壊的生体反応症候群:autodestructive host-response syndrome(AHRS)という新しい症候群を提唱している。これは編者の永年にわたるこの分野における基礎的研究と臨床経験からの発想と理解され,説得力がある。
第2章では,サイトカイン,ケミカルメディエータ,血管内皮と微小循環障害,虚血再灌流障害,組織酸素代謝障害がキーワードとなり,SIRS・ショック・MODSの病態を詳細に解説している。
第3章では,ショックを「急性全身性循環障害で,重要臓器機能を維持するのに十分な血液循環が得られない結果発生する生体機能異常を呈する症候群」と定義している。従来は不十分であったショックの定義を端的に表現しており,含蓄のあるものである。ショックの分類も I.血液分布異常性(A.感染性,B.アナフィラキシー,C.心原性),II.循環血液量減少性(A.出血性,B.体液喪失),III.心原性(A.心筋性,B.機械性,C.不整脈),IV.心外閉塞・拘束性(A.心タンポナーデ,B.収縮性心膜炎,C.重症肺塞栓症,D.緊張性気胸)と,新しいものを採択している。この分類に最初は多少の戸惑いを覚えるが,内容を吟味すると納得のいくものと理解できる。この章では新しい分類に基づき,SIRS患者のトリアージ,ショックの診断と初療が順序よく記述されており,次の第4章のSIRS・ショック・MODSの治療に引き継がれている。
第4章では,呼吸管理,輸液・輸血・栄養管理,血管作動薬,蛋白分解酵素阻害薬と抗メディエータ治療,血流浄化法が総論的にまとめられている。
第5章では,新分類による各種ショックごとに,A.病態生理,B.検査・診断のポイント,C.治療の実際がコンパクトにまとめられている。
第6章では,臓器サポートを呼吸不全,心不全,腎不全,肝不全,消化器出血とDIC,中枢神経障害に分けて,病態生理,鑑別診断,早期診断そして治療の実際を,治療を行なう立場から小気味よく記述している。
◆心憎いほど伝わる編者の意気込み
本書では,各項のあとに3編ずつの文献抄録が付され,ショックに対する古典的なものから最新の考え方まで紹介されている。頁をめくるにつれてSIRS・ショック・MODSの知識が深まっていき,編者の本書に託す意気込みが心憎いほど伝わってくる。本書は,クリティカルケアに関与するすべての医師,看護婦(士)に推薦できるSIRS・ショック・MODSに関するガイドブックであると同時に,各科の研修医あるいは医学生にもぜひ一読を勧めたい良書である。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。