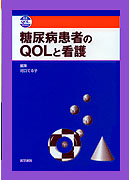糖尿病患者のQOLと看護
患者のQOLに基本を据えた看護婦による糖尿病へのかかわりを紹介する
もっと見る
糖尿病の治療には、セルフケアが大きな要素を占めている。糖尿病患者が明確な病識を持ち、セルフケアを進めるために看護婦の果たす役割は大きい。本書は、患者のQOLを基本にすえ、糖尿病をかかえての生活、患者の病識や自己決定へのかかわり、患者の成長発達段階、治療の場、糖尿病の合併症などに対する看護の取り組みを紹介する。
| 編集 | 河口 てる子 |
|---|---|
| 発行 | 2001年01月判型:B5頁:296 |
| ISBN | 978-4-260-33106-7 |
| 定価 | 3,520円 (本体3,200円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 書評
書評
開く
QOLを重視した看護のあり方を追求
書評者: 川田 智惠子 (岡山大医学部教授・保健学科)
本書は題名のごとく,糖尿病患者の種々の場面,症状,そしてライフステージにおけるQOLを考え,QOLを大事にした看護のあり方を追求しようとした著作である。章によってその「出来」には多少の差があるが,糖尿病の医療に関わっている者ならば誰でも求めているQOLを課題にして果敢に挑戦している。ぜひ一読をお勧めしたい。
◆両立困難な自己管理の維持とQOLの確保
糖尿病者が良好なコントロールを維持するには,厳格な食事療法や運動療法がどうしても必要であるということで,ある医療者は「健康のためなら,患者は辛くてもそれらを守るべきだ」と真剣に自己管理の必要性を指導し,あるいは強制し,またある医療者は,「指導はするが,守れないのはわかるから結果は期待しない」と曖昧に対応してきた。自己管理を続けることとQOLを保つことは両立が難しいのである。また,不幸にして糖尿病の合併症を発症した患者にとっては,自己管理の上に合併症によって引き起こされた障害がQOLに影響してくる。
◆患者・家族も執筆者に
本書は,実践者,研究者,さらに糖尿病患者・家族が執筆者になっている。
目次を見ると,「糖尿病をもちながらの生活と患者」,「患者の生活する場と治療の場」,「患者の成長発達段階とQOLの変化」,「治療と合併症の患者のQOLと看護」および「糖尿病患者の求めるQOL」の5部構成になっている。
第1部の「糖尿病をもちながらの生活と患者」では,患者の生活と心理,および家族や社会と患者のQOLについて考察し,看護職の援助について,例えばコンプライアンスとアドヒアランス,アンドラゴジ-,インフォームド・コンセントなどの理論の解説を織り交ぜて述べている。第5章の「命を慈しむ―――わだち会とともに」は患者会の創設と活動の意義,患者会の主体性とQOLについて書かれているが,この本の患者の執筆者はこの会に所属している方である。
第2部の「患者の生活する場と治療の場」では,外来と訪問看護を取りあげて,各々の場での看護職の役割について,ケースを紹介しつつ述べている。
第3部の「患者の成長発達段階とQOLの変化」は,小児期,思春期,壮年期,老年期に分けて,保護者のかかわりの強い年代から,自律・自立の年代を経て,一家の中心の役割を担う年代,そうしてさまざまな喪失を体験する年代への移行をそれぞれの生活の特徴と,自己管理とQOLがどのような関係になっているか描いている。
第4部の「治療と合併症の患者のQOLと看護」は,食事療法,運動療法,インスリン療法,糖尿病性網膜症,糖尿病性腎症,糖尿病性血管障害,糖尿病性神経障害と患者のQOLについて述べているが,後半の合併症と患者のQOLについての章は少しもの足りないところがあった。
第5部の「糖尿病患者の求めるQOL」は学ぶところが多かった。「QOLとは,1人の人間が歩んできた生きざまやものの見方,人生観であり,糖尿病患者のQOLは糖尿病を持った人間の疾患,医療,自己管理とその生きざまが密接に結びついて生み出されるその人だけのものである」と述べ,QOLを「よりよい生活をめざす心のあり方」と定義したいと書いている。また他の方は,糖尿病患者のQOLには,患者を取り巻く社会状況,医療・社会保障・福祉システムや教育制度のあり方が深く関わっていると述べている。
◆患者のQOLを配慮した支援
本書は,編者および患者自身が述べているごとく,「患者の生活を知り,患者の気持ちに共感しながら一緒に可能な方法を模索する,つまり患者のQOLを配慮した支援をすることが,結局のところ一番大切ではないか」という考え方で貫かれている。
書評者: 川田 智惠子 (岡山大医学部教授・保健学科)
本書は題名のごとく,糖尿病患者の種々の場面,症状,そしてライフステージにおけるQOLを考え,QOLを大事にした看護のあり方を追求しようとした著作である。章によってその「出来」には多少の差があるが,糖尿病の医療に関わっている者ならば誰でも求めているQOLを課題にして果敢に挑戦している。ぜひ一読をお勧めしたい。
◆両立困難な自己管理の維持とQOLの確保
糖尿病者が良好なコントロールを維持するには,厳格な食事療法や運動療法がどうしても必要であるということで,ある医療者は「健康のためなら,患者は辛くてもそれらを守るべきだ」と真剣に自己管理の必要性を指導し,あるいは強制し,またある医療者は,「指導はするが,守れないのはわかるから結果は期待しない」と曖昧に対応してきた。自己管理を続けることとQOLを保つことは両立が難しいのである。また,不幸にして糖尿病の合併症を発症した患者にとっては,自己管理の上に合併症によって引き起こされた障害がQOLに影響してくる。
◆患者・家族も執筆者に
本書は,実践者,研究者,さらに糖尿病患者・家族が執筆者になっている。
目次を見ると,「糖尿病をもちながらの生活と患者」,「患者の生活する場と治療の場」,「患者の成長発達段階とQOLの変化」,「治療と合併症の患者のQOLと看護」および「糖尿病患者の求めるQOL」の5部構成になっている。
第1部の「糖尿病をもちながらの生活と患者」では,患者の生活と心理,および家族や社会と患者のQOLについて考察し,看護職の援助について,例えばコンプライアンスとアドヒアランス,アンドラゴジ-,インフォームド・コンセントなどの理論の解説を織り交ぜて述べている。第5章の「命を慈しむ―――わだち会とともに」は患者会の創設と活動の意義,患者会の主体性とQOLについて書かれているが,この本の患者の執筆者はこの会に所属している方である。
第2部の「患者の生活する場と治療の場」では,外来と訪問看護を取りあげて,各々の場での看護職の役割について,ケースを紹介しつつ述べている。
第3部の「患者の成長発達段階とQOLの変化」は,小児期,思春期,壮年期,老年期に分けて,保護者のかかわりの強い年代から,自律・自立の年代を経て,一家の中心の役割を担う年代,そうしてさまざまな喪失を体験する年代への移行をそれぞれの生活の特徴と,自己管理とQOLがどのような関係になっているか描いている。
第4部の「治療と合併症の患者のQOLと看護」は,食事療法,運動療法,インスリン療法,糖尿病性網膜症,糖尿病性腎症,糖尿病性血管障害,糖尿病性神経障害と患者のQOLについて述べているが,後半の合併症と患者のQOLについての章は少しもの足りないところがあった。
第5部の「糖尿病患者の求めるQOL」は学ぶところが多かった。「QOLとは,1人の人間が歩んできた生きざまやものの見方,人生観であり,糖尿病患者のQOLは糖尿病を持った人間の疾患,医療,自己管理とその生きざまが密接に結びついて生み出されるその人だけのものである」と述べ,QOLを「よりよい生活をめざす心のあり方」と定義したいと書いている。また他の方は,糖尿病患者のQOLには,患者を取り巻く社会状況,医療・社会保障・福祉システムや教育制度のあり方が深く関わっていると述べている。
◆患者のQOLを配慮した支援
本書は,編者および患者自身が述べているごとく,「患者の生活を知り,患者の気持ちに共感しながら一緒に可能な方法を模索する,つまり患者のQOLを配慮した支援をすることが,結局のところ一番大切ではないか」という考え方で貫かれている。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。