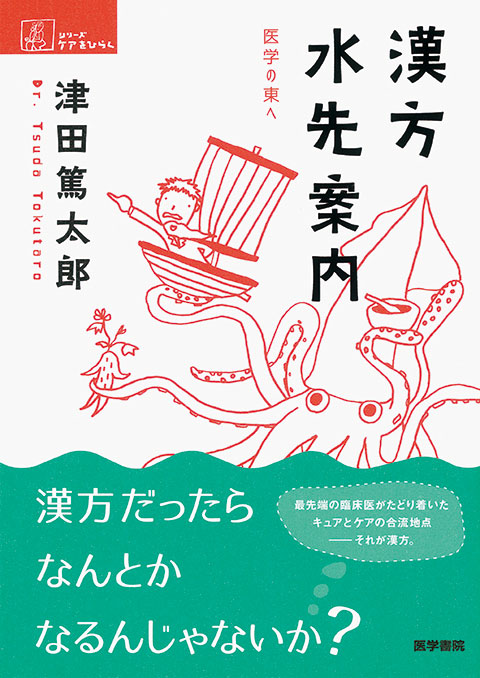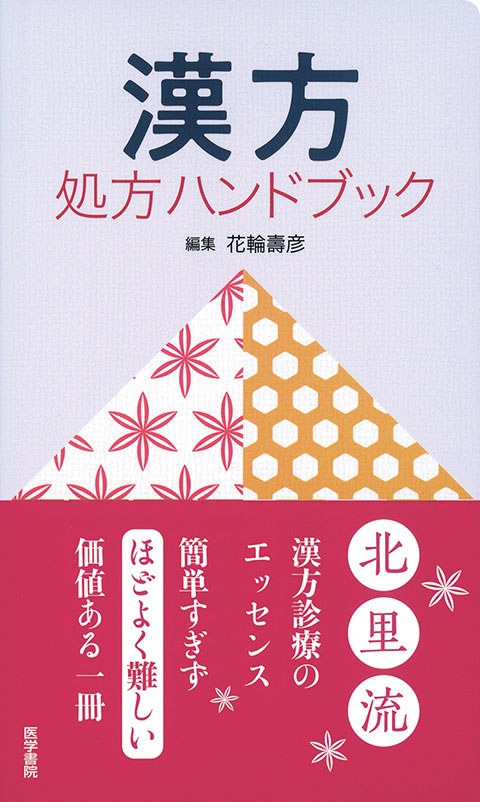漢方を交えた医療論
和漢診療学からの提言
「漢方ならこう考える」という視点からまとめた現代医療への提言書
もっと見る
日本の漢方医療の第一人者が、50年余東西両医学を活用する臨床医として活躍する中で見えてきた「漢方と科学の関係」や「理想とする医療の姿」について記した書。本書では、東西の壁を取り除き、漢方の知恵を活用する医療論を読者に説いている。より良き日本の医療を願う著者の熱い想いが込められた必読の1冊。
| 著 | 寺澤 捷年 |
|---|---|
| 発行 | 2024年11月判型:A5頁:240 |
| ISBN | 978-4-260-05741-7 |
| 定価 | 5,500円 (本体5,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
はじめに
わたしは後期高齢者と呼ばれる歳になりますが、わたしにも研修医の時代がありました。50年以上前のことです。今と違って卒業するとすぐに大学のどこかの医局に入局したのです。考えるとずいぶんと乱暴な話で、この医局選びはクラブの先輩の誘いや臨床実習で各科を回っている時に飲み会でご馳走になったということで決まることもありました。父親が開業医の場合にはその跡継ぎになる診療科を選ぶ人もいました。それとは別に、たとえば内科領域では第二内科には学力が優れた人が集まっており、循環器と内分泌に特化していましたが、第一内科はのんびりとした雰囲気で肝臓、腎臓、消化管、神経、感染症などデパートのようでした。そこでわたしは第一内科を選びました。
ただし、卒業したその年は「このような医局制度は変えなくてはならない」という医学生の運動が全国で起こったため、これに賛同して大学に入局しないで、千葉市内の地域基幹病院(川崎製鉄千葉病院)で内科の研修をさせてもらいました。この運動の結果として現在の研修医制度ができあがったわけです。
しかし、運動の現実はきびしく、大学の医局から派遣される「正規の医師」ではないので、月給は微々たるものでした。それでも研修内容は充実しており、一人の研修医に一人の指導医体制で、わたしは佐藤重明先生から内科の基本をみっちりと指導していただきました。
今でも覚えていることは「腰椎穿刺をするような場合、毎回、臨床検査学の検査手技の項目を事前に必ず読むこと」で、慣れてしまうことの危険性を教えてもらったのです。さらに、「クスリは極力数を少なく処方しなさい」、「抗菌薬は細菌培養を行い、感受性の有無を確認してからなるべく狭いスペクトルのものを選択しなさい」という教えも受けました。
●
入局の翌年(卒後三年目)の四月からは入局者全員が医局の関連病院に出向することになっていましたが、わたしは東京学芸大学山岳部(登高会)のヒマラヤ遠征隊の医師として参加することを二年前に約束していたので、教授にお願いして関連病院へは九月から出向することにしました。
ヒマラヤ遠征は七月・八月でしたので、四月から六月はフリーでした。そこで、かねてから興味のあった「心療内科」の現場を見学したいと思い、九州大学心療内科の池見酉次郎教授の医局に内地留学しました。心と身体を関連づけて解決法を見出すという期待したとおりの素晴らしい臨床でした。池見酉次郎先生のお人柄、人間力にも触れることができました。
一方、漢方は千葉大学に入学と同時に「千葉大学東洋医学研究会」というサークルに入会し、藤平健、小倉重成両先生の教えを受け、夏休みなどには小倉先生宅に寝泊まりして臨床実習に励みました。このような努力の結果、医学部卒業時には漢方で診察し、治療ができるレベルに達していました。一九七六年に漢方エキス製剤が保険薬価に大幅に採用されたので、アルバイト先の病院で活用し、ますます漢方の腕を磨くことができたのです。
五年間の内科研修を終えたところで、本格的な神経内科医になる修行を始めましたが、始めてみて気づいたことは、脳の解剖学が重要であることでした。そこで大学院(中枢神経解剖学)に入学し、同時に第一回の神経内科専門医試験に合格しました。大学院を一九七九年三月に修了し、医学博士の学位をいただきました。博士論文は、たとえば野球の打者が高速度のボールを見るために左右の眼球を同期させて動かす神経回路を明らかにしたものです。そして四月に新設の神経内科学講座の医局に入ったのですが、その七月のこと、突然に「東西医学の融合統一」を建学の理念とする富山医科薬科大学附属病院(現・富山大学附属病院)の和漢診療部に招かれて十月に赴任しました。博士号を持ち、漢方の臨床能力を兼ね備えている人材は当時皆無であったのです。
●
以来、四十余年、東西両医学を活用する臨床医として働いてきましたが、そこから見えてきた「漢方と科学」との関係や「理想とする医療の姿」があります。わたしの描く医療の姿、東西の壁を取り除き、漢方の知恵を活用する医療論ですが、これを若い皆さんの柔らかな頭脳に訴え、評価していただきたいと考え本書の執筆を思い立ったのです。
「医学概論」については澤瀉久敬先生[1]や川喜田愛郎先生[2]の名著がありますが、臨床医が東西両医学を俯瞰した「医療論」を記した著作はこれまでにありません。本書によって若い皆さんが、より良い医療人となっていただきたい。さらには日本の医療が国家としてのアイデンティティーを主張できる医療システムに向かって歩んでほしいと願い、本書を出版します。
参考文献
[1] 澤瀉久敬:医学概論 第三部・医学について.東京創元社.一九五九
[2] 川喜田愛郎:医学概論.筑摩書房.二〇一二
目次
開く
はじめに
第1章 医療の本質
第1節 医療を論じる前に
第2節 医療と何か? 医学=医療ではない
第3節 医療を実践する医師の人間力
第2章 漢方も交えて医療を考える
第1節 自然治癒力にもっと注目しよう
第2節 心と身体は一つ
第3節 陰陽という見方、考え方
第4節 触診の大切さを見直そう
第5節 腹診の具体的な方法
第6節 縦割り医療の弊害は国民に行き渡っている
第7節 木を見て森を見ず──還元主義の宿命
第3章 漢方と科学を考える
第1節 漢方と医学の歴史
第2節 還元主義と複雑系
第3節 漢方は効くのか? その有効性の評価
第4節 クスリの有効性を高める方法を探そう
第4章 漢方の診断と治療、そして死生観
第1節 COVID-19後遺症に対する漢方の診断と治療の実際
第2節 漢方診療の実際、自覚症状の重視
第3節 漢方の死生観とACP(Advance Care Planning)
第5章 医学教育と漢方
第1節 初期研修医へのインタビュー
第2節 そもそもモデル・コア・カリキュラムはどうしてできたのか
第3節 医師国家試験と漢方
第4節 漢方教育を担う人材の育成と教員選考の問題点
第6章 漢方を取り入れた医師たちへのQ&A
第1節 なぜ漢方を学ぼうと思ったのか
第2節 研修医の皆さんへのメッセージ
第7章 印象に残った症例
第8章 漢方と社会 現状と将来展望
第1節 新たなエキス製剤を保険適用にしたい
第2節 エキス製剤の効能効果の見直し
第3節 漢方エキス製剤、供給の問題
第4節 漢方と医療経済、将来の展望
第9章 日本型医療システムの提案
第1節 新たな医療を構成する諸要素
第2節 かかりつけ医機能の発揮と漢方
第3節 漢方とポリファーマシーの困った現状
第4節 総合診療科に期待するもの
第5節 第一一改訂・国際疾病分類(ICD-11)の意義
第6節 もう一つの伝統医学、鍼灸について
第7節 日本型医療システムの提案
おわりに
索引
コラム
気虚の診断基準 ICD-11
治ろうとしない患者。疾病利得の話
意地悪な医師会員
扱いにくい患者・人格病
上部消化管内視鏡の際の看護師さん
直観こそが生命の本質を捉える
一八〇〇年前の『傷寒論』には感染症に伴う症状が多数記されている
アナログ認識とデジタル認識
書評
開く
日本の医療の美点を放棄してしまわないための提言
書評者:津田 篤太郎(新潟医療福祉大教授・鍼灸健康学)
本書には評者と同世代の漢方医の名前が何人も出てくる。評者は四半世紀にわたり寺澤捷年先生の著作に学んでいるのであるが,この世界でいかに多くの後進を教え導いておられるのかを改めて思い知らされた。
「桃李成蹊」のたとえのごとく,寺澤先生の著作や講演はどんな読み手・聞き手をも惹きつけてやまないものがあるが,その魅力はいったいどういったところにあるのだろうか――それは明晰でわかりやすく,どこか親しみやすい“語り口”にあるように評者は思う。
……二二歳の男性患者。頭部打撲後の脱毛症の症例を記します。職場での精神的ストレスが強く,上司との関係も良くなかった(後日談)そうですが,二週間前,棚から8 kg程の商品を下ろそうとしたときに,運悪く,段ボール箱の角が頭頂部に当たったのです。「コブ」は比較的厚みのある皮下血腫ですが,日を追うごとに頭髪が脱落して円形の脱毛症になってしまいました……
症例提示はしばしば冷たい事実の羅列になりがちで,それは「科学性」「客観性」を保つ上で仕方のないことであるが,寺澤先生の症例の描き方は生き生きとしており,患者の顔つきやしぐさまで目に浮かぶようである。
以前,寺澤先生のお弟子さんから,次のような話を伺ったことがある。先生は講演だけでなく,落語をお演りになることもできる。車を運転されるときは必ず古典落語の録音を流して,噺の稽古に余念がないのだとか……だから,先生の“語り口”は魅力的なのか,と感心したものだが,最近になり「いやいやそれだけではない……」と思い直すようになった。
漢方の世界には「親試実験」という言葉がある。自分の目や手で確かめた事実を最も信頼できる立脚点とし,全ての議論をそこから出発させようという学問的態度を意味する。これは中国で発展した観念的なものの見方に対するアンチテーゼであり,日本の漢方医は理屈のフィルターを取り払って目の前のヴィヴィッドな現実をじかに感じ取る,その“肌触り”を重んじてきた。長年にわたる研究の中で寺澤先生は早くから日本漢方のそういった特質を見抜き,ご自身で体現されているからこそ,治療経験の「語り」が輝きを放つのではないだろうか……。
しかし本書では,その「語り」の中にいくばくかの陰りがさしているように見える。これまで,度重なる漢方薬の保険収載外しの動きや,漢方薬を処方すればするほど差損が生じる「逆ザヤ」問題をなんとか乗り越えてきたが,COVID-19パンデミックの後で起こったのが漢方薬の供給不足である。他方で医師の知識不足から不適切な漢方薬の処方も横行しており,寺澤先生はこうした現状に強く警鐘を鳴らしている。
ひょっとすると,もはや医療を提供する側とその恩恵にあずかる側の合意だけでは,漢方が存続できない時代に入りつつあるのかもしれない。もしそうであるとすれば,漢方や医療に関心を示さない「外部」にも働きかけ,日本の伝統医学の大切さを知ってもらうことが必要だということになる。そのためには,「親試実験」から一歩進み出て,新たな「観念」や「理論」で武装しなくてはならないのだろうか。
寺澤先生はその方向性を本書の後半部分で指し示している。欧化政策を急ぐ明治新政府が西洋医学中心の医制を定めたちょうど150年前,旧弊とされた伝統医学は,今や世界保健機関(WHO)の国際疾病分類第11版(ICD-11)の体系に採り入れられ,その経済合理性に注目し費用対効果を検証する研究がなされるなど,普遍的な価値を持つものとして再評価する機運が世界中で高まっている。だが,それに呼応する国内の動きはまだまだ鈍いと言わざるを得ない。日本の医療の美点を自らみすみす放棄してしまうようなことにならないようにするために,本書のメッセージは医療人にはもちろん,博く「外部」の人々にも届けられなくてはいけない。
医療者に贈る「目覚めの一冊」
書評者:寺澤 佳洋(口之津病院総合診療科)
本書を読み進めるうちに,私の人生の貴重な1ページが鮮明によみがえりました。それは今から10数年前,私が初期研修医として医学の道を歩み始めたころのことです。寺澤捷年先生の診察に陪席しながら漢方を学んだあの時間は,非常に貴重でぜいたくな時間でした。同じ「寺澤」の姓ということもあり,来院された患者さんに「私の孫が勉強に来たよ。一緒に診るよ」と冗談めかして診察が始まり,皆にとって心地良い時間が流れていました。まさにそこで行われていた,長年の経験で培われた身体診察の方法や症例報告は,本書に詳しく記されています。
一方で,柔和でユーモアにあふれる診察時間の中に,私に対しても患者さんに対しても時に厳しい提言や指導があったのも印象的です。しかし,その厳しさの裏側には深い愛情が感じられ,患者さんも「こんなに厳しく言ってくれて,うれしいのよ」と感謝されていました。後に聞いた話では,捷年先生はその人との長い関係性の中で,厳しく伝えるべき相手を見極めていたそうです。そのような愛情に満ちた厳しい提言が,本書にも随所に反映されています。その対象として,漢方に対する偏見,還元主義,終末期の医療など多岐にわたります。
それらの提言の多くは,現代医療における『当たり前』や『前例踏襲』を疑う姿勢の重要性を訴えているように感じました。医療の現場では,いつの間にか『当たり前』とされる考え方や手法が積み重なり,それを疑うことすら難しくなっているのが実情です。しかし,捷年先生は漢方の視点を交えながら,『当たり前』に再び目を向ける必要性を提言しています。そこからは,医療者だけでなく患者さんや社会全体に対しての深い愛情を感じ取ることができます。
捷年先生はこの書籍を,特に若い医療者や学生たちに届けたいと語っていました。まだ『当たり前』が固まっていない,医療の入り口に立つ彼らにこそ,読んでほしいとの願いが込められているようです。一方で,私のように10年以上医療現場に携わり,すでに『当たり前』が知らず知らずのうちに出来上がってしまった医療者にとっても,この本は価値ある一冊であると感じました。
本書を通じて,私が捷年先生の臨床研修指導から感じた深い愛情を,多くの読者にも共有していただきたいと願っています。そして読了後にはきっと,新たな視点を手に入れ,本書が「目覚めの一冊」になったことを実感されるでしょう。医療人としての考え方や姿勢を振り返りたい方,漢方の世界に触れてみたい方,さらには医療全般に関心のある方に,ぜひ本書を手に取っていただきたい。
漢方を交え,新しい日本型医療システムへ
書評者:中島 正光(広島国際大薬学部教授・生薬漢方診療学/和漢医薬学会理事長)
医学書院から出版された寺澤捷年先生の素晴らしい著書を拝読させていただきました。読みやすく,引き込まれる内容で,どんどんと先を読みたくなる本です。本書を読んでいただければ,日本の未来の医療は漢方を交えることによって,さらに素晴らしく,より世界に誇れる医療となることがわかります。いかにして貴重な日本の文化遺産である漢方を守り,活用させ,発展させることが重要であるかが読み解けるようになっています。
具体的な内容を記載すると,漢方と医療・科学・診断法・死生観・教育,医師の生の声,現状と将来展望,世界に誇れる日本型医療システムの提案など漢方の優れた特性と現状の問題点がさまざまな手法で説明されています。寺澤先生は,世界に類を見ない漢方を交えた新しい日本の医療が頭の中で見えているのだとわかります。このように,日本の医療が漢方を交えることによって新しい日本型医療システムへと変わる道筋を示している書物を私はまだ見たことがありません。
魅力を高めている本書の内容を少しご紹介します。例えば,寺澤先生の貴重な経験を吸収できるコラムや症例,加えて15人の執筆協力者の記載内容は本書を理解するのに良い助けとなっています。漢方を始めようとする先生には「漢方とはどのようなものか」,漢方のベテランの先生には「今後どのように漢方を活用,発展させるべきか」,そして医学界のリーダーの先生には「漢方を交えた医療による日本型医療システムの提案」を理解していただけると思います。大変,役に立つ,実に素晴らしい書物と感じました。
ぜひ,皆さんに読んでいただき,感動していただくとともに実践に役立てていただきたい作品です。
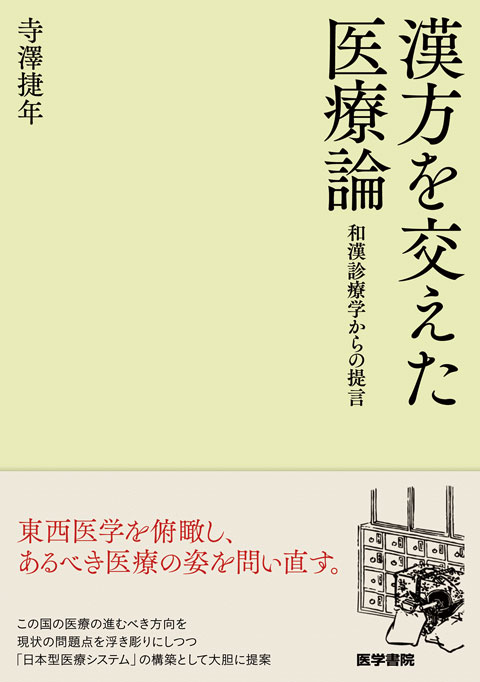
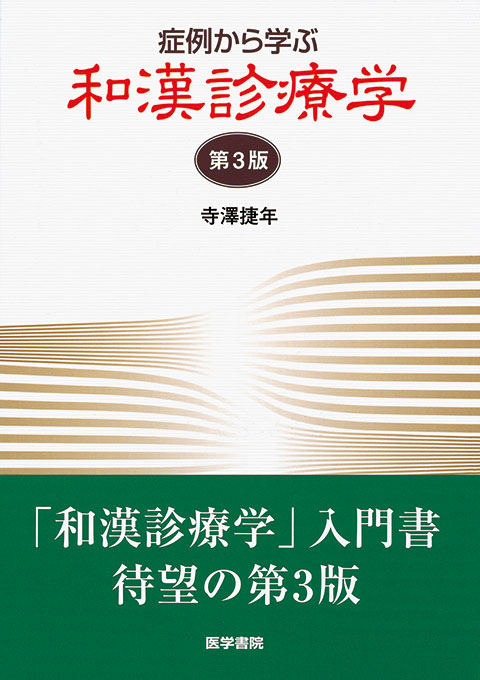
![はじめての漢方診療 十五話[WEB動画付] 第2版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/8416/2788/8744/110303.jpg)