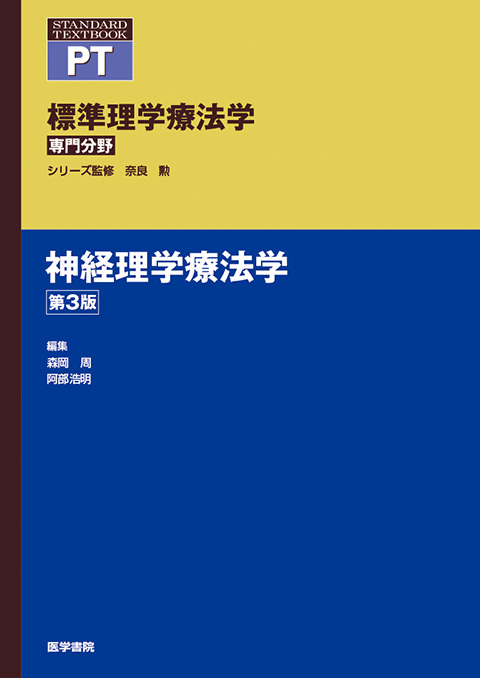神経理学療法学 第3版
脳卒中に重点を置きつつ、新項目を追加。神経理学療法の新しいスタンダードテキスト!
もっと見る
理学療法士の養成校で多くの時間が割かれる「脳卒中の理学療法」に重点を置きつつ、今版からは「病期別の脳卒中理学療法」や「頭部外傷」「脊髄損傷の障害と理学療法」などの新項目を追加。神経理学療法の最前線の内容も盛り込み、一流の執筆陣が漏れなく、分かりやすく神経理学療法を教授する。神経理学療法学の新しいスタンダードテキストが大改訂!
| シリーズ | 標準理学療法学 専門分野 |
|---|---|
| シリーズ監修 | 奈良 勲 |
| 編集 | 森岡 周 / 阿部 浩明 |
| 発行 | 2022年12月判型:B5頁:476 |
| ISBN | 978-4-260-04989-4 |
| 定価 | 5,720円 (本体5,200円+税) |
更新情報
-
正誤表を掲載しました。
2024.05.20
- 序文
- 目次
- 正誤表
序文
開く
第3版 序
2013年に初版,2018年に第2版を発行した『神経理学療法学』も第3版となった.そして,長年,神経理学療法学を牽引された吉尾雅春先生が編集者から退任された.先生は私たち後輩に対して神経理学療法学の向かうべき道を示してくれた.まずは先生のこれまでの多大なる功績に感謝を申し上げたい.
本書『神経理学療法学』は「標準理学療法学専門分野」シリーズの1冊として9年前に産声をあげた.当初から「標準とは何か?」を編集者の1人として自問しながら,その目次や内容を吟味してきた.第3版にしてやっと骨格が完成したように思える.これには神経理学療法学にかかわる人材が豊富になったことが背景にあるように思う.
理学療法あるいは理学療法学は運動器領域と神経領域によって発展してきたことは自明である.古くから存在してきた領域であるがゆえに,呪縛からの脱却が難しいととらえることもできる.脳・神経系の機能のほとんどがブラックスボックスと称されていた時代においては,経験中心的な理学療法に頼らざるをえなかった.それ自体はなんら否定されるべきものではなく,個々の経験によって開発された各種アプローチは神経理学療法の草創期を支え,黎明期として1つの文化を構築してきた.それから時代は経過し,脳・神経系の科学が発展し,脳・神経系の機能がある程度解明されてきた.一時期は“脳ブーム”がおこり,あることないこと脳が重要と脳科学が独り歩きした時代も過ぎ去り,やっと落ち着いてきた.今こそ,標準的な神経理学療法学とは何かを明示し,理学療法を学ぶ者に対して標準神経理学療法学を提供すべきときであると考える.
標準的な学びがなぜ必要か.それはもちろん神経障害を呈する対象者のためである.そして,共通言語で議論するためでもある.そういう意味で教科書の責任は重い.神経理学療法学は神経障害を呈する対象者のためにある.ゆえに,学術情報の品質管理・担保はきわめて重要である.情報が明らかに誤っていたり,個人の経験によって大いに歪められたりしてはならない.本書はその点にこだわり,第3版では信頼のおける執筆者を新たに迎えた.第3版ではそれぞれの章にその領域のスペシャリストを配置した.また,第2版までは含んでいなかった「脊髄損傷の理学療法」を加えた.再生医療の進歩とともに脊髄損傷の理学療法は進化している.だからこそ,学び直さないといけないし,新たな知見を常識化させないといけないと思う.さらに今版では,「病期別の脳卒中理学療法」に関する章を設けた.急性期,回復期,生活期において理学療法の役割は異なる.健康寿命の延伸に貢献すべき理学療法にとって,この役割の相違を理解することが求められる.
いずれにしても,本書はわが国における“神経理学療法学の羅針盤”であるといえる.ゆえに,神経障害の理学療法に携わる,あるいはこれから携わろうとする,多くの関係者に手に取っていただきたい.
2022年9月
編集者を代表して
森岡 周
目次
開く
I 脳卒中の理学療法
1 脳卒中の障害総論
1 中枢神経系の構造と脳画像
A 脳の構造──中枢神経の構造と機能
B 神経線維束の構造と連絡──脳内の主要
C 脳血管の走行と灌流領域
D 脳画像の基礎知識
2 中枢神経系のネットワークと機能障害
A はじめに
B 大脳皮質連合野と神経ネットワーク
C 各大脳皮質連合野からなる神経ネットワークの機能損傷,症状との関連
D 大脳と大脳以外の中枢神経系構造からなる神経ネットワークの機能,損傷,症状との関連
E おわりに
3 脳卒中の回復メカニズム
A 神経の可塑性
B 脳卒中後の機能回復に影響する因子
●コラム:水頭症
4 脳卒中の障害構造と評価
A 脳卒中と障害
B 脳卒中後の障害に対する評価の意義
C 脳卒中理学療法の代表的評価法
D 脳卒中後の障害に対する病期別の理学療法士の役割
5 脳卒中の病態とリスク管理
A 脳卒中の病態
B 脳卒中理学療法におけるリスク管理
C 理学療法開始時期と中止基準
●コラム:眼症状
2 脳卒中の障害と理学療法
1 運動麻痺
A 運動制御に関与する神経機構
B 運動麻痺
C まとめ
2 感覚障害
A 感覚障害とは
B 脳卒中後感覚障害とは
C 感覚障害の評価
D 感覚障害への理学療法
E 感覚障害に対する理学療法戦略とは
●コラム:視床
3 異常筋緊張
A はじめに
B 異常筋緊張の種類
C 痙縮の病態と発生メカニズム
D spastic movement disorder
E 痙縮の評価
F 痙縮の治療
4 運動失調
A 運動失調とは
B 協調運動の神経機構
C 運動失調の発生メカニズム
D 運動失調の種類とその症状
E 運動失調の評価
F 運動失調症例の理学療法
5 身体失認,病態失認
A 身体・病態失認とは
B 責任病巣
C メカニズム
D 評価
E 理学療法
6 半側空間無視
A 半側空間無視とは
B 注意の分類とその神経機構
C 半側空間無視のメカニズム
D 半側空間無視の評価
E 半側空間無視のサブタイプおよび応用的な評価の視点
F 半側空間無視のリハビリテーション
G おわりに
7 姿勢定位障害
A pusher現象
B lateropulsion
8 失行
A 失行の定義と種類
B 失行の評価
C 失行の病巣と発生メカニズム
D 失行に対するリハビリテーション
●コラム:失語症
9 歩行障害①──基礎(神経生理・バイオメカニクス)
A 歩行に関する神経機構
B 脳卒中片麻痺の歩行障害
10 歩行障害②──臨床(評価・治療)
A 歩行評価
B 理学療法の目的と実際
●コラム:歩行自立度
11 上肢機能障害
A 上肢運動にかかわる神経機構とその障害の特徴
B 上肢機能障害の評価
C 上肢機能障害に対するアプローチとそのエビデンス
D 複合的アプローチ
12 脳卒中後疼痛
A 痛みの定義と分類
B 脳卒中後疼痛の分類
C 脳卒中後疼痛の評価
D 脳卒中後疼痛の理学療法
13 二次性機能障害(関節可動域制限,サルコペニア・フレイル)
A 脳卒中における関節可動域制限
B 脳卒中におけるサルコペニア・フレイル
3 病期別の脳卒中理学療法
1 急性期
A 急性期とは
B 急性期における理学療法士の役割
C 早期離床
D 急性期予後予測
E 急性期から行う運動機能改善のための理学療法
F おわりに
2 回復期
A 回復期とは
B 回復期における理学療法士の役割
C 回復期における脳卒中患者の歩行障害の目標
D 回復期における脳卒中患者の理学療法の流れ
E 脳卒中患者の歩行と下肢運動障害
F 下肢運動障害に対するアプローチ
G 回復期脳卒中後片麻痺患者に対する装具療法
H 脳卒中患者の起居動作
I 退院後の生活環境の調整
J おわりに
3 生活期
A 生活期とは
B 本章を理解するための対象者像
C 生活期に生じる脳卒中後遺症者の諸問題
D 生活期の脳卒中理学療法に求められる視点と対応
II 神経筋疾患の障害と理学療法
1 Parkinson病の理学療法
A 疾患概要
B 理学療法評価
C 理学療法の実際
●コラム:嚥下障害
2 脊髄小脳変性症の理学療法
A 疾患の概要と障害の特徴
B 理学療法の実施に必要な基礎知識
C 標準的な理学療法評価
D 標準的な理学療法介入
3 筋萎縮性側索硬化症の理学療法
A 疾患の概要
B 疾患・障害のとらえ方
C 理学療法の実際
D 理学療法士の役割
4 多発性硬化症の理学療法
A 疾患の概要
B 疾患・障害のとらえ方
C 理学療法の実際
D 理学療法に求められるもの
5 Guillain-Barré症候群の理学療法
A 疾患概念
B 亜型
C 診断
D 病態
E 治療
F 理学療法
III 頭部外傷の障害と理学療法
1 頭部外傷の理学療法
A 疾患概念
B 定義と重症度分類
C 形態的分類と画像所見の特徴
D 治療
E 急性期の理学療法
F 回復期の理学療法
G 理学療法に求められるもの
IV 脊髄損傷の障害と理学療法
1 脊髄損傷の病態
A 中枢神経系における脊髄の構造と機能
B 疾患概要
C 脊髄損傷後の運動機能回復のメカニズム
2 不全損傷の理学療法
A 評価から理学療法までの流れ
B 不全損傷者の機能および動作能力評価,予後
C 不全損傷者の理学療法
3 完全損傷の理学療法
A 脊髄損傷の診断と評価
B 脊髄損傷完全麻痺者の理学療法
C 脊髄損傷後の機能予後
索引
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。
更新情報
-
正誤表を掲載しました。
2024.05.20