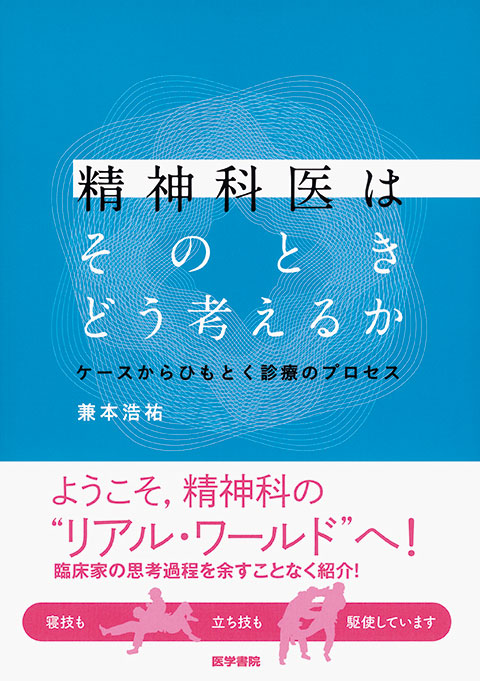精神科医はそのときどう考えるか
ケースからひもとく診療のプロセス
これぞ精神科のリアル・ワールド!
もっと見る
豊富な症例提示を通して精神科医が身につけるべき思考プロセスや臨床上の着眼点について解説するとともに、精神医療・精神医学に関する著者のフィロソフィーをふんだんに盛り込んだ1冊。精神科全般に精通する臨床家として有名な著者の、長年の臨床経験を凝縮したライフワーク的な内容は、精神医学の初学者からベテランまで、どのレベルの読者が読んでも得るものがあるだろう。
| 著 | 兼本 浩祐 |
|---|---|
| 発行 | 2018年06月判型:A5頁:182 |
| ISBN | 978-4-260-03612-2 |
| 定価 | 3,740円 (本体3,400円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
はじめに
総合病院で働いていて他科のお医者さんから言われることを聞いていると,精神科医の業務は誤解されているのではないかと思うことが時々あります。「他科と比べて楽である」「誰でも訓練なくできる」「悩みを延々と聞いていると具合が悪くならないか」「精神科医は冷たい」など,直接言われることもあれば,間接的に人伝えにそんな疑問が伝わってくることもあります。実際には精神科医は体を診る普通のお医者さんと同じ業務を行うところもあれば,少し違うところもあって,精神科医自身が修養の過程で自分は本当にプロフェッショナルとして世に立っていると言っていいのだろうかと少なからず自問自答する時期があるのですが,それでもやはり他科と同じように先輩から薫陶を受け,一定の訓練を経なければ一人前になれないプロフェッショナルな職業の1つだと,私は今では思っています。本書は,精神科医はどのようなことをする職業なのかを,そのリアル・ワールドに近い形で,医学生の皆さんや研修医の方々,身体科の先生,それから精神科をこれから利用しようかと考えていらっしゃる精神科ユーザーの方に紹介したいという動機から書きました。基本的には標準的な精神科医がどんな場面でどのように感じて仕事をしているかを思い浮かべていただけるようにと考えて書いてみたのですが,精神科医の仕事は現場によって大きく変わるところもあり,リアル・ワールドであるがゆえに,どうしても自身の臨床現場(私であれば総合病院の有床精神科)から生まれた「私の」リアル・ワールドになってしまった感は否めません。確かに,オープンダイアローグの実践などを考えるともう少ししたら随分と違った臨床の形が出てくるようにも思いますし,時代やところを鋭敏に反映して大きく姿を変えるという点も精神科の特性であるようにも思うので,「標準的精神科医は…」という表現を何度か本書では用いていますが,総合病院で働いているというバイアスがかかっていて,かなり純精神科医というよりは精神神経科医的なものの見方になっている側面があると読み返してみると感じます。しかし,それでも,今の時点では,決して進歩的ではないとはいえ,際立って時代錯誤的でもない精神科医の一般的な実臨床をある程度は反映した本になったのではないかと考えています。
それから,ここで紹介している事例は実際の体験をモデルにはしましたが,そのままそうした事例があったわけではなく,断りのない限りいくつかの典型的な事例のエッセンスを抜き出した紹介のためのフィクションに近いと考えていただくと良いかと思います。また本書はほぼ全体を書き下ろしたものですが,『精神病理と脳―心因・内因・外因:Schneiderの太線を我々はかくもナイーブに飛び越えて良いのか』(臨床精神病理 34:207-214, 2013)『一般精神科医はどのような事例にどの認知行動療法を適用すればよいか―他の様々の精神療法との比較も踏まえて』(精神科治療学 32:853-862, 2017)の2つの論文の一部を本書の中に取り込んであります。
本書は愛知医科大学病院精神神経科で毎週行っている医局でのケース検討会,月1回行っている臨床心理士の先生達とのケース検討会,同じく月1回行っているてんかんのケース検討会をその主な発想源としています。精神科医にとってのケース検討会は,診断や治療に関して様々の知恵を寄せ合うという通常のケース検討会の役割だけでなく,1人では背負い難いケースの責任を全員で背負うこと(たとえば摂食障害の面会制限や難しいケースでの強制的治療の可否など)やケースが精神科ユーザーと主治医の私的な関係にならないように公の検討をそれに加えるといった特殊な機能を併せ持っていると考えています。本書は愛知医科大学でのケース検討を抜きにしては存在しえなかったことは間違いなく,ケース検討会でともに議論していただいた諸先生に深く感謝致します。
またちょうど21世紀の変わり目から現在まで,6,725人の方を愛知医科大学で初診させていただきましたが,シュライバーについていただいていた若い先生達と外来の看護師さん,ベテランの受付の方の手助けがなければ筆者の診療は全くできなかったことは間違いなく,それらすべての人とともに,この間を過ごした精神科ユーザーの方々に本書を通じて深く感謝したいと考えています。
2018年4月
長久手にて 兼本浩祐
総合病院で働いていて他科のお医者さんから言われることを聞いていると,精神科医の業務は誤解されているのではないかと思うことが時々あります。「他科と比べて楽である」「誰でも訓練なくできる」「悩みを延々と聞いていると具合が悪くならないか」「精神科医は冷たい」など,直接言われることもあれば,間接的に人伝えにそんな疑問が伝わってくることもあります。実際には精神科医は体を診る普通のお医者さんと同じ業務を行うところもあれば,少し違うところもあって,精神科医自身が修養の過程で自分は本当にプロフェッショナルとして世に立っていると言っていいのだろうかと少なからず自問自答する時期があるのですが,それでもやはり他科と同じように先輩から薫陶を受け,一定の訓練を経なければ一人前になれないプロフェッショナルな職業の1つだと,私は今では思っています。本書は,精神科医はどのようなことをする職業なのかを,そのリアル・ワールドに近い形で,医学生の皆さんや研修医の方々,身体科の先生,それから精神科をこれから利用しようかと考えていらっしゃる精神科ユーザーの方に紹介したいという動機から書きました。基本的には標準的な精神科医がどんな場面でどのように感じて仕事をしているかを思い浮かべていただけるようにと考えて書いてみたのですが,精神科医の仕事は現場によって大きく変わるところもあり,リアル・ワールドであるがゆえに,どうしても自身の臨床現場(私であれば総合病院の有床精神科)から生まれた「私の」リアル・ワールドになってしまった感は否めません。確かに,オープンダイアローグの実践などを考えるともう少ししたら随分と違った臨床の形が出てくるようにも思いますし,時代やところを鋭敏に反映して大きく姿を変えるという点も精神科の特性であるようにも思うので,「標準的精神科医は…」という表現を何度か本書では用いていますが,総合病院で働いているというバイアスがかかっていて,かなり純精神科医というよりは精神神経科医的なものの見方になっている側面があると読み返してみると感じます。しかし,それでも,今の時点では,決して進歩的ではないとはいえ,際立って時代錯誤的でもない精神科医の一般的な実臨床をある程度は反映した本になったのではないかと考えています。
それから,ここで紹介している事例は実際の体験をモデルにはしましたが,そのままそうした事例があったわけではなく,断りのない限りいくつかの典型的な事例のエッセンスを抜き出した紹介のためのフィクションに近いと考えていただくと良いかと思います。また本書はほぼ全体を書き下ろしたものですが,『精神病理と脳―心因・内因・外因:Schneiderの太線を我々はかくもナイーブに飛び越えて良いのか』(臨床精神病理 34:207-214, 2013)『一般精神科医はどのような事例にどの認知行動療法を適用すればよいか―他の様々の精神療法との比較も踏まえて』(精神科治療学 32:853-862, 2017)の2つの論文の一部を本書の中に取り込んであります。
本書は愛知医科大学病院精神神経科で毎週行っている医局でのケース検討会,月1回行っている臨床心理士の先生達とのケース検討会,同じく月1回行っているてんかんのケース検討会をその主な発想源としています。精神科医にとってのケース検討会は,診断や治療に関して様々の知恵を寄せ合うという通常のケース検討会の役割だけでなく,1人では背負い難いケースの責任を全員で背負うこと(たとえば摂食障害の面会制限や難しいケースでの強制的治療の可否など)やケースが精神科ユーザーと主治医の私的な関係にならないように公の検討をそれに加えるといった特殊な機能を併せ持っていると考えています。本書は愛知医科大学でのケース検討を抜きにしては存在しえなかったことは間違いなく,ケース検討会でともに議論していただいた諸先生に深く感謝致します。
またちょうど21世紀の変わり目から現在まで,6,725人の方を愛知医科大学で初診させていただきましたが,シュライバーについていただいていた若い先生達と外来の看護師さん,ベテランの受付の方の手助けがなければ筆者の診療は全くできなかったことは間違いなく,それらすべての人とともに,この間を過ごした精神科ユーザーの方々に本書を通じて深く感謝したいと考えています。
2018年4月
長久手にて 兼本浩祐
目次
開く
第1章 心と脳の境界線を引く
1つの初診例からまず考えてみる
脳との距離感から心の問題を3つの階層に分ける
鑑別診断と類型診断
心因性の疾患は「診断」が可能か
第2章 「主訴」を探る,「主訴」を決める
治療者とユーザーの「主訴」がずれる場合
本当の主訴がまずは否認される場合
精神科という奇妙なお店
共同作業の中で「主訴」を形にする
第3章 枠組みをつくる,距離をとる
どのくらい来てもらい,どのくらい話してもらうか
どんな時にそれ以上の通院を断るか
受け入れに精神科特有の覚悟が必要となる場合―身体合併症
受け入れに精神科特有の覚悟が必要となる場合―暴力
第4章 人権を制限する
精神科医にとって心理的負担になる強制治療とそうでない強制治療
精神科医が強制治療に前のめりになる事例
電気けいれん療法
精神科医が強制治療に二の足を踏む事例
第5章 心を覆う・覆いをとる,浅く診察する・深く診察する
心を覆う手だすけをする
覆いがとれることが避けられなかった事例
事例化のタイミングと臨床心理士さんとの連携
寄り添うということと路傍の石のような精神科医の立ち位置
第6章 精神科医の寝技と立ち技
寝技と立ち技
一歩進んだ立ち技
寝技のルール
心理カウンセリングと認知行動療法
付録 小精神薬理学
1 神経細胞の成り立ちとシナプス
2 神経細胞の電気的興奮の仕組み
3 イオンチャンネルと抗てんかん薬
4 神経伝達物質
5 ドーパミン神経系と抗幻覚妄想薬
5-1 定型薬
5-2 部分アゴニスト
5-3 非定型抗精神病薬
6 抗うつ薬
6-1 選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)
6-2 選択的セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)
6-3 ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)
6-4 三環系抗うつ薬(TCA)
7 抗不安薬
7-1 ベンゾジアゼピン系薬剤
7-2 SSRI
索引
COLUMN
1 摂食障害
2 意識障害を記載する精神科用語
3 解離性障害
4 4大認知症
5 一級症状
6 内因性精神疾患と遺伝子
7 妄想知覚
8 評価尺度
9 双極II型障害
10 精神保健福祉法
11 DSM
12 自閉症スペクトラム障害
13 エビデンス
14 操作的診断
15 認知行動療法
1つの初診例からまず考えてみる
脳との距離感から心の問題を3つの階層に分ける
鑑別診断と類型診断
心因性の疾患は「診断」が可能か
第2章 「主訴」を探る,「主訴」を決める
治療者とユーザーの「主訴」がずれる場合
本当の主訴がまずは否認される場合
精神科という奇妙なお店
共同作業の中で「主訴」を形にする
第3章 枠組みをつくる,距離をとる
どのくらい来てもらい,どのくらい話してもらうか
どんな時にそれ以上の通院を断るか
受け入れに精神科特有の覚悟が必要となる場合―身体合併症
受け入れに精神科特有の覚悟が必要となる場合―暴力
第4章 人権を制限する
精神科医にとって心理的負担になる強制治療とそうでない強制治療
精神科医が強制治療に前のめりになる事例
電気けいれん療法
精神科医が強制治療に二の足を踏む事例
第5章 心を覆う・覆いをとる,浅く診察する・深く診察する
心を覆う手だすけをする
覆いがとれることが避けられなかった事例
事例化のタイミングと臨床心理士さんとの連携
寄り添うということと路傍の石のような精神科医の立ち位置
第6章 精神科医の寝技と立ち技
寝技と立ち技
一歩進んだ立ち技
寝技のルール
心理カウンセリングと認知行動療法
付録 小精神薬理学
1 神経細胞の成り立ちとシナプス
2 神経細胞の電気的興奮の仕組み
3 イオンチャンネルと抗てんかん薬
4 神経伝達物質
5 ドーパミン神経系と抗幻覚妄想薬
5-1 定型薬
5-2 部分アゴニスト
5-3 非定型抗精神病薬
6 抗うつ薬
6-1 選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)
6-2 選択的セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)
6-3 ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)
6-4 三環系抗うつ薬(TCA)
7 抗不安薬
7-1 ベンゾジアゼピン系薬剤
7-2 SSRI
索引
COLUMN
1 摂食障害
2 意識障害を記載する精神科用語
3 解離性障害
4 4大認知症
5 一級症状
6 内因性精神疾患と遺伝子
7 妄想知覚
8 評価尺度
9 双極II型障害
10 精神保健福祉法
11 DSM
12 自閉症スペクトラム障害
13 エビデンス
14 操作的診断
15 認知行動療法
書評
開く
精神科医のレーゾンデートルを問う,卓抜な臨床実践書
書評者: 熊木 徹夫 (あいち熊木クリニック院長)
かつて,兼本浩祐先生の診療を目の当たりにした衝撃を忘れることができない。一体,どのように表現すればそれが伝わるだろうか。少々無理やりではあるが,野球に置き換えてみよう。私は先生から,希代の名手,広島東洋カープの菊池涼介二塁手を思い浮かべる。ともかく尋常ではない広すぎる守備範囲(外因・内因・心因問わず,どのような領域も治療の射程に収めている),どんな時も神業的なグラブさばき(難治,もしくはかかわりの難しい患者さんであっても,的確な治療的アプローチが行える),絶体絶命のヒットコースをリカバーしアウトにしてしまう(ほとんどの精神科医にとりどうしようもない場合でも,何とか結果が出せる)。これを単に天才とするなら,話が早い。しかしずっと,そう単純ではない気がしていた。本書を読み解くことで,今更ながら「ああ,そうだったのか」と気付かされた。以下に,本書の特質を列記する。
◆着眼の独自性・抜きん出た洞察・兼本精神医学体系の説得力
本書のどの細部を取り出しても,ステレオタイプでおざなりな表現は見いだせない。徹底的に考え尽くされ選ばれた表現は,緩い思考を許さないが,頭を絞ればこれまで行き着いたことのない臨床の深みに達せられる。かといって,無意味に晦渋ではぐらかすようなところがない。よくある精神科術語も,先生にかかれば全く新しい意味が付帯され,独特の精神医学体系が立ち上がる。そして,それらはいずれも大変魅力的なものだ。
◆圧倒的な臨床体験の質・量
それぞれの症例が,まるで眼前に立ち現れたかのようなリアリティで迫ってくる。たとえ外因を論じる場合であっても,必ずそこに“人間”が描かれている。これはできそうでいて,なかなかできることではない。これは先生が,どんな状況でも症例を単純化するため要素還元的に思考していないことの証しである。そして,「症例は細部にこそ魂が宿る」という含意があるはずである。
また,32の症例の配置が絶妙である。私は,本書のような症例配置が成されているものを,かつて見たことがない。全く独特なのだが,それぞれが置き換え不可能なまでに,すっぽりそこに嵌っている。私は「この症例を示して,先生は何を言おうとしているのか」予想しながら,読み進めた。驚きの展開の連続。「なるほど,そうくるか」「次はこのような症例が置かれているはず」,しかし,こちらの予想をたびたび裏切り,思いがけない洞察に導かれていく。それはしびれるような知的快楽であった。
見渡すとやはり,先生が獲得されてきた臨床体験の質量のすごさを再確認する結果となった。
◆精神科医の自意識についてのシャープな分析
「精神科臨床には立ち技・寝技※がある」という卓見にはじまり,精神科医の自意識についての洞察,精神科医のレーゾンデートル(存在価値)についての言及など,覚醒した精神科医としての思考が隅々まで浸透している。これは先生が,常々自らに治療的陶酔を許さず,ご自分の来し方を顧みてこられたからに他ならない。これはハリー・スタック・サリヴァンが言うところの「参与観察者としての精神科医」の実践が体現されたものである。
◆後輩精神科医への温かさ・教育者としての熱意
精神科医が抱きがちな思考傾向・示しがちなシンパシィ・陥りがちなディレンマなど,「よくぞここまで」というところまで,理解が示されている。そしてどのような精神科医に対しても,向けられるまなざしが温かい。そしてそれは,精神科医のみならず,研修医・コメディカル,そしてユーザー・家族にまで及んでいる(それゆえ誰が読んでもフレンドリーであり,建設的な治療に結び付く本なのだ,といえる)。
また本書は,「精神科医としての職能をどうやって陶冶してゆくべきか」という提言書とも読み取れ,極めて優れた臨床教育の書である。言うまでもないが,精神科医の職能のための安直なマニュアルは存在せず,伝承自体困難である。それは暗黙知の要素があまりに濃いからである。しかし本書では,その伝承への取り組みが果敢に行われている。そしてそれが,ある理想的なかたちで達成されているように感じる。そう,先生は「名選手のみならず,名コーチ・名監督」なのだ。本書は初学者のみに役立つのではない。ベテランにもお薦めできる。読み手のレベルに応じて,開ける景色が変わり,獲得できる臨床スキルが変遷していく,そのような本だからだ。
最後に,本書から抜粋しておきたい。これらは,精神科医の自意識・立ち居振る舞いについてのほんの一部である。これだけ見ても,直線的記載ではなく,複層的記載であることがわかるであろう。本書には,心理や技の綾に触れた,このような魅力的表現が横溢している。
例えば,治療契約というものが医療者の保身のため体良く持ち出されることが多い現状に対し,「枠組み作りの際に,なぜ目の前のユーザーを今手助けできないのかをそれぞれのユーザーと一緒に虚心坦懐に考えるのが,本来の意味の治療契約(p.63)」と本道を示されるものの,「治療契約という防衛線を張り巡らすことを忘れて,この戦闘を開始した医療者側は,自身の陣営がどこまで後退してもさらに攻撃され続け破壊される恐怖におののくことになりますから,しばしば医療者側はこの防衛線を頑なに守ろうとしてしまいます(p.67)」と医療者が抱きがちな心情に一定の理解を示される。
また,「面接空間の中ではお互いのナルシシズムを傷つけあうのを厭わずに対峙する,つまりはお互いの身の安全を確保したうえで触れ合うためのスタジアムを作るのが,治療のための枠組み作りの本来の趣旨でしょう(p.142)」とともすれば空疎かつ形骸化したものになりがちな治療の枠組み作りの本来の在り方を想起させようとされ,「自分に一瞬たりとも触れさせないことが(つまり立ち技にどうしても留まる[中略]ことが)自己目的化しないように注意が必要ではないか(p.142)」と自ら泥にまみれようとしない医療者の姿勢に疑問を投げかけられる。
さらには,「愛を少しでも処方すると無限の愛を要求されるという恐怖が精神科医の側には確かにあって,そのために絶対に寝技の関係にはなるまいという硬直した姿勢にそうした恐怖はつながる(p.143)」と,寝技を忌避しようとする医療者の自意識の在り方を指摘される一方で,「自ら進んで気負って寝技に突入する場合,何らかの個人的な欲望がそこには介在していないかどうかの自己モニターが必要となるかもしれません。救世主願望などもそこには含まれているかもしれませんし,自分の力量を試したいといった気持ちもあるかもしれません(p.140)」と,真逆に寝技に持ち込もうとする医療者の陶酔をも適確に指摘されるという具合だ。
※立ち技…タクシー運転手のように,技術的職能を果たすこと,寝技…学校教諭のように,個人的なつながりを前提として機能すること
現代精神医学の知性が語る臨床論
書評者: 井原 裕 (獨協医大埼玉医療センターこころの診療科・診療部長)
「精神科医の業務は誤解されているのではないか」,そう著者は問う。それもまた無理もない。精神科医の業務は,「時代やところを鋭敏に反映して大きく姿を変える」(p.iii)からである。そのような不定形性が際立つのが,総合病院精神科である。
著者は,総合病院精神科をフィールドとして,不定形な業務の中に筋を通そうとしている。そこには,精神科医でなければ行えない重大な判断がある。「心と脳の境界線を引く」(p.1)ことである。精神医学の用語を使えば,「心因」と「外因」といってもいいが,著者はあえて,「愛の問題」と「脳の問題」(p.17)という表現を用いている。それは,単なる病因の鑑別に留まらない,倫理的問題でもある。自己決定権vsパターナリズムという二項対立である。一般には,自己決定権を有する人格として一人の患者を見るところに医療倫理の原点がある。ところが,外因性疾患の場合,脳の損傷次第では「当事者能力」(p.2, 81)が損なわれる。そのような場合は,自己決定権の過ぎた尊重は,なお及ばざるがごとしである。本人にとって不利益どころか,自殺という最悪の結果すらもたらし得る。かといって,医療側の惻隠の情も,行き過ぎれば悪しきパターナリズムに傾く。その判断は,しばしば極めて難しい。
本書では,このジレンマを摂食障害(事例1),てんかん発作後もうろう状態(事例2),抗NMDA受容体脳炎(事例4),抗VGKC抗体陽性脳炎(事例7),うつ病挿話後に発症した統合失調症(事例8)など,判断の迷う例を引用して,説明している。
著者は碩学であると同時に詩人でもあり,内容は難しいが言葉は選び抜かれている。例えば,「内因性」という錯綜した概念を,次のようにまとめている。「脳が構造としては大きな変化を起こさずにとりあえずは一過性のモード・チェンジをきたしている」(p.18)と。かつて三島由紀夫は,森鴎外の文体を評して,「非常におしゃれな人が,非常に贅沢な着物をいかにも無造作に着こなして,そのおしゃれを人に見せない」と述べた。著者の場合も,難解な概念を見事なほど明快に言い換えている。実はそれは無造作を装った高度の技巧なのだが,そのさりげなさに潜む美意識こそが文体の魅力をなしている。
本書の内容は,高度である。しかし,「治療者とユーザーの『主訴』がずれる場合」(p.37)とは,治療契約の相互欺瞞のことであり,「枠組みをつくる,距離をとる」(p.57)とは,治療構造論であろう。「心を覆う・覆いをとる,浅く診察する・深く診察する」(p.99)は,「ストーリを読む」(土居健郎)か「猥雑性を避ける」(笠原嘉)かの二項対立である。第6章の「精神科医の寝技と立ち技」とは,転移・逆転移にかかわる事項であろう。こう考えると,現代精神医学を代表する知性が本書で語った事柄は,実は臨床の古典的な課題なのであった。
書評者: 熊木 徹夫 (あいち熊木クリニック院長)
かつて,兼本浩祐先生の診療を目の当たりにした衝撃を忘れることができない。一体,どのように表現すればそれが伝わるだろうか。少々無理やりではあるが,野球に置き換えてみよう。私は先生から,希代の名手,広島東洋カープの菊池涼介二塁手を思い浮かべる。ともかく尋常ではない広すぎる守備範囲(外因・内因・心因問わず,どのような領域も治療の射程に収めている),どんな時も神業的なグラブさばき(難治,もしくはかかわりの難しい患者さんであっても,的確な治療的アプローチが行える),絶体絶命のヒットコースをリカバーしアウトにしてしまう(ほとんどの精神科医にとりどうしようもない場合でも,何とか結果が出せる)。これを単に天才とするなら,話が早い。しかしずっと,そう単純ではない気がしていた。本書を読み解くことで,今更ながら「ああ,そうだったのか」と気付かされた。以下に,本書の特質を列記する。
◆着眼の独自性・抜きん出た洞察・兼本精神医学体系の説得力
本書のどの細部を取り出しても,ステレオタイプでおざなりな表現は見いだせない。徹底的に考え尽くされ選ばれた表現は,緩い思考を許さないが,頭を絞ればこれまで行き着いたことのない臨床の深みに達せられる。かといって,無意味に晦渋ではぐらかすようなところがない。よくある精神科術語も,先生にかかれば全く新しい意味が付帯され,独特の精神医学体系が立ち上がる。そして,それらはいずれも大変魅力的なものだ。
◆圧倒的な臨床体験の質・量
それぞれの症例が,まるで眼前に立ち現れたかのようなリアリティで迫ってくる。たとえ外因を論じる場合であっても,必ずそこに“人間”が描かれている。これはできそうでいて,なかなかできることではない。これは先生が,どんな状況でも症例を単純化するため要素還元的に思考していないことの証しである。そして,「症例は細部にこそ魂が宿る」という含意があるはずである。
また,32の症例の配置が絶妙である。私は,本書のような症例配置が成されているものを,かつて見たことがない。全く独特なのだが,それぞれが置き換え不可能なまでに,すっぽりそこに嵌っている。私は「この症例を示して,先生は何を言おうとしているのか」予想しながら,読み進めた。驚きの展開の連続。「なるほど,そうくるか」「次はこのような症例が置かれているはず」,しかし,こちらの予想をたびたび裏切り,思いがけない洞察に導かれていく。それはしびれるような知的快楽であった。
見渡すとやはり,先生が獲得されてきた臨床体験の質量のすごさを再確認する結果となった。
◆精神科医の自意識についてのシャープな分析
「精神科臨床には立ち技・寝技※がある」という卓見にはじまり,精神科医の自意識についての洞察,精神科医のレーゾンデートル(存在価値)についての言及など,覚醒した精神科医としての思考が隅々まで浸透している。これは先生が,常々自らに治療的陶酔を許さず,ご自分の来し方を顧みてこられたからに他ならない。これはハリー・スタック・サリヴァンが言うところの「参与観察者としての精神科医」の実践が体現されたものである。
◆後輩精神科医への温かさ・教育者としての熱意
精神科医が抱きがちな思考傾向・示しがちなシンパシィ・陥りがちなディレンマなど,「よくぞここまで」というところまで,理解が示されている。そしてどのような精神科医に対しても,向けられるまなざしが温かい。そしてそれは,精神科医のみならず,研修医・コメディカル,そしてユーザー・家族にまで及んでいる(それゆえ誰が読んでもフレンドリーであり,建設的な治療に結び付く本なのだ,といえる)。
また本書は,「精神科医としての職能をどうやって陶冶してゆくべきか」という提言書とも読み取れ,極めて優れた臨床教育の書である。言うまでもないが,精神科医の職能のための安直なマニュアルは存在せず,伝承自体困難である。それは暗黙知の要素があまりに濃いからである。しかし本書では,その伝承への取り組みが果敢に行われている。そしてそれが,ある理想的なかたちで達成されているように感じる。そう,先生は「名選手のみならず,名コーチ・名監督」なのだ。本書は初学者のみに役立つのではない。ベテランにもお薦めできる。読み手のレベルに応じて,開ける景色が変わり,獲得できる臨床スキルが変遷していく,そのような本だからだ。
最後に,本書から抜粋しておきたい。これらは,精神科医の自意識・立ち居振る舞いについてのほんの一部である。これだけ見ても,直線的記載ではなく,複層的記載であることがわかるであろう。本書には,心理や技の綾に触れた,このような魅力的表現が横溢している。
例えば,治療契約というものが医療者の保身のため体良く持ち出されることが多い現状に対し,「枠組み作りの際に,なぜ目の前のユーザーを今手助けできないのかをそれぞれのユーザーと一緒に虚心坦懐に考えるのが,本来の意味の治療契約(p.63)」と本道を示されるものの,「治療契約という防衛線を張り巡らすことを忘れて,この戦闘を開始した医療者側は,自身の陣営がどこまで後退してもさらに攻撃され続け破壊される恐怖におののくことになりますから,しばしば医療者側はこの防衛線を頑なに守ろうとしてしまいます(p.67)」と医療者が抱きがちな心情に一定の理解を示される。
また,「面接空間の中ではお互いのナルシシズムを傷つけあうのを厭わずに対峙する,つまりはお互いの身の安全を確保したうえで触れ合うためのスタジアムを作るのが,治療のための枠組み作りの本来の趣旨でしょう(p.142)」とともすれば空疎かつ形骸化したものになりがちな治療の枠組み作りの本来の在り方を想起させようとされ,「自分に一瞬たりとも触れさせないことが(つまり立ち技にどうしても留まる[中略]ことが)自己目的化しないように注意が必要ではないか(p.142)」と自ら泥にまみれようとしない医療者の姿勢に疑問を投げかけられる。
さらには,「愛を少しでも処方すると無限の愛を要求されるという恐怖が精神科医の側には確かにあって,そのために絶対に寝技の関係にはなるまいという硬直した姿勢にそうした恐怖はつながる(p.143)」と,寝技を忌避しようとする医療者の自意識の在り方を指摘される一方で,「自ら進んで気負って寝技に突入する場合,何らかの個人的な欲望がそこには介在していないかどうかの自己モニターが必要となるかもしれません。救世主願望などもそこには含まれているかもしれませんし,自分の力量を試したいといった気持ちもあるかもしれません(p.140)」と,真逆に寝技に持ち込もうとする医療者の陶酔をも適確に指摘されるという具合だ。
※立ち技…タクシー運転手のように,技術的職能を果たすこと,寝技…学校教諭のように,個人的なつながりを前提として機能すること
現代精神医学の知性が語る臨床論
書評者: 井原 裕 (獨協医大埼玉医療センターこころの診療科・診療部長)
「精神科医の業務は誤解されているのではないか」,そう著者は問う。それもまた無理もない。精神科医の業務は,「時代やところを鋭敏に反映して大きく姿を変える」(p.iii)からである。そのような不定形性が際立つのが,総合病院精神科である。
著者は,総合病院精神科をフィールドとして,不定形な業務の中に筋を通そうとしている。そこには,精神科医でなければ行えない重大な判断がある。「心と脳の境界線を引く」(p.1)ことである。精神医学の用語を使えば,「心因」と「外因」といってもいいが,著者はあえて,「愛の問題」と「脳の問題」(p.17)という表現を用いている。それは,単なる病因の鑑別に留まらない,倫理的問題でもある。自己決定権vsパターナリズムという二項対立である。一般には,自己決定権を有する人格として一人の患者を見るところに医療倫理の原点がある。ところが,外因性疾患の場合,脳の損傷次第では「当事者能力」(p.2, 81)が損なわれる。そのような場合は,自己決定権の過ぎた尊重は,なお及ばざるがごとしである。本人にとって不利益どころか,自殺という最悪の結果すらもたらし得る。かといって,医療側の惻隠の情も,行き過ぎれば悪しきパターナリズムに傾く。その判断は,しばしば極めて難しい。
本書では,このジレンマを摂食障害(事例1),てんかん発作後もうろう状態(事例2),抗NMDA受容体脳炎(事例4),抗VGKC抗体陽性脳炎(事例7),うつ病挿話後に発症した統合失調症(事例8)など,判断の迷う例を引用して,説明している。
著者は碩学であると同時に詩人でもあり,内容は難しいが言葉は選び抜かれている。例えば,「内因性」という錯綜した概念を,次のようにまとめている。「脳が構造としては大きな変化を起こさずにとりあえずは一過性のモード・チェンジをきたしている」(p.18)と。かつて三島由紀夫は,森鴎外の文体を評して,「非常におしゃれな人が,非常に贅沢な着物をいかにも無造作に着こなして,そのおしゃれを人に見せない」と述べた。著者の場合も,難解な概念を見事なほど明快に言い換えている。実はそれは無造作を装った高度の技巧なのだが,そのさりげなさに潜む美意識こそが文体の魅力をなしている。
本書の内容は,高度である。しかし,「治療者とユーザーの『主訴』がずれる場合」(p.37)とは,治療契約の相互欺瞞のことであり,「枠組みをつくる,距離をとる」(p.57)とは,治療構造論であろう。「心を覆う・覆いをとる,浅く診察する・深く診察する」(p.99)は,「ストーリを読む」(土居健郎)か「猥雑性を避ける」(笠原嘉)かの二項対立である。第6章の「精神科医の寝技と立ち技」とは,転移・逆転移にかかわる事項であろう。こう考えると,現代精神医学を代表する知性が本書で語った事柄は,実は臨床の古典的な課題なのであった。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。