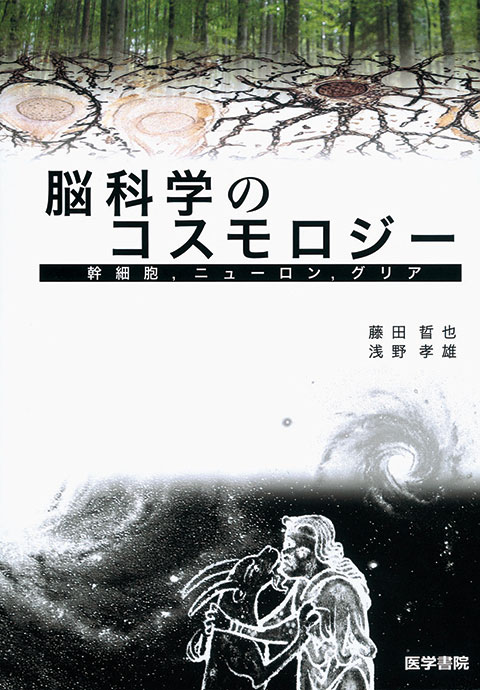脳科学のコスモロジー
幹細胞,ニューロン,グリア
新しいグリア学への手引き
もっと見る
ニューロンとともに脳活動を支えるグリアに関する入門書。アストロサイトを中心に、その形態と機能に関する最新の知見を紹介しつつ、神経疾患の病態生理から治療までをコンパクトにまとめた。グリアの時代を象徴する1冊。
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序 幹細胞,ニューロン,グリアからみた脳科学
神経科学における機能と形態の研究はこれまでニューロンに関するものにほとんどの関心が集まり,ニューロン以外の細胞,特に幹細胞やグリアの役割について,教科書の中では,きわめて軽く扱われてきた。しかし,幹細胞やグリア細胞には,ニューロンの学と同等あるいは,それを上回る充分な配慮をした脳科学が必要であると思われる。
わが国では1971年ごろから新潟の中田瑞穂193)が Neuro-Gliology の重要性を力説していた。しかし,現在では,この思想をさらに拡大し,“幹細胞とニューロンとグリアの脳科学”の見地が重要であると思う。この立場に立つことで,初めて,脳の機能と形態を根本的に理解でき,また理論的脳科学や,その応用学ともいうべき治療学の将来とるべき方向を真に見通せるようになると著者らは考える。
ニューロンとグリアの発生を考えても両者は,単一の胚性幹細胞であるマトリックス細胞から順に分化してくる兄・妹のような細胞であることが明らかになってきた。両者の分化が,このような意味で場所的にも相関するものを持ち,機能的にも緊密に関連したものであるのは当然と考えられる。にもかかわらず,最近まで,このような考え方は意識的にも無意識的にも無視ないし軽視される潮流が脳科学を支配していた。その間に,神経幹細胞の存在とその重要な意義が認識されるようになり,他方では,グリア細胞を構成するアストロサイト・オリゴデンドロサイト・ミクログリアの新しい機能が続々と発見されている。これらの新しい概念に十分な配慮をしながら,“幹細胞とニューロンとグリアの脳科学”を,それにふさわしい見方で再認識し,本書の中で,統一性のある新しい脳科学の提案を行いたい。
本書の第I部では,脳を構成する細胞の形態や機能を,幹細胞からのニューロンとグリア発生研究の歴史を踏まえながら,三種のグリアの発生と分化,ニューロンとグリアの関係,それらと幹細胞との関係について,十分な考慮を払いつつ明らかにする。
脳という組織の空間の中では,グリア細胞は全体としてニューロンとほぼ同じくらいの体積を占め,その数はニューロンの10倍にも達する。特にアストロサイトは,脳内微小血管とニューロンとの間に介在し,物質交換・代謝や脳内イオン環境の調節に重要な役割を果たすことが古くから知られていたが,かれらは,ニューロンのようにスパイクを発射したり,それを伝達することがないので,脳内における情報処理に直接関与するものとは見なされず,主役であるニューロンの「物言わぬ脇役」としての地位しか認められていなかった。このような認識は,急速に変ってきた。1980年代から90年代にかけて,アストロサイトには多種類のレセプターチャンネルが存在すること,それらが物理的・化学的刺激を受けることによって細胞内カルシウム濃度が急激に上昇し,その波がゆっくりと周囲に伝播することが発見・報告されるようになってきたのである。ニューロンのナトリウムイオンによるシグナル伝達とは違って,アストロサイトの活性化は,細胞内セカンド・メッセンジャーであるカルシウム・イオンの濃度上昇によって,細胞内シグナル伝達機構が全体的・部分的に賦活され,その結果,多種多様な細胞反応が生じることを意味する。活性化アストロサイトがサイトカインや,モノアミンをはじめとするさまざまな神経伝達物質を産生・放出し,かつそれらに対する受容体を有すること,またアストロサイトの無数のラメラやフィロポデイアと呼ばれる小さな突起がほとんどすべてのシナプスを包み込んでおり,そこでアストロサイトとニューロンのクロストークが営まれていることが次第に明らかとなってきた。
シェリントン以来,シナプスはニューロンの突起同士が接合する構造(bipartite synapse)と考えられてきたが,現在では,シナプスはそれらにアストロサイトの突起を加えた3つの部分から構成されるという意味で,トリパータイト・シナプス(tripartite synapse)と呼ばれている。アストロサイトは,シナプス間隙から外部に漏れ出した神経伝達物質によって活性化され,多様な物質の放出を介して逆にシナプスに作用し,その新生・破壊・伝達効率の変化・可塑性など,数々の重要な変化を引き起こす。つまりアストロサイト(他のグリア細胞も部分的に共通する働きを有する)は,トリパータイト・シナプスを介してニューロンと相互的に作用し合うことが確立されたのである。換言すれば,アストロサイトを中心とするグリア細胞は,主にそのシナプスに対する作用を介して,高次脳機能を含むニューラル・ネットワークの働きに直接的な影響を及ぼすことが明らかとなった。しかも,この刺激応答反応はアナログでかつ寛徐に変化する,というニューロンにない特性を持つ。これは脳の高次機能において重要な役割を果たす。この認識に基づく新しいグリア学は,脳科学の伝統であるニューロン・ドクトリンに対する挑戦として始まったが,それは今や大きな広がりを持つ「脳科学の革命」として,急速に発展しつつある。
本書第II部では,多種多様なグリア細胞の内で特にアストロサイトに焦点を当て,その脳内物質代謝,脳微小循環調節,血液脳関門,シナプスの新生・伝達効率・可塑性,脳の病態(脳梗塞とアルツハイマー病)における役割などについて解説する。本書が,幸いにして読者の興味を喚起することができ,新しいグリア学への,時宜を得た手引きとして広く利用されることを祈っている。
2009年 2月
藤田晢也・浅野孝雄
文献
193.中田瑞穂:Glio-Neurology 新潟医誌 85:667-668,1971
神経科学における機能と形態の研究はこれまでニューロンに関するものにほとんどの関心が集まり,ニューロン以外の細胞,特に幹細胞やグリアの役割について,教科書の中では,きわめて軽く扱われてきた。しかし,幹細胞やグリア細胞には,ニューロンの学と同等あるいは,それを上回る充分な配慮をした脳科学が必要であると思われる。
わが国では1971年ごろから新潟の中田瑞穂193)が Neuro-Gliology の重要性を力説していた。しかし,現在では,この思想をさらに拡大し,“幹細胞とニューロンとグリアの脳科学”の見地が重要であると思う。この立場に立つことで,初めて,脳の機能と形態を根本的に理解でき,また理論的脳科学や,その応用学ともいうべき治療学の将来とるべき方向を真に見通せるようになると著者らは考える。
ニューロンとグリアの発生を考えても両者は,単一の胚性幹細胞であるマトリックス細胞から順に分化してくる兄・妹のような細胞であることが明らかになってきた。両者の分化が,このような意味で場所的にも相関するものを持ち,機能的にも緊密に関連したものであるのは当然と考えられる。にもかかわらず,最近まで,このような考え方は意識的にも無意識的にも無視ないし軽視される潮流が脳科学を支配していた。その間に,神経幹細胞の存在とその重要な意義が認識されるようになり,他方では,グリア細胞を構成するアストロサイト・オリゴデンドロサイト・ミクログリアの新しい機能が続々と発見されている。これらの新しい概念に十分な配慮をしながら,“幹細胞とニューロンとグリアの脳科学”を,それにふさわしい見方で再認識し,本書の中で,統一性のある新しい脳科学の提案を行いたい。
本書の第I部では,脳を構成する細胞の形態や機能を,幹細胞からのニューロンとグリア発生研究の歴史を踏まえながら,三種のグリアの発生と分化,ニューロンとグリアの関係,それらと幹細胞との関係について,十分な考慮を払いつつ明らかにする。
脳という組織の空間の中では,グリア細胞は全体としてニューロンとほぼ同じくらいの体積を占め,その数はニューロンの10倍にも達する。特にアストロサイトは,脳内微小血管とニューロンとの間に介在し,物質交換・代謝や脳内イオン環境の調節に重要な役割を果たすことが古くから知られていたが,かれらは,ニューロンのようにスパイクを発射したり,それを伝達することがないので,脳内における情報処理に直接関与するものとは見なされず,主役であるニューロンの「物言わぬ脇役」としての地位しか認められていなかった。このような認識は,急速に変ってきた。1980年代から90年代にかけて,アストロサイトには多種類のレセプターチャンネルが存在すること,それらが物理的・化学的刺激を受けることによって細胞内カルシウム濃度が急激に上昇し,その波がゆっくりと周囲に伝播することが発見・報告されるようになってきたのである。ニューロンのナトリウムイオンによるシグナル伝達とは違って,アストロサイトの活性化は,細胞内セカンド・メッセンジャーであるカルシウム・イオンの濃度上昇によって,細胞内シグナル伝達機構が全体的・部分的に賦活され,その結果,多種多様な細胞反応が生じることを意味する。活性化アストロサイトがサイトカインや,モノアミンをはじめとするさまざまな神経伝達物質を産生・放出し,かつそれらに対する受容体を有すること,またアストロサイトの無数のラメラやフィロポデイアと呼ばれる小さな突起がほとんどすべてのシナプスを包み込んでおり,そこでアストロサイトとニューロンのクロストークが営まれていることが次第に明らかとなってきた。
シェリントン以来,シナプスはニューロンの突起同士が接合する構造(bipartite synapse)と考えられてきたが,現在では,シナプスはそれらにアストロサイトの突起を加えた3つの部分から構成されるという意味で,トリパータイト・シナプス(tripartite synapse)と呼ばれている。アストロサイトは,シナプス間隙から外部に漏れ出した神経伝達物質によって活性化され,多様な物質の放出を介して逆にシナプスに作用し,その新生・破壊・伝達効率の変化・可塑性など,数々の重要な変化を引き起こす。つまりアストロサイト(他のグリア細胞も部分的に共通する働きを有する)は,トリパータイト・シナプスを介してニューロンと相互的に作用し合うことが確立されたのである。換言すれば,アストロサイトを中心とするグリア細胞は,主にそのシナプスに対する作用を介して,高次脳機能を含むニューラル・ネットワークの働きに直接的な影響を及ぼすことが明らかとなった。しかも,この刺激応答反応はアナログでかつ寛徐に変化する,というニューロンにない特性を持つ。これは脳の高次機能において重要な役割を果たす。この認識に基づく新しいグリア学は,脳科学の伝統であるニューロン・ドクトリンに対する挑戦として始まったが,それは今や大きな広がりを持つ「脳科学の革命」として,急速に発展しつつある。
本書第II部では,多種多様なグリア細胞の内で特にアストロサイトに焦点を当て,その脳内物質代謝,脳微小循環調節,血液脳関門,シナプスの新生・伝達効率・可塑性,脳の病態(脳梗塞とアルツハイマー病)における役割などについて解説する。本書が,幸いにして読者の興味を喚起することができ,新しいグリア学への,時宜を得た手引きとして広く利用されることを祈っている。
2009年 2月
藤田晢也・浅野孝雄
文献
193.中田瑞穂:Glio-Neurology 新潟医誌 85:667-668,1971
目次
開く
序 幹細胞,ニューロン,グリアからみた脳科学
I.神経幹細胞からみた脳の発生学
1.中枢神経系細胞発生学の歴史的展開
2.中枢神経系発生の第I期
3.神経細胞が発生する第II期
4.グリア細胞の分化をめぐる論争
5.グリア細胞が発生する第III期
6.アストロサイトとオリゴデンドロサイトの発生と分化
7.ミクログリアという脳組織防衛システム
8.ゲノムからみたニューロンとグリア細胞分化のメカニズム
9.マトリックス細胞の増殖・分化と脳の形
10.脳室下層
11.グリア細胞の機能の歴史的展望
II.グリアル・ネットワークとニューラル・ネットワーク
1.正常脳におけるグリアル・ネットワークの働き
A.グリアル・ネットワーク
B.脳内環境の維持・物質代謝とアストロサイト
C.脳微小循環とアストロサイト
2.脳病態におけるグリア細胞の役割
A.地球上における酸素の発生と生物の進化
B.脳虚血におけるグリア細胞の役割
C.アルツハイマー病におけるグリア細胞の役割
D.グリア細胞とハムレット
III.ニューラル・ネットワークとグリアル・ネットワーク
1.ニューラル・ネットワーク
A.ニューロンとシナプスの基本的な形態と機能
B.ナトリウム・ポンプ
C.神経回路の形成
D.「ヘッブの原理」とシナプスの可塑性
E.ニューラル・ネットワークのモデル
2.大脳皮質機能の局在と統合
A.大脳皮質の機能局在
B.知覚から認知へ
3.記憶のメカニズム
A.記憶の定義と分類
B.記憶と辺縁系
C.記憶・学習の機序
4.言葉と文字
A.Broca野とWernicke野
B.ミラーニューロン
C.他者の理解-感情移入
5.トップダウン処理
A.作業記憶
B.作業記憶と前頭前野
C.想像力と探索行動
6.情動と動機づけ
A.情動についての諸理論
B.高位系路と低位系路
C.意思決定のシステム
7.ニューロンとグリア細胞の相互作用
A.アストロサイトとシナプス可塑性
B.アストロサイトと脳高次機能
C.精神現象へのグリア細胞の関与
索引
I.神経幹細胞からみた脳の発生学
1.中枢神経系細胞発生学の歴史的展開
2.中枢神経系発生の第I期
3.神経細胞が発生する第II期
4.グリア細胞の分化をめぐる論争
5.グリア細胞が発生する第III期
6.アストロサイトとオリゴデンドロサイトの発生と分化
7.ミクログリアという脳組織防衛システム
8.ゲノムからみたニューロンとグリア細胞分化のメカニズム
9.マトリックス細胞の増殖・分化と脳の形
10.脳室下層
11.グリア細胞の機能の歴史的展望
II.グリアル・ネットワークとニューラル・ネットワーク
1.正常脳におけるグリアル・ネットワークの働き
A.グリアル・ネットワーク
B.脳内環境の維持・物質代謝とアストロサイト
C.脳微小循環とアストロサイト
2.脳病態におけるグリア細胞の役割
A.地球上における酸素の発生と生物の進化
B.脳虚血におけるグリア細胞の役割
C.アルツハイマー病におけるグリア細胞の役割
D.グリア細胞とハムレット
III.ニューラル・ネットワークとグリアル・ネットワーク
1.ニューラル・ネットワーク
A.ニューロンとシナプスの基本的な形態と機能
B.ナトリウム・ポンプ
C.神経回路の形成
D.「ヘッブの原理」とシナプスの可塑性
E.ニューラル・ネットワークのモデル
2.大脳皮質機能の局在と統合
A.大脳皮質の機能局在
B.知覚から認知へ
3.記憶のメカニズム
A.記憶の定義と分類
B.記憶と辺縁系
C.記憶・学習の機序
4.言葉と文字
A.Broca野とWernicke野
B.ミラーニューロン
C.他者の理解-感情移入
5.トップダウン処理
A.作業記憶
B.作業記憶と前頭前野
C.想像力と探索行動
6.情動と動機づけ
A.情動についての諸理論
B.高位系路と低位系路
C.意思決定のシステム
7.ニューロンとグリア細胞の相互作用
A.アストロサイトとシナプス可塑性
B.アストロサイトと脳高次機能
C.精神現象へのグリア細胞の関与
索引
書評
開く
卓越した脳発生学と「Neuro-Gliology」
書評者: 生田 房弘 (新潟大名誉教授・神経病理学/現・新潟脳外科病院)
著者の一人藤田氏と私は,全く同時代を共に脳に魅せられ今日に至った。藤田氏は,当初から脳の発生一筋に目を据えておられたように見えた。既に1960年代前半,「神経細胞もグリア細胞もマトリックス細胞に由来する」との一元論を立ち上げ,二元論一色の世界を相手に,着々とその証拠を自ら築き,堂々と主張を展開していかれた。
引き換え私は,神経病理学に魅せられ,同じ1960年代前半,ニューヨークで来る日も来る日もヒト疾患脳の観察を4年余続けただけで帰国した。以来,師,中田瑞穂先生の部屋で語ったことのほとんどはグリア細胞とニューロンの関係についてであった。私の4年余の経験は,脳病変をわれわれに教えてくれるのはグリア細胞をおいてないことなど,思うまま述べた。師の質問も繰り返された。意識についても話題にされた。やがて1971年,先生は神経細胞やグリア細胞,それぞれの研究ではなく“両者の相関”を解明してほしい,両者で脳の機能はつくられているのだと思うからと,その切々とした疑問を「Neuro-Gliology」と題し,そっと書き残された(新潟医誌 1971;85:667)。
本書の序でもこの中田先生の「Neuro-Gliology」に触れられており,遠い昔,藤田氏が時折,脳腫瘍病理学の草分けで,私の師でもあった伊藤辰治先生を訪れられたことなど想い起こした。
私自身も,ずっと後の1978年に至り,何としても脳の発生を観察する必要に迫られた。でもその折は既に確立された藤田氏の主張が私どもの教科書となり,そのすべての所見や見方は私どもの観察にも合致することを確信してきた。
そのような末に,本書の書評を,との藤田氏のご依頼を心から光栄に思いながら,私はその第I章の発生学は既に卒業しているつもりで読み始めた。ところが,確かに藤田氏のマトリックス細胞(Bayer SA, Altman JらのNeuroepitheliumに相当するというと叱られるだろうか)にすべてのニューロンやグリア細胞はその起源を持つという一元論の大黒柱は微動もせずそこにあった。
さらに,脳室下における細胞分裂像は血管新生に付随したものであること,「ラジアルグリア」は,誤ったGFAP染色がもたらした誤名であることなども読めた。
そしてそこには,病的状態におけるアストロサイトの増殖反応の記載を除けば,氏の深い観察と素直な解釈から生まれ,日本が世界に誇りうる数々の独創的真実が記載されていた。しかし今回は,脳発生過程のあらゆる局面に,接着因子など無数に近い分子機構が導入され,50年,30年前に私が理解した往年の面影はもはやなく,まさに現在の分子機構に裏打ちされた発生の科学に変身していた。読み進みながら「真実とはかくも美しく,爽やかなものか」と胸のすく想いで読了させてもらった。
さらにミクログリアをめぐる今日的考え方も整然と述べられ,そこでは,O-2A細胞やNG2陽性細胞などの考え方も,見事なグリア細胞発生のプロセスの中でとらえられ,考察されていたと思う。脱帽のほかはない。
余談になるが,文科省は2003-2008年3月の5年間,特定領域研究「グリア-ニューロン回路網による情報処理機構の解明」という,班員・協力者数百名の巨大な研究班(班長:工藤佳久氏)を発足させた。総括班に,濱清先生らと私も参加させていただき,発足の基調講演で,中田先生の「Neuro-Gliology」に触れた。分科会の目標はいずれもGlia-Neuronの相互認識,その機能分子,あるいは相互調節機構など,まさに全班員が5年間Neuro-Gliology相関をめざし続けた。その一部は『BRAIN and NERVE』誌にもみられる(2007;59(7))。他方,本書は奇しくも,その班の報告書が提出された直後の2009年4月1日に発行されている。
本書の第II,III章は,第I章とは大きなコントラストを示している。それは,ここでの論拠となる礎石はすべて,ここ10年程の世界の最先端をいく,実に493編の論文や単行書の膨大な知見や考え方におかれている点にあると思う。著者はそれらを完全に理解された上で,極めて広い視点から論旨を展開しておられる。また,この章の初めに,地球環境の永い歴史的変化の中で生命を理解しようとされている著者の姿勢に私は深い共感を覚えた。
ともあれ,いわゆるトリパータイトシナプスという1999年に報告された名称(2007年にはトライパータイトと日本で紹介されたこともあった),すなわち“シナプスはアストロサイトに包まれており,ニューロンとグリアは相互に認識しあっている”という点を重要な礎石の一つとし,ニューラル・ネットワークとグリアル・ネットワークが相互にコントロールし合っているという論旨は,5年間上記研究班で叫ばれてきたことと深く重なり合うように思われた。しかし,著者はさらに広範多彩な論旨を展開され,“無意識にはアストロサイトが関与している可能性が十分に考えられる”などと,心の問題にまで「Neuro-Gliology」を深く踏み込んでおられる。
ただ,ここに記されているまばゆいばかりの論旨の合間で,私には良く理解しきれない部分もあった。例えば「膨化したアストロサイトが次々と破裂して死んでゆく」という記載が繰り返されているが,私自身はまだそのような超微形態に遭遇したことがなかったためであった。
すなわち,第II,第III章の重要な礎は,シナプスはアストロサイトに包まれているという点にあるのだと思う。第I章に“シナプスはアストロサイトに包まれていて当然”との記載も見られる。しかし私自身は,アルゼンチンのDe Robertis EとGerschenfeld H Mが1961年に緻密な電顕観察の末,すべてのシナプスがアストロサイトに包まれていることを初めて指摘した一枚の図は,今日まで人目を引くことはなかったが,これこそが今日の神経学発展の原点であると永年信じ続けてきた。
さらにまた,1979年,Norenberg M Dが初めて“アストロサイトがシナプス間隙からグルタメイトを取り込み,グルタミンを合成する”ことを述べたときも,世界の誰もその重要性に興奮しなかった。しかし,これはニューロンがグリア細胞と話していることを初めて指摘したもので,後に日本の学会でこのアストロサイトの重要性を受け容れ始めたのは1990年頃からで,本質は何も変わらない「シナプス」なのに,トリパータイトシナプスなどという名がつくられたのはさらにその後の2000年に近くなってからである。
私は,世が注目してこなかったこうした先人達の陰の努力にも,もし本書が触れていてくれたら,どんなに嬉しかったことかと思う。
ともあれ,本書は2段組みにされていることなどで,大きく内容の理解を容易にしている。
今日神経学に携わっておられるすべての方々にとって,本書は,その内容の重要さから必読,必携の書であると心から推挙致したい。
卓越したグリア論
書評者: 兼本 浩祐 (愛知医大教授・精神科学)
本書にも引用されている偉大な心理学者,ウィリアム・ジェームズは,その人がもともと楽観的な心“cheerful soul”を持っているか悲観的な心“sick soul”を持っているかといった研究者間の気質の相違によって,そうした個人的資質とは本来は無関係なはずの科学的学問の質も違ってくるのだといったことを書いている。『脳科学のコスモロジー』は,自らの手で何百,何千のプレパラートを切り出し,染色したであろう第一線の研究者にしか書き得ないと思われる重厚な手触りのグリア論をその前半の内容としている。
そして後半では圧倒的な情報量とともに,脳科学が今や哲学の領域に侵攻し,科学的に蓄積可能な解答をその領域でも提出しつつある様子を克明にレポートしている。フッサール,フロイト,メルロ・ポンティ・・・哲学と科学は決して対立するものではなく,脳科学の進歩において統合され,私達はきっと前人未到の未来へと進んでいくという楽観が全編ににおい立つ。本書には科学を志す者,そして科学において粘り強い営みを続けて新たな領域を切り開く者にとって極めて重要な資質の一つである“cheerful soul”が躍動している。
前半ではグリア論の展開におけるドラマチックな歴史が,その歴史の形成に実際に立ち会った当事者の立場から極めて生き生きとした臨場感を持って活写されている。神経細胞発生学の父,偉大な解剖学者,ウィルヘルム・ヒスは,神経組織の発生は初めからグリアおよびニューロンのいずれに分化するかが前もって決定されている二種類の異なった母細胞から成り立っているという二元論を展開したという。しかし,ヒス自身はさすがに慧眼であり,自説の矛盾を指摘する反論にも耳を傾け,自説を修正しようと試みる懐の深さを死の直前まで示していたが,ヒス亡き後,機械的に早い時期のヒスの説をそのまま金科玉条としてしまった後世のエピゴーネン達は,単一の母細胞からグリアの原基もニューロンの原基も生ずるというグリアの一元的マトリックス起源説を長期間にわたり圧殺してしまう。
サンティアゴ・ラモン・イ・カハールの業績もドラマに満ちている。カハールはニューロンがそれぞれ一つ一つ独立した細胞であると考える現在のニューラル・ネットワークの基本概念を構想し,ノーベル賞を同時受賞したゴルジの網状説と激しく対立したが,その論争には勝利する一方で,弟子のピオ・デル・リオ・オルテガとの論争には歴史的には敗れてしまう。ニューロン,アストロサイトと対照的に,中枢神経組織においてカハール自身はその突起を染め出すことができなかった一群の細胞を,カハールは第三要素と名付け,これも外胚葉性のグリアの一種であろうと断定したが,優れた染色によってこの第三要素が突起のあるオリゴデンドログリアと突起の無いミクログリアに分かれることをオルテガは発見する。自説を覆したオルテガに激怒したカハールはオルテガを破門してしまう。本書での多くの登場人物はまさにグリアに彼らの人生を捧げていたといっても過言ではなく,科学研究というものも人間の愛憎のドラマを色濃く反映していることがよくわかる。
こうした先人達の人生を賭した論争の歴史の中で獲得されてきたグリアについての知識の頂点として本書の後半で呈示されているのが,グリアはニューロンを単に栄養補給といった面で助けているのではなく,ニューロン本来の機能である情報処理においても補完する存在であるという知見である。極めて興味深いのは・ニューラル・ネットワークが計算式に従う(すなわちデジタル的な)ある種のコスモスを形成し,その代償としてそこから抜け出すことが困難な常同的な反応(アトラクターと呼ばれている)に落ち込むのに対して,グリアル・ネットワークはよりアナログ的に作動することで小さな破局反応をこのコスモスに持続的に作り出し,ニューラル・ネットワークをアトラクターから脱出させて新たな地平(あるいは新たな演算の開始)へと導き出す原動力となるのではないかという主張である。離散値を基本に置くニューラル・ネットワークと連続的な値を取るカオスを体現するグリアル・ネットワークの対比,この壮大な構想を目の前にして高ぶる気持ちを抑えられない著者の鼓動が聞こえそうである。
ただおそらくはジェイムズの言うように気質の違いにもよるのであろう。悲観的な心にとっては本書の後半は少しばかりまばゆすぎるところもある。例えば夢の中に現れる欲望はフロイトにおいても理性と比べて低次元で抑圧すべき対象が表出される場と必ずしも断罪されているわけではない。通常の意味では絶望的に見える破綻した生のあり方であっても,自らの運命を生ききることが幸福であるという場合もあろう。つまりは世間的な意味では破綻してしまうような夢の欲望を充足し,実際に破綻することの方が,その人本来の生を生ききったと言える場合もあると考えれば,フロイトの無意識やラカンの現実界は善悪の彼岸にある。あるいはこのまばゆさは,治療というもののめざす方向があらかじめ明確な臨床の場と,まずはどちらへ向かって行けば良いのかに戸惑うことも多い臨床の場に身を置く者の違いなのかもしれない。
いずれにしても,本書が卓越したグリア論であり,一読の価値があることは論をまたない。
書評者: 生田 房弘 (新潟大名誉教授・神経病理学/現・新潟脳外科病院)
著者の一人藤田氏と私は,全く同時代を共に脳に魅せられ今日に至った。藤田氏は,当初から脳の発生一筋に目を据えておられたように見えた。既に1960年代前半,「神経細胞もグリア細胞もマトリックス細胞に由来する」との一元論を立ち上げ,二元論一色の世界を相手に,着々とその証拠を自ら築き,堂々と主張を展開していかれた。
引き換え私は,神経病理学に魅せられ,同じ1960年代前半,ニューヨークで来る日も来る日もヒト疾患脳の観察を4年余続けただけで帰国した。以来,師,中田瑞穂先生の部屋で語ったことのほとんどはグリア細胞とニューロンの関係についてであった。私の4年余の経験は,脳病変をわれわれに教えてくれるのはグリア細胞をおいてないことなど,思うまま述べた。師の質問も繰り返された。意識についても話題にされた。やがて1971年,先生は神経細胞やグリア細胞,それぞれの研究ではなく“両者の相関”を解明してほしい,両者で脳の機能はつくられているのだと思うからと,その切々とした疑問を「Neuro-Gliology」と題し,そっと書き残された(新潟医誌 1971;85:667)。
本書の序でもこの中田先生の「Neuro-Gliology」に触れられており,遠い昔,藤田氏が時折,脳腫瘍病理学の草分けで,私の師でもあった伊藤辰治先生を訪れられたことなど想い起こした。
私自身も,ずっと後の1978年に至り,何としても脳の発生を観察する必要に迫られた。でもその折は既に確立された藤田氏の主張が私どもの教科書となり,そのすべての所見や見方は私どもの観察にも合致することを確信してきた。
そのような末に,本書の書評を,との藤田氏のご依頼を心から光栄に思いながら,私はその第I章の発生学は既に卒業しているつもりで読み始めた。ところが,確かに藤田氏のマトリックス細胞(Bayer SA, Altman JらのNeuroepitheliumに相当するというと叱られるだろうか)にすべてのニューロンやグリア細胞はその起源を持つという一元論の大黒柱は微動もせずそこにあった。
さらに,脳室下における細胞分裂像は血管新生に付随したものであること,「ラジアルグリア」は,誤ったGFAP染色がもたらした誤名であることなども読めた。
そしてそこには,病的状態におけるアストロサイトの増殖反応の記載を除けば,氏の深い観察と素直な解釈から生まれ,日本が世界に誇りうる数々の独創的真実が記載されていた。しかし今回は,脳発生過程のあらゆる局面に,接着因子など無数に近い分子機構が導入され,50年,30年前に私が理解した往年の面影はもはやなく,まさに現在の分子機構に裏打ちされた発生の科学に変身していた。読み進みながら「真実とはかくも美しく,爽やかなものか」と胸のすく想いで読了させてもらった。
さらにミクログリアをめぐる今日的考え方も整然と述べられ,そこでは,O-2A細胞やNG2陽性細胞などの考え方も,見事なグリア細胞発生のプロセスの中でとらえられ,考察されていたと思う。脱帽のほかはない。
余談になるが,文科省は2003-2008年3月の5年間,特定領域研究「グリア-ニューロン回路網による情報処理機構の解明」という,班員・協力者数百名の巨大な研究班(班長:工藤佳久氏)を発足させた。総括班に,濱清先生らと私も参加させていただき,発足の基調講演で,中田先生の「Neuro-Gliology」に触れた。分科会の目標はいずれもGlia-Neuronの相互認識,その機能分子,あるいは相互調節機構など,まさに全班員が5年間Neuro-Gliology相関をめざし続けた。その一部は『BRAIN and NERVE』誌にもみられる(2007;59(7))。他方,本書は奇しくも,その班の報告書が提出された直後の2009年4月1日に発行されている。
本書の第II,III章は,第I章とは大きなコントラストを示している。それは,ここでの論拠となる礎石はすべて,ここ10年程の世界の最先端をいく,実に493編の論文や単行書の膨大な知見や考え方におかれている点にあると思う。著者はそれらを完全に理解された上で,極めて広い視点から論旨を展開しておられる。また,この章の初めに,地球環境の永い歴史的変化の中で生命を理解しようとされている著者の姿勢に私は深い共感を覚えた。
ともあれ,いわゆるトリパータイトシナプスという1999年に報告された名称(2007年にはトライパータイトと日本で紹介されたこともあった),すなわち“シナプスはアストロサイトに包まれており,ニューロンとグリアは相互に認識しあっている”という点を重要な礎石の一つとし,ニューラル・ネットワークとグリアル・ネットワークが相互にコントロールし合っているという論旨は,5年間上記研究班で叫ばれてきたことと深く重なり合うように思われた。しかし,著者はさらに広範多彩な論旨を展開され,“無意識にはアストロサイトが関与している可能性が十分に考えられる”などと,心の問題にまで「Neuro-Gliology」を深く踏み込んでおられる。
ただ,ここに記されているまばゆいばかりの論旨の合間で,私には良く理解しきれない部分もあった。例えば「膨化したアストロサイトが次々と破裂して死んでゆく」という記載が繰り返されているが,私自身はまだそのような超微形態に遭遇したことがなかったためであった。
すなわち,第II,第III章の重要な礎は,シナプスはアストロサイトに包まれているという点にあるのだと思う。第I章に“シナプスはアストロサイトに包まれていて当然”との記載も見られる。しかし私自身は,アルゼンチンのDe Robertis EとGerschenfeld H Mが1961年に緻密な電顕観察の末,すべてのシナプスがアストロサイトに包まれていることを初めて指摘した一枚の図は,今日まで人目を引くことはなかったが,これこそが今日の神経学発展の原点であると永年信じ続けてきた。
さらにまた,1979年,Norenberg M Dが初めて“アストロサイトがシナプス間隙からグルタメイトを取り込み,グルタミンを合成する”ことを述べたときも,世界の誰もその重要性に興奮しなかった。しかし,これはニューロンがグリア細胞と話していることを初めて指摘したもので,後に日本の学会でこのアストロサイトの重要性を受け容れ始めたのは1990年頃からで,本質は何も変わらない「シナプス」なのに,トリパータイトシナプスなどという名がつくられたのはさらにその後の2000年に近くなってからである。
私は,世が注目してこなかったこうした先人達の陰の努力にも,もし本書が触れていてくれたら,どんなに嬉しかったことかと思う。
ともあれ,本書は2段組みにされていることなどで,大きく内容の理解を容易にしている。
今日神経学に携わっておられるすべての方々にとって,本書は,その内容の重要さから必読,必携の書であると心から推挙致したい。
卓越したグリア論
書評者: 兼本 浩祐 (愛知医大教授・精神科学)
本書にも引用されている偉大な心理学者,ウィリアム・ジェームズは,その人がもともと楽観的な心“cheerful soul”を持っているか悲観的な心“sick soul”を持っているかといった研究者間の気質の相違によって,そうした個人的資質とは本来は無関係なはずの科学的学問の質も違ってくるのだといったことを書いている。『脳科学のコスモロジー』は,自らの手で何百,何千のプレパラートを切り出し,染色したであろう第一線の研究者にしか書き得ないと思われる重厚な手触りのグリア論をその前半の内容としている。
そして後半では圧倒的な情報量とともに,脳科学が今や哲学の領域に侵攻し,科学的に蓄積可能な解答をその領域でも提出しつつある様子を克明にレポートしている。フッサール,フロイト,メルロ・ポンティ・・・哲学と科学は決して対立するものではなく,脳科学の進歩において統合され,私達はきっと前人未到の未来へと進んでいくという楽観が全編ににおい立つ。本書には科学を志す者,そして科学において粘り強い営みを続けて新たな領域を切り開く者にとって極めて重要な資質の一つである“cheerful soul”が躍動している。
前半ではグリア論の展開におけるドラマチックな歴史が,その歴史の形成に実際に立ち会った当事者の立場から極めて生き生きとした臨場感を持って活写されている。神経細胞発生学の父,偉大な解剖学者,ウィルヘルム・ヒスは,神経組織の発生は初めからグリアおよびニューロンのいずれに分化するかが前もって決定されている二種類の異なった母細胞から成り立っているという二元論を展開したという。しかし,ヒス自身はさすがに慧眼であり,自説の矛盾を指摘する反論にも耳を傾け,自説を修正しようと試みる懐の深さを死の直前まで示していたが,ヒス亡き後,機械的に早い時期のヒスの説をそのまま金科玉条としてしまった後世のエピゴーネン達は,単一の母細胞からグリアの原基もニューロンの原基も生ずるというグリアの一元的マトリックス起源説を長期間にわたり圧殺してしまう。
サンティアゴ・ラモン・イ・カハールの業績もドラマに満ちている。カハールはニューロンがそれぞれ一つ一つ独立した細胞であると考える現在のニューラル・ネットワークの基本概念を構想し,ノーベル賞を同時受賞したゴルジの網状説と激しく対立したが,その論争には勝利する一方で,弟子のピオ・デル・リオ・オルテガとの論争には歴史的には敗れてしまう。ニューロン,アストロサイトと対照的に,中枢神経組織においてカハール自身はその突起を染め出すことができなかった一群の細胞を,カハールは第三要素と名付け,これも外胚葉性のグリアの一種であろうと断定したが,優れた染色によってこの第三要素が突起のあるオリゴデンドログリアと突起の無いミクログリアに分かれることをオルテガは発見する。自説を覆したオルテガに激怒したカハールはオルテガを破門してしまう。本書での多くの登場人物はまさにグリアに彼らの人生を捧げていたといっても過言ではなく,科学研究というものも人間の愛憎のドラマを色濃く反映していることがよくわかる。
こうした先人達の人生を賭した論争の歴史の中で獲得されてきたグリアについての知識の頂点として本書の後半で呈示されているのが,グリアはニューロンを単に栄養補給といった面で助けているのではなく,ニューロン本来の機能である情報処理においても補完する存在であるという知見である。極めて興味深いのは・ニューラル・ネットワークが計算式に従う(すなわちデジタル的な)ある種のコスモスを形成し,その代償としてそこから抜け出すことが困難な常同的な反応(アトラクターと呼ばれている)に落ち込むのに対して,グリアル・ネットワークはよりアナログ的に作動することで小さな破局反応をこのコスモスに持続的に作り出し,ニューラル・ネットワークをアトラクターから脱出させて新たな地平(あるいは新たな演算の開始)へと導き出す原動力となるのではないかという主張である。離散値を基本に置くニューラル・ネットワークと連続的な値を取るカオスを体現するグリアル・ネットワークの対比,この壮大な構想を目の前にして高ぶる気持ちを抑えられない著者の鼓動が聞こえそうである。
ただおそらくはジェイムズの言うように気質の違いにもよるのであろう。悲観的な心にとっては本書の後半は少しばかりまばゆすぎるところもある。例えば夢の中に現れる欲望はフロイトにおいても理性と比べて低次元で抑圧すべき対象が表出される場と必ずしも断罪されているわけではない。通常の意味では絶望的に見える破綻した生のあり方であっても,自らの運命を生ききることが幸福であるという場合もあろう。つまりは世間的な意味では破綻してしまうような夢の欲望を充足し,実際に破綻することの方が,その人本来の生を生ききったと言える場合もあると考えれば,フロイトの無意識やラカンの現実界は善悪の彼岸にある。あるいはこのまばゆさは,治療というもののめざす方向があらかじめ明確な臨床の場と,まずはどちらへ向かって行けば良いのかに戸惑うことも多い臨床の場に身を置く者の違いなのかもしれない。
いずれにしても,本書が卓越したグリア論であり,一読の価値があることは論をまたない。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。