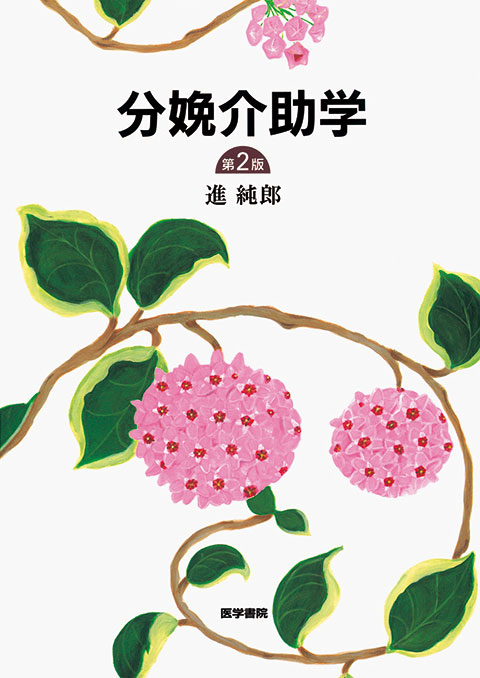分娩介助学
分娩介助の基本技術のすべてを網羅したスタンダードな手引書
もっと見る
分娩介助の基本技術のすべてを網羅。分娩は生理的な現象であり、まず正常分娩のメカニズムを十分に理解することが大切である。そして母子が安全・快適に出産を成就することができるよう、分娩介助者は最新の知識と技術、産む人のニーズに精通していなければならない。分娩介助者にとってのスタンダードな手引書。
| 著 | 進 純郎 |
|---|---|
| 発行 | 2005年11月判型:B5頁:408 |
| ISBN | 978-4-260-00068-0 |
| 定価 | 5,280円 (本体4,800円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 目次
- 書評
目次
開く
■分娩介助学総論
第1章 世界と日本のお産の歴史
第2章 出産におけるパラダイムと自然なお産
第3章 WHOの59か条と新しいお産の考え方
■分娩介助学各論
第1章 骨産道,軟産道,胎児
第2章 胎児と骨盤の関係
第3章 仰臥位分娩
第4章 さまざまな分娩体位(フリースタイル出産)
第5章 児頭の回旋・進入・胎位・胎勢の異常
第6章 児頭下降度と分娩進行度の評価
第7章 分娩の進行とその異常
第8章 CPDの診断とその対応
第9章 分娩時胎児心拍数モニタリング
第10章 産痛とその対応
第11章 分娩誘発と陣痛促進
第12章 骨盤位分娩介助術
第13章 肩甲難産
第14章 双胎の分娩
第15章 会陰裂傷・切開と会陰の縫合
第16章 吸引分娩
第17章 鉗子分娩
第18章 帝王切開
第19章 臍帯結紮
第20章 新生児仮死の診断と対応
第21章 産科救急
文献
索引
第1章 世界と日本のお産の歴史
第2章 出産におけるパラダイムと自然なお産
第3章 WHOの59か条と新しいお産の考え方
■分娩介助学各論
第1章 骨産道,軟産道,胎児
第2章 胎児と骨盤の関係
第3章 仰臥位分娩
第4章 さまざまな分娩体位(フリースタイル出産)
第5章 児頭の回旋・進入・胎位・胎勢の異常
第6章 児頭下降度と分娩進行度の評価
第7章 分娩の進行とその異常
第8章 CPDの診断とその対応
第9章 分娩時胎児心拍数モニタリング
第10章 産痛とその対応
第11章 分娩誘発と陣痛促進
第12章 骨盤位分娩介助術
第13章 肩甲難産
第14章 双胎の分娩
第15章 会陰裂傷・切開と会陰の縫合
第16章 吸引分娩
第17章 鉗子分娩
第18章 帝王切開
第19章 臍帯結紮
第20章 新生児仮死の診断と対応
第21章 産科救急
文献
索引
書評
開く
『分娩介助学』を医師の夫と助産師の妻で読みました (雑誌『助産雑誌』より)
書評者: 伊集院 秀明・伊集院 佐由美
私たちは鹿児島市内で夫婦でクリニックと助産院をやっています。同じ敷地内にありますので,医療が必要になったときは,すぐに応援が得られますので,助産師の私にとって安心して出産ケアができるのがメリットです。
産科医の夫とは,出産のスタイルなどについてもよく話し合います。このたび,『分娩介助学』が出版されましたので,夫婦で読んでみました。最初,『基本分娩介助学』の改定版なのかなと思っていましたら,まったく新版でした。本書は分娩介助の知識と技術だけにしぼってあるのがポイントで,助産学生・医学生にとって,大変役に立つと思います。
佐由美:
非常にユニークだったのは,総論で世界と日本のお産の歴史にはじまり出産におけるパラダイムと自然なお産,WHOの59か条と新しいお産の考え方と題し,21世紀のお産のありかたについて著者の進純郎氏のご意見が述べてあったところでした。
秀明:
私は産科医になった時から分娩は仰臥位で行なっていました。当然,分娩体位は仰臥位と思っていたのが,このお産の歴史を読んで仰臥位分娩になった経過がよくわかりました。この体位は医療者側に立った分娩スタイルだったということですね。
佐由美:
私たちは歴史を知っているようで知らないわね。こういう知識がないと21世紀の分娩は語れないですね。
ところで1年半前クリニックに隣接して私は助産院を開院したのですが,私のところを受診される妊婦さんはお産に対する自分の思いを持って来ます。ただ医療に守られながら,助産院で自分なりの満足できるお産をしたいという方が多いように思います。私自身も病院に勤務した期間が長かったせいか,隣接してクリニックがあるということは安心して分娩介助ができます。
秀明:
だから最近日本では,院内助産院のスタイルが増えてきているのかな。この著書のなかで21世紀のローリスクのお産はフリースタイル出産であると書いてあったけど,やはり君のところのマミィ助産院でも希望者が多いかい?
佐由美:
これまでアクティブバースで出産という方が多かったけど,先日,本書を参考にしつつフリースタイル出産を行なってみたら産婦さんがとても満足され喜ばれました。この本によると両者は別のもの。非常に細かく介助法のすべてが一から十まで書かれているので,これからフリースタイル出産に取り組もうとする助産師さんには,ぜひ読んでいただければいいと思います。
秀明:
そうだね。産科医もこの本を参考に助産師さんたちと共にフリースタイル出産を行なってみたらいいね。このフリースタイル出産は助産師さんが中心となって,助産師さんを信頼して産科医が見守り行なっていくということになるね。そのためには助産師さんにとっても産科医にとっても非常に参考になる手引書だ。
進先生が言われるように昨今の少子化,親子関係の破綻,乳幼児虐待,青少年犯罪の多発などに鑑みると,人間の原点である出産に携わるものとして早急に取り組むべきことではないかな。
佐由美:
そう考えると21世紀での私たちの役割は非常に大きく,責任を感じます。そのためには,分娩介助に関する幅広い知識と経験が必要ですね。その点,この著書は先生の経験など事細かに解説してあり,私たち助産師にも理解しやすい本だと思います。
秀明:
私は,進先生と同じ年代で長年臨床に携わってきました。そのためかこの本を読むと,これまで経験したいろいろな症例が目に浮かんできます。自分たちが医者になったころにはこのような著書はなく,先輩に教わりながら試行錯誤しつつ医療を行なってきました。これから産科医を目指す先生方の指標となる本だと思います。
佐由美:
産科医の先生の立場から書いてある著書なので,助産師にとっては,先生方の臨床を行なううえでの考え方や処置や手技を学ぶと同時に,どの時点で医療が必要になるかの判断の材料となることと思います。これからの助産師はさらに分娩介助に対する知識を学び,自分たちの仕事の役割を自覚して,産科医と協力して21世紀のお産に取り組んでいかなければならないですね。
秀明:
進先生も書かれていたけど,助産師さんの役割は大きいね。僕たちはこの本に出会えてよかったと思うよ。
佐由美:
仲良く頑張っていきましょう。
(『助産雑誌』2006年5月号掲載)
書評者: 伊集院 秀明・伊集院 佐由美
私たちは鹿児島市内で夫婦でクリニックと助産院をやっています。同じ敷地内にありますので,医療が必要になったときは,すぐに応援が得られますので,助産師の私にとって安心して出産ケアができるのがメリットです。
産科医の夫とは,出産のスタイルなどについてもよく話し合います。このたび,『分娩介助学』が出版されましたので,夫婦で読んでみました。最初,『基本分娩介助学』の改定版なのかなと思っていましたら,まったく新版でした。本書は分娩介助の知識と技術だけにしぼってあるのがポイントで,助産学生・医学生にとって,大変役に立つと思います。
佐由美:
非常にユニークだったのは,総論で世界と日本のお産の歴史にはじまり出産におけるパラダイムと自然なお産,WHOの59か条と新しいお産の考え方と題し,21世紀のお産のありかたについて著者の進純郎氏のご意見が述べてあったところでした。
秀明:
私は産科医になった時から分娩は仰臥位で行なっていました。当然,分娩体位は仰臥位と思っていたのが,このお産の歴史を読んで仰臥位分娩になった経過がよくわかりました。この体位は医療者側に立った分娩スタイルだったということですね。
佐由美:
私たちは歴史を知っているようで知らないわね。こういう知識がないと21世紀の分娩は語れないですね。
ところで1年半前クリニックに隣接して私は助産院を開院したのですが,私のところを受診される妊婦さんはお産に対する自分の思いを持って来ます。ただ医療に守られながら,助産院で自分なりの満足できるお産をしたいという方が多いように思います。私自身も病院に勤務した期間が長かったせいか,隣接してクリニックがあるということは安心して分娩介助ができます。
秀明:
だから最近日本では,院内助産院のスタイルが増えてきているのかな。この著書のなかで21世紀のローリスクのお産はフリースタイル出産であると書いてあったけど,やはり君のところのマミィ助産院でも希望者が多いかい?
佐由美:
これまでアクティブバースで出産という方が多かったけど,先日,本書を参考にしつつフリースタイル出産を行なってみたら産婦さんがとても満足され喜ばれました。この本によると両者は別のもの。非常に細かく介助法のすべてが一から十まで書かれているので,これからフリースタイル出産に取り組もうとする助産師さんには,ぜひ読んでいただければいいと思います。
秀明:
そうだね。産科医もこの本を参考に助産師さんたちと共にフリースタイル出産を行なってみたらいいね。このフリースタイル出産は助産師さんが中心となって,助産師さんを信頼して産科医が見守り行なっていくということになるね。そのためには助産師さんにとっても産科医にとっても非常に参考になる手引書だ。
進先生が言われるように昨今の少子化,親子関係の破綻,乳幼児虐待,青少年犯罪の多発などに鑑みると,人間の原点である出産に携わるものとして早急に取り組むべきことではないかな。
佐由美:
そう考えると21世紀での私たちの役割は非常に大きく,責任を感じます。そのためには,分娩介助に関する幅広い知識と経験が必要ですね。その点,この著書は先生の経験など事細かに解説してあり,私たち助産師にも理解しやすい本だと思います。
秀明:
私は,進先生と同じ年代で長年臨床に携わってきました。そのためかこの本を読むと,これまで経験したいろいろな症例が目に浮かんできます。自分たちが医者になったころにはこのような著書はなく,先輩に教わりながら試行錯誤しつつ医療を行なってきました。これから産科医を目指す先生方の指標となる本だと思います。
佐由美:
産科医の先生の立場から書いてある著書なので,助産師にとっては,先生方の臨床を行なううえでの考え方や処置や手技を学ぶと同時に,どの時点で医療が必要になるかの判断の材料となることと思います。これからの助産師はさらに分娩介助に対する知識を学び,自分たちの仕事の役割を自覚して,産科医と協力して21世紀のお産に取り組んでいかなければならないですね。
秀明:
進先生も書かれていたけど,助産師さんの役割は大きいね。僕たちはこの本に出会えてよかったと思うよ。
佐由美:
仲良く頑張っていきましょう。
(『助産雑誌』2006年5月号掲載)
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。