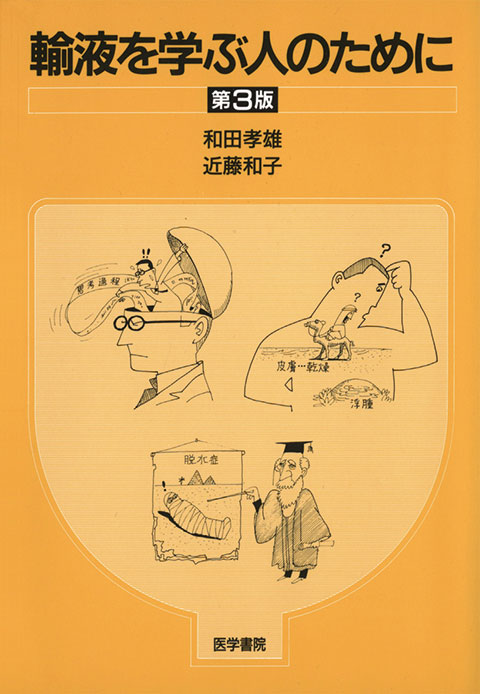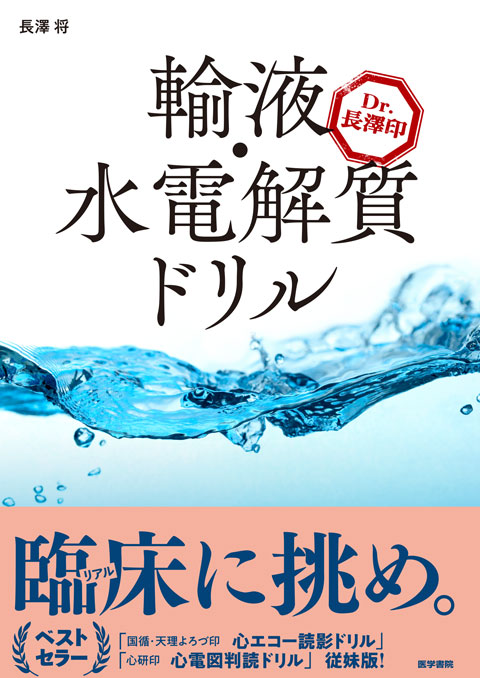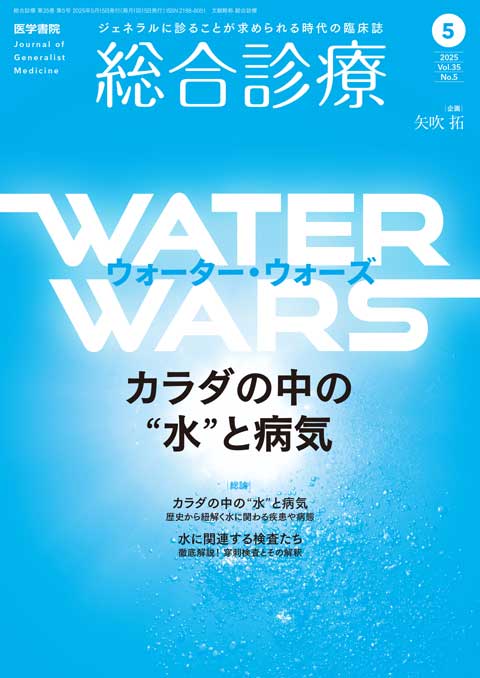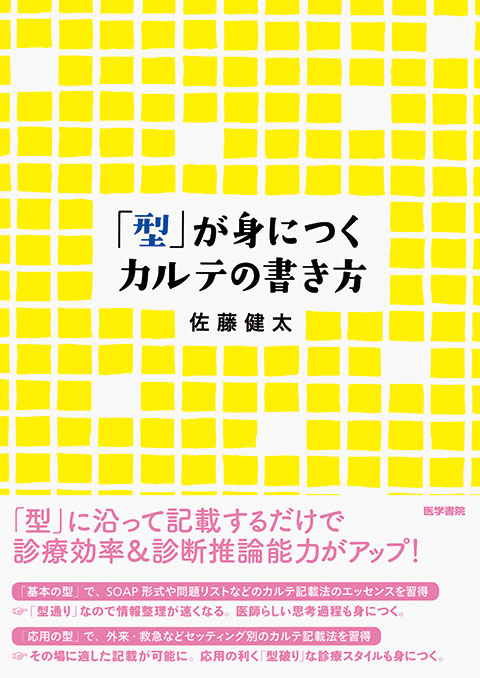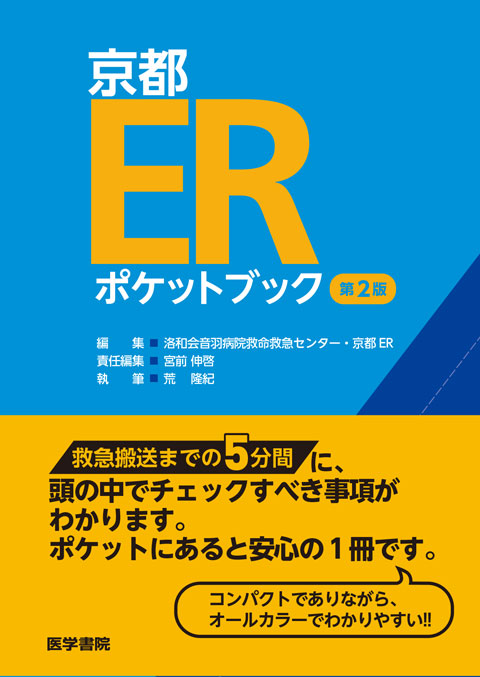輸液を学ぶ人のために 第3版
もっと見る
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 目次
- 書評
目次
開く
2 浸透圧の話
3 ナトリウムの必要量について
4 基礎輸液の概念
5 維持輸液
6 輸液の指標としての検査データ
7 低ナトリウム血症の考えかた
8 高ナトリウム血症の考えかた
9 脱水症
10 輸液剤の種類
11 輸液のコツとは何か
12 輸液と栄養
13 輸液の速度
14 尿量のみかた
15 カリウム
16 「ある医師の思考過程」より
17 栄養輸液は難しい
18 高カロリー輸液の基礎知識 他
書評
開く
温故知新,「勤務医の働き方改革時代の病棟」の輸液療法の指針となる一冊
書評者:杉本 俊郎(滋賀医大教授・総合内科学)
私は,滋賀の田園地域中核病院の内科の責任者をしており,現在,「病棟での輸液の質・安全性」を担保するにはどうすべきかと苦慮しています。その中で,数十年ぶりに本書を電子書籍で読みかえしました。
本書との最初の出合いは,研修医だったころ(1989年),大学附属病院での当直の夜,カンファレンスルームにある本棚でしたが,その時読んだのはこの版ではなかったと思います。初版は1981年と書かれており,青い表紙だったようです。私が手に取った本の表紙は黄色だったので,第2版と思われます。1997年に出版された第3版が電子書籍で購読可能ということは,この本がいまだに“現役”であることを示しています。
本書は,医師の和田孝雄先生,看護師の和田和子師長,梶原めぐみさんの語り口調でまとめられています。つまり,初版の時点から,「輸液療法は,医師と看護師との協働が必要である」ことが述べられているのです。「勤務医の働き方改革時代の病棟」には看護師さんをはじめとした病棟スタッフとの協働が必須ですが,本書は約40数年前から「働き方改革」についても述べられていたことになります。さらに,「教科書に書いてあることは当てはまらない。理論は理論,実臨床とは異なる」「検査異常を治療するのではない,患者を治療するものである」「輸液でむくみをつくってはだめ」「輸液計画は所詮,計画。輸液を開始したら経過を追うことが重要」など,私が常々述べていることが,既に本書に書かれていることに驚愕しました。
本書には,輸液療法の標準的治療“state of art therapy”の基本が簡潔・明瞭に書かれています。現在,急性期の輸液理論は変貌しており,“fluid stewardship”の重要性や,“fluid creep”を避けることが言われていますが,本書には既に同様のことが記載されています。第3版の序文には栄養輸液について整理したとの記載があり,既にそれらについて書かれていたことにも驚愕しますが,初版に“fluid stewardship”や“fluid creep”といった概念についても記載されていたと思われ,驚嘆します。
私は,多くの腎臓内科医の目標の一つに,「『輸液を学ぶ人のために』を超える輸液の教科書を書く」があると聞いたことがあります。しかし,うっ血・浮腫といった体液過剰の専門家となりつつある(Fluid therapy can be considered “reverse nephrology”.)現在の腎臓内科医にとって,この目標を超えることは不可能なのではないか,と考えています。
和田先生は既に他界され,直接の薫陶を受けられないのは残念ですが,半世紀近く“現役”であり続けている本書を読み返す度に多くの学びが得られます。初学者だけでなく,経験を積まれた医師,看護師さんにぜひ読んでいただきたい一冊です。