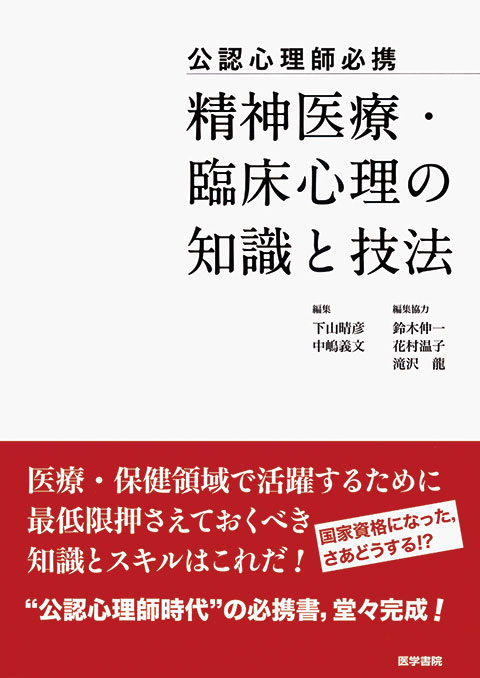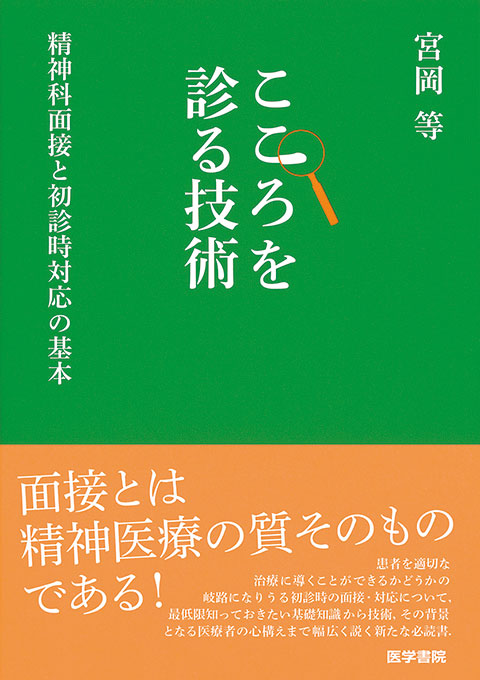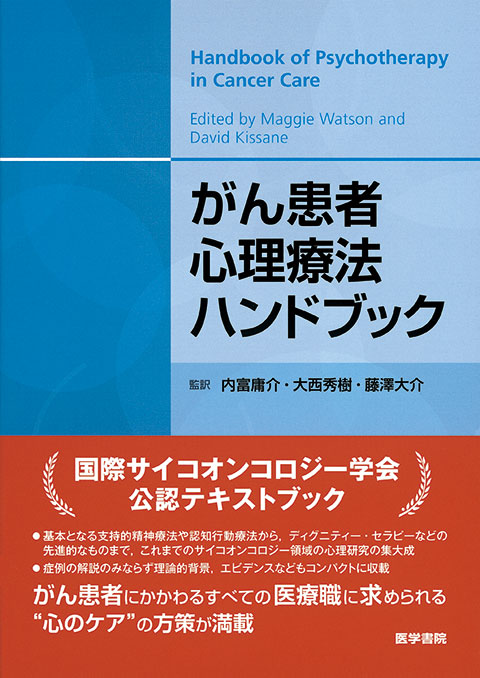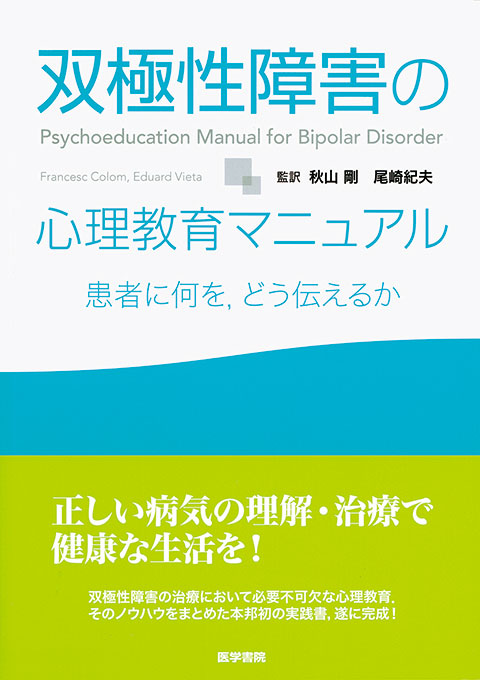公認心理師必携 精神医療・臨床心理の知識と技法
これからの心理職に求められる知識とスキルはこれだ!
もっと見る
国家資格になるのであればここまでは知っておきたい! 医療の基本知識から精神症状の診かた、うつ病や不安症などの精神疾患の特徴、心理アセスメント技法まで、医療・保健領域の現場でメンタルヘルス活動を適切に行うために必要な情報を幅広くカバー。症例を用いて具体的な心理介入のプロトコルも解説しており、実践でも役立てられる1冊となっている。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
本書を手に取られた方は,ぜひ最初に目次をご覧いただきたい.類書にはない,斬新な内容となっているとの印象をもっていただけると思う.それととともに,「これ1冊あれば大丈夫」といった安心感ももっていただけるはずである.
本書は,チーム医療とエビデンスに基づく心理的支援を基本コンセプトとし,専門性の高いメンタルヘルス活動を実践するためのレファレンスブックとして編まれたものである.より質の高いメンタルヘルス活動を,より多くの方に提供することを目標とし,心理職と医療職が協働して編集を行い,現場で活躍している多様な専門職の協力を得て執筆作業を進めた.実際にできあがった内容をみて,臨床現場においてメンタルヘルス活動を適切に実践するための専門的な知識と技法を網羅し,しかも最新かつ実践的な臨床情報をコンパクトにまとめることができたと確信している.
わが国は多くのメンタルヘルスの問題を抱えており,その解決は社会全体の重要な政策課題である.そのような状況と関連して2015年9月に公認心理師法が国会で成立・公布され,心理職が国家資格を有する専門職である公認心理師となることとなった.心理職の国家資格化が先進国のなかで非常に遅れていたわが国においても,ようやく公認心理師として心理職がメンタルヘルス活動に正式に参加することになったのである.
医療・保健領域におけるチーム医療に参加する場合は言うまでもなく,福祉や教育などの他領域においても,適切な実践活動をするためには精神医療の基本的な知識と技法は必須である.また,より専門性の高い心理的支援を実践するためには,従来のカウンセリングや心理療法の知識と技法だけでなく,エビデンスに基づく臨床心理学の最新の知識と技法の習得が必要となる.本書は,公認心理師が高い専門性を備え,多職種協働チームによるメンタルヘルス活動に貢献するための知識と技法を整理し,簡潔に解説した必携書となっている.特に,幅広い精神医療の制度や実践的手続きに加えて,今や社会的要請となっているエビデンスベースド・プラクティスのための最新プロトコルが問題別で解説されている点は,他書にはない本書の特徴である.
このように本書は,公認心理師を目指して教育を受けている訓練生や若手心理職のテキストだけでなく,現場で働く中堅・ベテランの公認心理師が活動の最前線で困った際に参照できるレファレンスブックともなっている.さらには,公認心理師と協働して,より質の高い活動を展開することを目指す医療職をはじめとする他職種にとっても,大いに参考にできる内容となっている.本書が多くのメンタルヘルス専門職に活用され,わが国のメンタルヘルス活動の改善や向上に少しでも貢献できることを祈念して筆を擱く.
2016年7月
編集者を代表して 下山晴彦
本書を手に取られた方は,ぜひ最初に目次をご覧いただきたい.類書にはない,斬新な内容となっているとの印象をもっていただけると思う.それととともに,「これ1冊あれば大丈夫」といった安心感ももっていただけるはずである.
本書は,チーム医療とエビデンスに基づく心理的支援を基本コンセプトとし,専門性の高いメンタルヘルス活動を実践するためのレファレンスブックとして編まれたものである.より質の高いメンタルヘルス活動を,より多くの方に提供することを目標とし,心理職と医療職が協働して編集を行い,現場で活躍している多様な専門職の協力を得て執筆作業を進めた.実際にできあがった内容をみて,臨床現場においてメンタルヘルス活動を適切に実践するための専門的な知識と技法を網羅し,しかも最新かつ実践的な臨床情報をコンパクトにまとめることができたと確信している.
わが国は多くのメンタルヘルスの問題を抱えており,その解決は社会全体の重要な政策課題である.そのような状況と関連して2015年9月に公認心理師法が国会で成立・公布され,心理職が国家資格を有する専門職である公認心理師となることとなった.心理職の国家資格化が先進国のなかで非常に遅れていたわが国においても,ようやく公認心理師として心理職がメンタルヘルス活動に正式に参加することになったのである.
医療・保健領域におけるチーム医療に参加する場合は言うまでもなく,福祉や教育などの他領域においても,適切な実践活動をするためには精神医療の基本的な知識と技法は必須である.また,より専門性の高い心理的支援を実践するためには,従来のカウンセリングや心理療法の知識と技法だけでなく,エビデンスに基づく臨床心理学の最新の知識と技法の習得が必要となる.本書は,公認心理師が高い専門性を備え,多職種協働チームによるメンタルヘルス活動に貢献するための知識と技法を整理し,簡潔に解説した必携書となっている.特に,幅広い精神医療の制度や実践的手続きに加えて,今や社会的要請となっているエビデンスベースド・プラクティスのための最新プロトコルが問題別で解説されている点は,他書にはない本書の特徴である.
このように本書は,公認心理師を目指して教育を受けている訓練生や若手心理職のテキストだけでなく,現場で働く中堅・ベテランの公認心理師が活動の最前線で困った際に参照できるレファレンスブックともなっている.さらには,公認心理師と協働して,より質の高い活動を展開することを目指す医療職をはじめとする他職種にとっても,大いに参考にできる内容となっている.本書が多くのメンタルヘルス専門職に活用され,わが国のメンタルヘルス活動の改善や向上に少しでも貢献できることを祈念して筆を擱く.
2016年7月
編集者を代表して 下山晴彦
目次
開く
第1部 チーム医療と心理師の役割
第1章 医療の基本知識
医療とは
医療の質
第2章 チーム医療
現代のチーム医療と心理師の役割
チーム医療を構成する専門職
チーム医療の理論と方法
第3章 医療におけるメンタルヘルス
病むこと
支えること
第2部 精神医療の基本
第4章 精神症状のみかた
感情・気分障害
意識障害
認知障害
第5章 診断とその経過
精神科診断の方法論
神経発達症群
統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害群
双極性障害および関連障害群
抑うつ障害群
不安症群
強迫症および関連症群
心的外傷およびストレス因関連障害群
解離症群
身体症状症および関連症群
食行動異常および摂食障害群
睡眠-覚醒障害群
性機能不全群・性別違和
秩序破壊的・衝動制御・素行症群
物質関連障害および嗜癖性障害群
神経認知障害群
パーソナリティ障害
パラフィリア障害
第6章 治療のあり方
予診・初診の進め方
入院適応・行動制限の判断
自殺リスクの評価
精神症状に影響を及ぼす諸要因
身体療法
精神科リハビリテーション
精神科救急
第7章 薬物療法
抗うつ薬
抗不安薬・睡眠薬
抗精神病薬
その他の向精神薬
第3部 精神医療システム
第8章 精神医療資源
精神科病院
総合病院
精神科診療所・メンタルクリニック
精神科アウトリーチ
第9章 精神保健サービス
医療外資源
小児・児童に対する精神保健福祉サービス
成人に対する精神保健福祉サービス
高齢者に対する精神保健福祉サービス
第10章 関連する法規と制度
精神保健福祉法・精神障害者保健福祉手帳
障害者総合支援法
発達障害者支援法
知的障害者福祉法・知的障害者更生相談所・児童相談所・療育手帳
心身喪失者等医療観察法・司法精神医学
成年後見制度
物質乱用・依存関連法規
介護保険法
障害年金・生活保護
第4部 心理師の専門技能
第11章 心理師の役割とスキル
精神医療にかかわる心理師の必須技能
心理師の倫理
生物-心理-社会モデル
機能分析
ケース・フォーミュレーション
エビデンスベースド・アプローチ
報告書の作成
第12章 心理アセスメントの技法
初回面接
行動観察
心理評定尺度
知能検査
神経心理学検査
脳画像検査
発達検査
認知症にかかわる検査
投映法
アセスメント結果のフィードバック
第13章 個人心理療法
動機づけ面接
応用行動分析
認知行動療法
第3世代認知行動療法
行動医学
認知リハビリテーション
対人関係療法
森田療法・内観療法
精神分析的心理療法
第14章 家族・集団支援技法
カップル療法・家族療法
患者の家族支援
ペアレント・トレーニング
集団療法
ソーシャルスキル・トレーニング
心理教育
第15章 コミュニティ・アプローチ
コンサルテーション
危機介入
リエゾン
アウトリーチ
サポートネットワーク
デイケア
第5部 問題別心理介入プロトコル
第16章 不安関連障害
総論
パニック症・広場恐怖症
社交不安症(対人恐怖症)
全般不安症
強迫症
心的外傷後ストレス障害
選択性緘黙
分離不安症
第17章 抑うつ障害
総論
うつ病
第18章 統合失調症スペクトラム障害
総論
統合失調症
第19章 発達障害
総論
自閉スペクトラム症
注意欠如・多動症
限局性学習症
第20章 心身症
総論
神経性やせ症
神経性過食症
不眠障害
過敏性腸症候群
緊張型頭痛
第21章 物質関連障害および嗜癖性障害
総論
アルコール関連障害
薬物関連障害
ギャンブル障害
第22章 触法精神医療における心理的アプローチ
総論
触法行為を伴った精神疾患
性犯罪者の再犯防止
第23章 身体疾患に伴う心理的問題
総論
がん
循環器疾患
高次脳機能障害のリハビリテーション
生活習慣病の行動管理
小児疾患
第24章 プロトコルの適用が困難な事例への対応
プロトコルによる対応が困難に陥った際の心得
付録 脳の構造
付録 略語集
和文索引
欧文索引
第1章 医療の基本知識
医療とは
医療の質
第2章 チーム医療
現代のチーム医療と心理師の役割
チーム医療を構成する専門職
チーム医療の理論と方法
第3章 医療におけるメンタルヘルス
病むこと
支えること
第2部 精神医療の基本
第4章 精神症状のみかた
感情・気分障害
意識障害
認知障害
第5章 診断とその経過
精神科診断の方法論
神経発達症群
統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害群
双極性障害および関連障害群
抑うつ障害群
不安症群
強迫症および関連症群
心的外傷およびストレス因関連障害群
解離症群
身体症状症および関連症群
食行動異常および摂食障害群
睡眠-覚醒障害群
性機能不全群・性別違和
秩序破壊的・衝動制御・素行症群
物質関連障害および嗜癖性障害群
神経認知障害群
パーソナリティ障害
パラフィリア障害
第6章 治療のあり方
予診・初診の進め方
入院適応・行動制限の判断
自殺リスクの評価
精神症状に影響を及ぼす諸要因
身体療法
精神科リハビリテーション
精神科救急
第7章 薬物療法
抗うつ薬
抗不安薬・睡眠薬
抗精神病薬
その他の向精神薬
第3部 精神医療システム
第8章 精神医療資源
精神科病院
総合病院
精神科診療所・メンタルクリニック
精神科アウトリーチ
第9章 精神保健サービス
医療外資源
小児・児童に対する精神保健福祉サービス
成人に対する精神保健福祉サービス
高齢者に対する精神保健福祉サービス
第10章 関連する法規と制度
精神保健福祉法・精神障害者保健福祉手帳
障害者総合支援法
発達障害者支援法
知的障害者福祉法・知的障害者更生相談所・児童相談所・療育手帳
心身喪失者等医療観察法・司法精神医学
成年後見制度
物質乱用・依存関連法規
介護保険法
障害年金・生活保護
第4部 心理師の専門技能
第11章 心理師の役割とスキル
精神医療にかかわる心理師の必須技能
心理師の倫理
生物-心理-社会モデル
機能分析
ケース・フォーミュレーション
エビデンスベースド・アプローチ
報告書の作成
第12章 心理アセスメントの技法
初回面接
行動観察
心理評定尺度
知能検査
神経心理学検査
脳画像検査
発達検査
認知症にかかわる検査
投映法
アセスメント結果のフィードバック
第13章 個人心理療法
動機づけ面接
応用行動分析
認知行動療法
第3世代認知行動療法
行動医学
認知リハビリテーション
対人関係療法
森田療法・内観療法
精神分析的心理療法
第14章 家族・集団支援技法
カップル療法・家族療法
患者の家族支援
ペアレント・トレーニング
集団療法
ソーシャルスキル・トレーニング
心理教育
第15章 コミュニティ・アプローチ
コンサルテーション
危機介入
リエゾン
アウトリーチ
サポートネットワーク
デイケア
第5部 問題別心理介入プロトコル
第16章 不安関連障害
総論
パニック症・広場恐怖症
社交不安症(対人恐怖症)
全般不安症
強迫症
心的外傷後ストレス障害
選択性緘黙
分離不安症
第17章 抑うつ障害
総論
うつ病
第18章 統合失調症スペクトラム障害
総論
統合失調症
第19章 発達障害
総論
自閉スペクトラム症
注意欠如・多動症
限局性学習症
第20章 心身症
総論
神経性やせ症
神経性過食症
不眠障害
過敏性腸症候群
緊張型頭痛
第21章 物質関連障害および嗜癖性障害
総論
アルコール関連障害
薬物関連障害
ギャンブル障害
第22章 触法精神医療における心理的アプローチ
総論
触法行為を伴った精神疾患
性犯罪者の再犯防止
第23章 身体疾患に伴う心理的問題
総論
がん
循環器疾患
高次脳機能障害のリハビリテーション
生活習慣病の行動管理
小児疾患
第24章 プロトコルの適用が困難な事例への対応
プロトコルによる対応が困難に陥った際の心得
付録 脳の構造
付録 略語集
和文索引
欧文索引
書評
開く
公認心理師をめざす学生,精神科医,看護師も活用できる良書
書評者: 井村 修 (阪大教授・臨床心理学)
公認心理師法が2017年9月より施行される。心理職の国家資格がいよいよ誕生である。心理技術者の国家資格が検討され始め,約半世紀の紆余曲折を経て,ようやく実現した。日本の心理職もやっと国際水準に達したのだろうか。公認心理師法では,公認心理師の業務を以下のように規定している(公認心理師法第二条より)。
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察,その結果の分析
(2)心理に関する支援を要する者に対する,その心理に関する相談及び助言,指導その他の援助
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言,指導その他の援助
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
そして,これらの業務を,医療・保健,教育,福祉,司法・行政,産業などさまざまな分野で実践することが期待されている。とりわけ国家資格が前提の医療・保健分野では,心理職の国家資格化が待ち望まれていた。したがって,本書『公認心理師必携 精神医療・臨床心理の知識と技法』は,タイムリーな企画といえるだろう。
本書の特徴は総勢122名からなる多彩な執筆陣にある。精神医学と認知行動療法が基盤になってはいるが,精神医学の研究者から臨床医,臨床心理学の研究者から心理臨床の実践家まで幅広い。
また,第1部で「チーム医療と心理師の役割」,第2部で「精神医療の基本」,第3部で「精神医療システム」と医療に関するテーマが扱われ,第4部で「心理師の専門技能」,第5部で「問題別心理介入プロトコル」と,公認心理師としての業務と直結したテーマが扱われている。
第1~3部の中で,これまで心理学系の大学・大学院で教えられてきたことは,第4章「精神症状のみかた」と,第5章「診断とその経過」であり,その他の章の内容はほとんど教わっていない。精神科の病院に就職した卒業生から,医療の現場に行って驚いたことは,感染症予防の手洗いを指導されたことだと聞いたことがあった。第1章にはその手洗いが図解されている。医学の常識が心理の教育では十分でなかったことがわかる。
第7章の「薬物療法」の説明も有用である。処方用量例と副作用も示されているのでわかりやすい。ある程度の薬物療法の知識は,公認心理師がチーム医療を担うためには必要である。
本書の最大の特徴は第5部である。第17章の「抑うつ障害」を例に挙げると,まず抑うつ障害の総論があり,理論と心理的アプローチが解説されている,次に心理的アプローチのプロトコルが示され,症例提示,心理的アプローチの実際,本症例のまとめとなっている。わずか数ページではあるが,うつ病の心理的アプローチのエッセンスが記載されている。統合失調症スペクトラム障害や心身症など,他の精神障害に関する章も同じような形式になっている。
本書は,公認心理師を対象としたものではあるが,公認心理師をめざす大学生・大学院生も活用できる良書である。さらに,第4部と第5部は,精神医療において公認心理師が何ができるのかを示しており,精神科医や看護師に読んでいただければ,より質の高いチーム医療が可能となるだろう。
公認心理師カリキュラム格好の教科書
書評者: 黒木 俊秀 (九大大学院人間環境学研究院教授・臨床心理学)
わが国で初めての心理専門職の国家資格となる公認心理師は,平成29年度内の制度の施行を目前に控え,国家試験の受験資格となる教育カリキュラムの概要が間もなく発表される予定である。公認心理師養成のカリキュラムとこれまでの臨床心理士養成課程との最も大きな違いは,前者が学部(4年制大学)から始まる点であろう。学部において必要な単位を修得後,臨床心理士と同じく大学院(修士課程)を修了したものが基本のコースとなるが,学部卒業後に所定の施設において一定期間の実務経験を積んだ者にも受験資格が与えられる。いずれの場合でも,医療,福祉,教育,産業,司法といった心理専門職が必要とされる学外の現場における実習体験の比重が大きくなる。さまざまな領域で多職種との連携が求められる点も,従来,相談室臨床を基本に発展してきた臨床心理士との相違と言えるかもしれない。
以上のようにわが国の心理専門職のあり方が大きく変わろうとするこの時期に,「公認心理師必携」と題する本書は,まさに時宜を得た出版と言えるだろう。
本書は,「チーム医療と心理師の役割」「精神医療の基本」「精神医療システム」「心理師の専門技能」,および「問題別心理介入プロトコル」の5部から構成されている。特に第1部「チーム医療と心理師の役割」は,医療領域における公認心理師の立ち位置を理解する意味で重要と思われる。ここでは,現代の医療の特性や医療制度,医療の質,チーム医療,医療におけるメンタルヘルスなどが概説されるが,従来の臨床心理士教育が全く触れていなかった感染対策(手洗いの図説あり)や診療記録の書き方にも言及している。この箇所は新鮮に感じるが,公認心理師には他のコメディカル・スタッフと同等の「医療現場の常識」が求められるのであり,多職種連携という理念を具体化したものと言えよう。
また第3部「精神医療システム」も現行の精神保健サービスや法制度の説明に紙面を多く割いており,これも実務上役立つだろう。
さらに第5部「問題別心理介入プロトコル」は,各疾患・病態別に症例を提示し,公認心理師に可能な支援の実際を簡潔にまとめている。多彩な執筆陣による分担執筆の著作の例に漏れず,そのノウハウの記述には濃淡があるものの初学者はアウトラインを理解することができよう(ただし,原田誠一氏による最終章「プロトコルの適用が困難な事例への対応」(p.327)は経験豊富な現場のスタッフこそ必読すべきである)。
公認心理師カリキュラムの到達目標の中には“精神疾患とその治療”に関する理解の項目が設けられるようだが,今後,同カリキュラムにおいて学び,学外の医療機関において実習や実務経験を積もうとする人には本書は格好の教科書となり得るだろう。ただ,公認心理師は医療領域に特化した資格ではない。その他の領域(福祉,教育,産業,司法)にも汎用性のある,公認心理師教育にふさわしいテキストの出版も希望したい。
書評者: 井村 修 (阪大教授・臨床心理学)
公認心理師法が2017年9月より施行される。心理職の国家資格がいよいよ誕生である。心理技術者の国家資格が検討され始め,約半世紀の紆余曲折を経て,ようやく実現した。日本の心理職もやっと国際水準に達したのだろうか。公認心理師法では,公認心理師の業務を以下のように規定している(公認心理師法第二条より)。
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察,その結果の分析
(2)心理に関する支援を要する者に対する,その心理に関する相談及び助言,指導その他の援助
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言,指導その他の援助
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
そして,これらの業務を,医療・保健,教育,福祉,司法・行政,産業などさまざまな分野で実践することが期待されている。とりわけ国家資格が前提の医療・保健分野では,心理職の国家資格化が待ち望まれていた。したがって,本書『公認心理師必携 精神医療・臨床心理の知識と技法』は,タイムリーな企画といえるだろう。
本書の特徴は総勢122名からなる多彩な執筆陣にある。精神医学と認知行動療法が基盤になってはいるが,精神医学の研究者から臨床医,臨床心理学の研究者から心理臨床の実践家まで幅広い。
また,第1部で「チーム医療と心理師の役割」,第2部で「精神医療の基本」,第3部で「精神医療システム」と医療に関するテーマが扱われ,第4部で「心理師の専門技能」,第5部で「問題別心理介入プロトコル」と,公認心理師としての業務と直結したテーマが扱われている。
第1~3部の中で,これまで心理学系の大学・大学院で教えられてきたことは,第4章「精神症状のみかた」と,第5章「診断とその経過」であり,その他の章の内容はほとんど教わっていない。精神科の病院に就職した卒業生から,医療の現場に行って驚いたことは,感染症予防の手洗いを指導されたことだと聞いたことがあった。第1章にはその手洗いが図解されている。医学の常識が心理の教育では十分でなかったことがわかる。
第7章の「薬物療法」の説明も有用である。処方用量例と副作用も示されているのでわかりやすい。ある程度の薬物療法の知識は,公認心理師がチーム医療を担うためには必要である。
本書の最大の特徴は第5部である。第17章の「抑うつ障害」を例に挙げると,まず抑うつ障害の総論があり,理論と心理的アプローチが解説されている,次に心理的アプローチのプロトコルが示され,症例提示,心理的アプローチの実際,本症例のまとめとなっている。わずか数ページではあるが,うつ病の心理的アプローチのエッセンスが記載されている。統合失調症スペクトラム障害や心身症など,他の精神障害に関する章も同じような形式になっている。
本書は,公認心理師を対象としたものではあるが,公認心理師をめざす大学生・大学院生も活用できる良書である。さらに,第4部と第5部は,精神医療において公認心理師が何ができるのかを示しており,精神科医や看護師に読んでいただければ,より質の高いチーム医療が可能となるだろう。
公認心理師カリキュラム格好の教科書
書評者: 黒木 俊秀 (九大大学院人間環境学研究院教授・臨床心理学)
わが国で初めての心理専門職の国家資格となる公認心理師は,平成29年度内の制度の施行を目前に控え,国家試験の受験資格となる教育カリキュラムの概要が間もなく発表される予定である。公認心理師養成のカリキュラムとこれまでの臨床心理士養成課程との最も大きな違いは,前者が学部(4年制大学)から始まる点であろう。学部において必要な単位を修得後,臨床心理士と同じく大学院(修士課程)を修了したものが基本のコースとなるが,学部卒業後に所定の施設において一定期間の実務経験を積んだ者にも受験資格が与えられる。いずれの場合でも,医療,福祉,教育,産業,司法といった心理専門職が必要とされる学外の現場における実習体験の比重が大きくなる。さまざまな領域で多職種との連携が求められる点も,従来,相談室臨床を基本に発展してきた臨床心理士との相違と言えるかもしれない。
以上のようにわが国の心理専門職のあり方が大きく変わろうとするこの時期に,「公認心理師必携」と題する本書は,まさに時宜を得た出版と言えるだろう。
本書は,「チーム医療と心理師の役割」「精神医療の基本」「精神医療システム」「心理師の専門技能」,および「問題別心理介入プロトコル」の5部から構成されている。特に第1部「チーム医療と心理師の役割」は,医療領域における公認心理師の立ち位置を理解する意味で重要と思われる。ここでは,現代の医療の特性や医療制度,医療の質,チーム医療,医療におけるメンタルヘルスなどが概説されるが,従来の臨床心理士教育が全く触れていなかった感染対策(手洗いの図説あり)や診療記録の書き方にも言及している。この箇所は新鮮に感じるが,公認心理師には他のコメディカル・スタッフと同等の「医療現場の常識」が求められるのであり,多職種連携という理念を具体化したものと言えよう。
また第3部「精神医療システム」も現行の精神保健サービスや法制度の説明に紙面を多く割いており,これも実務上役立つだろう。
さらに第5部「問題別心理介入プロトコル」は,各疾患・病態別に症例を提示し,公認心理師に可能な支援の実際を簡潔にまとめている。多彩な執筆陣による分担執筆の著作の例に漏れず,そのノウハウの記述には濃淡があるものの初学者はアウトラインを理解することができよう(ただし,原田誠一氏による最終章「プロトコルの適用が困難な事例への対応」(p.327)は経験豊富な現場のスタッフこそ必読すべきである)。
公認心理師カリキュラムの到達目標の中には“精神疾患とその治療”に関する理解の項目が設けられるようだが,今後,同カリキュラムにおいて学び,学外の医療機関において実習や実務経験を積もうとする人には本書は格好の教科書となり得るだろう。ただ,公認心理師は医療領域に特化した資格ではない。その他の領域(福祉,教育,産業,司法)にも汎用性のある,公認心理師教育にふさわしいテキストの出版も希望したい。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。