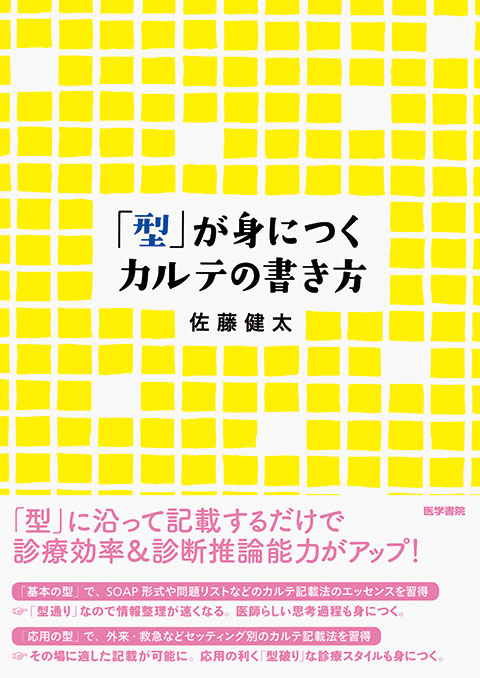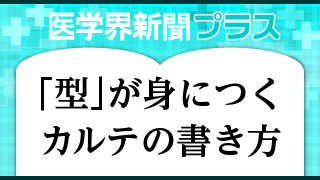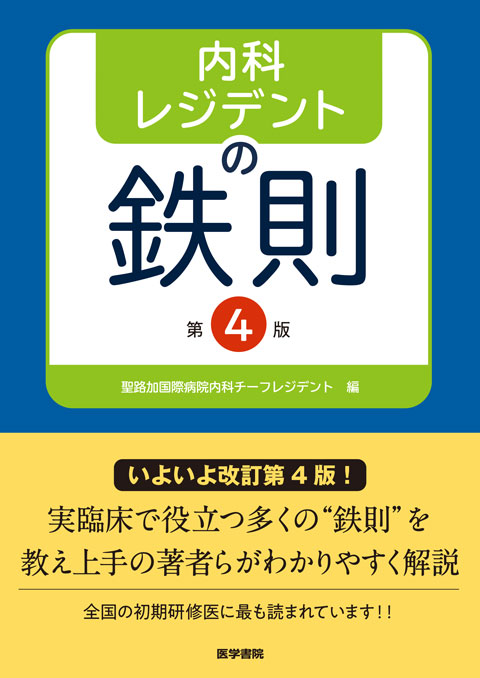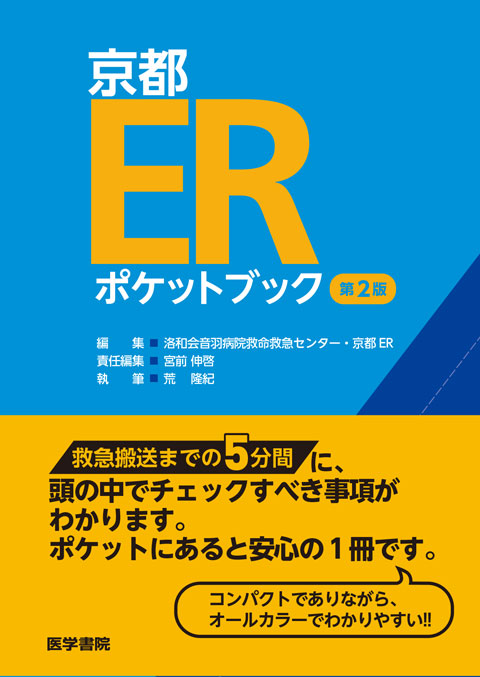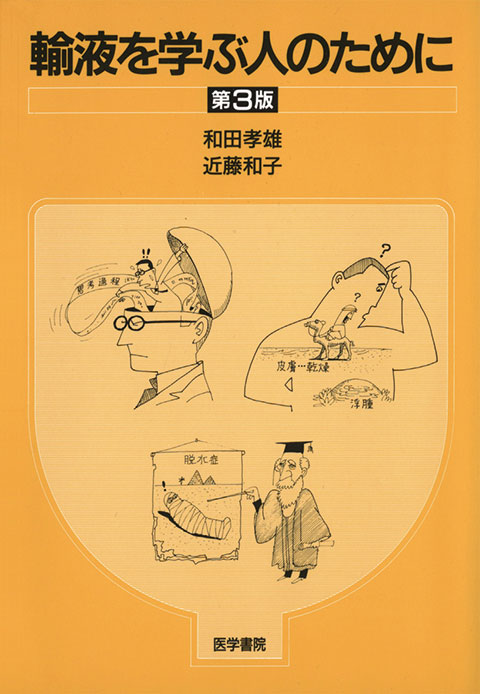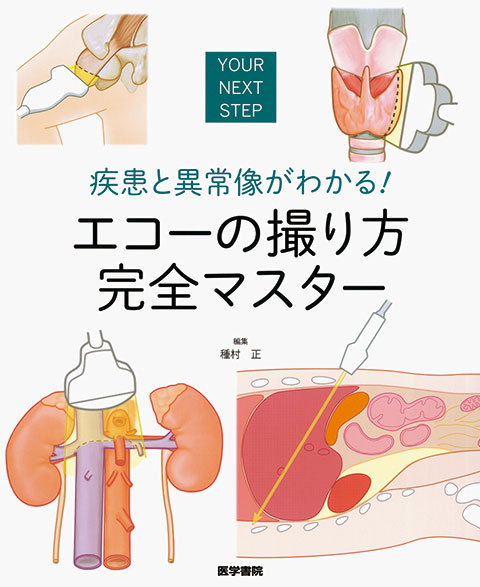「型」が身につくカルテの書き方
「型」に沿って記載するだけで診療効率&診断推論能力がアップする!
もっと見る
「週刊医学界新聞」 の人気連載を書籍化。「基本の型」の部で、SOAP形式や問題リストなどのカルテ記載法のエッセンスを習得(⇒医師らしい思考過程も身につく)。「応用の型」の部で、外来・救急などセッティング別のカルテ記載法を習得(⇒応用の利く「型破り」な診療スタイルも身につく)。「型ができていない者が芝居をすると型なしになる。型がしっかりした奴がオリジナリティを押し出せば型破りになれる」(by 立川談志)。
| 著 | 佐藤 健太 |
|---|---|
| 発行 | 2015年04月判型:B5頁:140 |
| ISBN | 978-4-260-02106-7 |
| 定価 | 3,080円 (本体2,800円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
はじめに
総合診療医の佐藤健太と申します。医学教育の専門家でも,ましてやカルテ記載法の大家でもない,市中病院の一臨床医ですが,自分なりに「よいカルテ」を追求し,試行錯誤してきました。カルテに関してはちょっとこだわりのある指導医です。
医師ならばカルテをきちんと書くことの重要性は認識しているはずですが,「どうしたら上達するのか?」と聞かれると答えられないのではないでしょうか。毎日なんとなく書いては頭を悩ませているのかもしれません。私もかつてはそうでした。
私が「カルテの書き方」に向きあい始めたのは医学部4年生のときで,もう10年以上も前になります。OSCE(Objective Structured Clinical Examination:客観的臨床能力試験)対策の一環として,カルテの書き方を勉強しようとしたのですが,書店では適当な書籍が見つからず,学内で配布されたOSCEのテキストで該当箇所だけを読んで済ませました。5年生になり臨床実習に出てみると,「達筆すぎて解読不能」「SOAPにのっとっていない」「病名も方針も書いていない」カルテばかりで良いお手本が見当たりません。また,学生にカルテ記載の権限がない科も多く,たまに書く機会に恵まれても書き方を教えてもらうことはありませんでした。
そんなとき,大学の枠を超えて医学生が参加するメーリングリスト(college-med)を先輩に紹介されました。そこは,提示された症例に対して医学生が鑑別診断や検査・治療プランを提示し,全国の教育熱心な臨床医からフィードバックがもらえるという夢のような環境でした。そして,特に目を引く学生の投稿を読んでいると,知識量や発想がすごいというだけではなく,記載様式がわかりやすく思考過程が読み取りやすいことに気付いたのです。この経験から「きちんとカルテを書くことによって論理的思考力が身につき,診断能力を高められる。思考過程が相手に伝わりやすいため,適切な指導を受けることもできる」という期待感と,「大学内で学べないことはWebで学べばよい」というヒントを得ました。Web検索で「内科学研鑽会」のサイトを見つけ,そこで紹介されていた「総合プロブレム方式」を毎晩少しずつ勉強してカルテの書き方を身につけました。
その後実際に医師として働き始め,原則論だけでは対応できない状況もたくさん経験しました。初期研修開始初日に担当した急性腎盂腎炎の患者では,総合プロブレム方式にのっとって入院記録を書いたところ,「プロブレム15個,A4サイズの紙カルテで7頁」の長編となってしまいました。指導医からは「長すぎる」というコメントだけで中身についての言及はなく,看護師からも苦笑いしかありませんでした(今思うと当然です)。その後,同期や指導医のカルテを読んだり他職種からフィードバックをもらったりしながら改善を重ね,家庭医療学や医学教育学のエッセンスも取り入れつつ,後期研修が修了するころにようやく現在のカルテ記載法にたどり着きました。
そのうち,指導医としてカルテ記載法を研修医に教える機会が増えました。教えても理解できない研修医や,基本的な考え方は理解できても実際に書くことはできない研修医にたくさん出会いました。それでも根気強く,カルテ記載が上手な研修医とそうでない研修医の性格や学習スタイルの特徴,書き方の違いなどを観察していく中で,「教え方」についても一定の方法論を見いだせるようになりました。現在は,基本的なポイントをレクチャーし,その後定期的にカルテをチェックしていくことによって,ほとんどの研修医がわかりやすいカルテを書けるようになるだけでなく,情報収集や診断推論の能力まで伸びるように感じています。
こうやって私が10年かけて見いだしたカルテ記載法とその指導法をベースに,本書を執筆しました。「週刊医学界新聞」の連載記事(2012年から全13回)を元に大幅な加筆修正を行っています。
全体は,「基本の型」と「応用の型」の2部構成になっています。「基本の型」では,あらゆるセッティングに応用可能な,カルテ記載法のエッセンスを解説します。次の「応用の型」では,外来/救急などセッティング別のカルテ記載方法について学び,明日から実践可能な「型」を解説します。さらに「おまけの型」では,病棟患者管理シートなどカルテ以外の「型」を収録しています。カルテにまつわる小ネタはColumnで触れているので,学生や研修医を指導する際に使えるトリビアも得られるでしょう。
なお,病歴聴取法や身体診察法もカルテの書き方と密接に関わってきますが,全てをカバーすると膨大な頁数になってしまうため,「カルテを書く」ことに直結する内容に絞りました。一方で,私の専門領域である総合診療医学や家庭医療学などは幅広く複雑な問題を扱うための枠組みを提供してくれるため,折に触れてその考え方を提示しています。
皆さんの周りにカルテの書き方を教えてくれる指導医がいなくても,ある程度までは独学で到達できるように様々な工夫を凝らしています。できれば順を追って,読み進めていただければ幸いです。
2015年3月吉日
佐藤健太
総合診療医の佐藤健太と申します。医学教育の専門家でも,ましてやカルテ記載法の大家でもない,市中病院の一臨床医ですが,自分なりに「よいカルテ」を追求し,試行錯誤してきました。カルテに関してはちょっとこだわりのある指導医です。
医師ならばカルテをきちんと書くことの重要性は認識しているはずですが,「どうしたら上達するのか?」と聞かれると答えられないのではないでしょうか。毎日なんとなく書いては頭を悩ませているのかもしれません。私もかつてはそうでした。
私が「カルテの書き方」に向きあい始めたのは医学部4年生のときで,もう10年以上も前になります。OSCE(Objective Structured Clinical Examination:客観的臨床能力試験)対策の一環として,カルテの書き方を勉強しようとしたのですが,書店では適当な書籍が見つからず,学内で配布されたOSCEのテキストで該当箇所だけを読んで済ませました。5年生になり臨床実習に出てみると,「達筆すぎて解読不能」「SOAPにのっとっていない」「病名も方針も書いていない」カルテばかりで良いお手本が見当たりません。また,学生にカルテ記載の権限がない科も多く,たまに書く機会に恵まれても書き方を教えてもらうことはありませんでした。
そんなとき,大学の枠を超えて医学生が参加するメーリングリスト(college-med)を先輩に紹介されました。そこは,提示された症例に対して医学生が鑑別診断や検査・治療プランを提示し,全国の教育熱心な臨床医からフィードバックがもらえるという夢のような環境でした。そして,特に目を引く学生の投稿を読んでいると,知識量や発想がすごいというだけではなく,記載様式がわかりやすく思考過程が読み取りやすいことに気付いたのです。この経験から「きちんとカルテを書くことによって論理的思考力が身につき,診断能力を高められる。思考過程が相手に伝わりやすいため,適切な指導を受けることもできる」という期待感と,「大学内で学べないことはWebで学べばよい」というヒントを得ました。Web検索で「内科学研鑽会」のサイトを見つけ,そこで紹介されていた「総合プロブレム方式」を毎晩少しずつ勉強してカルテの書き方を身につけました。
その後実際に医師として働き始め,原則論だけでは対応できない状況もたくさん経験しました。初期研修開始初日に担当した急性腎盂腎炎の患者では,総合プロブレム方式にのっとって入院記録を書いたところ,「プロブレム15個,A4サイズの紙カルテで7頁」の長編となってしまいました。指導医からは「長すぎる」というコメントだけで中身についての言及はなく,看護師からも苦笑いしかありませんでした(今思うと当然です)。その後,同期や指導医のカルテを読んだり他職種からフィードバックをもらったりしながら改善を重ね,家庭医療学や医学教育学のエッセンスも取り入れつつ,後期研修が修了するころにようやく現在のカルテ記載法にたどり着きました。
そのうち,指導医としてカルテ記載法を研修医に教える機会が増えました。教えても理解できない研修医や,基本的な考え方は理解できても実際に書くことはできない研修医にたくさん出会いました。それでも根気強く,カルテ記載が上手な研修医とそうでない研修医の性格や学習スタイルの特徴,書き方の違いなどを観察していく中で,「教え方」についても一定の方法論を見いだせるようになりました。現在は,基本的なポイントをレクチャーし,その後定期的にカルテをチェックしていくことによって,ほとんどの研修医がわかりやすいカルテを書けるようになるだけでなく,情報収集や診断推論の能力まで伸びるように感じています。
こうやって私が10年かけて見いだしたカルテ記載法とその指導法をベースに,本書を執筆しました。「週刊医学界新聞」の連載記事(2012年から全13回)を元に大幅な加筆修正を行っています。
全体は,「基本の型」と「応用の型」の2部構成になっています。「基本の型」では,あらゆるセッティングに応用可能な,カルテ記載法のエッセンスを解説します。次の「応用の型」では,外来/救急などセッティング別のカルテ記載方法について学び,明日から実践可能な「型」を解説します。さらに「おまけの型」では,病棟患者管理シートなどカルテ以外の「型」を収録しています。カルテにまつわる小ネタはColumnで触れているので,学生や研修医を指導する際に使えるトリビアも得られるでしょう。
なお,病歴聴取法や身体診察法もカルテの書き方と密接に関わってきますが,全てをカバーすると膨大な頁数になってしまうため,「カルテを書く」ことに直結する内容に絞りました。一方で,私の専門領域である総合診療医学や家庭医療学などは幅広く複雑な問題を扱うための枠組みを提供してくれるため,折に触れてその考え方を提示しています。
皆さんの周りにカルテの書き方を教えてくれる指導医がいなくても,ある程度までは独学で到達できるように様々な工夫を凝らしています。できれば順を追って,読み進めていただければ幸いです。
2015年3月吉日
佐藤健太
目次
開く
基本の型
基本の型を身につけよう
1 カルテ記載の心構え
2 SOAP(1) SとO
3 SOAP(2) A
4 SOAP(3) P
応用の型
応用の型を身につけよう
5 病棟編(1) 入院時記録
6 病棟編(2) 経過記録
7 病棟編(3) 退院時要約
8 外来編(1) 初診外来
9 外来編(2) 継続外来
10 訪問診療
11 救急外来
12 集中治療
おまけの型
13 病棟患者管理シート
14 診療情報提供書
column
意味のある情報,意味のない情報
シャープ? ナンバー?
プレゼンテーションスキル
カルテの歴史と法
退院時要約に書く項目の要件
カルテの語源
訪問診療と往診は何が違う?
電子カルテの特性を生かしたカルテ記載のコツ
おわりに
索引
基本の型を身につけよう
1 カルテ記載の心構え
2 SOAP(1) SとO
3 SOAP(2) A
4 SOAP(3) P
応用の型
応用の型を身につけよう
5 病棟編(1) 入院時記録
6 病棟編(2) 経過記録
7 病棟編(3) 退院時要約
8 外来編(1) 初診外来
9 外来編(2) 継続外来
10 訪問診療
11 救急外来
12 集中治療
おまけの型
13 病棟患者管理シート
14 診療情報提供書
column
意味のある情報,意味のない情報
シャープ? ナンバー?
プレゼンテーションスキル
カルテの歴史と法
退院時要約に書く項目の要件
カルテの語源
訪問診療と往診は何が違う?
電子カルテの特性を生かしたカルテ記載のコツ
おわりに
索引
書評
開く
医療行動科学を包括した画期的なカルテ記載テキスト
書評者: 長谷川 仁志 (秋田大大学院教授・医学教育学)
医学教育の国際認証時代に入り,基礎医学・臨床医学および医療行動科学が十分に統合された医学生への教育の提供と,それによる基本的診療能力のパフォーマンスレベルでの質保証が必須となってきた。診療参加型実習(クリニカル・クラークシップ)の充実が強く求められている日本で,しっかりと熟考されたカルテ記載能力の修得は,まさに医学教育の集大成となる目標の一つである。しかし,現時点で,カルテ記載教育は必ずしも充実しておらず,学生・研修医と各科指導医の双方における日本の課題となっている。私は,1年次からカルテ記載について学習することが,基礎医学,臨床医学および医療行動科学を十分に統合して学ぶべき医学生の目標設定となり,医学学習のモチベーションにつながると考えた。そして,数年前から担当している1年次通年の医療面接・臨床推論学習に,模擬患者による医療面接OSCEとともに,カルテ記載を取り入れてきた経緯もあり,本テキストを楽しみに読ませていただいた。
本書は前半で,カルテ記載の「基本の型」として,あらゆる診療科の基本となるべきSOAP(S:Subjective data, O:Objective data, A:Assessment, P:Plan)に沿った詳細なポイントを,良い例,悪い例を比較して提示しながら解説している。特に,「S・O以上に書くべき内容や,記載形式が曖昧で,医師によって書き方の違いが大きい」とされ,書き方や指導に悩む医師が多いAについても,実際の場面やS・Oと関連付けて説明する工夫により,わかりやすく記載されている。後半では,「応用の型」として,実際の臨床現場における「入院時記録」から「経過記録」「退院時要約」「初診外来」「継続外来」までのみならず,「訪問診療」「救急外来」「集中治療」にわたる各セッティング場面におけるカルテ記載のポイントを説明している。その際,初めのところで「診察・カルテ記載に使える時間」「事前情報・問題リストの量」「患者の重症度」「患者の関心」「多職種の関心」などの医療行動科学の重要な視点から成る「各セッティングの特徴一覧」を表で記載し,その後の各セッティングのページで,それぞれの詳細を実際のカルテ例,図表,Q&A,まとめ,column等を豊富に使って解説している。さらに,最後の「おまけの型」では,「病棟患者管理シート」「診療情報提供書」にまで言及している。
全般を通して,著者の日々の臨床経験や指導医としての経験から,ポイントや疑問点を中心にコンパクトにしっかりと解説されており,熱意が十分伝わってくるテキストであると感じた。特に,その内容の多くが,カルテ記載や指導に悩む医師への基本的なポイント指導のみならず,上記の各セッティング場面ごとに,常に患者・家族や医療者(チーム)の意識を十分考慮した目線での記載ポイントを細やかに解説していることに非常に感銘を受けた。すなわち,初めに述べたように基礎や臨床医学の能力のみならず,日本でようやく重要視されてきた医療行動科学の教育にも通じる内容が十分に散りばめられている画期的なテキストといえる。あらゆる場面で医療行動科学を意識して学習・教育すべき医学生から,研修医,若手~ベテランの指導医まで,カルテ記載およびその教育に携わるすべての医師がぜひ一読する価値の高いものと感じた。また,私自身,今後,本テキストを研修医や各科指導医に推奨するとともに,前述の1年次の学習から学年横断的に使っていきたいと考えている。
コミュニケーションと思考訓練の場としてのカルテ
書評者: 藤沼 康樹 (医療福祉生協連家庭医療学開発センター長/千葉大大学院看護学研究科附属専門職連携教育研究センター特任講師)
これまで寡聞にして,カルテ記載に関してフォーマルな医学教育カリキュラムはあまり目にしたことがない。むろんいわゆるPOSシステムにおけるSOAP(主観的情報,客観的情報,評価,診療計画)に分けて記載することはよく普及しているが,その意味はあまり知られていない。
本書の特徴は,医学教育における医師の成長段階としてのRIMEモデル(Reporter→Interpreter→Manager→Educator)とSOAP(Subjective, Objective, Assessment, Plan)を対応させて,診療記録を教育や診療の質改善と結び付けているところにある。そして,これまでは単に“患者の訴えを書く領域”とされていたSOAPにおける「S」を「間接的に得られた情報」,“診察や検査結果を記載する領域”とされていた「O」を「直接観察による所見」と明快に定義し直している(これらの情報をどう集めるかは診療の場によって違うことも強調されている)。アセスメントの「A」はしばしば問題リストや異常値の羅列になるが,これを「意見」と定義し,省察のもとに自身の考えを記載する場としている。このアセスメント「A」に意見を論理的に記載すること自体が,臨床推論能力の訓練そのものになるであろう。それに基づき診療計画「P」を記載するが,ここに含まれる内容として予防や退院調整,介護福祉サービスを重視しているところが,著者の総合診療医らしさを感じる。
著者は,診療所における地域ケアや在宅診療から,大規模総合病院まで非常に幅広い場での診療経験があり,本書における診療の場(病棟,外来,訪問診療,救急,ICU)ごとのカルテ記載の記述は圧巻である。恐らくこれだけのバリエーションのある診療現場における診療情報に関して深い洞察ができる医師はそうそういないし,分担執筆になりがちなこうしたテーマを単著として完成させた著者に敬意を評したい。
今後の日本のヘルスケアシステムの大きな課題が連携であり,カルテがそのためのコミュニケーションの重要な結節点になるであろう。若い研修医だけでなく,自身の診療の質の向上をめざしている全ての臨床医に一読を勧めたいと思う。
ありそうでなかった「カルテ記載のランドマーク的書籍」
書評者: 志水 太郎 (東京城東病院総合内科)
本書は,医学部を卒業して研修医となり,医師として初めて取り組む大事な仕事の一つ,カルテやその他の重要書類の書き方を示した本である。研修医がつまずきやすい箇所に関して,わかりやすい言い回しと例文を交えながら,順を追って丁寧に解説されており,著者の佐藤健太先生の指導医としてのお人柄,現場でのお仕事ぶりが透けて見えるようだ。
内容は,「基本の型」「応用の型」「おまけの型」の3部構成となっている。
「基本の型」の第1章「カルテ記載の心構え」では,繰り返し練習して「基本の型」を身につける重要性に話は始まり,「ダメなカルテ」と「良いカルテ」の実例を用いながら,「良いカルテ」を書く上での大切なポイントが「全体像が一発でつかめる一文を入れる」などのコツとともに説明されている。「良いカルテ」を書くことによって実際にどのように自分が成長していけるのかの道筋も示されており,カルテの書き方を習得することのゴールが見えるため,研修医のモチベーションも上がりそうである。2章からは,SOAPの各項目の解説に入る。例えば,Sの時制は過去形でOは現在形にすること,各欄に何をどのような順番で書けばよいのか,「方針(A)と計画(P)は別物」など,実際にカルテを書いていくと研修医がぶつかる壁を踏まえて解説されている。
「応用の型」の部では,入院診療(入院初日・入院翌日以降・退院前後)外来診療(初診外来・継続外来),訪問診療,救急外来,集中治療のカルテの書き方に分かれている。それぞれのセッティングに応じた書き方や重点の置き方が記されている実践編であり,本書を一冊持っていればいつでも,より良いカルテの書き方のアドバイスを受けることができそうである。
さらに「おまけの型」の部では,著者が普段使っているという「病棟患者管理シート」や,すべての研修医が書かなければならない「診療情報提供書」の書き方についてもヒントを得ることができる。
カルテを書くことは医師の基本業務であり,だからこそ,その方法をしっかり学べば,医師間だけではなく,その他の医療従事者との仕事やコミュニケーションも円滑になる。俯瞰的かつ網羅的であり,ありそうでなかった「カルテ記載のランドマーク的な書籍」になると言っても過言ではない。かく言う私も研修医に勧めている,お勧めの一冊である。
書評者: 長谷川 仁志 (秋田大大学院教授・医学教育学)
医学教育の国際認証時代に入り,基礎医学・臨床医学および医療行動科学が十分に統合された医学生への教育の提供と,それによる基本的診療能力のパフォーマンスレベルでの質保証が必須となってきた。診療参加型実習(クリニカル・クラークシップ)の充実が強く求められている日本で,しっかりと熟考されたカルテ記載能力の修得は,まさに医学教育の集大成となる目標の一つである。しかし,現時点で,カルテ記載教育は必ずしも充実しておらず,学生・研修医と各科指導医の双方における日本の課題となっている。私は,1年次からカルテ記載について学習することが,基礎医学,臨床医学および医療行動科学を十分に統合して学ぶべき医学生の目標設定となり,医学学習のモチベーションにつながると考えた。そして,数年前から担当している1年次通年の医療面接・臨床推論学習に,模擬患者による医療面接OSCEとともに,カルテ記載を取り入れてきた経緯もあり,本テキストを楽しみに読ませていただいた。
本書は前半で,カルテ記載の「基本の型」として,あらゆる診療科の基本となるべきSOAP(S:Subjective data, O:Objective data, A:Assessment, P:Plan)に沿った詳細なポイントを,良い例,悪い例を比較して提示しながら解説している。特に,「S・O以上に書くべき内容や,記載形式が曖昧で,医師によって書き方の違いが大きい」とされ,書き方や指導に悩む医師が多いAについても,実際の場面やS・Oと関連付けて説明する工夫により,わかりやすく記載されている。後半では,「応用の型」として,実際の臨床現場における「入院時記録」から「経過記録」「退院時要約」「初診外来」「継続外来」までのみならず,「訪問診療」「救急外来」「集中治療」にわたる各セッティング場面におけるカルテ記載のポイントを説明している。その際,初めのところで「診察・カルテ記載に使える時間」「事前情報・問題リストの量」「患者の重症度」「患者の関心」「多職種の関心」などの医療行動科学の重要な視点から成る「各セッティングの特徴一覧」を表で記載し,その後の各セッティングのページで,それぞれの詳細を実際のカルテ例,図表,Q&A,まとめ,column等を豊富に使って解説している。さらに,最後の「おまけの型」では,「病棟患者管理シート」「診療情報提供書」にまで言及している。
全般を通して,著者の日々の臨床経験や指導医としての経験から,ポイントや疑問点を中心にコンパクトにしっかりと解説されており,熱意が十分伝わってくるテキストであると感じた。特に,その内容の多くが,カルテ記載や指導に悩む医師への基本的なポイント指導のみならず,上記の各セッティング場面ごとに,常に患者・家族や医療者(チーム)の意識を十分考慮した目線での記載ポイントを細やかに解説していることに非常に感銘を受けた。すなわち,初めに述べたように基礎や臨床医学の能力のみならず,日本でようやく重要視されてきた医療行動科学の教育にも通じる内容が十分に散りばめられている画期的なテキストといえる。あらゆる場面で医療行動科学を意識して学習・教育すべき医学生から,研修医,若手~ベテランの指導医まで,カルテ記載およびその教育に携わるすべての医師がぜひ一読する価値の高いものと感じた。また,私自身,今後,本テキストを研修医や各科指導医に推奨するとともに,前述の1年次の学習から学年横断的に使っていきたいと考えている。
コミュニケーションと思考訓練の場としてのカルテ
書評者: 藤沼 康樹 (医療福祉生協連家庭医療学開発センター長/千葉大大学院看護学研究科附属専門職連携教育研究センター特任講師)
これまで寡聞にして,カルテ記載に関してフォーマルな医学教育カリキュラムはあまり目にしたことがない。むろんいわゆるPOSシステムにおけるSOAP(主観的情報,客観的情報,評価,診療計画)に分けて記載することはよく普及しているが,その意味はあまり知られていない。
本書の特徴は,医学教育における医師の成長段階としてのRIMEモデル(Reporter→Interpreter→Manager→Educator)とSOAP(Subjective, Objective, Assessment, Plan)を対応させて,診療記録を教育や診療の質改善と結び付けているところにある。そして,これまでは単に“患者の訴えを書く領域”とされていたSOAPにおける「S」を「間接的に得られた情報」,“診察や検査結果を記載する領域”とされていた「O」を「直接観察による所見」と明快に定義し直している(これらの情報をどう集めるかは診療の場によって違うことも強調されている)。アセスメントの「A」はしばしば問題リストや異常値の羅列になるが,これを「意見」と定義し,省察のもとに自身の考えを記載する場としている。このアセスメント「A」に意見を論理的に記載すること自体が,臨床推論能力の訓練そのものになるであろう。それに基づき診療計画「P」を記載するが,ここに含まれる内容として予防や退院調整,介護福祉サービスを重視しているところが,著者の総合診療医らしさを感じる。
著者は,診療所における地域ケアや在宅診療から,大規模総合病院まで非常に幅広い場での診療経験があり,本書における診療の場(病棟,外来,訪問診療,救急,ICU)ごとのカルテ記載の記述は圧巻である。恐らくこれだけのバリエーションのある診療現場における診療情報に関して深い洞察ができる医師はそうそういないし,分担執筆になりがちなこうしたテーマを単著として完成させた著者に敬意を評したい。
今後の日本のヘルスケアシステムの大きな課題が連携であり,カルテがそのためのコミュニケーションの重要な結節点になるであろう。若い研修医だけでなく,自身の診療の質の向上をめざしている全ての臨床医に一読を勧めたいと思う。
ありそうでなかった「カルテ記載のランドマーク的書籍」
書評者: 志水 太郎 (東京城東病院総合内科)
本書は,医学部を卒業して研修医となり,医師として初めて取り組む大事な仕事の一つ,カルテやその他の重要書類の書き方を示した本である。研修医がつまずきやすい箇所に関して,わかりやすい言い回しと例文を交えながら,順を追って丁寧に解説されており,著者の佐藤健太先生の指導医としてのお人柄,現場でのお仕事ぶりが透けて見えるようだ。
内容は,「基本の型」「応用の型」「おまけの型」の3部構成となっている。
「基本の型」の第1章「カルテ記載の心構え」では,繰り返し練習して「基本の型」を身につける重要性に話は始まり,「ダメなカルテ」と「良いカルテ」の実例を用いながら,「良いカルテ」を書く上での大切なポイントが「全体像が一発でつかめる一文を入れる」などのコツとともに説明されている。「良いカルテ」を書くことによって実際にどのように自分が成長していけるのかの道筋も示されており,カルテの書き方を習得することのゴールが見えるため,研修医のモチベーションも上がりそうである。2章からは,SOAPの各項目の解説に入る。例えば,Sの時制は過去形でOは現在形にすること,各欄に何をどのような順番で書けばよいのか,「方針(A)と計画(P)は別物」など,実際にカルテを書いていくと研修医がぶつかる壁を踏まえて解説されている。
「応用の型」の部では,入院診療(入院初日・入院翌日以降・退院前後)外来診療(初診外来・継続外来),訪問診療,救急外来,集中治療のカルテの書き方に分かれている。それぞれのセッティングに応じた書き方や重点の置き方が記されている実践編であり,本書を一冊持っていればいつでも,より良いカルテの書き方のアドバイスを受けることができそうである。
さらに「おまけの型」の部では,著者が普段使っているという「病棟患者管理シート」や,すべての研修医が書かなければならない「診療情報提供書」の書き方についてもヒントを得ることができる。
カルテを書くことは医師の基本業務であり,だからこそ,その方法をしっかり学べば,医師間だけではなく,その他の医療従事者との仕事やコミュニケーションも円滑になる。俯瞰的かつ網羅的であり,ありそうでなかった「カルテ記載のランドマーク的な書籍」になると言っても過言ではない。かく言う私も研修医に勧めている,お勧めの一冊である。