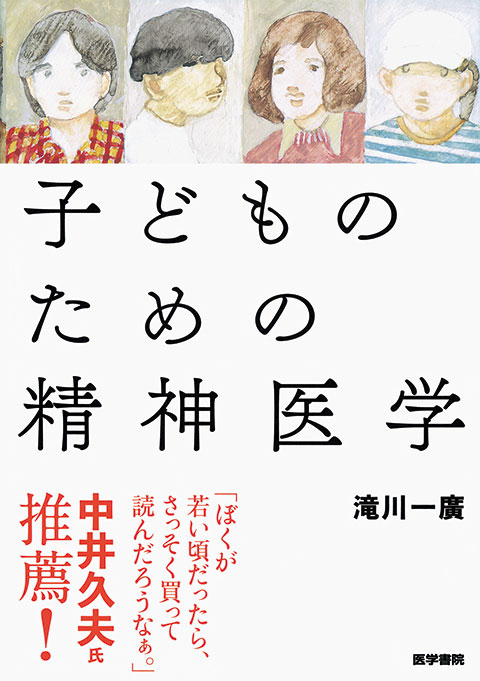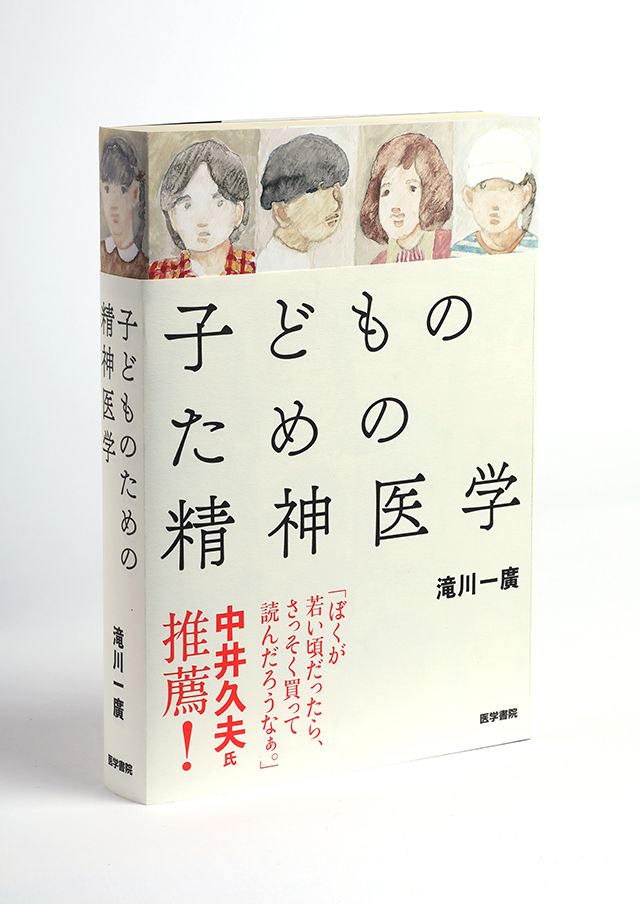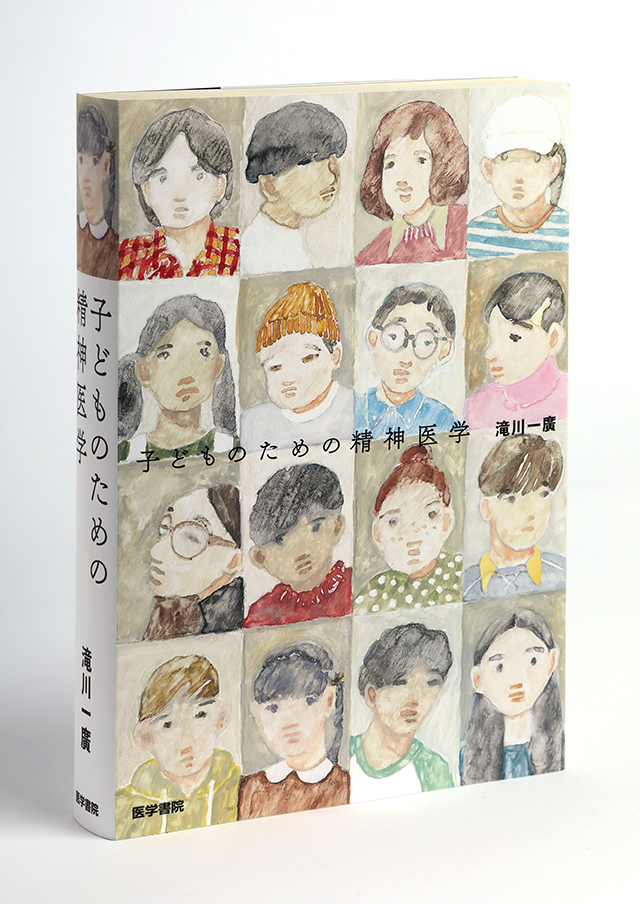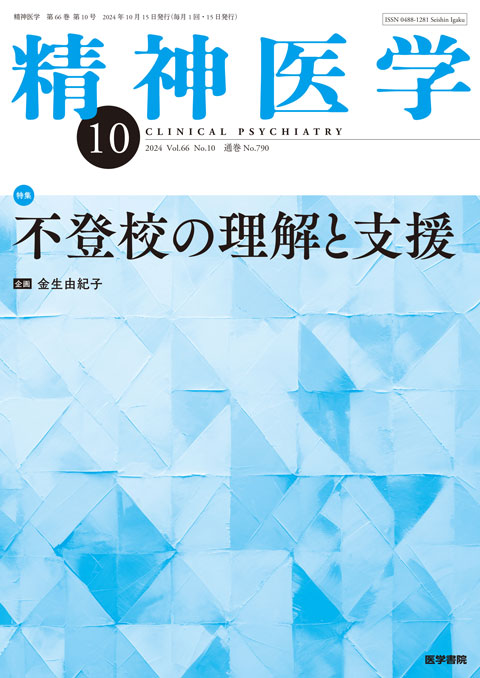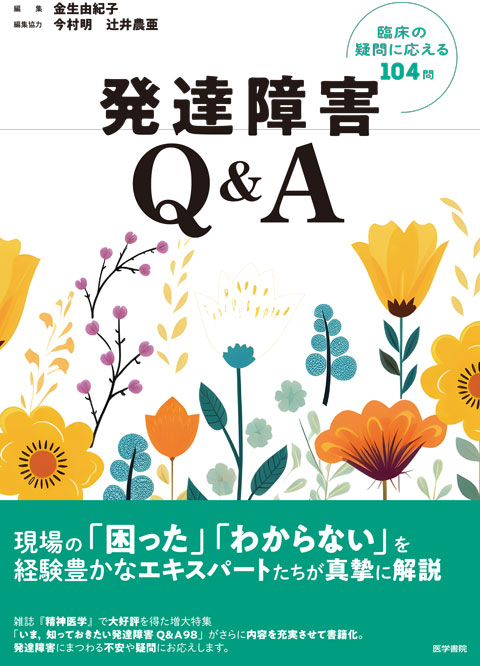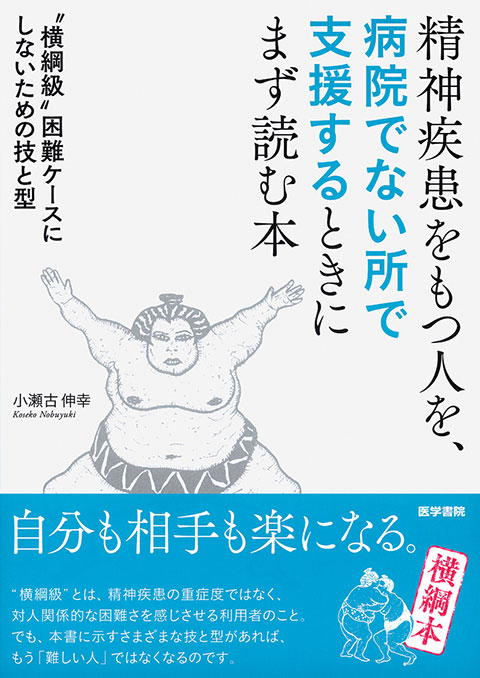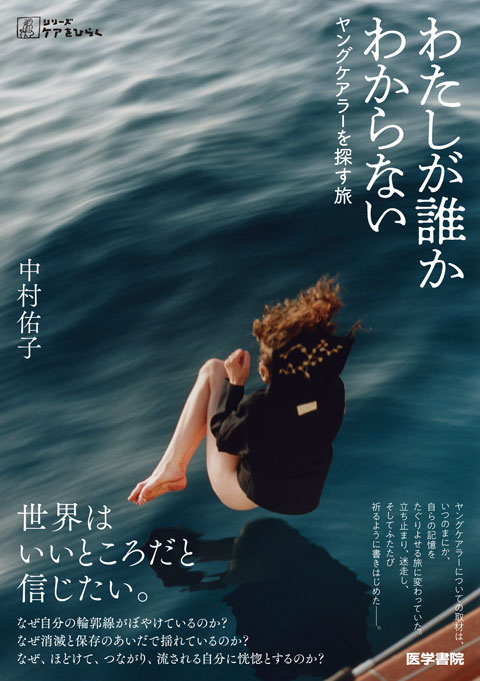子どものための精神医学
素手で読める児童精神医学の「基本書」。子どもの〈こころ〉にかかわるすべての人へ
もっと見る
発達障害? アスペルガー症候群? 知的障害? 自閉症? ADHD? LD? ところでスペクトラムって何?-本書を読めば、錯綜する診断名を「認識と関係の座標軸」のもとに一望できるようになる。読めば分かるように書いてある、ありそうでなかった児童精神医学の基本書。事例の機微をすくい上げる繊細な筆さばき、理論と実践の生き生きとした融合、そして無類の面白さ! マニュアルでは得られない「納得」がここに。
●新聞で紹介されました! 《463ページにも及ぶ分厚い専門書なのに、興奮しながら一気に読み切った。タイトルには精神医学とあるが、内容は「何かにつまずく全ての子ども」についての考察と助言だ。》―鈴木大介(ルポライター) (共同通信社配信、『熊本日日新聞』2017年5月14日 書評欄、ほか) 《著者は、日本を代表する児童精神科医の一人。育つ側の難しさを語りつつ、育てる側の難しさも平等にフォローした。》 (『読売新聞』2017年4月26日より) 《〈疾患〉ではなく〈障害〉と言われる概念の理解に主眼をおき、教員・保育士・看護師・心理士向けにわかりやすく解説する。》 (『東京新聞』2017年6月18日より)
●雑誌で紹介されました! 《児童精神科医学者である著者は五十年間の研究の末、子どもの「精神発達の座標軸」を発見した。その原理と実践をつないで体系化したのが本書だ。》―本田哲也(toBe塾主宰) (『児童心理』2017年8月号 BOOK REVIEWより) 《この書物は、児童精神医学の教科書ではない。しかし、その道へ進みつつある臨床家に向けての教導書ではある。》―清水將之(三重県立看護大学理事) (『こころの科学』2017年7月号、BOOKS ほんとの対話より)
| 著 | 滝川 一廣 |
|---|---|
| 発行 | 2017年04月判型:A5頁:464 |
| ISBN | 978-4-260-03037-3 |
| 定価 | 2,750円 (本体2,500円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
- 正誤表
序文
開く
この本では、子どもの精神障害を扱う。
とはいっても、「児童精神医学」の網羅的な教科書や啓蒙的な解説書をめざす本ではない。日々の暮らしのなかで子どもたちと直接かかわる人たち-教員、保育士、看護師、心理士などをはじめ、さまざまな子どもにかかわる職域にある人びと、そしてもちろん親たち-にとって、子どものこころの病気や失調、障害を理解したりケアしたりするために役だつことをめざす本である。子どもの診療にあずかる医師にも役にたてばと願っている。
その目的のため、この本は次の3つの観点を基本にしている。
(1)子どもとは育ちつつあるもの、成長途上の存在である。
子どもはそだちのさなかにある、身体的にも精神的にも。だから、子どもの精神障害に対しては、いまある状態を横断的にとらえるだけでなく「精神発達」の流れをたどって縦断的にとらえないかぎり、十分に理解することもケアの道を探ることもできない。それに加え、本書は、狭い意味での「医療」にあずかる人たちばかりでなく、先に述べたような人びと、なんらかのかたちで子どもたちの「そだち」「育み」にかかわる人たちを頭においている。
そこでこの本では、こころの成長、精神発達という軸のなかで子どもの精神障害を考えていきたい。これが、この本の縦軸となる。
(2)子どもとは社会のなかを生きている存在である。
子どもは「社会の鏡」「時代の鏡」といわれる。その社会のあり方や時代の変化を鋭敏に映しだしながら、子どもは生きている。だから、子どもの精神障害を、その子個人のなかにある問題としてばかりとらえるのでなく、社会的・文化的な視野のなかでとらえることが不可欠である。実際、私たちの社会では、子どもの精神的な問題は、しばしば「社会問題」としてクローズアップされてくる。
それに加え、(1)にあげた精神発達というプロセス自体、一個の生物体(個体)として生まれ落ちた子どもが社会的・文化的な共同存在へと育まれていくプロセスなのである。その観点からも社会・文化の問題ははずせない。
そこでこの本では、社会・文化という軸のなかで子どもの精神障害を考えていきたい。これが、この本の横軸となる。
(3)子どもの育みもケアも、マニュアルどおりにはいかない。
人生とは一人ひとりに個別的であり、しかも一回かぎりのものである。子育てとは、そうしたとりかえのきかぬ人生でのかかわりである。こうすればかならずOKという模範解答はない。太郎くんでこうだったから次郎くんでもこう、とはかぎらない。
この本では、できるだけ具体的・実践的に考えていくけれども、ハウツー的な「マニュアル」やマスターキーのような「公式」を示すものではない。それよりも、子どもというもの、子どもの精神障害というものへの「基本的な考え方」や「基本的なかかわりの姿勢」を、一回かぎりの人生を歩みはじめている子どもたちとのかかわりに生かせるかたちで伝えられたらと願う。
「基本」とは要点やさわりではない。基本的に考えるとは、基や本から考えること、土台から考えを積むことである。実践に役にたつ土台を提供するのがこの本の大きな目的で、しっかりした土台さえあれば、臨機応変や応用が可能。マニュアルやハウツーは、そこに書かれたことしかできず、臨機応変や応用が効かない。急ぐ読者にはもどかしいかもしれないけれども、ていねいに土台から積んでいきたい。
目次
開く
第1章 〈こころ〉をどうとらえるか
1 哲学にとっての〈こころ〉、科学にとっての〈こころ〉
2 精神医学にとっての〈こころ〉
3 日常生活にとっての〈こころ〉
4 〈こころ〉は共同の世界
5 「精神障害」という〈こころ〉のあり方
第2章 「精神医学」とはどんな学問か
1 精神医学の誕生
2 精神医学の黎明期
3 精神医学は「理系」か「文系」か
4 正統精神医学
5 力動精神医学
6 児童精神医学のはじまり
第3章 精神障害の分類と診断
1 分類とはどういうものか
2 伝統的な診断分類
3 操作的診断分類
4 児童精神医学における診断分類
5 精神医学での「診断」とは何か
6 「診断」のもつ意味
第4章 「精神発達」をどうとらえるか
1 なぜ決定版がないのか
2 認識の発達、関係の発達
3 「認識」と「認知」の区別
4 精神発達の基本構造
第5章 ピアジェの発達論
1 同化と調節
2 知性の発達
3 シェマ
4 発達の4段階
5 精神発達の最終段階
第6章 フロイトの発達論
1 小児性愛
2 リビドー
3 発達の5段階
第7章 精神発達の道筋
1 精神発達の歩み
2 精神発達を推し進める力
3 なぜ個人差が生じるのか
第8章 「共有」の発達としての精神発達
1 まどろみとほほえみ
2 啼泣とマザリング
3 マザリングとアタッチメント
4 感覚の共有(分化)
5 首のすわりと探索行動
6 安心の共有と探索
7 バブリングと情動の共有
8 関心の共有
9 模倣の行為(しぐさ)の共有
10 しつけと意志の発達
11 言葉のはじまり
12 認識の社会化
13 関係の社会化
第II部 育つ側のむずかしさ 発達障害をもつ子どもたち
第9章 発達障害とは何か
1 この本での定義
2 全般的な発達のおくれ-知的障害と自閉症スペクトラム
3 発達の分布図
4 外因・内因・心因
5 必要条件・負荷条件・決定条件
6 発達障害と外因
7 発達障害と内因
8 発達障害と環境因(心因)
第10章 発達障害における体験世界
1 発達の領域分け
2 不安・緊張・孤独
3 発達のおくれと言葉のおくれ
4 認識発達のおくれと孤独
5 関係発達のおくれと孤独
6 高い感覚性の世界
7 感覚世界の混乱性
8 感覚の混乱性への対処努力
9 高い衝動性の世界
10 情動的混乱と対処努力
11 自閉症スペクトラムと知的能力
12 発達の歩みのスペクトラム
13 アタッチメントと自閉症スペクトラム
14 ひとへの関心、ものへの関心
15 C領域における体験世界
第11章 関係発達のおくれにどう支援するか
1 乳児期における支援
2 幼児期における支援
3 学童期における支援
4 思春期における支援
5 現代社会と自閉症スペクトラムの増加
第12章 部分的な発達のおくれ
1 学習障害とはどういうものか
2 学業不振のとらえと支援
3 ADHDとはどういうものか
4 落ち着きのない子どもたち
5 ADHDへの支援
第III部 育てる側のむずかしさ 親や支援者はどうかかわるか
第13章 子育てをめぐる問題
1 親が育てるわけ
2 子育ての歴史
3 現代日本の子育て
第14章 子育て困難の第一グループ
1 家庭内暴力~ひきこもり
2 摂食障害
3 問題の背景
4 問題への対処と支援
第15章 子育て困難の第二グループ
1 不備な子育てはなぜ生じるか
2 「児童虐待」という概念の誕生
3 虐待防止法制定後
4 子育ての失調への家族支援
5 子どもへの支援-3つの困難
6 心理的な問題がもたらすもの
7 PTSD的な問題がもたらすもの
8 PTSDの症状にどうかかわるか
9 発達的な問題がもたらすもの
10 子育ての失調の予防
第IV部 社会に出てゆくむずかしさ
第16章 児童期~思春期をめぐる問題
1 児童期とその発達課題
2 思春期とその発達課題
3 思春期の〈性〉の問題
4 不登校現象のはじまり
5 不登校現象の増加
6 学校へ行く意味
7 現代社会の不登校
8 不登校への具体的対応
9 子ども同士の関係の失調(いじめ)
10 伝統的な「いじめ」と80年代からの「いじめ」
11 「いじめ」の変化とその社会的背景
12 規範意識と「いじめ」
13 学校ストレスと「いじめ」
14 「いじめ」への対処
第17章 その他の精神医学的な問題
1 子どものうつ病
2 子どもの「神経症性」の障害
文献
読書案内
索引
あとがき
著者紹介
書評
開く
書評者: 青木 省三 (川崎医大教授・精神科学)
「素手で読める」と「あとがき」にある。専門用語も厳選して用いてあり,難しい理論で説明を押し切ることもなく,平易な美しい日本語で綴られている。だが,読みはじめると,「基(もと)や本(もと)から考えること,土台から考えを積むこと」(「はじめに」)により,ふと気づくと,私たちの常識や当たり前がしばしばくつがえされている。
私たちが観察する障害特徴と呼ばれるものは,当の子どもにはどのように体験されているものなのだろうか。滝川先生は一貫して子どもの体験世界を理解しようとする。その中で,子どもたちの“病理現象”と呼ばれているもの,例えば,変化への恐れは“世界を少しでも安定した世界としてキープする”試みであり,無意味な常同行動は“味わい深い興味尽きない遊び”であり,“適応のための合理的な対処努力”でもあると捉えていく。
極めて不安と緊張の高い世界で,周囲の人との関係という支えがないまま,過剰なナマの感覚刺激にさらされ,孤独に生きている子どもたち。それは,人々の中に生きているにもかかわらず,人と接点なく生きていることであり,とても孤独なものである。しかも,子どもは生まれてからずっと人と親密に交わる経験がないまま成長しているので,孤独として感じ取ることもできない。このような圧倒的な孤独を,私たちはどれほど感じ取ることができるのであろうか。
そういう子どもへの支援について,滝川先生は考え進めていく。圧倒的な孤独の中ででも,子どもは微(かす)かかもしれないが,人を,そして人と関係を築くことを求めている。だが,人との関係を築く力が弱いぶんだけ,養育者や支援者の側からの関係づくりには配慮が求められるのである。養育者や支援者の急速な接近や熱い接近,すなわち“過刺激”は,子どもに混乱と恐怖を与える。だからといって,距離を置き,遠くに構え,接近しないでいると,孤独な世界は変わらない。
「目の前の生身の相手の気配や雰囲気を,言葉(概念)以前の直覚的なもので敏感にキャッチする」(258ページ)子どもに対して,滝川先生は,子どもを脅かさず,子どものサインに応えていくことを考える。「はたらきかけが,その子にとって刺激が強すぎて侵入的なものにならない配慮が不可欠で,その呼吸が勘どころになる」(247ページ)という。支援は何か特殊なことではなく,基本は普通の子育てやかかわりと同じ世界の中にある。理解は深く根源的に,支援は丁寧で穏やかなものをと,考えるのである。
例えば,「おもしろい子じゃないかという親和感も抱ければ,その親和感は子どもにおのずとキャッチされ,ふたりをつないでくれる」(257ページ)という一文がある。グイグイ引っ張る熱血教師と比べて,「おもしろい子じゃないか」という教師は,一見地味ではある。だが,その教師の眼差しから,子どもたちは負荷のない,だが大切な暖かさを感じ取り,変わりはじめるのである。発達障害の人たちには,このような熱くない,さっぱりとした暖かさが,しばしば支援の“勘どころ”となる。
読んでいると,圧倒的な孤独の中で生きている子どもが浮かび上がり,子どものそばで,その孤独をヒリヒリと感じながら寄り添っている滝川先生が見えてきた。
滝川先生は,いつの時かにご自身も,孤独な世界を微かに体験し,それを貴重な財産としてこころの中に大切に持っているのではないか。それが,子どもや人への理解と共感を深いものとし,地道で粘り強い支援に向かわせているのではないか。それだけでなく,支援者というものは,自身のうちにある孤独を大切にしながら,丁寧に人との繋がりを紡いでいく存在ではないかと感じた。そもそも,私も含めて,人が生きていくということはそういうことではないか,などと感じながら,本を読み終えた。
発達や障害だけでなく,人間とは,そして生きることとは何かを考えさせる,本当に奥の深い本であった。
背中に1本「太い背骨」を入れてもらった
書評者: 村上 伸治 (川崎医大講師・精神科学)
本書は,児童精神医学の真髄をその大家が平易に解説することに挑んだ書である。
その第I部では「人の精神はどのように発達するのか」を丁寧に解説している。精神発達において著者は「養育者との相互交流」による「共有」を重視する。例えば,身体感覚が分化するには外部からの調整が必要であり,赤ん坊が泣き親が世話をする中で,親子間で感覚体験が共有され,身体感覚の分化と共有が認識の発達の土台となるという。感覚の共有から始まって体験や情動を共有し,関心を共有することで行為の共有(模倣)が生まれ,言葉が生まれ,世界を共有するようになる,としている。
第II部は発達障害を詳説している。認識の発達をy軸,関係性の発達をx軸として,定型発達,知的障害,自閉症,アスペルガー症候群などを座標上に位置づける説明が秀逸である。そして,症例や当事者の文章を多数提示しながら,発達障害の子どもが体験している世界がリアルにイメージできるよう全力を挙げている。
関係性の発達に遅れがあり親を頼れない子どもにとっては,この世は不安や緊張や孤独に満ちたものであること,頼るものがないので変化がない常同性などに頼らざるを得ないこと,そして,彼らの立場に立つと障害特性の「こだわり」は適応のための対処行動だと理解できる,などが示されている。
具体的な支援については,例えばこだわりについても,理屈で説明され腑に落ちれば行動を変えられる場合が多いので,まずは「その子の理屈を共有する」ことから始めるよう勧めている。丁寧なやり取りによって判断を交換する体験の積み重ねが大切であり,真の目的は説き伏せて行動を変えさせることよりも,人と判断をやり取りする体験を与えることである,としている。
第III部では育てる側の問題を扱っている。子育て困難については「親を責めるよりも子育ての難しさへの共感」を重視し,「虐待の概念を捨てること」すら勧めている。被虐待児への支援では支援者が本人から試し行為や攻撃を受けることも多いことを挙げ,「この感情を親たちも強いられていた」ことに思いを馳せる必要性を指摘する。施設では熱心なスタッフの孤立やスタッフ間の対立が起きやすいことなども説明している。
第IV部は現代社会に対する論考を主としている。不登校を始めとした子どもを取り巻く問題を,戦後の日本の社会の変化,学校の位置付けの変化などを踏まえて解説している。
さて,本書は実はかなり分厚く,464ページもある。しかし読み始めてみると,平易な文章で難解な表現もなく,専門用語も最小限なので,医療者だけでなく教育関係者や福祉関係者にも読みやすい。
評者は発達障害も診る精神科医として,精神発達についてひと通りわかっているつもりであったが,本書によって浅い理解だったと痛感するとともに,今後は目の前の子どもを2つの軸の発達の歴史のイメージで捉えられそうに思えた。子どもを発達の側面から理解する際の,背中に1本「太い背骨」を入れてもらったような気がする。
自閉症を最初に報告したカナーは27年後に追跡調査を行い,「初期の類似性から離脱して,完全な荒廃から制限はあるが表面上円滑な社会適応を示す職業的適応までを含む変化が生じた」(p.225)と報告していることも触れられている。当初は類似した状態であったのに,これほどに予後を分けたのは一体何なのだろうか。本書にはっきりとは書かれていないが,著者が強調する「共有」へのアプローチがそれを分けたのではないか,そしてそれは育つ過程だけでなく明日から目の前の患者との間でも可能なのではないか,と本書を読んで思い始めた。
“予後を変えることは可能で,そのヒントがこの本にはある”そう思えて,今読み直しているところである。
予測がつかない(でもたまに面白い)毎日だから(雑誌『精神看護』より)
書評者: 畑中 麻紀 (翻訳家)
はじめまして、自閉症スペクトラム男子の母で翻訳家の畑中麻紀と申します。うちの息子はアスペルガー症候群、つまり本書『子どものための精神医学』におけるC領域の人。
小学校・中学校と普通級に在籍しながら通級指導学級にも通い、普通科の高校を卒業して大学に入学。大学生となると発達論的にはもう、子どもの域ではないけれど、本書を読んで、そうか!と腑に落ちたのが、すべての子どもは発達の道を歩んでおり、「自閉症スペクトラムのなかに分布する子どもたちもそうで、スペクトラムのなかのひとつの場所にとどまったままではない」(225頁)という「発達の歩みのスペクトラム」の項だ。
◆親が持つ、自立への不安と焦り
問題行動で悩まされてばかりの日々から、高校生になってからは落ち着きを感じられるようになったものの、「この子は社会に出られるようになるのだろうか」という不安と焦りは大きくなっていった。定型発達の子であれば、成人することは喜ばしい限りだろうが、スペシャルな子育ての場合、自立へのタイムリミットを突きつけられるという危機感が先行してしまう。とはいえ、大学という新しい環境に適応するだけでも大仕事なのだから、それ以上を期待するのは難しいだろうと高をくくっていた。
◆ところが変わってきたのです
ところが1年も経たないうちに、それまでどんなに促しても絶対拒否だったアルバイトに自分から応募して働き、食感や味が気持ち悪くて嫌だ、と頑として受け付けなかった食材や料理を、何の違和感もなく進んで食べ始めたのだ。もっとも、知覚の非恒常性、予定変更に対する弱さなど、日常生活での不便はまだまだあるが、もう大人になるのに、ずっとこのままなのか……と諦める必要なんてないのだと改めて実感した。
そして、そういえば、と最初の主治医に言われた言葉を思い出す。「今はね、定型の子と大きく差が開いているけれど、環境を整えて療育も継続していくと、その差はだんだん縮まっていくよ。諦めちゃうとそこで止まっちゃうけど」……うむ、やっぱりそこを忘れちゃいけないのね。子どもを目の前にして悲観的になっている(主に)お母さんたち、大丈夫ですよ。支援の積み重ねはちゃんと形になっていくから。
◆親の心がずばり書いてある本
ところがどっこい、その効果が出るまでには時間がかかる。年単位でかかるものも少なくない。それがいつやってくるのか予測もつかず、つまり、先の見通しが持てず不安ばかりが先立つ(と、これはまさしく自閉圏の子どもたちが日常的に抱えている困難だ!)。
だから大切なのは、養育者の心が健康に保たれていることだろう。しかし、息切れすることのほうが多いのに、とかく母親はこう言われてしまう。「お子さんが安定するためには、お母さんが元気じゃないとね」……わかってる。私だってニコニコ元気でいたい! でも、それが簡単にはできないから困っちゃうのよ!! と心の中で叫んだ経験のある母がどれだけたくさんいることか。
そんな母たちの心の内をずばりと、滝川先生は書いてくださっている。「わが子でありながら、なぜこんな思いにまかせないのか。気持ちがどこか届き合わない親子関係。なぜこんなに気持ちが逆撫でされるのだろうか。そして、とかくもちあがる厄介事。そうしたうまくいかなさへの抑えきれない怒り、投げ出したい思い、いらだち、ゆううつ、無力感。その一方で親としてのわが子への深い執着(関係の意識)……」(334頁)
これは虐待をしてしまう親の心理について書かれているのものだが、かつての私も、学校トラブルの嵐だった義務教育期間、まさにこういう気持ちで過ごしていた。当時としては、かなり手厚い支援を受けていたのにもかかわらず、である。私だけではない。周囲を見渡すと、大半の親が同じように思いつめ、幸い虐待行為には至らなくても自らの心身に不調をかかえ、それでもなんとか紙一重のところで子育てをしてきたのだ。もっとも、定型発達の子であっても、特に乳幼児の時期に「この子を虐待してしまうかも……」と危機感を抱く母親は少なくないだろう。だが、自閉圏の子を育てる親は追い詰められ感が尋常ではなく、しかもそれが何年にも渡って続いていく。子どものタイプにもよるが、一歩外に出れば「ご迷惑をおかけして申し訳ございません」と謝ってばかり。うちの中でも子どものこだわり由来の行動や言動に振り回される。そういう状況下でも心を壊さずにいることは、大げさではなく本当に難しい。
◆本書を読んで、深呼吸しよう
子どもにはしあわせに生きてほしい。その想いは親も、子どもにかかわる親以外の人たちも同じだろう。それなのに、行き違いが生じてしまうこともある。そういう場合は往々にして親の気持ちはささくれ立ち、こんな気持ちになること自体ダメ親だと罪悪感まで抱いたりするのだ! だから、そういった時には本書を思い出していただき、共に育て合う同士として、親たちに深呼吸を促していただけたらうれしいと思う。「かわいそうな私」から脱却し、「この子とじゃないと味わえない面白さ」をまた思い出せるように。
(『精神看護』2017年9月号掲載)
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。