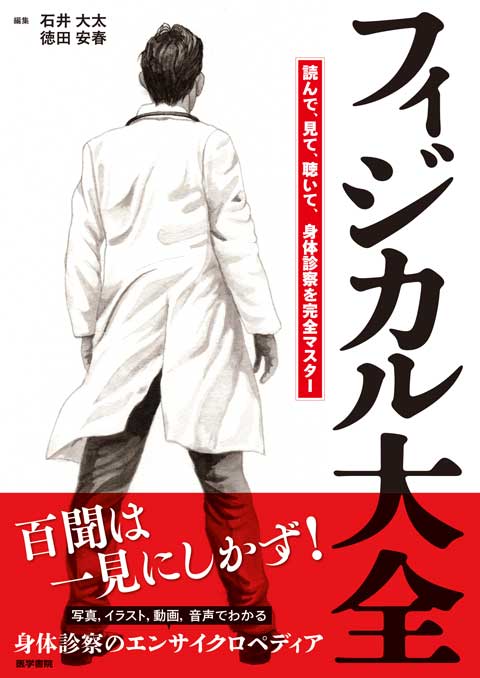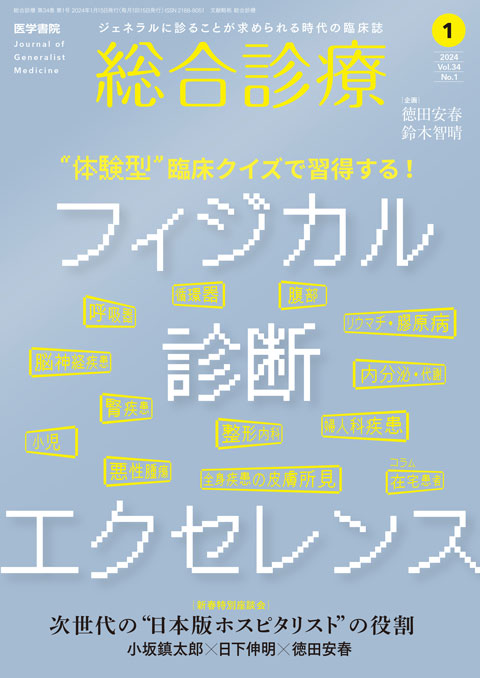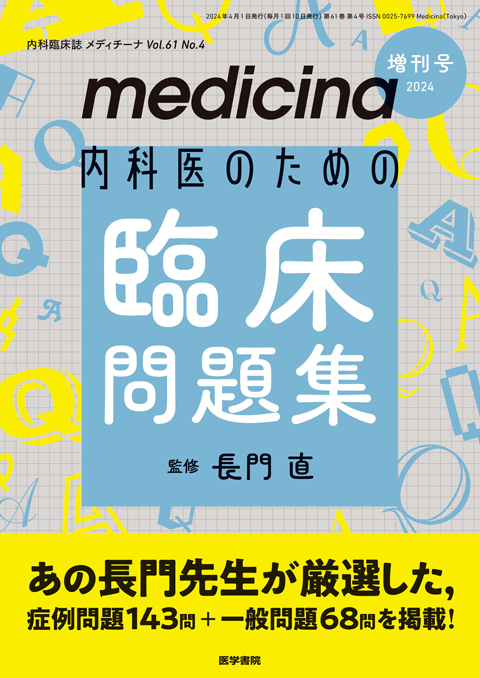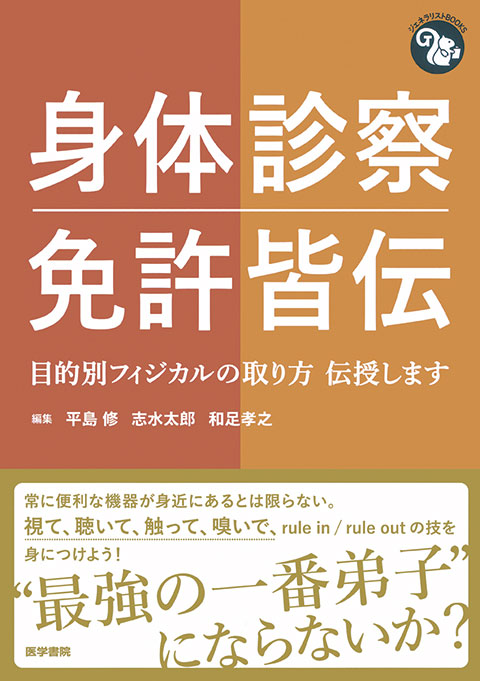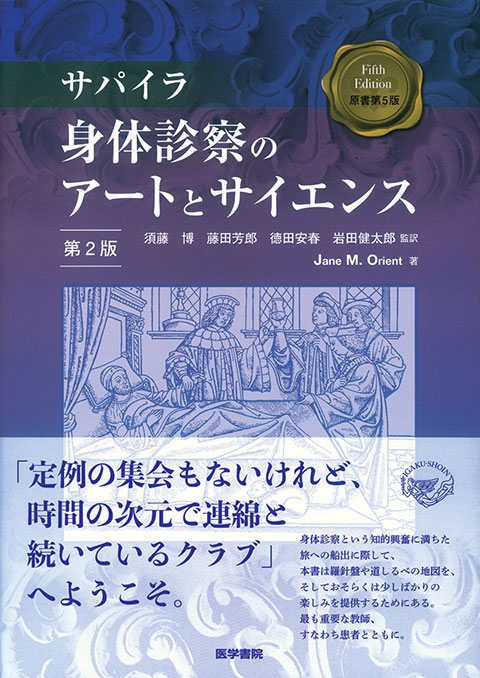フィジカル大全
読んで,見て,聴いて,身体診察を完全マスター
百聞は一見にしかず! 図、動画、音声でわかる身体診察のエンサイクロペディア
もっと見る
好評を博したmedicina2022年増刊号「フィジカル大全──読んで、見て、聴いて、身体診察を完全マスター」が待望の書籍化! 書籍化にあたりオールカラー化し、さらに見やすく使いやすい1冊となった。写真やイラストに加えて、動画・音声を豊富に収載。通読することで身体診察の要諦を押さえることができる内科医・総合診療医必携のエンサイクロペディア。
更新情報
-
2025.07.16
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序──徴候病態生理学でフィジカルの熟練度を高める
2023年8月に箱根で医師と医学生高学年者を対象とした勉強会を行った.私は,臨床的に重要度の高い「細菌性髄膜炎」の実臨床ケースを紹介した.そのケースの診察スキルについて13人の医療関係者に対して尋ねた結果,項部硬直の正確な診察手技については約半数の参加者が正解を示した.しかし,Kernig徴候については,正解者はゼロであった.診療の質を高めるためには,診察スキルの向上のための学習を深める必要がある.
Semio-Pathophysiologyという用語がある.身体所見での徴候を説明する,徴候病態生理学だ.例えば,髄膜炎では,脳,脳幹,そして脊髄を守るために,これらの脳神経細胞が物理的に伸展しないよう,筋肉のスパスムが起こるのだ.項部硬直もKernig徴候も徴候病態生理学で説明すると,正確な手技を実行することができる.
身体診察において,エビデンスの重要性はもちろん認識すべきだ.しかし,まずは熟練度を高めることが何より重要である.臨床研究におけるデータの信頼性は検査を行った医師の熟練度に左右され,再現性が低いデータの感度や特異度をそのまま採用することは不適切だからだ.Sapira先生によるショパンの法則と呼ばれている原則である.各論的フィジカル診断を高い再現性をもって正確に行うための徴候病態生理学に基づく解説書が本書である.
medicina59巻4号(増刊号)「フィジカル大全──読んで,見て,聴いて,身体診察を完全マスター!」として誕生した本書は,書籍化でさらにパワーアップした.ポイントは以下の通りである.本文をオールカラー化した.目次構成は増刊号を踏襲するものの,掲載順を再整理し,読者がより活用しやすい形にした.
循環器,呼吸器,消化器,感染症,膠原病,筋骨格,内分泌・代謝,脳神経などの主要な章の冒頭には総論としての「診察の仕方」を配置した.
また,新設項目として以下を追加した.
・ 手・爪の疾患
・ 泌尿器科疾患による腹部症候
・ 産婦人科疾患による腹部症候
・ 蜂窩織炎と壊死性軟部組織感染症
・ 性感染症
・ 易出血性/出血傾向
・ 外傷性筋骨格系およびスポーツ関連筋骨格系疾患
・ Parkinson症候群
・ 口腔疾患
これらの改善によって診察技術と知識がさらに充実し,幅広い臨床ニーズに応える内容となることを期待している.それが実現すれば,編集者の一人としてこれ以上の喜びはない.
2025年4月吉日 沖縄にて
徳田安春
目次
開く
第1章 バイタルサイン
1 血圧の異常,ショック
2 脈拍・心拍の異常
3 静脈圧
4 呼吸状態・呼吸数・呼吸リズムの異常
5 意識障害
6 体温の異常
第2章 全身
1 手・爪の疾患
2 発熱と皮疹
3 脱水
4 浮腫
5 黄疸
6 肥満,低栄養
7 外傷
第3章 循環器
1 循環器の診察の仕方
2 心不全
3 大動脈弁狭窄症
4 大動脈弁閉鎖不全症
5 僧帽弁狭窄症
6 僧帽弁閉鎖不全症,僧帽弁逸脱症
7 三尖弁逆流症,肺高血圧症,肺血栓塞栓症,深部静脈血栓症
8 急性心膜炎,心タンポナーデ,収縮性心膜炎
9 動脈硬化症,先天性血管異常
第4章 呼吸器
1 呼吸器の診察の仕方
2 肺炎
3 COPD,喘息,気胸,縦隔気腫
4 胸水
5 睡眠呼吸障害
第5章 消化器・腹部・骨盤
1 消化器・腹部の診察の仕方
2 急性腹症の診かた
3 直腸診
4 肝臓と脾臓の疾患,腹水
5 胆囊・胆管・膵臓の疾患
6 後腹膜スペース・腰背部・腹壁・胸壁の疾患
7 泌尿器科疾患による腹部症候
8 産婦人科疾患による腹部症候
第6章 感染症
1 感染症の診察の仕方
2 咽頭痛
3 感染性心内膜炎
4 旅行者感染症
5 蜂窩織炎と壊死性軟部組織感染症
6 性感染症
第7章 血液・腫瘍
1 貧血
2 リンパ節腫脹
3 易出血性/出血傾向
第8章 膠原病
1 膠原病の診察の仕方
2 関節リウマチ
3 全身性エリテマトーデス(SLE),強皮症(SSc),混合性結合組織病(MCTD)
4 多発性筋炎,皮膚筋炎,抗ARS抗体症候群
5 血管炎,リウマチ性多発筋痛症
第9章 筋骨格
1 筋骨格の診察の仕方
2 手根管症候群,胸郭出口症候群
3 頸椎・腰椎疾患
4 肩関節疾患
5 反応性関節炎
6 痛風・偽痛風・代謝内分泌疾患による骨関節疾患
7 外傷性筋骨格系およびスポーツ関連筋骨格系疾患
第10章 内分泌・代謝
1 内分泌・代謝の診察の仕方
2 甲状腺疾患
3 視床下部・下垂体・副腎疾患
4 遺伝性代謝疾患
5 糖尿病と膵内分泌疾患
6 ビタミン・微量元素欠乏症
第11章 腎臓・電解質異常
1 尿毒症,腎不全
2 電解質異常
第12章 脳神経・精神
1 脳神経の診察の仕方
2 脳神経の診かた
3 髄膜刺激徴候,頭蓋内圧亢進徴候
4 協調運動障害,運動失調
5 脊髄・馬尾障害
6 感覚異常
7 振戦
8 深部腱反射,病的反射
9 めまい
10 けいれん
11 筋力低下
12 歩行の異常
13 認知機能低下
14 Parkinson症候群
第13章 眼・耳鼻咽喉
1 充血,眼底疾患
2 聴力低下,耳鳴,耳漏
3 口腔疾患
索引
書評
開く
“身体診察の決定版”とも呼ぶべき渾身の一冊
書評者:鈴木 富雄(大阪医科薬科大教授・総合診療医学)
本書は,従来の身体診察の教科書とは一線を画す,“身体診察の決定版”とも呼ぶべき渾身の一冊である。各臓器別(循環器系,呼吸器系,筋骨格系,神経系など)に分類された診察手技について,診療に必要な基本的な方法が正確かつ極めて丁寧に記載されているのはもちろんのこと,さらに,臨床的には有用と耳にしたことはあっても,これまで実際の診察方法について十分に記述されてこなかったような,ややマニアックな手技に関しても,明瞭なカラー写真や図解を交えて詳細かつ実践的に解説されている。身体診察に関する書籍は数多く存在するが,ここまで系統的かつ網羅的に,そして現場の臨床家の目線に立って記述されたものは極めてまれである。
本書のもう一つの大きな魅力は,Web上からアクセス可能な多数の動画が用意されている点である。重要な診察手技については,紙面での理解を補完するように,実際の動作を視覚的に確認できる動画が付属しており,学習効果を飛躍的に高めている。中には音声解説付きの動画もあり,まるで熟練の臨床医がそばで直接指導してくれているかのような臨場感と安心感の中で学ぶことができる。
本書は,初学者にとっては丁寧な記述で基礎を固めるのに適しており,また経験を積んだ臨床医にとっても,見落とされがちな手技や解剖学的背景を再確認し,診察の質をさらに高めるための示唆に満ちている。まさに,身体診察を改めて学び直したい全ての医師にとって有益であるとともに,学生・研修医など若い世代に身体診察の面白さや重要性を伝えたい臨床教育者にもぜひ手に取ってほしい内容である。
文章も平易で読みやすく,それでいて内容は奥深い。解説の随所に臨床的な背景や注意点が巧みに織り込まれており,単なる手技の羅列ではなく,“生きた診察”を学べる技術書としての完成度は極めて高い。読者の診察に対する感受性を豊かにし,目の前の患者と真摯に向き合う姿勢そのものを再考させるような,静かな感動をも呼び起こす。身体診察が軽視されがちな現代医療において,本書はその意義と可能性を再認識させてくれる,力強いメッセージを内包している。実技と知識の双方を融合させた本書は,今後長きにわたって多くの臨床家の座右の書となるに違いない。
なお,付属の動画の中には音声解説が付いていないものもあり,その場合には紙面の記述と照らし合わせながら理解する必要があるため,やや手間を感じることもあるかもしれない。今後の改訂の際に全ての動画に簡潔なナレーションや要点の解説が加われば,動画だけでも理解が深まる,より完成度の高い学習教材へと発展していくと思われる。本書の今後のさらなる進化にも,大いに期待したい。
身体診察の奥深さを悟る一冊
書評者:山中 克郎(諏訪中央病院)
かつて新型コロナウイルス感染症の拡大によって,私たちは「触れない診療」を余儀なくされた。聴診器を胸に当てることさえもためらわれた時代を経て,いま,身体診察の意味があらためて問われている。
AI時代を迎え,医学知識の「暗記」にはかつてほどの価値がなくなりつつある。むしろ,患者が語る言葉の背景にある「物語」に耳を傾け,意味付けを施し,適切な問診と身体診察によって診断に迫る力が,これからの臨床医には求められているのだ。
本書『フィジカル大全』は,そうした変化の中で,医師にとっての原点とも言える「身体診察」に再び光を当てる。通読しながら,自身の診察に曖昧な部分があることに気付き,大切な手技に印を付け診療スタイルを見直すきっかけとなった。
特に循環器や神経内科の章は秀逸で,音声や動画による心音や身体所見の提示が印象的である。診察という行為は,教科書を読むだけでは決して身につかない。にもかかわらず,他者の診察を実際に見学する機会は,医師になってからは意外なほど少ない。本書はそのギャップを埋め,手技の「共有知」として貴重な役割を果たしている。
診断において,最も大きな比重を占めるのは「問診」である。患者の語ることに耳を傾け,背景や物語をくみ取るこの作業が,診断の8割を決める。残りの2割のうち,1割は身体診察,もう1割が検査による。問診によって診断の輪郭が浮かび上がり,身体診察によってそれを確かめ,検査が最後の裏付けとなる。身体診察の診断的な寄与は1割かもしれない。だが,患者の体に触れるという行為は,単なる診断以上の意味を持つ。
私自身,上部消化管の検査を受けたときのことを,今も鮮明に覚えている。苦しさに耐えていた私の背中を,看護師さんがそっとなでながら言った。「つらいですね。でも,もうすぐ終わりますよ」。その一言と優しい手のぬくもりに,どれほど救われたことか。
本書は,身体診察を初めて学ぶ初期研修医にはもちろん,自らの診療を再点検しようとするベテラン医師にも強く薦めたい。「診る」という行為が,単なる確認作業ではなく,患者の人生にそっと寄り添う行為であることを,この本は静かに教えてくれる。