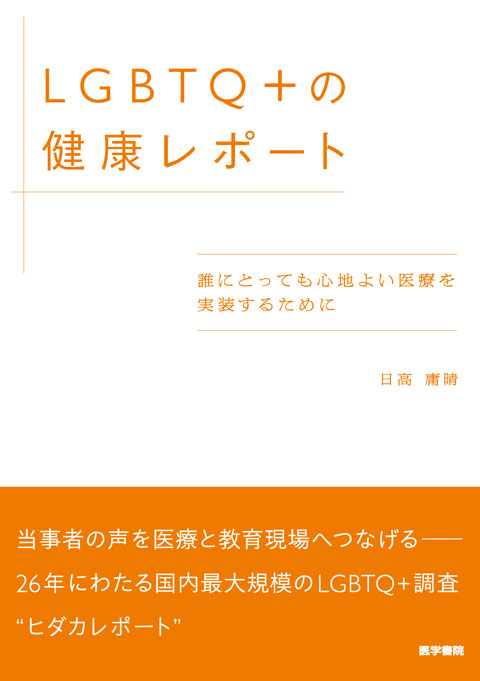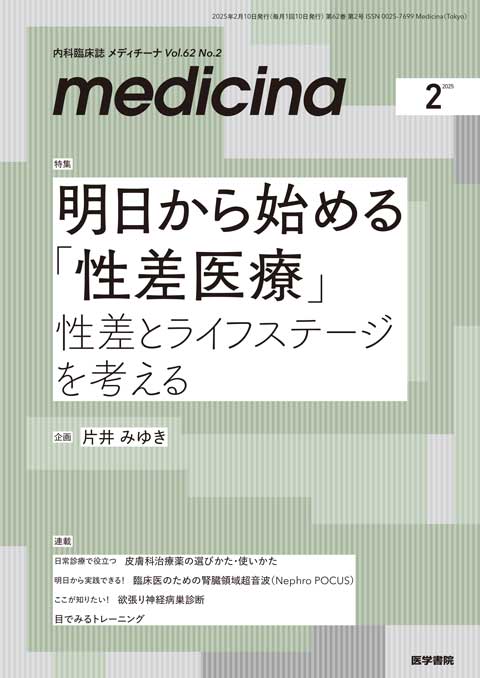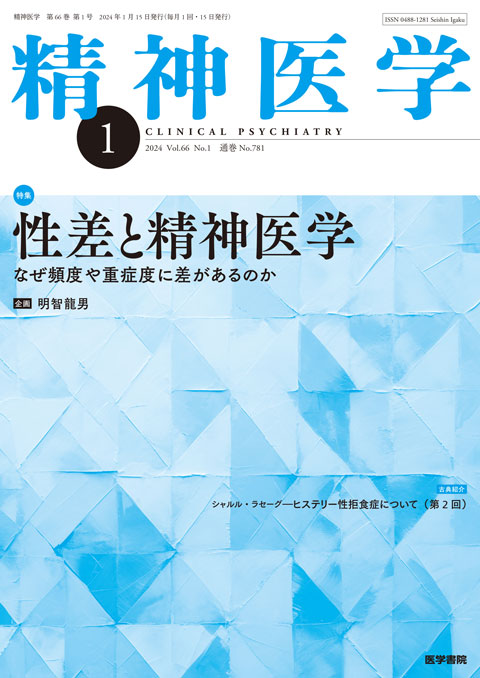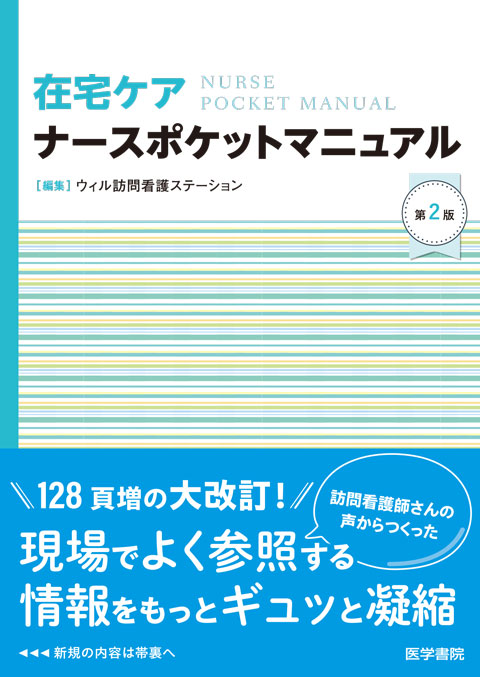LGBTQ+の健康レポート
誰にとっても心地よい医療を実装するために
特別ではなく、1人ひとりを大切にしたあたり前のケアを
もっと見る
国内でもセクシュアリティを取り巻く環境が徐々に変化している。しかし実際は、LGBTQ+当事者への偏見や戸惑いが存在し、世間の表向きの理解と現実のギャップは大きい。それは医療・教育現場も同様だ。そこで本書では、著者が長年にわたり行ってきた大規模調査データや当事者の語りをもとに、医療を必要としている当事者が戸惑うことなく受診できるための実装方法を解説した。調査データの一部を巻末資料として収載。
| 著 | 日高 庸晴 |
|---|---|
| 発行 | 2024年08月判型:A5頁:264 |
| ISBN | 978-4-260-05616-8 |
| 定価 | 2,860円 (本体2,600円+税) |
更新情報
-
2025.12.05
-
2025.04.21
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
はじめに
社会的マイノリティの健康課題や当事者が社会的に置かれている現況を明確化するために,筆者はいわゆる量的研究手法を用いて,長年にわたり数多くの研究課題に取り組んできた。LGBTQ+のみならず,深夜の都会の繁華街に集う若者の性行動調査や,治療法が確立していない進行性の難病である網膜色素変性症患者の生活実態を明らかにする調査,HIV陽性者の長期療養に関する調査などである。
性的指向やジェンダーアイデンティティは最たる個人情報のひとつであり,当然ながら住民基本台帳のような名簿は存在しない。他の社会的マイノリティにおいても同様であり,それゆえ可視化されにくく,いずれもサンプリング(調査の対象者として抽出すること)が比較的困難であり,調査の参加そのものを募ることも難しい対象である。そのため調査実施に際しては,当事者が集まる場所に赴き調査参加を直接的に募ったり,Web/SNS空間で調査実施を告知したりなど,対象や時勢に合った調査手法を模索してきた。また,質問票の回答端末にスマートフォン,タブレットなどICT(Information and Communication Technology)と呼ばれる情報通信技術を活用して,古典的な“紙と鉛筆(paper-pencil surveyと呼ばれることもある)”による調査とは一線を画した調査手法を採用してきた。一方で,約1万人の高校生を対象にした調査の実施にあたっては教室で“紙と鉛筆”による手法も用いるなど,対象に応じた調査に取り組んできた。
社会的に可視化困難であるとは,つまり存在そのものが見えにくいことを意味するが,だからといって社会的に存在していない訳では決してない。それはいうまでもないであろう。その一方で断言できることは,存在が可視化されないことによっていつまでも現状が把握されず,その結果としてニーズがあるにもかかわらず公の施策の対象となりにくいという現実である。そもそもマイノリティであるがゆえに,マジョリティに比して社会的に置かれている環境やそれに起因する所得や健康格差などがあることは調査の実施を待たずとも容易に推測できよう。加えて,解消されない格差や不利益は,当事者だけが背負わざるを得ず,その負担と損失は救済されることのないループに陥っているように思えてならない。
筆者が考える研究者の仕事のひとつに,社会的に不可視である存在を調査で可視化し,点から線,線から面へと展開し,それを立体的に顕していく作業がある。これまでの継続した調査により現状を数字として示し,当事者の直面する困りごとや社会の構造的問題を調査から得られた結果という根拠と共に顕在化させることに努めてきた。繰り返し実施した調査結果は蓄積したエビデンスとなり,研究論文・新聞記事・授業や研修資料として,様々な形態で社会に還元されている。
加えて研究成果の最も効果的な活用方法は,国や地方自治体の施策に反映されることであり,そこまでして初めて当事者の役に立つ,と心底思うようになった。現在では,調査データが施策の必要性を訴えるエビデンスとなり,多くの当事者や支援団体,国会や地方自治体の議会の質疑で用いられ,政策決定の場でも活用していただけるようになってきた。
本書で報告する調査データは紙幅や筆者の力の限界もあり,四半世紀の研究成果のごく一部にすぎないが,保健・医療・福祉・教育の現場など,それぞれの専門職にご活用いただくその一助になることを切に願ってやまない。
2024年7月
日高 庸晴
目次
開く
本書に関連する用語一覧
LGBTQ+当事者を対象にした調査の概要
第1部 当事者が置かれた現状と困難
第1章 当事者を取り巻く現状
蓄積した調査データが語ること
医学界における性的指向とジェンダーアイデンティティの取り扱いの変遷
26年にわたる調査研究の実施継続での経験
〔当事者の声①〕わたしたちも受診しています。
〔当事者の声②〕「私の家族」と「病院の考える家族」
〔当事者の声③〕誰もが安心して自分を表現できる世の中に
第2章 国内外の人権課題
憎悪犯罪(ヘイトクライム)
LGBTQ+を取り巻く国内の主な動き
文部科学省通知における児童生徒への対応
同性婚を取り巻く世界の動き
世論調査が示す「同性婚」賛成割合
LGBTQ+全国調査が示す同性婚のニーズ
司法の動き
第3章 カミングアウトとメンタルヘルス
カミングアウトとは
自覚する平均年齢は13歳という再現性あるデータ
若い世代が最も「誰かに相談したかった」
カミングアウトまでの年数
親へのカミングアウトと地域差の実際
職場でのカミングアウト率
LGBTQ+のメンタルヘルス
異性愛者を装うことによる役割葛藤とメンタルヘルスの安寧の阻害
LGBTQ+のメンタルヘルスの不調
自殺未遂リスクの推定
さまざまなメンタルヘルスの安寧の阻害要因
第4章 性暴力・DV被害と援助希求行動の難しさ
LGBTQ+当事者の性暴力被害の現状
110年ぶりの刑法改正
LGBTQ+当事者における被害の現状
相談と支援体制の現状
援助希求行動の難しさ
第2部 医療と教育現場での実装
第5章 LGBTQ+当事者にとっての医療機関と受診控えの現状
個々の患者には多様な背景がある
メンタルヘルス専門外来の受診歴
メンタル系治療薬の服用歴
医療従事者へのカミングアウト
他院の受診を勧める際には
医療者への恐れを抱えたままの受診
医療機関の受診控え
第6章 専門職として医療従事者に求められること
医療従事者に求められること
病院の職員を対象にした意識調査から分かる対応の遅れ
患者情報の共有のあり方
安心して受診できるようにするために
診療の同意をとるべき家族の範囲の変化
病院の対応が定まらないことによる弊害
医療従事者に求められる高い倫理観と公正さ
早急に取り組むべき理由──経営リスク等の観点から
第7章 学齢期におけるいじめ被害や自傷行為が人生に与える影響
調査結果が示すいじめ被害・自傷行為・不登校経験率
困ったときに相談できる場所を知らせる
小・中・高等学校・特別支援学校の教員のLGBTQ+意識・対応経験の実態
正しく知ると,子どもとの関わり方が変わる
第8章 LGBTQ+の学生のために教育機関ができること
FD/SD研修の実施
規程やガイドラインなどでできること
講義でできること
実習でできること
学内演習でできること
学生相談室ができること
当事者サークル活動への支援としてできること
事務手続き・事務窓口ができること
就職活動支援でできること
巻末資料
REACH Online 2016(2016年調査)調査データの概要
REACH Online 2019(2019年調査)調査データの概要
REACH Online 2022(2022年調査)調査データの概要
おわりに
索引
書評
開く
世の中が変わる以前からの丹念な科学的データの集積
書評者:片岡 仁美(京都大学医学教育・国際化推進センター副センター長)
歴史に残る1冊である,ということをまず述べたい。歴史が動く時がある。その渦中に居る時,たった数年間で世の中が変わった,とわれわれは実感する。しかし,その動きの速さに流されながら「世の中は変わった」と,わかったように納得してはいないだろうか。
本書はまさにLGBTQ+について世の中が大きく変わっていくさなかに出版されたが,著者による科学的な検証の端緒は27年前にさかのぼる。精緻で科学的な視点で丹念にデータを集積し,経時的にそれを分析した結果の重さは,潮目が大きく変わる時期においてその価値は一層大きい。
そして,科学的,歴史的な価値のみならず,私は著者の一貫した考え方に非常に感銘を受ける。それは「社会的に可視化困難であるとは,つまり存在そのものが見えにくいことを意味するが,だからといって社会的に存在していない訳では決してない。(中略)存在が可視化されないことによっていつまでも現状が把握されず,その結果としてニーズがあるにもかかわらず公の施策の対象となりにくいという現実である」(「はじめに」)という文章に端的に表れている。見えにくいからないのではない。見えにくいから見なくてよいのではない。その信念に触れ,特に医療にかかわるものとして背筋を伸ばさざるを得ない。
本書には本来悩みや苦しみをもって訪れる方の癒しの場であるはずの病院が,LGBTQ+の方にとっては期待とともに「恐れ」を抱く場であることを多くのデータとともに示している。性的指向は隠すことも話すことも不安が伴う。これらのことが受診を控えることにつながることも少なくなく,無理解による辛い体験はさらに受診への障壁を大きくする。自身も患者の立場になった時,医療従事者の何気ない一言をどんなに深く受け止めてしまうかということを経験した。LGBTQ+の方が受診そのもののハードルを乗り越え,勇気を振り絞って自身の奥深い部分まで開示して,そこで理解が得られなかったら,その失望と苦痛はいかほどだろう。
著者は,「専門職として医療従事者に求められること」という第6章の冒頭で「個々の患者はさまざまな生活実態や背景を持ち,その背景の1つに性的指向やジェンダーアイデンティティを含むセクシュアリティの多様性がある。そしてそれらは,人格形成の根幹をなす基本的人権の1つであることを,医療従事者は認識する必要がある」(p.121)と述べている。患者の背景を理解する必要がある,ということを私たちは意識すべき,したいと思っている。しかし,そのためにはいつも自分が見えているものは十分だろうか,と振り返ることが必要である。患者の大切な部分に触れることの重さを本書を通して改めて問われた気がした。本書に込められた思いをわれわれは深く受け止めたい。
社会的不可視性に挑む医療の未来──自律尊重の医療を誰にでも当たり前に提供するために
書評者:三田村 七福子(社会医療法人誠光会 淡海医療センター 専門看護実践室 助産師/母性看護専門看護師)
■待望の書籍の発行
「やっとや……待ってました」。本書を手にできたとき、思わず口からこぼれた言葉です。しかし、拝読した直後から、「これを“当たり前”とできる医療者や医療施設が、いまの日本にどれだけ存在するのだろう」という懸念がどんどん膨れ上がっています。
数年前から、当院の倫理委員会や倫理コンサルテーションチームに、以下のような情報や相談がもたらされるようになりました。診察券やカルテの「名前・性別表記」の変更要請、性別と異なる臓器の記載が含まれる書類の扱い、入院病棟や大部屋の利用について等々。その都度議論しなんとか対応してきましたが、私たちに圧倒的に不足していたのが、データや根拠でした。
ケアの標準化・システム化を進めること、そしてその合意形成において、対象の概数や病院への期待・責任など、いろいろな知見や前例提示が必要です。しかし、それらになかなか辿り着けずに困っていたとき、もうすぐこの書籍が発刊されると知り、今か今かと待ち望んでいた次第です。
■医療者が「知らない」では済まない情報が満載
著者は、《社会的に不可視である存在を可視化する》と、1998年から行動疫学調査を続けられています。本書は、その長年のご研究結果による現状と課題が示されていますが、医療・教育現場についてさらに着目するといった2部構成となっています。
【第1部 当事者が置かれた現状と困難】では、世界と日本における変遷や調査結果について丁寧に提示・解説されています。アウティング(暴露されること)への恐怖、メンタルヘルスの安寧や受診行動の難しさなどについて、その背景や対策の意義とともに記されています。また巻末には、70ページにわたって種々の調査データが掲載されていて、全ての読者の理解を支えてくれる内容です。
個人的には、性的マイノリティへの無理解が自殺念慮の社会的要因の1つになり得ると国の自殺対策ガイドラインで言及されていたこと(2012年)、同性婚を法律で認めてほしいと求める人(n=7172)の74.5%にも及ぶ方々のその理由が「診療場面で同性パートナーを家族と認めてもらうため」という事実(2022年)は、看過できない情報だと感じています。
そして、医療従事者と医療機関がかみ締めなくてはならない内容が、【第2部 医療と教育現場での実装】の第5章・第6章に記されています。
■正解はわれわれ医療者が創っていく
本書を拝読した今、自分たちのこの方向性は間違っていないと安堵する一方で、改めてその意味や責任が圧し掛かってきています。「電子カルテの性別欄の変更は適切だったのか」「現在の受付対応フローは逆にステレオタイプ的ではないか」「さまざまな変更によって職員に混乱が生じ、かえって不快や不利益を与えてしまうことにならないか」といった懸念が次々と湧いてきます。また、家族・パートナーの定義見直しのみならず、この先には代理意思決定やACP、親権に関連する課題もあります。
しかし当たり前ですが、その正解は本書に明記されていません。私たちが私たちの施設なりに創っていくしかありません。本書に散りばめられたヒントを参考に、数年かけて段階的に整えていくつもりです。
少し前、性別変更にも性別適合手術が必須ではなくなり、東京高等裁判所でも同性婚に関する新たな判決が出ました。
しかし一方で、医療や治療は“生物学的性別”ありきです。エビデンス然り、システム然り。さらに、ホルモン療法や性別適合手術を受けた方々に関する中長期にわたる医学的エビデンスはいまだ十分とは言えません。
社会的のみならず、医学的にもまだまだ不可視です。この溝をどのように埋めて、追いつき、両立させるのか。1人の看護実践家として考え続けたいと思っています。
(「看護管理」 Vol.35 No.2 掲載)
自分の常識の枠を外し、思い込みを問い直す大切さを知る
書評者:大木 幸子(杏林大学保健学部看護学科 地域看護学研究室)
■数値の中にある物語
私たちの信じている「常識」とは、マジョリティ(多数派)の思い込みである場合が多い。そうした事象のひとつに、セクシュアリティがあるのだろう。マジョリティである異性愛者の中には、セクシュアリティの多様性について十分認識していると考える方も少なくないだろう。しかし、“生活を共にしている同居人”がいると察すると、それは妻あるいは夫であることを前提に話をしてしまい、DVは夫から妻への、あるいは男性から女性に対する暴力だと想像してはいないだろうか。そのような思い込みに気づかせてくれるのが本書の魅力でもある。
本書は、LGBTQ+当事者の人権、健康、社会関係、医療、教育などに関する深刻な問題と当事者の孤立を、著者の大規模な量的調査結果を示しながら、浮かび上がらせる。8章で構成され、第4章までの第1部は、当事者の現状を概説し、国内外の人権課題、カミングアウトとメンタルヘルス、性暴力とDVが取り上げられている。各章で引用される調査結果は、「思い込み」の前で声を出せず不可視化されてきた困難を可視化した当事者の声である。数値の中に人びとの物語が読み取れるのは、調査結果の記述の前後で、丁寧に社会的背景や歴史的動向、海外の状況が紹介されているからであろう。特に第1章に収載された当事者の声では、セクシュアリティの多様性に対する理解や配慮のない医療者のふるまいや医療機関のルールによって、病いや死に直面する人生の重大な場面で、無理解さへの対処に心と頭を使わざるを得ない状況が語られている。
■調査結果を実装に結びつける
第5章以降の第2部では、医療現場と教育現場を取り上げ、それらの課題と医療者、教育機関に期待される実装のあり方が、調査結果とともに丁寧に論述されている。保健医療の現場や医療従事者の教育に携わる方々には、同様の場面が思い浮かび、自分の「常識」を問い直すきっかけになると思う。
また、巻末には、LGBTQ+当事者への3回の大規模な量的調査結果の概要が収録されている。この「巻末資料」は著者の26年にわたる膨大な仕事の一部であり、70ページにわたって集計表が並ぶ。本文と照らし合わせながらこれらの集計表を眺めると、興味深い読み物になるという体験が待っていた。ぜひ、巻末ページを繰られることをお勧めしたい。
本書の全編を通し、社会の事象を多面的に、そして当事者の視点から捉えようとする著者の思慮に、はっとする箇所が多くある。一貫して、マイノリティや差別の存在に視点を置く著者の姿勢に背中を押され、自分の中の「常識」の枠を外し、当たり前と思っている事象を捉え直すべく一歩を踏み出そうと思える1冊である。
(「保健師ジャーナル」 Vol.80 No.6 掲載)
タグキーワード
更新情報
-
2025.12.05
-
2025.04.21