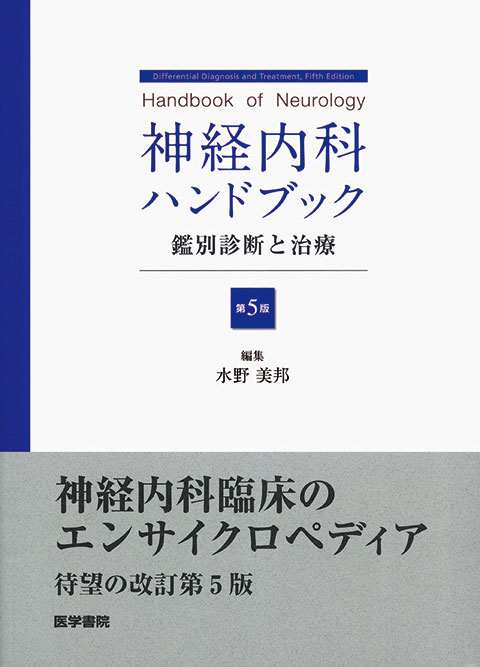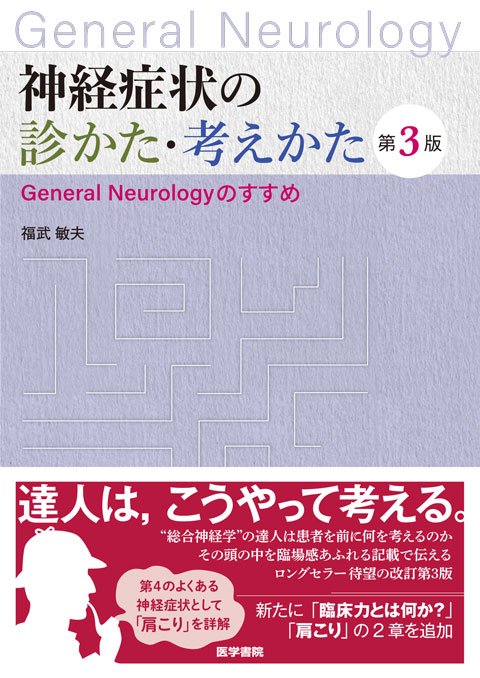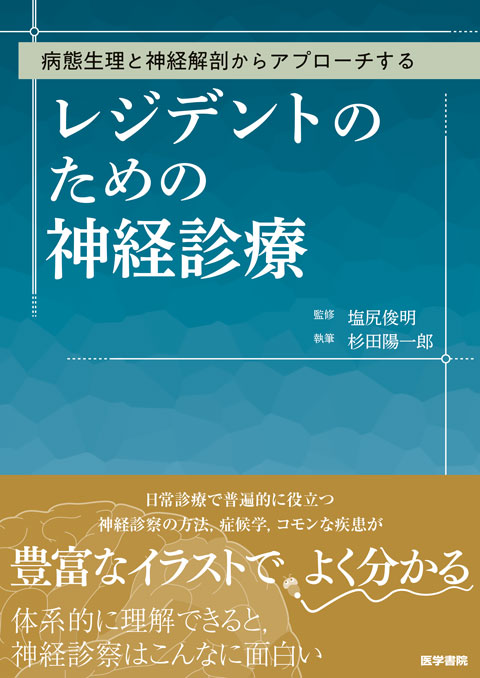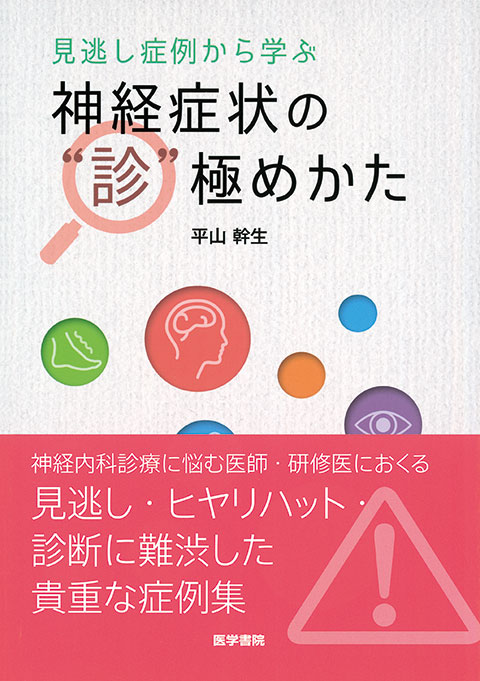神経内科プラクティカルガイド
神経内科の実践知がこの1冊に!
もっと見る
好評書『神経病レジデントマニュアル』を研修医のみならず若手内科医全般に役立つ神経内科診療の手引き書としてアップデート。神経診察や検査の項では手技の写真や解剖図を多用しわかりやすく解説。さまざまな神経疾患を網羅した疾患各論では「診断の決め手」や具体的な処方例を含む治療法を明快に提示。巻末には脳波所見や画像など診療に役立つ付録も収載。神経内科の臨床に長年携わってきた著者の実践知が詰まった1冊。
| 著 | 栗原 照幸 |
|---|---|
| 発行 | 2014年04月判型:A5頁:408 |
| ISBN | 978-4-260-01893-7 |
| 定価 | 4,730円 (本体4,300円+税) |
- 販売終了
- 電子版を購入( 医書.jp )
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
『神経病レジデントマニュアル』初版を1987年,第2版を1997年に,筆者(栗原)と木下和夫先生(宮崎大学名誉教授)の共著により刊行した.宮崎医科大学(現宮崎大学医学部)で神経内科と脳神経外科でカンファレンスを一緒にしながら,木下先生とともに診療をしてきたことも,よい思い出となっている.2005年まで,増刷をするごとに筆者が少しずつ加筆はしてきたが,その後新しい薬も多く出てきて,改訂しないといけない時期になった.今回筆者の手で大幅に改訂を行い,『神経内科プラクティカルガイド』という書籍として出版することになった.
木下先生は写真を撮ることが上手く,うっ血乳頭,頭部外傷の写真,脳動脈瘤,慢性硬膜下血腫,脊髄腫瘍などの脳神経外科的に重要な症候や画像は,2014年になっても時代遅れになることはなく,大切な写真として教育的価値があり,この本でもご厚意によりそのまま残してある.
宮崎医大第3内科の荒木淑郎教授が当時よく言われた,「新しいことがあったらよく記録をしておくことが大切である」というご助言もあって,筆者も診察の写真をたくさん撮影してきた.そして深部腱反射や病的反射の写真では,マルチストロボ多重撮影などもして,診察の仕方がよくわかるように工夫してきた.筆者は1987~2008年までの21年間,東邦大学医療センター大橋病院にて教授職に就いていたが,日本神経学会の認定委員も長年務め,2005年からは卒後教育小委員会の委員長も務めていた.そのため,神経学会の専門医試験を受けにくる若い方たちと毎年接することがあり,彼らの口頭試問のときの診察をみて,神経学的診察がもっと上手にできるようにならないものかと考えてきた.なお,セミナーでは神経学的診察の講義や実習を行う中で,自分の診察を日経BP社からビデオにして出版した.
本邦では,ここ数年間高齢化の影響もあり,神経疾患では特にパーキンソン病,認知症などが増えてきて,また新しい治療薬も出てきたので,本書ではそれらの記載をした.また,高齢になると男性は良性前立腺肥大(BPH)の症例が多く,神経疾患も伴っているので,夜間頻尿とそのために睡眠不足になるという訴えを多く聞く.女性も夜間頻尿を訴える人があり,男性でも女性でも膀胱粘膜が過敏になって,尿が大してたまっていなくても,膀胱が勝手に収縮して尿意を来し,夜間に何回もトイレに起きるために睡眠不足となる場合がある.過活動膀胱も,悪性腫瘍などを否定した後は治療薬があるので,本書では男性と女性の場合の薬物療法を記載した.
本邦で比較的多い視神経脊髄炎(NMO)は,進行すると失明と対麻痺を来し,従来の治療に反応しにくい疾患であるため,記述を加えた.視神経の障害,脊髄には3椎体にわたる病変があり,血中の抗アクアポリン4抗体が陽性となることなど,これを見出した日本人研究者の業績は立派である.治療はステロイドパルス,血漿交換でも効果が不十分なことが多く,生物学的製剤(リツキサン)が用いられて効果がみられている.
片頭痛は10代,20代に始まって,女性に多く,母親から娘へと家族性にみられることが多い.ズキンズキンとする頭痛,嘔気・嘔吐を伴い,仕事や学業に支障を来すが,頓挫薬のトリプタン製剤は高価であり,片頭痛さえ起きなくなれば生活しやすくなるという場合もある.そのため予防薬があり,テラナス,インデラルなどが有効である.さらに抗てんかん薬のバルプロ酸が保険採択され,抗てんかん薬として用いる量よりずっと少なく,1日1回400mgくらいで片頭痛の予防になり,この量なら催奇形性もないということで,これらについても今回記載した.片頭痛予防薬では,片頭痛の頻度も減り,頭痛の強度も軽くなるのでありがたいことである.
筆者が教授職に就いていた2008年までは,下肢静止不能症候群の症例は経験しなかったが,この6年間では,本症の情報がむずむず脚症候群としてマスコミで報道されたこともあって患者数が増えている.薬物治療が有効であり,ドパミンアゴニストやガバペンチン(商品名:レグナイト)も使われているので,これらについても記載した.
高齢化に伴い,認知症の患者が増えているが,病気が進むと幻覚や行動異常が出てくる.その治療として非定型抗精神病薬,あるいは漢方薬の抑肝散などを用いることがある.神経内科医も精神科の知識や,薬物の用い方についてある程度の知識が必要になるため,それらの記述も追加した.
神経内科疾患の診療にあたっては,よい病歴聴取をすることがまず大切であるが,かなり時間を要するので,忍耐強く行う必要がある.よく聞いてもらったということで,それだけで病気の症状が軽くなると言う患者もいる.そのため,本書では医療面接の章(2 問診のとり方)を設けた.また,神経解剖の図も入れて,解剖と対比して診察ができるように記載している.実際の臨床の現場では問診が不十分であることに気がついて,もう一度病歴を聞き直す必要があることも少なからずある.そして,神経系のどこに,どのような病気が存在するかを推測して,診断確定のために検査を組み,問診と神経診察所見から考えて臨床診断をして,検査によってそれを確認するということが望ましい.
現代は医師や研修医にとって忙しい時代であるため,「この疾患にはこの薬」「エビデンスはどうか」などを一目でわかるように本に示してほしいという読者の要求もある.しかし,文献的にもエビデンスがない疾患もあるので,神経内科専門医を志す方は,卒後研修において,できるだけ多くの症例を経験して,自分の頭の中に治療指針を叩き込むことが望ましい.医学部を卒業した方は卒後のプログラムによって,十分な研修を受ければ,どの診療科の専門医にもなりうるポテンシャルをもっていると筆者は考えている.
神経内科にしても,約3年間に,成人の神経内科,小児神経内科,精神科,脳神経外科,脳波・筋電図,神経放射線,神経病理の各分野で一定期間専門家について勉強することが望ましい.どのようにしたらよい神経内科医が育つかという観点から,卒後教育プログラムを組んで実行することが不可欠である.
本書は,臨床の現場において,索引から必要な項目を読んですぐ使うという利用の仕方もあるが,医学生や神経内科の勉強を始めてすぐの研修医の方には,ぜひ通読していただきたい.米国のレジデントプログラムも記載したので,神経内科医の育成を行う方も本書を参考にしていただけると幸いである.
2014年3月
栗原照幸
『神経病レジデントマニュアル』初版を1987年,第2版を1997年に,筆者(栗原)と木下和夫先生(宮崎大学名誉教授)の共著により刊行した.宮崎医科大学(現宮崎大学医学部)で神経内科と脳神経外科でカンファレンスを一緒にしながら,木下先生とともに診療をしてきたことも,よい思い出となっている.2005年まで,増刷をするごとに筆者が少しずつ加筆はしてきたが,その後新しい薬も多く出てきて,改訂しないといけない時期になった.今回筆者の手で大幅に改訂を行い,『神経内科プラクティカルガイド』という書籍として出版することになった.
木下先生は写真を撮ることが上手く,うっ血乳頭,頭部外傷の写真,脳動脈瘤,慢性硬膜下血腫,脊髄腫瘍などの脳神経外科的に重要な症候や画像は,2014年になっても時代遅れになることはなく,大切な写真として教育的価値があり,この本でもご厚意によりそのまま残してある.
宮崎医大第3内科の荒木淑郎教授が当時よく言われた,「新しいことがあったらよく記録をしておくことが大切である」というご助言もあって,筆者も診察の写真をたくさん撮影してきた.そして深部腱反射や病的反射の写真では,マルチストロボ多重撮影などもして,診察の仕方がよくわかるように工夫してきた.筆者は1987~2008年までの21年間,東邦大学医療センター大橋病院にて教授職に就いていたが,日本神経学会の認定委員も長年務め,2005年からは卒後教育小委員会の委員長も務めていた.そのため,神経学会の専門医試験を受けにくる若い方たちと毎年接することがあり,彼らの口頭試問のときの診察をみて,神経学的診察がもっと上手にできるようにならないものかと考えてきた.なお,セミナーでは神経学的診察の講義や実習を行う中で,自分の診察を日経BP社からビデオにして出版した.
本邦では,ここ数年間高齢化の影響もあり,神経疾患では特にパーキンソン病,認知症などが増えてきて,また新しい治療薬も出てきたので,本書ではそれらの記載をした.また,高齢になると男性は良性前立腺肥大(BPH)の症例が多く,神経疾患も伴っているので,夜間頻尿とそのために睡眠不足になるという訴えを多く聞く.女性も夜間頻尿を訴える人があり,男性でも女性でも膀胱粘膜が過敏になって,尿が大してたまっていなくても,膀胱が勝手に収縮して尿意を来し,夜間に何回もトイレに起きるために睡眠不足となる場合がある.過活動膀胱も,悪性腫瘍などを否定した後は治療薬があるので,本書では男性と女性の場合の薬物療法を記載した.
本邦で比較的多い視神経脊髄炎(NMO)は,進行すると失明と対麻痺を来し,従来の治療に反応しにくい疾患であるため,記述を加えた.視神経の障害,脊髄には3椎体にわたる病変があり,血中の抗アクアポリン4抗体が陽性となることなど,これを見出した日本人研究者の業績は立派である.治療はステロイドパルス,血漿交換でも効果が不十分なことが多く,生物学的製剤(リツキサン)が用いられて効果がみられている.
片頭痛は10代,20代に始まって,女性に多く,母親から娘へと家族性にみられることが多い.ズキンズキンとする頭痛,嘔気・嘔吐を伴い,仕事や学業に支障を来すが,頓挫薬のトリプタン製剤は高価であり,片頭痛さえ起きなくなれば生活しやすくなるという場合もある.そのため予防薬があり,テラナス,インデラルなどが有効である.さらに抗てんかん薬のバルプロ酸が保険採択され,抗てんかん薬として用いる量よりずっと少なく,1日1回400mgくらいで片頭痛の予防になり,この量なら催奇形性もないということで,これらについても今回記載した.片頭痛予防薬では,片頭痛の頻度も減り,頭痛の強度も軽くなるのでありがたいことである.
筆者が教授職に就いていた2008年までは,下肢静止不能症候群の症例は経験しなかったが,この6年間では,本症の情報がむずむず脚症候群としてマスコミで報道されたこともあって患者数が増えている.薬物治療が有効であり,ドパミンアゴニストやガバペンチン(商品名:レグナイト)も使われているので,これらについても記載した.
高齢化に伴い,認知症の患者が増えているが,病気が進むと幻覚や行動異常が出てくる.その治療として非定型抗精神病薬,あるいは漢方薬の抑肝散などを用いることがある.神経内科医も精神科の知識や,薬物の用い方についてある程度の知識が必要になるため,それらの記述も追加した.
神経内科疾患の診療にあたっては,よい病歴聴取をすることがまず大切であるが,かなり時間を要するので,忍耐強く行う必要がある.よく聞いてもらったということで,それだけで病気の症状が軽くなると言う患者もいる.そのため,本書では医療面接の章(2 問診のとり方)を設けた.また,神経解剖の図も入れて,解剖と対比して診察ができるように記載している.実際の臨床の現場では問診が不十分であることに気がついて,もう一度病歴を聞き直す必要があることも少なからずある.そして,神経系のどこに,どのような病気が存在するかを推測して,診断確定のために検査を組み,問診と神経診察所見から考えて臨床診断をして,検査によってそれを確認するということが望ましい.
現代は医師や研修医にとって忙しい時代であるため,「この疾患にはこの薬」「エビデンスはどうか」などを一目でわかるように本に示してほしいという読者の要求もある.しかし,文献的にもエビデンスがない疾患もあるので,神経内科専門医を志す方は,卒後研修において,できるだけ多くの症例を経験して,自分の頭の中に治療指針を叩き込むことが望ましい.医学部を卒業した方は卒後のプログラムによって,十分な研修を受ければ,どの診療科の専門医にもなりうるポテンシャルをもっていると筆者は考えている.
神経内科にしても,約3年間に,成人の神経内科,小児神経内科,精神科,脳神経外科,脳波・筋電図,神経放射線,神経病理の各分野で一定期間専門家について勉強することが望ましい.どのようにしたらよい神経内科医が育つかという観点から,卒後教育プログラムを組んで実行することが不可欠である.
本書は,臨床の現場において,索引から必要な項目を読んですぐ使うという利用の仕方もあるが,医学生や神経内科の勉強を始めてすぐの研修医の方には,ぜひ通読していただきたい.米国のレジデントプログラムも記載したので,神経内科医の育成を行う方も本書を参考にしていただけると幸いである.
2014年3月
栗原照幸
目次
開く
1 神経内科を学ぶには
1 アメリカでのインターン経験
2 日本での卒後研修の取り組み
2 問診のとり方
3 神経学的診察
1 神経学的診察の進め方
2 今日の外来
3 神経学的レベル診断
4 臨床検査の進め方
4 意識障害・昏睡
1 一般原則
2 救命処置およびバイタルサインの確保
3 病歴の聴取
4 意識障害の程度の経時的な観察・記録
5 原因の検索
6 診断の決め手となる臨床所見
7 検査プランの立て方と鑑別点
8 治療の基本方針
5 頭痛
1 よくみかける頭痛
2 一般原則
3 日常臨床に当てはまる頭痛の分類
4 緊張型頭痛およびうつ病に伴う頭痛
5 片頭痛
6 群発頭痛
7 三叉神経痛
8 高血圧性頭痛
9 側頭動脈炎に伴う頭痛
10 髄膜炎に伴う頭痛
11 くも膜下出血に伴う頭痛
12 脳出血に伴う頭痛
13 脳腫瘍による頭痛
14 眼科的疾患に伴う頭痛
15 耳鼻科的疾患に伴う頭痛
16 その他の原因による頭痛
6 頭蓋内圧亢進
1 症状・病態
2 原因の検索
3 除外すべき疾患・病態
4 緊急処置
7 てんかん(痙攣発作)
1 一般原則
2 治療の進め方
3 原因の検索
4 大発作の治療法
5 精神運動発作の治療法
6 焦点性運動発作・感覚発作の治療法
7 小発作の治療法
8 痙攣重積状態の治療法
9 抗てんかん薬の血中レベル
10 発作の予後,休薬できるか否か
11 新しい抗てんかん薬
8 めまい
1 原因の検索
2 鑑別
3 薬物の副作用で起こるめまい
4 中耳炎
5 急性内耳炎
6 前庭神経炎
7 Ménière病
8 良性発作性頭位めまい
9 聴神経腫瘍
10 脳血管障害,特に椎骨脳底動脈不全症に伴うめまい
11 側頭葉てんかんに伴うめまい
12 脳神経外科的疾患に伴うめまい
9 認知症
1 一般原則と原因疾患
2 認知症患者に必要な臨床検査
3 治療法
10 不随意運動
1 概要
2 振戦の治療法
3 Wilson病のflapping tremor(羽ばたき振戦)の治療法
4 舞踏病の治療法
5 ジストニアの治療法
6 バリスムの治療法
7 ミオクローヌスの治療法
8 チックの治療法
9 片側顔面痙攣の治療法
10 Gilles de la Tourette症候群の治療法
11 ジスキネジアの治療法
12 下肢静止不能症候群の治療法
11 脳血管障害
1 治療の現状
2 分類
3 診断の決め手と一般原則
4 一過性脳虚血発作(TIA)の治療法
5 脳血栓発症後4.5時間を過ぎている場合の治療法
6 脳塞栓症の治療法
7 脳出血の治療法
8 くも膜下出血の治療法
9 脳浮腫の治療法
12 頭部外傷
1 慢性硬膜下血腫
2 脳挫傷,硬膜外血腫
3 外傷後てんかん
13 神経感染症(脳炎・髄膜炎・プリオン病など)
1 徴候
2 髄液所見の診かた,および治療法
3 プリオン病感染因子の滅菌法
14 脳膿瘍
1 感染経路
2 診断の決め手
3 治療法
15 脳腫瘍
1 症状・病態
2 検査
3 脳神経外科医への移送上の注意
4 治療法
16 後頭骨頸椎移行部の骨奇形
1 一般的な注意
2 診断の決め手
3 治療法
17 脊髄障害
1 徴候
2 原因疾患
3 一般的診療の進め方
4 横断性脊髄炎の治療法
5 外傷性脊髄損傷の治療法
18 神経・筋疾患
1 重症筋無力症
1 診断の決め手
2 治療の原則
3 拡大胸腺摘除術後の不安定状態への対処法
-副腎皮質ステロイドホルモン
4 抗Achエステラーゼ薬
5 血漿交換療法
6 myasthenic crisis
2 Lambert-Eaton症候群
1 診断の決め手
2 治療の原則
3 ボツリヌス中毒
1 診断の決め手
2 治療方針
4 ミオトニー疾患
1 ミオトニー疾患とは
2 ミオトニーを見出す方法
3 ミオトニーを伴う疾患
4 チャネル異常からみたミオトニー疾患の分類
5 治療方針
6 ミオトニーの薬物治療
7 パラミオトニーの治療法
5 多発性筋炎
1 治療の原則
2 診断の決め手と治療法
3 副腎皮質ステロイドホルモンに反応しないときには,どのように治療するか
6 周期性四肢麻痺
1 診断の決め手
2 周期性四肢麻痺の種類
3 低K血性四肢麻痺の治療法
4 低K血性四肢麻痺の予防
5 高K血性四肢麻痺の治療法
7 低K血性ミオパチー
1 診断の決め手
2 治療法
8 甲状腺機能亢進症に伴うミオパチー
1 診断の決め手
2 治療法
19 末梢神経障害
1 分類
2 原因を明らかにする検査プラン
3 原因と基礎疾患の追求
4 Guillain-Barré症候群の治療法
5 慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチーの治療法
6 Miller Fisher症候群の治療法
7 Lewis-Sumner症候群の治療法
8 持続性伝導ブロックを伴う多巣性脱髄性ニューロパチーの治療法
9 急性外傷性末梢神経障害の治療法
10 慢性外傷性末梢神経障害の診断と治療法
11 その他の末梢神経障害の治療法
12 神経痛の治療法
20 神経皮膚症候群
1 神経皮膚症候群とは
2 結節硬化症(tuberous sclerosis)
3 von Recklinghausen病
4 Lindau病,von Hippel-Lindau病
5 Sturge-Weber病
21 パーキンソン病
1 診断
2 本態性パーキンソン病の治療法
3 パーキンソン病患者のうつ状態
4 パーキンソン病治療ガイドラインと筆者の治療法との違いについて
5 便秘の対策
6 パーキンソン病の新薬
7 ジスキネジア(dyskinesia)の治療法
8 L-ドパの持続時間が短時間で
wearing-offやon-off症状が出るときの治療法
9 パーキンソン病の運動症状以外の症状
(non-motor symptoms of Parkinson’s disease)
22 アミロイドポリニューロパチー
1 疫学と本疾患の自然経過
2 診断の決め手
3 血清学的診断
4 治療法
23 運動ニューロン疾患
1 診断の決め手
2 運動ニューロン疾患のケア
24 脊髄小脳変性症
25 脱髄性疾患
1 多発性硬化症の診断基準
2 多発性硬化症急性増悪時の治療法
3 視神経脊髄炎(NMO)
26 自律神経障害
1 起立性低血圧
2 便秘症
3 排尿障害
27 リハビリテーションの基本
1 基本的理念
2 初期プランニングの方法
3 片麻痺のリハビリの実際
4 家に帰ってからのリハビリ-在宅ケアの基本方針
5 失語症患者へのアプローチ
トピックス
遅発性ウイルス感染症,プリオン病,牛海綿状脳症,
非定型的Creutzfeldt-Jakob病
DM2について
新しい治療薬の人への応用
日本神経学会のガイドライン
付録
1 NIHSS判定表
2 Japan Stroke Scale調査票(第5版)
3 脳波の読み方の実際
4 代表的な神経・筋疾患の針筋電図を行ったときの所見
5 末梢神経伝導速度の正常値
(運動神経伝導速度,感覚神経伝導速度,M波振幅)(平均±1SD)
6 F波潜時の正常値
7 誘発電位の正常値
8 正常MRIとその解剖
9 頭頸部MR血管撮影(MRA)
索引
1 アメリカでのインターン経験
2 日本での卒後研修の取り組み
2 問診のとり方
3 神経学的診察
1 神経学的診察の進め方
2 今日の外来
3 神経学的レベル診断
4 臨床検査の進め方
4 意識障害・昏睡
1 一般原則
2 救命処置およびバイタルサインの確保
3 病歴の聴取
4 意識障害の程度の経時的な観察・記録
5 原因の検索
6 診断の決め手となる臨床所見
7 検査プランの立て方と鑑別点
8 治療の基本方針
5 頭痛
1 よくみかける頭痛
2 一般原則
3 日常臨床に当てはまる頭痛の分類
4 緊張型頭痛およびうつ病に伴う頭痛
5 片頭痛
6 群発頭痛
7 三叉神経痛
8 高血圧性頭痛
9 側頭動脈炎に伴う頭痛
10 髄膜炎に伴う頭痛
11 くも膜下出血に伴う頭痛
12 脳出血に伴う頭痛
13 脳腫瘍による頭痛
14 眼科的疾患に伴う頭痛
15 耳鼻科的疾患に伴う頭痛
16 その他の原因による頭痛
6 頭蓋内圧亢進
1 症状・病態
2 原因の検索
3 除外すべき疾患・病態
4 緊急処置
7 てんかん(痙攣発作)
1 一般原則
2 治療の進め方
3 原因の検索
4 大発作の治療法
5 精神運動発作の治療法
6 焦点性運動発作・感覚発作の治療法
7 小発作の治療法
8 痙攣重積状態の治療法
9 抗てんかん薬の血中レベル
10 発作の予後,休薬できるか否か
11 新しい抗てんかん薬
8 めまい
1 原因の検索
2 鑑別
3 薬物の副作用で起こるめまい
4 中耳炎
5 急性内耳炎
6 前庭神経炎
7 Ménière病
8 良性発作性頭位めまい
9 聴神経腫瘍
10 脳血管障害,特に椎骨脳底動脈不全症に伴うめまい
11 側頭葉てんかんに伴うめまい
12 脳神経外科的疾患に伴うめまい
9 認知症
1 一般原則と原因疾患
2 認知症患者に必要な臨床検査
3 治療法
10 不随意運動
1 概要
2 振戦の治療法
3 Wilson病のflapping tremor(羽ばたき振戦)の治療法
4 舞踏病の治療法
5 ジストニアの治療法
6 バリスムの治療法
7 ミオクローヌスの治療法
8 チックの治療法
9 片側顔面痙攣の治療法
10 Gilles de la Tourette症候群の治療法
11 ジスキネジアの治療法
12 下肢静止不能症候群の治療法
11 脳血管障害
1 治療の現状
2 分類
3 診断の決め手と一般原則
4 一過性脳虚血発作(TIA)の治療法
5 脳血栓発症後4.5時間を過ぎている場合の治療法
6 脳塞栓症の治療法
7 脳出血の治療法
8 くも膜下出血の治療法
9 脳浮腫の治療法
12 頭部外傷
1 慢性硬膜下血腫
2 脳挫傷,硬膜外血腫
3 外傷後てんかん
13 神経感染症(脳炎・髄膜炎・プリオン病など)
1 徴候
2 髄液所見の診かた,および治療法
3 プリオン病感染因子の滅菌法
14 脳膿瘍
1 感染経路
2 診断の決め手
3 治療法
15 脳腫瘍
1 症状・病態
2 検査
3 脳神経外科医への移送上の注意
4 治療法
16 後頭骨頸椎移行部の骨奇形
1 一般的な注意
2 診断の決め手
3 治療法
17 脊髄障害
1 徴候
2 原因疾患
3 一般的診療の進め方
4 横断性脊髄炎の治療法
5 外傷性脊髄損傷の治療法
18 神経・筋疾患
1 重症筋無力症
1 診断の決め手
2 治療の原則
3 拡大胸腺摘除術後の不安定状態への対処法
-副腎皮質ステロイドホルモン
4 抗Achエステラーゼ薬
5 血漿交換療法
6 myasthenic crisis
2 Lambert-Eaton症候群
1 診断の決め手
2 治療の原則
3 ボツリヌス中毒
1 診断の決め手
2 治療方針
4 ミオトニー疾患
1 ミオトニー疾患とは
2 ミオトニーを見出す方法
3 ミオトニーを伴う疾患
4 チャネル異常からみたミオトニー疾患の分類
5 治療方針
6 ミオトニーの薬物治療
7 パラミオトニーの治療法
5 多発性筋炎
1 治療の原則
2 診断の決め手と治療法
3 副腎皮質ステロイドホルモンに反応しないときには,どのように治療するか
6 周期性四肢麻痺
1 診断の決め手
2 周期性四肢麻痺の種類
3 低K血性四肢麻痺の治療法
4 低K血性四肢麻痺の予防
5 高K血性四肢麻痺の治療法
7 低K血性ミオパチー
1 診断の決め手
2 治療法
8 甲状腺機能亢進症に伴うミオパチー
1 診断の決め手
2 治療法
19 末梢神経障害
1 分類
2 原因を明らかにする検査プラン
3 原因と基礎疾患の追求
4 Guillain-Barré症候群の治療法
5 慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチーの治療法
6 Miller Fisher症候群の治療法
7 Lewis-Sumner症候群の治療法
8 持続性伝導ブロックを伴う多巣性脱髄性ニューロパチーの治療法
9 急性外傷性末梢神経障害の治療法
10 慢性外傷性末梢神経障害の診断と治療法
11 その他の末梢神経障害の治療法
12 神経痛の治療法
20 神経皮膚症候群
1 神経皮膚症候群とは
2 結節硬化症(tuberous sclerosis)
3 von Recklinghausen病
4 Lindau病,von Hippel-Lindau病
5 Sturge-Weber病
21 パーキンソン病
1 診断
2 本態性パーキンソン病の治療法
3 パーキンソン病患者のうつ状態
4 パーキンソン病治療ガイドラインと筆者の治療法との違いについて
5 便秘の対策
6 パーキンソン病の新薬
7 ジスキネジア(dyskinesia)の治療法
8 L-ドパの持続時間が短時間で
wearing-offやon-off症状が出るときの治療法
9 パーキンソン病の運動症状以外の症状
(non-motor symptoms of Parkinson’s disease)
22 アミロイドポリニューロパチー
1 疫学と本疾患の自然経過
2 診断の決め手
3 血清学的診断
4 治療法
23 運動ニューロン疾患
1 診断の決め手
2 運動ニューロン疾患のケア
24 脊髄小脳変性症
25 脱髄性疾患
1 多発性硬化症の診断基準
2 多発性硬化症急性増悪時の治療法
3 視神経脊髄炎(NMO)
26 自律神経障害
1 起立性低血圧
2 便秘症
3 排尿障害
27 リハビリテーションの基本
1 基本的理念
2 初期プランニングの方法
3 片麻痺のリハビリの実際
4 家に帰ってからのリハビリ-在宅ケアの基本方針
5 失語症患者へのアプローチ
トピックス
遅発性ウイルス感染症,プリオン病,牛海綿状脳症,
非定型的Creutzfeldt-Jakob病
DM2について
新しい治療薬の人への応用
日本神経学会のガイドライン
付録
1 NIHSS判定表
2 Japan Stroke Scale調査票(第5版)
3 脳波の読み方の実際
4 代表的な神経・筋疾患の針筋電図を行ったときの所見
5 末梢神経伝導速度の正常値
(運動神経伝導速度,感覚神経伝導速度,M波振幅)(平均±1SD)
6 F波潜時の正常値
7 誘発電位の正常値
8 正常MRIとその解剖
9 頭頸部MR血管撮影(MRA)
索引
書評
開く
著者の米国での研修成果を感じさせる魅力的な書
書評者: 鈴木 則宏 (慶大教授・神経内科学)
東邦大学名誉教授の栗原照幸先生が,神経内科臨床の実践での活用を目的とする『神経内科プラクティカルガイド』を著された。栗原先生と私とは,医学部の先輩後輩で,同じ神経内科の道に入ったという点では志を同じくし,共通点は多いわけであるが,その研修の道のりはずいぶん異なる。栗原先生は,1967年医学部ご卒業後,当時のインターン制度で研修中にECFMG試験にパスし米国に留学され,Washington University, Barnes-Jewish Hospitalで神経内科の臨床トレーニングを開始された。神経内科レジデントと神経生理学リサーチフェローを経験されている。すなわち,根っからの米国仕込みの「神経内科学」を体得された先生である。したがって,本書は著者の米国でのハードな研修と豊かな経験の成果を隅々に至るまで感じ取ることができる魅力的な書である。
本書は,まず著者の米国留学の体験から語られる。日本での大学紛争最盛期に医学部を卒業され,臨床研修初期から米国に渡られ,新たな世界と研修現場に触れられた体験の記述は興味深いだけでなく,スリリングでさえある。また,現在のわが国の医学教育や臨床研修に対しては,米国の臨床研修を十分に積まれた医師からしか出ないような厳しいコメントも見られる。「日本の医学界は,研究論文を比較的よい雑誌に投稿していることが高く評価されるようになっているので,教授選考でもたくさんの論文を書いて,できるだけ一流の医学雑誌に英文論文を書いていることが,評価の対象になっている傾向がある。しかし臨床で一番大切なことは何であろうか。協調性を兼ね備え,相手の気持ちを考えて,話をよく聞くことができ,損得や出世ではなくて,目の前の患者のために一番助けになる治療でしかもスタンダードな方法を用いて対処することではないだろうか。(後略)」このような,患者と同じ目線で全ての章が書かれている本書は,世に出ている多くの神経内科領域の教科書としても極めてユニークであるといえよう。
内容は,診察の中で最も重要な「問診」から始まり,神経学的診察および病巣診断の解説に移る。神経学的診察では,随所にお若いころの著者の診察手技の写真が登場する。言葉で説明するだけでなく「実際にやって見せる」という著者の姿勢がひしひしと伝わってくる。さらに,読み進むと「神経内科主要症候」の章となる。意識障害・昏睡,頭痛,頭蓋内圧亢進,てんかん,めまい,認知症,不随意運動,と一般外来や救急外来で遭遇する頻度の高い症候が検査,診断,初期対応などについて要領よくまとめられており,実践に役立つ。さらに,「主要神経内科疾患」となり,脳血管障害,頭部外傷,神経感染症,脳膿瘍,脳腫瘍,後頭骨頸椎移行部の骨奇形,脊髄障害,神経・筋疾患,末梢神経障害,神経皮膚症候群,パーキンソン病,アミロイドポリニューロパチー,運動ニューロン疾患,脊髄小脳変性症,脱髄性疾患,自律神経障害と,実臨床で経験する代表的な神経内科疾患が登場する。そして,患者を第一に考える著者の姿勢のまとめとして,最終章には「リハビリテーションの基本」がくる。実に独特なまとめ方である。なお,付録としてNIHSS判定表,Japan Stroke Scale調査票,脳波の読み方の実際,筋電図(針筋電図・神経伝導検査)・誘発電位の所見と正常値,正常頭部・頸部MRI/MRAと解剖が付いている。実にありがたい。
医学部学生,研修医,専門医をめざす神経内科医のみでなく,大成した神経内科専門医にとっても一読の価値のあるすばらしいガイドである。
長年にわたる実地診療の経験からまとめ上げられた書
書評者: 高橋 昭 (名大名誉教授・神経内科学)
本書は,1987年以来,名著として改版や増刷を重ねてきた『神経病レジデントマニュアル』を全面的に改訂増補した書である。本書について語るとき,先生のご経歴を素通りすることはできない。
著者の栗原照幸先生は,1967年に慶應義塾大学医学部を卒業,米国ECFMG(外国人医師卒業教育委員会)試験に合格,ワシントン大学バーンズ病院でインターン,神経内科レジデント。神経生理学リサーチフェロー,宮崎医科大学神経内科学助教授(教授:荒木淑郎先生),東邦大学内科教授を経て,現在東邦大学名誉教授,神経内科津田沼で神経内科の実地診療に従事しておられる,日本を代表するベテラン神経内科医のお一人である。米国の医学教育システムを日本に紹介,日本神経学会では卒後教育委員として医学教育,特に卒後の研修に情熱をもって当たられ,現在の専門医制度の導入に大きな力を発揮された。
このようなご経歴の持ち主の栗原先生が,長年にわたる神経内科の実地診療のご経験を基にまとめ上げられたのが本書であり,上記の前身の書から25年以上の歴史が光る。神経内科学を学ぶに当たっての栗原先生の信条は,本書の第1章に詳述されているので,まずはこの章を熟読してほしい。
本書は症候学や診断手法の詳細を記した一般の神経内科診断学書ではない。「神経学的診察」の章では,むしろ簡潔に診察の要点が述べられ,これに対して「問診」の比重が大きく,神経疾患の診断にはベッドサイドの診察とともに問診が重要であることが強調され,その具体的な指針が述べられている。
「神経学的診察」の章では,多くのオリジナルの写真と図を用いられており,初心者や学生にとっても理解しやすいあたたかい配慮が随所に見られる。
神経疾患患者の診察への第一歩は神経症候の理解と分析である。このことから,日常多く経験される主要な神経内科領域のcommon symptomや徴候として,意識障害・昏睡,頭痛,てんかん,めまい,認知症,不随意運動,便秘・排尿障害などの自律神経障害がそれぞれ独立の章として記述され,実際の診療に大変有用である。さらに,本書の大きな特徴は,これらの症候の治療の要点が的確かつ簡潔にまとめられていることである。例えば「不随意運動」の章では,まず概要の項で診察の仕方と発症機序などがまとめられ,それに続く項では,主要な不随意運動の治療の要点が述べられている。この著述方針は本書の基本をなすものであり,これら以外の神経疾患についても治療に主眼が置かれている。このため,読者は実際の治療に際し,本書をひもとけば,診断や治療の指針が得られる。また各薬剤の,有害事象,薬価,保険点数の問題点にまでも言及されており,患者の経済的負担を考慮して診療に当たるように警鐘が鳴らされている。これらは類書に見ることができない本書の特徴である。
日常診療で最も多く直面する「脳血管障害」「認知症」「パーキンソン病」の章では,最近の治療法の利点欠点をご自身の長年にわたる豊富な経験や考え方に立脚して記されており,参考になる点が多い。
「神経・筋疾患」の項は,栗原先生のご専門が発揮された圧巻ともいえる内容である。重症筋無力症,多発性筋炎,周期性四肢麻痺などは,特にその感が強い。
付録として,ベッドサイドの診察に加えて,電気生理学的検査,画像診断の解説があり,これらへのアプローチと診断的有用性が述べられている。
座右の書として診察室に常備されることをお薦めしたい。
書評者: 鈴木 則宏 (慶大教授・神経内科学)
東邦大学名誉教授の栗原照幸先生が,神経内科臨床の実践での活用を目的とする『神経内科プラクティカルガイド』を著された。栗原先生と私とは,医学部の先輩後輩で,同じ神経内科の道に入ったという点では志を同じくし,共通点は多いわけであるが,その研修の道のりはずいぶん異なる。栗原先生は,1967年医学部ご卒業後,当時のインターン制度で研修中にECFMG試験にパスし米国に留学され,Washington University, Barnes-Jewish Hospitalで神経内科の臨床トレーニングを開始された。神経内科レジデントと神経生理学リサーチフェローを経験されている。すなわち,根っからの米国仕込みの「神経内科学」を体得された先生である。したがって,本書は著者の米国でのハードな研修と豊かな経験の成果を隅々に至るまで感じ取ることができる魅力的な書である。
本書は,まず著者の米国留学の体験から語られる。日本での大学紛争最盛期に医学部を卒業され,臨床研修初期から米国に渡られ,新たな世界と研修現場に触れられた体験の記述は興味深いだけでなく,スリリングでさえある。また,現在のわが国の医学教育や臨床研修に対しては,米国の臨床研修を十分に積まれた医師からしか出ないような厳しいコメントも見られる。「日本の医学界は,研究論文を比較的よい雑誌に投稿していることが高く評価されるようになっているので,教授選考でもたくさんの論文を書いて,できるだけ一流の医学雑誌に英文論文を書いていることが,評価の対象になっている傾向がある。しかし臨床で一番大切なことは何であろうか。協調性を兼ね備え,相手の気持ちを考えて,話をよく聞くことができ,損得や出世ではなくて,目の前の患者のために一番助けになる治療でしかもスタンダードな方法を用いて対処することではないだろうか。(後略)」このような,患者と同じ目線で全ての章が書かれている本書は,世に出ている多くの神経内科領域の教科書としても極めてユニークであるといえよう。
内容は,診察の中で最も重要な「問診」から始まり,神経学的診察および病巣診断の解説に移る。神経学的診察では,随所にお若いころの著者の診察手技の写真が登場する。言葉で説明するだけでなく「実際にやって見せる」という著者の姿勢がひしひしと伝わってくる。さらに,読み進むと「神経内科主要症候」の章となる。意識障害・昏睡,頭痛,頭蓋内圧亢進,てんかん,めまい,認知症,不随意運動,と一般外来や救急外来で遭遇する頻度の高い症候が検査,診断,初期対応などについて要領よくまとめられており,実践に役立つ。さらに,「主要神経内科疾患」となり,脳血管障害,頭部外傷,神経感染症,脳膿瘍,脳腫瘍,後頭骨頸椎移行部の骨奇形,脊髄障害,神経・筋疾患,末梢神経障害,神経皮膚症候群,パーキンソン病,アミロイドポリニューロパチー,運動ニューロン疾患,脊髄小脳変性症,脱髄性疾患,自律神経障害と,実臨床で経験する代表的な神経内科疾患が登場する。そして,患者を第一に考える著者の姿勢のまとめとして,最終章には「リハビリテーションの基本」がくる。実に独特なまとめ方である。なお,付録としてNIHSS判定表,Japan Stroke Scale調査票,脳波の読み方の実際,筋電図(針筋電図・神経伝導検査)・誘発電位の所見と正常値,正常頭部・頸部MRI/MRAと解剖が付いている。実にありがたい。
医学部学生,研修医,専門医をめざす神経内科医のみでなく,大成した神経内科専門医にとっても一読の価値のあるすばらしいガイドである。
長年にわたる実地診療の経験からまとめ上げられた書
書評者: 高橋 昭 (名大名誉教授・神経内科学)
本書は,1987年以来,名著として改版や増刷を重ねてきた『神経病レジデントマニュアル』を全面的に改訂増補した書である。本書について語るとき,先生のご経歴を素通りすることはできない。
著者の栗原照幸先生は,1967年に慶應義塾大学医学部を卒業,米国ECFMG(外国人医師卒業教育委員会)試験に合格,ワシントン大学バーンズ病院でインターン,神経内科レジデント。神経生理学リサーチフェロー,宮崎医科大学神経内科学助教授(教授:荒木淑郎先生),東邦大学内科教授を経て,現在東邦大学名誉教授,神経内科津田沼で神経内科の実地診療に従事しておられる,日本を代表するベテラン神経内科医のお一人である。米国の医学教育システムを日本に紹介,日本神経学会では卒後教育委員として医学教育,特に卒後の研修に情熱をもって当たられ,現在の専門医制度の導入に大きな力を発揮された。
このようなご経歴の持ち主の栗原先生が,長年にわたる神経内科の実地診療のご経験を基にまとめ上げられたのが本書であり,上記の前身の書から25年以上の歴史が光る。神経内科学を学ぶに当たっての栗原先生の信条は,本書の第1章に詳述されているので,まずはこの章を熟読してほしい。
本書は症候学や診断手法の詳細を記した一般の神経内科診断学書ではない。「神経学的診察」の章では,むしろ簡潔に診察の要点が述べられ,これに対して「問診」の比重が大きく,神経疾患の診断にはベッドサイドの診察とともに問診が重要であることが強調され,その具体的な指針が述べられている。
「神経学的診察」の章では,多くのオリジナルの写真と図を用いられており,初心者や学生にとっても理解しやすいあたたかい配慮が随所に見られる。
神経疾患患者の診察への第一歩は神経症候の理解と分析である。このことから,日常多く経験される主要な神経内科領域のcommon symptomや徴候として,意識障害・昏睡,頭痛,てんかん,めまい,認知症,不随意運動,便秘・排尿障害などの自律神経障害がそれぞれ独立の章として記述され,実際の診療に大変有用である。さらに,本書の大きな特徴は,これらの症候の治療の要点が的確かつ簡潔にまとめられていることである。例えば「不随意運動」の章では,まず概要の項で診察の仕方と発症機序などがまとめられ,それに続く項では,主要な不随意運動の治療の要点が述べられている。この著述方針は本書の基本をなすものであり,これら以外の神経疾患についても治療に主眼が置かれている。このため,読者は実際の治療に際し,本書をひもとけば,診断や治療の指針が得られる。また各薬剤の,有害事象,薬価,保険点数の問題点にまでも言及されており,患者の経済的負担を考慮して診療に当たるように警鐘が鳴らされている。これらは類書に見ることができない本書の特徴である。
日常診療で最も多く直面する「脳血管障害」「認知症」「パーキンソン病」の章では,最近の治療法の利点欠点をご自身の長年にわたる豊富な経験や考え方に立脚して記されており,参考になる点が多い。
「神経・筋疾患」の項は,栗原先生のご専門が発揮された圧巻ともいえる内容である。重症筋無力症,多発性筋炎,周期性四肢麻痺などは,特にその感が強い。
付録として,ベッドサイドの診察に加えて,電気生理学的検査,画像診断の解説があり,これらへのアプローチと診断的有用性が述べられている。
座右の書として診察室に常備されることをお薦めしたい。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。