第56回日本癌学会総会開催
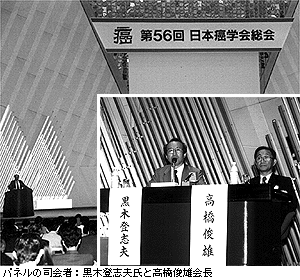 癌研究は分子生物学の日々の新たな進歩とともに飛躍的な進歩を遂げており,一方,ここで得られた癌研究の新しい知見は,分子生物学のさらなる進歩を生み出している。
癌研究は分子生物学の日々の新たな進歩とともに飛躍的な進歩を遂げており,一方,ここで得られた癌研究の新しい知見は,分子生物学のさらなる進歩を生み出している。
このような昨今の状況を背景に,第56回日本癌学会総会が,高橋俊雄会長(京都府立医大教授・外科)のもと,さる9月25-27日,京都市の国立京都国際会館において開催された。
外科からは15年ぶりの会長となった高橋氏は,「基礎研究と臨床との相互のフィードバックによって,癌研究の究極の目的が達せられる」として,“from bench to bed, from bed to bench”をキーワードにプログラムを編成。シンポジウム19題,パネルディスカッション4題(別掲参照),「Control of cell proliferation by cell cycle and the telomerase generation clock」(R.A.ワインバーグ氏),「Transcriptional control by the STAT family」(J.E. ダーネル氏)の2題の特別講演が企画された。
また,学会初日の夜には,公開サテライトシンポジウム「がんの素因の遺伝子診断の倫理的・法的・社会的問題をめぐって」(主催=家族性腫瘍研究会)が企画され,特に遺伝子診断に対しては医学・医療界を超えて幅広い論議を惹き起こした。
なお,本年度の吉田賞は橋本嘉幸氏(佐々木研究所長),長與賞は西満正氏(癌研究会附属病院名誉院長)が受賞し,最終日に授賞式および同記念講演が行なわれた(関連記事)。


パネル「癌研究におけるScienceとPractice」
1980年代初めの癌遺伝子の発見を契機とした,癌遺伝子,癌抑制遺伝子,および癌の転移に関係する遺伝子などの相次ぐ分離,あるいはヒトの癌を研究対象とすることを可能にした遺伝子分析技術であるPCR法の開発などにより,今日,癌研究は遺伝子の時代に入った。パネルディスカッション「癌研究におけるScienceとPractice」(司会=昭和大教授 黒木登志夫氏,高橋俊雄会長)では,「基礎研究によって明らかになった遺伝子の変異は直ちに臨床の場で確認され,臨床の問題点は基礎研究者によって分析される。ベンチとベッドはこれまでになく近づいたと言える」との司会者の言葉を受けて,癌研究の進展と実践について第一線の研究者が話題を提供した。
癌の遺伝子診断とは何か
「癌の遺伝子診断-その光と影」を口演した中村祐輔氏(東大医科研ヒトゲノム解析センター長)は,癌の遺伝子診断を,(1)発症前診断(リスク診断),(2)癌細胞そのものの診断(体内の癌細胞の有無の診断,腫瘍としてでてきたものが悪性であるのか良性であるのかの判定),(3)すでに癌ができてしまっている場合にどのような治療をすればいいのかという指標を考える上で用いられるもの,の3通りに分類。(3)についてはさらに,「癌の広がりを遺伝子で診断するもの」,「どのような性質の癌なのか診断するもの」,「治療に対する感受性を調べるもの」の3通りに分類し,誤解を生みがちな“癌の遺伝子診断”の枠組みを明確にした上で,中村氏は大腸癌についての研究成果を提示した。
中村氏によれば,これまでの大腸癌における再発予測の診断方法は,リンパ節を採ってその中に腫瘍細胞が含まれているかどうかを調べるものであるが,実際に腫瘍細胞がないと診断されたとしても,20-30%の人が遠隔転移を起こして癌で死亡している。そこで,「これらの再発しやすいグループをどのようにして選別するか。それに対していかなる治療をすべきか,あるいはすべきでないか」と治療のスタイルを問い,その視点から,「リンパ節への癌細胞の広がりを遺伝子レベルで診断すること」を試みた。これは,PCR法を工夫し,正常遺伝子は増幅せずに変異遺伝子だけを増幅して目に見えるようにする“MASA(Mutated Allele Specific Amplification)”法を用いて,非常に微量の癌遺伝子の異常を リンパ節中に発見して癌細胞がリンパ管に流れているかということを指標とするものである。
ここから得られた結果をもとに,リンパ節転移が病理学的には陰性であったが,遺伝子レベルでは陽性であったものと,病理学的にも遺伝子レベルでも陰性であった症例を比較。「遺伝子レベルで陰性の患者は,1人も再発していないが,病理学的には陰性の人であっても遺伝子レベルで陽性の患者は半数近くが再発している」と報告し,「遺伝子レベルでリンパ節転移陰性の患者には化学療法を避けるという選択はあってもよい。また,非常に微量な癌細胞が検出された症例に対しては積極的に化学療法をすることにより,転移・再発が防げる」と治療法選択の新たな可能性を示した。
不可欠な基礎研究の評価制度
次いで,抗癌剤や放射線治療に対する感受性の問題に触れ,遺伝子異常を目印に見当をつけた個々の癌細胞の性質によって治療法を選択する可能性について検討。中村氏は,治療を行なった結果としてしか抗癌剤や放射線治療が有効かどうか判定することができない現在の癌治療の問題点を指摘し,「抗癌剤を使用する際には,抗癌剤の使用によってあきらかに予後がよくなるグループと,逆に癌細胞をたたけずにホストを弱らせてしまい,結果的にマイナス効果をもたらしてしまうグループに分ける,というように,個々の癌の性質を把握して的確な対応を考えていかなければならない」と強調した。
p53遺伝子によって誘導されるGML(GPI-anchored molecule like protein)という遺伝子の発現の有無が,化学療法を行なう場合の感受性と関係するとのデータを例に,「このような遺伝子をシステマティックに調べ,どのような患者に抗癌剤治療をすべきか,すべきでないのかという指標をつくらなければならない。遺伝子基礎研究での成果は出ても,それが正しいかどうかを判定・評価する制度が日本には乏しい。遺伝子の研究は進むが,患者さんは影にいるだけだということになりかねない」と危惧を表明した。
社会的側面に多くの課題
遺伝子診断の社会的側面については,「癌の遺伝子治療の倫理的課題」を口演した武部啓氏(京大教授)とともに(1)貧困な遺伝医学教育の現状,(2)不十分な診断技術の評価,(3)カウンセリング,スクリーニング体制の遅れ,(4)プライバシーの侵害という社会的不利益から当事者を保護する法整備を含めた社会的インフラ整備の遅れ等を指摘し,これらの克服を喫緊の課題とした。「遺伝子診断はうまく用いれば,癌の予防,早期発見,早期治療に繋がって患者を完全に治癒させる。あるいは社会復帰を可能にする。また,さまざまな癌の個性診断に用いると非常に的確に治療法を選択できる。しかし,使い方を間違えると,プライバシーの侵害による社会的な不利益,差別,生命保険の拒否,患者さんの精神的な不安を増すだけでなく,未熟な技術により患者さんに迷惑をかけることもあり得る」と中村,武部両氏は,社会的な理解の乏しい現状に警鐘を鳴らした。
ベンチからベッドへ,ベッドからベンチへ
一方,小俣政男氏(東大教授)は「がん研究の進展とその実践-ベンチからベッドへ,ベッドからベンチへ」を口演。本邦における肝細胞癌の95%が肝炎ウイルスによって惹起され,肝炎ウイルスの中でもC型肝炎ウイルスが85%前後の肝癌の原因となっているが,「重要なことは現在までに行なわれた抗ウイルス療法が,従来の方法ではまったく不可能であったHCVキャリア患者の3割に永久的なウイルス駆除をもたらした点である」と指摘。臨床の結果を基礎的につきつめる
さらに「ウイルスが駆除された集団では,肝癌発生率が非駆除群に比べて減少されていることが明らかにされている。従ってベンチに戻るとしたら,なぜ7割で駆除できないのかという研究を,駆除された3割の集団とウイルス増殖の面で基礎的につきつめることによって,もしかしたら100%の集団においてウイルス駆除が可能になるかもしれない」との観点から研究成果を報告した。| ●シンポジウム
(1)ゲノムの不安定性と発癌 (2)癌転移・浸潤の分子機構と人癌での実態 (3)血液細胞の分化と白血病発症機構 (4)難治癌の分子生物学的解析 (5)癌抑制遺伝子 (6)癌とテロメア・テロメラーゼ (7)アポトーシスと癌 (8)癌の化学予防 (9)癌の遺伝子治療 (10)癌の悪性度を決定する糖鎖 (11)新規抗癌剤・その開発の基礎と治療への展望 (12)癌治療における造血幹細胞移植療法 (13)癌の遺伝子診断 (14)フリーラジカルと発癌機構 (15)癌の血管新生とその制御 (16)サイトカインと癌の制御 (17)ウイルス発癌の新しい展開 (18)Drug Delivery Systemを利用した癌治療 (19)癌量子治療の新展開 ●パネルディスカッション
|
