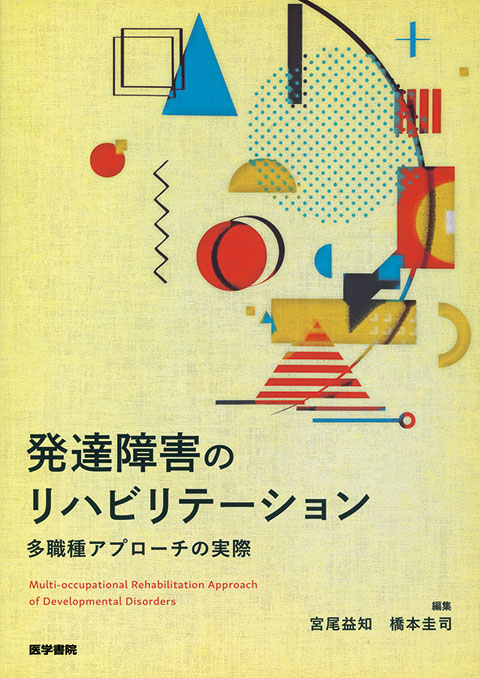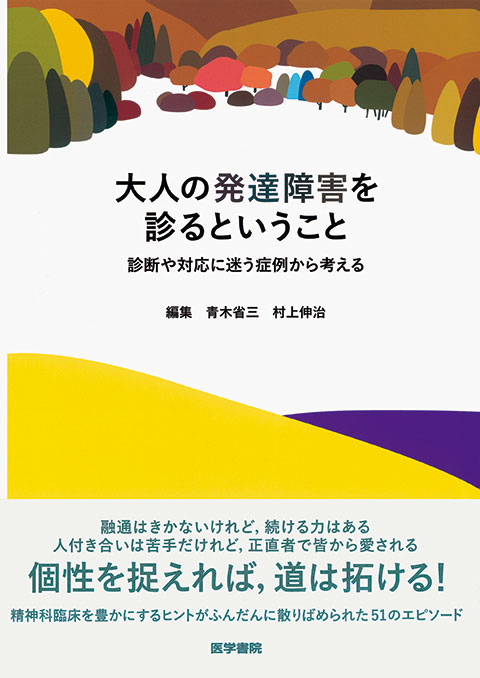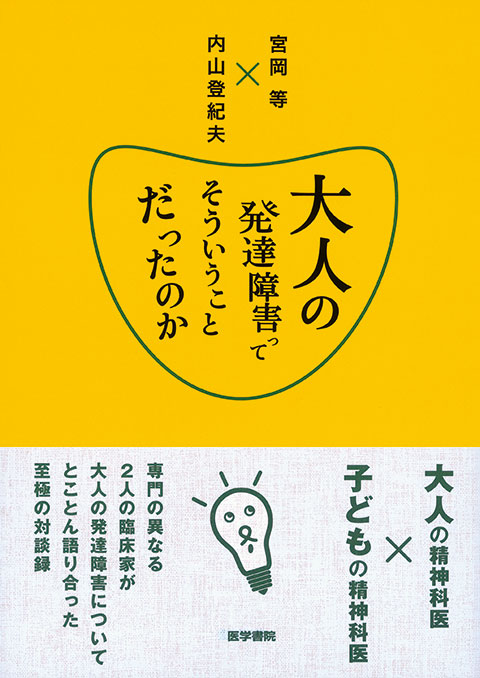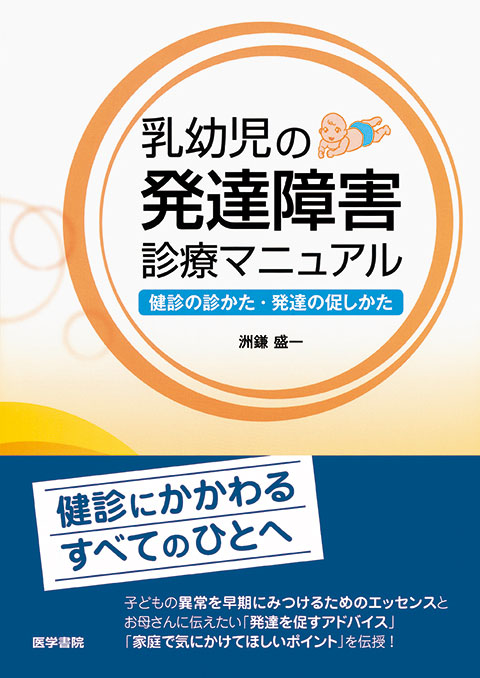発達障害のリハビリテーション
多職種アプローチの実際
発達障害支援に関わるすべての専門職へ-ライフステージを通した支援のための手引書
もっと見る
多くの職種が関わる発達障害者支援。各職種での支援のノウハウは蓄積されつつあるが、多職種間ではほとんど共有されていないのが現状である。幼児期から成人期までの幅広いライフステージにおよぶ発達障害者支援には医療、地域、福祉、教育、労働など多分野の連携が不可欠である。本書は、発達障害者に関わるさまざまな職種の取り組みを立体的に紹介。「多職種による連携」をキーワードに発達障害者支援に関わるための手引書。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
はじめに
これまで,リハビリテーションの分野では,発達障害のリハビリテーションについては,成人の整形外科疾患や脳血管障害のリハビリテーションに比べて,関連する医師やコメディカルからの関心はそれほど高くはありませんでした.小児神経科や児童精神科,療育や障害児教育の分野において,さまざまなノウハウが蓄積されているにもかかわらず,「一般の」リハビリテーション関係者には馴染みの薄い分野であったといえます.
しかしながら近年,わが国における少子化の波は歯止めがきかず,ハイリスク児の増加や発達障害概念の拡大,核家族化などの社会構造の変化もあり,子どもから成人まで,発達障害児者が増え続けています.発達障害児は将来,必ず大人になり,社会へと巣立って行きます.発達障害児者への支援は小児期だけで終わらず,当然のことながら医師だけでできるものではなく,看護師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,心理療法士,ソーシャルワーカーなどのコメディカルスタッフが皆で協力し,医療,福祉,教育,就労の分野がお互いに手を携えて,多職種による新たな文化の醸成をすることが必要です.
本書籍を発刊するきっかけは,医学書院から発刊されている月刊誌「総合リハビリテーション」において,「発達障害のリハビリテーション」という特集を企画したところ,読者から大きな反響があったことでした.
同誌の編集顧問である上田敏氏は,「患者・障害者のリハビリテーション」とは,疾患・障害のために人間らしく生きることが困難になった人の「人間らしく生きる権利の回復」であり,これは医学だけではなく,教育,職業,福祉,介護などの専門家と,地域社会が,本人・家族を中心に行う「総合リハビリテーション」でなければならない,と述べています.
本書籍は,臨床の現場で発達障害児者の支援に日々奮闘している各分野の専門家に,発達障害児者へのアプローチの実際について実践的にご執筆いただきました.
どのページからでも構いません.ご自分の関心のある分野から発達障害のリハビリテーションの扉を開いていただき,それが読者の皆様1人ひとりが実践できる「総合リハビリテーション」の始まりになれば幸いです.
2017年3月
橋本圭司
これまで,リハビリテーションの分野では,発達障害のリハビリテーションについては,成人の整形外科疾患や脳血管障害のリハビリテーションに比べて,関連する医師やコメディカルからの関心はそれほど高くはありませんでした.小児神経科や児童精神科,療育や障害児教育の分野において,さまざまなノウハウが蓄積されているにもかかわらず,「一般の」リハビリテーション関係者には馴染みの薄い分野であったといえます.
しかしながら近年,わが国における少子化の波は歯止めがきかず,ハイリスク児の増加や発達障害概念の拡大,核家族化などの社会構造の変化もあり,子どもから成人まで,発達障害児者が増え続けています.発達障害児は将来,必ず大人になり,社会へと巣立って行きます.発達障害児者への支援は小児期だけで終わらず,当然のことながら医師だけでできるものではなく,看護師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,心理療法士,ソーシャルワーカーなどのコメディカルスタッフが皆で協力し,医療,福祉,教育,就労の分野がお互いに手を携えて,多職種による新たな文化の醸成をすることが必要です.
本書籍を発刊するきっかけは,医学書院から発刊されている月刊誌「総合リハビリテーション」において,「発達障害のリハビリテーション」という特集を企画したところ,読者から大きな反響があったことでした.
同誌の編集顧問である上田敏氏は,「患者・障害者のリハビリテーション」とは,疾患・障害のために人間らしく生きることが困難になった人の「人間らしく生きる権利の回復」であり,これは医学だけではなく,教育,職業,福祉,介護などの専門家と,地域社会が,本人・家族を中心に行う「総合リハビリテーション」でなければならない,と述べています.
本書籍は,臨床の現場で発達障害児者の支援に日々奮闘している各分野の専門家に,発達障害児者へのアプローチの実際について実践的にご執筆いただきました.
どのページからでも構いません.ご自分の関心のある分野から発達障害のリハビリテーションの扉を開いていただき,それが読者の皆様1人ひとりが実践できる「総合リハビリテーション」の始まりになれば幸いです.
2017年3月
橋本圭司
目次
開く
第1章 発達障害とは何か
1 国内外の現状と課題
2 早期からの発見と支援の現状
3 低出生体重児と発達障害
4 診断の実際
5 治療の実際
6 リハビリテーションのマネジメント
7 成人期の支援
第2章 各障害へのアプローチ
1 こころと認知の発達
2 ASD
3 ADHD
4 LD
5 DCD
6 高次脳機能障害
第3章 多職種アプローチ
1 セラピストによる実践
1)作業療法
2)言語聴覚療法
3)理学療法
4)発達心理検査
2 歯科の実践
3 教育の実践
4 ソーシャルワークの実践
5 発達障害の就労移行支援事業
6 ペアレントトレーニング
索引
1 国内外の現状と課題
2 早期からの発見と支援の現状
3 低出生体重児と発達障害
4 診断の実際
5 治療の実際
6 リハビリテーションのマネジメント
7 成人期の支援
第2章 各障害へのアプローチ
1 こころと認知の発達
2 ASD
3 ADHD
4 LD
5 DCD
6 高次脳機能障害
第3章 多職種アプローチ
1 セラピストによる実践
1)作業療法
2)言語聴覚療法
3)理学療法
4)発達心理検査
2 歯科の実践
3 教育の実践
4 ソーシャルワークの実践
5 発達障害の就労移行支援事業
6 ペアレントトレーニング
索引
書評
開く
多角的な視点で学べる発達障害のバイブル
書評者: 本田 真美 (みくりキッズくりにっく院長)
20年前,発達障害の概念がここまでの広がりをみせるとは誰が想像したであろうか。診察室や教室で「ちょっと気になる」子どもたちは,「障害」という括りの中でクローズアップされ,その診断,治療,対応,制度の改正などについてさまざまな専門家たちが議論を重ねてきた。
普通学級に通う子どもたちの約7%が発達障害のスペクトラムを持つ,という文部科学省の衝撃的な発表は話題となったが,発達障害という概念自体がスペクトラムであり,正常か異常かの境界線は曖昧なものである。その境に「社会適応」というキーワードは重要であり,実際に社会で「適応」している発達障害のスペクトラムをもつ児(者)の数は想像をはるかに超え,その中には異彩を放ち大活躍している方々が大勢いると推測される。
average(平均)=normal(正常)と考えがちなのは日本人の習性なのかもしれないが,特性の偏りを持つ発達障害児(者)が集団の中でabnormalな存在ではなく,個のcharacterとして受容し,受容されながら社会の一員として安定して生活を送れるようにすることが発達障害医療の目標でありゴールといえよう。
本書を編集した宮尾益知氏(どんぐり発達クリニック院長)は私の20年来の恩師であるが,小児神経科医として常に第一線で活躍し続け,その先見の明と抜群の診療センスは他に類をみない医師として定評がある。彼の後を追い続け小児神経科医として同じ道を歩んでいるが,20年たった今でも会うたびに新しい情報を教示してくださり,私にとってはいつまでたっても追い越すことができない大きな存在である。
同じく編集者の橋本圭司氏は私の大学時代の同級生であり,成人の高次脳機能障害における第一人者である。彼は小児の発達障害という概念にリハビリテーション医療からの新しい切り口として,多職種連携や成人までの連続した児者一貫支援,社会とのつながりについて強調している。
この二人が編集した本書が,これまで出版されてきた多くの発達障害に関する書籍とは全く別次元のものであることは言うまでもない。手に取ったものの「どこから読み進めるか」ということから悩んでしまうほど,執筆されている先生方は著名な方ばかり,多種多様な視点から書かれた内容はどれも知りたかったものばかりである。本書に,今日からすぐに診療で使える内容が満載なのは,臨床医として長年多くの患児,家族を診てこられたお二人だからこそなしえたのであり,さすがの一言である。
本書は医師だけでなく,発達障害児(者),家族の幸せを願う全ての職種の方々のまさにバイブルといえよう。
書評者: 本田 真美 (みくりキッズくりにっく院長)
20年前,発達障害の概念がここまでの広がりをみせるとは誰が想像したであろうか。診察室や教室で「ちょっと気になる」子どもたちは,「障害」という括りの中でクローズアップされ,その診断,治療,対応,制度の改正などについてさまざまな専門家たちが議論を重ねてきた。
普通学級に通う子どもたちの約7%が発達障害のスペクトラムを持つ,という文部科学省の衝撃的な発表は話題となったが,発達障害という概念自体がスペクトラムであり,正常か異常かの境界線は曖昧なものである。その境に「社会適応」というキーワードは重要であり,実際に社会で「適応」している発達障害のスペクトラムをもつ児(者)の数は想像をはるかに超え,その中には異彩を放ち大活躍している方々が大勢いると推測される。
average(平均)=normal(正常)と考えがちなのは日本人の習性なのかもしれないが,特性の偏りを持つ発達障害児(者)が集団の中でabnormalな存在ではなく,個のcharacterとして受容し,受容されながら社会の一員として安定して生活を送れるようにすることが発達障害医療の目標でありゴールといえよう。
本書を編集した宮尾益知氏(どんぐり発達クリニック院長)は私の20年来の恩師であるが,小児神経科医として常に第一線で活躍し続け,その先見の明と抜群の診療センスは他に類をみない医師として定評がある。彼の後を追い続け小児神経科医として同じ道を歩んでいるが,20年たった今でも会うたびに新しい情報を教示してくださり,私にとってはいつまでたっても追い越すことができない大きな存在である。
同じく編集者の橋本圭司氏は私の大学時代の同級生であり,成人の高次脳機能障害における第一人者である。彼は小児の発達障害という概念にリハビリテーション医療からの新しい切り口として,多職種連携や成人までの連続した児者一貫支援,社会とのつながりについて強調している。
この二人が編集した本書が,これまで出版されてきた多くの発達障害に関する書籍とは全く別次元のものであることは言うまでもない。手に取ったものの「どこから読み進めるか」ということから悩んでしまうほど,執筆されている先生方は著名な方ばかり,多種多様な視点から書かれた内容はどれも知りたかったものばかりである。本書に,今日からすぐに診療で使える内容が満載なのは,臨床医として長年多くの患児,家族を診てこられたお二人だからこそなしえたのであり,さすがの一言である。
本書は医師だけでなく,発達障害児(者),家族の幸せを願う全ての職種の方々のまさにバイブルといえよう。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。