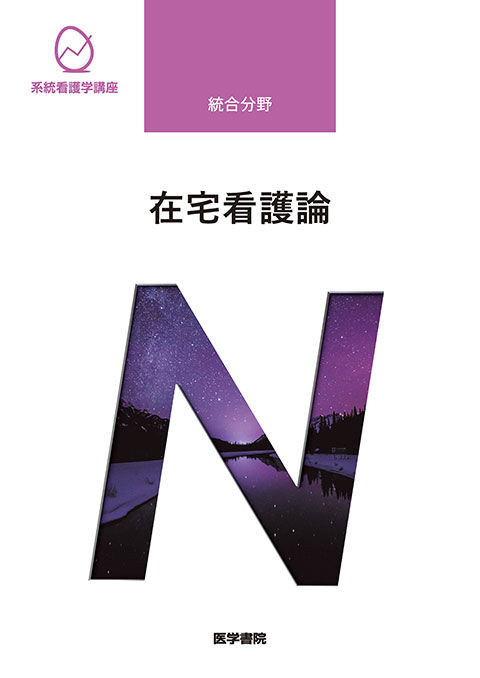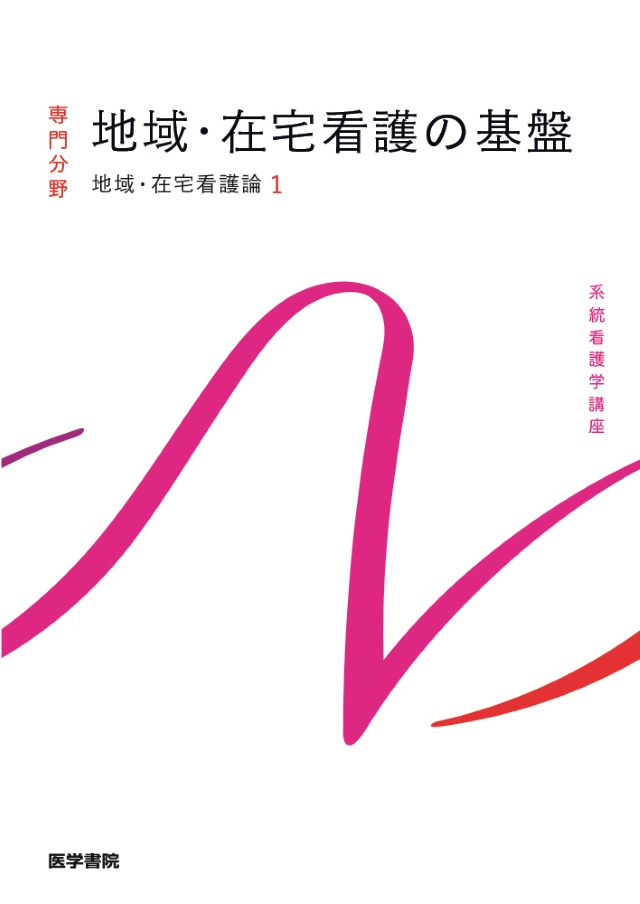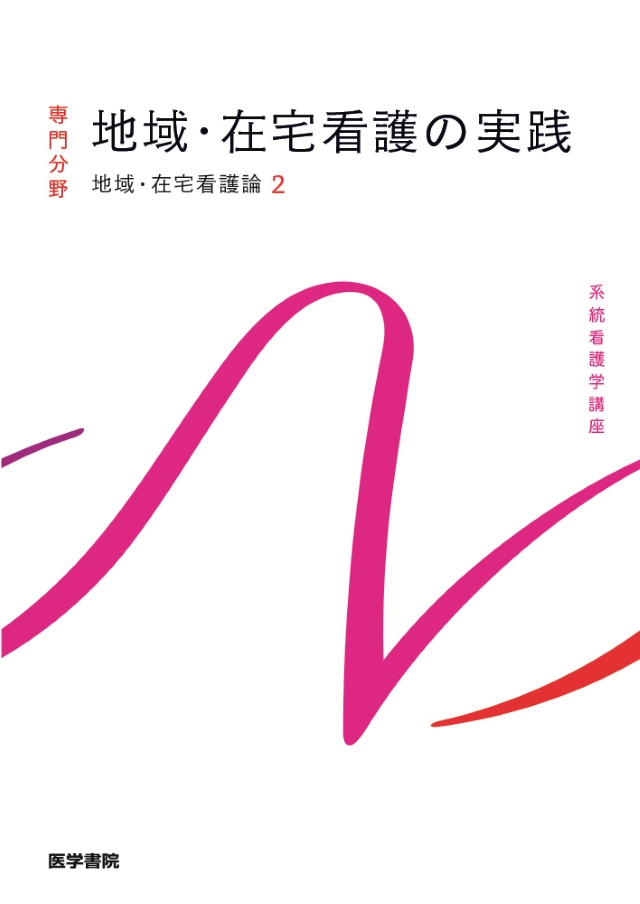在宅看護論 第5版
もっと見る
・患者の自宅で看護を提供するイメージをもちやすくするため、訪問看護師の仕事を紹介する〈序章〉を設けました。また、統合分野として、本書でどのようなことを学習するかを示しています。
・本書では構成を〈総論編〉と〈実践編〉に分けて展開しています。
・〈総論編〉では、まず在宅看護の目的や特徴、背景となる対象者や家族、制度、在宅看護過程の展開など、基礎的な知識を学びます。家族への看護や退院支援・退院調整、地域包括ケアなどに関する内容を充実させました。
・次に〈実践編〉で、在宅看護で必要とされる技術について学びます。新たに「コミュニケーション支援」や「外来がん治療の支援」を設け、国家試験や実習の場でもいかせる知識を得ることができます。
・第7章では、臨床場面をイメージできるように在宅看護の臨床場面として特徴的な事例を9つあげて展開しています。これらの事例を通して、在宅看護の臨床現場を意識しながら在宅看護に必要な知識や在宅看護の展開を学べるように努めています。
・付章では、資料として「実習の心得」や「保健医療福祉の動向と訪問看護の歴史」一覧表などを掲載しています。
| シリーズ | 系統看護学講座-統合分野 |
|---|---|
| 著 | 秋山 正子 / 小倉 朗子 / 乙坂 佳代 / 加藤 希 / 亀井 智子 / 河原 加代子 / 清崎 由美子 / 久保 祐子 / 佐藤 美穂子 / 島田 珠美 / 島田 恵 / 清水 準一 / 清水 奈緒美 / 鈴木 志律江 / 高橋 美保 / 高村 浩 / 武田 貴子 / 戸村 ひかり / 長濱 あかし / 花田 政之 / 平原 優美 / 福井 小紀子 / 堀内 園子 / 松下 祥子 / 山田 雅子 / 和田 洋子 |
| 発行 | 2017年01月判型:B5頁:448 |
| ISBN | 978-4-260-02762-5 |
| 定価 | 2,860円 (本体2,600円+税) |
- 2022年春 分冊化
- 改訂情報
更新情報
-
正誤表を追加しました。
2021.04.16
- 序文
- 目次
- 正誤表
序文
開く
看護の対象である人間は,周囲の環境から影響を受け,環境との相互作用のなかでたえず変化しながら生活を営んでいる。外部からの刺激に巧みに対応し,患者の生命力の消耗を最少にするように環境を整え,健康の回復に寄与することが看護学の根底をなす考え方である。看護基礎教育における在宅看護論では,人々が生活する在宅という環境において,対象者の「生きること」を支えるという,看護の基本となるものを学習することが大きなねらいとなる。
平均寿命やがん罹患後の生存年数の延伸など,社会情勢の変化や医療の発展に伴い,医療・介護に対する人々のニーズも変化してきた。この変化に対応するため,病気などになっても住み慣れた地域で暮らすことのできる,地域包括ケアシステムの構築が強く推進されている。そのなかで看護師には,認知症者のケアや,がん患者の看護,人生を最期まで生ききることへの支援など,幅広い年齢を対象とする,診療科をこえた看護が求められるようになっている。
在宅医療において最も求められるのは,1人ひとりの生き方に応じた医療を,卓越した技能をもって提供する専門性である。日々の生活を支えるという,一見簡単にもみえる在宅での看護は,対象者の個別性に応じると同時に,医療の提供方法に独創性を必要とする応用的な分野である。
地域でのケアが進められるなかで,在宅看護はあらためてその重要性が認められ,(1)対象者を全人的にとらえてその生活を重視する,(2)生活する場を熟知している,(3)対象者を取り巻く環境やシステム,人的・物的資源の活用に能力を発揮するなど,専門性が明確化されてきた。たとえば,医療依存度の高い人の在宅でのケアでは,日々の健康状態を的確に判断・評価し,緊急時には臨床判断・実践能力をもって適切に対応する。在宅生活の継続を支援するためには,地域の人的・物的資源を効果的に活用する。また,人生の最終段階を迎える対象者には,その人が最期までどう生きるか,その人にとっての尊厳ある生き方を支える。
そのほか,地域の社会資源の活用や地域ネットワークの構築に向けても,在宅看護はその専門性を発揮して,独自の役割を担う。たとえば,看護師が療養者の暮らしのなかからデータを収集し,その結果に基づいて行政などに新しいサービスを提案している。さらに,個別の看護実践にとどまらず,経験や技術を共有することで,エビデンスに基づいた在宅看護実践の向上に寄与することも求められている。
改訂にあたって
看護基礎教育においては,2008年のカリキュラムの改正により「在宅看護論」が「統合分野」に位置づけられた。これを受けて本書は第3版より,総論編・実践編の2部構成として,カリキュラムに十分に対応できるかたちをとっている。第5版への改訂にあたっては,介護保険制度や難病法など,法令・制度に関する情報の更新を行うと同時に,「保健師助産師看護師国家試験出題基準平成26年版」をもとに内容の精査を行い,今日の在宅看護論のテキストとして十分な内容となるように加筆・修正を行った。
今回の改訂では,はじめに,初学者が在宅看護について具体的にイメージできるように,訪問看護師の仕事を紹介する序章を設けた。
総論編は,在宅看護を展開するうえで必要な知識を学習するものとした。地域包括ケアや在宅療養移行支援などを大きく取り上げるとともに,熱中症の予防,サービス提供者の権利擁護などについても新たに項目を設けた。第3章「在宅療養の支援」を新たに加え,在宅看護の提供方法,療養の場の移行,そして,在宅看護に取り組む者がなにを行うかとして,在宅看護の基本となるものをまとめた。
実践編は,在宅で看護を提供するうえでの実践的な知識をまとめ,事例により在宅看護の流れを学習できる内容とした。在宅看護技術にかかわるガイドラインや医療機器について内容をアップデートするとともに,コミュニケーションの支援や,外来がん治療の支援の項目を新設した。第7章では,各事例の最後に「発展的学習」の項目を設け,事例を学んだうえで,学生に考えてもらいたい課題を設定した。
なお,在宅において看護を必要とする人々についての表現は,前版と同様に「療養者」を基本とした。
在宅看護論は,今後ますます対象者の多様なニーズに応え得る教育内容に発展し,その重要性が大きくなることが予想される。今回の改訂によって,在宅看護の知識を身につけるとともに,在宅で看護を提供することの意義やおもしろさに気づいてもらえることを願う。本書をご活用いただき,読者の皆さんの忌憚のないご意見をいただければ幸いである。
2016年11月
著者を代表して
河原加代子
目次
開く
●第1部 総論編
第1章 在宅看護の目的と特徴 (山田雅子)
A 在宅看護の目ざすもの
1 在宅看護が提供される場
2 在宅看護の場の広がり
3 在宅看護に求められていること
4 あらゆる面からQOLを考える
B 在宅看護における看護師の役割
1 超高齢多死社会の進展と地域包括ケア
2 対象者のケアニーズに応じた在宅看護の提供
3 在宅看護における看護師の倫理
第2章 在宅看護の対象者 (福井小紀子・河原加代子)
A 対象者の特徴
1 年齢からみた対象者の特徴
2 疾患からみた対象者の特徴
3 障害からみた対象者の特徴
4 在宅療養状態別にみた対象者の特徴
B 住まい方と健康
C 家族
1 在宅看護の対象者としての家族
2 家族のとらえ方と看護師のかかわり
3 家族のアセスメント
4 家族への支援
5 地域システムの視点から家族を支える
第3章 在宅療養の支援 (島田恵・戸村ひかり・清崎由美子・島田珠美・山田雅子)
A 在宅看護の提供方法
1 外来看護
2 訪問看護
3 施設での看護
4 通所サービスでの看護
B 療養の場の移行
1 患者・家族の意思決定支援と調整
2 退院支援・退院調整
3 入退院時における医療機関との連携
4 入退所時における施設との連携
C 在宅看護の基本となるもの
第4章 在宅看護にかかわる法令・制度とその活用 (福井小紀子・乙坂佳代)
A 訪問看護制度の創設と発展経緯
B 在宅看護にかかわる法令・制度
C 介護保険制度
D 訪問看護の制度
1 訪問看護の利用者と訪問回数
2 訪問看護ステーションに関する規程
3 訪問看護の利用までの手順
4 訪問看護の費用
E 訪問看護サービスの提供
F ケアマネジメントと社会資源の活用
G 地域における多職種連携
1 在宅における連携の特徴
2 医師との連携
3 地域の社会資源との連携
4 ネットワークづくり
第5章 在宅看護の展開 (清水準一・松下祥子・河原加代子・清崎由美子・島田珠美・久保祐子・高村浩)
A 在宅看護過程展開のポイント
1 療養者の多様な生活と価値観
2 生活環境や家族への視点
3 時間的な広がりへの着目
4 生活を支える制度・支援体制の理解
5 まとめ
B 在宅看護過程の展開方法
1 在宅看護過程の特徴
2 情報収集とアセスメント
3 目標の設定・計画
4 実施と評価
5 在宅看護の標準化に向けた取り組み
C 療養上のリスクマネジメント
1 在宅看護におけるリスクとは
2 環境の整備による安全の確保
3 身体損傷の防止
4 薬物による事故の防止
5 感染の防止
6 災害に対する準備と対応
D 在宅看護における権利保障
1 個人の尊厳
2 自己決定権
3 個人情報の保護
4 個人情報等の情報の開示
5 成年後見
6 虐待の防止
7 サービス提供者の権利擁護
8 在宅看護における法律問題の事例
●第2部 実践編
第6章 在宅看護技術
島田珠美・清水準一・長濱あかし・加藤希・清水奈緒美・高橋美保)
1 在宅看護の活動を支えるコミュニケーション
2 在宅看護を展開するうえで検討すべきポイント
B 在宅で求められる看護技術
1 呼吸に関する在宅看護技術
2 食生活・嚥下に関する在宅看護技術
3 排泄に関する在宅看護技術
4 移動・移乗に関する在宅看護技術
5 清潔に関する在宅看護技術
6 認知機能のアセスメント法と援助技術
7 コミュニケーションの支援
8 在宅におけるエンドオブライフケア
C 在宅における医療管理を要する人の看護
1 褥瘡の予防とケア
2 尿道留置カテーテル
3 ストーマ(人工肛門・人工膀胱)
4 経管栄養法
5 在宅中心静脈栄養法(HPN)
6 非侵襲的陽圧換気療法(NPPV)
7 在宅酸素療法(HOT)
8 在宅人工呼吸療法(HMV)と排痰法
9 外来がん治療の支援
10 疼痛緩和
第7章 在宅看護の実際
(亀井智子・島田珠美・鈴木志律江・堀内園子・小倉朗子・武田貴子・秋山正子・花田政之)
A 在宅看護介入時期別の特徴
1 在宅療養準備期(退院前)
2 在宅療養移行期
3 在宅療養安定期
4 急性増悪期
5 終末期(看取り期)
6 在宅療養終了期
B 脳卒中をおこした患者の在宅療養導入の事例展開
1 療養者についての情報
2 リハビリテーション病院からの退院計画
3 在宅療養の開始
C パーキンソン病の療養者に対する在宅看護の事例展開
1 療養者についての情報
2 アセスメント
3 看護目標・計画
4 訪問看護の実施経過と評価
D 認知症の療養者に対する在宅看護の事例展開
1 療養者についての情報
2 アセスメント
3 看護目標・計画
4 訪問看護の実施経過と評価
E 小児の療養者に対する在宅看護の事例展開
1 療養者についての情報
2 退院計画
3 退院時のカンファレンス
4 在宅療養の開始
5 日常の看護の実際
F ALSで人工呼吸療法を実施する療養者の在宅看護の事例展開
1 療養者についての情報
2 アセスメント
3 看護目標・計画
4 訪問看護の実施経過と評価
G COPDの療養者に対する在宅看護の事例展開
1 療養者についての情報
2 アセスメント
3 看護問題と看護目標・計画
4 訪問看護の実施経過
5 評価
H 独居の療養者に対する在宅看護の事例展開
1 療養者についての情報
2 アセスメント
3 看護目標・計画
4 訪問看護の実施経過
5 評価
I 終末期(がん)の療養者に対する在宅看護の事例展開
1 療養者についての情報
2 退院後訪問開始初期(終末期前期)
3 安定期:訪問開始2週目から約1か月
4 終末期・臨死期(終末期後期):死亡前10日間
5 死亡直後
J 統合失調症の療養者に対する在宅看護の事例展開
1 療養者についての情報
2 アセスメント
3 看護目標・計画
4 訪問看護の経過とケアの実際
5 短期目標・計画の評価
付章 資料編 (清水準一・佐藤美穂子・松下祥子・河原加代子)
A 在宅看護論における実習の手引き
1 実習に向けた心構え
2 服装や身だしなみ
3 態度と行動
4 実習における学習方法
5 感染予防
6 事故・災害等発生時の対応
7 個人情報の取り扱い
B 訪問看護倫理要綱
1 在宅看護の対象者の権利
2 訪問看護師の使命,「療養生活支援の専門家」としての誇りと自律性
3 訪問看護師とケアチーム
C 保健・医療・福祉の動向と訪問看護の歴史
D 参考資料
索引
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。
更新情報
-
正誤表を追加しました。
2021.04.16