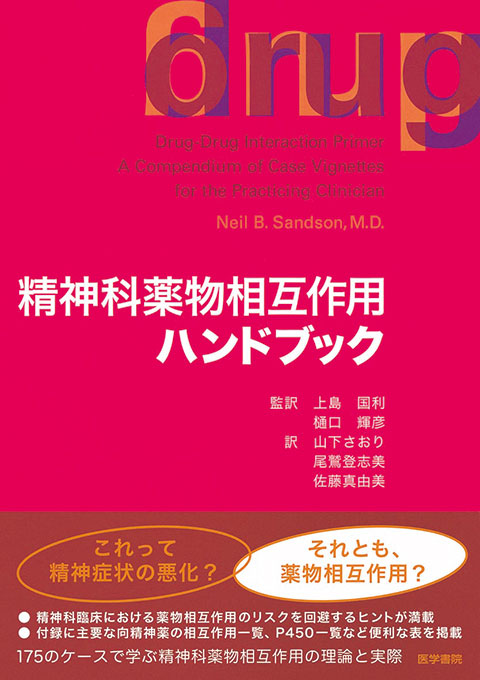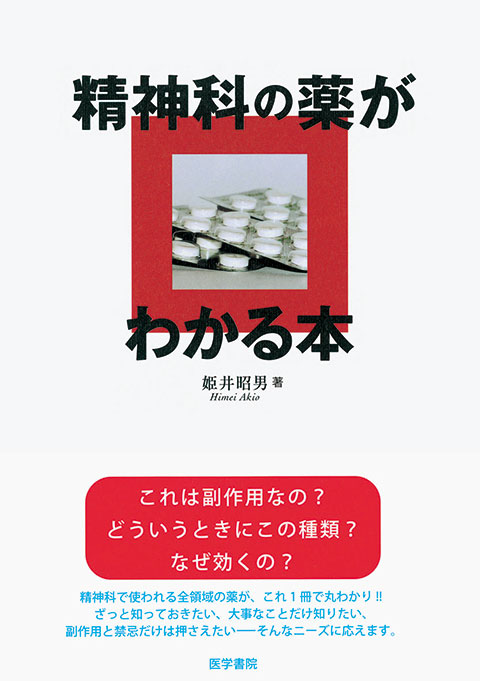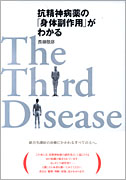内科医が知っておきたい
向精神薬の選び方・使い方
内科医が日常診療で出会う精神疾患とその治療法を専門医がわかりやすく解説
もっと見る
内科医が日常診療で出会う精神疾患,その治療法を専門医がわかりやすく解説。症状の把握の仕方,診断と治療の手順が具体的に述べられており,向精神薬を用いた薬物療法は処方例をあげて親切に呈示。今,身近にある患者の“心の問題”に対して内科医がすべきこと,できることを教えてくれる書。
| 著 | 中河原 通夫 |
|---|---|
| 発行 | 2004年04月判型:A5頁:180 |
| ISBN | 978-4-260-10652-8 |
| 定価 | 3,080円 (本体2,800円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 書評
書評
開く
精神科を専門としない医師の疑問に答える
書評者: 森脇 龍太郎 (埼玉医大講師・高度救命救急センター)
わが国の自殺既遂者は1998年より年間3万人を超えている。そして自殺未遂者は少なくともその10倍以上存在するといわれている。このような自殺企図患者の治療の中心的役割を果たしているのが救命救急センターであるが,自殺手段としては向精神薬を中心とした薬剤の大量摂取を選択することが多いようである。したがって,救命救急センターに長く勤務していると,向精神薬の薬理作用にも自ずから詳しくなるものである。
なまじ詳しくなると,内科外来でうつ病らしき患者にたまに出会うと,向精神薬を処方したくてうずうずしてくる。かねてより坑不安薬や睡眠薬はときどき処方していたが,SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)やSNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)の登場以来,現在は坑うつ薬も含めて頻繁に処方するようになった。しかし,向精神薬の選択に当たって十分な根拠と自信をもって処方しているわけではない。効果がなかったときの第2選択薬は?効果があった場合はいつまで続ける?などなど,さまざまな疑問が湧いてくる。おそらく一般内科医も同じような疑問を持ちながら向精神薬を処方しているのではないかと思われる。
◆研修医も含めたすべての医療者に推薦する
このような折,まさにタイムリーな本が上梓されたものである。第1章「内科医がよく出会う精神疾患とその治療法」では,日常内科外来で遭遇する代表的な精神疾患について言及しているが,各々の疾患の特徴,治療の手順(専門医に任せるかどうかについても言及),処方例,第2選択薬,副作用とその対策,病気の経過,薬剤の減量法などが簡潔にかつ明瞭に述べられており,上述した疑問が氷解した思いである。
第2章「身体疾患に伴って現れる精神症状とその治療法」,および第3章「薬剤によって起こる精神症状とその治療法」では,精神症状を起こしやすい内科疾患および薬剤を取り上げて,各々の内科疾患や薬剤服用中に起こりやすい精神症状の特徴からはじまって,第1章と同様の切り口で治療の手順(専門医に任せるかどうかについても言及),処方例,第2選択薬,副作用とその対策,病気の経過,薬剤の減量法などが述べられている。
さらに第4章「向精神薬の効果と副作用」では漢方薬も含めた代表的な向精神薬について簡便にポイントを押さえて述べられており,精神科を専門としない一般医にとってはたいへん便利であろう。また処方例が具体的に商品名でも提示されているのも実用的で,小生は外来診療に当たってポケットに入れて,必要に応じて参照している。
「内科医が知っておきたい」という前置きがあるが,一般内科医のみならずすべての医療従事者にも推薦したい良書である。本年度から研修制度が変更になり,精神科研修も必須となったようであるが,その研修前に必読の書として研修医の方々にも強く推薦したい。
精神科を専門としない医師が患者の悩みを救うために
書評者: 高橋 祥友 (防衛医大教授・行動科学研究部門)
◆うつ状態の患者の6割が内科を最初に受診
数年前にローマで小さな学会が開催されたが,そのテーマは「プライマリ・ケアにおける精神科治療」であった。欧米ではプライマリ・ケア医が診療している患者の約20%は精神科関連の問題を抱えていると知り,私は驚いた。その背景には,欧米であっても,精神科受診に対して一般の人には抵抗があることや,最近になってSSRI(選択的セロトニン再取込阻害薬)などといった比較的副作用が少なくて使いやすい抗うつ薬が開発されてきたことが関係している。
わが国でも,たとえば,うつ状態になった患者が最初に受診する先は約6割が内科であって,精神科に受診する患者は1割に満たないという報告さえある。うつ病はけっして稀な病気ではないのだが,最悪の場合は自殺まで起こり得る。そこで,最近,日本医師会も「自殺予防マニュアル―一般医療機関におけるうつ状態・うつ病の早期発見とその対応」という冊子を編集したほどである。
このような現状を考えると,『内科医が知っておきたい向精神薬の選び方・使い方』はまさに医療関係者に必須の好著である。本書は次の4章からなる。第1章「内科医がよく出会う精神疾患とその治療法」,第2章「身体疾患に伴って現れる精神症状とその治療法」,第3章「薬剤によって起こる精神症状とその治療法」,第4章「向精神薬の効果と副作用」。
わが国では精神疾患や精神科受診に対する抵抗感が強いために,気楽に精神科に受診できない雰囲気がある。そこで,日頃から身体的な健康管理をしてもらっている医師から,精神疾患の治療をも同時に受けることができるならば,患者はより一層安心できるはずである。
◆専門外の読者にもわかりやすく
本書の第1章で取り上げられているさまざまな精神疾患の中で,少なくとも,うつ病,パニック障害,不眠症に関する正しい知識を身に付けるだけでも,精神科を専門としない医師が多くの患者の悩みを救うことができるだろう。
著者は臨床精神薬理学の第一人者であるが,本書は精神科を専門としない人にとっても,ポイントを押さえて,実にわかりやすく書かれてある。精神科医の書いた文章は長々しく難解な内容が多いと一般に思われているが,著者の文章は簡潔で明解である。なお,「内科医が知っておきたい」と題にあるが,むしろ広く医療従事者一般に推薦したい本である。また,研修医制度が本年度から改正されたが,研修医の時代に本書を読んでおくことは必須である。ぜひ,一読をお奨めする。
書評者: 森脇 龍太郎 (埼玉医大講師・高度救命救急センター)
わが国の自殺既遂者は1998年より年間3万人を超えている。そして自殺未遂者は少なくともその10倍以上存在するといわれている。このような自殺企図患者の治療の中心的役割を果たしているのが救命救急センターであるが,自殺手段としては向精神薬を中心とした薬剤の大量摂取を選択することが多いようである。したがって,救命救急センターに長く勤務していると,向精神薬の薬理作用にも自ずから詳しくなるものである。
なまじ詳しくなると,内科外来でうつ病らしき患者にたまに出会うと,向精神薬を処方したくてうずうずしてくる。かねてより坑不安薬や睡眠薬はときどき処方していたが,SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)やSNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)の登場以来,現在は坑うつ薬も含めて頻繁に処方するようになった。しかし,向精神薬の選択に当たって十分な根拠と自信をもって処方しているわけではない。効果がなかったときの第2選択薬は?効果があった場合はいつまで続ける?などなど,さまざまな疑問が湧いてくる。おそらく一般内科医も同じような疑問を持ちながら向精神薬を処方しているのではないかと思われる。
◆研修医も含めたすべての医療者に推薦する
このような折,まさにタイムリーな本が上梓されたものである。第1章「内科医がよく出会う精神疾患とその治療法」では,日常内科外来で遭遇する代表的な精神疾患について言及しているが,各々の疾患の特徴,治療の手順(専門医に任せるかどうかについても言及),処方例,第2選択薬,副作用とその対策,病気の経過,薬剤の減量法などが簡潔にかつ明瞭に述べられており,上述した疑問が氷解した思いである。
第2章「身体疾患に伴って現れる精神症状とその治療法」,および第3章「薬剤によって起こる精神症状とその治療法」では,精神症状を起こしやすい内科疾患および薬剤を取り上げて,各々の内科疾患や薬剤服用中に起こりやすい精神症状の特徴からはじまって,第1章と同様の切り口で治療の手順(専門医に任せるかどうかについても言及),処方例,第2選択薬,副作用とその対策,病気の経過,薬剤の減量法などが述べられている。
さらに第4章「向精神薬の効果と副作用」では漢方薬も含めた代表的な向精神薬について簡便にポイントを押さえて述べられており,精神科を専門としない一般医にとってはたいへん便利であろう。また処方例が具体的に商品名でも提示されているのも実用的で,小生は外来診療に当たってポケットに入れて,必要に応じて参照している。
「内科医が知っておきたい」という前置きがあるが,一般内科医のみならずすべての医療従事者にも推薦したい良書である。本年度から研修制度が変更になり,精神科研修も必須となったようであるが,その研修前に必読の書として研修医の方々にも強く推薦したい。
精神科を専門としない医師が患者の悩みを救うために
書評者: 高橋 祥友 (防衛医大教授・行動科学研究部門)
◆うつ状態の患者の6割が内科を最初に受診
数年前にローマで小さな学会が開催されたが,そのテーマは「プライマリ・ケアにおける精神科治療」であった。欧米ではプライマリ・ケア医が診療している患者の約20%は精神科関連の問題を抱えていると知り,私は驚いた。その背景には,欧米であっても,精神科受診に対して一般の人には抵抗があることや,最近になってSSRI(選択的セロトニン再取込阻害薬)などといった比較的副作用が少なくて使いやすい抗うつ薬が開発されてきたことが関係している。
わが国でも,たとえば,うつ状態になった患者が最初に受診する先は約6割が内科であって,精神科に受診する患者は1割に満たないという報告さえある。うつ病はけっして稀な病気ではないのだが,最悪の場合は自殺まで起こり得る。そこで,最近,日本医師会も「自殺予防マニュアル―一般医療機関におけるうつ状態・うつ病の早期発見とその対応」という冊子を編集したほどである。
このような現状を考えると,『内科医が知っておきたい向精神薬の選び方・使い方』はまさに医療関係者に必須の好著である。本書は次の4章からなる。第1章「内科医がよく出会う精神疾患とその治療法」,第2章「身体疾患に伴って現れる精神症状とその治療法」,第3章「薬剤によって起こる精神症状とその治療法」,第4章「向精神薬の効果と副作用」。
わが国では精神疾患や精神科受診に対する抵抗感が強いために,気楽に精神科に受診できない雰囲気がある。そこで,日頃から身体的な健康管理をしてもらっている医師から,精神疾患の治療をも同時に受けることができるならば,患者はより一層安心できるはずである。
◆専門外の読者にもわかりやすく
本書の第1章で取り上げられているさまざまな精神疾患の中で,少なくとも,うつ病,パニック障害,不眠症に関する正しい知識を身に付けるだけでも,精神科を専門としない医師が多くの患者の悩みを救うことができるだろう。
著者は臨床精神薬理学の第一人者であるが,本書は精神科を専門としない人にとっても,ポイントを押さえて,実にわかりやすく書かれてある。精神科医の書いた文章は長々しく難解な内容が多いと一般に思われているが,著者の文章は簡潔で明解である。なお,「内科医が知っておきたい」と題にあるが,むしろ広く医療従事者一般に推薦したい本である。また,研修医制度が本年度から改正されたが,研修医の時代に本書を読んでおくことは必須である。ぜひ,一読をお奨めする。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。