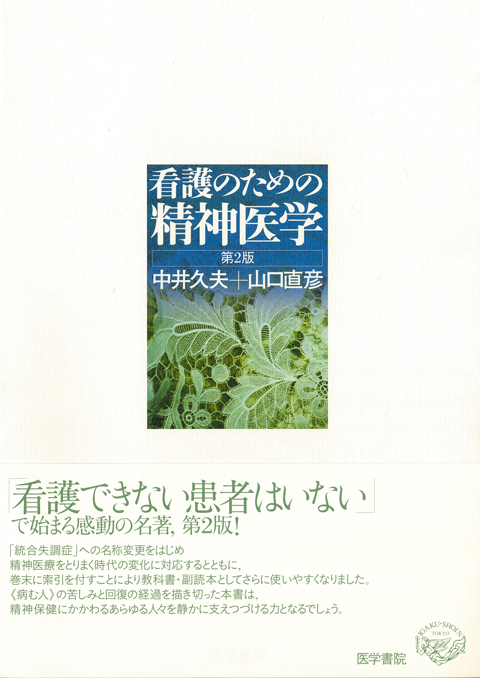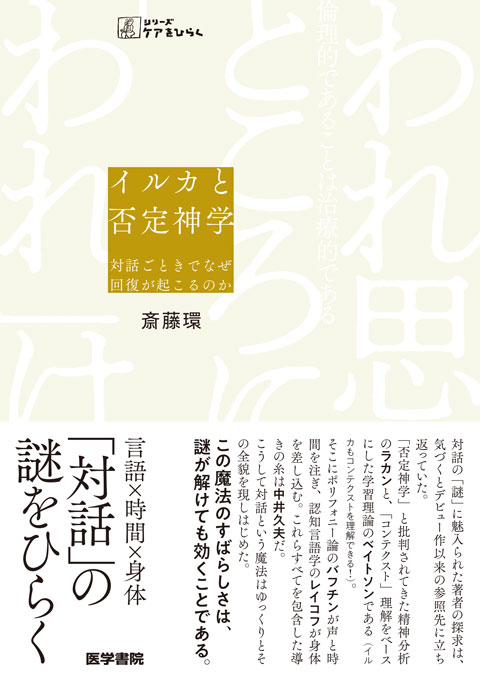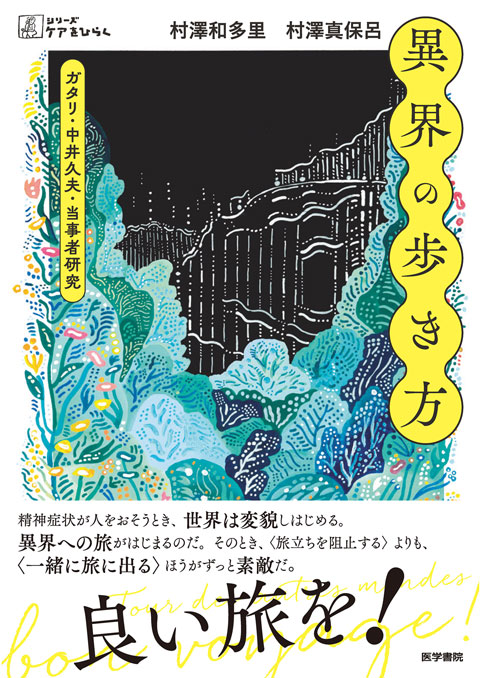こんなとき私はどうしてきたか
「希望を失わない」とは、どういうことか。
もっと見る
初めて患者さんと出会ったとき、暴力をふるわれそうになったとき、“回復に耐える力”がなさそうなとき、私はどんな言葉をかけ、どう振る舞ってきたか――。当代きっての臨床家であり達意の文章家として知られる著者渾身の1冊。ここまで具体的で美しいアドバイスが、かつてあっただろうか!
| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |
|---|---|
| 著 | 中井 久夫 |
| 発行 | 2007年05月判型:A5頁:240 |
| ISBN | 978-4-260-00457-2 |
| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- TOPICS
- 目次
- 書評
TOPICS
開く
●『シリーズ ケアをひらく』が第73回毎日出版文化賞(企画部門)受賞!
第73回毎日出版文化賞(主催:毎日新聞社)が2019年11月3日に発表となり、『シリーズ ケアをひらく』が「企画部門」に選出されました。同賞は1947年に創設され、毎年優れた著作物や出版活動を顕彰するもので、「文学・芸術部門」「人文・社会部門」「自然科学部門」「企画部門」の4部門ごとに選出されます。同賞の詳細情報はこちら(毎日新聞社ウェブサイトへ)。
目次
開く
1 患者さんと出会ったとき
2 幻聴を四期に分けて考える
3 幻聴や妄想を実りあるものにするために
4 「匙を投げない」ことをどう伝えるか
2 治療的「暴力」抑制論
1 患者さんを安全に抑える方法
2 “手負い”にしてはならない
3 患者さんにはどう見え、どう聞こえているか
4 ふっと力が抜けるとき
3 病棟運営についていくつかのヒント
1 どんな環境が人を苛立たせるのか
2 人的環境としての「部屋割り」
3 病棟スタッフの和をどう支えるか
4 改革時の病棟マネジメント--私の経験から
4 「病気の山」を下りる
1 保護室の内と外
2 山を下りるということ
3 回復初期はからだに注目
4 下山のエネルギーを補給する
5 回復とは、治療とは……
1 回復期は疲れる
2 疲れている患者さんに何を言うか
3 家族の方に知ってほしいこと
4 「依存」という切り口から
5 「回復に耐える」ということ
付章1 インタビュー・多少の補記を兼ねて
付章2 精神保健いろは歌留多
あとがきにかえて
索引
書評
開く
●新聞で紹介されました
《「知恵」を語る言葉のおだやかさ》――冨山 太佳夫(青山学院大学文学部英米文学科教授)
(毎日新聞 2007年7月1日 東京朝刊「今週の本棚」より)
【特別寄稿】中井久夫『こんなとき私はどうしてきたか』を読む――練達精神科医の典雅な下山道談義(『週刊医学界新聞』より)
書評者:坂部 恵(東京大学名誉教授/哲学)
書評を見る閉じる
「ふつうの医療者が理解し実行もできるような精神医学を私はずっと目指してきた。いくぶんなりとも達成できているだろうか」
著者中井氏は,本書の「あとがきにかえて――この本が生まれるまで」の末尾でこのように述べられ,おなじ文言は裏表紙の帯にも転載されている。
本書は,中井氏が神戸大学を定年で退かれた後,兵庫の有馬病院「医師,看護師,合同研修会」,「医局,看護部,臨床心理室のみなさんが合同で,ごく初歩的なことを私が語るのを聞く」会の記録を雑誌『精神看護』(医学書院)に連載し,さらに手を入れて形を整えられたものである。
「ふつうの医療者が理解し実行もできるような精神医学」は,ふつうの医師,ふつうの医療者では書けない。あるいは,学会誌向けの研究論文や著書などにすぐれた業績をもつ医療者であっても,そのことだけではこうした一般向けの講話をよくする素地には足りない。
専門の精神科医・精神病理学者としての精緻な観察・学識と長い臨床経験から学び取ったものを平易なことばとして後進に伝えうる医療者だけが,しかもおそらくみずからのキャリアの下山道にさしかかったところで,はじめてこうした仕事をよくしうるのである。
著者は,本書のあとがきで,ご自身の回復(寛解)過程論が,その論の生まれた場である青木病院で「私が去って久しい後まで看護部に語りつがれ」て,患者さんの病状を見ながらの対応に活用されていたこと,また,大学の系列からすれば著者のとは別の有馬病院で,研修医クラスの人によく著書のサインなど求めれるので,不思議に思って聞くと,当時その大学で著者の統合失調症の回復(寛解)過程論が参考文献として指示されていたのを知ってうれしくおもった,と述べておられる。
実際,まったく素人の読者の目から見ても,患者の心身の変動を日を追って細かく観察し,それをきわめて精細なグラフにあらわした中井氏の統合失調症回復(寛解)過程論は,日本の精神医学に一時期を画したといわれる東京大学出版会の分裂病(統合失調症)の精神病理シリーズのなかにあっても,むしろ成因論的な研究が目立つなかで,ひときわ異彩を放っていたように記憶するし,何人かの専門領域の方からもこの論文の独自・秀逸なるゆえんについて聞き及んでもいる(篤実な看護師さんの看護日誌が大きな助けになっていたことは,本書ではじめて知った)。
本書でも,やはり,回復過程について細心の注意をはらうべきことが説かれている。
「治りかけというのはとても大切な時期です。しかしわれわれは,患者の症状が収まったら急に気を抜きがちではないでしょうか。患者が回復期に入るか入らないうちに,医療者にはだいたい次の患者が待っているんですね。だから保護室から出てみんなのなかで生活をしはじめた時の患者さんは――このことは忘れられがちなのですが――非常にさびしい」
回復(寛解)過程論にあったのとおなじ細かい目くばりと心づかいがここにも見られる,とわたくしはおもう。こういう時期にかえって自殺の危険も高いのだと著者は付言される。
あるいはつぎのような指摘。
「異常現象そのものはくわしく調べられているけれど,その現象に対する「耐え方」というか「構え方」「受け止め方」のほうは,まだ未知の大陸のような気がしますね。こちらのほうが重要かもしれませんね。未知であるとは,そういうものがないということではないと思うのです」
中井氏がつづけて述べられているとおり,「耐え方」,「受け止め方」は,当然ひと通りではないだろうし,患者さんひとりひとりによって,おなじ患者さんでも個々の場合や時期によって有効な対処法はおのずからちがってくるだろう。中井氏は,一般理論を組み立てるよりも,一貫して個々の症例を徹底的に観察することから部分的あるいは全体的に応用可能なマニュアルを探り出す道を探ってこられたのだとおもう。西洋の人文主義者・法賢慮の実務家たちがiudicium(判断力)と呼んで重んじた個と普遍を創造的に媒介する能力。今日の人文学でも,この部分はまだ大方未知の大陸である。
「病的な面に注目するのは,熱心な,あるいは秀才ドクターの陥りやすい罠です。私も何度かそういうところに陥ったし,まわりにもそういう人を見てきました。精神病理学者に多くのものを与えた患者の予後はよくないのです」
つづく箇所には,
「たいていの患者は看護師が健康な面に光を当てているからこそ治るのかもしれません」
と,医師には耳の痛いことばがある。
中井氏が業余に現代ギリシャ詩の翻訳をよくせられ,また達意のエッセイの書き手であられることはよく知られていよう。治療者集団への講話に特化した今回の仕事でも,自在な語り口のなかに,年輪とともに,そうした自分の専門領域を外から見ることのできる「余裕」が存分に生かされている,とおもう。iudiciumと縁の深いinventio(発見法)を何より重んじたバロック人フランシス・ベーコンもまた,英文学史上屈指の随筆の書き手であった。
わたくし自身,1990年代にうつ病で三度の比較的長期の入院生活をし,患者(たち)の立場から医療の現場を経験する機会をもった。入院中,同棟の仲間も含めて,何とはなしもの哀しい感じは変わらないが,それでも患者のミーティングがひらかれたり,若い患者さんたちにソシアルワーカーが積極的な援助の手をさしのべたり,医療やケアがすこしずつ変わりつつあるらしいというたしかな実感があった。患者の回復・下山過程に細やかな目をそそぐ中井氏の心が,後進の医療者たちに受け継がれてほしい。
(『週刊医学界新聞』第2744号に【特別寄稿】として掲載)
書評(雑誌『精神看護』より)
書評者:馬渕 寿史(神奈川県立精神医療センター芹香病院・看護師)
書評を見る閉じる
どうしてこんなセリフが言えるんだ!?
中井久夫先生の新刊『こんなとき私はどうしてきたか』は、毎章、「みなさん、こんにちは」と、やさしげな口調ではじまる講演録です。それは看護人世代の先輩が夜勤の空いた時間に語ってくれた体験談に似ていました。
次のような文章があります。『まずは、精神科の用語を使わないことが大事です。「幻聴」じゃなくて「きみの幻の声」と言います。「空耳というのもあるよね」とか。「それは絶対違います」と患者さんが言ったら、「どこがちがいますかねぇ」続いたりする』。
精神科に入職したての頃だったら、「はぁ?? 教科書に、幻聴には否定も肯定もしないって書いてあるのに……これはわけがわからん」とすぐにさじを投げたことでしょう。50歩100歩かもしれませんが、今では「この人はどこからこんなことを思いついたんだろう」とページをめくるたびに好奇心が湧いてくる程度になりました。
疾患しか見ていなかった私
私は看護学校を卒業してからの4年間、救急救命センターで働き、そのあと精神科単科の病院へと移りました。
救急救命センターで仕事をしはじめてすぐに実感したのは自分の知識の少なさでした。知識がなければ状態の判断ができないし、何をやっていいのかもわかりません。私は、ただ指示されたことを行なっていました。気がつくと対象は患者から疾患になっており、なるべく多くの症例を短時間でこなしてやろう、としか考えないようになりました。そのときは正直いって、患者1人1人のニーズなどはどうでもよく、人として看ていなかったと思います。
しかしそんな私のやり方が通じなかった人たちがいました。それは「精神科の患者」でした。夜間、診察室で叫び暴れる人、支離滅裂なことを言い続ける人。彼らには、私の「診察の回転のために1つでも多くの症例を短時間でやっつける」が通じなかったのです。
私の底つき体験
それから、配属先として精神科の門を叩くことになった私は、底つきといえるような体験をしました。それは病院へ案内されたときからはじまりました。
病院は政令指定都市にあるのに交通の便がかなり悪く、人里離れたへんぴな場所にあり、広い敷地のなかに病棟の建物が散らばって建っていました。病棟は塗装をかけられずにむき出しのままのコンクリートの薄暗い床になっており、入るときには精神科のお決まりアイテム、「鍵」が必要でした。ヤニが染みつき壁は黄ばんでいました。
病棟のなかを案内されながら歩くと、こちらをしげしげと観察するように見ている目があります。それは患者たちでした。はしゃぎながら近づく患者、反応がない患者もいます。夕方の陽射しが入っているのに病院内は暗く、トイレはオンボロで臭く汚かった。個室は当然のように鍵がかかっており、大部屋には畳とベッドがあるものの、たこ部屋といった感じ……。
本当にここで働いていけるのだろうか、どんなことをするのだろうか……。私は病院に入ったほうがおかしくなりそうだと感じました。早くここから出たいと、外来から無理矢理連れてこられた入院患者のように思っていました。
環境に馴染むことのできなかった私は、患者のとらえ方はもとより、どのように身を処し動いてよいのかわからず、指示されたことすら行なえず、いったいどうすればよいのかと激しく悩みはじめました。
フレームが作れない困難は,〈私たち〉の想像を絶している。その意味では本書を,共感的に読むことは難しい。しかし,「もし〈私たち〉がフレーム問題に直面したらどうなるか」という思考実験として読むなら,本書ほど刺激的な本も少ないだろう。
自明とされることを徹底的に懐疑するところから哲学がはじまるとすれば,本書が投げかけるのはすぐれて哲学的な問いでもある。私はかつて,ドナ・ウィリアムズの著書の感想として「哲学的障害」という言葉を記したことがある。〈彼ら〉の言葉には,〈私たち〉の知覚や認識,あるいは感情や行動が,どのようにして成立しているかを解き明かすヒントが数多く含まれているからだ。
本書をさらに読み進めれば,この障害を持つ人たちを「自閉」的と形容することが果たして適切か,という疑問すら湧き起こってくる。それというのも,綾屋さんの記述を読む限り,〈彼ら〉はあまりにも「他者」に対して開かれているがために自閉的に見えているだけなのではないか,としか思えないからだ。
人を看るってこういうこと?
そこで当時、本屋にある精神科に関する書物を食い漁るように読んでみたのですが、じゃあ明日からどう行動すればよいなどということは書いてあるはずもなく、中井久夫先生のように病棟を魚が水を泳ぐようにできるわけもなく、ただ看護室のなかを徘徊していただけでした。
そんなとき、看護人世代の先輩らによる言葉にずいぶん背中を押され踏ん切りがつきました。なんでも本に頼ろうとする私に、「○○さんの散歩って、本に書いてあんのか?」という声が飛んできます。しかたなく、患者に付き添っているのか付き添われているのかわからないまま散歩へ行くところから、私は精神科の環境に慣れていきました。
そのうち、ハッピーエンドが存在しない現実の問題のなかで、それまで想像すらできなかった他人の暮らしのさまざまな問題に直面し、その深さに自分も悩みはじめた頃から、やっと周囲を見渡せるようになってきたように思います。そしてそこには間違いなく疾患ではなく人を看ている自分がいました。もちろん解決法なんぞ頭をフル活用しても出てこないものは出てきません。
しかしそんなときに、看護人世代の先輩は教科書に1つも書かかれてない解決法により解決させてしまうのでした。くやしかったので先輩の看護人も観察してみました。結果、先輩の看護人らは、患者の具合のよし悪しを経験で判断していました。経験は蓄積された体験データですから、判断としては間違っていません。間違っていないというレベルではなく、ほぼ正確に患者の状態をとらえることができていました。残念なのは、そのデータを言語化ではなく本人だけの独特なアンテナ感覚のようなものでつかんでいるため、先輩らの喩え話を理解できないと全くわからない話になってしまうことです。夜勤のとき、「あの患者さん昔はこうだったんだよ」と、以前の症状が強かったときの話やカルテに記入されてないような裏話を聞いて、彼らの神業が出るところの根拠をかいま見たような気がしていました。
いつか自分もこんなセリフが言えるのでしょうか
この本を読んでいるうちに、そのときの感覚が思い出されてきました。
しかし今、精神科で同じように話が聞けるかといったら、そういう場がなくなっていると感じます。本のなかで中井久夫先生が飲み心地を知ろうとして医局にサンプルとして散乱していた抗精神薬を試したり、3ベッドの真ん中を空けておいたといった話がありましたが、今の精神科ではそうした試みは許されなくなってきているんじゃないでしょうか。スピーディ、効率化、根拠、責任……そうしたものをむやみに追求する時代になってきたように思うからです。一昔前にあった、よい意味でのあいまいさや、保留にしたり、余裕をもつなんてことが、無駄として省かれてきているからかなぁと私は思います。
おそらくここには,発達障害児の療育上の重要なヒントが示されている。複数のコミュニケーション・スタイルで,一つのメッセージを伝えようとすること。ここにはひょっとすると,「フレーム問題」を突破する契機すらも含まれているのではないか。
中井先生がこの本から僕へ投げかけてくるボールはキャッチできるようでもできなくて、もしできたとしてもなかなか投げ返せないような重さですが、いつかはぼくも投げてみたいボールです。
どうか神様、私も中井久夫先生のように、または先輩看護人のように、「なんでこんなセリフが言えるんですか!」と突っ込みを入れられるような言葉を一度でも退職するまでに言えますように……。
日々の看護管理への気づきに富んだ生きた参考書 (雑誌『看護管理』より)
書評者:宮井 千恵(高知大学医学部附属病院看護部長)
書評を見る閉じる
統合失調症患者が回復するまでの長い道のりにどう関わるか
“こんなとき私はどうしてきたか”というタイトルを見たとき,その書名から,本を開いて見てみたいという興味が湧いてきました。一方で,精神科の患者さんについて書かれた本であることから,苦手意識を感じたものの,読むにつれて引き込まれ,内容のリアルさから一気に読み終えてしまいました。
主に統合失調症の患者さんが病気になってから回復していくまでの長い道のりで,患者さんに表面的に現れる症状や内面の心の動きに対して,医師や看護師がどのように受け止め,関わっていったらいいのかということが,著者の経験と専門的な知識を駆使して読み手の心に届くよう書かれています。
本書は大きく分けて4つにくくられています。まず1つ目は,患者さんと出会ったときの関わり方として,初めて精神科を受診したときこそが大事であること,“希望”を処方するということ,そして幻聴について,症状と対処の仕方があたかも自分がその場に居合わせているかのようにリアルに書かれています。2つ目は,患者さんの暴力にどう対応していくか,また暴力を起こさない対応の仕方などについて。3つ目は,病棟運営の方法について。部屋割りの仕方や同室患者さん同士の影響力,病棟スタッフがどうあるべきかなどについて,深みのあるヒントが語られています。4つ目は,病気の回復期について,患者さん自身がどのように自分を感じ,回復のいろいろな段階をどのように乗り越えていっているのか,また家族の理解も不可欠であるといったことが,手に取るようにわかります。
現場の問題人の解決の糸口を見つけるために
筆者は精神科看護の経験はありませんが,看護管理者として,看護の基本である患者さんをよく観察し,よく聴くということが一番大事であると感じました。そして,患者さんを観察するときの姿勢として患者さんに寄り添うということが大切であり,そうするためには,患者さんの思っていること,生育歴,生活環境などを理解しておく必要があります。そのうえでなければ,よく観察することもよく聴くこともできませんし,信頼関係を築いていくことも難しくなります。
さらにそうしたことの裏付けとなる専門的知識が不可欠だと思います。これは精神科に限らずすべての領域の患者さんに対して言えることであり,知識・技術・態度を磨いていくことです。病棟運営のあり方についても病室の構造的環境,人的環境を配慮することの大切さ,医師と看護師のチームワークがいかに重要かなどについて気づかされることが多くあり,参考になりました。
本書は,看護師はもちろん研修医にも役立つと思います。精神科病棟の看護師には患者さんとの関わりのなかで,現場で直面している多くの問題について解決の糸口を見つけるための生きた参考書になります。精神科だけでなく,一般病棟の看護師にも精神疾患を理解するためにぜひ読んでほしいと思います。また,平易なことばで書かれていますので,患者さんやご家族の方でも理解が深まると思います。特に現場の看護師の皆さんには,急がずに丁寧に読み込んでほしい一冊です。
この本で「希望」を処方されるのは患者ばかりではない
書評者:津田 篤太郎(東京都立大塚病院リウマチ膠原病科)
書評を見る閉じる
神戸大学で行われた有名な「最終講義」から,はや10年が経った。私はまだ学生で,精神科の授業も始まってない時分だったが,大学生協の片隅で『最終講義』(みすず書房)を立ち読みするなり,著者の大ファンになった。格調高い文体,絶妙な比喩表現もさることながら,臨床家としての姿勢に学ぶところが大きかった。
“内なる自然”への農学書
著者は別の著作のなかで,自分は江戸時代の農学書をモデルとして書いている,というようなことを述べている。作物を植える時期・肥料の種類といった技術上のアドバイスから,農村経営に必要な財務管理,人材配置の仕方まで幅広い知識を盛り込んだ実用書が江戸時代の農学書とすれば,本書『こんなとき私はどうしてきたか』も疾患の治療論から病棟運営までを射程におく,視野の広いマネージメントの書である。
さらにもう一点,農学書との符合を見出すとすれば,“大自然”を相手にしている,ということであろうか。
患者の予期せぬ急変に茫然と立ち尽くす医療者の姿は,河川の氾濫や日照りといった自然の猛威になす術もない農民に,どこか似ているように思える。現代医学が長足の進歩を遂げたとはいえ,精神病の“内なる自然”に関してはまだまだブラックボックスの部分が多い。
ブラックボックスにどう鍬を入れるか
しかし医療スタッフは,ブラックボックスの部分があるから何もできない,というのは許されない。何かをなすよう常に迫られる。著者はその該博な治療経験から,どのように起こったことを捉え,どのように対処していくのかを明らかにしていく。
私は免疫疾患を専門に選んだが,精神病と同じくブラックボックスが大きい領域である。いずれもネットワークに支えられたシステムであり,さまざまな外乱要因を吸収しながらホメオスタシスを保っている。「免疫力を高める」「脳力開発」などと,システムのパフォーマンスにのみ注目するむきが多いが,著者は終章の「精神保健いろは歌留多」で「無理を通せばチェルノブイリ」と警告する。
つまり,適切に制御されているからこそシステムの安定が保たれる,というのである。「安全率」という工学上の概念を援用した卓抜な発想は,長年ブラックボックスの現象を丹念に追ってきた著者ならではのものだ。
希望としての「ダメもと医学」
「ダメでもともと医学」という表現が出てくる。挨拶や握手をする,相槌のレパートリーを増やすといった,「お金もかからず無害なこと」なら何でもやってみよう,という態度である。その根底には,“精神病には治癒があるかないか……あるほうに賭けよう。賭けが外れたとして,失うものは何もない”とする,“精神医学版パスカルの賭け”とも言えるべき信念がある。これは,治療の士気を維持していくためにたいへん重要なのではないかと思う。
長期にわたる治療では,希望を繋ぎとめることがしばしば難しい課題となる。この本にはそうした局面を打開するためのアドバイスが詰まっていて,慢性疾患を診る側のはしくれである私も,勇気付けられることが多かった。
ただし,「ダメもと医学」は「無害」が大前提である。著者の繊細な観察眼は,思わぬことが患者にダメージを与えている事実をも描き出している。たとえば,医者は患者の病的な面ばかりに目がいきがちになるが,それでは患者の人生は病気中心になってしまう,といった指摘には,何度もハッとさせられる。
一見些細だがデリケートな治療上の工夫の積み重ねの末,「年をとってくると,病気も病人も分からないけど,なぜか患者さんはよくなる」と言う筆者は,“パスカルの賭け”に勝ったと言えよう。
内科医の私はまだ5回しか読んでいない
書評者:長嶺 敬彦(清和会吉南病院内科部長)
書評を見る閉じる
実用書であると同時に,読者を鼓舞する「哲学書」である
《ふつうの医療者が理解し実行もできるような精神医学を私はずっと目指してきた。いくぶんなりとも達成できているだろうか》と中井先生自らがあとがきで書いておられるように,本書のめざすところは誰でも実践できる精神医学である。精神科医でない私が読むと,明日から精神科医になれそうな気分になる。それくらい懇切ていねいで実用的な優れた本である。
こう書くと,本書がまるで精神科の“How to 本”つまり実用書と誤解されそうである。実用書は1回読めば新しい発見はない。しかし本書は2度,3度と読み返すたびに新鮮な感動がある。繰り返し読むことで,読者自らが考え,成長できるのである。例えば次のような記載がある。
《身体症状に対する精神療法は,まずていねいな身体診察です。診察せずに内科の薬を出したり,抗精神病薬を増量しては実りがないです。せっかくのチャンスなのにもったいない》(140頁)
1回目にここを読んだとき私は,「精神症状から身体的な問題を訴える患者さんには,身体診察を通して安心させることが大切だ」と,表面的な精神科での実践的な対応方法を学んだ。しかし2回目には《せっかくのチャンスなのにもったいない》というくだりが妙に私の前頭前野を刺激し,「身体を診察する行為は,ときとして精神療法になり得る。内科の薬も抗精神病薬も,身体診察という患者さんとの交流が基盤になければその効果を十分に発揮できない。身体症状と精神症状は奥深いところで繋がっている」と1回目より解釈が深くなったのである。
病的体験だけに目を向けない
通常,医学は病的な側面を取り除くことにすべてのエネルギーを使う。病巣を取り除くことに挑戦しつづけている。精神医学も幻覚・妄想を撲滅することにエネルギーを費やしている。しかしすべての妄想を消し去ろうとすると,抗精神病薬が必要以上に増量になり「身体副作用」が出現する。身体副作用を最小限にするにはどうすればよいのか,常々悩んでいたが,この本で一つの答えが見つかった。
《驚くべき病的体験,たとえば世界が粉々に分解するというような,まだ誰も報告していない現象を話してくれる患者がいたとします。その彼が友達と映画を観に行ったり,ベースボールをしたり,喫茶店に行ったりしたことを,私は驚くべき病的体験の話よりも膝を乗り出して興味を持って聴けるか。……》
つまり病的な側面だけを診るのではなく,日常を見ることである。妄想も健康な面も,患者さんのかけがえのないその人らしさとしてあるがままに傾聴すれば,自ずと抗精神病薬は至適投与量となり,身体副作用は減少する。
精神科医が独占するのはもったいない
この本を読めば,精神科医療での問題の解決方法が見えてくる。事例が豊富だからである。しかし繰り返すが,実用書とは異なり,何度読んでも新鮮に感じる。実用的な提言の奥に,深い思索(哲学)が隠れているからである。
その哲学は,科を問わず医学全般に応用が可能である。つまり人間理解に欠かせない視点を教示している。読めば読むほどその奥深さに気づく。私はまだ5回しか読んでいない。でも読むたびに新しい発見がある。本書を精神科医が独占するのはもったいない。すべての医療従事者が読むべき本の一つである。
*
先日大阪で,「抗精神病薬による身体副作用」に関するセミナーを行った。セミナーや学会などの講演会では,会場で医学書の販売がある。たくさんの医学書が所狭しと並べられていた。そのなかに,当然この本も平積みされていた。
私は田舎に住んでいるので,なかなか医学書を置いてある書店に行くことができない。そこで帰りに親しい人へのお土産にこの本を買ってかえろうと思った。ところがいざ自分の講演が終わり,書籍コーナーに立ち寄ったら,どうしてもこの本が見つからない。そこで係の人に「中井先生の本がありましたよね」と尋ねたら,80冊用意しておいたが講演の休憩時間に完売したとのことである。見つけたときに買っておけばと後悔した次第である。
「お買い求めはお早めに!」とお勧めする名著である。