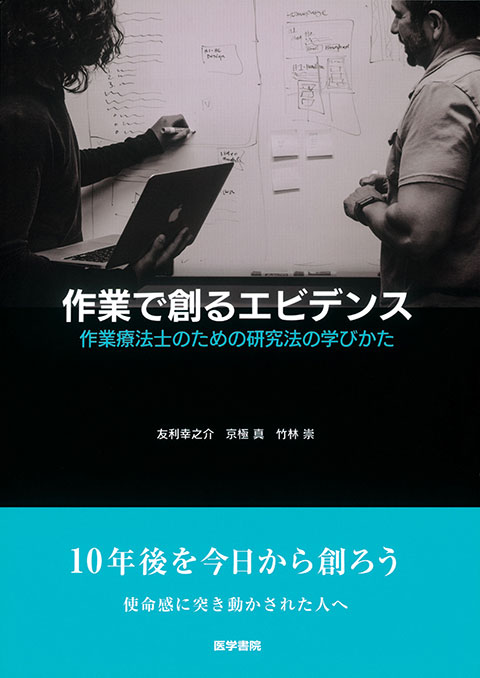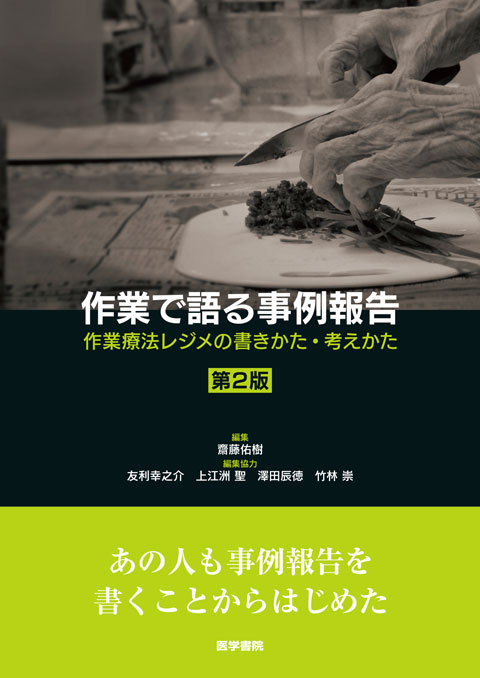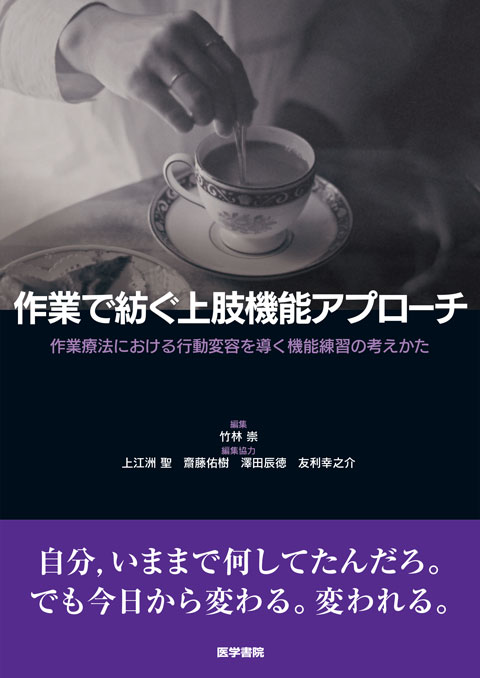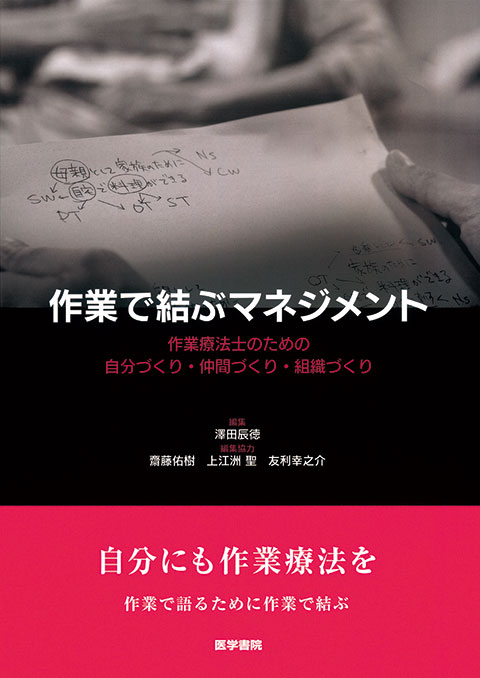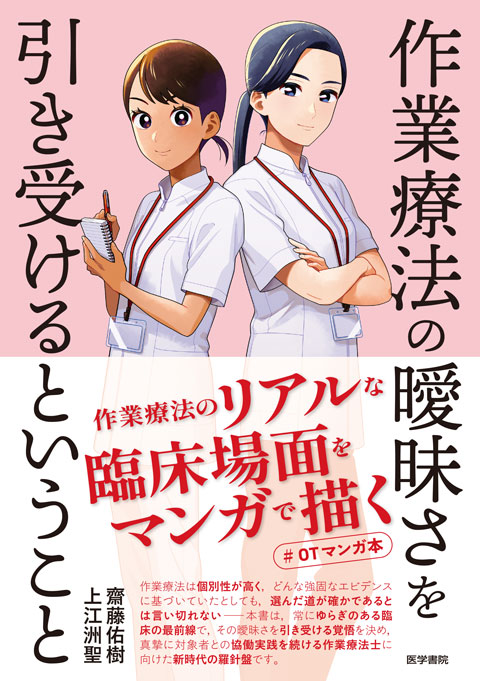作業で創るエビデンス
作業療法士のための研究法の学びかた
作業療法のエビデンスを共創するために、まず研究を始めてみよう!
もっと見る
根拠に基づいた作業療法実践(EBOT)を広めるためには、現場で介入する臨床家や、養成校学生に教授する教育者が、まず、研究の使いかたを理解する必要がある。本書は、エビデンスの作りかたと使いかたをテーマに、最新の研究を含め、著者らが実際に行った研究をもとに、なぜこの方法を用いたのかという思考過程と実際的な活用法を紹介する。また、初学者が研究活動を身近に感じてもらえるよう、各研究法の概要を示したマンガを折々に挿入している。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
作業療法という仕事は雲のように掴みどころがありません.
われわれのように他の専門職から「なにをやっているのか」と突っ込まれ,自分たちでも「私たちの専門性はなんだろう」と自虐的に問い続けている専門職もそうは多くないと思います.しかし作業療法理論によってわれわれのアイデンティティは紡がれ,2018年の定義改定で今後の方向性も定まりました.
これからの作業療法のありかたは,研究によって示されるべきです.
もちろん臨床・教育現場,どこも多忙であることは重々承知していますが,すべての臨床家と研究者が手を取り合い,作業療法のエビデンスを共創していく時代です.その使命感を持って本書を執筆しました.
「日々の臨床で精一杯なのに研究なんてできません!」という方もいらっしゃると思いますが,まず研究を「使う」ことから始めてみてはどうでしょうか.研究を「する」こと自体は確かにオプショナルかもしれませんが,最新の研究結果を臨床に取り入れることは専門職としての責務です.本書は第3章でエビデンスに基づいた実践(EBP)について触れており,このEBPを理解するだけで研究が身近に感じられるかもしれません.
日々エビデンスを調べるなかで,既存の研究だけではわからないことが出てきたときが研究を「する」絶好の機会です.そこで第1章の研究法概論に戻り,研究仮説の作りかたや,研究デザインなどを調べてみるとよいかもしれません.特に本書では,研究活動を始めるまでの初期摩擦をできるだけ少なくする目的でマンガを採用してみましたので,そちらも参考になれば幸いです.
また,新人教育プログラムや学会などで発表し,なんとなく研究に興味は持っているけれども,次にどうすればいいかわからず足踏みをされている方も多いと思います.そういう方が次のステップに進むために,本書のなかの現場に根ざした観察研究(4章),効果を検証する介入研究(5章),臨床の実態を丁寧に分析する質的研究(6章)などが参考になると思いますし,自分で新しい何かを開発したいときには,理論研究(7章)や尺度研究(8章)も役立つでしょう.
研究のコツは,まずやってみることです.
研究方法や統計がわからないので自分には無理,と誤解されがちですが,私たちも最初はよくわからないままスタートし(倫理的に問題のない範囲で),実際に研究しながら理解してきました.研究にはスマートなイメージがあると思いますが,実際には泥臭いものです.
断言してもいいですが,本書もただ読むだけではいつまでも理解できないでしょう.もちろん本書は業界では類を見ない最新の研究手法も多々扱っていますが,そもそも研究法を学ぶという行為自体が「知行合一」的な性格を持っていることも理解していただき,実際に研究を運用しながら本書を“活用”してみてください.まずやってみることが大切です.
研究を学ぶには,それなりの時間と努力を要します.研究を始めるには多少ストレスがかかることでしょう.しかし,ストレスが「人生のスパイス」とたとえられるように,作業療法研究が皆さまにとっての「スパイス」となり,不確実な作業療法を味わう機会につながるなら筆者らも望外の喜びです.
10年後を「今日から」創りましょう.
使命感に突き動かされた人へ贈ります
2019年2月
筆者を代表して 友利幸之介
作業療法という仕事は雲のように掴みどころがありません.
われわれのように他の専門職から「なにをやっているのか」と突っ込まれ,自分たちでも「私たちの専門性はなんだろう」と自虐的に問い続けている専門職もそうは多くないと思います.しかし作業療法理論によってわれわれのアイデンティティは紡がれ,2018年の定義改定で今後の方向性も定まりました.
これからの作業療法のありかたは,研究によって示されるべきです.
もちろん臨床・教育現場,どこも多忙であることは重々承知していますが,すべての臨床家と研究者が手を取り合い,作業療法のエビデンスを共創していく時代です.その使命感を持って本書を執筆しました.
「日々の臨床で精一杯なのに研究なんてできません!」という方もいらっしゃると思いますが,まず研究を「使う」ことから始めてみてはどうでしょうか.研究を「する」こと自体は確かにオプショナルかもしれませんが,最新の研究結果を臨床に取り入れることは専門職としての責務です.本書は第3章でエビデンスに基づいた実践(EBP)について触れており,このEBPを理解するだけで研究が身近に感じられるかもしれません.
日々エビデンスを調べるなかで,既存の研究だけではわからないことが出てきたときが研究を「する」絶好の機会です.そこで第1章の研究法概論に戻り,研究仮説の作りかたや,研究デザインなどを調べてみるとよいかもしれません.特に本書では,研究活動を始めるまでの初期摩擦をできるだけ少なくする目的でマンガを採用してみましたので,そちらも参考になれば幸いです.
また,新人教育プログラムや学会などで発表し,なんとなく研究に興味は持っているけれども,次にどうすればいいかわからず足踏みをされている方も多いと思います.そういう方が次のステップに進むために,本書のなかの現場に根ざした観察研究(4章),効果を検証する介入研究(5章),臨床の実態を丁寧に分析する質的研究(6章)などが参考になると思いますし,自分で新しい何かを開発したいときには,理論研究(7章)や尺度研究(8章)も役立つでしょう.
研究のコツは,まずやってみることです.
研究方法や統計がわからないので自分には無理,と誤解されがちですが,私たちも最初はよくわからないままスタートし(倫理的に問題のない範囲で),実際に研究しながら理解してきました.研究にはスマートなイメージがあると思いますが,実際には泥臭いものです.
断言してもいいですが,本書もただ読むだけではいつまでも理解できないでしょう.もちろん本書は業界では類を見ない最新の研究手法も多々扱っていますが,そもそも研究法を学ぶという行為自体が「知行合一」的な性格を持っていることも理解していただき,実際に研究を運用しながら本書を“活用”してみてください.まずやってみることが大切です.
研究を学ぶには,それなりの時間と努力を要します.研究を始めるには多少ストレスがかかることでしょう.しかし,ストレスが「人生のスパイス」とたとえられるように,作業療法研究が皆さまにとっての「スパイス」となり,不確実な作業療法を味わう機会につながるなら筆者らも望外の喜びです.
10年後を「今日から」創りましょう.
使命感に突き動かされた人へ贈ります
2019年2月
筆者を代表して 友利幸之介
目次
開く
序
第1章 研究法概論
作業療法研究
研究のプロセス
文献検索
研究のアイデアを得る
臨床疑問を研究疑問へ変換する
研究デザイン
研究計画書
研究倫理
学会・論文発表
第2章 統計
統計学はなぜ必要なのか
仮説検定モデルと統計モデリング
母集団とサンプル,そしてパラメータの推定
尺度水準とデータのまとめかた
サンプルサイズ設計
パラメトリック検定とノンパラメトリック検定
相関分析
カットオフ値,リスク比,オッズ比
研究仮説が正しい確率
確率分布
欠損値処理
統計モデルの評価
推定法
一般化線形モデル
一般化線形混合モデル
構造方程式モデル
潜在ランク理論
第3章 EBP(evidence-based practice)
エビデンスとは?
介入研究結果をまとめた診療ガイドライン
EBPのためのコミュニケーション
EBPの5ステップ
EBP事例(脳卒中)
EBP事例(精神障害)
第4章 観察研究
臨床の実態を調べる観察研究
観察研究の基本過程
観察研究の評価
サンプリング法と調査方法
誤差とその対処
相関と因果
記述的研究と生態学的研究
横断研究
ケースコントロール研究
コホート研究
統計的因果探索という新しい方法
第5章 臨床介入研究
介入研究の種類
介入研究のポイント
介入研究における倫理
事例報告からエビデンスを紡ぐ
事例報告・事例研究とは?
事例報告─新しいニューロモデュレーションとCI療法の併用─
ケースシリーズ
シングルシステムデザイン
群内前後比較研究
ランダム化割付けとは
CONSORT声明
偽・非ランダム化比較試験
ランダム化比較試験
傾向スコアによる効果推定
システマティックレビュー
メタ・アナリシス
医療技術の経済的評価(費用対効果評価)研究
第6章 質的研究
クライエントの心境の変化を知りたい
質的研究の評価基準と質
質的研究のサンプリング
インタビューの注意点
観察の注意点
構造構成的質的研究法(SCQRM)
複線径路等至性アプローチ(TEA)
SCAT
コンセンサスメソッド
事例コードマトリックス
修正版グラウンデッドセオリーアプローチ(M-GTA)
KJ法
混合研究法
質的研究は科学なのか
事例報告の質を高めるには
第7章 理論研究
作業療法独自の理論を作りたい
理論研究の事始め
理論研究に必須の知識
原理的思考
論証の技術
歴史分析法
概念分析法
理論統合法
理論修正法
理論継承法
理論研究の質の吟味と理論論文の書きかた
第8章 尺度研究
評価尺度を作りたい
尺度研究の手順
潜在変数と観測変数
尺度項目の作りかた
項目反応理論
妥当性
信頼性
反応性
解釈可能性
頑健性
開発した評価尺度と実践をつなぐ
あとがき
索引
Column
VPN
研究の壁
事例研究における倫理と個人情報
プレゼンのコツ
サンプリングの重大さ
検定力に基づくサンプルサイズの設計の例
統計を勉強するコツ
平均への回帰
統計と人工知能と機械学習と…
統計学が世界を変える
ソフトウェア・初級(HAD,JASP)
ソフトウェア紹介・中級(RとRstudio)
ソフトウェア紹介・上級(Stan)
臨床と研究
介入研究と基礎研究
リアルワールドデータ
レスポンスシフト
臨床上の意味のある最小重要差(MCID)
最小化法
交絡とは
盲検化とは
作業に焦点を当てた実践をテーマに介入研究に取り組む際のポイント
トライアンギュレーション
作業機能障害の種類と評価(CAOD)
尺度研究で使用する統計モデルの一覧
第1章 研究法概論
作業療法研究
研究のプロセス
文献検索
研究のアイデアを得る
臨床疑問を研究疑問へ変換する
研究デザイン
研究計画書
研究倫理
学会・論文発表
第2章 統計
統計学はなぜ必要なのか
仮説検定モデルと統計モデリング
母集団とサンプル,そしてパラメータの推定
尺度水準とデータのまとめかた
サンプルサイズ設計
パラメトリック検定とノンパラメトリック検定
相関分析
カットオフ値,リスク比,オッズ比
研究仮説が正しい確率
確率分布
欠損値処理
統計モデルの評価
推定法
一般化線形モデル
一般化線形混合モデル
構造方程式モデル
潜在ランク理論
第3章 EBP(evidence-based practice)
エビデンスとは?
介入研究結果をまとめた診療ガイドライン
EBPのためのコミュニケーション
EBPの5ステップ
EBP事例(脳卒中)
EBP事例(精神障害)
第4章 観察研究
臨床の実態を調べる観察研究
観察研究の基本過程
観察研究の評価
サンプリング法と調査方法
誤差とその対処
相関と因果
記述的研究と生態学的研究
横断研究
ケースコントロール研究
コホート研究
統計的因果探索という新しい方法
第5章 臨床介入研究
介入研究の種類
介入研究のポイント
介入研究における倫理
事例報告からエビデンスを紡ぐ
事例報告・事例研究とは?
事例報告─新しいニューロモデュレーションとCI療法の併用─
ケースシリーズ
シングルシステムデザイン
群内前後比較研究
ランダム化割付けとは
CONSORT声明
偽・非ランダム化比較試験
ランダム化比較試験
傾向スコアによる効果推定
システマティックレビュー
メタ・アナリシス
医療技術の経済的評価(費用対効果評価)研究
第6章 質的研究
クライエントの心境の変化を知りたい
質的研究の評価基準と質
質的研究のサンプリング
インタビューの注意点
観察の注意点
構造構成的質的研究法(SCQRM)
複線径路等至性アプローチ(TEA)
SCAT
コンセンサスメソッド
事例コードマトリックス
修正版グラウンデッドセオリーアプローチ(M-GTA)
KJ法
混合研究法
質的研究は科学なのか
事例報告の質を高めるには
第7章 理論研究
作業療法独自の理論を作りたい
理論研究の事始め
理論研究に必須の知識
原理的思考
論証の技術
歴史分析法
概念分析法
理論統合法
理論修正法
理論継承法
理論研究の質の吟味と理論論文の書きかた
第8章 尺度研究
評価尺度を作りたい
尺度研究の手順
潜在変数と観測変数
尺度項目の作りかた
項目反応理論
妥当性
信頼性
反応性
解釈可能性
頑健性
開発した評価尺度と実践をつなぐ
あとがき
索引
Column
VPN
研究の壁
事例研究における倫理と個人情報
プレゼンのコツ
サンプリングの重大さ
検定力に基づくサンプルサイズの設計の例
統計を勉強するコツ
平均への回帰
統計と人工知能と機械学習と…
統計学が世界を変える
ソフトウェア・初級(HAD,JASP)
ソフトウェア紹介・中級(RとRstudio)
ソフトウェア紹介・上級(Stan)
臨床と研究
介入研究と基礎研究
リアルワールドデータ
レスポンスシフト
臨床上の意味のある最小重要差(MCID)
最小化法
交絡とは
盲検化とは
作業に焦点を当てた実践をテーマに介入研究に取り組む際のポイント
トライアンギュレーション
作業機能障害の種類と評価(CAOD)
尺度研究で使用する統計モデルの一覧
書評
開く
時代を創る使命感を持った療法士に読んでほしい一冊
書評者: 藤本 修平 (京大大学院・社会健康医学)
これからの時代,リハビリテーション医療における意思決定には,臨床現場で創られた実証結果であるエビデンスが求められることは想像に難くない。そのエビデンスとは何か? 臨床および社会で生かすための幅広い研究法エッセンスを学べる書籍が本書である。
本書の構成として小生が捉えた特徴的な点は3つである。1点目は研究デザインの網羅性,2点目はエビデンスの活用法にも触れている実用性(実践性),3点目はマンガを用いた理解へのリーチ性である。
研究デザインを網羅的かつ適切に示した研究法の書籍は,作業療法業界のみならず理学療法業界,リハビリテーション業界でもあまり見かけない。研究はデザインが命である一方で,研究デザインの理解を得ずに研究が進められてきた背景がある。多くの臨床研究者の質があらためて見直されている中,本書の網羅性には公衆衛生学が専門である小生もうなった。例えば,臨床に従事している者は知識が必須である“臨床的に意味のある最小の差”を表すMinimal Clinically Important Difference(MCID)や費用対効果分析の説明のように,主にそれらの専門書でしか見かけないような痒いところにも手が届いているのが印象的であった。
2点目で挙げたエビデンスの活用法については,読者への気遣いが感じられる。これまでの研究法の書籍類は得てして,研究者のための書籍になっていた。当然,内容は難しくとっかかりにくい。他方で,入門書は割愛されている部分も多く,研究への誤解を生んでいた。しかし,何のために研究を行うのか? という原点に立ち返ってみると,臨床で活用されることも目的の一つである。“エビデンスを活用する(Evidence-based practice)”という視点から本書にたどり着くことで,臨床での活用まで見据えて,エビデンスおよび研究法への理解を進めることができるだろう。
3点目は,いわゆる読者へのリーチ性に配慮したエンタメの導入である。本書の中でも紹介されているが,エビデンスは“つくる・つたえる・つかう”という側面がある。臨床で目の前の患者さんに対峙する際,まずはつたえる・つかうという能力が必要であるが,当然書籍も読者の理解まで踏み込まなければならない。近年,エンタメを用いた行動変容が検証されているが,まさに本書も研究に踏み込む上での“あるある”をマンガに載せ,本論へ誘導しているのが印象的であった。
タラレバではあるが,小生が理学療法士になった10年前,このような書籍があればどれだけ助かったかと現在本書を手に取れる療法士をうらやましく思う。作業療法や理学療法,言語聴覚療法のプレゼンスを高めるためのエビデンス創出,その臨床応用を担う使命を少しでも感じる,もしくは何か今の自分にもどかしさを感じるのであれば,ぜひ本書を手にとってほしい。著者らの作業療法への思いや実証を基にした業界を発展させるエッセンスとともに,読者のステップアップを手助けしてくれることだろう。
臨床家が研究を始めることを後押ししてくれる良書
書評者: 鈴木 誠 (東京家政大教授・作業療法学)
作業療法に研究は必要なのでしょうか?
脳血管障害によって立位で調理をすることが難しくなった対象者に対する作業療法を想定してみます。作業療法士は,この対象者の下肢筋力を測定してレジスタンストレーニングを行い,行動様式を評価して行動練習を行い,筋力や行動を補うための福祉用具の処方や環境調整を行うのではないかと思います。
そもそも,なぜ,立位で調理をすることが難しくなった対象者に対して,作業療法士は下肢筋力を測定するのでしょうか? その判断の基をたどっていくと,脳血管障害によって下肢筋力が低下することや,立位に下肢筋力が影響を及ぼすこと,またレジスタンストレーニングによって下肢筋力が向上することが,研究によって明らかになっているからなのです。つまり,研究によって得られた実践の指針を参考にして,現在の実践が組み立てられているということになります。しかし,現実の臨床場面は,現在の研究によって得られた実践の指針では説明できないことが無数にあります。
この対象者が作業療法士に質問をしたとします。「立って調理をするためにはどのくらいの足の力が必要なのですか?」「このトレーニングを続けたら,来月にはどのくらい力がついているのですか?」「この行動練習を続けたら,どのくらいの期間で調理ができるようになるのですか?」「他に選択できる練習方法はあるのですか?」
これらの問いに,現在の作業療法はどのくらいの答えを用意することができるのでしょうか?
対象者の問いに作業療法士が答えられるようになるためには,多くの症例研究を積み重ねて多様な疾患や障害に応じた介入方法を探索するとともに,前向きコホート研究やランダム化比較試験によって作業療法の効果や予後を科学的に実証していかなくてはなりません。
作業療法は,研究を必要としているのです。
本書の著者らは,「これからの作業療法のありかたは,研究によって示されるべき」と冒頭で宣言しています。研究を推進することこそが,未来の作業療法を形作るという強い決意を感じます。この決意に裏打ちされるように,本書では一貫して作業療法を実践する臨床家の視点から研究の意義が描かれています。研究とは何か,エビデンスとは何かという根本的な問いに始まり,質的研究,横断研究,コホート研究,ランダム化比較試験などの研究を進めるための考え方が丁寧に解説されています。
研究は,過去の作業療法と未来の作業療法をつなぎます。本書は,臨床家が研究に一歩踏み出すことを後押ししてくれる良書です。多くの作業療法士が本書を手に取ることによって,研究に裏付けられた新しい実践の指針が次々と生み出され,作業療法が発展していくことを願っております。
書評者: 藤本 修平 (京大大学院・社会健康医学)
これからの時代,リハビリテーション医療における意思決定には,臨床現場で創られた実証結果であるエビデンスが求められることは想像に難くない。そのエビデンスとは何か? 臨床および社会で生かすための幅広い研究法エッセンスを学べる書籍が本書である。
本書の構成として小生が捉えた特徴的な点は3つである。1点目は研究デザインの網羅性,2点目はエビデンスの活用法にも触れている実用性(実践性),3点目はマンガを用いた理解へのリーチ性である。
研究デザインを網羅的かつ適切に示した研究法の書籍は,作業療法業界のみならず理学療法業界,リハビリテーション業界でもあまり見かけない。研究はデザインが命である一方で,研究デザインの理解を得ずに研究が進められてきた背景がある。多くの臨床研究者の質があらためて見直されている中,本書の網羅性には公衆衛生学が専門である小生もうなった。例えば,臨床に従事している者は知識が必須である“臨床的に意味のある最小の差”を表すMinimal Clinically Important Difference(MCID)や費用対効果分析の説明のように,主にそれらの専門書でしか見かけないような痒いところにも手が届いているのが印象的であった。
2点目で挙げたエビデンスの活用法については,読者への気遣いが感じられる。これまでの研究法の書籍類は得てして,研究者のための書籍になっていた。当然,内容は難しくとっかかりにくい。他方で,入門書は割愛されている部分も多く,研究への誤解を生んでいた。しかし,何のために研究を行うのか? という原点に立ち返ってみると,臨床で活用されることも目的の一つである。“エビデンスを活用する(Evidence-based practice)”という視点から本書にたどり着くことで,臨床での活用まで見据えて,エビデンスおよび研究法への理解を進めることができるだろう。
3点目は,いわゆる読者へのリーチ性に配慮したエンタメの導入である。本書の中でも紹介されているが,エビデンスは“つくる・つたえる・つかう”という側面がある。臨床で目の前の患者さんに対峙する際,まずはつたえる・つかうという能力が必要であるが,当然書籍も読者の理解まで踏み込まなければならない。近年,エンタメを用いた行動変容が検証されているが,まさに本書も研究に踏み込む上での“あるある”をマンガに載せ,本論へ誘導しているのが印象的であった。
タラレバではあるが,小生が理学療法士になった10年前,このような書籍があればどれだけ助かったかと現在本書を手に取れる療法士をうらやましく思う。作業療法や理学療法,言語聴覚療法のプレゼンスを高めるためのエビデンス創出,その臨床応用を担う使命を少しでも感じる,もしくは何か今の自分にもどかしさを感じるのであれば,ぜひ本書を手にとってほしい。著者らの作業療法への思いや実証を基にした業界を発展させるエッセンスとともに,読者のステップアップを手助けしてくれることだろう。
臨床家が研究を始めることを後押ししてくれる良書
書評者: 鈴木 誠 (東京家政大教授・作業療法学)
作業療法に研究は必要なのでしょうか?
脳血管障害によって立位で調理をすることが難しくなった対象者に対する作業療法を想定してみます。作業療法士は,この対象者の下肢筋力を測定してレジスタンストレーニングを行い,行動様式を評価して行動練習を行い,筋力や行動を補うための福祉用具の処方や環境調整を行うのではないかと思います。
そもそも,なぜ,立位で調理をすることが難しくなった対象者に対して,作業療法士は下肢筋力を測定するのでしょうか? その判断の基をたどっていくと,脳血管障害によって下肢筋力が低下することや,立位に下肢筋力が影響を及ぼすこと,またレジスタンストレーニングによって下肢筋力が向上することが,研究によって明らかになっているからなのです。つまり,研究によって得られた実践の指針を参考にして,現在の実践が組み立てられているということになります。しかし,現実の臨床場面は,現在の研究によって得られた実践の指針では説明できないことが無数にあります。
この対象者が作業療法士に質問をしたとします。「立って調理をするためにはどのくらいの足の力が必要なのですか?」「このトレーニングを続けたら,来月にはどのくらい力がついているのですか?」「この行動練習を続けたら,どのくらいの期間で調理ができるようになるのですか?」「他に選択できる練習方法はあるのですか?」
これらの問いに,現在の作業療法はどのくらいの答えを用意することができるのでしょうか?
対象者の問いに作業療法士が答えられるようになるためには,多くの症例研究を積み重ねて多様な疾患や障害に応じた介入方法を探索するとともに,前向きコホート研究やランダム化比較試験によって作業療法の効果や予後を科学的に実証していかなくてはなりません。
作業療法は,研究を必要としているのです。
本書の著者らは,「これからの作業療法のありかたは,研究によって示されるべき」と冒頭で宣言しています。研究を推進することこそが,未来の作業療法を形作るという強い決意を感じます。この決意に裏打ちされるように,本書では一貫して作業療法を実践する臨床家の視点から研究の意義が描かれています。研究とは何か,エビデンスとは何かという根本的な問いに始まり,質的研究,横断研究,コホート研究,ランダム化比較試験などの研究を進めるための考え方が丁寧に解説されています。
研究は,過去の作業療法と未来の作業療法をつなぎます。本書は,臨床家が研究に一歩踏み出すことを後押ししてくれる良書です。多くの作業療法士が本書を手に取ることによって,研究に裏付けられた新しい実践の指針が次々と生み出され,作業療法が発展していくことを願っております。