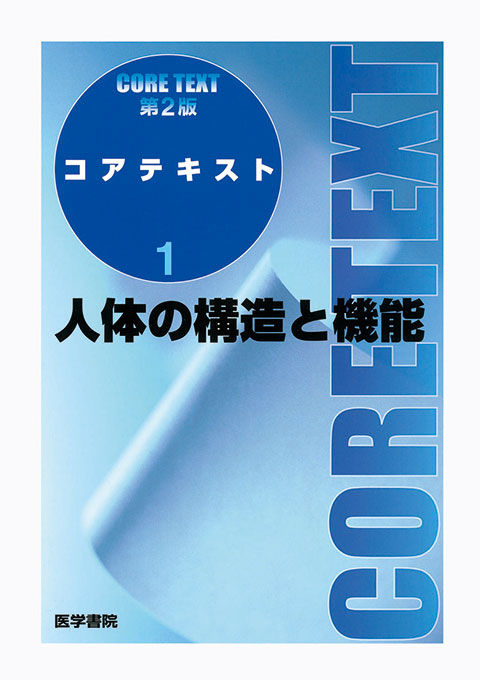人体の構造と機能
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 目次
- 書評
目次
開く
第1章 生命とは
A. 細胞の構造と機能
B. エネルギー代謝
C. 体内環境の恒常性
D. 生体のリズム
E. 人体の基礎構造
F. 人体をおおう組織の構造と機能
第2章 生体の防御機構
A. 非特異的生体防御機構
B. 特異的生体防御反応(免疫応答)
C. 生体防御系の発生・発達
D. 血液の成分と働き
E. 止血機構
F. 血液型
第3章 流通路としての循環系
A. 心臓血管系
B. リンパ系
C. 循環系の発達・老化
第4章 神経性調節と刺激の受容
A. 神経系のしくみ
B. 神経系を守るしくみと動脈
C. 神経系を構成する細胞と組織
D. 神経細胞と情報伝達
E. 回路別にみた神経系
第5章 液性調節(内分泌系)
A. ホルモンの作用機序
B. ホルモン分泌の調節
C. 内分泌器官の構造と機能
第6章 生活行動を支える運動系
A. 体位と姿勢
B. 骨格の構造と機能
C. 筋の構造と機能
D. 骨格筋の種類と役割
E. 関節の構造と機能
第7章 呼吸の機構
A. 換気
B. ガス交換
C. ガスの運搬
D. 呼吸調節
第8章 栄養摂取の機構
A. 食欲
B. 咀嚼
C. 嚥下
D. 消化と吸収
E. 代謝
第9章 排泄の機構
A. 尿の生成と腎臓の働き
B. 尿の調節
C. 排尿
D. 排便
第10章 性と生殖に関する機構
A. 女性の生殖器系
B. 男性の生殖器系
推薦図書・参考文献
索引
A. 細胞の構造と機能
B. エネルギー代謝
C. 体内環境の恒常性
D. 生体のリズム
E. 人体の基礎構造
F. 人体をおおう組織の構造と機能
第2章 生体の防御機構
A. 非特異的生体防御機構
B. 特異的生体防御反応(免疫応答)
C. 生体防御系の発生・発達
D. 血液の成分と働き
E. 止血機構
F. 血液型
第3章 流通路としての循環系
A. 心臓血管系
B. リンパ系
C. 循環系の発達・老化
第4章 神経性調節と刺激の受容
A. 神経系のしくみ
B. 神経系を守るしくみと動脈
C. 神経系を構成する細胞と組織
D. 神経細胞と情報伝達
E. 回路別にみた神経系
第5章 液性調節(内分泌系)
A. ホルモンの作用機序
B. ホルモン分泌の調節
C. 内分泌器官の構造と機能
第6章 生活行動を支える運動系
A. 体位と姿勢
B. 骨格の構造と機能
C. 筋の構造と機能
D. 骨格筋の種類と役割
E. 関節の構造と機能
第7章 呼吸の機構
A. 換気
B. ガス交換
C. ガスの運搬
D. 呼吸調節
第8章 栄養摂取の機構
A. 食欲
B. 咀嚼
C. 嚥下
D. 消化と吸収
E. 代謝
第9章 排泄の機構
A. 尿の生成と腎臓の働き
B. 尿の調節
C. 排尿
D. 排便
第10章 性と生殖に関する機構
A. 女性の生殖器系
B. 男性の生殖器系
推薦図書・参考文献
索引
書評
開く
マンネリ化した基礎教育に一石を投じる書
書評者: 中木 高夫 (日赤看護大教授)
目を閉じて思い浮かべてほしい。高校を卒業したての,主として若い娘たちが授業を受けている姿を。ついこのあいだまで,彼女たちは医学の「い」の字も知らなかった。ところが,看護師養成施設(その中には大学・短期大学・専門学校が含まれる)に入学するやいなや,週に1回ないし2回の「人体の構造と機能」という授業を受けることになる。
授業形態は,大部分の養成施設では講義が多いだろう。「人体の構造と機能」という科目で,プロブレム・ベースド・ラーニング(PBL)をやるには勇気が必要だろう。彼女たちは何も知らないのだから,人間の身体面への最初の入り口である「人体の構造と機能」は,網羅的でなければならない強迫観念にも似た思いがある。
◆「人体の構造と機能」で学生に求めるもの
筆者は,自分ではプロパーな看護学教育者を目指しているが,医師免許しか有していないということが災いして,いまは看護基礎教育における医師役割を演じている。つまり,「人体の構造と機能」と「疾病の成り立ちと回復」の部分が主たる担当科目というわけだ(本当は「看護診断学」「看護診断学演習」「看護診断学実習」といった科目を担当したいのだけれど,残念ながらわが学舎にはそのようなイカガワシイ科目は存在していないのだ)。筆者の目の前にいる学生たちは,冒頭で想像してもらったような学生たちである。
そういう学生を前にして,筆者は何を念頭において「人体の構造と機能」を担当しているのかというと,医療の世界で用いられる専門用語の伝達である。まず教科書を自分で音読し,その中に含まれる専門用語を解説し,場合によってはその語のもとになった英語を示して語彙がつくられる構造もあわせて解説している。つまり,専門家が駆使する用語の概念を教えようとしているわけだ。
「人体の構造と機能」という科目は,その名称が示すとおり,「解剖学」と「生理学」ではない。身体を機能を中心にすえて,その機能を発揮するためにいかに合目的的な構造を神様はおつくりになったのかという不思議を学ぶための科目と解釈している。しかも,1年1学期から学ぶ科目である。これからの50年近くを過ごす医療の世界の,はじめの一歩なのである。
◆本文は簡潔に,コラムを充実教育者として工夫をこらす
『コアテキスト1:人体の構造と機能』は1984年に大学を卒業し,病理学を専門とし,多くはネーベンとして看護基礎教育の場で「人体の構造と機能」を教えてきた人たちの著である。したがって,実際に教育を担当する者としてのさまざまな工夫をこらしている。その特徴を一言でいえば「ハイパーテキスト性」である。要点は,できるだけ簡潔に述べたい。だが,それでは専門用語がつまづきになって,読者である学生には理解が困難になる。そこで「Word」や「ワンポイント」,「ステップアップ」という本文外のコラムを充実させている。
マンネリ化していた看護基礎教育のための教科書に一石を投じるものとして,『コアテキスト1:人体の構造と機能』にかける期待は大きい。しかし,まだはじめの一歩である。筆者の方々が実際に通して使われてみれば,一層バランスのとれた,充実した改訂版に生まれ変わるに違いないだろう。
生命活動への理解はいつの時代もケアの基本
書評者: 川島 みどり (日本赤十字看護大学・健和会臨床看護学研究所)
◆身体機能別に人間を知る
看護の視点は,人間を総合的にとらえるべきとの考え方が教育に根づいて久しく,日常の看護を展開する場合にも,そのことへの意識がケアプランに反映する。一方で,こうした看護の独自性の強調により,心理・社会面に偏りがちであるとの批判があることも事実である。本書はチーム医療を実践する医師たちが,看護師らのそうした傾向を憂う立場から,疾患理解を基盤にした看護の重要性を考え,「最低限このくらいの知識の共有を」と願って執筆された。
本書は,ヒトの身体が生体としての自己を維持し,生命活動を営みながらどのような機能を統合して日常生活行動を継続していくのかを,臨床に引き寄せながら理解できるように,従来の医学体系とは異なった視点で構成されている。すなわち,人間の生きる姿のうちの「生きている状態」とはどのようなことかを,解剖生理学や生化学,病理学などの壁を取り除いて,身体機能別に融合させることを意図された点が,類書とは異なる本書の特徴である。
このように,まず生命体としての人間の身体活動をしっかりとふまえたうえで,病んでいるその人の身体内部で起きている事象を組み立て理解することは,臨床の場においての個別ケアを実践するうえで欠かせないことである。また,看護実践能力や看護判断力を高める基礎教育の課題にも通じるものである。今後刊行を予定している本シリーズ全巻を通じて,「看護師国家試験出題基準」に準拠することを目ざしていると聞けば,看護の基礎教育におおいに活用できるに違いない。
◆看護の視点からの「注文」
ただ,不満がないわけではない。本書は看護だけのものではなく,リハビリや薬学,臨床検査など広範囲の専門職を対象にしたコアテキストという位置づけでもあるので,看護の立場からのみ注文をつけるのに躊躇がないわけではないが,あえて意見を述べさせてもらうと,各領域における用語の概念を踏まえたうえでの検討をしてもらいたかったと思う。
たとえば,6章の生活行動を支える運動系に目を向けた場合,まず「生活行動」という用語の概念を抜きにはできない。看護におけるそれは,「生命維持のために行なう日常的・習慣的営み」をいい,かなり広範な意味を持たせている。しかも,いわゆる看護本来の専門性をその行動の援助においている。
ところがここでの運動は,静止姿勢から各関節運動と連動した筋肉の収縮など,文字通り従来の運動の範疇であり,必ずしも生活行動を支える運動とは言えないのではないだろうか。もし看護の立場で考えるとするなら,4章の神経性調節と刺激の受容の中で触れられている回路別に見た神経系と,この6章の内容との組み合わせによってはじめて,個々の生活行動が自立して支障なく営まれるのではないかと思えた。
つまり,過去の教科の配列とは異なった,人間の行動に焦点を当てた解剖・生理学や生化学の知識のまとまりが,このような形でまとめられたらどんなによかっただろうかと,看護の立場で考えた次第である。とはいえ,本書全体のスタンスへの共感はいささかも揺らぐものではない。個別ケアの基礎となる人間へのケアの基本は生命活動である。その最新の知識を効率的に学ぶうえで,豊富な工夫されたイラストは読者を助けることであろう。ともすると断片的になりやすい知識を統合する際の貴重なテキストとして,看護教育の場はもちろん,臨床での活用をおすすめする。
情報化時代だからこそ「コア」を学ぶ
書評者: 畑尾 正彦 (日本赤十字武蔵野短期大学)
◆機能から構造を学ぶ
このほど病理学を学んで医療に貢献しようと志す「病理医の会」の方々が,看護教育にも関わる立場からコアテキストを刊行された。看護専門教育の土台となる解剖学,生理学,生化学,栄養学,病理学,微生物学,免疫学,薬理学などを融合して学ぶものである。これらの分野の膨大な知識からコアとなる基本的な内容を精選し,その理解が深まるように工夫して書かれた本文と,「コラム」「ワンポイント」「ステップアップ」「Word」などの小さな欄とに書き分けられ,「生命とは」「生体の防御機構」「流通路としての循環系」「神経性調節と刺激の受容」「液性調節(内分泌系)」「生活行動を支える運動系」「呼吸の機構」「栄養摂取の機構」「排泄の機構」「性と生殖に関する機構」の10章から成っている。
従来の教科書が,まず構造を解説する“静”から,それらがどのような機能を果たしているかを解説する“動”への方向で組み立てられたものが多かったのに対して,このコアテキストは見やすい図を多用しながら,人の生活を感じる“動”から“静”に向けて展開する構成になっている。高校を卒業して間もない学生さんが,興味を持ちながら,看護やその他の医療の勉強を効率よく進めるのを助けるに違いない。
◆限られた時間で何を学ぶか
医学・医療に関する情報量の急速な増加は幾何級数的であり,入学したときに習ったことが,卒業後にも通用するという保証はない時代である。看護教育においても教員が講義で知識を伝える従来の授業スタイルでは対応できないことは自明であり,限られた修学年限の中での授業内容は,担当教員の関心はさておいて,基本的なコアに絞ることが肝要である。その意味でも,このコアテキストの刊行は時宜を得たものといえよう。
医学教育がかつてない改革の波に洗われている背景にも,こうした情報量の急速な増加がある。卒前医学教育にコア・カリキュラムが提案され,全国の医学部が,このコア・カリキュラムを念頭においたカリキュラム改革に乗り出している。この状況は看護界でも同じはずである。加えて大学の看護教育の目的や内容が,あまりにも各大学の独自性に任された結果,大学卒業生を受け入れる看護の臨床現場の戸惑いが小さくないことが指摘され,大学の看護教育に対してもコア・カリキュラムが提案されている。
しかし看護界には,このコア・カリキュラムに対応しようとする動きは,医学部の場合のようには感じられない。コア・カリキュラムに盛り込まれた内容は,すでに実施しているという声も聞くが,これはコア・カリキュラムが提案された真意をまったく取り違えているとしか思えない。コア・カリキュラムに盛り込まれた内容以外をすべて捨て去ったうえで,大学に求められる看護教育は何なのかを,真摯に策定する姿勢を看護教育担当者に持っていただきたいと思う。
◆チーム医療の一翼を担うために
このコアテキストには,チーム医療のメンバーに「少なくともこれくらいの知識を共有してほしい」という著者たちのメッセージが込められている。著者に限らず,そう願う医師たちは多いと考えられるが,そういう人たちには,医療をともに担う看護の本来の使命と業務とは何なのかを理解し,それを尊重する責任があるだろう。医療においては患者さんの立場を,教育においては学生さんの視点を常に中心におく代表編著者の下先生は,紛れもなくその責任を果たしている1人だ。そのこともこのコアテキストを,自信をもってお勧めできる所以である。シリーズ続刊の刊行が待たれる。
書評者: 中木 高夫 (日赤看護大教授)
目を閉じて思い浮かべてほしい。高校を卒業したての,主として若い娘たちが授業を受けている姿を。ついこのあいだまで,彼女たちは医学の「い」の字も知らなかった。ところが,看護師養成施設(その中には大学・短期大学・専門学校が含まれる)に入学するやいなや,週に1回ないし2回の「人体の構造と機能」という授業を受けることになる。
授業形態は,大部分の養成施設では講義が多いだろう。「人体の構造と機能」という科目で,プロブレム・ベースド・ラーニング(PBL)をやるには勇気が必要だろう。彼女たちは何も知らないのだから,人間の身体面への最初の入り口である「人体の構造と機能」は,網羅的でなければならない強迫観念にも似た思いがある。
◆「人体の構造と機能」で学生に求めるもの
筆者は,自分ではプロパーな看護学教育者を目指しているが,医師免許しか有していないということが災いして,いまは看護基礎教育における医師役割を演じている。つまり,「人体の構造と機能」と「疾病の成り立ちと回復」の部分が主たる担当科目というわけだ(本当は「看護診断学」「看護診断学演習」「看護診断学実習」といった科目を担当したいのだけれど,残念ながらわが学舎にはそのようなイカガワシイ科目は存在していないのだ)。筆者の目の前にいる学生たちは,冒頭で想像してもらったような学生たちである。
そういう学生を前にして,筆者は何を念頭において「人体の構造と機能」を担当しているのかというと,医療の世界で用いられる専門用語の伝達である。まず教科書を自分で音読し,その中に含まれる専門用語を解説し,場合によってはその語のもとになった英語を示して語彙がつくられる構造もあわせて解説している。つまり,専門家が駆使する用語の概念を教えようとしているわけだ。
「人体の構造と機能」という科目は,その名称が示すとおり,「解剖学」と「生理学」ではない。身体を機能を中心にすえて,その機能を発揮するためにいかに合目的的な構造を神様はおつくりになったのかという不思議を学ぶための科目と解釈している。しかも,1年1学期から学ぶ科目である。これからの50年近くを過ごす医療の世界の,はじめの一歩なのである。
◆本文は簡潔に,コラムを充実教育者として工夫をこらす
『コアテキスト1:人体の構造と機能』は1984年に大学を卒業し,病理学を専門とし,多くはネーベンとして看護基礎教育の場で「人体の構造と機能」を教えてきた人たちの著である。したがって,実際に教育を担当する者としてのさまざまな工夫をこらしている。その特徴を一言でいえば「ハイパーテキスト性」である。要点は,できるだけ簡潔に述べたい。だが,それでは専門用語がつまづきになって,読者である学生には理解が困難になる。そこで「Word」や「ワンポイント」,「ステップアップ」という本文外のコラムを充実させている。
マンネリ化していた看護基礎教育のための教科書に一石を投じるものとして,『コアテキスト1:人体の構造と機能』にかける期待は大きい。しかし,まだはじめの一歩である。筆者の方々が実際に通して使われてみれば,一層バランスのとれた,充実した改訂版に生まれ変わるに違いないだろう。
生命活動への理解はいつの時代もケアの基本
書評者: 川島 みどり (日本赤十字看護大学・健和会臨床看護学研究所)
◆身体機能別に人間を知る
看護の視点は,人間を総合的にとらえるべきとの考え方が教育に根づいて久しく,日常の看護を展開する場合にも,そのことへの意識がケアプランに反映する。一方で,こうした看護の独自性の強調により,心理・社会面に偏りがちであるとの批判があることも事実である。本書はチーム医療を実践する医師たちが,看護師らのそうした傾向を憂う立場から,疾患理解を基盤にした看護の重要性を考え,「最低限このくらいの知識の共有を」と願って執筆された。
本書は,ヒトの身体が生体としての自己を維持し,生命活動を営みながらどのような機能を統合して日常生活行動を継続していくのかを,臨床に引き寄せながら理解できるように,従来の医学体系とは異なった視点で構成されている。すなわち,人間の生きる姿のうちの「生きている状態」とはどのようなことかを,解剖生理学や生化学,病理学などの壁を取り除いて,身体機能別に融合させることを意図された点が,類書とは異なる本書の特徴である。
このように,まず生命体としての人間の身体活動をしっかりとふまえたうえで,病んでいるその人の身体内部で起きている事象を組み立て理解することは,臨床の場においての個別ケアを実践するうえで欠かせないことである。また,看護実践能力や看護判断力を高める基礎教育の課題にも通じるものである。今後刊行を予定している本シリーズ全巻を通じて,「看護師国家試験出題基準」に準拠することを目ざしていると聞けば,看護の基礎教育におおいに活用できるに違いない。
◆看護の視点からの「注文」
ただ,不満がないわけではない。本書は看護だけのものではなく,リハビリや薬学,臨床検査など広範囲の専門職を対象にしたコアテキストという位置づけでもあるので,看護の立場からのみ注文をつけるのに躊躇がないわけではないが,あえて意見を述べさせてもらうと,各領域における用語の概念を踏まえたうえでの検討をしてもらいたかったと思う。
たとえば,6章の生活行動を支える運動系に目を向けた場合,まず「生活行動」という用語の概念を抜きにはできない。看護におけるそれは,「生命維持のために行なう日常的・習慣的営み」をいい,かなり広範な意味を持たせている。しかも,いわゆる看護本来の専門性をその行動の援助においている。
ところがここでの運動は,静止姿勢から各関節運動と連動した筋肉の収縮など,文字通り従来の運動の範疇であり,必ずしも生活行動を支える運動とは言えないのではないだろうか。もし看護の立場で考えるとするなら,4章の神経性調節と刺激の受容の中で触れられている回路別に見た神経系と,この6章の内容との組み合わせによってはじめて,個々の生活行動が自立して支障なく営まれるのではないかと思えた。
つまり,過去の教科の配列とは異なった,人間の行動に焦点を当てた解剖・生理学や生化学の知識のまとまりが,このような形でまとめられたらどんなによかっただろうかと,看護の立場で考えた次第である。とはいえ,本書全体のスタンスへの共感はいささかも揺らぐものではない。個別ケアの基礎となる人間へのケアの基本は生命活動である。その最新の知識を効率的に学ぶうえで,豊富な工夫されたイラストは読者を助けることであろう。ともすると断片的になりやすい知識を統合する際の貴重なテキストとして,看護教育の場はもちろん,臨床での活用をおすすめする。
情報化時代だからこそ「コア」を学ぶ
書評者: 畑尾 正彦 (日本赤十字武蔵野短期大学)
◆機能から構造を学ぶ
このほど病理学を学んで医療に貢献しようと志す「病理医の会」の方々が,看護教育にも関わる立場からコアテキストを刊行された。看護専門教育の土台となる解剖学,生理学,生化学,栄養学,病理学,微生物学,免疫学,薬理学などを融合して学ぶものである。これらの分野の膨大な知識からコアとなる基本的な内容を精選し,その理解が深まるように工夫して書かれた本文と,「コラム」「ワンポイント」「ステップアップ」「Word」などの小さな欄とに書き分けられ,「生命とは」「生体の防御機構」「流通路としての循環系」「神経性調節と刺激の受容」「液性調節(内分泌系)」「生活行動を支える運動系」「呼吸の機構」「栄養摂取の機構」「排泄の機構」「性と生殖に関する機構」の10章から成っている。
従来の教科書が,まず構造を解説する“静”から,それらがどのような機能を果たしているかを解説する“動”への方向で組み立てられたものが多かったのに対して,このコアテキストは見やすい図を多用しながら,人の生活を感じる“動”から“静”に向けて展開する構成になっている。高校を卒業して間もない学生さんが,興味を持ちながら,看護やその他の医療の勉強を効率よく進めるのを助けるに違いない。
◆限られた時間で何を学ぶか
医学・医療に関する情報量の急速な増加は幾何級数的であり,入学したときに習ったことが,卒業後にも通用するという保証はない時代である。看護教育においても教員が講義で知識を伝える従来の授業スタイルでは対応できないことは自明であり,限られた修学年限の中での授業内容は,担当教員の関心はさておいて,基本的なコアに絞ることが肝要である。その意味でも,このコアテキストの刊行は時宜を得たものといえよう。
医学教育がかつてない改革の波に洗われている背景にも,こうした情報量の急速な増加がある。卒前医学教育にコア・カリキュラムが提案され,全国の医学部が,このコア・カリキュラムを念頭においたカリキュラム改革に乗り出している。この状況は看護界でも同じはずである。加えて大学の看護教育の目的や内容が,あまりにも各大学の独自性に任された結果,大学卒業生を受け入れる看護の臨床現場の戸惑いが小さくないことが指摘され,大学の看護教育に対してもコア・カリキュラムが提案されている。
しかし看護界には,このコア・カリキュラムに対応しようとする動きは,医学部の場合のようには感じられない。コア・カリキュラムに盛り込まれた内容は,すでに実施しているという声も聞くが,これはコア・カリキュラムが提案された真意をまったく取り違えているとしか思えない。コア・カリキュラムに盛り込まれた内容以外をすべて捨て去ったうえで,大学に求められる看護教育は何なのかを,真摯に策定する姿勢を看護教育担当者に持っていただきたいと思う。
◆チーム医療の一翼を担うために
このコアテキストには,チーム医療のメンバーに「少なくともこれくらいの知識を共有してほしい」という著者たちのメッセージが込められている。著者に限らず,そう願う医師たちは多いと考えられるが,そういう人たちには,医療をともに担う看護の本来の使命と業務とは何なのかを理解し,それを尊重する責任があるだろう。医療においては患者さんの立場を,教育においては学生さんの視点を常に中心におく代表編著者の下先生は,紛れもなくその責任を果たしている1人だ。そのこともこのコアテキストを,自信をもってお勧めできる所以である。シリーズ続刊の刊行が待たれる。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。