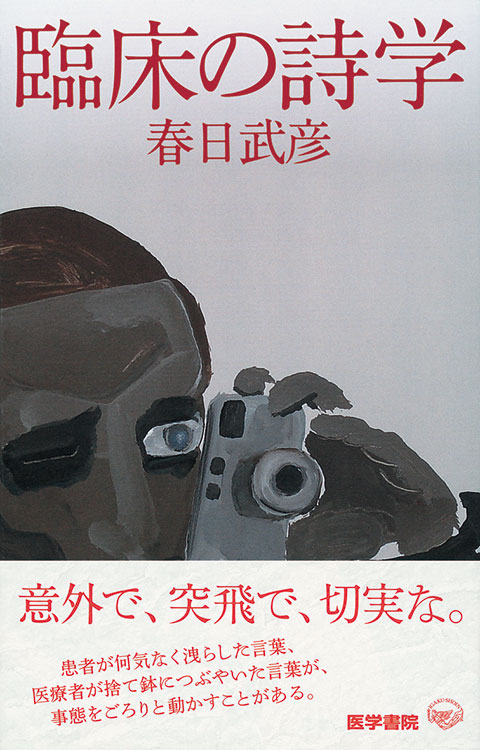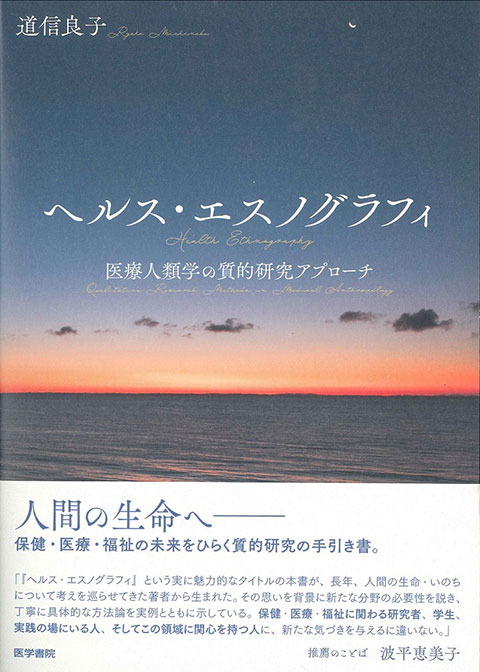臨床の詩学
私は一冊の日記帳である。
もっと見る
患者が何気なく洩らした言葉、医療者が捨て鉢につぶやいた言葉が、行き詰まった事態をごろりと動かすことがある。現場で働く者なら誰でもが知っているそんな《臨床の奇跡》を、手練れの精神科医が祈りを込めて書き留める。医療者を深いところで励ます、意外で、突飛で、切実な言葉のコレクション。
| 著 | 春日 武彦 |
|---|---|
| 発行 | 2011年02月判型:四六変頁:336 |
| ISBN | 978-4-260-01334-5 |
| 定価 | 1,980円 (本体1,800円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
序 わたしが精神科医でいられる理由
本書は二つのパートから成り立っている。すなわち前半が《臨床の詩学》、後半が《辺境の作法》である。
これらは互いに陽画/陰画の関係になっている。そして全体のテーマは、「精神科領域という特異な角度から、言葉やコミュニケーションや他者理解についてその意外性や突飛さや切実さを探る試み」ということになる。
前半の《臨床の詩学》においては、一見したところはコミュニケーションが成立していないように映るにもかかわらず、心の交流が起き得る不思議さや驚きに力点が置かれる。詩を中心とした文学作品を補助線として用いなければ語りきれない内容であるところに、それなりの興趣があるかもしれない。医療関係者のみならず「言葉」に関心を寄せるあらゆる人々に読んでいただければ嬉しいと思っている。
後半の《辺境の作法》では、特にパーソナリティ障害を中心に、表面的には言葉のやりとりが成立しているにもかかわらず心の交流が成り立たない不気味さや困惑に力点が置かれる。精神医療という世界の難しさを窺い知る端緒ともなり得れば、書き綴った甲斐があるというものである。
おそらく、前半には希望の光がちらほらと見え、後半には絶望や無力感の闇がうっすらと漂っているように感じられるのではないか。双方を心の中に同居させられなければ、精神科の臨床現場をつとめ上げていくことはできない。
*
それにしても、わたしは言葉に興味があるからこそ精神科医として生きていけるのだなあと、つくづく思うのである。
たとえばM病院に勤務していたときのことである。近道をするため、病棟に囲まれた中庭を斜めに突っ切っていたら、患者のAさんにいきなり声をかけられた。ちなみに彼の主治医はわたしではないが、何年も入院しているので顔見知りの関係ではある。Aさんは興奮した様子で語ってくる。
「先生、ぜひ来てください。絶滅したと言われるシロバナタンポポが、この病院に生えていたんです。発見したんです!」
たしかにタンポポは黄色が普通だろう。白いタンポポはきわめてめずらしいのかもしれない。だが、ドードー鳥(一六八一年絶滅)やタカノホシクサ(一九五〇年代に絶滅)、オレンジヒキガエル(一九九〇年絶滅)のように、シロバナタンポポは本当に絶滅種なのだろうか。
とにかくAさんの後を追って閉鎖病棟の裏へ回ると、目印の代わりに古バケツが置かれ、その脇になるほど白いタンポポがある。彼の言を信ずるならば、いきなりワライフクロウ(一九一四年絶滅)と出会ったようなドラマチックな話である。Aさんは「どうです!」と胸を張っているので、とりあえずわたしは「凄い発見ですねえ。植物のことは詳しくないんですけど、大変なものを見せていただいたようです。いや、ありがとうございました」と応じておいた。
あとで調べてみたら、シロバナタンポポは北海道以外の日本各地に点在しており、決して絶滅種ではない。また黄色いタンポポの突然変異でもない。ただし花粉には受精能力が欠け、卵細胞が発達して種子をつくるクローン植物だそうで、そういった意味では特異な花であるらしい。おそらくAさんはそのあたりを誤解して絶滅種と思い込んだのだろう。
と、そんな経緯はともかくとして、「絶滅したと言われるシロバナタンポポ」というフレーズはなんと驚異に満ちていることか。どれほど非日常的であることか。Aさんの単調で楽しみの少ない病院生活のなかへ突如登場した「絶滅したと言われるシロバナタンポポ」は、こちらの想像以上に彼へ甘美な興奮をもたらしたに違いない。
Aさんの誤解を笑うことは簡単である。だが絶滅という言葉がこれほどリアルに驚異を喚起した事実を、わたしは寿〈ことほ〉がずにはいられない。たったひとつの言葉がもたらすかけがえのない瞬間に立ち会えたと実感することで、わたしはまぎれもなく喜びを彼と共有したのである。
*
統合失調症で外来通院していたBさん(中年女性、生活保護を受けつつアパートに独り住まい)は、診察室の椅子に腰を掛けた途端にさまざまな悩みを次々に述べ立てる。寝つきが悪い、腰が痛い、毎日寂しいうえに退屈である、体重がちっとも減らない、アパートの隣人が大きな音でテレビをつけるのでイライラする、蛍光灯が切れかけている、今でもときおり幻聴が聞こえるが無視することは可能である等々。
そんなに困りごとがたくさんあっては大変でしょうということで、医療に関することはなんとかしましょうと処方箋を取り出すと、彼女は無表情のまま「いえ、処方はいつもと同じでいいです。薬は変えないでください」と主張する。それがいつものパターンなのである。
症状はあれこれ述べるのに、処方は現状を堅持することにこだわる。これは矛盾した態度ではないか。わたしにことさら同情や慰めの言葉を期待しているようでもない。
そんな次第でわたしはいつも同じ処方を出しつづけていたが、医師の立場としては居心地が悪い。自分はBさんの役に立っているのか、信頼されているのか、そういったところがちっとも見えてこないので不安だし気まずい。
ある日、ふと気がついた。彼女にとって外来を受診するという行為は、いわば日記をつける振る舞いに近いのではないか、と。日記の目的は人によって多種多様だろうが、わざわざ読み返したり何かに活用するというよりは「きちんと日記をつける」こと自体が最大の目的ではないだろうか。些細で取るに足らないことであろうとそれを記入することで日々の流れに区切りをつけ、明日という営みを続けていこうという一種の現状肯定に近い儀式としているのではないか。
おそらくBさんは日々の不満や困難をひととおり述べ、しかし「あれこれあったが明日も生活を継続していく自分がいる」と、日記をひっそりと書き込むような心持ちで外来を訪れているのではないか。
そう思いついたら、わたしは外来でBさんと向き合うことが楽になった。気まずさに悩まされなくなった。彼女が診察室に入ってきた途端、わたしは一冊の日記帳に変身する。「日記」という言葉が、当方の気持ちを整理してくれたのであった。(以上抜粋)
本書は二つのパートから成り立っている。すなわち前半が《臨床の詩学》、後半が《辺境の作法》である。
これらは互いに陽画/陰画の関係になっている。そして全体のテーマは、「精神科領域という特異な角度から、言葉やコミュニケーションや他者理解についてその意外性や突飛さや切実さを探る試み」ということになる。
前半の《臨床の詩学》においては、一見したところはコミュニケーションが成立していないように映るにもかかわらず、心の交流が起き得る不思議さや驚きに力点が置かれる。詩を中心とした文学作品を補助線として用いなければ語りきれない内容であるところに、それなりの興趣があるかもしれない。医療関係者のみならず「言葉」に関心を寄せるあらゆる人々に読んでいただければ嬉しいと思っている。
後半の《辺境の作法》では、特にパーソナリティ障害を中心に、表面的には言葉のやりとりが成立しているにもかかわらず心の交流が成り立たない不気味さや困惑に力点が置かれる。精神医療という世界の難しさを窺い知る端緒ともなり得れば、書き綴った甲斐があるというものである。
おそらく、前半には希望の光がちらほらと見え、後半には絶望や無力感の闇がうっすらと漂っているように感じられるのではないか。双方を心の中に同居させられなければ、精神科の臨床現場をつとめ上げていくことはできない。
*
それにしても、わたしは言葉に興味があるからこそ精神科医として生きていけるのだなあと、つくづく思うのである。
たとえばM病院に勤務していたときのことである。近道をするため、病棟に囲まれた中庭を斜めに突っ切っていたら、患者のAさんにいきなり声をかけられた。ちなみに彼の主治医はわたしではないが、何年も入院しているので顔見知りの関係ではある。Aさんは興奮した様子で語ってくる。
「先生、ぜひ来てください。絶滅したと言われるシロバナタンポポが、この病院に生えていたんです。発見したんです!」
たしかにタンポポは黄色が普通だろう。白いタンポポはきわめてめずらしいのかもしれない。だが、ドードー鳥(一六八一年絶滅)やタカノホシクサ(一九五〇年代に絶滅)、オレンジヒキガエル(一九九〇年絶滅)のように、シロバナタンポポは本当に絶滅種なのだろうか。
とにかくAさんの後を追って閉鎖病棟の裏へ回ると、目印の代わりに古バケツが置かれ、その脇になるほど白いタンポポがある。彼の言を信ずるならば、いきなりワライフクロウ(一九一四年絶滅)と出会ったようなドラマチックな話である。Aさんは「どうです!」と胸を張っているので、とりあえずわたしは「凄い発見ですねえ。植物のことは詳しくないんですけど、大変なものを見せていただいたようです。いや、ありがとうございました」と応じておいた。
あとで調べてみたら、シロバナタンポポは北海道以外の日本各地に点在しており、決して絶滅種ではない。また黄色いタンポポの突然変異でもない。ただし花粉には受精能力が欠け、卵細胞が発達して種子をつくるクローン植物だそうで、そういった意味では特異な花であるらしい。おそらくAさんはそのあたりを誤解して絶滅種と思い込んだのだろう。
と、そんな経緯はともかくとして、「絶滅したと言われるシロバナタンポポ」というフレーズはなんと驚異に満ちていることか。どれほど非日常的であることか。Aさんの単調で楽しみの少ない病院生活のなかへ突如登場した「絶滅したと言われるシロバナタンポポ」は、こちらの想像以上に彼へ甘美な興奮をもたらしたに違いない。
Aさんの誤解を笑うことは簡単である。だが絶滅という言葉がこれほどリアルに驚異を喚起した事実を、わたしは寿〈ことほ〉がずにはいられない。たったひとつの言葉がもたらすかけがえのない瞬間に立ち会えたと実感することで、わたしはまぎれもなく喜びを彼と共有したのである。
*
統合失調症で外来通院していたBさん(中年女性、生活保護を受けつつアパートに独り住まい)は、診察室の椅子に腰を掛けた途端にさまざまな悩みを次々に述べ立てる。寝つきが悪い、腰が痛い、毎日寂しいうえに退屈である、体重がちっとも減らない、アパートの隣人が大きな音でテレビをつけるのでイライラする、蛍光灯が切れかけている、今でもときおり幻聴が聞こえるが無視することは可能である等々。
そんなに困りごとがたくさんあっては大変でしょうということで、医療に関することはなんとかしましょうと処方箋を取り出すと、彼女は無表情のまま「いえ、処方はいつもと同じでいいです。薬は変えないでください」と主張する。それがいつものパターンなのである。
症状はあれこれ述べるのに、処方は現状を堅持することにこだわる。これは矛盾した態度ではないか。わたしにことさら同情や慰めの言葉を期待しているようでもない。
そんな次第でわたしはいつも同じ処方を出しつづけていたが、医師の立場としては居心地が悪い。自分はBさんの役に立っているのか、信頼されているのか、そういったところがちっとも見えてこないので不安だし気まずい。
ある日、ふと気がついた。彼女にとって外来を受診するという行為は、いわば日記をつける振る舞いに近いのではないか、と。日記の目的は人によって多種多様だろうが、わざわざ読み返したり何かに活用するというよりは「きちんと日記をつける」こと自体が最大の目的ではないだろうか。些細で取るに足らないことであろうとそれを記入することで日々の流れに区切りをつけ、明日という営みを続けていこうという一種の現状肯定に近い儀式としているのではないか。
おそらくBさんは日々の不満や困難をひととおり述べ、しかし「あれこれあったが明日も生活を継続していく自分がいる」と、日記をひっそりと書き込むような心持ちで外来を訪れているのではないか。
そう思いついたら、わたしは外来でBさんと向き合うことが楽になった。気まずさに悩まされなくなった。彼女が診察室に入ってきた途端、わたしは一冊の日記帳に変身する。「日記」という言葉が、当方の気持ちを整理してくれたのであった。(以上抜粋)
目次
開く
序 わたしが精神科医でいられる理由
I 臨床の詩学
苦戦中
ありありとしたイメージ
やさしい心
制御不能
ちっぽけな光景
不意の言葉
怪談
木と木々
救いの言葉
決壊
演歌的
パンの断面とミルクティー
II 辺境の作法
「精神科」というところ
「境界性パーソナリティ障害者」、この困った人たち
「反社会性パーソナリティ障害者」を忌み嫌うことは医療者として恥なのか
「躁病患者」を前にして腹立たしさを覚えるということ
「うつ病患者」の頭の中を知ると取るべき対応が見えてくる
「クレーマー」を生み出す言動、生み出さない言動
「家族」、歪んだ人の再生産装置
あとがき
I 臨床の詩学
苦戦中
ありありとしたイメージ
やさしい心
制御不能
ちっぽけな光景
不意の言葉
怪談
木と木々
救いの言葉
決壊
演歌的
パンの断面とミルクティー
II 辺境の作法
「精神科」というところ
「境界性パーソナリティ障害者」、この困った人たち
「反社会性パーソナリティ障害者」を忌み嫌うことは医療者として恥なのか
「躁病患者」を前にして腹立たしさを覚えるということ
「うつ病患者」の頭の中を知ると取るべき対応が見えてくる
「クレーマー」を生み出す言動、生み出さない言動
「家族」、歪んだ人の再生産装置
あとがき