【鼎談】社会不安障害と精神医学の課題 |
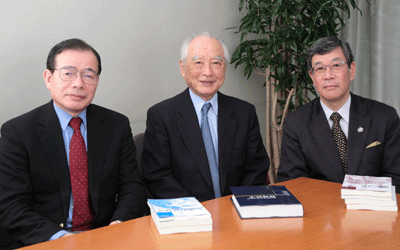 |
|
小山 司氏(北海道大学教授・精神医学分野)
笠原 嘉氏(名古屋大学名誉教授/桜クリニック院長) 田邉敬貴氏=司会(愛媛大学教授・脳とこころの医学) |
人前で話したり食事をする時に,強い不安や恐怖を感じ社会生活に支障をきたす――社会不安障害(social anxiety disorder:SAD)は,1980年米国精神医学会のDSM(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)-IIIで社会恐怖(social phobia)として取り上げられ,その後94年のDSM-IVでSADという名称が追加されている(診断基準は表参照)。米国の疫学データによるとSADの生涯有病率はおよそ13%,実に7-8人に1人が発症するとされている。
| 表 社会恐怖Social Phobia(社会不安障害Social Anxiety Disorder)の診断基準 | |
|
本紙では,田邉,笠原,小山の3氏にお集まりいただき,社会不安障害を中心に,強迫性障害,統合失調症をめぐる話題について,神経心理学,精神病理学,精神薬理学などの立場からお話しいただいた。
田邉 今回鼎談を企画したいきさつですが,最近,精神障害が重なるということで,コモビディティ(comorbidity)という概念がよく言われます。私は常々そのことに疑問を持っていました。最近取り上げられることの多い社会不安障害も社会不安障害とうつ病が併存するという言い方をします。対人恐怖や赤面恐怖の社会不安で患者さんが悩みだすと,当然うつ状態になります。それをコモビディティと呼んでいいのか。例えば統合失調症(schizophrenia)にしても,疾患単位として確立しているのか,ある意味非常に疑わしい部分があり,コモビディティという言い方に疑問を持つわけです。
先日,小山先生がオーガナイズされたある会で,私は上記のことを発言して,笠原先生にフォローしていただきました。懇親会の席で笠原先生と精神病理の話にもなり,どうせそういう話をするのなら,ということで『医学界新聞』に取り上げてもらうことになりました。笠原先生が精神病理,小山先生が精神薬理,私が神経心理と分野が違うので,3人で率直に意見交換したいと思います。
アメリカの「社会恐怖」と日本の「対人恐怖」
田邉 社会不安障害ですが,笠原先生の「アメリカには社会不安障害はほとんどなかったのに,いまやいっぱいある」というお話は,私自身「そんなものか」と勉強になりました。最初に,笠原先生から,社会不安障害と対人恐怖の関係についてお話しください。笠原 日本には対人恐怖症という名前で,1920年頃から森田正馬氏の研究ないし治療法の発表がありました。ただ,私は森田療法に関心を持ったのではなく,1970年頃に精神病と神経症の境界状態に関心を持ち,いろいろなケースを集めていました。その中に,体臭恐怖という自分の体から臭いが出て,それが皆にわかって,どこへ行っても噂されるという神経症か精神病かよくわからないケースがたくさんあり,対人恐怖症の重症型と分類していました。
1990年にAPA(米国精神医学会)のシンポジウムに「social phobia(社会恐怖)」が取り上げられ,そこで日本の話をするよう依頼されました。それで,アメリカへ行ったのですが,田邉先生に申し上げたのはその時の印象です。1980年のDSM-IIIにすでにsocial phobiaの概念はできていましたが,1990年のこのシンポジウムには聴衆はほんの少ししかいませんでした。ということは,その頃はsocial phobiaはアメリカの精神科医のあいだではまったくポピュラーでなかったと言えると思います。ところが,それから10年もしたら,アメリカ中にたくさんあると変わってしまった。この激変には公衆衛生学がおおいに関わったのではないかと思います。DSMやICD(国際疾病分類)は,公衆衛生の人にとても評判がいいですよね。「精神医学もようやく一人前の科学になったか」と(笑)。いずれにしても,ある時から突然アメリカに多い神経症になったわけです。
social phobiaという言葉をつくったのは,イギリスのMarksですが,Marksの言葉を入れてDSM-IIIにカテゴリーを作った途端に,「ある,ある」ということになったわけで,DSMの力はそういう意味では大きいです。何かの概念をきちんとつくれば,いたるところからそういうものが同定でき,どのくらいの数があるとか,たちどころにわかるようになる。それは,いままでのヨーロッパ風の診察室・病室中心の精神医学に完全に欠けていたことです。ですから,非常にプラスだったと思いますが,一方でいままでなかったものが突然出てくる,チェックリストによる今風の精神医学にあやふやさみたいなものも感じたわけで,そのことを田邉先生にお話ししました。
田邉 小山先生はいかがですか。
小山 私は1973年に入局しましたが,その頃教室では,笠原先生もご研究された自己臭恐怖の症例を100例ほど集めて,臨床精神医学的,記述的,了解的なアプローチで検討していました。ですから,DSM-IIIで「社会恐怖」という概念が出てきた時も,さほど違和感なく受け入れることができたのですが,問題は「社会恐怖」と日本の「対人恐怖」の間の微妙なニュアンスの違いです。それは,症状そのものが少し違うということもありますが,構造的に違うのではないかということです。日本の対人恐怖はどちらかというと相手に対して,「相手を傷つけるんじゃないか」「相手に嫌な思いをさせるんじゃないか」と他者配慮的であるのに対して,アメリカの社会恐怖は,「自分自身が公衆の前で恥ずかしい思いをするんじゃないか」と自己志向的で,自己の位置づけが違うという印象がありました。
笠原先生は,以前に対人恐怖を(1)青年期に一時的に見られるもの,(2)恐怖症段階に留まるもの,(3)関係妄想性を帯びているもの(重症対人恐怖),(4)前統合失調症症状,統合失調症回復期に見られるもの,の4型にお分けになっています。(3)の重症対人恐怖をDSMにあてはめて考えると,文化背景に基づいた妄想性障害で特定不能型という診断になり,社会恐怖に入らないということで,これからの国際的な議論の対象になるのではないかと思っています。
笠原先生は,社会不安障害を1つのスペクトラムのように位置づけ,その中に,隣接する病態として社会不安障害と対人恐怖を捉えていると理解していたのですが,それでよろしいですか。
笠原 そうですね。私のクリニックにも重症の人が来ます。先生がいまおっしゃった,第3型にあたるような妄想型の人が何人かいます。その中には,SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)で治る人と,非定型抗精神病薬を少し混ぜないと治らない人がいますが,いずれにしてもSSRIが必要な気がしています。
小山 そうなんです。治療反応性という側面から見ますと,いわゆる妄想性障害でも,見事に効果のある方がおられるんですね。ですから,私はそういう意味で,症状の重なりや治療反応性からいって,両者を社会不安障害なら社会不安障害,対人恐怖なら対人恐怖と同じカテゴリーに入れて検討していくのが妥当と思っています。
田邉 自己臭恐怖のように自分がほかの人に迷惑をかけると思うタイプと,社会に出て自分の中で緊張が高まるDSMの社会不安障害のタイプを比べると,SSRIの反応性としては,後者のほうが効果的な場合が多いという理解でいいですか。
小山 はい。DSMの社会不安障害の治療に関してはいくつものエビデンスがあります。しかし,いわゆる古典的な日本の対人恐怖に対する薬物反応性に関するエビデンスはきわめて乏しいのが現状です。
田邉 そうなると,自己臭恐怖に近いタイプは,アメリカでは社会不安障害に含めないのですか。
笠原 よくわかりませんが,結局,文化結合症候群(culture-bounds syndrome)であろうと言われてしまいます。
田邉 ということは,自己臭恐怖は,アメリカにはないということですか。
笠原 あまり記載はないんじゃないでしょうか。
田邉 向こうの人は,もともと体臭が強いからかなぁ。
笠原 いや,違うんじゃないかなぁ(笑)。そういう点は研究に値すると思うんですよ。だいたいshame(恥)という概念がちょっと違うでしょう。そういうことを,面白いと感じるか,感じないか。治療上必要と思うか思わないか。それは,これからの精神科医の治療的スタンスですね。
小山 総じて言えることは,欧米圏にはほとんどないということです。ヨーロッパ圏内では,赤面や視線恐怖はありそうですが,自己臭恐怖は日本,韓国あたりに限定されている,というのがだいたいのコンセンサスです。ですから,文化結合症候群的なところがあるんじゃないでしょうか。
局所か全体か
田邉 私は,強迫神経症あるいは強迫性障害と呼ばれるものは,ある意味で性格だと思っています。そういう性格的なものがコロッと変わるだろうかと常々疑問に思っています。ただ,私自身もSSRIが著効した強迫性障害の患者さんを経験していて,そうなると,本来の性格そのものは変わらないにしても,SSRIは不安を断つのかなという感じはしています。笠原 そうですね。それに関連して言えば,薬を使いながら診察室で不安症状が軽くなっていくのをみていると,不安の軽減と同時に万事に強迫性の「こだわり」が軽くなる。例えば万事に「まあ,いいか」と思える度合いが増えてくる。それは不安が減る当然の結果なのか,あるいは並行的に「楽しい」とか「面白い」という感じが少しずつ出てくることと同列の心理なのか。いずれにしても純粋な精神病理というよりは,薬と関係するもうちょっと脳に近い感じがする所見ではないか。
小山 確かに,環境とか対人関係とか,わだかまりの中で精神症状は形成されてきます。でも,なんとなく自分と環境,対人関係といったものの折り合いがついてくることが,安定期を迎える指標だと思うことがあります。
笠原 それを脳の局所で考えるか,もう少し全体的なレベルの,例えば心的エネルギー水準みたいな曖昧さを許容して考えるかという課題が,その向こうにあると思います。
田邉 「不安の回路」といわれているものについてはいかがですか。
小山 不安障害にいろいろな亜型が定義されてきましたが,不思議なことにSSRIが抗うつ薬として出てきてから,かなり幅広く不安障害全般に適応症を持つことになりました。ですから,現象としてのフェノタイプ(phenotype)は確かにそれぞれ違いがありますが,その基本には,進化の過程で形成されてきた心理生物学的な基盤があるはずです。進化は人類が環境に適応するために構築してきた脳のシステムといえます。扁桃体あたりをアラームシステムとして,それを中心とした不安の神経回路網というようなものがあるようです。
田邉 根幹にそういうものがあって,そこで何かが起こると,気分障害と言われている人はうつの症状が出て,強迫性障害の傾向を持っている人はその症状が出てくる。あるいは統合失調症の人であれば,幻覚,妄想が再燃しやすいとか,そういう可能性もありますね。
笠原 診察していていつも思うのですが,脳研究はうんと進んだが,診察室では脳の機能を直接にみる方法はまだない。直接みているのは依然として心理現象で,それもテスト・バッテリーを駆使して間接的にみた認知力ではなくて,より感情心理的なことがら,ヤスパースが100年前に言ったように,患者さんの言動の心理的了解的な文脈はどこまでか,その先は「説明」によるしかなく,脳のどこかとつながっている可能性がある,と考える程度でないか。
人格は変わるのか
笠原 いつも,神経心理の人に聞きたいと思いながら,なかなか機会がなかったんですが,精神医学というのは,あまりよくわからない,おおまかな概念を使うじゃないですか。例えば人格(パーソナリティ)という概念。特に私どもは,臨床をしていても,研究をしていても,人格からは片時も離れられない。例えば統合失調症で,脳の研究が非常にはかどったのは大変喜ぶべきですが,人格という言葉を深めるような知見は出てきませんね。田邉 もし人格というものが培われるのであれば,おそらく前頭葉が非常に関係しています。ただし,根幹にある本来の性格というものは,おそらくもっと大脳深部にある。人間の行動は前頭葉でいくらでも修飾可能です。認知症(dementia)になって前頭葉がやられてくると,ある意味で上品にボケる方と,非常に困った行動を取る方がいます。マナーがよくて,できた人間だと言われていた人が崩れたとすれば,それは崩れたのではなくて,そういうふうに修飾していたというか,装っていたのだと思います。
笠原 診察室で「この人をどうするか」という問題で,われわれがいちばん困るのは統合失調症の人格変化,それも軽い変化です。これをもう少し改善できれば,けっこう親というのは子どもの面倒をみてくれるわけです。精神科医より,はるかに彼らのほうがキープする力は強い。だけど,統合失調症特有の人の変わり方,これはやはり一緒に住んでいて耐えがたいところがあるようです。
どうしていまのアメリカの精神医学は,統合失調症の人格変化に言葉をついやさなくなったのか。要するに統合失調症の人格変化は認知の障害として説明しきれるのか。せいぜい,ソシウス(socius)から外れてしまうこと。彼らの持っている社会性が壊れる。だから,時には暴力にもなるし,引きこもりにもなる,くらいの説明はいるのでは?
田邉 だけど私は,それは「変わった」とは思いません。もともとその患者さんは,そういうものを持っていて,ある意味でそれをこらえて,修飾して生きてきたと思うのです。統合失調症の人は素朴な人が多いけれど,非常に困った行動を取る人も,粗暴になる人もいて,それは先生の言われるように「変化した」のではなく,私はそれが“地”ではないかと思います。
笠原 地が出てきたと。はあ,面白い考えですね。
田邉 これは証明のしようがないですが。
小山 その件に関して,私の意見は折衷的なものになります。はっきりしているのは発症前の適応能力がどうであったかが,その人の予後を決める因子としては,いちばん信頼のおけるものになっています。それから,アメリカで注目されているのは,ファースト・エピソードをいかに早期発見し,早期治療するか,また,そのことが病気の予後をどこまで改善するかということで,これについては大がかりなスタディがすでに始まっています。
その根柢にあるのは,シュープ(Schub)を繰り返すごとに,ニューロンのアポトーシスが惹起されて,器質的,形態的に微小な病変が起こってくるのではないか,そして,それが性格変化,予後の悪さにつながっていくのではないかという仮説です。そこでシュープのたびに起こるニューロンの障害をできるだけ防止して,それがアウトカムにどういう形でつながってくるかをみる,そういう仕事がなされているようです。
笠原 いままでの薬の中で,例えばオランザピンくらい,私の考えている「人格変化」を一時的なりとも改善する薬はない。その意味では,人格変化は脳の問題だと改めて思います。しかしながら,精神薬理学はその問題に神経心理学的局在を考えない。個々のニューロンの問題・変化であって,前頭葉でなくてもいいですが,どこかに人格というものの変化を顕著に引き出すような,あるいはそこをやられたら人格変化を起こすような,そういう局在を考えないのですか。
田邉 シュープの話になると,どちらかというとディフェクト(defect)的なものになってくるというのは,辺縁系領域を含めて変わってきていて,おそらく前頭葉とのコネクションでアクティビティが落ちてくると考えられるかなとは思うのですが。たしかに,オランザピンが非常に効く場合もありますが,逆にものすごく悪い場合もあります。だから,私は非定型抗精神病薬が出てきて,錐体外路症状が少ないのは非常に納得しますが,これでほんとうに統合失調症の症状の沈静化が全部できるかというと,まだまだそこまできていないと思います。
小山 最近,気分障害の領域でもそうですが,神経保護作用が言われています。炭酸リチウムやバルプロ酸にアポトーシスを防ぐ働きがあるということがわかってきたり,オランザピンやクエチアピンといった非定型抗精神病薬が,アポトーシスを防止するといったレポートも出てきています。ですから,笠原先生が日常観察されていることのバックグラウンドには,やはり何かがあると思います。
笠原 私は,脳の認知の問題ばかりでなく,もっと精神医学的な視点が必要と思います。統合失調症で何がディフェクトになるかというと,やはり社会とのつながりみたいなものが独特の崩れ方をするわけで,それが人格変化の特徴ではないかと思っています。
今後の課題
田邉 きょうの議論を踏まえて,今後の課題についてお話しください。笠原 私は昔から,脳の局所だけを考えるのはまずいのではないかと思っています。全体のエネルギーとか「これがちょっと落ちたから,こういうふうになった」「治ってきたのは-私の言葉でいうと-休息の効果がでてきた」とか,局所に何か薬が効いて治るというのもあるかもしれないですが,少しエネルギーを溜めてよくなるとか,複眼的にみないといけないと思います。冒頭に,田邉先生が言われたコモビディティも,二様三様の見方ができて,それが治療にむしろ役立つと私は思っております。
小山 私も,いまさらながら精神症状の成り立ちは複眼的にみていく必要があると思います。それを意識してベースにしていかなければいけません。いくら神経科学,薬理学,診断技術の進歩があっても,精神症状をいかに精緻に把握するかという,ヤスパースあたりまでの伝統を忘れてはいけないと思います。ヤスパースの記述的あるいは了解的なアプローチ,心の活動を全体的な関連の中で体験として把握していくという方法は,主観的であり時には非合理的であり時に誤ることもあるかもしれません。しかし,その試行錯誤の中により精緻化したものがあるわけで,それを伝承していくことは何も非科学的なことはなく,科学そのものであるわけです。
いまの精神医学についていちばん危惧するところは,病因論に基づいた分類にみっちり取り組んでいこうという流れが,まだまだ見えてこないところです。
笠原 内因なんてわかりにくいけど(笑),しかし,わかるとか,わからないというのが精神医学の診察室では,いまだに非常に大事なことなんです。そこを教える必要があるかと思います。
小山 きょうの議論にもありましたが,そういう状態を把握したうえで,この成り立ちは何なのか,どの神経回路網が関係しているのか,どういう伝達物質が関係しているのかということの試行錯誤をすること,そして治療薬がちょうどそのプローブのような形になるでしょうか。そういう日常臨床の積み重ねに,将来の精神医学の発展の希望があると思っています。
田邉 本日はありがとうございました。
| 田邉敬貴氏
1977年阪大卒。同附属病院を経て,86-87年スイス・ローザンヌ・ヴォドゥワ大留学。96年愛媛大教授。専門は神経心理学,とくに認知症。著書に『痴呆の症候学』『失語の症候学』(ともに医学書院〈神経心理学コレクション〉)など。 |
 |
| 笠原嘉氏
1952年京大卒。63年京大助教授(保健管理センター)を経て,72年名大教授,91年藤田保衛大教授。現在,名大名誉教授,桜クリニック院長。専門は精神病理学。著書に『軽症うつ病』(講談社),『精神病』『アパシー・シンドローム』(ともに岩波書店)など。 |
 |
| 小山司氏
1973年北大卒。同附属病院,市立旭川病院を経て,83-85年米国シカゴ大留学。85年米国ケースウエスタン・リザーブ大留学。87年北大助教授,93年同教授。専門は精神薬理学,神経内分泌学。著書に『臨床精神薬理ハンドブック』(医学書院),『社会不安障害治療のストラテジー』(先端医学社)など。 |
 |
