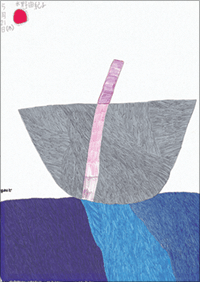| 【対談】 りゅうろ 流露する,アート 障害を持つ人の創作活動 |
|
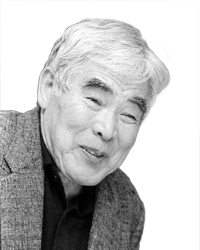 |
 |
| 吉永太市氏 元・知的障害者更生施設 「一麦寮」寮長 |
小出由紀子氏 インディペンダント・ キュレーター |
月刊誌『病院』では,ダウン症候群を持つ水野由紀子さんの作品を2006年の表紙絵として掲載している。細かい線を塗り重ねた独特のタッチ,大胆に二次元化した構図と非写実的な色使いが斬新で,その作品には不思議な魅力がある。
一般の人々や芸術家が,美術作品として制作するものと異なり,既成の価値観や制約に影響を受けない知的障害者が生み出す作品は,創作する喜びの中から人間の奥底にあるものが外に流れ出る,「内面の流露(りゅうろ)」だという。そのような作品に接した時,われわれは何を感じるのだろうか。
本対談では水野さんの絵をはじめ,欧米の「アール・ブリュット/アウトサイダー・アート」(注)を日本に紹介し,障害者の作品を新しい視点から紹介する活動をしてきた小出由紀子氏と,滋賀県にある一麦寮で創作活動を通じて先駆的な知的障害者教育を行ってきた吉永太市氏が,障害者による創作について語る。
| 注:フランス語で「生の芸術」を意味する。既存の美術教育を受けていない人々が,美術学校や画廊,美術館といった枠組みの外で自発的に生み出した美的所産。知的障害者・精神障害者らが生み出す芸術と同義ではないが,そうした人々の作品がアール・ブリュットとして評価を受けるケースも多い。 |
■戦後日本で始まった,障害者の創作活動
小出 私が初めて一麦寮にうかがったのは,たしか1993年だったと思います。当時アメリカで暮らしていて,アール・ブリュットやアウトサイダー・アートと呼ばれるジャンルの作品に,非常に興味を持っていました。それらは皆,欧米の作品だったのですが,日本にもそういうものはないかと思い,帰国のたびにリサーチをしていました。最初に訪ねたのは京都の「みずのき寮」という知的障害者の施設で,1964年から,寮生を対象にした絵画教育が行われていました。そこで絵を教えていらっしゃった画家の西垣籌一(ちゅういち)先生から,滋賀県に粘土を使った創作活動をしている画期的な施設があると聞き,一麦寮を訪ねたのです。
スイス・ローザンヌにあるアール・ブリュット収集館の学芸員から,ぜひ日本の作品で展覧会をやりたいという話もあったので,1997年にみずのき寮の絵と一麦寮をはじめとする,滋賀県内4つの施設の立体作品で「アート・インコグニト」という展覧会を行いました。その際,吉永先生には大変お世話になりました。吉永先生はもともと,近江学園という施設から一麦寮へ移られたんですよね。
吉永 はい。近江学園は戦後1946年,田村一二(いちじ),糸賀一雄,池田太郎の3人が設立した児童福祉施設で,知的障害児と養護児童,戦災孤児が中心でした。田村先生は知的障害児教育の草分け的な存在で,その啓蒙に尽くし,後に映画化もされた『手をつなぐ子ら』『茗荷村見聞記』などの小説を書いています。知的障害児の教育は学校だけでは限界があり,寝食をともにする生活施設が必要であると感じ,近江学園や一麦寮などでそれを実践しました。さらに,賢愚の差を越え,万人が水平に存在する理想郷「茗荷村」を希求し,提唱しています。
近江学園は児童施設であり,大きくなった子どもたちに対応する施設として1961年に一麦寮が設立されました。創設者の田村先生が初代寮長をされ,私は近江学園で1年間ほど訓練を受けた後,新設の一麦寮へ赴任しました。私が寮長を引き継いたのが1975年で,2000年まで務めました。
小出 粘土による創作活動を始めたきっかけは,何だったのでしょうか。
吉永 一麦寮が発足した時,近江学園だけでなく全国から子どもが集まってきました。創立時は15歳以上の男子50名を受け入れましたが,当時は他にあまり施設がなかったので,新設の一麦寮へ殺到してくるような状態でしたね。
ところがそういった子どもたちは,それまで社会との関係を絶たれ,家の中で幽閉されていたような状態で,急に施設という集団生活の,まったく違う生活環境の中に放り込まれたわけです。そのため新しい環境に戸惑い,気持ちが不安定になり,問題行動を起こしてしまう。毎日誰かが勝手に外出してしまうし,ガラスは日に40枚も割られました。ガラスが割れた窓にはベニヤ板で代わりをするのですが,ひと月もすると,どの部屋も真っ暗です(笑)。どうしたら落ち着いて生活できるかということが,課題でした。
そんな時,興奮したり何かで機嫌を損ねると必ず,泥が溜まった大きいドブへものすごい勢いで飛び込んでいく子どもがいたんです。そこで泥をこねまわしたり,体中に塗って泥の中にひそむようにしているのですが,30分ぐらいするとニコニコして機嫌よく出てくるのです。それを見ていて「母なる大地」という言葉がありますが,土には何か気持ちを癒してくれる作用があるのかなという気がしました。
田村先生は思ったことはすぐにやる人ですから,さっそく粘土室を作りました。子どもが土に対してどういう関係を持つか,その様をじっくりと見ようということで,制約も干渉もせずに土に触らせてみました。
小出 教えるのではなく,自由勝手にさせるわけですか。
吉永 はい,自由勝手にやってくれることを期待したのです。当時,「知的障害の人たちは自発的に何かできる人間ではない」というのが一般的な考え方で,障害者の自立を求めるよりも,いかに健常者に近づけるかが課題でした。そのため教育もいわゆる“水増し教育”,つまり健常者がやることの程度を低めて,何回も何回も繰り返して覚えさせるというものだったんですね。一麦寮では,そうした考え方に疑問を持っていました。子どもたちの自発性を引き出すためにも,子どものほうから何か起こしてくることに期待していたわけです。
そして実際に粘土に触れさせてみたところ,叩いたり延ばしたりするだけではなく,頭に塗りつけたり,食べたり,いろいろなことをする子どもがいました。小さい粒を床へ落として,積もっていく形を見て楽しむ子がいたり,上へ放り上げて,天井にくっついた粘土が乾いて落ちてくるのを何時間でも待っているという子がいたり(笑)。それは,まったく予想していなかった光景でした。
粘土は子どもたちの力を引き出すための非常によい媒体でした。彼らは自発的な力を発揮しうる,能力が劣っているのではなく,何かわれわれとは違う世界を持っているということに,気づかせてくれたのです。
■“流露”としての作品
小出 そうした一麦寮の姿勢は,今でこそ前進的だったと言えるのでしょうけれど,当時はずいぶん特異な考え方だったのではないかと思います。滋賀県は陶磁器産業が地場産業ですよね。普通であれば,同じ粘土を使うにしても,知的障害者に何か生産的な活動をさせようという考え方が出てくるのが自然だと思うんです。その環境の中で,あえて自発性を待たせることをお考えになったわけですよね。
吉永 たしかに当時としては画期的なことで,子どもから出てくるものを待つという指導姿勢は,まわりからはげしい非難を浴びたものです。そして,ずいぶん長い間,理解されずにきました。ただ,一麦寮へよく来ていた陶芸家の八木一夫先生は「干渉しない,誘導しない,すべてを子どもに委ねる」という方針に同感し,関心を持ち続けてくださいました。
私たちは,生産的なことはもとより,造形や美術ということすら,まったく意図していませんでした。ところが,活動を始めて1年もたっていない時に,その八木先生が「展覧会をしよう」ともちかけてこられました。私たちは美術とは「人に見せるものを美しく創る技術」と教えられていましたから,「こんな荒唐無稽な作品で展覧会ができますか」と驚いたのですが,「これは,やらないかん。こんなにすごいものは他にない」「よくよく見ろ。この作品はものを言っている,息遣いが聞こえる」と八木先生は積極的でした。それに田村先生も同意され,「一般の芸術家は制作という過程をとるが,この子どもたちは内面の流露という過程をとる」として,“流露”という言葉を使われたのです。
流露とは,何かを写そうとしたり,人に見せることを意図せず,人間の根源から無垢な心情が流れ出てくることです。そしてそれは,子どもたちが本当に創作を楽しんだ時に出てくるものであって,その流露の結果を見て,われわれは非常に安らかな気持ちになったり,あるいは恐ろしさや悲しみを感じたりします。「この流露がすばらしいのだ,これこそが芸術なのだ」と田村先生はおっしゃっていたわけです。
小出 八木一夫といえば,戦後日本を代表する前衛作家で,美と伝統にがんじがらめになった陶芸を,土と火の原点に還って探究したアーチストです。八木さんのような方が,精神的指導者としてかかわっておられたのですね。展覧会はなさったのですか?
吉永 第1回目は,1966年に大阪の阪神百貨店で行いました。多くの方が来てくださり,作品の7割が売れてしまったんです。とにかく皆さん,喜んで見てくれまして,びっくりしました。それ以降の展覧会でも,美術関係ではない一般の人が高く評価してくれ,われわれの目を開くきっかけをくれたと考えています。
また,1969年には東京の八重洲でも「あざみ寮」という別の知的障害者更正施設の織物作品と合同で展覧会を開催し,その後も毎年何回か開催しました。その中でも強く印象に残っていることですが,1978年に東京で展覧会をやった時,ある男性が作品の前で「ワッハッハ」と大きな声で笑うんです。そして一度出ていったかと思うとまた戻ってきて,さっきと同じように1つずつ作品を見ては「ワッハッハ」と笑う。「いったい何者だろう」と思っていたら,1週間ほど後にテレビにその人が出てきて,書家の井上有一氏であることがわかりました。こうしたことがあって,「これらの作品には,人に何かを与える力があるんだな」と確信を深めるようになったのです。
人間の創造の原点
小出 私も一麦寮の作品を見ていて,そうした力を感じます。笑いを誘うだけでなく,人間のこころの内奥にある,暗いものや本能的なものを感じさせる作品もありますね。例えば吉田修三さんの作品(図1)は,アフリカやオセアニアの部族の人たちが作るマスクやトーテムなどのように原始的でシンボリックな感じがしますね。こうしたものがいったい彼のどこから出てくるのか,とても興味があります。一麦寮の姉妹施設である,「もみじ寮・あざみ寮」の藤関美佐枝さんの作品(図2)は,大きな壷に粘土の粒を根気よく貼り付けていくという行為の反復からできています。女性の再生願望,増殖本能が視覚化されているようで,現代美術作家の草間弥生さんの仕事などを彷彿とします。これらは意図して制作された美術作品ではないけれど,人間が創造したり表現したりする,その原点を照らしてくれるものなのだと思います。本当に,人によって出てくるもの,流露してくるものは異なり,創造をめぐる謎の深さに魅入られてしまいます。
 |
 |
■楽しい驚きに魅せられる,水野さんの作品
小出 今回『病院』誌の表紙絵を描かれた水野由紀子さんと私が出会ったのは2003年です。(財)日本ダウン症協会から,展覧会を開催したいと,私に企画の依頼がありました。全国のダウン症候群を持つ成人の方で,長く創作活動を続けている8名の作品を紹介することになり,水野さんもそのひとりでした。
水野さんは自宅で暮らしておられ,小さい頃から絵を描くのが好きだったそうです。今でも毎晩,夕食後に居間で絵を描いています。
吉永 細かく並べられたペンのタッチが変化に富んでいて,独特の量感と触感がありますね。これは,現代のファッションでしょうか(図3)。単純な形と色で塗り分けられていますが,絶妙な統一感があります。
小出 実はこの絵は,皇太子殿下とのご婚約が発表された雅子様を描いたものなんです。
吉永 なんと。幸福感や喜びに満ちていますね。次の絵(図4),これは何を描いたものでしょう。ストローがガラスの器に立っている? 光が物に反射して生まれる,不思議で微妙な変化が丹念に描き分けられていますね。大胆な形と細かく描き込まれた細部が作品に力を与えています。
小出 これは榊原郁恵さんが主演したミュージカル『ピーター・パン』に登場する船を描いたものです。このように,対象が思いがけない色と形で再現されていて,驚きがあります。他の作品も,これは何を描いたんだろうと想像して,わくわくしながら見ることができます。
|
|
生活リズムの中に自発的な創作が生まれる
吉永 一麦寮の子どもたちは,粘土をいじっていると口数が少なくなって,まるで儀式のような,緊張した雰囲気が漂い始めます。彼らは夜パジャマに着替えてからでも粘土室にやってきます。ひとたび興が乗ると,作品を完成させるまで,3日間寝ずにやった人もいます。もっとも,その後3日間寝ていましたが(笑)。
寮の先生たちからは,常軌を逸しているとずいぶん怒られましたが,止められるものでもありません。彼らの創作活動を見ていると,それほどに人間の奥底の何かがあふれるように外へ出てくる感じがしていました。
小出 吉永先生がおっしゃったような環境は,他にはそうありませんよね。同じように創作活動をしている施設でも,何曜日の,何時から何時までと決まっていたりします。何度か一麦寮へお邪魔しましたが,あまり制約のない暮らしぶりは印象的でした。
吉永 彼らは各々に,生活の中に「いま粘土に触れたい」という瞬間があるんです。私たちは24時間彼らを見ているから,それを察知して粘土室へ誘うことができました。通所の作業所のようなところでは,生活全体を見ることができない。だから学校での図工の時間のように「この時間は粘土をしましょう」とならざるを得ないかもしれません。ですが,子どもたちの生活リズムの中に,自然に創作活動が入っていくようでないと,自発的な創作活動はできないように思うんです。朝起きてすぐ始める子どももいます。
小出 水野さんも晩ご飯が終わると,当然のように座って絵を描き始めます。創作活動というより,家事のような感じですね。食器を片づけたり,洗濯物を畳むのと同じレベルの仕事という印象を受けます。水野さんにも,生活のリズムとして創作する時間があるということですね。
「芸術家の家」の取り組み
小出 知的障害と精神障害の違いを認識する必要はありますが,オーストリアのウィーン郊外にあるグギング精神病院の敷地内には「芸術家の家」という画期的な施設があります。精神病の患者さんで,創作活動に興味を持っている人,あるいは才能があると思われる人,15人ほどを集めて共同生活をしています。1人ひとりに個室があり,行動は基本的に自由です。自分の部屋で描きたくない人は,共同アトリエで描く。治療や指導ではなく,自主性を尊重して,その人のペースで生活の中で創作することを目的としています。
施設の運営や材料費には,作品の売買収益も充てられていて,彼らのもつ能力を活かして,社会とのかかわりを手助けすることにもなっています。世界でもそこが唯一の施設ですが,日本でも,こうした施設ができたらと思います。
吉永 ただ私は,「芸術家の家」が理想かというと,必ずしもそうは言えないのではないかと思います。芸術家として生活を保障され,自由に表現できる場を与えられたとしても,それがただちに自由な創作活動につながるとは思えません。生活のさまざまな場面で感じる高揚感といったような,その人の生活リズムの中から自然に出てくるものから,流露としての作品が生まれてくるのではないでしょうか。必要なのは実生活を通して,豊かな体験をすることだと思います。
また,優れた人を選抜して援助するという点についても,創作活動を限られた人に限定するのは不自然に思われます。もともと,創造活動には,すべての人が参加してよいはずですし,その中に優劣もないはずです。
小出 個人主義が徹底している背景もありますが,「芸術家の家」を創設したレオ・ナブラティル博士は芸術的造詣の深い精神科医で,1950年代から「精神病と芸術」というテーマを探究してきた人です。ですから,芸術としての創作活動の支援であって,一麦寮で行われている,教育としての取り組みとは目的が異なると思います。
私自身は,これまで多くの作品を見てきて,制作を意図しない「流露」であっても,個人によって資質の違いがあると思います。創作に向かうエネルギーの高さ,表現の深さや強さ,造形的感覚などです。
■流露するアートに触れる
小出 障害を持つ人が自発的に創作する場を維持していくには,吉永先生のような現場の方たちの理解と努力はもちろん,こうした活動の存在を外部の人に知ってもらうこと,PRしていくことも大事だと思います。
それがあってはじめて,私たちはこうした作品の存在を知ることができるわけです。知られることがなければ,残念なことに,そして過去そうだったように,消滅していってしまうことが非常に多いと思います。
吉永 そうですね。彼らが創造した新しい世界を,ぜひとも知っていただきたいと思います。創造の喜びを共有してもらうことは大切で,そのためにも人々の目に触れる機会は多いほうがよいのです。ただ残念ながら,日常の仕事に追われて私たちには余力がなかったのも事実です。
一麦寮では「展覧会のために作品を作れ」と寮生に言っているわけではありません。しかし,展覧会が迫って教師たちが作品の焼成などに忙しくしていると,そうした雰囲気に誘われてか,作品制作に励む寮生も出ていました。作る雰囲気を醸成することにもなっています。
それと,展覧会は作品が溜まるのを防いでくれます(笑)。おびただしい数の作品ができて保管場所に困るのですが,大切な作品ですから潰すわけにもいきません。展覧会で作品が売れるならば,これがもう1つの効用です。
展覧会も重要ですが,何といっても作ることが重要です。彼らはただ粘土の感触に陶酔し,無垢な心象を粘土に託して,自在にひねり,無心に遊び,土と一体になる。そこに喜びがあるのです。それらの作品に接した時,われわれは雑念を切り捨てられないでいる人間の表層を打ち崩してくれるような,人間の奥底にあるおおらかさやのびやかさ,言いようのない寂しさなどをひっくるめた内面の流露に触れることができるのです。
小出 昨年開催したアール・ブリュットの展覧会では,精神障害,知的障害を持つ人たちも含め,59人の作品を紹介したのですが,若い人たちを中心に大きな反響がありました。感受性がみずみずしい若い人たちは,そこに自分自身にも通底する何かを見出したようです。今後も積極的に,こうした活動を続けていきたいと思います。本日はありがとうございました。
今回の対談紙面では,モノクロでしかご紹介できませんが,ぜひ一度『病院』誌を手に取っていただいて,水野さんの作品をご鑑賞ください。また,弊社ホームページでも本記事をカラーでご覧いただけます。読者の皆さまには,ぜひ水野さんの流露としての作品を,1年間味わっていただければと思います。
(週刊医学界新聞編集室)
吉永太市氏(よしながたいち)
元・知的障害者更生施設「一麦寮」寮長。知的障害者の自由で創造的な人格育成の手段として,粘土を使っての創作活動に長年取り組み,早くより,その作品展を全国的に開催。先駆的指導者として現在も幅広く活動している。
小出由紀子氏(こいでゆきこ)
早稲田大卒。資生堂勤務を経てインディペンダント・キュレーター。欧米のアール・ブリュット,アウトサイダー・アートを日本に紹介するとともに,日本の知的障害者の創作を新しい視点から見直すべく,多くの展覧会や出版物を手がけてきた。昨年は,ハウス・オブ・シセイドウで開かれた「Passion and Action生の芸術―アール・ブリュット展」を企画。