新春随想
2006
脳科学の夢
金澤一郎(国立精神・神経センター総長)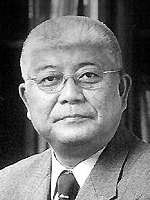 脳の科学が,近頃特に注目されていると感じる。私自身がその分野に身を置いているせいかと思うと,どうもそれだけではないらしい。まったく別分野の研究者から,同じような感想を何度も聞いたからだ。この場合は,多少では済みそうにない「やっかみ」も含めてではあるが……。それでも,他分野から嫉妬されるほど,今,脳科学が輝いていることは間違いないだろう。
脳の科学が,近頃特に注目されていると感じる。私自身がその分野に身を置いているせいかと思うと,どうもそれだけではないらしい。まったく別分野の研究者から,同じような感想を何度も聞いたからだ。この場合は,多少では済みそうにない「やっかみ」も含めてではあるが……。それでも,他分野から嫉妬されるほど,今,脳科学が輝いていることは間違いないだろう。
こんな話を耳にした。ある研究者が脳科学の面白い洋書の訳本を出そうと出版社に持ち込んだところ,「脳科学の本は多すぎますからね。これはという特徴がないとダメですよ」と言われたという。時実利彦先生が,一般の人たちに脳のことをもっと知ってもらう必要があると決心されて,1962年に岩波新書から『脳の話』を出版された。その時は,一部の研究者から一般書を書くなど研究者にあるまじき行為だと批判されたという。今はそんな時代がむしろ懐かしいほど,一般書としての「脳の話」は氾濫しているということか。確かに,学問的には必ずしも確定していないことを,わかりやすく耳当たりがよいというだけで,あたかも正しいことのように,商業主義の甘い言葉に乗せられる人もいるようだ。「こうすれば頭がよくなる」などのキャッチフレーズは,「こうすれば楽に痩せられる」「こうすれば健康でいられる」といったヤセ薬や健康食品の宣伝と同じで品格がない。われわれ研究者は心しないといけない。
ところで,学問的にはわれわれは何をめざしているのだろうか? 例えば,人間が人間らしく生きている原理に対して,現在使える道具(検査・研究機器)を用いて,現在使える方法(測定法・検出法など)を適応し,その本質に迫ることが1つであろう。特に脳科学では,「ある脳機能(例えば言語)に対して,脳のどの領域のどのニューロンが,どの分子を使ってどの分子群のサポートを得ながらその機能を果たしているか,について生きている脳で明らかにする」といったイメージがある。これは1つの夢であろう。
一方で,「大脳のニューロン群の電気的活動を脳の外に誘導し,コンピュータ処理しその中から有効情報を抽出し,体外の『機器』を動かす」という研究の方向がある。実際に米国を中心に進んでいるが,臨床応用できる時が来れば身体障害者には大いなる福音になるだろう。これも1つの夢であるが,実現の可能性があるような気がする。
最後が脳の病気の克服であり,最近解明されたヒトゲノムの知識の上に立った創薬も夢ではなくなっている。それもあるが,私はむしろ近年大いに発達してきたRNAiに期待を寄せている。悪いことをする遺伝子の発現を選択的に抑制するこの方法が,臨床的に利用できるかも知れない期待に胸を膨らませている。かつては不可能の一言であった遺伝病(すべてではないが)の治療も,こうした分子を脳内に確実に届ける方法を確立すれば,夢ではなくなると思っている。新しい年がこうした夢実現への確実な一歩を踏み出す年でありますようにと祈っている。
心の原点
中田 力(新潟大学統合脳機能研究センター・センター長) 白川静博士の言を借りるまでもなく,古代日本を築いた人々が商(殷)王朝文化の継承者であったことは,間違いないようである。漢字を生み出し,アジア文化の祖となる中国古典文化を作り上げた商王朝は,神権政治の国家であった。古代エジプト王朝にも似たこの組織は,自然の中の人間という存在をはっきりと意識した,ある意味,融和を求める優しい心の文化が生み出したものである。神がまだ人々を支配する存在ではなく,単に母なる自然の代弁者だった,古き,良き,時代である。そして,そこから医療が生まれた。
白川静博士の言を借りるまでもなく,古代日本を築いた人々が商(殷)王朝文化の継承者であったことは,間違いないようである。漢字を生み出し,アジア文化の祖となる中国古典文化を作り上げた商王朝は,神権政治の国家であった。古代エジプト王朝にも似たこの組織は,自然の中の人間という存在をはっきりと意識した,ある意味,融和を求める優しい心の文化が生み出したものである。神がまだ人々を支配する存在ではなく,単に母なる自然の代弁者だった,古き,良き,時代である。そして,そこから医療が生まれた。
神の国を滅ぼした交戦的な周王朝ですら穏健に見えるほど,世界は,更なる戦いの時代へと移行する。始皇帝の時代を生き抜き,漢の建国でわずかに蘇った古典文化も,力だけがすべてであるとする圧倒的な時代の流れに逆らうことはできず,遂には,征服者の前に跪くこととなった。それでも,人々が信じた心の原点は消え去ることはなく,今でも,内なる心そのものに息づいている。日本という国家は,もともと,この,優しさの古典文化を守り続けた民が開いた国家なのである。時代こそ違い,実は,アメリカという国家の建設も,同じような人々が新天地を求めて旅立ったことに始まる。
より高い刺激を求めるメディアに圧倒されて,どうしても超近代的な側面ばかりが強調されがちなアメリカ医学ではあるが,本当の意味でアメリカ医学を支えているのは,底辺の医療を守る,報道されない人々である。民主主義が老化し,優しさが風化したアメリカという国家で,何故か,人々と共に歩む医療の原点は,しっかりと根付いているのである。優しい日本にできないわけがない。
表面的なアメリカ文化ばかりを模倣し続け,空虚なマネーゲームが横行するようになってしまった現代社会では,医学にも科学にも,うまく立ち回ろうとする詐欺師たちがうごめいている。心の汚い人たちが,絶望的なまでに社会の中心を占めてしまった現実の中で,人々の切なる叫びは,傲慢な笑い声にかき消されている。それでも,心の原点が消え去ってしまったわけではない。医療とは,心の故郷を求める声に,眠れない夜を過ごす人たちがたどり着く場所である。人間が好きで,性善説を捨てきれず,勝つことも負けることも嫌いで,そのくせ,人の温もりを求めている,そんな人間たちだけが集まって来れば良い世界なのである。
変革期の診療情報
阿南 誠(国立病院機構九州医療センター企画課専門職/医療情報部診療情報管理室長・診療情報管理士指導者) 2005年の初頭は,4月から全面施行される「個人情報保護法」に備え,連日の議論を重ねていたことが思い出される。恐らく歴史的に,わが国の診療録(以下,より広い意味で,「診療情報」という表現を用いる)に関しての初めての本格的議論であったと思う。
2005年の初頭は,4月から全面施行される「個人情報保護法」に備え,連日の議論を重ねていたことが思い出される。恐らく歴史的に,わが国の診療録(以下,より広い意味で,「診療情報」という表現を用いる)に関しての初めての本格的議論であったと思う。
従来から,診療情報管理士や病院管理者を中心とした一部の医師は,その重要性について,日本診療録管理学会等を舞台に果てしない議論を重ねてきた。しかし,今回のように病院が一丸となり,「職員教育」が末端の職員にまで至ったことは,間違いなく初めてである。とはいうものの,個人情報保護法への対応は,診療情報の重要性を本当に医療者に理解させたのだろうか。法律の全面施行からいくらも経たないうちに,喉元過ぎれば何とやら,とならないように厳しく捉えなければいけない。たとえ医療者が忘れても,国民(患者さん)は法律の全面施行でその重要性を学び,過去に逆戻りはしないことを強く意識すべきであろう。
また,2005年はDPCへの関心が高騰したという意味でも忘れられない年となった。小泉首相もDPCの拡大を示唆し,DPC制度は急性期医療の中で生き残りをかける医療機関にとって対応すべき課題となっている。
DPC制度は,「診療情報管理」を診療報酬制度という分野に持ち込むものである。診療情報を適切に管理し,利活用する能力があるのか,すなわち診療情報管理能力が問われている。そして成功の鍵は,診療情報管理にかかわる人材の能力次第であると言っても過言ではないであろう。以上のように診療情報管理にかかわる者にとっては,この2つの課題に対応していくことが急務であり,重要な責務である。
これらの課題は,医療機関の存続さえもかけたハードルである。2006年に向け,われわれ診療情報管理士は,医療機関の存続という重責を担っていると考えなければならない。
ホスピス・緩和ケアの教育・研修の充実をめざして
恒藤 暁(大阪大学助教授・人間科学研究科) 私がホスピス・緩和ケアに従事してから約20年が経過しました。この間を振り返ってみると隔世の感があります。20年前に私が淀川キリスト教病院ホスピスで勤務することを決めた時に,ある方は私のことを思って「ホスピスのように“麻薬漬け”するようなところには行くな」と止めました。また別の方は「末期ケアは医師の仕事ではない」「治らない患者に医療費を使うのは無駄遣いである」と言われました。当時はホスピス・緩和ケアに対して誤解と偏見が強くあり,ホスピス・緩和ケア医は奇人・変人扱いされていました。
私がホスピス・緩和ケアに従事してから約20年が経過しました。この間を振り返ってみると隔世の感があります。20年前に私が淀川キリスト教病院ホスピスで勤務することを決めた時に,ある方は私のことを思って「ホスピスのように“麻薬漬け”するようなところには行くな」と止めました。また別の方は「末期ケアは医師の仕事ではない」「治らない患者に医療費を使うのは無駄遣いである」と言われました。当時はホスピス・緩和ケアに対して誤解と偏見が強くあり,ホスピス・緩和ケア医は奇人・変人扱いされていました。
1990年4月にホスピス・緩和ケアが医療保険の診療項目として正式に制度化され,「緩和ケア病棟入院料」という診療報酬項目が新設されました。許認可を受けたホスピス・緩和ケア病棟で行われるホスピス・緩和ケアに対して,定額の医療費が支払われる制度です。この制度の導入により2005年12月現在,ホスピス・緩和ケア病棟は152施設,2848病床となりました。
また,2002年4月に診療報酬項目として「緩和ケア診療加算」が新設されてから,随所で緩和ケアチームの活動が始動しており,緩和ケア診療加算届出受理施設(一定の条件を満たす緩和ケアチームが設置されている施設)は,2005年6月現在,49施設となっています。また,大学病院を対象とした調査では,30施設に緩和ケアチームがすでに存在し,「2年以内に設立の予定がある」と回答したものは9施設でした。
さらに1996年7月に日本緩和医療学会(http://www.jspm.ne.jp)が創立され,2005年11月現在,学会員数は約4000名に増加し,研究や教育への取り組みが活発になってきています。
私がホスピスで働くことに反対された方に,数年前久しぶりにお会いした時に「本当によい選択をした」とお褒めの言葉を頂戴し,嬉しく思いました。
今後,わが国でのホスピス・緩和ケアの教育・研修の充実がますます必要になります。そのために微力ながら励んでいきたいと強く願っています。
リハビリテーションの質
園田 茂(藤田保健衛生大学七栗サナトリウム・病院長)
リハビリの位置づけ
今改めてリハビリテーション(以下,リハビリ)の位置づけを確認してみたい。リハビリは神経系や骨関節系など臓器レベルの診断・治療とともに,日常生活動作など障害(能力)への対応を重視する医療である。臓器への治療を縦糸とすればリハビリは横糸である。
そのリハビリの質が問われている。医療でも介護でも「リハビリ」はしばしば登場するものの,具体的内容が不明確である。手足を動かしさえすればリハビリなのではない。評価し,必要な内容を選択実行して初めてリハビリである。しかし,この判断を担うべき専門医は全国で1100名しかいない。また,集中的なリハビリを行うための回復期リハビリ病棟の病床数は全国で3万床に留まり,病棟スペックも規定下限の療法士数(3名)で行われるケースがかなりある。
リハビリ医療に必要な知識
身体の動作を理解し,どの部分が問題なのか判断するために,リハビリでは機能解剖や運動学を駆使する。また習っていない新たな動作をできるようにする意味では運動学習・コーチングの知識が必要である。この運動学習の視点から,休日にリハビリを休むより週7日リハビリをした方が,医療効果が高くなることが推察できる。実際,七栗サナトリウムでは週7日,一日中のFIT programにより脳卒中リハビリの治療効率を高めることに成功した。
また,脳卒中片麻痺の患者の麻痺していない手を抑制することにより麻痺側の使用頻度を増やし麻痺改善を図る,脊髄損傷者の懸垂式トレッドミル歩行訓練など新たな治療手段も開発されてきている。
リハビリへの期待と限界
リハビリで達成できることには限界がある。急性期治療の区切りに「治療は終わりました。後はリハビリです」と家族や本人に説明して,リハビリをすれば完治するとの幻想を与えないでほしい。リハビリは運動麻痺のある程度の改善,廃用症候群の改善,障害が残るなりの動作のしかたの習得を主目的としている。認知障害があれば運動学習が妨げられ到達レベルが下がることも知っておいてほしい。
電子カルテシステムの新しい目覚め
今田光一(黒部市民病院関節スポーツ外科/富山大学臨床教授) 電子カルテシステムをはじめとした医療ITが,ついに大きく覚醒しようとしている。本邦でオーダリングシステムの延長として出現した電子カルテシステムは,初期に導入した医療機関では,機能的にも費用対効果の面でも決して評判がよいと言えなかった。しかしここ数年,医療業務の理解が徐々に進み,本当に必要な機能とは何か,という点について各ベンダーと医療者が協働して開発を進めていく環境ができあがりつつある。
電子カルテシステムをはじめとした医療ITが,ついに大きく覚醒しようとしている。本邦でオーダリングシステムの延長として出現した電子カルテシステムは,初期に導入した医療機関では,機能的にも費用対効果の面でも決して評判がよいと言えなかった。しかしここ数年,医療業務の理解が徐々に進み,本当に必要な機能とは何か,という点について各ベンダーと医療者が協働して開発を進めていく環境ができあがりつつある。
医療機関のIT化は,他の業種とは違い,ユーザー(医療者)に加えて,ユーザーとともに情報を欲する2次ユーザー(患者)をも満足させなければならないという使命を帯びている。この点が,医療という分野が工業的なプロセス管理だけでは到底網羅できない一因でもある。これは教育分野やエンターテイメントにおけるIT化と共通するものがある。
かつてウルトラマンなどの特撮でしか見ることができなかった「画像付携帯電話」が現実のものとなり,情報の時間・空間同一性が著しい速度で進歩している時勢ではあるが,アナログで行っていた基本業務のすべてが必ずしもデジタルでは行えないことも随分わかってきた。
急激に進んだ医療IT化は,「患者から離れたところでも患者のことがわかる」点に重点を置きすぎた。しかし,ベッドサイドにモニターがあるからといって,スタッフによる患者への説明や声かけを省略できるわけではない。執刀医が手術日の朝に顔を見に来てくれると患者が安心するのは今も昔も変わらない。
IT化することで,急に手術や検査技術がうまくなったり,医療者が優しくなったりするわけではない。些細なことを見逃さない第六感を養ったり,技術の研鑽や,患者を安心させようとする努力が必要なのは当然のことである。医療におけるITの便利さとその限界を充分に理解し,IT化の役割を充分に発揮させることができれば,医療の原点である「ヒューマンコンタクト」を見出すことができるようになるだろう。
クリニカルパスが多くの病院で作成され,患者にも一般的に知られるようになってきた。かつては標準化という言葉と画一化という言葉が混同され,パスがあたかも「この通りにしなければならないスケジュール」と誤解されていた。
IT化,標準化は,個別性に対してより的確に丁寧に対応するための手段である。
医療というデリケートな分野の質を上げるには,多くの分野とのコラボレーションが必要であり,電子カルテシステムを作り上げることはその1つの凝縮系だ。どれだけの英知と経験がそこに組み込めるか? その覚醒が今広がりつつあることに対して,期待を持って迎えたい。


