新連載 | |
ディジーズ・マネジメントとは何か?第1回 ディジーズ・マネジメントとは | |
| 坂巻弘之 | 医療経済研究機構研究部長 |
| 森山美知子 | 広島大学医学部教授・臨床看護学 |
はじめに
欧米先進諸国の保健医療政策において,共通した課題として医療コストの高騰がとりざたされている。そのような状況を克服するための新たな取り組みとして注目されているのがディジーズ・マネジメント(Disease Management)である。ディジーズ・マネジメントの概念は米国の健康保険プランで生まれてきたものであるが,現在では,英国,ドイツ,オーストラリア,シンガポールなど,欧米にとどまらず,各国で導入が試みられている。ディジーズ・マネジメントが目標とするものは,特定の疾患について診療ガイドラインをベースに,医療提供者,患者,住民への働きかけを行ない,保健医療コストのコントロールとサービスの質の向上を実現しようとするものである。
わが国においても,保健医療コストのコントロールは重要な課題であるが,診療報酬点数の操作などの医療費コントロール策だけでは,コストコントロールと質の向上を同時に達成することは困難であり,生活習慣病の増加にあわせ,個別疾患に焦点を当てたディジーズ・マネジメントへの関心が高まってきている。そこで,本シリーズでは,ディジーズ・マネジメントの概念,プロセス,諸外国ならびにわが国における取り組みなどについて解説していくこととする。
ディジーズ・マネジメントの定義とは
ディジーズ・マネジメントには,さまざまな定義があり,目的と対象によってその内容は若干異なっている。表に定義のいくつかを示した。これらの定義の多くは,特定の疾病(特に慢性疾患)の重症化予防に焦点を当てたものが多いが,定義者の関心領域により範囲やアプローチはかなり異なっている。例えば,1次予防にフォーカスを当て健康増進や健康教育に重点をおくものや,日常生活や受診行動に大きな問題を抱える患者に対する個別介入を行なうケースマネジメントに重点をおいたものもある。そこで,近年,こうした1次予防から集団に対する介入を行なう狭義の意味でのディジーズ・マネジメントやケースマネジメントまでを包含したものを広い意味でのディジーズ・マネジメントとして,これを集団健康マネジメント(Population Health Management)と呼ぶこともある1)。ディジーズ・マネジメントのコア
DMAAでは,ディジーズ・マネジメントのコアコンポーネントとして以下の6つをあげている。(1)集団特定プロセス
(2)エビデンスに基づく診療ガイドライン
(3)医師とサポートサービス提供者の連携による診療モデル
(4)患者自己管理のための教育・啓発
(5)プロセスとアウトカムの計測,評価ならびにマネジメント
(6)定期的な報告とフィードバック
これらのコンポーネントは,品質管理のPlan-Do-Check-Action(PDCA)サイクルの考え方をもとに整理することができる。すなわち,まず集団のリスク評価をもとに介入すべき対象を明らかにする「現状分析・目標設定」のコア(Plan),目標を達成するために,実施ガイドラインをもとにした医療関係者への教育ツール・患者啓発ツールの作成と医療現場での周知徹底を行なう「介入」のコア(Do),そしてプログラムの成果の「分析・評価」コア(Check)であり,評価結果は目標へフィードバックされ(Action),継続的改善につなげてゆく。このプロセスにツールを重ねたものが図である。
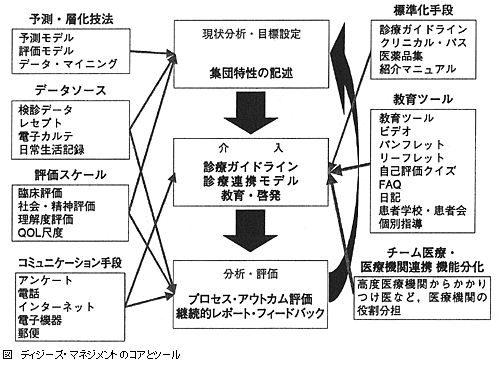
(1)現状分析・目標設定
慢性疾患における医療費は,ある疾患において患者間で一様に発生しているわけではなく,重症度や患者要因によって異なっている。例えば,糖尿病であれば,末期腎障害や進行した網膜症,心筋梗塞などの大血管障害の治療に相対的に多額の費用がかかっており,喘息では,緊急入院費用が大きなものである。
そこでディジーズ・マネジメントでは,特定の疾病について,人口学的要因,疾病の重症度,治療遵守や患者行動,費用構造,再発頻度などのデータをもとに,費用削減となりうる集団を特定する。また,個々の患者,住民に対する介入目標などの設定も行なわれる。
(2)介入
ディジーズ・マネジメントは,通常,疾病に罹患した患者の重症化防止に焦点があてられ,日常生活や治療遵守に関する教育プログラムとコミュニケーション・システムによる介入がなされる。教育プログラムは,単に患者に禁煙をすすめる,食事に気をつけるなどの指針を示したものではなく,医師,薬剤師,看護師,栄養士など各医療従事者の役割と患者への接し方・教育方法が明確化された標準的なツールが作成され,患者の日常の行動変容につなげるものとなっている。また,ツールが的確に用いられるためには,医療提供者に対する教育も必要になり,患者用,医療提供者用それぞれの教育ツールがシステム化されている。
特に慢性疾患におけるディジーズ・マネジメントにおいては,介入を効率的に行なうために,プライマリ・ケア医-専門医,医師-コメディカルスタッフなどの連携が必要である。そこで,それぞれが,どのタイミングでサービスを提供するのかを明確にしておく必要があり,情報の共有化,連携システムも作成される必要がある。
(3)分析・評価
ディジーズ・マネジメントにおいて重要なことは,介入して終わりでなく,介入による成果(アウトカム)を評価し,評価結果をもとによりよい医療サービスを提供する点にある。評価においては,医学的評価だけでなく,患者の行動や,目標達成のために医療提供者がどの程度標準にそった診療を行なっているか,などの視点からも検討がなされる。例えば,糖尿病の疾病管理プログラムについてみると,最終的には,血糖コントロールレベルやQOLの改善,糖尿病合併症の減少,それらの医学的指標の改善に基づく費用減少が最終目標であるが,患者の日常生活へ順守などの評価も行なわれる。
ディジーズ・マネジメントの対象疾患
ディジーズ・マネジメントは,すべての疾患が対象とされるわけではなく,慢性疾患で,疾病の費用構造が明確で戦略構築が可能であるものが対象とされることが多い。具体的には,喘息,糖尿病,がん,HIV/AIDS,胃潰瘍,アルツハイマー病,関節炎,骨粗鬆症,うつ病・神経症,心血管系疾患などが対象とされている2)。ディジーズ・マネジメントは,疾病特異型のアプローチであるため,それぞれの疾患ごとに目標設定や介入方法が異なっており,わが国においても,疾患ごとのディジーズ・マネジメントプログラムの開発が必要となる。
おわりに
米国では,人頭払いのもとではコスト意識が強く働くため,健康保険プランだけでなく医療提供者も,合併症罹患など費用のかかる状態にならないよう,ディジーズ・マネジメントに積極的に取り組む経済的なインセンティブが存在している。これに対し,わが国では,出来高払いを基調としており,医療機関においては診療報酬への関心はあっても,コストへの関心は相対的に低いといわざるをえなかった。しかしながら,わが国においても,生活習慣病の増加と医療費の増大は大きな問題であり,一方で,診療ガイドラインの普及と医療機関機能分化の進展など,医療現場においてもディジーズ・マネジメントを実施するための環境が整いつつある。今後,わが国固有の状況に配慮しつつも,医療サービスの標準化と効率性を追求するうえで有用な手段として広がっていくことが期待される。
●文献
1)Disease Management Purchasing Consortium & Advisory Council: http://www.dismgmt.com/frame10.htm
2)Hall, M.: Disease Management-what role for the industry in Europe? Scrip Magazine, June 1995, p29-32.
|
DMAA(Disease Management Association of America)
自己管理の努力が必要とされる患者集団のために作られた,ヘルスケアにおける介入・コミュニケーションのシステム。医師と患者との関係や医療計画をサポートする。エビデンスに基づく診療ガイドライン,患者を主体とする医療の戦略により,症状悪化・合併症の防止に重点をおく。総体的な健康改善を目標として,臨床的,人的,経済的アウトカムを評価する。 Disease Management Association of America:http://www.dmaa.org
BCG(Boston Consulting Group)
Gray, J. Lauyer, P:The Promise of Disease Management. Stern, CW, Stalk, Ged.:Perspectives on Strategy from The Boston Consulting Group John Wiley & Sons 1998
研究者
Plocher DW:Disease Management, Kongstvedt PR eds The Managed Health Care Handbook. Aspen Publishers Inc 1996
|


