新春随想
2004
感染症対策の未来
吉倉 廣(国立感染症研究所長)経済格差の広がりと流動人口の増加
 ここ10年ほど,毎年2-3回,中国のいろいろな場所に行っております。この間,大きな変化がありました。ここ2-3年の経済的発展は目覚ましく,それは北京のような大都市に限りません。しかし,車で30分も行くと前とまったく変わらない状況です。診療所を調査しても,医療状況も相変わらず悪いままです。前よりも悪くなっているかはわかりませんが,よくなっている風情ではありません。地方分権化,特に経済的な分権化で,貧しい所はいよいよ貧しくなっているようです。同じ省の中でも,豊かな地区と貧乏な地区があります。豊かな地区に職を求めて人々が流れていきます。
ここ10年ほど,毎年2-3回,中国のいろいろな場所に行っております。この間,大きな変化がありました。ここ2-3年の経済的発展は目覚ましく,それは北京のような大都市に限りません。しかし,車で30分も行くと前とまったく変わらない状況です。診療所を調査しても,医療状況も相変わらず悪いままです。前よりも悪くなっているかはわかりませんが,よくなっている風情ではありません。地方分権化,特に経済的な分権化で,貧しい所はいよいよ貧しくなっているようです。同じ省の中でも,豊かな地区と貧乏な地区があります。豊かな地区に職を求めて人々が流れていきます。
一昨年末エチオピアに参りましたが,干ばつと飢餓で土地を離れ都市部に人々が流れ,道ばたにぼろきれのように転がっていました。しかし,その真ん前には日本にもないような豪華なホテルがあります。
経済発展と貧富の格差,それに伴う流動人口の増加は世界の共通の問題です。日本でも,不法滞在,医療保障から脱落した人口の増加,貧困,結核やエイズなどの感染症の増加,さらには一般医療施設への影響が見られます。例えば,新宿の浮浪者がそばの国立病院に送られて入院し,後で結核患者であったことがわかる,といった状況があります。ホームレスの妊婦が送られてきて出産し,後で,100人近くが暴露され,30人位に予防投薬をしなければならなかった,というような事件もありました。
食料輸入大国としての課題
性格がかなり違いますが,感染症に関係して,次に問題と思われるのは,食品の問題です。わが国の食料の輸入への依存率は,カロリー換算で60%といわれておりますから,食品衛生も,6割の食品については,外国に依存している,という理屈になります。食料の6割を外国に依存していること自体,わが国の食料保障に問題があるということになりますが,それはひとまず置くとして,輸入食品に関わる病原体汚染,抗生物質残留,農薬残留は今後ますます大きな問題になると思います。生鮮魚介類,生鮮野菜は,中国,タイ,インドネシア,フィリピンなど途上国から入ってきていますが,輸入品の病原体,残留物汚染などは,その国の衛生状況,それに影響する社会状況,経済状況とも関係します。そこで,先進国の消費者は,経済的に弱い立場にある途上国の生産者に対して,心ゆくまで,用心のために過度な安全性要求をしてよいのだろうか,という疑問が出て参ります。例えば,肉,魚,野菜,などの個々に,トレーサビリテイなどを途上国に要求してよいのでしょうか。トレーサビリテイの導入は,やり方によっては,莫大な資本投入が必要になりますので,貿易の問題として今後難しい議論が出てくるように思います。個々の食品の直接安全性にはかかわらないが,消費者が心配で知りたい表示,例えば生産地,生産者表示,を輸入食品についてどのくらい要求できるのか?「農園から消費者への一貫した安全保障」が,極端に走りますと,日本の大企業が途上国の漁民や農民を管理しなければ満足しないようなことになるかも知れません。それは,いわば植民地でしょう。
人権と公共利益のバランス
一昨年のニューヨークのテロ事件と,直後に起きた炭疽が郵便物に入れられた事件をきっかけにバイオテロの問題も出ております。日本でも,これに便乗したいたずらが多量に出ました。このため,地方衛生研究所は一時業務に支障が出るほどでした。悪戯でも十分に行政機能を麻痺させ得ることを示した事件でした。米国では有事法案ともいうべき法案が出されました。有事法であれば個人のプライバシー,人権,と集団安全保障の問題が出て参ります。この法案はハーラン判事の言葉を引用し,社会との契約ということでこの問題に対処しております。感染症対策における人権と公共利益の緊張関係を認識し,共通理解に到達することが必要と思います。身体の復権-保健医療者が取り戻すべき視点とは
三砂ちづる(国立保健医療科学院疫学部)「身体」の全貌
 人間にはどのような身体機能が備わっているのだろう。実は私たちは,その全貌を知るにはあまりにもわずかな知識しか持っていないのではないだろうか。ぎりぎりの状況で,まったく自分の知らなかった身体の機能が発揮された経験を持つ人は,実はとても多いのだと思う。
人間にはどのような身体機能が備わっているのだろう。実は私たちは,その全貌を知るにはあまりにもわずかな知識しか持っていないのではないだろうか。ぎりぎりの状況で,まったく自分の知らなかった身体の機能が発揮された経験を持つ人は,実はとても多いのだと思う。
例えば,最近,「多くの暗記をしなければならない状況に臨んでいて,目に入った本のページがそのままカメラで撮るように頭に入ってしまう」,という機能が一時的に身についた人の話を2人続けて,耳にした。彼らにとって暗記した知識の問われる受験などは何ということのないものになったという。
子宮筋腫が消えた,ガンがなくなった,なぜよくなったのかわからない,という話は,日常的に誰もがどこかで聞いたことがあるだろう。それらは奇跡,などという言葉とは程遠い,実感を伴う身体の経験であるらしい。
EBMと身体の持つ「力」
コクラン・ライブラリーにその名を残すEBM(Evidence Based Medicine:根拠に根ざした医療)の祖のひとりであるイギリスの疫学者,アーチー・コクランは,第二次世界大戦のころ,設備も医薬品も絶対的に足りない捕虜収容所のただ1人の軍医として働いた経験がある。ジフテリアなどの感染症が蔓延し,1日600キロカロリーの栄養しか摂れず,何百という人がひざから上に浮腫を持っていた。そんな状態の中,使える薬はアスピリン,消毒剤,制酸剤程度。医師として,彼は多くの死を覚悟したが,結局亡くなったのは銃創による4人だけだった。この経験から,コクランは,「人体の力と比較した場合の治療の非重要性」への示唆を受ける*。治療は重要だが,人間の力と比べるべくもない,というのである。彼はここで受けた示唆をもとに,本当に科学的根拠があり,効果がある医療介入を選りすぐっていく必要性を感じ,そのために,RCT(Randomised Controlled Trial:無作為割付対照試験)を駆使することを提案する。EBMの体系はそのように作られていったのである。
人間に秘められた可能性
医学は人間の身体の全貌を知ろうと長い努力を続けてきた人類の至宝のひとつである。多くの医療介入が数え切れない恩恵をもたらしてきた。しかし,私たちは身体の持つ力について,まだまだ知らないことも多い。人間にはもともと回復する力がある。だからこそ医療介入を行なう時は,細心の注意がはらわれなければならないし,介入すると決めた時には,最新の医学知識が適用されるべきだ,というコクランの主張を思い出す時,では,私たちのもともと持っている力とはどういうものか,というところにあらためて立ち戻ってくる。今は,もっとも多くの人の持ちうる身体能力を基準として考えてきているわけだが,その力は,おそらくは,時代や,状況の要請によって,かなり大きく変化しうるものなのではないか。現実に医療分野にかかわるわれわれは,身体の持つ力はそのように変化しうる未知のものである,と謙虚になりながら,今,目の前にある地道な日々の仕事を続けていくことしかできない。しかし,同時に,直感を磨き,人間の持つ力の可能性について,医療分野を越えた,さまざまな人間の知と経験の蓄積へのまなざしを,より深くしていければ,と思う。
*コクラン著,『効果と効率』(サイエンティスト社,1999年)に詳しい。
医療情報の標準化・透明化と医療制度改革
松田晋哉(産業医大教授・公衆衛生学)合意形成のための「標準化」
 人口構造および疾病構造の変化と医療技術の進歩,そして国民の医療に対する要求水準の高まりによって増大する医療費をいかにコントロールするかが先進国共通の課題となっている。しかしながら,支払い者,患者,サービス提供者間の種々の利害が複雑に関連する医療の領域において,改革を行なっていくことは容易ではない。異なる利害関係を持つ関係者間で納得のいく合意形成がなされるためには,その根拠となる客観的な情報が必要である。しかしながら,これまでの医療の現場では,医療情報の標準化が遅れてきたために正確で使える状態の情報が少なく,また情報化が行なわれている場合でも,相互の比較可能性が考慮されてこなかったのが実情である。
人口構造および疾病構造の変化と医療技術の進歩,そして国民の医療に対する要求水準の高まりによって増大する医療費をいかにコントロールするかが先進国共通の課題となっている。しかしながら,支払い者,患者,サービス提供者間の種々の利害が複雑に関連する医療の領域において,改革を行なっていくことは容易ではない。異なる利害関係を持つ関係者間で納得のいく合意形成がなされるためには,その根拠となる客観的な情報が必要である。しかしながら,これまでの医療の現場では,医療情報の標準化が遅れてきたために正確で使える状態の情報が少なく,また情報化が行なわれている場合でも,相互の比較可能性が考慮されてこなかったのが実情である。
例えば,わが国では全国すべての医療機関から,傷病名と行なわれた医療行為に関する情報がレセプトに記載されて保険者に提出されるという他の先進国では見られないユニークなシステムが存在する。しかしながら,1つの病態に対する複数の傷病名の存在や病名と行なわれた医療行為の紐付けが行なわれていないなどといった問題点のために,せっかく収集した情報が分析できず,結果として医療制度改革の議論のために有効に使われていないという状況となっている。現在,医療のIT化戦略に基づいてレセプトの電子請求が進みつつあるが,今一度記載する内容の標準化に関する検討が必要であろう。
医療政策の第一の目的は,患者中心の視点に立って,国民にいかに質の高い医療を提供するかにある。しかしながら,現在の厳しい経済環境を前提とすれば,医療サービスの質の維持・向上を担保したうえで,医療費の適正化のためにある程度の経済的制約は受け入れざるを得ない。従って,医療機関としては,サービスの有効性と効率性について第三者が評価できる情報を開示する必要がある。そして,医療評価が相対的なものである以上,そのような評価のためには標準化された情報が不可欠である。そして,その情報に基づいて関係者間の議論と合意がなされていく体制,いわゆるEvidence Based Negotiationの体制を確立することが,今後の医療制度改革の基盤となると筆者は考えている。例えば,医療の現状に関する客観的な情報が整備され,仮に,医療の質を担保するためには,明らかに過少ファイナンスであるということが明らかになれば,関係者および国民の合意として医療費の総額を増やすことが可能であろう。もちろん,費用効果の面から疑問がある診療行為については,それに見合った評価をすることも可能になる。
DPC導入と今後の可能性
平成15年度4月から全国の特定機能病院等82施設を対象にわが国独自の診断群分類であるDPC(Diagnosis Procedure Combination)を用いた包括支払い制度が開始されている。筆者はこのDPC開発に携わっているが,急性期入院医療の包括評価というこれまでにない大きな制度改革であるために,関係者の関心は非常に高く,今後の動向に注目が集まっている。DPC開発の第一の目的は,本記事の主題である「医療に関連する情報の標準化と透明化」である。ただし,DPCがこの情報の標準化と透明化のためのツールとしての機能を十分に果たすためには,さらなる分類の精緻化とDPCを用いた質の評価手法の開発が課題となる。DPCが臨床現場で使われるものである以上,臨床的な妥当性が第一に保証されなければならない。そのためには臨床専門家からの意見が重要であり,われわれDPCの開発に携わるものはそのような意見を傾聴する姿勢を持たなければならないと考えている。また,DPCが病院管理に使われるものである以上,病院管理の実務者の意見も傾聴し,そのための方法論を開発していかなければならない。関係者の方々のさらなるご指導・ご鞭撻をお願いして稿を終えたい。
北里柴三郎生誕150年
加我君孝(東京大教授・耳鼻咽喉科学/医学教育国際協力研究センター長)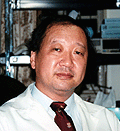 昨年は江戸開府400年をはじめとして病理学者の吉田富三,映画監督の小津安次郎生誕100年など多くの行事が開催された。わが国の医学界における話題としては北里柴三郎生誕150年の行事も開催された。
昨年は江戸開府400年をはじめとして病理学者の吉田富三,映画監督の小津安次郎生誕100年など多くの行事が開催された。わが国の医学界における話題としては北里柴三郎生誕150年の行事も開催された。
小生は本紙の1998年の新年のエッセーに“東大創立120周年記念プロジェクトと北里柴三郎先生のこと”を掲載させていただいた。その中で「東京大学医学部の卒業生で戦前に世界の医学に大きな足跡を残した人は誰かと聞かれれば,明治16年卒の北里柴三郎先生ではないかと思うようになった」として北里柴三郎が62歳の時の「伝染病研究所が大隈内閣により内務省から文部省への移管により東京大学に所属した問題」が「後世の医史家が現在なお東大医学部の横暴と書く者が少なくない,真実は何であったろうか」と疑問を書いた。
その後,2000年に東京大学が招いたノーベル賞の利根川進教授を,傑出人の脳のコーナーのある医学部標本室にご案内した時,周囲を見回して,“北里柴三郎のものは何かないの。東大出身だろう”と言われた。その弟子の志賀潔の“昭和医箴”という額はあるが本人に関したものは何もない。それは伝染病研究所は現在は医科学研究所として港区白金台にある独立した組織であることによる。2001年に医科学研究所には新しいミュージアムが完成し,北里柴三郎関連の資料が展示されている。
小生が中心になって歴史的にこの問題を取り上げることにし,昨年の3月13日に東京大学キャンパスの新教育研究棟で“北里柴三郎先生生誕150周年記念シンポジウム-教育者・研究者としての北里柴三郎先生-”を企画し開催した。シンポジストは6名にお願いした。シンポジストと演題は次の通りである。北里研究所病院長の土本憲二先生の「北里柴三郎と福沢諭吉」,東京大学医科学研究所元教授の小高健先生の「北里柴三郎と伝染病研究所」,小生の「伝染研究所移管問題と東京大学」,東京大学医科学研究所の高津聖志教授の「抗体療法とその将来展望」,医学教育国際協力研究センターの北村聖教授による「世界の切手でみる北里柴三郎と野口英世」そして明治製菓株式会社・北里一郎会長の「祖父・北里柴三郎」。本シンポジウムのポスターのデザインは綿羊の前に北里柴三郎が立つセピア色の写真で学内の掲示板に貼ると盗まれるほどの評判であった。
伝研移管問題の経緯をめぐるさまざまな記録
伝研移管問題については,管轄が内務省から文部省に移管される計画が発表されると,大日本帝国議会では白熱の議論となり新聞も盛んに取り上げる大事件となった。八木議員の質問主意書によると,これは大隈首相が東京帝国大学の青山胤道学長に請託を決めたことで「なぜ文部省に移管するのか,その理想は何か。北里所長辞職の可能性をどうするのか。東京帝国大学の医学部に属するということを文部大臣はどのように考えているのか」とある。政友会により「政府の処置は不当である」という議案が出され,採決の結果,“不当でない”が171,“不当”が186で不当であるほうが成立した。しかし,この時の内閣提案の12個師団増設問題を中心に議会は衝突し,解散。その後の選挙の結果,政友会が敗北したことでこの採決は無効となり,結果的に伝研は大正3年文部省へ移管することになる。
当時の文部大臣であった一木先生は回顧録の中で,「大正3年7月,欧州大戦,第一次世界大戦が始まり日英条約により英国は出兵を要求。急に不景気となる。経費削減のために各種機関を統合することにした。伝研と水産講習所が対象になった。北里柴三郎氏は巧みに宣伝し,各新聞は政府に反対した。」と記録している。また,「北里を辞めさせるのは明治大帝の思し召しに背く。留学に明治天皇の奨学金で行ったので,辞めさせるのは失礼である」という反対意見があったことも記されており,これに対し,「もし功労者なるが故に何時までもその地位に置かねばならぬというなら世の中に進歩はない」と記載されている。
東京帝国大学側の伝研問題の記録を調べてみた。当時の山川健次郎総長によると,自身の総長時代の難問の1つが伝研の移管問題であったとして,その経緯が記されている。
一木文部大臣の勧めで,「学術研究は文部省の所轄として大学が之に当たり,別に財団法人の機関を設けて血清の事業に当たらせよう」という提案がされた。内科の青山教授は賛成したが,薬理の林,病理の長与教授は断固反対し,「受けるなら事をすべて受けるのがいい」と主張。医学部長であった青山教授は衛生学を衛生学と細菌学に2分し,細菌学は北里柴三郎氏を教授として迎えたいという希望を持っていたが,大隈首相は直情直言直行の性格で移管を閣議で決定し進めた。外科の佐藤三吉教授が大隈首相に聞いたところ「我輩は身体のことなら青山君の指図を聞くが,政治は自ら別である。北里君も医界の硯学であることから十分に尊敬するが,しかしサイエンスは大学に委ねたほうが医政の常道であるのみならず,研究にも便利であると信じて決行したんである」と答えている。
一昨年発行された長与又郎日記(医学部長,総長にもなった病理の長与教授による全2巻の記録)の大正3年11月7日には,「どうも青山先生と北里先生の間で民間のさまざまな議論があるが,この頃は北里先生に関する学問上の評価に大分変化が来ており,必ずしも北里先生を支援できない」と書かれている。
客観的に調べることで見えた真実
現在もなお移管問題を東大対慶応,官立対私立のように書く人が少なくない。局所的にみるのではなく十分な双方の資料を調べ歴史を客観的に調べることでより本質がはっきり見えてくる。北里研発行の1656頁もある「北里柴三郎論説集」を読むと,本人の生の言葉がたくさん掲載されているので読んでいただきたい。本学の耳鼻咽喉科学教室の行事にも参加し祝辞を述べているように東京帝大との交流が盛んであったことがわかる。学問的論争はそれぞれの学説に立って活発に論争,友情は友情というのが北里柴三郎であった。お孫さんの明治製薬株式会社会長の北里一郎氏は,移管問題を後世の人がおもしろおかしく書いているが真実ではないと述べている。小生は今年も本学医学部の学生に「戦前最も偉大な卒業生は北里柴三郎であるが,ではどのような独創的な発見をしたのか」と問うことにする予定である。
変わる薬剤師教育と医療
内山 充(日本薬剤師研修センター理事長) 薬剤師教育に大きな変化が起きようとしている。近年,医療の質の一層の改善が求められる中で,処方せん調剤を通じて患者の安全と有効な治療を確保するという医薬分業本来の目的に応え,さらにチーム医療の一員として急速に高度化しつつある医療技術と薬物療法に薬学的専門知識を生かして貢献するために,質の高い薬剤師の活躍が期待されている。
薬剤師教育に大きな変化が起きようとしている。近年,医療の質の一層の改善が求められる中で,処方せん調剤を通じて患者の安全と有効な治療を確保するという医薬分業本来の目的に応え,さらにチーム医療の一員として急速に高度化しつつある医療技術と薬物療法に薬学的専門知識を生かして貢献するために,質の高い薬剤師の活躍が期待されている。
そもそも,医療のように日々進歩し高度化する領域では,大学教育を修了しただけで専門職が務まるとは誰も思ってはいない。生涯を通じて継続的に学習・研鑚を続けることが,専門職としての資質を向上し役割を果たすうえで必要であることは言うまでもない。しかし,大学教育が生涯学習の基盤であり,卒後に期待通りの専門職能を発揮するうえでもっとも大きな影響をもたらすことも間違いのないところである。したがって,薬剤師が医療の担い手として薬学の専門性を生かすためには,薬剤師1人ひとりの自覚に基づく生涯学習による職能開発と,薬剤師教育にかかわる大学教育の拡充強化が緊急に必要となる。
薬学部6年制が実現へ
これらの背景のもと昨年半ばに,文部科学省の「薬学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議」は,「薬剤師養成のためには基礎薬学と医療関連の内容のバランスを考慮した6年間の薬学教育が必要」という報告をまとめ,同じく厚生労働省の「薬剤師問題検討会」は,「薬剤師国家試験の受験資格として,医療薬学および臨床教育の充実した6年間の学部教育と,最低6か月程度の実務実習を必要とする」旨の報告を行なった。両省の歩調をそろえた改革案によって,薬学の修業年限の6年への延長と長期実務実習の必修化はごく近いうちに実現する見通しとなった。現行の4年の学部教育の中でも,医療を通じて積極的に社会に貢献できるように教科内容を改善し,さらに患者と接する医療人として高い倫理観と人間性を重視したカリキュラムへの改変が,すでに多くの大学で進められつつある。
教育改善は遠回りのようできわめて早い確実な効果が期待できる。薬剤師は今後,薬物治療に加えて保健予防からリハビリ・介護までの広い意味での医療の中で,patient safetyを最大の目標として常に念頭におきつつ,医薬品の開発改良をはじめ,安全・適正な薬物療法や患者指導を通じての医療協力,さらには医療従事者や患者・家族に対する情報提供などに一層貢献できるようになると期待していただきたい。
生涯研修制度の利用で職能向上を
一方,すでに職場にある薬剤師は,生涯にわたって自己学習を積み重ねて自らの資質の向上を図り,業務に必要な新しい知識,技能,態度を身につけて,他の医療担当者および患者との信頼関係を構築するように努めることが必要である。すでに10年ほど前から,薬剤師の生涯研修制度が発足し,心ある薬剤師は常に自らの職能の向上に励んでいる。そしてその証拠として,研修認定薬剤師証や実務研修修了証が発給されている。現在全国で2万人弱の薬剤師は,何らかの認定証を取得している。生涯研修は,能力,経験の不足を補うためだけのものではない。学問技術の進歩に即応するためのものである。そして,認定証は能力を示すというよりも自己資質向上の意欲を示す指標と見ることができる。したがって,責任ある立場,指導的立場の薬剤師も進んで取得すべきものと考えられる。医療職の方々へのお願いとして,同じ職場の薬剤師に研修への参加と認定証取得の有無を尋ねて,当人の職能向上への意欲を評価する指標にしていただきたい。研修認定薬剤師制度の詳細は下記ホームページに掲載されている。
URL=http://www.jpec.or.jp
医療被害防止・救済センターの実現に向けて
加藤良夫(南山大教授・法学/弁護士) 7歳の子どもが虫垂切除術を受けた時の脊椎麻酔の事故で脳に障害が残り,寝たきりの状態になった。この事件では最高裁の判決が出され救済されるまでに20年の歳月を要した。この間,両親は裁判を闘いながら介護などを続けてきた。私はこのケースを担当し医療被害者の早期救済を図ると同時に医療現場等へ再発防止策をフィードバックすること,併せて診療レベルの向上,医療制度の改善,患者の権利の確立を図ることなどを目的とする「医療被害防止・救済センター」の必要性を痛感した。
7歳の子どもが虫垂切除術を受けた時の脊椎麻酔の事故で脳に障害が残り,寝たきりの状態になった。この事件では最高裁の判決が出され救済されるまでに20年の歳月を要した。この間,両親は裁判を闘いながら介護などを続けてきた。私はこのケースを担当し医療被害者の早期救済を図ると同時に医療現場等へ再発防止策をフィードバックすること,併せて診療レベルの向上,医療制度の改善,患者の権利の確立を図ることなどを目的とする「医療被害防止・救済センター」の必要性を痛感した。
被害者の救済拡大と「過ちから学ぶ」文化への変革
「医療被害防止・救済センター」では,以下のような活動をめざしている。・医療被害者はいつでも電話など自由な方法で相談申し込みができる。
・救済すべき事案についてはセンターが被害者に対して補償をする。加害者側が事故を隠そうとするなどの問題がある場合にはセンターは被害者に代わって加害者側に求償する。ただし,速やかに被害者に謝罪し真相究明に協力し再発防止へむけた改善策を立案し実践したような場合には求償しないこともできることとする。
・センターの理事の過半数は患者・市民とし,医療を受ける側の人たちの声が反映されるような仕組みを作っておく。職員は一般公募方式で採用する。
・内部機構としては,相談に応ずる部門,講師を派遣する部門,より安全な医療政策を立案する部門などが必要である。
・財源については,互助の精神から税金および患者の一部負担金を充て,医療側・医療メーカーも利益の一部を被害救済のための基金に拠出する。
この構想では無過失のケースでも因果関係があれば補償されるので,医療被害者の救済が拡大する。事例がセンターに集まることにより早期にさまざまな情報が集まり,再発防止・被害拡大防止のヒントも含まれてくることにもなり,安全な医療の実現につながる。そして国民が被害情報にアクセスできるように,ホームページを開設し情報公開を進める。事故情報を隠蔽するのではなく「過ちから学ぶ」ことを「文化」として作り上げていきたい。
実現に向けたこれまでの動きと展望
「医療被害防止・救済センター」構想については,市民グループ「患者の権利法をつくる会」や,医療過誤の被害者で構成される「医療過誤原告の会」,医療過誤訴訟に患者側で取り組む弁護士の組織「医療事故情報センター」のシンポジウムなどで検討がなされてきた。2001年9月には「医療被害防止・救済システムの実現をめざす会」(仮称)準備室が名古屋に開設された。準備室の任務は,第一に新しいシステムないし第三者機関の必要性を広報すること,第二に呼びかけ人,賛同者などの輪を広げていくこと,第三に「めざす会」準備会の発足に向けて諸活動を展開することである。
準備室では冊子「医療事故を防止し被害者を救済するシステムをつくりたい」(A4,26頁)を約1万5千部発行・配布してきた。また,日本病院会や厚労省,学会,病院,大学などで話をするとともに,2003年9月には医療事故被害救済に関する初めての「市民判定会」が名古屋で開催された。
当面はセンター構想の内実を豊かにしていく作業を並行して進め,2004年9月には要綱案を確定させ(併せて「めざす会」の準備会を発足させ),2005年9月には法案を確定させ(併せて「めざす会」を発足させ),2007年3月の国会で法案が可決されることを目標としている。
安全な医療を実現することはすべての人の願いである。医療事故を防止し被害者を救済するためにいかなるシステムを構築すべきかという課題は,わが国だけにとどまらず世界各国でも検討されている。
「医療被害防止・救済センター」構想についてぜひご意見をお聞かせ願いたい。
URL=http://homepage2.nifty.com/pcmv/
『これから』のそれから
夏井 睦(慈泉会相澤病院外傷治療センター長) 私は数年前から,創傷治療,外傷治療,そして術後の創処置に関するインターネットサイト「新しい創傷治療」を作っている。従来からの方法への疑問を思いつくままに並べただけのサイトである。医学界の王道である「過去の文献を探してその正当性を主張する」方法論はまったく無視し,いくつかの普遍的事実をベースにして,それらをもとに理論的に演繹し,個々の医療行為が正しいのか間違っているのかを思考実験するというスタイルである。要するに,過去の文献を探すのが面倒なため,このような方法論を思いついたようなものだ。まさに私的インターネットサイトだから許される方法論だろうと思う。
私は数年前から,創傷治療,外傷治療,そして術後の創処置に関するインターネットサイト「新しい創傷治療」を作っている。従来からの方法への疑問を思いつくままに並べただけのサイトである。医学界の王道である「過去の文献を探してその正当性を主張する」方法論はまったく無視し,いくつかの普遍的事実をベースにして,それらをもとに理論的に演繹し,個々の医療行為が正しいのか間違っているのかを思考実験するというスタイルである。要するに,過去の文献を探すのが面倒なため,このような方法論を思いついたようなものだ。まさに私的インターネットサイトだから許される方法論だろうと思う。
そういう「書き捨て御免」のサイトが医学書院の編集者の目に留まり,あれよあれよという間に出版の話が進んだ。立案からわずか1年で拙書『これからの創傷治療』が2003年7月末に出版されることになった。
多勢に無勢の中で医学ゲリラ
もちろん,自分の本を出すことは生涯の夢だったし,インターネットサイトで主張している内容には絶対的な自信があった。だが,これほど早く出版されることは正直,予想していなかった。何しろ「傷は乾かすな,消毒するな」と,従来からの創処置,外傷治療の根本を全面否定しているのである。いくら正しいこととはいえ,それが理解されるにはそれなりの下地が必要なはずだ。だから私の主張が一般に受け入れられるのが難しいことは最初からわかりきっていた。何しろ,病棟や外来のあらゆる処置に消毒はつきまとっているのである。また,どんな家庭医学書にだって,「傷はまず消毒し……」と書かれている。要するに,傷を消毒することはすべての医療関係者,すべての日本国民の脳味噌深くにまで食い込んでいるのだ。これを否定するのは非常に難しい。多勢に無勢,という言葉があるが,まさに究極の無勢である。
だから私は最初から,ゲリラで行こうと考えていた。勢力が拮抗しているなら正規戦でもよいだろうが,多勢に無勢の争いで無勢側が正規戦を仕掛けるのは自殺行為である。無勢側に勝つチャンスがあるとすれば,ひたすらゲリラ戦に徹するしかない。ゲリラ戦に徹していれば無勢側にも勝機があることは歴史が証明している。
医学におけるゲリラ活動として私が選んだのがインターネットサイトの開設だった。医学の正規戦とも言うべき論文も書かず,学会報告もせずにひたすら「医学ゲリラ」に徹し,少しずつでも賛同者を増やしていこうと思っていた。いずれ本も書きたいとは考えていたが,それはまだまだ先のことだろうと思っていた。
外傷治療の定説を覆す勝負の時
ところが,医学書院から提案された書籍の話がとんとん拍子に進んで出版の運びとなり,しかも思いのほか,売れているらしい。いわばこれは,自分はゲリラ戦士だと思っていたのに,いきなり正規戦の表舞台に引きずり出されたような感覚,といったらご理解いただけるだろうか。さいわい,多勢側,正規軍方面からの表立った反論はまだいただいていないので胸をなでおろしているが,本が売れ,名前が知られるようになればなるほど,正規軍方面からの本格的攻撃を受けるのではないかと,実は内心ビクビクなのである。本質的に根は小心者なのである。過去130年以上にわたって信じられてきた「外傷治療の定説」をひっくり返せるかどうかは,これからが勝負であろうが,クラウゼヴィッツの『戦争論』などをひもときながら,次なる戦略を模索しているところである。


