〔インタビュー〕 日本における抗菌薬使用の実際から
急速な増加をみせる薬剤耐性菌の脅威
生方公子氏(北里大学・北里生命科学研究所教授)に聞く 近年,種々の耐性菌が増加していることは周知の通りであるが,日本ではセフェム系抗菌薬が多く使用される背景から,BLNAR(β-lactamase-nonproducing ABPC-resistant H. influenzae)と呼ばれるインフルエンザ菌の耐性株が急速に増加しているという。この耐性株による重症感染症は,基礎疾患を持たない小児で多く発症しているが,化膿性髄膜炎例では後遺症を残す率が高いと言われる。また,一見臨床効果のあるような薬剤が,実は効いていない場合があるということも警告されている。
今回は,急速な耐性化が指摘されている肺炎球菌とともに,インフルエンザ菌についても独自のサーベイランス研究に取り組んでいる,北里大学・北里生命科学研究所の生方公子氏に,薬剤耐性菌の現状および,とるべき対策についてお話しいただいた。
| (「週刊医学界新聞」編集室) |
■細菌の薬剤耐性化にまつわる日本の事情
肺炎球菌にみる耐性化の背景
――日本における耐性菌増加の背景についてはどのようなことがあるのでしょう?生方 日本では「PRSP(penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae)」と呼ばれる肺炎球菌による化膿性髄膜炎の第1例目が1988年に報告されましたが,その後急速に増加してきています。
私どもがそれ以前に保存しておいた肺炎球菌の遺伝子学的な検索をした成績では,87年頃から軽度耐性肺炎球菌(PISP)が出現し始め,それらも含めた耐性菌がこの10年間で急速に増えてきたと考えられます。
PRSPは,私どもが共同研究をしておりますApplebaum博士(米国・ペンシルベニア州立大学・ハーシー・メディカルセンター)が80年代初めに報告し,その後スペイン,東欧諸国で問題となりました。つまり,日本以外の国で先に問題となり,10年ほど遅れて日本でも議論されるようになってきたと言えます。
しかし,耐性菌の割合は日本ではすでに欧米を上回っているという逆転現象が起きています。欧米では外来診療においてはペニシリン系薬が第1選択薬として処方されていますが,日本では経口セフェム系薬が好まれているという違いがあります。日本においては,それらが臨床で使われ始めた時期と耐性菌の増加が並行しているようにみえます(図1)。
これらの経口セフェム系薬に対し,厚生労働省(以下,厚労省)によって認められている常用投与量時の血中濃度のピークは,ほとんどが1μg/ml程度にしか達していません。恐らく開発された当時には今問題となっているような耐性菌がなく,感性菌だけ抑えればよかったため,その投与量で臨床効果が十分得られていたのだと思います。問題はここ10年ぐらいの間に急速に増加しつつある耐性菌に対し,厚労省,製薬企業,そして抗菌薬を使う立場の人たちがいかに対応していくかだと思います。
抗菌薬の血中濃度と臨床効果との関係については,「Craig博士の理論」があります。一般的な経口β-ラクタム系薬では8時間おきに服用することになりますが,ペニシリン系薬では8時間の35%前後の時間維持される血中濃度,セフェム系薬の場合は殺菌力がやや劣るので,投与間隔の50%維持される血中濃度が重要となります。
その維持される濃度のMIC(最小発育阻止濃度)を示す菌まで臨床効果が期待できるとされています。これを「Time above MIC」といいます。多くの経口セフェム系薬のTime>MICは,0.5μg/mlから0.7μg/ml程度と算出されます。つまり,その程度のMICを示す菌までにしか臨床効果が期待できないことを意味しています。
経口薬の中ではアモキシシリンの血中濃度が高いので,Time>MICは1.8μg/ml前後と算出され,2μg/ml近いMICの菌まで臨床効果が期待できるという成績になっています。欧米でアモキシシリンが推奨されている理由です。日本で開発されたセフジニル,セフポドキシム,セフジトレン,それからセフカペン,ファロペネムなど多くは,Time > MICがすべて1μg/ml以下なのです。
現在,中耳炎などが治りにくくなってきていますが,それは薬剤が浸透し難い部位の炎症であるからです。そこで,PRSPという耐性菌に対する感受性累積分布を組織移行濃度の目安である0.125μg/mlを基準としてみますと,ほとんどの薬剤がその条件を満たしておりません。これだけ多くの抗菌薬が市販されているにもかかわらず,PRSPに対して有効性の期待できるものがほとんど見当たらないということが問題です。
一般的に,日本における抗菌薬の用法・用量は米国の半分程度です。起炎菌に対して有効に作用させることが目的ですから,下痢などを多少認めても,事情をきちんと説明し,服用が継続可能であれば引き続き服用してもらうことが必要です。その点,自分の判断で服薬を中止してはいけないなど,いわゆるコンプライアンスに注意が払われていないことが多いのではないでしょうか。
耐性菌による感染症で最も留意しなければならないのは,経口薬は菌に対して多少のダメージは与えても,菌を完全に死滅させることはもはやできないという事実です。つまり,遺伝子上に変異の入った耐性菌を選択しやすい状態になっているわけです。「臨床効果がもうひとつ」と思われたなら,用法・用量が許されている範囲で,投与量を増量してみるなどの工夫も必要だと思います。
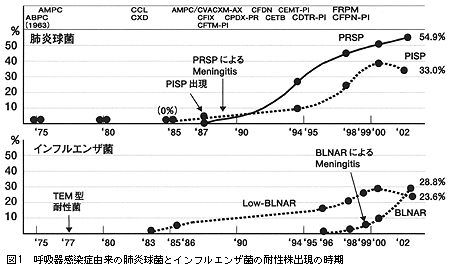
■新たな耐性菌との対峙
BLNARの増加
――先生は現在特にインフルエンザ菌の新しい耐性株の増加を警告されています。生方 はい。BLNARと呼ばれる耐性菌が急速に増えてきております(図2)。
PRSPは,私たちが臨床における問題提起をしてからすでに10年ほど経過しましたのでかなり知られてきておりますが,BLNARはまだあまり理解されていないと思います。
インフルエンザ菌ではペニシリン系薬を不活化する酵素であるβ-ラクタマーゼを産生する菌が1980年代から認められ,15-20%前後で推移してきました。BLNARはそれとは異なるメカニズムによる耐性菌なのです(表)。
BLNARは菌が2つの細胞に分裂する際の仕切りを作る酵素,すなわち隔壁合成酵素をコードする遺伝子上に変異が生じた菌です。基本的には肺炎球菌と同じメカニズムに属します。肺炎球菌の場合には遺伝子が3つ関与しており,隔壁合成酵素,長軸方向に細胞壁を合成する酵素,そして菌の先端を形成する酵素の3つの遺伝子に変異が入っているのがPRSPです。インフルエンザ菌の場合には,現在,耐性との関係が明確にされているのは隔壁合成酵素の遺伝子変異のみで,その遺伝子(fts I)上の3か所に変異が入ってきています。1か所だけの変異では耐性レベルが軽度なので「Low-BLNAR」と呼んでいますが,2か所に変異が挿入されると,ちょうど2薬剤を使用した際の併用効果と同じように耐性レベルが明らかに上昇します。
問題は,一見抗菌力を有するようにみえる薬剤が細菌学的に効いていないことです。なぜ見かけほどの効果が得られないのかといいますと,薬剤を作用させてもインフルエンザ菌は単に隔壁形成が阻害されて伸長化するのみで,死滅(溶菌)し難いことが原因です。そして,抗菌薬が体内から消失すると,伸長化した菌は元の桿菌へと短時間で戻ります。
先ほど申し上げましたが,経口薬はきちんと服用していただくことが重要です。解熱したからといって服用させなくなるお母さんを見受けますが,中途半端に中止すると再発・再燃につながってきます。インフルエンザ菌の場合は,菌の特性から特にその傾向が強いと言われています。
むしろ,菌が球状化するペニシリンやカルバペネム系薬のほうが,意外と臨床効果が得られると言われるのは,薬剤の作用で変形した菌からの再増殖が生じ難いからです。
肺炎例の場合には,注射薬剤でも単剤である程度の臨床効果は得られると思いますが,髄膜炎例の場合には髄液への薬剤移行率の悪さを考えますと,BLNARによる症例の場合には,メロペネムとセフォタキシムの併用などのほうがよいのではないかと考えています。しかし,併用例の症例数がそれほど多くありませんので,何がベストの治療なのかは今後の課題です。
ちなみに,米国ではBLNARが滅多に分離されませんので,アモキシシリンとクラブラン酸の合剤で事足りているようです。なぜ合剤かといいますと,β-ラクタマーゼ産生菌(BLPAR)が40%と多いためです。しかし,日本では経口セフェム系薬がそれらに有効であったお陰で,BLPARはむしろ5%程度の分離率であり,そのため合剤があまり必要なかったとも言えます。その反面,経口セフェム系薬がBLNARを選択するのに適していたという皮肉な結果になったとも言えます。
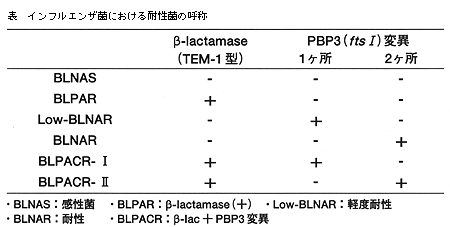
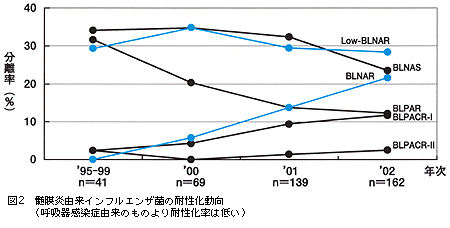
抗菌薬の臨床効果を左右する宿主側の5つのファクター
生方 抗菌薬の臨床効果を左右する要因は,抗菌薬側,菌側,そして宿主側にもあります。宿主側の要因として(1)年齢,(2)免疫能,(3)炎症部位,(4)基礎疾患の有無,そして(5)集団生活の有無,が挙げられます。いま,働くお母さんが非常に増えてきており,0歳保育へ預けられるお子さんが多くなっています。このことは,乳幼児が当然母体から移行して獲得すべき抗体が不十分であることを意味しております。そのようなお子さんが集団生活の中で,耐性菌を保菌しますと,呼吸器感染症や中耳炎などに罹患しやすい状況になると言えます。保育園を増やすことが社会的に要求されておりますが,0歳保育などにはリスクファクターもつきまとうことに留意しなければなりません。病児保育をどのように解決していくかということも大変重要だと思います。
Hibワクチンによる対策を
――BLNARに対して,今後どのような対策が必要でしょうか?生方 感染予防という意味でのインフルエンザ菌のタイプb(Hib)に対するワクチンがぜひとも必要です。このタイプは呼吸器感染症のみならず,化膿性髄膜炎を特異的に惹起するタイプとして知られています。
米国では10年ほど前からHibワクチン接種が行われ,Hibによる化膿性髄膜炎の発症率は,1997年には10万人当たり1.3人,そのうちHibは0.4人程度の発症率まで激減しています。一方,日本では4歳までの小児数が600万人弱となっていますので,私どもの収集した髄膜炎の例数で10万人あたりの発症率を計算しますと2001年2.3人,2002年2.7人となります。しかし,これは私どもが集積し得た成績からの推定数であり,実際はこの4倍程度,すなわち10万人あたり10人前後の発症率となっているのではないかと思われます。耐性菌がこのまま増え続けますと,発症率はさらに高くなる可能性を有しています。
日本では,Hibワクチンは未承認ですが,少なくとも保育園に通園するお子さんの場合には,Hibワクチンを接種してから入園することが望ましく,ワクチンが速やかに承認されることを期待しています。
最後にもうひとつ申し上げておきたいことがあります。日本においても医療費抑制の問題は避けて通れない状況となっています。今後はワクチン接種を含めた感染予防医学を真剣に考えなくてはならないと思います。
――本日はありがとうございました。
| 生方公子氏 1964年日本女子大卒,1968年より東大医学部附属病院分院小児科細菌研究室。1971年帝京大医学部小児科学教室,1980年同大臨床病理を経て,1981年医学博士。1990年帝京大医学部臨床病理助教授,1998年(財)微生物化学研究所特別研究員,2002年より,北里大学北里生命科学研究所・大学院感染制御科学部感染情報学教授に着任,現在に至る。 2000年より,「化膿性髄膜炎・全国サーベイランス速報」の発行を行なうなど,基礎研究の立場から薬剤耐性菌の増加に関しての提言を続けている |  |
