| 連載 第3回 | 再生医学・医療のフロントライン | ||||
角膜の再生
| |||||
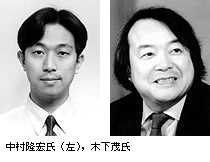 近年,遺伝子治療とともに21世紀の新しい医療として「再生医療」が注目されている。1997年のクローン羊の誕生や,1998年のヒト胚性幹細胞(ES細胞)の樹立により,世界の研究者がこれらの領域に注目し,飛躍的に進歩を遂げているこの研究分野は,われわれ眼科領域においてもしかりであり,再生医療にまつわる数多くの基礎および臨床研究が報告されている。
近年,遺伝子治療とともに21世紀の新しい医療として「再生医療」が注目されている。1997年のクローン羊の誕生や,1998年のヒト胚性幹細胞(ES細胞)の樹立により,世界の研究者がこれらの領域に注目し,飛躍的に進歩を遂げているこの研究分野は,われわれ眼科領域においてもしかりであり,再生医療にまつわる数多くの基礎および臨床研究が報告されている。
眼科領域における再生医療の対象としてはこれまで,角膜,網膜,視神経などが研究されてきたが,その中で特にわれわれが精力的に研究に関与している角膜(上皮)の再生について,その研究経緯ならび成果と今後の課題や方向性について述べる。
角膜再生の試み
外界からの視覚情報を脳へ伝達するための重要な情報入力器官である眼の中で,角膜は前眼部の1/6の面積を占める透光体組織であり,高い透明性とバリア機能を持ち,眼球組織を外界から物理的,生物学的に保護する役割を果たしている。角膜は5層構造を示し,そのうち最表層にある角膜上皮は厚さ約50umの非角化重層扁平上皮であり,周辺の輪部上皮や結膜上皮と一体になって眼表面(ocular surface)を構成している。この角膜再生に関する研究には大きくわけて2つの方向性があり,1つはpoly-methylmethacrylate(PMMA)などをはじめとする工学的材料を用いた人工角膜の開発であり,中にはすでに臨床応用されているものもある。しかし,その有効性に関しては不明の点が多く,組織適合性の問題や工学材料の技術革新が今後の研究課題である。
一方,角膜上皮幹細胞を生体外(in vitro)で分化増殖させ,上皮層のみを再構築しようという試みが近年大きく注目されている。これまで世界中の研究者が角膜上皮再生に挑み,例えば,角膜実質組織やタイプIVコラーゲンをキャリアとした角膜上皮の再生の報告がなされてきた。しかし,本当に臨床的に実用化されたものはなく,in vitro の環境で角膜上皮細胞層を形成することはきわめて困難であった。その中で,生体材料の1つである「羊膜」の出現により,その研究は大きく前進することとなる。
羊膜を用いた角膜上皮シート
 われわれの研究チームは,まずはじめに家兎を用いた動物実験を行ない,上皮を掻爬した羊膜が角膜上皮の幹細胞の培養の基質として適していることを示し,羊膜上に家兎の角膜上皮幹細胞を培養して,分化,重層化した角膜上皮シートを作成することに成功した。その後,作成した培養角膜上皮シートを同じ家兎の他眼に自家移植をした結果,培養した角膜上皮シートが眼表面に生着,伸展し,術後透明性を維持することを確認した。
われわれの研究チームは,まずはじめに家兎を用いた動物実験を行ない,上皮を掻爬した羊膜が角膜上皮の幹細胞の培養の基質として適していることを示し,羊膜上に家兎の角膜上皮幹細胞を培養して,分化,重層化した角膜上皮シートを作成することに成功した。その後,作成した培養角膜上皮シートを同じ家兎の他眼に自家移植をした結果,培養した角膜上皮シートが眼表面に生着,伸展し,術後透明性を維持することを確認した。
以上のような一連の基礎的実験データに基づき,1999年より大学倫理委員会の承認に従って十分なインフォームド・コンセントを行なった上で,難治性眼表面疾患に対する同種アロ培養角膜上皮移植を開始した(図1)。これまで角膜移植の適応外とされた急性期のStevens-Johnson症候群や,化学外傷を含む23例の難治性眼表面疾患に対して同移植を行ない,全例で移植後48時間における培養角膜上皮の生着を確認している。
今後の課題,方向性
難治性眼表面疾患に対する外科的再建という概念は,羊膜移植や培養角膜上皮移植などさまざまな外科的治療法が開発され,それなりの成功をおさめてきた。しかしながら難治性眼表面疾患の多くは両眼性であり,これらの治療法の多くは他人(アロ)からの組織の移植に頼らざるを得ず,術後の拒絶反応や細菌感染症といった問題が術後成績に大きく影響を与えているのが現状である。今後はこのような難治性眼表面疾患に対し,可能であれば,局所の幹細胞の存在が示唆されている結膜や口腔粘膜といった自己の他の健常な部位の粘膜組織を培養して粘膜上皮シートを作成し移植できれば,術後の拒絶反応等の危険性がなく理想的である。また,このような組織幹細胞を用いた再生医学的手法による眼表面の再生と同時に組織再生技術が進歩すれば,近い将来,ES細胞や骨髄幹細胞から角膜上皮様細胞を分化誘導可能となる日が訪れるかもしれない。
