インタビュー
子どものリハビリテーション
今,子どもの障害に関する新しい知見が蓄積され,臨床場面でも大きな変化が起こっている。本紙では,子どものリハビリテーションの現状から,障害像,機能評価,発達障害,リハ・サービスの4つのトピックスを取り上げ,各領域をリードする5人に話をうかがう機会を得た。


●子どもの障害像の現状
| 松井 潔氏 | (神奈川県立子ども医療センター・周産期医療部新生児未熟児科) |
| 山中美智子氏 | (同センター・周産期医療部産科) |
障害児を取り巻く変化
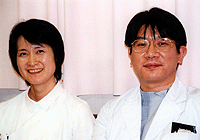 松井(写真右) 現在,超低出生体重児(1000g未満)や極低出生体重児(1500g未満)と言われるような未熟児の生命的予後は改善し,9割以上が生存します。一方で,障害を持った子どもの頻度は減少していません。
松井(写真右) 現在,超低出生体重児(1000g未満)や極低出生体重児(1500g未満)と言われるような未熟児の生命的予後は改善し,9割以上が生存します。一方で,障害を持った子どもの頻度は減少していません。
未熟児脳性麻痺の原因の多くは,脳室周囲白質軟化症(Periventricular Leuko-malacia;以下PVL)と脳室内出血によるものです。PVLは超低出生体重児より1000-1500gと比較的全身状態の安定している児に多く,予防対策も確立していません。当院でもこの10年間の頻度は変わらず,全国平均では8%,当院では約4%の発症率です。「PVLをいかに減らすか?」は,周産期医療の重要な課題の1つです。当院のNICUには,リハビリテーション(以下,リハ)科医師,理学療法士や作業療法士が診療に参加し,肺理学療法と運動機能評価,ポジショニングや哺乳の評価などを行なっています。退院時には,ご家族への指導もしてもらっています。
PVLによる脳性麻痺は軽度から重度まで幅が広く,超音波検査,MRI,脳波によりある程度の重症度の予測が可能になってきています。入院中に,外来フォロー,リハや定期的な脳波検査の重要性を説明し,将来的には地域の療育センターでの療育が必要になる可能性などをお話しています。
山中(写真左) 産科は,早産の可能性があればどのタイミングで分娩にさせるかを決定します。かつては感染や破水があっても,ともかく週数を伸ばすほうがよいとされていましたが,今はむしろ逆で,早くに出産して体外治療に結び付けるほうがよいという考え方もあります。また母体にステロイドを投与して,胎児の臓器成熟を促進するという方法もあります。
二分脊椎
松井 二分脊椎は,本邦では約3000出生に1人とされ,胎児期にみつかる脳奇形の中で最も多い疾患の1つです。二分脊椎は,複数の専門科による包括的な医療を必要とします。髄膜瘤の閉鎖術や水頭症の管理は脳外科,下肢の麻痺や変形はリハ科と整形外科,排尿障害は泌尿器科が関わり,総合的な管理は新生児科が行ないます。約半数は胎児診断されるようになり,このような例では,産科,麻酔科,脳外科,遺伝科,新生児科,看護婦,ソーシャルワーカー(SW)により胎児カンファレンスを行ない,分娩時期・方法,出産後の対策を検討し,ご両親に説明します。脊髄障害やキアリ奇形による脳幹障害の二次的損傷を予防するため,可能な限り帝王切開を選択しています。胎児診断されていない場合,キアリ奇形による呼吸・嚥下障害を有する例があり,管理の工夫により予後を少しでもよくしたいと思います。フィラデルフィア小児病院では胎児手術が行なわれ,脊髄障害が軽減し,キアリ奇形や水頭症も改善されたとの報告があります。このように二分脊椎は出生前からの包括医療が必要となってきます。この論文の中に,「胎児治療への挑戦は伝統的な科別の医療では成り立たない。多くの専門家の統合と協力によって可能になる」と書かれています。当センターでは開設以来1人1カルテで,すべての科の所見がそこに記載されており,二分脊椎の児の情報を共有できます。小児の包括医療の「こころ」がここにあります。妊娠前外来
山中 病気の子どもをもったお母さんで次の出産に対する不安が強い方のために,当センターでは「妊娠前外来」を設置し,産科の医師に相談できるようにしています。これは,二分脊椎の子どものケアを考える中から生まれました。二分脊椎の子どもがいる方の場合,次の子どもが同じ病気になる確率が一般の方より高くなると言われています。昨年,厚労省がコメントを出したように,葉酸の摂取でこの確率が低くなるというデータがあります。ただし,妊娠がわかってから摂取しても胎児の器官形成はほぼ終わっているので,遅いのです。
そこで,妊娠する前から次回妊娠に備えてもらえるようにと,1999年から外来を開始しました。月1回,私を含む遺伝専門医資格を有する産科医2人で行なっています。相談内容は,遺伝性を含めた子どもの病気のこと,前回の妊娠・分娩時のトラブル,習慣流産などです。この外来に通われて当院でお産された方もいます。これは,「遺伝カウンセリング」としては他にもありますが,ここでは産婦人科医が相談にあたることで,次の出産に対するイメージを持ちやすいことが特徴かもしれません。
松井 産期医療の経験の蓄積や画像診断の進歩により,種々の疾患が早期に診断され,長期的な展望がたてやすくなりました。ご両親に,出生前や症状が出現する前に疾患や予後をお話することは,医師にもつらいことですが,早期に話し合うことにより,疾患や障害について考える時間的猶予が与えられ,その結果,これからの困難に立ち向かっていく心構えが生まれてきます。胎児期や新生児期は療育のはじまり(方向づけ)と考えています。このようなアプローチの結果でしょうか? 次の妊娠に不安を持ちながらも,早い時期からの妊娠前外来の受診を希望されるご家族も増えています。
患者アドヴォカシーを
山中 当センターには「母子保健室」と呼ばれる,SWや保健婦,看護婦が社会的側からのサポートをする部署があります。医師が患者さんとご家族に病気についての説明する時には,一緒に話を聞いてもらっています。社会的資源の活用のための情報提供の他に,複数科での治療が必要な赤ちゃんのために,各科の橋渡し的な仕事をしてくれます。地域との繋がりも作ってくれます。松井 アメリカでは「患者アドヴォカシー(権利擁護)が大切」と言われています。今後は当院の母子保健室のように,患者さんを支援する専門家や,常に情報が家族の手に入るようなシステムの構築が必要と思います。
●子どもの機能評価
近藤和泉氏(弘前大学脳神経疾患研究施設助教授・脳機能回復部門)機能評価の枠組み
 近藤 現在,日本でも米国でも,脳性麻痺の子どもに対する特別決まった治療の組立てはありません。しかし昨年,米国脳性麻痺・発達医学会に参加し,脳性麻痺児の治療の根拠を提供し得る機能評価法として紹介されたものの中に,定番と言えるものがあることや,脳性麻痺の治療のコンセンサスを形成しつつあるという,一歩先んじた米国の流れを感じました。
近藤 現在,日本でも米国でも,脳性麻痺の子どもに対する特別決まった治療の組立てはありません。しかし昨年,米国脳性麻痺・発達医学会に参加し,脳性麻痺児の治療の根拠を提供し得る機能評価法として紹介されたものの中に,定番と言えるものがあることや,脳性麻痺の治療のコンセンサスを形成しつつあるという,一歩先んじた米国の流れを感じました。
きちんとした評価法がなければ,機能の改善,また改善の度合いなどの治療効果の検討はできません。しかし,1985年までは,欧米でも適切な評価が行なわれているわけではありませんでした。
この年1985年に発表された,カーシュナー(Kirschner)教授(カナダ・マクマスター大学)の論文「医療保健尺度の枠組み」により,初めてきちんと使える尺度が生まれました。その前にも評価法はありましたが,臨床的に重要な変化をとらえるための尺度構造が決まっていませんでした。それを決めたのがこの論文です。ここから大きく状況は変わります。例えば,GMFM(粗大運動能力尺度;脳性麻痺児のための評価的尺度)もそうですが,評価法のほとんどは,必ずこの論文を引用しています。まさに転換点となった論文ですね。
カーシュナーの偉大な点は,検査室での検査や心拍出量のようなデータと,ADLやQOLといった曖昧な,器械では検査できないものとの間に線を引いたことです。
もう1つ,氏の仕事がエポックメーキングであった点は,評価尺度を(1)診断や重症度を決める「判別的尺度」,(2) (1)を基にして,子どもの徴候から将来を見る,「予測的尺度」,(3)経時的に点数をつけて,強い医療的な介入前後の効果を見る「評価的尺度」,の3つに分けたところです。
「評価的尺度」では反応性(「Responsible-ness」)が重視されます。これは臨床的な変化に対応して,点数がきちんと変化することをさします。人間はいい加減で,点数をつけるほうも,評価されるほうも気分で違ってしまうことがあります。臨床的に重要な変化が点数に反映されなければ,医療現場で使える尺度はできません。
日本の機能評価をめぐる状況
近藤 このような背景のもと,1988年にGMFMが,またCOPM,PEDIなどの各種機能評価法が1990年代初頭に完成しています。これらが臨床で利用され,EBMの考え方も加わり,米国では脳性麻痺への対応にコンセンサスができつつあると言えます。一方,日本ではまだその動きはありません。日本の場合は医療保険が出来高払いで,医療行為に対する厳しい評価が行なれていないことが影響しています。
よく「7歳を過ぎると粗大運動能力はほとんど変化しない」と言われます。しかし現在,そのような子どもにも,「粗大運動能力訓練」が主に行なわれています。この時期の子どもは知能の発達も一緒に起こるので,社会的機能やADLを中心にアプローチすべきなのです。しかし,ある時期にどの能力が伸びるかが十分に理解されていないことから,適切な時期に適切な訓練がなされない可能性があります。米国でもこの流れは似ているようです。年齢によって子どもの能力は変化するので,そこに医療的な介入した後,どのようなアプローチでどう変化していくかという,経時的なトレンドを出す必要があります。
今後の課題
近藤 脳性麻痺ではそのような知見が特に求められています。それに合わせて,肢体不自由児施設も再編されていくだろうと思います。現場の人たちも,7歳以降に粗大運動能力訓練をしても効果がないことに気づき,「社会生活能力を伸ばすようなアプローチをすべきで,機能訓練にこだわる必要はない」という考え方が出てきています。しかし,日本の肢体不自由児施設はポリオがモデルで,「機能訓練で社会復帰ができる」という考えが,いまだに基盤になっています。しかし脳性麻痺はポリオとは異なります。
現在,厚労省・障害保健福祉総合事業の「脳性麻痺児の評価に対する研究」を3年間行なっており,評価の原型はできました。今後は,日本独自の生活・文化・習慣に根ざした評価が必要です。それぞれのニーズに合った評価法がきちんと整備されることが求められているのだと思います。
●発達障害-自閉症,アスペルガー症候群を中心に
清水康夫氏(横浜市総合リハビリテーションセンター・児童精神科) 清水 最近,自閉症への関心が高まっています。本症は児童精神医学が精神医学の新しい分野の1つとして出発した中で見つけられ,児童精神医学は自閉症の研究・臨床とともに歩んできたとも言われるほどです。しかし自閉症に対する考え方は,時代ごとの精神医学の影響を受けながら変遷を重ねてきました。
清水 最近,自閉症への関心が高まっています。本症は児童精神医学が精神医学の新しい分野の1つとして出発した中で見つけられ,児童精神医学は自閉症の研究・臨床とともに歩んできたとも言われるほどです。しかし自閉症に対する考え方は,時代ごとの精神医学の影響を受けながら変遷を重ねてきました。
かつて米国の精神医学では自閉症に対しても精神分析学的な考え方がなされ,原因は育児にあると考えられていました。しかし,その仮説のもとに治療を試みても結果はよくなく,そこがさまざまな自閉症の治療理論の錯綜する元になります。1970年前後,欧米で自閉症児の教育プログラムが登場し,良好な結果が得られたため,教育の必要性がわかってきました。
その頃から世界は急転回します。1つは教育,1つは脳研究の発展によって,自閉症に対する考え方が変わってきたのです。精神医学の舵取りが,心因論から脳科学へと変わってきました。現在でも,自閉症の脳障害に関して,脳科学はまだ根拠をつかんだとは言えませんが,自閉症の脳機能の異常を検証し,行動を説明するという方向で医学研究の足並みが揃ってきました。
加えて重要な背景に,児童心理学の発展があります。子どもは大人の単なる雛形か,という中世からのテーマに対して,子どもとして尊ばれなくてはいけないという,今では当然の考え方に沿って誕生した学問分野です。ここから「人間はどのようなプロセスを経て大人になるのか」の原理を知る学問「発達心理学」が生まれます。
発達障害-日本の状況
清水 自閉症の今後のテーマは,1つは「心の病理としてどう説明すべきか(精神病理)」で,もう1つは「脳の異常としてどう語るべきか」,の2点です。治療したり,また病理をもっても,なおきちんと成長するために,治療論と教育論とが関連を持ち始めたのが,最近の動向です。さらに,心の機能の障害を『発達』の軸で考える思想のもとに誕生したのが「発達障害」という言葉です。子どもは発達する存在で,子どもの精神障害を発達の軸で考えることは非常に重要です。特に自閉症ではその点が強調される必要がありました。
この30年間,自閉症の教育システムが整えられ,今ではそれに早期に乗せることが世界的なコンセンサスです。しかし,日本では自閉症に対する教育システムはまだ十分に整わず,また特殊教育への抵抗感も一部にはあるようです。にもかかわらず,実は日本ほど自閉症の早期発見・療育が広く行なわれている国もないでしょう。乳幼児健診における保健婦の活躍によると思います。わずか1歳半で自閉症の子が発見され,早期療育へとつなげられています。20年前とは比較にならないほど,自閉症の早期発見・療育が普及しました。
言葉という記号が包含する意味や機能を子どもが持ち始めるのは1歳半-2歳頃で,同時期に「ごっこ遊び」や「みたて遊び」ができるようになります。この機能と,文字における線のパターンが意味を持つことを理解する基本は同じです。自閉症にはそのような言語の障害,記号操作の障害があります。
一方,非言語的コミュニケーションの機能は1歳半までの間に急速に発達します。その1つが「指さし」や,俗に「目さし」と呼ばれる視線のコミュニケーションです。つまり,自閉症児はコミュニケーション活動そのものが幼少時から障害され,次いで言葉も障害されてくるのです。特に「指さし」では,三項関係で見られるある種の共感性が欠けていることがわかります。このように自閉症では,1-2歳からコミュニケーションの問題が見られるのです。子どもの行動を通して発達異常を知るのが,われわれの方法論です。「この時期にこのような行動が出ないのは,こういう発達の障害があるのではないか」と考えます。自閉症においてそれが最初に観察可能なのは,まさにこの頃なのです。
「発達リハビリテーション」
清水 横浜市では,症状が軽い場合でも4歳頃までには,大概の発達障害が発見されています。多くは2-3歳で早期療育の場へと紹介され,児童精神科医も加わって,自閉症児の早期療育が行なわれています。両親は子どもを育てるための技能やコツも学びます。両親のメンタルヘルスにも対応できないと,早期発見・療育は成功しません。自閉症に力を入れる理由は,これにより発達障害全体を押さえることができるからです。知的障害から入ると,自閉症の一部やアスペルガー症候群などを見逃してしまい,地域の発達障害の早期発見活動に限界が生じるので,このあたりが戦略的にも大事です。
自閉症を治療せずに放っておくとどうなるかはわかっています。それを防ぐと同時に,健全な方向に伸ばしていくことが早期療育のポイントです。その意味で自閉症治療はリハだと思います。ただ,機能が失われた時点で「どうするのか」という構図ではなく,機能が上がるところですでに方向が違っていて,かつしばしば機能的な低さにも対応するので,一般のリハとは違った考え方になります。それが,発達の軸であり,このような考え方のリハを「発達リハ」と私どもは名づけています。
アスペルガー症候群
清水 自閉症も軽症例まで診断されるようになり,現在では「高機能自閉症」「アスペルガー症候群」など,知的障害を持たない,ある意味で言葉の達者な自閉症も幼児期に発見・診断が可能になりました。いま児童精神医学の領域では,医師の間でそれぞれが自戒の念を込めて「アスペルガー症候群を誤診しないように」という暗黙のスローガンさえあります。この子どもは自閉症の症状が軽く,しばしばそれとは気づかれず,学校でいじめにあったり,不登校となることが少なくないのです。多動症状が目立つことがあるためにAD/HD(注意欠陥/多動性障害)と誤診されたり,成人の場合だと精神病と誤診されることさえあります。本症候群は,知能の障害がないから自閉症よりも軽く,何も手厚く治療する必要はないと考える一部の専門家もいます。しかし,何の手も尽くさなかったため悲惨な事態に至ることもあり,治療側に反省が起こりつつあります。子どもは案外に残酷なもので,そのような子を「村八分」したり,最悪な場合は,結果的に教師も加担してしまうケースもあります。友だちや親しい味方がなく孤立し,加えて「普通の子の中でよい刺激を与えたい」と希望するあまり,両親が子どもの心の傷に無頓着なこともあります。そこで子どもはさらに傷つく,という悪循環が起こり,これでは健全な精神発達はあり得ません。だからこそ,幼少時から正しく対応する必要があるのです。
●子どものリハ・サービス
小池純子氏(横浜市障害者更生相談所長) 小池 一般的に障害児の早期発見は,保健所の乳幼児健康診査から始まります。横浜市の早期発見・早期介入のシステムは,方面別に設置された地域療育センターが保健所と連携して行なう「療育相談事業」が軸になります。乳幼児健診でスクリーニングされたリスク児について,診断および専門的な療育が必要かどうか,保健所だけでは判断しきれない場合に「療育相談」を利用してもらいます。これは専門医,セラピストを保健所へ派遣し4か月児健診,1歳6か月児健診に対応して行なわれ,前者は脳性麻痺を中心とする運動発達障害,後者は自閉症,精神遅滞の早期発見が目的です。
小池 一般的に障害児の早期発見は,保健所の乳幼児健康診査から始まります。横浜市の早期発見・早期介入のシステムは,方面別に設置された地域療育センターが保健所と連携して行なう「療育相談事業」が軸になります。乳幼児健診でスクリーニングされたリスク児について,診断および専門的な療育が必要かどうか,保健所だけでは判断しきれない場合に「療育相談」を利用してもらいます。これは専門医,セラピストを保健所へ派遣し4か月児健診,1歳6か月児健診に対応して行なわれ,前者は脳性麻痺を中心とする運動発達障害,後者は自閉症,精神遅滞の早期発見が目的です。
発達障害は障害種別により発見の時期が異なります。児の年齢が小さいほど障害は未分化で診断する作業は難しく,障害の発生は予想できても,その種別,程度までは療育相談の時点では判断できないことも多いです。この特徴は4か月児療育相談のほうが明らかです。また,最近の傾向は,脳性麻痺およびそのリスク児の多数がNICUを持つ病院から直接に療育センターに紹介されるようになり,4か月児療育相談にはむしろ脳性麻痺以外の様々な発達障害が運動発達の遅れや歪みを主訴に受診することです。うつぶせを嫌がったり,抱っこしにくいなど母親が育てにくさを感じ育児負担となっていることもあり,このような子どもをフォローすると,その一部は自閉症を含む精神発達障害であることがわかりました。
地域療育センターでの早期療育は外来療育と通園療育からなっています。特に外来療育には「療育への導入」,「療育の第一段階」として重要な役割を持たせています。外来を受診された子どもには,個別訓練と併せて「外来集団療育」を利用してもらいますが,そこでは子どもの障害の多軸的評価とともに,評価結果を両親と共有して障害理解を深め,両親と合議のもとに就学までの療育計画を立てます。両親が主体的に療育サービスを選択し,私たちはそれをサポートするという姿勢が重要です。
訓練は教育の一環
小池 学齢期の障害児に対する問題点の1つは,施設間の連携の欠如です。就学まで機能していた保健(医療)・福祉・教育(保育)の療育ネットワークは学齢期に入ると分断されてしまう感があります。早期療育とは早期だけの療育ではなく,早期からの療育であると常々訴えている者としては頭の痛いところです。運動障害については,リハ医が養護学校の臨床指導医として教育の現場で定期的に相談にのる体制を作っていますが,精神発達障害に対するこのようなしくみは,まだ試行の段階です。運動障害児は訓練と教育のすり合わせがうまくいかず,つい訓練にばかりに目がいってしまうことが多いです。学齢期には障害の回復もほぼプラトーに達し,その後は障害とともにどう生きていくかを全人的に教育する必要があります。しかし,障害の治療的な見方に捕われ,生活的な見方への変換がうまくいかないことが問題ですね。
横浜市総合リハセンター併設の身体障害者更生施設には,養護学校高等部卒業生を対象とした「社会生活力プログラム」があります。これは障害児が社会人となるための入り口の部分を担うもので,公共交通機関の利用の仕方,補装具の給付制度,年金制度を学ぶなど,すべて親がかりだったことを,自分の力で行なえるように支援するプログラムです。このようなプログラムはもっと早い段階から少しずつ始めたいのですが,なかなかその受け皿がありません。
障害に対しては,残存能力の活用と代償手段の活用を考えます。しかし,学校教育では前者へのアプローチに主眼が置かれ, 「できないこと」に焦点をあてることは軽視されがちです。ある年齢になったら代償手段を積極的に利用して,社会経験を広げるほうが,子どもの発達によい影響があると思います。ただ,教育が協調されるあまり治療的要素がゼロになってはいけません。つまり,子どものリハは,治療と教育のバランスをとることがポイントなのです。
ニーズにあったリハ・サービスを
小池 横浜市では総合リハセンターを中核に地域療育センターを設置,地域療育システムとして事業を展開し,14年が経過しました。この間には医療技術の進歩に伴う障害発生の背景に変化があり,障害の早期発見については,スクリーニング技術の向上,療育ニーズの増大(超重心児,知的障害のない発達障害児)など新たな課題が生じています。現在,総合リハセンターを中心に「第三次構想」として新たな段階に向けての見直しが図られているところです。運動障害児に対しては,早期療育ルートの見直し,学齢期教育機関との連携,特殊クリニック(摂食,代替コミュニケーション,シーティング)の充実,リハ工学,リハスポーツを含めた総合的リハ・サービスのタイムリーな提供に向けて検討中です。一方,超重心児の療育のあり方についても,緊急焦眉の課題となっています。さらに横浜市では,「学齢期障害児支援事業」を開始しました。本事業はフォローの必要性が強調されながらもその受け皿の少なかった学齢期精神発達障害児に対し,リハ・サービス提供の道を開くものです。
今,福祉の施策は「措置」から「利用制度」「自己選択,自己決定」へと変革の時を迎えています。その中で豊かな社会生活が送れるよう,「自分で選べる大人の障害者」をめざしてリハ・サービスを充実させていきたいですね。
