Vol.16 No.4 for Students & Residents
医学生・研修医版 2001. Apr
医学生・研修医のために
| |||
 青木 眞氏 |
 磯野可一氏 |
 大平整爾氏 |
|
 斎藤 学氏 |
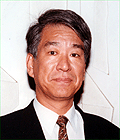 瀬戸山元一氏 |
 西澤潤一氏 |
|
 古川俊治氏 |
 松村真司氏 |
 水島広子氏 |
|
 宮坂信之氏 |
 向井万起男氏 |
 李 啓充氏 |
|
| 春になると本屋がにぎわいます。新しい年度を迎える区切りの時期に,「今年こそは……」と目標を掲げたり,自分の生き方について考えてみようと思う人々が少なくないのでしょう。確かに,すばらしい本との出会いは,人生を変えることすらあるかもしれません。
「週刊医学界新聞」では,今年も,各方面で活躍中の先生方に「医学生・研修医のために私が選ぶこの10冊」をお寄せいただきました。この中に,きっとあなたの探し求めている本があるはずです。読者のみなさんが,すばらしい本と出会うことを願っています。 (執筆者名の五十音順で掲載) |
■青木 眞氏
(感染症コンサルタント)
自分は「人生を語る」タイプの本を薦めることができるほどの人間ではない。純粋に後進の学生,研修医に有用な医学書を紹介する。
(1)Richard K. Riegelman「Studying a Study & Testing a Test : How to Read the Health Science Literature」(Lippincott Williams & Wilkins)
(2)Edgar R. Black「Diagnostic strategies for common medical problems」 2nd ed.(American College of Physicians)
米国に臨床留学する者が最も深く感銘を受けるものを1つだけあげるとすれば,自分に教え込まれる診療行為の根拠となるEBM的な考え方である。その意味では自分も例外ではなく,上記の2冊により,内科医としての目を開かれ基礎を与えられた時の感動は生涯忘れられないものである。1980年代の半ば,通常のジャーナルクラブに加えてPretest probability, Post-test probabilityといった概念に触れさせるEBM教育カンファレンスが,片田舎のケンタッキー大学にすでにあった事実は米国臨床教育の奥の深さを物語る。
(3)Steven A. Haist,他「Internal medicine on call」 2nd ed.(Appleton and Lange)
(4)寺沢秀一,他「研修医当直御法度」 第2版(三輪書店)
(5)植村研一「頭痛・めまい・しびれの臨床」(医学書院)
(6)Larry Waterbury「Hematology for the House Officer」(Lippincott Williams & Wilkins)
(3)はケンタッキー大学で,(4)は沖縄県立中部病院で自分のmentor的存在であった先輩レジデントがその後に大学の教員になり,記した本である。臨床をこよなく愛し日夜ベッドサイド教育に汗を流すこれらの先輩なしに今の自分はあり得ず,彼らの本はまさしく「使える」。その意味で通称「ズ・メ・シ」と呼ばれる。(5)も同様であるが自分のものは研修医に貸したきり遂に戻らない。(6)はHouse officerシリーズとして知られ,苦手な科のものを揃えることを勧める。自分はHematologyやNeurologyなどを愛用した。
(7)Richard E. Reese,他「A practical approach to infectious diseases」 4th ed.(Little Brown)
このマニュアルを一読すると筆者がベッドサイドの人であることが確信される。(おこがましいが)自分が医学書院から出した『レジデントのための感染症診療マニュアル』もこの本に少しでも近づくことが目標であった。
(8)Anthony S. Fauci,他「Harrison's Principles of Internal Medicine」 (McGraw Hill)
感染症のPetersdorf,心臓のBraunwald,神経のAdamsと内科学の巨星たちが築きあげてきた内科学のバイブルである。医学書に「香り」というものがあればまさにそのものである。今でもブドウ球菌感染症や連鎖球菌感染症の章を読んでは鳥肌が立つ経験をさせられる。その意味では『Cecil Textbook of Medicine』も同様。Gerald L. Mandell他の『Principles and Practice of Infectious Diseases』もすばらしいが,専門的に過ぎるので割愛。
(9)Medical Knowledge Self-Assessment Program 12(American College of Physicians-American Society of Internal Medicine)
これを知らずに内科の研修を終えるのはもったいない。卒後3-5年目の内科医が自分の知識を系統的に整理するのに最適である。ジャーナルほど新しすぎず,教科書ほど古すぎない。
(10)Neil W. Schluger「Tuberculosis Pearls」(Mosby)
いわゆるPearlsシリーズで,ファンになる人が多い。当直などで暇をもてあますことがあれば,ベッドに横になりながら読むと時の経つのを忘れる。
■磯野可一氏
(千葉大学長)
(1)信州大学教養部,生命論講座編「いま生命を語る」(共立出版)
(2)田中真澄「デール・カーネギーに学ぶ7つの生きる力」(大和出版)
(3)渋谷直樹「すべての存在へ」(総合協会)
(4)シーア・コルボーン,他「奪われし未来」(長尾力訳,翔泳社)
(5)伊藤 肇「帝王学ノート」(PHP研究社)
(6)日野原重明,斉藤武監修「医の倫理」(HBJ出版局)
(7)森岡恭彦編著「近代外科の父・パレ」(日本放送出版協会)
(8)チェマター・フィールド「わが息子よ,君はどう生きるか」(竹内均訳,三笠書房)
(9)佐藤雅彦,竹中平蔵「経済ってそういうことだったのか会議」(日本経済新聞社)
(10)柳澤桂子「『いのち』とはなにか」(講談社学術文庫)
医師という職業は古来,聖職と言われています。それだけに,医師は肉体的にも精神的にもタフでなければならず,人間的にも尊敬される人でなければなりません。したがって,Science,Art,Humanity,Knowledge,Technique,Attitudeなどと述べられる要素が要求されます。
そこで,医師たるものは生涯かけてこれらの要素を人からの教えにより,自らの体験を通して,書物によって体得しなければなりません。それゆえに,自ら求める書物には医学書の他に,哲学・文学・倫理学・宗教・心理学・社会学など多方面のものが必要であります。
しかし,人間性を含めての素地は,家庭教育の他,小学校から大学までの学生生活の中で,体験と読書を通じて身につけた知識によって培われている部分が大きい。したがって,一人前の医師になって読む本としては,各人が求めていく分野によって必要と思われるもの,特別に興味を持っているもの,自分に不足しているもの,そして当然趣味に関するものなど千差万別でありましょう。また,1冊の同じ本を読んでも感動する部分,意見の不一致の部分,考えさせられる部分など人によって大きく異なるものと思われます。
私は今,書棚に積まれている本の中から,純粋な医学書以外のものとして上記の10冊をあげさせていただきました。ご参考にしていただければ幸いであります。
その中で,(8)を読んで,子を思う父親の愛情を深く感じました。この本の内容は,むろん数百年前のイギリス社会を背景にしたものであり,日本の国に馴染まない部分もありますが,近代社会にも十分通用する事柄も少なくなく,社会のリーダーとして生きていく人には,大切な人生訓の書と言えます。
また(5)は,「雄」「魅」「師」「訓」「流」「戒」「徳」の7部からなっております。私が教授となってから読み始めた本であり,現在も座右の書としてときどき目を通しています。帝王たらずとも,1人の社会人として,専門職業人として,忠実に人生を生き,己を見つめることのできる書として推奨に価すると思います。
■大平整爾氏
(日鋼記念病院・外科/院長)
(1)日野原重明「院内ルールと医師のマナー」(ミクス社)
(2)塩田善朗「外来における患者への説明-よりよい信頼関係を築くために」(南山堂)
(3)中村 明「文章をみがく」(NHKブックス)
(4)中島和江・児玉安司「ヘルスケアリスクマネジメント」(医学書院)
(5)濃沼信夫「医療のグローバルスタンダード」(ミクス社)
(6)日経BP社編「21世紀の医学医療-日本の基礎・臨床科学者100人の提言」(日経BP社)
(7)荒井保男「医の名言」(中公文庫)
(8)池田知隆「日本人の死に方・考」(実業之日本社)
(9)関根清三「死生観と生命倫理」(東京大学出版会)
(10)Thomas E.Starzl「ゼロからの出発-わが臓器移植の軌跡」(加賀乙彦監修,小泉摩耶訳,講談社)
医学生と若い研修医に一読をお勧めしたい本は,実はたくさんあります。大部分の方が近々臨床の場へお出になるのでしょうから,この観点から上記の10冊の本をとりあえず選択してみました。臨床医学は個々の医師に専門性を要求しますが,これをきわめつつ,その専門性が抱え込む社会性と人間性(倫理性)にも大いなる関心を向けなければなりません。
臨床医学(医療)は,医療者と患者・家族との接触,対話から始まるわけですから,当然ながら院内ルールと医師としてのマナーとをしっかりと身につけ,患者への説明がいかにあるべきかを理解しておく必要があります。
この意味で(1),(2)をお読みいただきたいのです。現代医療は「無言実行」だけでは不十分であり,また,「巧言令色鮮(すくな)し仁」と嘯(うそぶ)くわけにもまいりません。必要な時には十二分の話し合いを旨としなければならず,したがって医療人は対話の達人をめざさなければなりません。
また,話すことの訓練と同時に,平易で明解な文章をものにする技量も要求される点から,(3)をお勧めします。医療には絶えず種々のリスクがつきまとうわけであり,(4)で心を引き締め個人的および組織的なリスクマネジメントの概要を学びましょう。
(5),(6)で日本の医療が全世界的に見てどのような立場にあるのか,第一線の先達が新世紀の医学・医療にいかなる提言をされているかを知っておきたいと考えます。(7)には多くの医の明言が盛られており,心に響くものを座右の銘としてご記憶ください。命と日々相対する臨床家は,生と同時に死とも無縁ではあり得ません。(8),(9)で,医療人が身につけるべき生命倫理を学んでほしいと思います。
(10)は,臓器移植,特に肝臓移植の分野で世界的な権威であるStarzl博士の苦闘と勇気に満ちた壮絶な自叙伝です。同じ外科・移植外科をめざした私自身には,きわめて印象的な半生記であり,困難を乗り越える勇気を与えてくれたものでした。「切った貼った」の外科は,時に即物的な側面のみが強調されがちですが,Starzl先生はご自分の領域の仕事に深い哲学的な洞察を加えており,彼の波瀾万丈の生涯とともに,心を打ち考えさせられます。本著は臓器移植にどのような立場をとるにせよ,また,移植以外の領域へ進む人々にとっても,一読に値する書物としてお勧めしたいものです。
Starzl先生は,来札の折りに北大構内のクラーク博士像に刻まれた“Boys, be ambitious.”をご覧になって,“Boys, be ambitious for what?”と漏らされたと聞き及びます。皆さんには大きな希望・大志を持っていただきたい。そして,それが次第に明確なものになることを願います。
名著一読が,必ずやこの一助になると思います。
■斎藤 学氏
(家族機能研究所代表・精神科医)
(1)ジグムンド・フロイト「フロイト著作集3 文化・芸術論」(高橋義孝他訳,人文書院)
(2)アリス・ミラー「魂の殺人」(山下公子訳,新曜社)
(3)ジュディス・L・ハーマン「父-娘近親姦」(斎藤学訳,誠信書房)
(4)アンリ・エレンベルガー「無意識の発見(上・下巻)」(木村敏,中井久夫監訳,弘文堂)
(5)テレンス・W・ディーコン「ヒトはいかにして人となったか」(金子隆芳訳,新曜社)
(6)山極寿一「家族の起源-父性の登場」(東京大学出版会)
(7)クロード・レヴィ=ストロース「親族の基本構造」(福井和美訳,青弓社)
(8)神庭重信「こころと体の対話-精神免疫学の世界」(文春新書)
(9)柳澤桂子「認められぬ病-現代医療への根源的問い」(中公文庫)
(10)ドナ・ウィリアムス「自閉症だった私へ」(河野万里子訳,新潮社)
フロイト著作集(人文書院)の中から1冊を選ぶとすれば,私の場合,「文化への不満」と「トーテムとタブー」が収載されている第3巻になる。私はこの2編と17歳の頃(当時は日本教文社版・第6巻)に接し,これに導かれるようにして精神医学の世界に入った。「文化への不満」という社会評論的な著述は,当時の私にも理解できたように思え,人類の未来に対する絶望的な筆致に,私は今でも共感してしまう。一方,「トーテムとタブー」に盛られた壮大な文化論は幼い私を魅了したが,これは結局,ヒトという動物が,なぜ人間になったのかという疑問への入り口だったのであって,その後,多数の著作がこの魅惑的な問いに答えようとしていることを知った。ここにはディーコン,山極,レヴィ=ストロースのものだけをあげた。
私は「家族」や「親族」という者の形成が,人を動物から分けたと思う者の1人で,患者の精神医学的訴えを聴取する時にもこのことを念頭に置いているのだが,この視点はレヴィ=ストロースの英訳本から教えられた。最近,日本語の改訂訳で読めるようになったのはありがたい。
ハーマンの著作としては,ここにあげたものより有名な『心的外傷と回復』(中井久夫訳,みすず書房)があるが,「家族の形成とその歪み」というテーマに鋭く切り込んでいるという点で,私は,ここにあげた著作のほうを高く評価している。近親姦禁止というタブーの内面化は,その失敗例を通してこそ,はっきりと見えてくる。ハーマンが研修医だった頃,近親姦の被害を訴える女性患者について指導医に相談すると,「それは嘘か幻想だ」と片づけられたという。それまで,常識とされてきたことを疑うところから新しい何かが始まることを改めて教えてくれる本でもある。
神庭の本は,精神・心理領域とされてきた問題が身体医療と不可分であることを知る格好の入門書と思う。柳澤とウィリアムスの本をここにあげたのは,研修医の段階で患者とされた者の痛みをきちんと把握しておいていただきたいと思うからである。
■瀬戸山元一氏
(高知県・高知市病院組合理事)
(1)ウィリアム・オスラー「平静の心」(日野原重明・仁木久恵訳,医学書院)
(2)金子みすゞ「金子みすゞ全集」(JULA出版局)
(3)ヘルマン・ホイヴェルス「人生の秋に」(林幹雄編:春秋社)
(4)日野原重明「死と,老いと,生と」(中央法規)
(5)フィリップ・アリエス「死を前にした人間」(成瀬駒男訳,みすず書房)
(6)L.ロンハバード「ダイアネティックス」(トランスレーション・ユニット東京編,ニュー・エラ・パブリケーションズ・ジャパン)
(7)ヒポクラテス「ヒポクラテス全集」(今裕編,岩波書店)
(8)プラトン「プラトン II」(田中美智太郎編,中央公論)
(9)アルビン・トフラー「第三の波」(徳山二郎編,日本放送出版協会)
(10)瀬戸山元一「ホントに患者さん中心にしたら病院はこうなった」(医療タイムス)
今日までの日本の医療の中にあって,医師の姿勢についての表現として「知らしむべからず,寄らしむべし(瀬戸山造語)」という言葉ほど適切なものはないであろう。それは医師の神格化と,患者に対する非人間的対応を意味しているとも言えなくない。それは,「研究室医学」の重要視と,日本型「パターナリズム」の拘泥という,大学医局講座制の中で成立し得た日本独特の歴史的産物でもある。
ところが,社会環境の激変に伴って,医療環境の変化が余儀なくされている今日においてもなお,この概念が生き続けているようにも思える。その背景には,古くから培われた医師に対する日本人特有の意識が介在しているように思われる。そこには,医療行為の基本となる高度な科学とモラルを修得し,我欲を捨て,すべての病める人に一視同仁の医術を施す,人格陶冶された人間医師像が尊敬と信頼を生んで存在していたのである。
しかし現代では,患者さんと医師との間に,このような対人関係とはいささか趣を異にする精神構造が存在している。それは高度に機能化された社会体制の中で,経済的基盤に裏打ちされた文化の意識構造からくる人間不信である。
そして,生じた不信の解消策として,より必要とされる尊敬と信頼を取り戻すべく努力を怠り,契約という物的証拠に頼りがちになる医師の姿勢であると言える。契約は欧米においては今日的慣習ではなく,例えば「シナイ契約」のような信頼関係が宗教的背景としてある。しかし,このような慣習は宗教心理を保有しない日本人の特性も関与して,日本社会の長期にわたる文化醸成の中で異質文化であり,一方では契約そのものは猜疑心を目芽えさせる側面をも有している。
とはいうものの,国際社会の一員としての日本は,好むと好まざるとにかかわらず,国際経済の先導役として文化の融合も図らねばならない時代を迎えている。このような社会状況のもとで,やはり医療の枢軸にある医師の立場とその社会性は,百花繚乱の医療論の中で大きく変貌せざるを得ない。すなわち,文頭に述べた言葉に代表される医師の姿勢そのものの瓦解は避けられず,新しい医師のあり方を思考しなければならない時代であると言える。
そこで,次世代の医学界,医療界を担う若い方々に,オスラーの教育論(『平静の心』より)を紹介して私の推薦とする。
「若い人はあらゆる世代の偉大な精神の持ち主が書き残した記録や本を読んで勉強すること,また,自然科学の美しい調和のとれた環境をよく観察すること,そして,仲間の人々の生き方の善し悪しがわれわれに及ぼす影響,まさにこれらがわれわれを教育し,発達過程にある精神を形成する」
■西澤潤一氏
(岩手県立大学長)
(1)山本周五郎「赤ひげ診療譚」(講談社)
(2)宮澤賢治「銀河鉄道の夜」(新潮文庫)
この2冊は,医学を志す方々に懐いてほしい心のロマン。
(3)司馬遼太郎「世に棲む日々」(文春文庫)
(4)ニーチェ「ツァラトゥストラはこう言った」(岩波文庫)
(5)キルケゴール「死に至る病」(岩波文庫)
以上の3冊は,人間の生きざまを強く訴える。
(6)平家物語(岩波文庫)
日本人の人生観。
(7)クローニン「帽子屋の城」(三笠書房)
(8)宮城谷昌光「重耳」(講談社文庫)
(9)トルストイ「戦争と平和」(岩波文庫)
(10)ブリッジマン「現代物理学の論理」(創元科学叢書)
現代社会の仕組みを考えていただくための書としては,(6),(7)をあげました。
山崎豊子『白い巨塔』(新潮社)とか,山本周五郎『樅の木は残った』(新潮文庫)なども同様の傾向で,いろいろと考えさせられる本だと思います。考えてください。
(8)は,要するに「人間は徳が大切」と語ってくれるし,(9)はロジェ・マルタン・デュガール『チボー家の人々』(白水社)と同じような社会の動きと人間の無力を悟らしめます。
(10)は,自然科学と言うより科学とは何か,ということを強く考えさせてくると思いますが,少々難解で,しかも現在絶版だと思います。しかし,よく読むと自然科学に限らず,「科学とは何か」ということを,根本的に教えてくれると思います。
■古川俊治氏
(慶應義塾大学・外科)
どんな時代にあっても,医療は人間生活を豊かにし,人間の幸福に役立つ技術である必要がある。今後の人間生活は一層流動的になり,価値観はますます多様化してくるものと考えられ,医療者として重要なのは,医療の外側から社会を考察する理論枠組を持っていることだと思う。その意味で,医学から離れた分野で,「この本」というよりは,数冊を通じて「この人」を読み,思想家の体系的な考え方に触れるとよいと思う。
以下にあげる本は,ほとんどがすでに歴史的著作となっているが,なお,現代に生きる視座を提示していると思う。
(1)A.カミュ「異邦人」「ペスト」「シーシュポスの神話」(新潮文庫)
(2)J.-P.サルトル「存在と無」「弁証法的理性批判」「自由への道」「実存主義とは何か」(人文書院)
(3)太宰 治「人間失格」(新潮文庫)
(4)V.E.フランクル「夜と霧」(みすず書房),「それでも人生にイエスという」(春秋社)
(5)M.フーコー「臨床医学の誕生」(みすず書房),「言葉と物」「狂気の歴史」「性の歴史」(新潮社)
(6)P.L.バーガー「日常世界の構成」「聖なる天蓋」(新曜社)
(7)K.R.ポパー「科学的発見の論理」(恒星社厚生閣)
(8)J.ハバーマス「イデオロギーとしての技術と学問」(紀伊国屋書店)
(9)E.H.カー「歴史とは何か」(岩波新書)
(10)J.K.ガルブレイス「豊かな社会」(岩波書店)
(1),(2)は,第二次世界大戦後の新しい価値観をリードした実存主義の代表的思想家であるが,その視点は,現代において人間存在を考える上でも生きていると思う。私にとっては,中学・高校時代から親しんだ思想家たちで,個人としての生き方を考える上で,強い影響を受けた。[異邦人]は,人間の不条理を鮮やかに描き得た歴史的名作である。(3)を,筆者の陰惨たる正体と見るか,人間のあり方の根本に関わる切実な問題と考えるかは,評価が分かれるところであろうが,私は後者である。(4)は,人間の尊さと生きる意味を語った万人の認めるすばらしい作品。(5)は,私が最も多く学び,最も影響を受けた思想家である。著作の多くは,社会的な権力が人間を抑圧していく構造を,理論的に考察しているものであるが,人生哲学から科学の方法論まで,広く適用可能な視座を提示している。(6)は,知識社会学・宗教社会学の秀作であり,人間の日常意識の憶測や宗派的偏見を理論的に検討したものである。さらに(7),(8)は,科学哲学における古典的名著であり,科学のイデオロギー性を明らかにしている。専門的知識の内側からは見出しがたい本質論としての批判的視点であり,医学・法学を問わず専門家として生きる上で,非常に貴重な考え方を学んだ。(9)には,知らず知らずのうちに受け入れてきた歴史観について,新たな認識を与えられ,大いに教えられた。(10)は,現代を代表する経済学者であり,他の著作とともに,経済的視座からの現代社会に対する卓抜した洞察であると思う。
■松村真司氏
(松村医院/東京大学医学教育国際協力研究センター)
(1)日野原重明,阿部正和「対話 医のアートとは」(バイエル・ブックレット・シリーズ)
(2)D.L.Sackett,他「Clinical Epidemiology」(Little Brown)
(3)飯島克己「外来におけるコミュニケーション技法」(日本医事新報社)
(4)坂口安吾「肝臓先生」(角川文庫)
(5)宮子あずさ「気持ちのいい看護」(医学書院)
(6)星野道夫「旅をする木」(文春文庫)
(7)岡崎京子「リバーズ・エッジ」(宝島社)
(8)トルストイ「民話 人はなんのために生きるか」(角川文庫)
(9)中島 敦「李陵・山月記」(角川文庫)
(10)佐野元春「ハートランドからの手紙」(角川文庫)
医師という職業を選ぶということは,多かれ少なかれ他者の生命とかかわっていくことを意味します。科学としての医学がこのかかわりにおいて一定の役割を果たしていることを否定するつもりはありません。しかし,医師としての生活の中では,音楽・文学・芸術・自然など,医学以外のことすべてが私たちを助けてくれます。それが何かは人それぞれ違うでしょうし,強要するつもりもありません。ここでは,個人的にこれまで私の心に響いたものの一部を紹介するにとどめます。何かの参考に。
(1)1988年に製薬会社が発行した小冊子なので,今では入手困難だと思いますが,プライマリケアへと自分を導いたものですので,あえてここにあげました。対談の最後で,阿部先生は「結局医療は言葉に始まり言葉に終わるのです」,日野原先生は「医学はますます学際的になるだろう」と締めくくっています。
(2)レジデント時代に出会った,臨床問題解決のための基本的な考え方を教えてくれる名著です。EBMに関して,今では数多くのよい解説書がありますが,あえて本家の1冊を。
(3)コミュニケーションの本も最近はたくさんよい本がありますが,気軽に読めて,安くて,役に立つという点ではこの1冊がおすすめ。
(4)大学にいるとなかなか見えませんが,日本にはずっと昔から町医者というすばらしいプライマリケア医がいます。グローバル・スタンダードにとらわれて足もとを見失いがちなプライマリケア志向の学生・研修医のために。
(5)高尚な理論より,現場の泥臭い言葉のほうが真実を雄弁に語ると思います。この本の中に出てくる,「正解は1つではない」という言葉を,試験に追われる学生さんたちへ。
(6)-(9)研修が進み,ある程度臨床能力がつきはじめると,医療技術を習得するだけでは問題は解決しないということを実感するようになります。生きる,病気になる,死ぬ,そしてまた生まれる。くり返す日々の生活。なぜ,人間にはこのようなことがあり,それにどうかかわっていけばよいのか。答えは見つかりませんが,文学・映画・音楽・芸術,何にでも触れ合って,いろいろな人といろいろな話をすることから始まると思っています。
(10)最後に,「プライマリケアをきちんと学びたい」のように,たとえ自分の中ではやりたいことがはっきりしていても,世の中うまくいかないことばかりです。「くだらねえ世の中,くだらねえ俺たち,そんなの縄文時代から現代まで全然変わってねえんだよ」とエレカシ宮本も歌っています。すべての価値観の変動期である今,既成の概念にとらわれず,しっかりした内的規範を持ち,それにしたがっていくことが大事だと私は思います。
君の心の中のナイーブさを守れ。
良質なユーモアとワイルドな理知をもって。
君の心の中のナイーブさを守れ。
そして……誰にも知らせるな。
(ハートランドからの手紙 #34より)
■水島広子氏
(衆議院議員・精神科医)
(1)岩田隆信「医者が末期がん患者になってわかったこと」(中経出版)
(2)本多勝一「はるかなる東洋医学へ」(朝日新聞社)
(3)本多勝一「日本語の作文技術」(朝日新聞社)
(4)神庭重信「こころと体の対話-精神免疫学の世界」(文春新書)
(5)ジュディス・L・ハーマン「心的外傷と回復」(中井久夫訳 みすず書房)
(6)上野千鶴子「近代家族の成立と終焉」(岩波書店)
(7)大塚敬節「漢方医学」(創元新書)
(8)岡本祐三「高齢者医療と福祉」(岩波新書)
(9)水島広子「親子不全=<キレない>子どもの育て方」(講談社現代新書)
(10)水島広子「『やせ願望』の精神病理 摂食障害からのメッセージ」(PHP新書)
(1)は,私の大学の先輩にもあたる脳外科医の故・岩田隆信氏が,ご自身が脳腫瘍になっての経験を書かれた貴重な1冊。私が慶応大学病院に勤務していた時に入院しておられたが,関係した多くの医療者がさまざまなことを学ばせていただいたようだ。ご夫婦の共著による続編もおすすめ。
(2)は,現代西洋医学との対比の中で東洋医学の特長をわかりやすく述べた1冊である。私は本多勝一氏のルポルタージュが好きで愛読していたが,まさか氏が私の専門分野の1つである東洋医学礼賛の著書を出すとは思ってもいなかったので,とても驚いた。
実際に読んでみると,社会について自分と同じようなことを考えている人は,医学についても同じようなことを考えるのだな,と改めて感心した。ジャーナリスト特有の懇切丁寧な説明に加え,医療サイドではなく,あくまでも医療を受ける側の立場で書かれているという点でも,価値のある1冊だと思う。
東洋医学は,日本で大きく発展した医学でありながら,明治以降の日本では「非科学」「二流」のレッテルを貼られ,主流派からは軽視されてきた。最近では日本よりも欧米で熱心に研究されており,日本も追随しなければならない立場になってきた。そんな状況下,この本を「非科学的で無意味」と切り捨てるようでは,人間という複雑な対象を適切に扱うことはできないと思う。
同じく本多勝一氏の(3)は,「日本語は論理的な言語ではない」などという誤解を解いてあまりある名著。論文を書く上でも,また,患者さんと正確なコミュニケーションをするためにも,日本語能力は重要である。医学においては英語の文献を読み書きする機会のほうが多いが,日本語で論理的な思考ができないようでは,英語も同レベルにとどまってしまうと思う。日本語のテキストとして他に例を見ない名著。
■宮坂信之氏
(東京医科歯科大学教授・内科学)
(1)多田富雄「免疫の意味論」(青土社)
(2)秋山秀樹「日本のインフォームド・コンセント」(講談社)
(3)「言いたくても言えなかったひとこと-医療編」(ライフ企画)
(4)保阪正康「大学医学部の危機」(講談社)
(5)奈良信雄「地獄の沙汰も医者次第-問われる医療システムと医師の資質」(集英社)
(6)米国医療の質委員会「人は誰でも間違える」(日本評論社)
(7)李 啓充「アメリカ医療の光と影-医療過誤防止からマネジメントケアまで」(医学書院)
(8)赤津晴子「続アメリカの医学教育」(日本評論社)
(9)青木冨貴子「星条旗のアメリカ」(文藝春秋)
(10)青木冨貴子「たまらなく日本人」(文藝春秋)
(1)生体は「自己」と「非自己」を識別することによってそのアイデンティティを確立し,自らを「病気(疫)」から守っている。この免疫の意味を超システムとしての生命という観点から論じたスケールの大きな本。
(2)わが国に臨床試験(治験)が導入されて久しいが,未だその正確な理解は医師側にも患者さんの側にも十分にはなされていない。著者は臨床の現場から,日米における臨床試験とインフォームド・コンセントの差異と問題点を紹介しながら,そのあり方を論じている。その続編とも言うべき『むしばまれる医療』(日本評論社)もおもしろい。
(3)患者さんおよびその家族,あるいは医療現場で働く人々が寄稿した医療に関する珠玉の短文集。思わず心にグサリと突き刺さるような厳しい一言が書かれており,ハッとする。
(4),(5)いずれも大学医学部の問題点や日本の医療の問題点を鋭く指摘している本である。国立大学医学部附属病院は独立行政法人化を目前に控え,構造上および意識上の大改革が迫られているため,私にとっては余計に興味深い。
(6)昨今,わが国における大学病院での医療過誤の多発が注目されており,明日はわが身と常に思うこの頃である。しかし,ただ単に「上意下達」で叱咤激励しているだけではこの問題は解決しない。本書は,ヒューマン・エラーは起こることは当たり前であるということを前提にしながら,より安全な医療システムの構築を指向するにはどうしたらよいかということを考えさせてくれる。
(7)アメリカにおける医療過誤の歴史と対策,医療経済事情などが赤裸々に語られている。また,アメリカ医療のグローバルスタンダードである「トランスペアレンシー;透明性」と「アカウンタビリティー;説明責任」の重要性を改めて感じさせられるとともに,日米の医療文化の違いを思い知らされる。
(8)日本の医学部の学生は勉強させられていると感じており,みずから勉強しようという意欲が欠けている。また,自分の頭を使う問題解決型思考ができずに,すぐに他人に頼りたがる傾向が大である。この本は,Good Doctorを育てるためには何が必要か?という点できわめて示唆に富んでいる。
(9),(10)私は自分が留学し,大きな影響を受けたアメリカにはいつまでも興味が捨てきれない。アメリカに移住した日本人が,無意識のうちにも日本と対比しつつアメリカ文化を論じている逸品。著者の歯切れのよい書き方に共感。
■向井万起男氏
(慶應義塾大学助教授・病理診断部)
(1)渡辺淳一「白き旅立ち」(新潮社)
(2)司馬遼太郎「胡蝶の夢」(新潮社)
(3)スティーヴン・ジェイ・グールド「ワンダフル・ライフ-バージェス頁岩と生物進化の物語」(早川書房)
(4)E・シュレーディンガー「生命とは何か-物理的にみた生細胞」(岩波書店)
(5)マイケル・ブリス「インスリンの発見」(朝日新聞社)
(6)ジョン・シーハン「ペニシリン開発秘話」(草思社)
(7)エブリン・フォックス・ケラー「動く遺伝子-トウモロコシとノーベル賞」(晶文社)
(8)立花隆「人体再生」(中央公論新社)
(9)リサ・ベルキン「いつ死なせるか-ハーマン病院倫理委員会の六カ月」(文藝春秋)
(10)李啓充「アメリカ医療の光と影-医療過誤防止からマネジドケアまで」(医学書院)
(1)元整形外科医の渡辺淳一の作品。日本における志願解剖第1号が吉原の遊女であった,という歴史的事実に基づいて書かれた小説。これを聞けば,もう読まずにいられなくなるはずだ。とにかく読み応えのあるおもしろい小説である。感動的な人間ドラマであることは言うまでもなく,日本における医学の歴史を江戸時代・維新まで遡って学ぶ上でも参考になる。読み終わった後,深い感動を覚えること間違いなし。
(3)この10年間で,私に最も知的興奮を与えてくれた本である。「すばらしい」の一語に尽きる本。1909年,カナディアン・ロッキー山中のバージェス頁岩から発見された五億年前のカンブリア紀の奇怪な化石群。この化石群の発見者で当時の米国古生物学会の権威者は,既存の節足動物の分類にこだわり,この化石群を既存の分類におさめてしまった。しかし,その半世紀後,3人の研究者たちが地道な研究の末,この化石群に対して驚くべき新解釈を提示する。
革新的な研究とはいかにしてなされるかということを教えてくれるだけではなく,生物の進化の偶発性,生命のおもしろさ・すばらしさを教えてくれる。多くの図版を駆使しながら,多少難しい文章で書かれた本であるが,なんとか半分くらいまで我慢して読み続けると,後は一気呵成に読める。そして,読み終わった後,この世界を見る目が変わるはずだ。人生観も変わるかもしれない。
(9)世界最大の医療複合体「テキサス・メディカル・センター」で最も歴史の古いハーマン病院を「ニューヨーク・タイムズ」紙のレポーターが取材した医学ノンフィクション。末期医療における倫理委員会の役割といったことなど,今日の医療の重要問題を扱っている。ハーマン病院の倫理委員会の議長は看護婦であるということを日本の医師,医学生は知っておくべきだろう。
■李 啓充氏
(マサチューセッツ総合病院・内分泌部門)
(1)Roxanne K. Young編「A Piece of My Mind」(AMA Press)
20年以上続いている「JAMA」誌の同名コラムからの選集。医師たちがその喜び・悲しみの体験を綴る感動のエッセイ集。
(2)William Broad & Nicholas Wade「Betrayers of the Truth: Fraud and Deceit in the Halls of Science」(A Touchstone Book)(邦題「背信の科学者たち」牧野賢治訳,化学同人)
科学におけるデータ捏造・剽窃の歴史を詳述,科学の本質について考えさせる。著者の1人Nicholas Wadeは「ニューヨーク・タイムズ」紙の科学部論説委員。同紙の毎週火曜日の医療・科学欄はきわめて質が高いので,本書とともに強く推薦したい。
(3)Jerry E. Bishop & Michael Waldholz「GENOME」(Simon & Schuster;邦題「遺伝子の狩人」牧野賢治,他,化学同人)
今年2月にヒト遺伝子全マップが発表されたが,ヒトゲノムプロジェクトの起源となった時代の分子生物学の革命的進歩を紹介する。遺伝病患者および家族の努力と熱意が研究を推進した事例が感動的に描かれる。
(4)井村裕夫「生命のメッセンジャーに魅せられた人びと-内分泌学の潮流」(羊土社)
元京大学長である著者が内分泌学の現状と歴史を詳述する。最終章は,「若い人々に捧げたい」と,筆者が現在勤務するマサチューセッツ総合病院内分泌部門の創始者フーラー・オーブライトの感動的生涯を紹介している。
(5)Gregory E. Pence「Classic Cases in Medical Ethics」2nd ed(McGraw Hill)
医療倫理の基礎について,歴史的な事例・判例をもとにわかりやすく詳述する。
(6)Robert Marion「The Intern Blues」(Ballantine Books)
ニューヨークの一病院の小児科インターン3人の研修実録。米国の卒後臨床研修の厳しさを伝える。
(7)北村叔子「退院勧告」(自由工房),Christopher Reeve「Still Me」(Random House)
北村叔子は某国立病院の元婦長。ご子息がある日突然,四肢麻痺となった後の苦闘を描く。筆者はこの書を文字どおり「息が詰まる」思いで読んだ。一方,Christopher Reeveはスーパーマンを演じるなどその肉体の頑健さを誇った俳優。落馬事故で四肢麻痺となった自己の体験を綴る。題名の「Still Me」は「動けない私だが,それでも自分であることに変わりはない」というかけことば(ダブル・ミーニング)。両書を読み比べると,脊損患者の支援体制についての日米の格差に愕然とせざるを得ない。
(8)John Irving「A Son of the Circus」(Ballantine Books)(邦題「サーカスの息子」岸本佐知子訳,新潮社)
主人公は軟骨発育不全症の原因を探求しようとする整形外科医。冒頭部に「誰もこの病気の遺伝マーカーを見つけていないし,一流の遺伝学者は誰もこの病気には興味を示そうとしない」と書かれたが,本書の出版直後に原因遺伝子が同定され,著者が同定した学者に本書を贈呈した話は有名。ちなみに,軟骨発育不全症は筆者の現在の研究テーマであるし,主人公のインド人医師がカナダで暮らす苦労は,同じ「移民」として身につまされ,個人的思い入れが強い本である。なお,著者が原作・脚本を担当した映画「サイダーハウス・ルール」は中絶・偽医者作りがテーマとなった名画。
(9)Robert Whiting「You Gotta Have Wa」(MacMillan)(邦題「和をもって日本となす」玉木正之訳,角川書店)
日本でプレーした「外人選手」に焦点を当て,野球を通じて日米文化の違いを際立たせる。分野は違うとはいえ,米国留学希望者には参考となろう。
(10)Neil Ravin「Informed Consent」(G.P. Putnam's Sons)(邦題「インフォームド・コンセント」李啓充訳,学会出版センター)
「インフォームド・コンセント」という言葉が日本で流行りだした80年代中頃に読み,「目から鱗が落ちる」思いを味わった小説。その後,10年がかりで翻訳し,98年に出版にこぎつけた。著者によると,本書はカナダのある医学部で「患者-医師関係」の教材に使われたとのことで,インフォームド・コンセントの真の意味を理解するために,学生,研修医にぜひ勧めたい。


