【座談会】
アウトカム評価におけるQOL研究
 池上直己氏<司会> 慶應義塾大学教授 医療政策・管理学 |
 福原俊一氏 京都大学大学院教授 医学研究科理論疫学分野 |
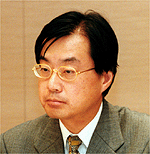 下妻晃二郎氏 川崎医科大学講師 乳腺甲状腺外科 |
 池田俊也氏 慶應義塾大学講師 医療政策・管理学 |
「QOL研究」について
池上〈司会〉 本日は「アウトカム評価におけるQOL研究」をテーマに座談会を行ないたいと思います。まず,「アウトカム評価」という言葉について説明しますと,アウトカムというのは,治療の結果を指すわけですが,最近の臨床現場では,「一命を取りとめた」というような明確な治療結果が出ないことがあります。特に,生活習慣病や慢性疾患がそれに該当します。そこでこれらを総合的に判断して,「どの程度よくなったのか」ということを判定する必要が生じてきました。その際に「検査値」や「医師の所見」だけでなく,「患者の視点」から判定する必要性が認識され,「アウトカム研究において患者のQOLを客観的に計測する」ことが重要になってきました。最初に,福原先生,このアウトカム評価におけるQOL研究についてご説明願えますか。
福原 まず,池上先生が解説されたアウトカム研究そのものが医療評価研究として非常に重要であることを申し上げたいですね。そして医療評価のために行なう時,QOL研究もアウトカム研究の一部であり,特殊視する必要はないということです。これまで,QOL研究というと曖昧で科学的に測定できないようにみられていました。しかしアウトカム研究の流れの中で,欧米ではすでに20年ほど前から,QOLは重要な「患者立脚型アウトカム(Patient-based outcome)」の1つであり,しかも科学的に測定し定量化できるものであるという認識が定着し,スタンダードな尺度も開発され広範に使われるようになりました。一流の雑誌にもアクセプトされる論文が出ています。例えば,現在UCサンフランシスコ校内科部長のリー・ゴールドマン(Lee Goldman)教授が行なったペースメーカー治療をQOLで評価する研究の結果は,雑誌“New England Journal of Medicine”(1998)の巻頭論文として発表されました。
「包括的尺度」
池上 QOL研究にはさまざまな側面があって,大きく分けると,患者の状態を問わず包括的にQOLを測る「包括的尺度」と,それぞれの病気の側面に着目する「疾患特異的尺度」があります。福原先生,次に「包括的尺度」についてご説明いただけますか。福原 包括的尺度というのは,その測定対象を特定の疾患を持つ患者に限定しないQOL尺度です。しかも,病気を持っていない,いわゆる「健康人」を対象にしても利用可能であることも大きな特徴です。これまで,臨床家は患者さんを「病気の人」と「病気でない人」という2つのカテゴリーに分類することを学び,実践してきたと言えます。しかしQOLの観点からは,はたしてこういう二元的な考え方が妥当かどうかという疑問があると思います。すなわち,「健康人」にも「病気を持っている人」にも適用が可能な包括的尺度を使うことによって,健康状態を連続的に捉えることが可能になりました。これは包括的尺度の特徴の1つで,SIP(Sickness Impact Profile),NHP(Nottingham Health Profile),WHOQOL,SF-36(MOS-Short Form 36)などの指標があります。
池上 中でも,「SF-36」が国際的に最もよく使われ,妥当性が証明されている標準的な指標ですが,その理由は何でしょうか。
福原 それは健康人も病人も選ばない包括的な尺度であるということと,誰でも簡単に理解し短時間に答えられる簡便性,また測定する内容を健康に起因する基本的な要素に限定していること,そしてもう1つはタイミングもあったと思います。
アウトカム研究の重要性が指摘され始めたのは今から20年ほど前で,その先駆けは1980年代中盤に行なわれた「Medical Outcomes Study(MOS)」です。これは糖尿病,高血圧,心疾患,関節疾患などの主要な慢性疾患を有する,全米の5大都市に在住する外来患者を対象にした縦断的な観察研究です。この研究では,死亡率,罹患率,合併症の発症率,医療費の消費など,さまざまなアウトカム指標が用いられました。さらに「患者立脚型のアウトカム指標」であるQOLを主要なアウトカムとして用いたことは,当時は画期的なことでした。SF-36はこの研究で用いられましたが,「MOS質問票(ロングフォーム)」という尺度はその原型でした。このロングフォームは100以上の項目があって,記入に30分以上もかかり,回答者に大きな負担を強いました。そこで,その計量心理学的な特性を損なわない範囲で36項目までに減らし,その結果,ほぼ5-10分で,16歳以上の成人であれば誰もが理解でき,回答できる尺度を作り上げたわけです。
そして,1990年から先進7か国で協力した「国際QOL研究プロジェクト」が開始されました。これによって,SF-36が北米だけではなく,国際的に汎用される尺度として使われるようになりました。
下妻 計量心理学的なものを損なうことなくショートフォームにしたということですが,QOLの概念の構造も変わっていないのでしょうか。
福原 ええ。もともと「身体」と「精神」という2つの基本的な概念的枠組みの下に,さらに8つの下位尺度の仮説をもとに作られた尺度で,ロングフォームでもショートフォームでも不変の構造です。しかし,この8つの下位尺度の仮説が他の国でも妥当であるのかをみるためには,この国際QOL研究プロジェクトを行なう必要がありました。SF-36に限りませんが,健康に関連したQOLを測定するための尺度では,「身体機能(Physical Functioning)」「メンタル・ヘルス」(これは主にどの程度落ち込んでいるか,不安であるかという基本的な心理状態),そしてWHOの健康の定義もあるように,健康状態によって社会的機能が妨げられていないかという「社会生活機能(Social Functioning)」の3つの基本的な構成要素を含んでいることがほとんどです。さらに仕事や家事などの「日常役割機能(Role Functioning)」が含まれることも一般的です。このへんについては,下妻先生のご意見をお聞きしたいのですが。
下妻 1947年のWHOにおける健康の定義では,健康とは,「単に病気でない状態を指すのではなく,身体的,心理的,社会的に満足のいく状態にあること」とされ,1998年にはさらに踏み込んで,霊性・実存面(スピリチュアリティ)のよさも定義に含めるかどうかについて議論されているところです。このWHOの健康の定義が,元来QOLの概念を考える際の拠り所とされてきた経緯があり,それから考えると,身体機能や精神状態,日常役割機能のみでは,QOLの概念構造としては不十分という考え方がありうると思います。
しかし,われわれが測定・評価したいのは,QOLの中でも特に,医療やケアの介入によって,改善あるいは悪化しうる可能性のある領域(いわゆる,健康関連QOL)ですから,SF-36が主に含む概念構造は妥当と思います。後で述べますような,ある疾患や治療特異的なQOL評価においては,介入によって変化しにくいと予想される社会面や霊性・実存面のQOLについても,必要に応じて注意深く測定・評価する,ということでよいと思います。
福原 特にスピリチュアルな問題などは,文化的,宗教的な側面にかなり影響を受けます。QOLのどのような要素を測定するかは,研究者の目的によって使い分ければよいと思います。その中で,「身体機能」「メンタル・ヘルス」「社会生活機能」「日常役割機能」は,健康に関連するQOLを構成する最も基本的な要素で,比較的文化的な影響を受けないと考えられ,国際的にもかなりコンセンサスが得られています。
池上 どうして多次元的に見る必要があるかと言うと,生活習慣病などで長期にわたって薬剤を投与された場合,身体面の改善はみられても,精神面で例えばうつ症状が出てくることもあります。また,精神面の機能が低下し,その結果,社会生活機能面も低下することがあります。今まで医師は,とかく身体のある断面だけを診がちでしたが,それでは患者の総合的なQOLは改善されていないという問題もあったわけです。QOLの効果測定という点では,包括的尺度であろうと,疾患特異的尺度であろうと,多次元的にみる必要があることには変わりありません。
福原 おっしゃるとおりです。これに関してですが,「身体機能」はMETSのような客観的な指標を用いればよい,「精神状態」はSDSのような特異尺度を使えばよいではないかという議論があります。しかし,慢性疾患がほとんどを占める現代にあっては,患者であっても日常生活を送る生活者であり続けます。QOL尺度は,生活者としての言葉で表現された項目で構成されており,このような尺度を用いることによって,患者の健康度や機能状態を,患者の日常生活の言葉に還元して理解するデータを得ることができます。このようなところにQOL尺度のQOL尺度たるゆえんがあるのではないかと考えています。
「選好に基づく尺度」と「効用理論」
池上 「アウトカム評価」が重要になってきたもう1つの理由に,医療費の高騰があります。これだけのお金を投入してどれだけ社会全体の福祉が向上したかという視点,わかりやすく言えばコストパフォーマンス,つまり「費用対効果」ということです。新しい薬剤や技術を投入したときに,従来と比較してどれだけ向上したかということです。これを,エビデンスとして見せる必要が生じてきたので,QOL尺度の中には経済的評価のために用いられている尺度もあります。その点について,池田先生から説明をお願いできますか。池田 「選好に基づく尺度(preference-based measure)」は,患者さんのQOLを多面的に捉える質問紙ですが,最終的に単一のサマリースコアが算出できるという特徴をもつQOL尺度です。領域によって優劣が別れる場合,最終的な価値判断をどうするかという点が,いわゆる多次元的QOL尺度では困難な場合があります。期待効用理論というモデルに従ってこれを単一の尺度である「効用値」にまとめ上げるというのが選好に基づく尺度と呼ばれるものです。
「効用理論」とは?
池上 池田先生,「効用理論」について簡単に説明していただけますか。池田 3つの仮定がありますが,まとめると表のようになります。このモデルはシンプルで,大変わかりやすいのですが,いくつか矛盾するような状況が報告されています。しかし,これに代わるより優れたモデルはこれまで開発されていないので,現在のところ最もよく使われています。
「EuroQOL(EQ-5D)」や「Health Utilities Index」などが代表的な尺度で,両方とも日本語版が利用可能になってきています。これは医療技術の経済評価にも使うことができます。先ほど池上先生の指摘があったように,医療費の高騰という中で,一定の医療費をできるだけ効率的に使い,できるだけ多くの健康を得るために医療技術を選択する際の政策決定にも使えます。詳細は拙訳書『医療の経済評価』(医学書院刊)をご参照いただければと思います。
池上 端的に言えば,「多次元なので,身体面と精神面のQOL改善の評価は,単純に合計して2で割ればよい」というわけではなく,総合的に評価して1つの目盛りに入れる必要があるということですね。
池田 そうですね。その場合の価値判断のモデルとして,効用理論が使われるわけです。術後の短期的な予後では大きなQOLの低下があるけれども,長期的に見るとQOLのよい状態で生存できるという治療法をいかに評価するか,という問題もあります。このような病態について,時間軸も含めた形で評価ができるのが,この選好に基づく尺度です。単一のサマリースコアとの組み合わせで,時間との総合的な質調整生存年という単位で,長期的な患者さんの経過,予後を評価できるという点では画期的な手法です。
福原 その話題に関連して,先ほど申しましたように,SF-36は精神面と身体面という二因子構造をもつプロファイル型尺度として分類されており,池田先生がおっしゃったような一元的な値を出せないと考えられていました。しかし最近,イギリスのシェフィールド大学のジョン・ブレイジア(John Brazier)先生が,SF-36から選好に基づいた値を推定するという研究を発表され,私どももブレイジア先生と共同で,SF-36からこのような選好に基づいた値を推定する共同研究を始めました。
| 表 | |
|
「EBM」と「アウトカム研究」
福原 現在,EBM(evidence-based medicine)が大きく取り上げられるようになっていますが,その4段階目として「患者さんの価値観とエビデンスに基づきながら,医師と共同して最終的な診療上の決定を行なう」という段階があります。英語では“shared decision making”と言いますが,患者さんでもわかる日常生活の言葉に換言されたエビデンスを医師と患者がshareすることによって,よりよい診療のdecisionに結びつけることを促進するわけです。QOLを用いたエビデンスはまさにその重要な1つであるわけです。このような動きが,現在,北米を中心に活発に展開されています。CD-ROMやインターネットなどの補助的な情報媒体が豊富に提供されるようになっていることも付け加えておきます。池上 整理しますと,ある薬剤の有効性を確立する際に,エンドポイントとしてQOL尺度を使うわけです。そこで統計的に有意であるからこの薬剤は優れているという,その段階の情報があって,それが仮にQOLの次元ごとに出た場合には,その次元ごとに,こういう面では優れているが,別の面では問題だという評価がされるわけです。 そういう情報が個々の薬剤ないし技術ごとに情報として蓄積され,その情報を医師と患者が相互に見ながら,最終決定を患者が行ないます,その際,開発の段階と実際に現場で利用するという2つの立場があり,それぞれのデータがさらに蓄積されます。
「自己評価」と「代理評価」
池上 ところで,この自己評価という問題は非常に重要です。医師の解釈や観察が入らないわけですが,これは原則であって,場合によっては他の評価が入ってもよいという面があると思います。池田先生,この問題についてはいかがでしょうか。池田 例えば痴呆の患者さんのQOLの特定は,やはり「観察者」や「代理人」の方が本人になり代わって評価をしていくことが必要な場合があります。
最近はアルツハイマー型痴呆は抗痴呆薬で治療可能になってきましたが,治療薬の効果を見る場合に,患者さん本人のQOLの測定が重要です。なぜかと言うと,それは延命でなく,QOLの向上を目的としているからです。ただ,痴呆患者さんのQOLを,本人に回答していただくというのは非常に難しい状況にあります。そうした中で,代理人ないしはトレーニングされた観察者による評価,あるいは介護者の負担感といったものも,広い意味でのQOLと捉えて検討していく必要があると思います。
下妻 脳腫瘍の患者さんやホスピスにおける末期状態の患者さんで,質問に答えることが難しい場合でも,池田先生がおっしゃったように,QOLを評価して治療に結びつけなければいけないという需要があります。この分野でも「代理人による適切な評価法」の研究が熱心に行なわれています。
池田 しかしながら,いずれにしても患者立脚型,つまり患者の視点に立った評価が重要だと思います。
福原 これまでは,ADLのような指標がありましたが,これは第三者が観察者として測定したものです。患者あるいは住民の視点に立って測ったわけではありません。本日のテーマであるQOLは,「医療を受ける側の視点に立った主観的な健康度や日常生活機能を測定したものである」ということから,従来のADLとは明確に分けられるのではないかと思います。
下妻 そうですね。今までの研究でも,医師が観察したQOL評価が,患者さん自身の評価と相関する領域と,そうではない領域があると思います。
池田 今後の研究が必要な分野ですね。
「疾患特異的尺度」
池上 下妻先生はがん研究および臨床の専門医ですが,疾患特異的尺度という場合,どういう具体的な項目が疾患特異的と言えるのでしょうか。下妻 がんの場合ですと,まずがんという疾患を患者が有していることそのものに起因する状態をしっかり測定できるような質問項目が並んでいることが基本です。具体的には,食欲不振,るいそう(emaciation),痛み,疲労感,確実な治療法が少ないことによる将来悲観などです。それから,治療に特異的な項目としては,手術による身体イメージの変化,抗がん剤による疲労感や吐き気,脱毛などがあげられます。
がん疾患特異的尺度においては,先ほど福原先生がおっしゃった,QOLに重要とされる身体面,心理面,社会面,機能面などの基本的領域について問う項目が,一般尺度(general scale)と,がん種別に特に大切な項目について質問する「追加尺度(module)」が備わっていることが通常です。
池上 その一般尺度として,先ほどのSF-36を使ってもよいわけですね。
下妻 ええ。例えば乳がんの患者さんは,比較的状態のよい方が多く,5年以上無再発で生存しておられるような対象の研究にはSF-36がよく使われています。ただ状態が悪い対象については,ほとんどの方のスコアが低いほうにかたよる,床効果(floor effect)が出てしまいます。本来,疾患特異的尺度は,抗がん剤などの臨床試験,ランダム化比較試験の二次エンドポイントとして用いられることが多いです。その場合に大切なことは,治療などの介入の前後のQOLスコアの変化です。そういう場面では,包括尺度よりも疾患特異的尺度のほうが,一般に変化が出やすいと思います。
池上 がんだけでなく,糖尿病や呼吸器疾患など,さまざまな疾患の特異的な側面が評価されるわけですね。
下妻 そうですね。
福原 包括的な尺度であろうと,疾患特異的な尺度であろうと,最低要求される共通の基準があります。このような基準を計量心理学的な検証を行なってクリアしなければQOL尺度としては通用しなくなってきているのが現状ではないでしょうか。
下妻 特に臨床試験などの場合も,通常,対象とした集団についての信頼性係数は確認することが多いと思います。
福原 逆に私が懸念しているのは,時としてあまりにもテクニカルなことが強調され過ぎ,最も重要な「尺度を構成する中身」の軽視がみられることです。
例えば,ある疾患に対する治療の効果を患者さんの生活の視点から評価したい場合,本人の経済状態や人生に対する満足度,ペットを飼っているかどうかに至るまでの,主に外的要因項目が1つの尺度の中に含まれており,それらすべてを合計し点数化して治療の評価に使うようなことがみられます。そういう尺度を使っているような先生方から,「まったく差が出ないけれども」という質問を受けるのです。考えてみればこれは当然のことでして,いかに計量心理学的に優れた尺度であっても,その使用目的にかなった,内容的に妥当な項目でなければ,尺度として不適切であることを確認しておく必要があると思います。
下妻 尺度そのものの問題もさることながら,どのような状態の患者さんを対象に,その尺度が開発されたのかをよく考えて使い分けなければいけないわけですね。
福原 おっしゃるとおりです。測定する目的と対象によって内容が規定されます。
池上 多くの尺度の中から,どのようにして選ぶかが重要になってくると思います。疾患的尺度にしても,まずこれをみておいて,それでもだめなら,新たに開発することも考えてよいと思います。
「がん特異的尺度」
下妻 疾患特異的尺度のうち,がんの分野では,1980年代にFLIC(Functional Living Index for Cancer)という質問紙が,カナダのマニトバー大学のシッパー(Schipper)らによって開発され,米国を中心に使われていました。しかし,1993年にNetherlands Cancer Instituteのアーロンソン(Aaronson)らがEORTC QLQ(European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire)を,また米国のセラ(Cella)らがFACT(Functional Assessment of Cancer Therapy)という質問紙を開発し,現在は,この2つの尺度が,がん臨床研究および臨床試験に最もよく使われるがん特異的尺度となっています。わが国では,同じく1993年に厚生省栗原班の班研究において開発されたQOL-ACD(「がん薬物療法におけるQOL調査票)」が開発され,国内のがん臨床研究,臨床試験ではよく使用されています。EORTCとFACTについては,1996年頃から日本語版の開発を進めています。最近,がんの分野では日米欧が共同で臨床試験をする機会が増えましたが,国際共同研究の場面で多国間・多文化間妥当性が確認されたうえで使える尺度の開発が行なわれているところです。
池上 単独の基準を使うことは,安心して使えるという面がありますが,やはり先行研究との比較や,先ほど福原先生がおっしゃったshared decision makingをするうえでも,その尺度を用いることによって可能になってきます。自己流にやると,比較や蓄積ができないという問題がありますね。
福原 それから包括的尺度,あるいは池田先生がおっしゃった選好に基づく尺度にも共通しますが,国民の標準的なデータを得ることが可能で,それによって断面研究のような研究でも,比較する群のデータが得られるという点も,標準化された尺度を使うもう1つの理由ではないかと思います。
池上 つまり,日本人である結果が出た時に,米国人の結果と等しいと言えるかどうかという問題を含めて研究が進んでいます。基本的には,一般住民あるいは患者集団における国による差を補正する方向にあるのでしょうか。
福原 国際比較をする場合,それぞれの国の生データを直接比較することは危険です。その理由の1つは,文化的なresponse biasなどの影響があるからです。標準値でまず補正してから,そこから標準偏差に換算してどのくらい下がっているのか,というようなワンクッション置いた比較をしないといけないでしょう。
池田 単に海外のQOL尺度をそのまま翻訳して,海外の基準値と比較するのは意味がなく,まず日本における一般人口なりの基準値を確立して,それとの比較という形で数値を捉える必要があるわけですね。
福原 EQ-5Dのご研究をなさった池上先生,池田先生も同じお考えではないかと思います。一般住民を対象にした研究結果でも,かなりヨーロッパと日本では違うとうかがっておりますが,いかがでしょうか。
池上 日本人は5段階尺度の両極端はあまり回答したがらないと一般的に言われています。それに,翻訳上の問題としては,例えば「寝たきり」という言葉の語感は,単に寝たきりという事実だけではなく,非常にネガティブなイメージがあります。
そういうものを,どうクリアするかは難しい問題です。患者さんが評価するわけですから,逆に「寝たきり」というような言葉でないと評価は困難です。しかし,そういう言葉を使うと,イメージとしてかなり重みが違ってきます。しかしこうした課題も福原先生がご指摘のように,標準値で補正すれば,国際比較するうえではクリアできると思います。
「標準化」について
池上 実際にQOLを使う場合に重要な点は,自己流のQOL尺度をいきなり開発するのでなく,既存のものを使ってみることだと思います。そのほうが標準化して比較もできます。その際,尺度によっては使用上の著作権の問題があることに注意する必要があります。例えば,SF-36についてはどうでしょうか。福原 SF-36は完全にパブリックドメインです。つまり,簡単な使用登録の手続きをとれば,無料で誰でも使えます。今のところ,私のところで日本における登録を代行しております〔FAX (075)753-4644〕。
池上 池田先生,選好に基づく尺度についてはどうですか。
池田 日本語版EuroQOLもパブリックドメインで,研究目的であれば使用登録をしていただければ,自由に使えます〔FAX(03)3225-4829〕。
池上 疾患特異的尺度はどうですか。
下妻 例えばがんの場合ですと,EORTCとFACTについては開発元に登録が必要です。インターネットを通して登録し,資料を取り寄せることも可能ですし,私のところにお問い合わせいただいても結構です。使用料に関しては,両方とも製薬会社がスポンサーになっている研究や臨床試験は有料です。アカデミックに用いる場合には,届けるだけでよいことになっています。日本のQOL-ACDは,オリジナルの文献を引用していただければ登録も使用料も必要ありません。
福原 疾患特異的尺度に関しては,透析患者のためのQOLの尺度「KDQOL(Kidney Disease Quality of Life)」があり,米国のランドコーポレーションが版権を持っていますが,これも私どもで代行しています。また,炎症性腸疾患の特異尺度である「IBDQ(Inflammatory Bowel Disease Questionnaire)」は,日比紀文先生(慶大)が中心となって管理なさってます。
池上 登録を求めている理由の1つは,説明書などを十分理解したうえで,正しく使ってほしいということがあると思います。
福原 まさにその通りです。共通の尺度を使っても,例えばスコアリングが標準化されていなければ共通の土俵に乗りません。スコアリングの標準化および標準値による補正などは重要なポイントです。
池上 ところで,新たに開発したい場合でも,ゼロから出発するのではなく,既存のものを参照する必要があります。そこで気をつけなければいけないのは,「これはよい項目だから採る,これはよくないと思うから捨てる」というやり方です。これは基本的には許されないことだと私は考えますが,先生方はどのようにお考えですか。
下妻 確立された尺度から,勝手に好きな項目を取り出して尺度を作って用いても,計量心理学的特性が崩れて,何を見ているかわからなくなるのでいけませんが,すでに開発された方々が開発の初期に集めた項目の中で,計量心理学的理由のみで捨てられた項目や,貴重なノウハウがあったりします。EORTCでは,それをアイテムバンクとしてウェブサイトで公表することにしているようです。新たな質問紙を作るときには用いられませんが,疾患や治療別の追加質問紙を作る場合には,何らかの登録を必要とされるものの,それらを利用する試みが行なわれるそうです。2000年の国際QOL学会で発表されていました。
福原 池上先生のおっしゃるとおり,項目を恣意的に取捨選択することは問題となります。ただ,尺度全体でなくても,内的一貫性が示されている下位尺度単位で使うことは可能です。それから,その尺度を翻訳して日本語版を作る時には,原作者に許可を得ることは最低のルールです。
池上 そうしませんと,いくつもの日本語版ができてしまい,お互いに互換性がなくなって,結果の比較ができなくなります。翻訳の際の言語が違うだけで,標準値が違ってくる可能性がありますから,かなり厳しく扱わないといけないでしょう。
標準的な尺度と申しましたが,やはり使っていただかないことには標準的な尺度になりません。これまでのQOL研究は,包括的尺度にしても,疾患特異的尺度についても,それぞれが別個に進み,どれが標準になっているかが必ずしも見えませんでした。また,ある尺度の開発に際して,どのような苦労があったのかということもわかりませんでした。
「国際QOL学会」について
池上 アウトカム評価も国際的な動きですが,QOLの研究も国際的に通用する尺度が中心テーマです。福原先生,国際QOL学会の動向についてご説明願えますか。福原 国際QOL学会(ISOQOL)は1991年に,健康・医療領域に関するQOL研究,特にアウトカム研究においてQOLをどのように活用し,方法論的な研究をどう進めるか,臨床研究や医療,政策研究への応用をどう進めるか,などを目的として設立されました。
学会員の構成は研究者が最も多く,臨床系,計量心理学系,経済学系などの研究者で構成されています。次に多いのが臨床系で,臨床医や看護,リハビリなどの方々も会員になられています。製薬会社など民間企業に勤められている研究者も2-3割おられます。特に欧米では現在,製薬企業でアウトカム研究部門を作る動きが活発です。この部門は,QOLを使った研究と医療経済評価の2つを主に担当している部門だと理解しております。また少数ですが,FDAなど政府関係者の方も会員になられています。
 2000年11月末に,9回目の年次集会がカナダのバンクーバーで開催され,下妻先生,池田先生にもご発表いただきました。今回のバンクーバーの学会で,東京大学の医学系研究科麻酔科の大学院生・西森美奈氏(写真)が,Young Investigator Awardをお取りになりました。彼女の研究は方法論だけにこだわらず,得られたデータが臨床的にどのような意義があるかということをアピールした点で評価されたと思います。これは大変喜ばしいことでした。
2000年11月末に,9回目の年次集会がカナダのバンクーバーで開催され,下妻先生,池田先生にもご発表いただきました。今回のバンクーバーの学会で,東京大学の医学系研究科麻酔科の大学院生・西森美奈氏(写真)が,Young Investigator Awardをお取りになりました。彼女の研究は方法論だけにこだわらず,得られたデータが臨床的にどのような意義があるかということをアピールした点で評価されたと思います。これは大変喜ばしいことでした。
そして2001年4月13日から15日まで,ISOQOLとして初めて「環太平洋集会」が東京で開催されます。
残念ながら,これまでの学会は,臨床以外の研究者が多くを占めていることがあります。ともすると「測定のための測定」のような研究に走りがちな傾向は否めなかったと思います。今後は日本やアジアの研究者,特に臨床家の先生方に,QOL研究が医療評価のためのアウトカム研究として重要であること,またQOLは重要な患者立脚型アウトカムであることの認識を深めていただくことを期待しています。そして,この認識の深まりとともに,より多くの臨床研究者がアウトカム研究およびQOL研究に参加されることを切に望みます。
池上 本日は,貴重なご意見をどうもありがとうございました。
(おわり)
| この座談会は,『臨床のためのQOL評価ハンドブック』(医学書院刊)に収載されている「座談会:アウトカム評価におけるQOL研究」を「週刊医学界新聞編集室」で再構成したものです。
「週刊医学界新聞編集室」 |
●国際QOL学会第1回環太平洋集会開催案内
4月13-15日/東京
国際QOL学会第1回環太平洋集会(Pan-Pacific Conference of the International Society for Quality of Life)が,黒川清(東海大学医学部長),福原俊一(京都大学教授)両会長のもとで,「Taking QOL research into the new millennium」をメインテーマに,きたる4月13-15日の3日間にわたり,東京・都市センター会館において開催される。
〔主なプログラム〕
<学会特別招聘講演>「患者立脚型研究における健康アウトカムとしてのQOL」(米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校教授・Lee Goldman氏)
<基調講演>(1)「インターネットによる健康アウトカム・モニタリングの意義」(米国Quality Metrics. Inc.・John E. Ware氏).(2)「SF-36を用いたPreference-based指標の推定」(英国シェフィールド大学教授・John Brazier氏)
<パネルディスカッション>「臨床試験のエンドポイントとしてのQOL」
<トレーニング・ワークショップ>(1)「SF-36」.(2)「慢性閉塞性肺疾患(COPD)の健康関連QOL」.(3)「がんにおけるQOL」.(4)「KDQOL」
<シンポジウム>(1)「Patient's Safety」.(2)「看護領域におけるQOL」.(3)「高齢者,障害者のQOL」
<サテライトシンポジウム>(1)「限局性前立腺がん患者のQOL:治療戦略へのフィードバック」.(2)「過活動膀胱と尿失禁患者のQOL」.(3)「IBDの新しい治療戦略:QOLを指標とした選択と評価」.(4)「性機能とQOL」.(5)「痴呆患者のQOL」
<ランチョンセミナー>(1)「EuroQOL(EQ-5D)」.(2)「DOPPS-透析患者に関するアウトカム研究」.(3)「気管支喘息における健康関連QOLとその評価をめぐって」
◆連絡先:TEL(03)5770-5531/FAX(03)5770-5532
URL=http://www.c-linkage.co.jp/qol/
