OSCEなんてこわくない
-医学生・研修医のための診察教室編集:松岡 健(東京医科大学第5内科教授)
第8回 バイタルサイン(後編)
内藤雄一(東京医科大学第2内科講師)山科 章(東京医科大学第2内科教授)
■手順
診察する旨を告げ,了承を得ます| (1)橈骨動脈を触診します(写真1) |
| (2)呼吸数を数えます |
| (3)上腕動脈を触診します(写真2) |
【以上,(1)-(3)は前号で解説】
| (4)血圧計のマンシェットを巻きます(写真1) |
前腕の高さは心臓と同じ高さ(左第4肋間)に置きます。ラバーの中央が上腕動脈に当たる位置にあて,マンシェットの下縁が肘窩の2-3cm上になるように巻きます。指2本ぐらい挿入できる強さが適当です。
| (5)触診法にて血圧を測定します(写真3) |
橈骨動脈(上腕動脈でもよい)を触れながらカフを急速に加圧していくと拍動が消えます。この点よりさらに約30mmHg水銀柱を上昇させ,毎秒2-3mmHg(1心拍ごと水銀柱の1目盛くらい)の速さでゆっくりと圧を下げていきます。脈拍を触れるようになった点が収縮期血圧です。ショック時など聴診法でKorotkoff(コロトコフ)音が聞こえない時にも有効です。
| (6)聴診法にて血圧を測定します(写真4) |
上腕動脈拍動上に膜型聴診器をあてます。マンシェットで聴診器を圧迫しないように,特に拡張期血圧測定時は聴診器で強く動脈を圧迫しないように注意します。触診法でもとめた収縮期圧よりさらに約30mmHg速やかに水銀柱を上昇させ,触診法と同様に毎秒2-3mmHgの速さでゆっくりと圧を下げていきます。拍動ごとにコロトコフ音(少なくとも2つ)が聞こえてきた点(Swan第1点)を収縮期血圧,完全に消失した点(Swan第5点)を拡張期血圧とします(図1)。通常は触診法より聴診法による収縮期血圧のほうがやや高く出ます。
OSCE-落とし穴はここだ
血圧の測定ではマンシェットの正しい巻き方ができません。なかには聴診器の上から肘を中心に巻いている学生もいます。医者になってから看護婦さんに教えてもらうようでは困りますので基本はしっかり覚えておきましょう。拡張期血圧をSwanの第4点にするか5点にするかは異論のあるところですが,質問するとSwanさえ知らないで血圧を測っている学生がいることには驚かされます。 |
 |  マンシェットには加圧空気がはいるゴム嚢がはいっています。上腕動脈にあてる位置が示してあるマンシェットもありますが,自分で確認しゴム嚢の中央で動脈を圧迫するようにあてます。 | |
 |  |
・OSCEでは
血圧測定ではマンシェットの巻き方(下縁は肘窩より2-3cm上,ゴム嚢の中央が上腕動脈にあたっている,巻く強さが適当),触診法はできるか,水銀の上げ下げ(カフのねじ操作,速度,触診法の収縮期血圧より30mmHgくらい上げたかなど)をみています。
■解説
| 血圧の測定 |
血圧は血液が動脈壁に及ぼす側圧であり,心拍出量×末梢血管抵抗で表わされます。
心室収縮時の最高値を収縮期血圧(最高血圧),心室拡張終期に一致した最低値を拡張期血圧(最低血圧)と言い,またその差を脈圧と言います(図2)。
15分以上安静にし30秒以上の間隔で最低2回は測るのが理想的です。また初診時には左右の血圧を測定すべきですがOSCEでは時間制限があり,血圧測定は片側のみ1回でよいなどと指示があります。
平均血圧
血圧の平均値を意味しますが,拡張期血圧+1/3×脈圧で計算されます。
聴診間隙
カフ圧を下げていくと聞こえていたコロトコフ音がいったん消え,再び聞こえ始まることを言います。血圧測定にあたって注意が必要です。触診法で収縮期血圧の目安をつけておくことでミスが少なくなります。
血圧の異常
高血圧とは血圧の高い状態をいいますが,合併症発症の相対リスクが約2倍となる血圧値以上を高血圧と定義していることが多いようです。
世界保健機関(WHO)と国際高血圧学会(ISH)の高血圧ガイドラインによる血圧分類を示します(図3)。これでは成人では140/90mmHg以上を高血圧としています。
最近ではエビデンスに基づき,糖尿病,高脂血症,喫煙などの心血管系危険因子や合併症を層別化し加味したガイドラインもあります。逆に収縮期血圧が100-90mmHg以下を低血圧と言い,ショック時など収縮期血圧が70mmHg以下になると意識障害をきたし早急な処置が必要です。血圧には日内変動があり,携帯型血圧記録計による24時間の血圧測定(ABPM)も行なわれています。
| 先輩からのアドバイス
バイタルサインのチェックは基本さえ知っていればOSCEでは容易なステーションだと思います。私たち循環器医の日常診療では毎日すべての患者に行なっている基本中の基本ですが,特に救急医療での不正確な把握は直接患者の生命にかかわるものであることを銘記しておきましょう。バイタルサインとともに救急蘇生法を練習するとよいと思います。さらに循環器系の診察法として内頚静脈の観察(静脈圧の推定,Kussmaul徴候,肝頚静脈逆流など),前胸部の触診,心臓の聴診法を関連して覚えるとよいと思います。東京医大のOSCEでは血圧と心臓の聴診法など組み合わせて出題されています。 |
| 図1 減圧によるコロトコフ音の変化 | |||||||||||
|
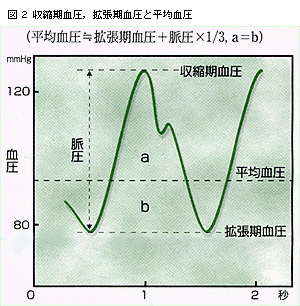
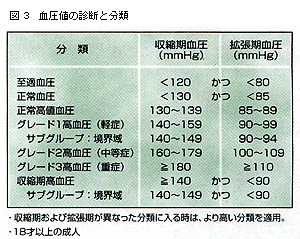
| ●調べておこう -今回のチェック項目 □遅脈と速脈 |
