【対談】
Narrative Based Medicine
医療における「物語と対話」
 | |
| 河合隼雄氏 (国際日本文化研究センター所長) | 斎藤清二氏 (富山医科薬科大学助教授・内科学) |
医療における物語と対話の意味
物語を生み出すもの
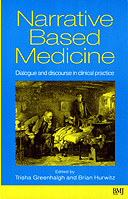 |
| 『Narrative Based Medicine-Dialogue and discourse in clinical practice』(T.Greenhalgh,B.Hurwitz編集,BMJ発行,1998) |
河合 医療関係の方々の前では,多くは「医学と医療とを分けて考えたらどうか」というお話をします。日本は「医学」という場合に近代科学の考え方が非常に強く,医学を勉強すること,イコール近代科学的になります。近代科学的とは対象を客観視して人体を研究することです。これは大事なことですが,実際の臨床場面になるとそれだけではなく,人との関係が生まれます。患者さんのほうも医師との関係を期待していますし,また患者さんとは孤立した人体ではなく,たくさんの関係の中に生きているものです。すると医療は,近代科学だけではどうしても十分にいきません。人間関係を大切にすることを前提にした場合,別の体系,例えば「医療学」が必要になってきますし,医学とは分野が違うという気持ちを持たないと困るのではないかと思います。そのような中で「物語(=narrative)」は非常に大事になってきます。
物語の特徴とは「関係づける」ことです。例えば,「王様と王妃がいました。王様が死にました。それから3日後に王妃も死にました」。これは事実だけが並べてあります。ところが,「王様が亡くなったので,悲しみのあまり王妃も死にました」となれば物語です。事象の関係づけが始まると,物語が生まれてくるのです。
ところが,近代科学は「物語」の対極です。逆に,物語を取り入れないことで急激に発達したとも言えます。今度はそれを近代医学の成果を十分に取り入れつつ,その人間が持っている物語を大事にしなくてはなりません。これはとても難しいことですが,それを医療従事者の方々にお願いしたいのです。ということで,たくさんの医師の前で,「医療の中の物語」について話してきました。
最近,この『Narrative Based Medicine』(BMJ発行,写真)の存在を知り,とても驚きました。私が前から考えていたようなことがすべて書いてあり,嬉しくなって紹介しているのです。本書を紹介してくれたのは福井次矢先生(京大総合診療部)です。福井先生は「Evidence Based Medicine(EBM)」の重要性を研究しておられる方で,とても守備範囲が広いですね。
NBMとEBM-医療を考え直す新しい視点
―― 斎藤先生,この「Narrative Based Medicine(NBM)」についてご解説ください。斎藤 NBMは,イギリスのジェネラル・プラクティショナーという,日本では開業医にあたる方々の中から出てきた運動です。専門性に偏らず,また患者さんだけでなくて,その家族も含めて,患者さんの全体と実際にかかわっておられる立場の先生方の間から生まれました。
河合先生がおっしゃったように,医療は患者さんとの1対1の関係を基盤としています。しかし医師自身は,科学的・生物医学的(Bio‐medical)な方法論を徹底的にたたき込まれています。それ自体は大変役に立ちますが,実際に患者さんとお話をすると,それだけでは対応できない問題がたくさん出てきます。それは医師にとってもフラストレーションですし,自分たちの行為は本当に意味があるのかと考えさせられます。そういう時に「患者さんが語る物語」あるいは「医師側の物語」にも焦点を当て,もう1度医療を考え直してみるという新しい視点がNBMだと思います。「物語と対話に基づく医療」と言えますね。この視点は科学としての医学と,人間の触れ合いという意味の医療とのギャップを埋めていく効果を持つ可能性があると思います。
本書の編集はEBMを研究してきた方々です。EBMは基本的には,科学的な証拠を重視して曖昧な部分をできるだけなくするという発想のムーブメントですが,EBMを突き詰めていくとそれを補うものが必要になるということでしょうか。
河合 EBMから生まれてきたことが,とてもおもしろいですね。
斎藤 本書の中にも「EBMとNBMは矛盾するものではなく,お互い相補うものだ」という章があります。本当にそう思います。
河合 それと同じようなことから,「ナラティブ・セラピー」が出ていますが,これもシステム論や機械論を研究してきた方の中から生まれています。
心理療法の世界でも,フロイトにしろユングにしろ「科学」と言わないと信用されませんから,無理をしても科学と言おうとしました。そのうちに,それではうまくいかないところから「物語」が出てきます。同じことですね。私は心理療法から物語を考えていったのですが,今後は医療の世界にもこの考え方はとても大事だと思い始めたのです。
個人が持つそれぞれの物語
河合 私は医師と一緒に仕事をする機会が多いのですが,先日,「糖尿病患者さんの生活指導はどうすればよいか」というテーマで講演をしました。その時に「医者や看護婦さんが正しいことを言えば人が従うと思うのは大間違いだ」という話をしました。「言って正しいことができるなら,僕は最初に自分に言いたい」と。「酒をやめて貯金しなさい」,「朝早くから起きて勉強しなさい」とか,正しいのですが,言うだけで誰がしますか,そんなもん。個人はその個人の物語を生きています。そこへまったく違う筋書きをポンと入れても,変わるはずがありません。「正しいことを言えば変わる」では単純すぎます。
私はその時,「個人はそれぞれの物語を持っているのだから,正しいことだけでなくて,個人の生き方を尊重したらどうですか」と話しました。するとある医師がその通りにされたんだそうです。その方が言うには,「人の言うことを何も聞かなかった人が,急にお酒をやめられ,生きる姿勢が変わって,病状もよくなった」。そこで理由を聞きましたら,「釣りで海に落ちそうになって死の恐怖を感じた時に,ふっと気がついて酒をやめた,と患者さんが話しました」とのことでした。
これは物語としておもしろいですが,自然科学的に受け止めると意味はありません。「糖尿病の方は全員釣りを」ではナンセンスですね。ところが,そういう物語の展開があることがわかったら,次には1人ひとりの患者を大事にしようという意味を持つのです。
患者の混乱を整理すること
斎藤 医療現場での例をあげますと,患者さんは体の調子が悪くなり,気分も落ち込むという形で病院に来ます。そこで「うつではないか」となります。このような患者さんはたくさんおられて,必ずしも精神科だけに行くわけではありません。例えば仕事が大変なところへつらい出来事があって,体の調子も悪いとなると,「精神的なものとは思えない。自分はどこか体が悪いんじゃないか。しかし,医師には異常がないと言われた」というように,自分の中で物語が整理されずに苦しんでいるわけです。「私には絶対に身体に病気がある。身体だけをなんとかしてくれ」や,「検査はもういやだ。実はストレスのせいだと思っている」と言う人もいて,彼らはそれぞれ異なった物語を持っています。そして物語こそ違いますが,最初は皆ごちゃごちゃしているのです。
最近,気分が落ち込んで元気のない人が来ると,「脳内のセロトニンの代謝がおかしい」と診断するのが主流です。私はこれを「セロトニン物語」と呼んでいます。このような見方から患者さんをみれば,生物学的な変化という「物語」があてはまり,選択的セロトニン取込み阻害薬(SSRI)という薬を出せばよいとなりますね。それで運よく回復する方もいますが,そうでない人もたくさんいます。
何かの1つの物語に収束して,うまくいく場合は問題になりません。ところが,難しい,困っている患者さんの場合はそれがうまくいっていないのです。ある物語に基づいた治療をしていても,その物語が破綻してしまった時,医師が物語を1つしか持っていないと,治療が行き詰まってしまうし,患者さんも不幸になります。
最も多いのは,患者さんがひそかに持っている物語と,医師の物語がかみ合わない場合です。患者さんは「もっと悩みを聞いて支えてほしい」。一方医師は,「セロトニンの薬だけ飲めばいい」では破綻してしまいます。医療現場で大事なのは,患者さんの話を十分に聞いて,ご自身の病気についてどのような物語を持っているのか。別な言い方をすれば,自分の物語をどう解釈し,どう理由づけているかを理解することですね。医療面接の世界では「解釈モデル」というちょっと堅い言葉を使います。
河合 その人の物語ということですね。自然科学的なモデルなら,この方法でこうなったと,それで終わりです。薬を飲んだり,手術をすれば実際に治りますし,方法と結果が1対1で対応している場合もあり,今まではそれだけで成功してきたわけでしょう。腸チフスの人に物語を聞く必要はなく,ひたすら治療すればよいわけです。ところが,それではうまくいかない例が増えてきた。そこで,医療の現場が難しくなってきたのではないですか。
人間は,時には病気にでもならないとしようがない時があります。そう言ってしまうと言い過ぎですが,病気が人生の中である種の意味を持つという側面があります。その時に,近代医学でただひたすら治されてしまうと,よけいに自分の中が混乱してしまいます。そのようなことからも,原因のわからない病気が増えてきたのではないかと,僕は思っています。
患者さんの物語の場合,それを医師に語ることは非常に少ないです。言っても相手にしてもらえない,と思っています。しかし,看護婦や家族はそれを知っています。医師がそれについて知ると,診断や治療に役立つこともあるのですが。
臨床現場とNarrative Based Medicine
診断・治療と物語の関係
 斎藤 診断とは医学にとって大事な概念です。ところが,目の前の患者さんをどうするかとなると,理路整然とした診断の体系が必ずしも役に立たないことがあります。それと,先ほど言ったように,複数の見方がどれも成り立つようなことが医療現場ではしばしばありますね。
斎藤 診断とは医学にとって大事な概念です。ところが,目の前の患者さんをどうするかとなると,理路整然とした診断の体系が必ずしも役に立たないことがあります。それと,先ほど言ったように,複数の見方がどれも成り立つようなことが医療現場ではしばしばありますね。
本書の中にも,「患者さんの物語を大事にするのか,ICD-10などの分類のほうを大事にするのか」という話があります。医師としては本当はどちらも大事にしたい。ただ,少し難しい患者さんの場合は,むしろ複数の見方ができると考えたほうが現実に合っていると思います。すると診断というのはあくまでも約束ごとに過ぎないと考えることもできるということになります。
そうなると,診断も1つの「物語」と言えるのではないでしょうか。診断は唯一の事実として正しいものがあるわけでなく,医師が「こう診断をすると,この患者さんにいちばんよい」と,合意した物語であると考えることも可能です。しかしこのような考え方は,下手をすると,「診断がすべて」と思っている人にとっては世界が崩壊するような話ですから,このへんをどう考えていくかは難しいと思います。しかし,必ずしも診断を唯一の物語としてとらえる必要はないと,私は思っています。
河合 それは,客観的に人体を研究していけば,診断は非常に明確です。ところが,個人とは1人ひとりで全部違うわけですね。1人ひとりが違えば,答えが1つという単純な診断はあり得ません。例えば,私の体のある部分における診断はあり得ますが,私という人間に診断をつけられたら,たまったものではありませんね。
そしてもう1つの問題は,私が病気になり治療できた時に,体はよくても,家族や職場の問題,また人生観が入ってきた時にどうなるか。病気としては治っていても,他にもいろいろなことが起こります。例えばあまり早く退院してもらっては困るということもあるかもしれません。その個人の問題がたくさん入ってくるわけです。医療でそれをすべて考えなくてはいけません。
私は医学的診断というのは,できるかぎり明確にしなくてはいけないと思いますが,先ほどの糖尿病から考えると,診断がついても,患者が自分で生活を管理しなかったら話になりません。そこまで考えた時に,この「物語」が生きてきます。
その時に,「物語」を広く考えていけば,斎藤先生がおっしゃる通り,「診断とは1つの物語である」という言い方ができると思います。たくさんの人に一般的に通用する物語,それが診断ということです。ところが,個別性が入ってきた場合にそこがどうしても違ってきます。現代は,人間の個別性を考えなくてならないことが増え,そこで物語を考えざるを得なくなってきたのではないか,と僕は思っています。
死からみた患者と医師との物語
斎藤 私は膵臓癌の診療を専門としているのですが,進行した根治不能の膵臓癌をみつけて診断することは難しくありません。ところがそう診断した時に,どのような言葉で患者さんに伝えればよいかということは重大な問題です。「癌は治すべきものだ」という物語しかないと,その後どうしてよいかわからなくなってしまいます。結果的には患者さんが突き放される形になり,非常に不幸な状態になります。そこで別の物語が必要になるのです。つまり疾患としては治せなくても,その方が亡くなっていくまでの間,どのような方法でサポートできるか,そこに複数の物語が出てきます。その1つがターミナルケアやホスピスケアで,ここ数年そういう物語もあるという認識が医療界に浸透してきました。
河合 ただ医師が,「あなたはこういう病気で,治りません」と言ったら,1つの恐ろしい物語をその人に与えたことになります。でも,医師の言い方1つで姿勢が変わってくると思うのです。「近代の医学では完治できませんが,あなたがこれからどのように生きていくか,あるいはどう対応していくかを一緒に考えましょう」と医師が言ってくれたら,物語が広がります。「治らない」だけでは「通告」です。すべての医療がこれにつながると思うのですが。
斎藤 おっしゃる通りです。先ほどの末期膵臓癌の話でもそうですが,極端なことをいうと,人間は必ず死ぬわけです。そこからみると,また物語が違ってきます。
医師は「治せないことは敗北」という物語と,さらに「患者を治せない自分はだめな医者だ」という物語を持っていますが,そんなこと言ったって,最終的に人間はみんな死ぬのですから。
河合 ただ,いつ死ぬか,そしてどう死ぬかだけの問題になりますね。
斎藤 そこに医師が関係性を持ってかかわれば,「死からみた時に何ができるんだろう」となると,まったく物語が変わってきます。しかしそこまで100%割り切れないというのも事実で,現場は非常に悩みます。
例えば,現時点では「膵臓癌は治らない」というコンセンサスがあるとします。これは将来変わるかもしれませんが。患者さんは苦しいけれど,化学療法でよくなるかもしれない。しかし,その見込みは少ない。そこで「治療をして助ける」という物語も半分ぐらい残っていて,でも苦しいことはこれ以上させたくないというのも半分ある。そこで医師は悩みます。
河合 それは当然患者さんを巻き込んでいるわけですね。特に今は,告知して納得してもらうという時代ですが,その説明の仕方によって変わってくるわけですよね。
私が経験した癌患者さんの例ですが,あと1週間ぐらいの命だろうと思われていた時に,「どうしても自分は書きたいことがある」とおっしゃるので,「すぐ書いたらどうです」と言ったら,本当にお書きになり,本を1冊完成して亡くなった人がおられます。その方は医学的に予期されていたよりもだいぶ長く生きられたそうです。手もあげられないほどの病状でしたが,天井からスカーフで腕を吊ってワープロを打つために看護婦さんたちもよく協力されたらしいです。その方は思いを残すことなく亡くなられたかと思いますね。その人の人生という言い方をすれば,すごいことですよ。
これは医療従事者以外の人間が行なってもよいことですが,その機会はなかなかありません。私は偶然お見舞いに行ってお話ができましたが,もっと他の人にもそのような機会があるとよいかもしれません。外国の場合は,宗教家がその役割を担っているように思います。しかし,だれが物語に入るのかは非常に難しいですね。
斎藤 各立場の人が自分のできる最善のことをサポートするしかないと思います。新しい努力は必要になるわけですが,全部やりとげた時には「これでよかったんだ」という感じが残るでしょうね。
河合 その時に,医師も「あの人は1週間で亡くなる」という話と,今のような協力関係で「一緒に1週間仕事をした」という感じとではずいぶん違うと思います。
医師の持つ物語
斎藤 これは医学教育とも絡みますが,医師のやりがいや達成感として最も大きいのは,自分が患者の役に立っているという実感です。しかもこのことには本来の医療の目的からみればきわめて大切な領域であるにもかかわらず,科学的な観点からみると意味がないと,今まで排除されていました。病院で若い研修医が一生懸命に患者さんに尽くして,場合によっては主治医が高齢の患者さんにお粥を食べさせていたのをみたことがあります。しかし,病院のカンファレンスで,「お前,何をやってんだ。そんな暇があったら薬の使い方を勉強しろ!」と言われる,というようなことが,今までは多かったのです。
臨床を志す若い医師が,患者のためにしたことが周囲から評価されない,科学的に意味がないと言われ,何をしてよいのかわからなくなってしまいます。では科学的に意味のあることをたくさんやれば満足感が得られるかというと,そうでもありません。
河合 私は「医療学会」を作ってほしいと,かねてから言っています。そうでないと,医療に一生懸命の方は,どこにも発表の場がないのです。いま学会では「医学」論文しか受け付けられませんし,医学論文数の多い人が,一応偉い先生となっています。
例えば,医師が患者さんにスプーンで食べさせることが,果たしてよいのかどうかわからない場合があります。下手すると,患者さんの敵意が自分の親族に向くのを助けることも起こり得ますね。そのような医師の行為がどのような意味を持っているかを考察することはすごい研究です。ところが今まで,そのような研究は発表する場がありません。先ほどの糖尿病の患者さんが態度を変えられたことも,医学論文としては意味はありませんが,医療的に発表すると皆が何かを考え始めます。しかしそうなると,何がよい医療の論文かという評価まで考えておかないといけませんね。
斎藤 そこが最も難しいと思います。これは本書でも触れられていますが,いわゆる事例報告や症例報告,あるいは典型例の報告が以前は評価され,医学教育の中でも価値があるとされていたのが,ここ最近で価値が下がってしまいました。
その理由は実際に,「1人がこうだから全部こうだ」という思考法になってしまうことがあるからだと思います。EBMは,それに対する反発からきたんですね。
河合 それはよくわかります。先ほど言ったように,釣りに行って恐怖を感じた人が成功したから,他の人にも釣りをさせる,というようなことに対してEBMは大事です。ところが,その話をどう解釈して,どう使うかまで考えないと,医療学になりません。しかし確かに,そう考える人がいるんですよ。アレルギーやアトピー治療でも,ある人に成功したのは事実でも,これでアトピーの治療法がわかったということとは,まったく別な話ですね。
斎藤 物語はそのような危ない面を持っています。きちんとした方法論を持っていなくてはいけません。しかし医学としては,今までは定量性があって再現性のある研究でないとだめと言われてきました。
河合 それは近代科学なんですよ。
方法論としていま可能性があるのは,臨床心理の領域でよく行なわれていますが,きちんとした事例報告であると思います。
斎藤 もう1つは,質的研究ではないかと思います。このような研究法が方法論として確立し,「量的」ではなく「質的」なものが評価されるようになると,物語もその中に入れていくことが可能になります。
医療を評価する方法
河合 医師のことを「アルツト(Arzt;アーチスト)」と言うでしょう。医師は芸術家なんです。医学とはテクノロジーと芸術の間にあるのですよ。完全にテクノロジー化した医学はとてもわかりやすいもので,近代医学です。そしてアートに近づくのがだんだん「医療」になってくるのです。最近,土居健郎先生が『図書』(岩波書店)におもしろいことを書いておられました。日本人がテクノロジーとしての医学に偏重してしまったせいで,「自分は医療の話をしても,日本の学者たちは聞かない」と。日本に医学を教えに来たドイツ人医師が嘆いているそうです。
もっと日本では「アートしての医療」を考えるべきでしょう。しかしアートの評価はとても難しいですね。ゴッホではありませんが,彼が絵を描いた当時は全然評価されずに,後でものすごく評価があがってくるということが起こるので,アートとしての医療の評価をどう考えるかは,今後論じる必要がありますね。
―― 臨床心理学における評価とは,どのようなものですか。
河合 これは芸術の評価に近くて,「ある1例が,その例を超えて非常に多くの事象にヒントを与える」というものだと思います。例えば,不登校の中学3年生の事例発表をした時に,それ聞いた人が,中年の患者にも喘息の患者を抱える人にも「なるほど」と思うところが多い事例が,私はよい発表だと思っています。
おもしろいことに,学会で事例研究発表を行なったところ,発表を聞く人がものすごく増えました。今までの,いわゆる科学的研究発表では誰も聞かないんですよ。聞いても,特にわれわれの場合は実際の臨床の役に立ちません。例えば,不登校を調査して,「長男はよくなる」とか,「不登校は都会のほうが多い」と言っても,実際の臨床には何の役にも立たないでしょう。ところが,ある不登校の中学生の具体的な事例はとても役に立ちます。
事実を超えてたくさんの異なる場面にヒントを与えるというのも,1つの魅力です。それだけではなく,もう少し事例研究の評価の魅力も考えてみようと思っています。
斎藤 医学系学会の最大の問題はそこにあります。臨床に関係する学会に出席しても,その経験が実際の臨床にはあまり役に立たないことが不満になっています。一方で,よい事例研究はとても人気がありますし,みな熱心に聞きますが,十分な時間をとった発表の場が確保できません。
本書の中にも「なぜnarrativeを勉強しなくてはいけないか」という章があり,その最後に,「narrativeというのはおもしろいのだ」とあります。「absorbing」という言葉を使っているので,吸い込まれるようなおもしろさということになりますか。こういう言い方をすると誤解される可能性がありますが,確かにそういう面があると思います。
話は変わりますが,実は医師も患者さんの話を物語として聞いていると思います。症状,検査データ,投薬という事実の羅列だけでは,おもしろくありませんし,何よりもすんなりと理解することが難しいのです。要するに,そういう事実の羅列を聞いても自分の中に何も生じてこないからです。人間というのはおもしろければ動くし,そうでないと動きません。ですから興味深い事例を30分以上かけてセッションを行なうと観客も多いですね。
河合 例えば,患者さんの入院から退院までをずっと記述する。その人はいつ行っても枕元に花があったとか,いつもキャラメルばかり食べているとか,それだけでも結構おもしろいんですよ。その患者さんが糖尿か,または摂食障害の子どもでは,また違ってくるでしょう。その子どもが隣のベッドの人とどのような付き合いをしていたかなどをうまく記述していけば,とても参考になると思いますね。
物語の危険性
斎藤 医療における物語を考える時,話が自己増殖するというか,都合のいいところだけを話してしまう危険性も考えておかなければなりません。何か主張したい意図があって,それに合わせて話を作るような場合があり,非常に危険ですね。河合 おっしゃる通りで,そのような話は妙に普遍化されてしまうのです。「この線でいけば治る」とか,いちばん危険なことですね。NBMの本当の狙いは個人です。「こういう個人がありました」ということから他の個人の物語を考えないといけないのに,その1つのnarrativeを全人類に広げようとするのがいちばん怖いんじゃないですか。その点を注意しないといけません。
斎藤 確かに「今までの医療が間違っていて,NBMだけがすばらしい方法だ」というような発想自体は非常に危険ですね。もっとも,NBMの基本的な考え方は,「たくさんの物語が存在することを認めていこう」というものですから,防止策は入っています。つまり,1つの物語だけで突っ走ってしまうのは,そもそもNBMの発想からはずれています。
河合 しかし,そうなりやすいから気をつけないといけませんね。
斎藤 また,医療において「物語を語る」ことの重要さを強調しすぎると,「患者さんに無理に語らせようとする」という危険が生じるおそれがあります。医師と患者の関係性の中で患者さんが自然に語るということが大切なのであって,そのためには時期が熟すまで待つ必要があることも多いのです。「未だ言葉として語られない物語」,あるいは「語られるための時期がまだ熟していない物語」を,大切なものとして尊重するという姿勢は,NBMにおける基本的態度の1つであると思います。
斎藤 話は戻りますが,物語の多様性ということで,特にNBMの考え方の基になっている「社会構築主義」(Social constructionism)は,ある意味でかなりラジカルなものです。唯一の正しい物語があるわけではなくて,物語とはその場その場で語られて創造されるものであるという立場ですから,すべてを相対化してしまうところがあります。それを極端に推し進めると,何も真実がないということになってしまうんですね。それはおもしろい考え方ですし,それが臨床の現場での対話を絶対的に尊重するという形で使われているならば,意味があるし,患者さんのためにもなります。
ただ,あまりそれがラジカルになると,本当に何を信用してよいのかがわからなくなってしまいます。そもそも人間は寄って立つところを全部消してしまうことはできないと思います。臨床の現場では,その時に自分が採用している物語を意識し,それを相対化しながらも,それにある程度のっていく必要はあると思いますね。
河合 ある意味では二律背反的になりますが,自分がそこで採用した物語というものに相当コミットするのです。またコミットする姿勢がなければだめですね。しかし,「こんなのもありますよ」と言うのは,たくさんの中の1つかもしれない,という客観視する姿勢や視点がなく,NBMの中にまったく入り込んだら,危険だと思いますね。その意味では,訓練がとても必要になります。
医師になるためのトレーニング
矛盾を抱える訓練
斎藤 先生のおっしゃる通り,患者さんの物語を上手に聞き,尊重して,自分の仲間とできるだけ物語を共有する形で治療や診療を実践していこうとなると,それを遂行するためのトレーニングあるいは教育が必要になると思います。私はその1つが「医療面接」だろうと思っています。医療面接の教育も最近は充実してきていますが,何が本当にいちばんよい方法かという結論は出ていません。さらに「マニュアル化」の問題が避けられず,本質的なことが抜けてしまう可能性が常にあります。そういう意味で,先生のお考えになる面接法の基本を,少しお話しいただけたらと思います。 河合 特にわれわれの場合,面接の基本は「主導権を患者に譲ること」ではないでしょうか。それがどれだけできるかです。
河合 特にわれわれの場合,面接の基本は「主導権を患者に譲ること」ではないでしょうか。それがどれだけできるかです。
しかし,近代医学的な面接は,検査をして自分の判断で診断を下していくわけで,完全に医師が主導権を持っていないといけません。つまり,医師として近代医学的なアプローチをして,今度は医療面接を行なうとなると,まるっきり逆転するようなことをしなくてはいけないのです。これは訓練としても難しいと思います。この点に関して井村裕夫先生(京大名誉教授)が,「医者の訓練は,本気でやろうと思ったら,矛盾することを教えないかんので,ものすごく難しい」とお話されていました。
これを大学教育のどのあたりで行なうか,そして,なぜこんなことをするのか,これまでと逆であるという点を教えていかないと,訓練を受ける人が混乱すると思います。こういう時,人は往々にしてどちらが正しいのかという考え方をしだすでしょう。そうではなくて,この患者さんにはこのぐらいの面接でいく,他の人の場合は,というように,自分の視線にバラエティを持たせることを教えないといけませんね。
斎藤 複数の矛盾するような要因を1つの面接の中に統合していこうということですから,非常に難しいものがありますね。どこまでできるかわかりませんが,今の流れとしては,医学生が臨床現場に出る前に,受容的な面接を教育しようという流れになっています。これはもともとは,アメリカのカウンセリングの考え方ですね。
河合 患者を受け入れながら,きちんとこちらの主体性も失わないわけですからね。何も患者さんに主体性を譲ると言ったって,医師に主体性がなくなったらだめなわけです。これは,特に心理療法の場合に起こりうるケースですが,相手に主体性を譲ろうとしすぎて,治療者の主体性がなくなることがあります。これはとても危険で悪い例です。しかし,その訓練はとても難しいものです。
スーパーバイザー制を導入する
河合 もしそのような教育を行なうなら,必ずスーパーバイザーが必要です。医学の場合は,スーパーバイザーのシステムがなさすぎるんですね。個々の患者さんとどのようなかかわりをしていくかですが,もう少し組織的訓練として入れるべきだと思います。臨床心理士の場合は,相当に取り入れています。1回面接したら必ずスーパーバイザーに報告して,いろいろアドバイスを受けます。それを何回か繰り返して,だんだん緩やかになって,何回に1回聞きにいくというようになります。これはとても大事です。斎藤 現在の卒後医学教育では,例えば検査値の読み方や検査計画の立て方,薬による治療方針などはスーパーバイズされています。これらはほとんどマンツーマンに近い形で教育されています。また,癌告知などの非常にシリアスな問題の時には必ず上級医が一緒にいて,その場に同席したり,診療が終わった後に議論するなど,ある意味ではスーパーバイズされています。
ところが,日常臨床のちょっとしたやりとりにはまったくスーパーバイザーがいません。特に外来診療はほとんど野放し状態です。これは医師にとっても困った問題ですね。他人の外来をみたことはありませんし,上級医がどのような外来を行なっているのかも知りません。ところが,最近では世の中が外来診療重視の時代になり,アメリカは特にそうですし,外来診療を適切に行なうということはますます大事になっていますので,これをどうスーパーバイズするかは大きな問題だと思います。
医師のカンファレンスも改善の余地がありますね。まだまだ自由に討論できる雰囲気のカンファレンスは少ない。若い人は黙っているか,たまに発言すると叱責されるために,体がそこにいても心がいないという状態です。そうすると,長時間拘束される割りには時間の無駄だという感覚が出てきて,出席率が悪くなるという悪循環です。
例えばNBMの考え方が普及して,学生の時に医療面接の実習を受けて研修医になったとします。しかしそれでも,いざ患者さんに向き合うと,個々の対応はそれほど簡単な話ではありませんからとても困ります。その時にその医師が「もっと教えてほしい」と感じた時に初めて,本当の教育効果があがるのだと思います。
河合 実際にこのような授業を始めると,学生が喜びますからね。本当に寝る奴なんかは絶対にいないし,意味があったら,みな完全に出席します。そのような動きが出てきて,それが広がっていけば,本当に教育的な効果があがってくると思います。
―― 本日は,ありがとうございました。


