座談会
機能評価
医療と福祉の共通言語
| 里宇明元氏 埼玉県総合リハビリテーション センター・副部長 |  |
| 千野直一氏(司会) 慶應義塾大教授・ リハビリテーション医学 | |
| 伊藤利之氏 横浜市総合リハビリテーション センター・所長 | |
| 園田 茂氏 慶應義塾大・月が瀬 リハビリテーションセンター |
機能評価とは何か
千野 本日は,「機能評価-医療と福祉の共通言語」をテーマに,お話しいただきたいと存じます。リハビリテーション(以下,リハ)医学は,1947年に米国で1つの医学・医療の専門領域として確立されました。その当時から「機能評価」というテーマは,リハ医学の中で大きな柱となり,今日に至っております。最近は急性期,慢性期の医療制度が,日本でも大きく変わりつつあります。そこで,患者さんをみる時に,病気の診断名だけではなく,運動機能や認知機能などを科学的,客観的に評価する「機能評価」を行ない,患者さんの状態を的確に把握するという動きが始まっています。これは,新しい医療に,ひいては慢性期医療から福祉に移る,2000年の介護保険制度の導入にも必須となります。
リハ医学の中の機能評価
千野 最初に,リハ医学の中で機能評価がどのように研究されてきたのかを,里宇先生からお話しいただきたいと思います。里宇 リハ医学において,患者さんの麻痺などの機能障害や,日常生活における障害を客観的に評価することは非常に重要です。個々の患者さんの機能状態をみることは,自立度や介護度を知り,それらにどのようにアプローチすべきかという課題を明らかにする意味があります。また,予後を予測したり,治療効果を判定したりする上でも,機能評価は非常に重要だと思います。
さらに地域の中で,患者さんの機能についての共通言語を持って,関係者とコミュニケーションが図れることはとても重要です。そういう意味でリハの分野では,歴史的にさまざまな機能を評価するための尺度が開発されてきました。
日常生活動作評価法
 里宇 能力低下や日常生活動作(ADL)の評価法は,これまでに何百という方法がありましたが,その中で残った評価法は,尺度としての標準化がなされて,信頼性,妥当性があるものです。具体的には欧米を中心にKatz Index,Barthel Index,Kenny Self-care Evaluationなどが,歴史的に使われてきました。これらは一定の信頼性,妥当性が報告され,実際の臨床場面で役割を果たしています。ただ,評価尺度段階が少し粗いとか,項目の中で身体的なADLは含まれてはいても,認知面が配慮されていないなどの欠点があります。
里宇 能力低下や日常生活動作(ADL)の評価法は,これまでに何百という方法がありましたが,その中で残った評価法は,尺度としての標準化がなされて,信頼性,妥当性があるものです。具体的には欧米を中心にKatz Index,Barthel Index,Kenny Self-care Evaluationなどが,歴史的に使われてきました。これらは一定の信頼性,妥当性が報告され,実際の臨床場面で役割を果たしています。ただ,評価尺度段階が少し粗いとか,項目の中で身体的なADLは含まれてはいても,認知面が配慮されていないなどの欠点があります。
その中で,米国ではリハ医学会が中心になって,1983年にADL評価に関する作業部会を開き,そこで共通言語としてのADLの尺度を検討しました。その結果,今日徐々に普及しつつある機能的自立度評価法「FIM」(Functional Independence Measure)が登場してきました。
障害の3つの概念
千野 ADLの概念を広義にとらえた場合,その中にIADL(Instrumental ADL;手段的日常生活動作)評価スケールがありますね。それを簡単に紹介してください。伊藤 IADL評価は,高齢者の活動能力を測るスケールとして提案されたものです。1969年に提案者のLawtonが示した評価項目は,電話の使用,買い物,食事の準備,掃除,洗濯,乗り物利用,服薬管理,家計管理の8項目で,要するに,われわれが日常生活の中でよく行なっている動作のうちで,セルフケアを除いた生活動作の評価法です。日本ではこれを「生活関連動作」として,狭義のADLであるセルフケアの評価と分けてきた経緯があります。
千野 約半世紀にわたるリハ医学の中で,ADLを中心とした評価法が確立されつつあります。ここで,障害とは何かという概念について,少し整理しておきましょう。
里宇 リハ医学において患者さんの障害をとらえる時に,1つのモデルとして,1980年にWHOが提唱した国際障害分類「ICIDH」があります。
これは大まかにいうと,
(1)生物学的なレベルでの障害をさす「機能障害」(Impairment)
(2)日常生活における障害や環境との関わりにおいてとらえられる「能力低下」(Disability)
(3)「社会的不利」(Handicap) とに分けることができます。それぞれリハ分野においては重要な評価項目です。
「機能障害」は,客観的な標準化された尺度で評価することにより,医学的概念の延長で考えやすいところだと思います。例えば,脳卒中で片麻痺が出た場合,その片麻痺の程度を「重い」,「軽い」だけではなく数量的に評価して,科学的な検討を行なうことが可能となります。
「能力低下」は,ある意味では機能障害によって起こる部分はありますが,さらに環境や介護者という要素が加わってきます。医学分野で大きな課題になると同時に,福祉分野の「介護」という概念とも結びつくと思います。その点に関しても,ある程度共通して使える標準的尺度が必要で,そのような流れの中で,FIMが登場します。
伊藤 今,里宇先生が紹介されたICIDHは,その後,障害者の歴史の中で,手足が麻痺していたり切断されている人たちが普通に生活できる社会こそ正常なんだという「ノーマライゼーション」思想が普及するようになって,1997年に改定案が出されています。例えば「機能障害」の概念はそのままですが,「能力低下」については「disability」という障害に着目するのではなく,逆に人間の「activity」に着目して,それが限定されているという視点から「activityの制約」という概念が提案されています。また,「社会的不利」についても「participationの制限」というように,社会参加が当然であることを前提に,それが制限を受けている状態との視点に変わってきています。
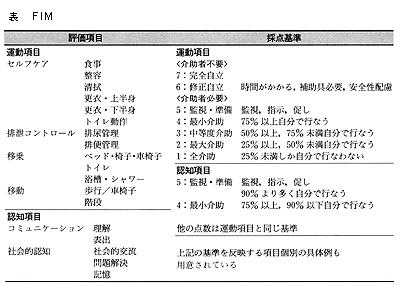
「機能障害」
 千野 医学の歴史の中で,われわれは病気の診断をつけることに努力を払い,診断名の確立はなされました。しかし,患者の状態を客観的に評価する機能評価に対しては,医療者側の中でも根本的な概念が掴めない方もいらっしゃると思います。
千野 医学の歴史の中で,われわれは病気の診断をつけることに努力を払い,診断名の確立はなされました。しかし,患者の状態を客観的に評価する機能評価に対しては,医療者側の中でも根本的な概念が掴めない方もいらっしゃると思います。
そこで,リハ医学の中で最も数の多い脳卒中を例にとって,客観性を持つと言われる「機能障害」と「能力低下」の評価法について,両者の違いを含めてご解説ください。
園田 脳卒中の機能障害で最も気になるのは運動の麻痺だと思います。まず1950年代頃にTwitchellが,運動麻痺のパターンを詳しく研究しました。それを受けてBrunnstromが,どのように治っていくかの過程をステージに示す「Brunnstrom stage」を表しています。その後,「Fugl-Meyer scale」が発表されまして,基本的には流れを受け継いでまとめていると思われます。
麻痺だけでなく,高次機能障害や麻痺側ではない側に比較的残っている力を含めて,機能障害全体をまとめる方法も出てきています。急性期に関しては,「NIH Scale」,「Canadian Neurological Scale」など,意識や半側無視などの項目を含んだ簡単な評価法があります。その他にリハが中心となる時期には,脳卒中機能評価法「SIAS」(Stroke Impairment Assessment Set)なども使われます。
評価法の信頼性・妥当性
園田 機能障害と能力低下の評価法はたくさんありますが,何でもいいというわけにはいきません。信頼性や妥当性をある程度満たしていることが条件だと思います。ここでいう信頼性とは,例えばAさんがつけても,Bさんがつけても同じような点数になることです。「Barthel Index」や「FIM」も,そのような研究が1000人単位のデータで評価されています。それから必要な条件は妥当性です。これは,測りたいものを測っているかということだと思います。例えば,ADLスコアがよくなったら,本当に患者さんの日常生活 がよくなっているのかということです。
医療の効果をevidence-basedで確かめる
千野 評価表はどのような目的で使われるのでしょうか。 園田 これらの機能障害,能力低下の評価法を使用する目的は,患者さんの現状を把握することが1つです。例えば,リハや介護などの何らかの介入をした場合に,状態がよくなっているか,または変化がなかったか,とかの把握です。さらに,予測的にも使います。こういう状況の方にこうすればきっとこうなるだろうと,その元の状況を「評価」するわけです。
園田 これらの機能障害,能力低下の評価法を使用する目的は,患者さんの現状を把握することが1つです。例えば,リハや介護などの何らかの介入をした場合に,状態がよくなっているか,または変化がなかったか,とかの把握です。さらに,予測的にも使います。こういう状況の方にこうすればきっとこうなるだろうと,その元の状況を「評価」するわけです。
その場合に,今までのリハの評価法は多くの場合が,「順序尺度」といって,点数を足したり引いたりできないことに問題がありました。例えば,「重い」,「中等度」,「軽い」にそれぞれ1,2,3と点数を付けると,1と2の違いと,2と3の違いでは,程度が異なるかもしれませんよね。そのあたりの問題を1989年にMerbitzが「Archives of Physical Medicine and Rehabilitation」誌に投稿し,大きな反響を呼びました。それ以来米国リハ医学会では,その点を気にするようになりました。
90年代になると,G.Raschによる「Rasch分析」という手法で,順序尺度を間隔尺度化して,足したり引いたり,かけ算できるような尺度に変換してみればいいではないか,との考え方が出てきました。
また,予後を予測する時に,数字を使うのではなくて,ある項目が悪かったらこちらに,よければ違う側にと分岐していく「classification tree」という方法を使って,行き付く先が答えであるとするやり方があります。それは,Stinemanたちがアメリカで「case mix」という手法を作る際にも活用しています。
それ以外に,例えば患者さんが退院した場合にどのくらいのADLになっているかを予測する時に,今までは「重回帰分析」という,わりと簡単な手法を使っていましたが,現在は「neural net」なども利用できます。
このように現在の評価法は,少しでも理論づけられた方法を見つけていく努力をするという動向にあると思われます。
千野 evidence-basedに機能評価を行ない,そこで医療効果を確かめることが,基本になりますね。
DRG/PPSとFRG
千野 今後,高齢化社会の中で慢性疾患はますます増えてきます。慢性疾患,またリハと関連のある疾患について,1つの疾患だけではなく,いわゆる「併存疾患」(comorbidity)といって,1人の方がさまざまな疾患を抱える状態が増えてきます。そういう場合に,ある診断名だけで治療を決定したり,診療報酬を払うのは非常に難しくなることが予測されます。現在,厚生省でDRG/PPS(診断群別包括支払方式;Diagnosis Related Groups/Prospective Payment System)の導入を検討し,いま試案が作られています。しかし,リハ医療においては,診断名だけで評価することには無理があるようです。
里宇 DRGは,診断群に基づいて患者さんを分類します。これは米国における基礎研究をもとにして,医療資源の消費量を反映するような分類として作られました。ところがDRGは,例えば脳卒中なら「脳卒中」という診断名で分類されてしまうため,一般の急性期医療での医療資源の消費を反映することは可能でも,さまざまな機能レベルを有するリハの対象となる患者さんについては,必ずしも正確に反映できません。そのために米国でもつい最近まで,リハ医療はDRGの対象外でした。
ところが,医療費は増大し,リハの分野でも医療資源の消費量を的確に反映するような分類システムが必要となってきました。そのような背景の中でFRG(Function Related Groups)というものが考えられました。これは,患者さんの機能をFIMで表された機能に基づいて,予測される在院日数に応じて患者さんを分類するものです。
FRG開発に当たっては,米国の医学的リハに関するデータベースであるUDS(Uniform Date System for Medical Rehabilitation)に登録された,5万人ほどの患者さんのデータがもとになっています。この分析を通して,できるだけ簡単な指標で在院日数に応じて患者さんを分類しようと作られました。その指標は,(1)脳卒中や外傷性脳損傷,脊髄損傷などの障害群,(2)年齢,(3)能力低下の評価法であるFIMを用いたスコア,の3つが用いられています。
実際,DRGだけですと,必要な在院日数の10%前後しか説明できなかったのですが,FRGで約30%くらい説明できるようになりました。現在,FRGのシステムに関しても,よりよい予測ができるように改良されてきています。
千野 リハ医学を,日本の21世紀の医療法改正に取り入れてほしいということもあって,日本リハ医学会としては,厚生大臣や日本医師会に要請をしております。
このような学問的な裏づけや合理的な医療のあり方を求めるためには,機能評価のサイエンスを確立しなければなりません。
医療と福祉の共通言語
「能力低下」をどうするか
千野 2000年4月から介護保険法が施行され,そこで介護度は,「要支援」から「要介護度1-5」の6段階で区分けすることになっています。リハ専門領域の概念からいうと,ADLが完全に自立している状態であれば,介護も支援も必要ないという意味からすれば,ADLの評価と要介護度の評価は,裏表の関係にあります。しかし両者はまったく同じものとは言いきれません。少し話題は変わりますが,要介護認定の前に,きちんとしたリハビリの治療を行なうという,「リハビリテーション医療の前置主義」を,厚生省でも推進しています。
そういう意味で,医療と福祉にとって別々の評価法を使うことはお互いに不合理です。お互いの共通言語を持ち,医療から福祉へ,またその逆へとスムーズに流れるようにする必要があると思います。患者さんは病院,医療施設から在宅あるいは介護施設へと移りますが,退院の時点で,病院や医療施設での医療関係者による評価を,そのまま要介護度に共有できれば,これは非常に合理的だと思います。
このように,両者が共有できる評価法をどのように考えるべきか,また機能評価を医療者と福祉との共通言語として,今まで以上に密接に共有するためにはどうあるべきかについて,ご意見をお聞かせください。
園田 先ほどあげた評価法の中に,FIMがありますが,これは「自立度評価法」といいながらIADLを介助量によって測るとされています。実際にそれを検証したデータもあります。具体的には,「time study」といって,患者さんがどのくらいの時間介助されたのかを測り,そして別個にFIMの点数をつけ,それらが一体どのような関係にあるかを調査したものです。
疾患によって多少異なりますが,大まかにいうと,例えばFIMが1点よくなると,介護の時間が2-5分ぐらい縮まるというように,点数が上がればその分だけ介護する時間が少なくなります。よって,FIMの合計点を使えば,大まかに介護する時間がどのくらいになるかがわかるわけです。これにより,リハ医療が終わる頃に,「介護時間」という1つの共通認識で,福祉側に患者さんをお渡しできるのではないかと思います。
ADL評価と現実のギャップ
千野 リハの専門病院でも,そのようなデータが出てきています。これは,実際の臨床にも応用できるのかについて,里宇先生,最近の研究の動向はいかがでしょうか。里宇 お話に出たように,FIMは介護時間をある程度反映することは確かです。しかし,在宅という環境でみた場合,FIMの点数だけを見れば,本当に介護者の介護負担を表せるかというと,そこまでいかない部分がありますね。具体的には,例えば全介助の人は,FIMの点数は低いですが,その人よりも部分介助,つまりFIMの点数がより高い人のほうが,実際には介助者の負担が大きい場合もあります。また,在宅での環境的なアプローチや,介護指導により介護者は楽になったとおっしゃる時にも,FIMの点数だけでみると変わらないことがあります。そのような感度という点でも,FIMは在宅の場面では,まだまだ不十分な点があると思います。
FIMのようなスケールで患者さんの機能を,病院から在宅を通して評価すると同時に,もう1つ別の面から,例えば介護者の主観的な介護負担度という観点も加えて,より在宅での問題を反映する努力が必要ではないかと思います。
人間関係が及ぼす影響
 伊藤 頭部外傷やクモ膜下出血によって生じる高次機能障害として,記憶障害,注意力障害,発動性の低下がありますね。このような患者さんたちの職業リハを行なっていると,例えば一般就労に結びつくか否かに最もよく反映されるのは,機能がよくなったどうかよりも,残念ながら障害者手帳をもっているか否かです。
伊藤 頭部外傷やクモ膜下出血によって生じる高次機能障害として,記憶障害,注意力障害,発動性の低下がありますね。このような患者さんたちの職業リハを行なっていると,例えば一般就労に結びつくか否かに最もよく反映されるのは,機能がよくなったどうかよりも,残念ながら障害者手帳をもっているか否かです。
もう1つ問題になるのは,問題行動,作業態度です。社会不適応の問題でいうと,われわれが常識的に持っている社会の秩序に対して問題行動を起こす,例えば,パニックに陥ったり,人とのコミュニケーションが悪いなど,心理的に周囲に迷惑をかけてしまうことが,復職してもだめになってしまう大きな理由になっています。
先ほど里宇先生がおっしゃった寝たきりの患者さんでも,あるいは動ける方でも,それぞれに介護する側との人間関係が最も介護負担度に影響してしまいます。そのあたりを今後どのように見ていくのか,医療側も科学的に何かできないかと思っています。
園田 例えば,問題行動には「適応行動尺度」という評価法があります。またFIMの最後の3項目(「社会的交流」,「問題解決」,「記憶」)と適応行動尺度は相関が高いことを以前に調査したことがありますが,これらはいかがでしょうか。
伊藤 ある程度使えることは間違いありませんが,それだけでは十分ではない部分もあります。つまりFIMの3項目は内容的に漠然としている面があるからです。
千野 頭部外傷のリハは,米国リハ学会でも大きなテーマになっています。確かに,評価法もまだ構築されてなく,これは痴呆による障害度の客観的な評価法がまだないのと同じ状況だと思います。これは今後リハの専門家が,他の関連した医療の専門家たちと共同で開発していかなくてはならない,大きなテーマであると思います。
ADL評価と要介護度
伊藤 ADL評価は確かに,医療と福祉の共通言語になると思います。しかし先ほど里宇先生がおっしゃったように,ADLは本人が環境に働きかけるものであるために,環境条件や使われる道具,介護者の態度などによって変わってきます。ですからADLの自立度と要介護度を加算して100%になればよいのですが,そうならないこともしばしば経験するわけです。そういうことで,この両者が表裏一体の関係にあるとは言えません。したがって,介護度は介護度として評価せざるを得ない部分が存在してしまうことに問題があると思います。
介護とリハビリテーション
障害の面からみた「介護」
伊藤 障害のほうから申しますと,例えば介護保険における尺度として,現在,国や福祉関係者が求めているのは「要介護度」です。介護保険下では,これが共通言語になるだろうというのはわかります。しかし共通言語を使う以上に難しいと思うのは,福祉と医療の両者の関係です。「要介護状態にある」人たちは,その背景に多くは障害や疾病があります。しかし福祉関係者の方は,純粋に現象としての要介護度だけを見ればよいと思っていらっしゃる向きを感じます。
病態が異なることによって,介護の方法も変わってくることを,福祉の方にも認識していただきたいと思います。
また,少し話は違いますが,現在,障害者のための介護支援専門員養成が行なわれています。今後,障害者の方への介護支援体制も早急に確立する必要がありますね。
要介護状態の方への対応
里宇 伊藤先生のお話にありましたが,要介護状態というのはある「状態」であって,そこに至る原因があるはずです。もちろん固定した要介護状態の方はおられますが,中にはいわゆる仮の要介護状態,例えば痛みやある部位の筋肉の力が弱いなどの要因によって,本来持っている機能を発揮することができずに,必要以上に要介護状態となっている方がいらっしゃいます。そういう方に,リハ医学の立場からちょっとしたアプローチをするだけで状態が変わることが,入院患者さんだけでなく,地域で生活されている慢性期の方にもあります。医学がすべてに関与する必要はないと思いますが,要所要所で的確な対応ができるシステムを作っておかないと,適切なアプローチが行なわれないために,介護の必要な方がどんどん増えてしまいますね。そこでまた,必要なコストがかさむ可能性があると思います。
伊藤 その点は,医学・医療,特にリハ医学・医療が主役ではないかもしれませんが,基盤である点を押さえていただきたいですね。
千野 今後,医療から福祉,福祉から医療と,その両方の共通言語を用いて,円滑な医療と福祉を構築しなければなりません。そのような時に,リハ医に求められる役割は今よりも増大するだろうと思います。
慢性期リハの問題
伊藤 障害のある人たちのADLを再構築するまでの過程は医学が担うとして,その後の生活スタイルの再構築を図る地域リハや機能維持のためのサービスは,介護保険が優先され,福祉制度がそれを下支えすることになっています。しかし,実際のサービス現場では医療と福祉が混在することになりますから,その住み分けはファジーですね。千野 医療と福祉の間に境界領域がありますね。そこを両者の歩み寄りでよりよくする努力が必要です。リハ医療をベースにし,介護保険制度が進むことによって,介護の必要な方や要介護度が減ってくることが大事なのです。これは医療側も福祉側も認識してほしい点ですね。
機能障害の評価は,診断名をつけるのと同じくらい重要なことです。急性期から機能障害,能力低下のレベルでの科学的な評価が行なわれ,それを向上させ,治療がきちんと行なわれていることを確かめることが大切です。福祉に移行するのは,これ以上治療法がなくなった時点であり,このとき初めて福祉の中での要介護認定にならなくてはいけません。それから,要介護に至った状態であっても,放っておけば機能の低下が起こってきます。そうなった時には,新たにリハの治療が行なわれなければいけません。この辺に関しては,日本リハ学会で作成した案を,日本医師会や厚生省の方々に差し上げております。これらを参考にして,急性期から慢性期,福祉へと移行するプロセスで,リハ医学・医療をさらに日本で活用してほしいと思います。
―――本日は,誠にありがとうございました。
(了)


