鼎談
神経学はいかにして作られたか
「臨床神経学辞典」発刊を機に
| 田代邦雄氏
(北海道大教授・神経内科学) |
 |
| 岩崎祐三氏
(国立療養所宮城病院長) | |
| 岩田 誠氏
(東京女子医大 脳神経センター所長) |
 ヴュルピアン |  ババンスキー |
『臨床神経学辞典』の読み方
――本日は,『臨床神経学辞典』(医学書院)の発刊を機に,ご尽力いただいた3人の先生におこしいただきました。本書は神経学に関連する2万語を収録,約1400頁にのぼる豊富な情報を擁し,加えて,辞典という範疇を超えた記述の豊かさ,ユニークさがその特徴かと思います。そこで,監訳の岩崎先生をはじめ,岩田先生,田代先生に,お話をうかがいたいと思います。最初に本書はいったいどのような辞典なのか,先生方の感じたことをお話ください。
岩崎 本書は神経学のさまざまな用語を解説した辞典であると同時に,1人の神経内科医が書いた世界初の百科辞典的特徴も備えた点に特徴があります。
著者のPryse-Phillips教授は,イギリスで教育を受けてカナダに移住しました。年齢は60歳ぐらいで,興味は教育とガーデニングと釣りだと,お願いした著者紹介にあります。この方は各国で翻訳されている学生向きの“Essential Neurology”の共著者でもあり,教育熱心な方ですね
そのことからも本書は,今まで集積された神経学を次代に伝えたいという意識が強い本だと思います。内容についても用語だけでなく,神経学の全体の流れもわかるし,幅広く,おもしろい辞典です。さらに実用的な部分も,疾患分類や診断基準などほとんどすべてを網羅しています。例えば現在,脳死が問題になっていますが,アメリカ大統の領諮問委員会が提出した脳死基準勧告をはじめ,数多くの疾患や症候群の診断基準なども全文載っています。
もう1つの特徴は,オリジナリティをとても大事にしている点で,例えば誰々と名のついた反射は,実は別の誰々が何年前にすでに行なっていたという点に非常に詳しい記述です。チャールズ・ベルの項目では,脊髄の前根,後根の話はベルにプライオリティがありますが,実はマジャンディのほうがきちんとやっている,とあります。趣味的な側面もありますが,プライオリティという言葉に対してはできる限り公平な記載をしているユニークな本だと思いますね。
田代 一般的には通説をとりますが,必ずしもそうせずに,よく検索してオリジナリティを出して紹介しているのはすごいことですね。
岩田 私が驚いたのは,「ALS協会」などの患者団体に関しても,成立過程や事務所の住所・電話番号まで書いてあることでした。そんな辞書は今まで見たことがなくて,こういうことまで書いていいんだという,新しい発見でした。
いまは,個人がこういう本を購入しなくなるような風潮がありますね。私の若い頃は,教科書は自分で買うものだと思っていましたが,今は必ずしもそうじゃない。しかし本書は,自分で持っていないと意味がないですね。図書館に調べにいくという本ではなく,時間があったらパラパラとめくって,おもしろいことを発見できる本です。
田代 本書はそのタイトルである「Companion to Clinical Neurology」から和訳するとなると「臨床神経学必携」が近いと思うのですが,これを「臨床神経学辞典」としたごとく,最初から読んでいくようなタイプの本ではないですね。暇なときにパッと開いて,その項目を読んでみると,そうなのかという新しい発見があります。しかも事実の記載の中に,この方の好みも入っていて,だからこそおもしろいのです。
岩崎 原著タイトルのように,自分の「伴侶」(コンパニオン)として活用してほしいですね。本書で人名を追っていくと,主に19世紀からの西欧を中心とする神経学の流れの中での人脈がきちんと書かれています。それをずっと追っていくと,人の流れがわかり,医学の歴史を覚えるというのはおもしろいですよね。
後は,1人ですべてを書いたこともあって,内容に誤りなどがいくつかありますね。しかし本書は,今後のたたき台のようなものになるものと思います。
岩田 大きな辞書や教科書は,間違い探しをされることは1つの役目なんですね。そうして次にちゃんとしたものができるわけですし,骨組がなければ何もでません。本書はその骨組みになりうる本です。
岩崎 本書にはいわゆる最新のデータは入ってなく,ある意味では古くならない,まさに「温故知新」の本ですね。最新というのは,明日には古くなってしまいます。そういう意味で本書は,現在判明している疾患の責任遺伝子をはじめとして,ある程度確立された事実をできるだけたくさん詰めこんだ本になっています。最新とあって,明日には使い物にならない本が今は非常に多いですが,本書にはそのリスクはありません。1冊手元にあるとよいと思います。
伊藤直樹先生のこと
――本書の翻訳の一番の立役者である伊藤直樹先生(前中村記念病院副院長)が,発刊を見る直前に亡くなられてしまいました。非常に残念なことです。伊藤先生のことをお話ください。岩崎 伊藤君は北大を1962年(昭和37年)に卒業し,私とは立川の米軍病院でインターンを一緒にやった仲間です。当時は北大にまだ神経内科がなく,1964年に九大脳研と,数か月遅れて新潟大脳研と東大に最初に神経内科ができたました。伊藤君は北大精神科に入局しましたが,神経内科を勉強したかったので,結局,満足できなくてアメリカにわたりました。
田代 最初にインディアナ大学のマーク・ダイケンの下で2年間神経内科レジデントをされ,最後の1年をセントルイス大学神経内科で学ばれました。帰国後は,順大の平山惠造先生のところにいかれましたね。
岩崎 平山先生が千葉大に移る折り,一緒に移っています。その後,札幌の中村記念病院に勤務され,そのまま残られました。
田代 伊藤先生は語学がとてもお得意で,細かなところまで気がつく方でした。最初は,数年前に,平山先生と神経治療学に関する本の翻訳を,フラー先生の『やさしい神経診察』(医学書院)を訳されています。私はこの本の書評を頼まれたので,原本と全部対比して読んだところ,翻訳はもちろん完璧であるばかりではなく,例えば本文中に出てくるイギリスの地図を日本の地図にする,また英語の早口言葉を普段われわれが使う日本語の早口言葉にかえるなど,単なる翻訳本を超えた日本語の教科書にできあがっていました。
そのうち伊藤先生から,「ものすごい本がある。この本を事典としてぜひ翻訳したい」というお話を受けたのが,1995年,すなわちこの本が出版されたその年で,そこから本書はスタートしたのです。
岩崎 その翌年に癌と診断され,1998年の11月25日に亡くなってしまった。本書の翻訳も彼から,体力的に無理ということで,手伝ってほしいと電話で言われたのが始まりで,ようやくここまで来たのです。
岩田 伊藤先生は『神経学会用語集』(文光堂)にも委員として,一生懸命おやりになりました。
岩崎 語学,言葉を大事にした人でしたね。
神経学の歴史をひもとく
19世紀ヨーロッパ-フランス
岩崎 本書には数多くの神経学者の記述がなされていますが,人名をたどっていくと人の流れがわかり,そこから神経学の歴史が浮かび上がってくることは先ほど申し上げました。今度はお2人から,現在の神経学が歴史の中でどのような流れとして形作られたかをお話をいただこうと思います。岩田 フランスでは19世紀に臨床医学が盛んになりますが,その背景にはフランス革命があり,新興ブルジュワジーの台頭と同時に市民生活レベルが上がってきて,それと同時に臨床医学も起こってきたという側面があります。
19世紀前半に,ラエネックやコルヴィザールという,有名な医師がたくさん現れて,ベッドサイドで患者さんを診るということが始まったのです。
その1つの流れとして,神経学はヨーロッパから起こってきます。特に内科系の中で神経学をみる動きが出てきて,中心になったのはシャルコー(ジャン-マルタン,1825-1893)です。彼は内科医でしたが,神経を専門領域とするのは自分の役目として,種々の神経疾患を分離しながら,ベッドサイドで診察し,患者さんが亡くなると解剖して病理学的な所見と対比するという,古典的な臨床・病理対応研究を行なっていきました。それはもともと,1820年代までにフランスで確立した方法を,そのまま神経疾患にあてはめたのです。
これらのことは日本神経学会の機関誌「臨床神経学」(第1巻1号)で,安藝基雄先生が細かく書いておられますね。
田代 図1はスタンレー・コブが1947年に神経学の100年間の歴史をレビューした図です。神経学と精神医学,脳神経外科学を含めたレビューをしています。この図の中央でクリニックとなっているのが臨床神経学で,ドイツのロンベルク(モーリスH., 1795-1873)が最初に神経学を系統づけたと言われています。それには高橋昭先生(名大名誉教授)も,「ロンベルクが最初の神経内科医」と,1995年の名古屋での日本神経学会総会の会長講演としてもお話されています。その後に,フランスのデュシェンヌらが出てきて,ジャクソンにつながっていきます。
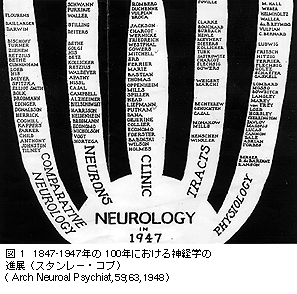
神経学と実験医学
岩田 フランスに遅れてドイツでは,「ラボラトリーメディスン」(研究室医学)が台頭します。リービッヒらが共同の研究室をつくって研究を進めました。一方,フランスにはそのような風土はなく,当時の研究者で有名なパスツールやクロード・ベルナールらも,自分の居室のような場所で研究しており,「研究室」ではないですね。この研究室医学に弱い部分が,後になってフランス神経学の問題点として出てくるのですね。興味深いのは,アメリカ神経学を築いた研究者には,フランスで学んだ人が非常に多いことです。例えば,サックス(バーナード,1858-1944)はシャルコーの下に来ていますが,彼はフランス神経学の欠点もつかんでいたのではないですかね。アメリカの神経学者たちは早くからドイツ的な研究室を中心とした研究方法を確立して,それが1900年代に入ってアメリカ神経学が伸びてくる1つの素地になったのではないかと思います。
一方,シャルコーのドイツ嫌いは有名ですが,ドイツのシステムを取り入れて研究室を作っています。臨床医学の中に研究室医学を導入して神経研究を始めた点でも,シャルコーは評価されるべきでしょうね。
シャルコーの残した研究室の中で有名なものの1つは写真です。「メディカル・フォトグラフィ」は,サルペトリエール病院でできたものです。その中心となったのはアルベール・ロンドという写真家で,同病院での写真を集めた『サルペトリエール病院写真集』というグラフィック雑誌の創刊者的な人です。
写真の技術に飛びついたのが,神経学と皮膚科学でした。しかも神経学は動きをとらえた写真を撮らなくてはいけないので,生理学者マレーの開発したクロノフォトグラフィの技術を取り入れ,ロンドが動きを見せる写真を撮影したのです。また世界最初のヌード写真というのはサルペトリエール病院でとられていますね。患者さんを裸で撮るのだから,当然といえば当然ですが。
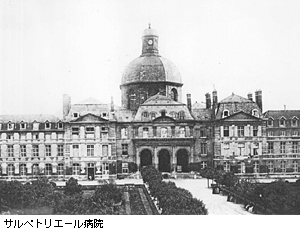
フランスの神経学者たち
デュシェンヌ 岩崎 デュシェンヌ(1806-1875)は地味な印象がありますが,シャルコーは「デュシェンヌは自分の師匠だ」と言ったそうですね。
岩崎 デュシェンヌ(1806-1875)は地味な印象がありますが,シャルコーは「デュシェンヌは自分の師匠だ」と言ったそうですね。
岩田 デュシャンヌは実験家で,臨床家としてよりも,電気刺激装置を持って診断したりと,神経生理学の好きな方だったそうです。さまざまな研究を行なって,その仕事にシャルコーが心酔したといいます。特にシャルコーは神経筋疾患にほとんど接したことがなく,彼に目が開かれて,自分の教室に定期的に来てもらい議論しながら患者をみていったようですね。シャルコーの診察記述を読むと,いつも年配の小柄な人とばかりしゃべっているが,あれがデュシェンヌ先生だとあります。
ヴュルピアン
岩田 フランスの神経学者の中で,ヴュルピアン(1826-1887)は忘れられているきらいがありますが,おもしろい人です。ババンスキーとデジュリンの学位論文の指導者はヴュルピアンです。非常に大きな流れをもっている人ですね。シャルコーは父親が車のインテリアデザイナーですから,新興市民の典型です。ヴュルピアンは貴族出身です。19世紀の初頭,シャルコーは,身分は低いが上昇気流にある人たちの1人で,一方ヴュルピアンは,貴族だったのがフランス革命で一般とされるという,下り坂の人です。それがちょうど一緒にやっているのです。シャルコーの残した功績は非常に大きいですが,ヴュルピアンがいなければシャルコーもあれだけのものを残せなかったでしょう。
彼は高潔な人で知られていて,またいろいろな経歴があります。例えば,当時パスツールの狂犬病ワクチンが物議をかもしていますが,医師ではないパスツールに代わって最初に患者さんにワクチンを注射したのはヴュルピアンでした。彼は最大の擁護者だったわけですね。
岩崎 有名な羊飼いの少年ですね。
岩田 また彼はパリ大学の医学部長ですが,大学に初めて女性の医学生が入学をさせるかが議論になった時,実際は反対派だったそうです。理由はいろいろでしょうが,この医学部長は,風紀が乱れるのを心配したそうです。女子学生は決して単独で講堂に行ってはいけない,必ずヴュルピアンの部屋に集まって,彼がみんなを講堂に連れていくというシステムを作ったと書いてあります。最初の女子医学生の1人が,後のデジェリヌ(ジュール・ジョゼフ,1849-1917)の妻になるクルムケさんですね。
岩崎 彼女はアメリカから渡ってきたそうですね。
岩田 アメリカの大金持ちの娘で,当初ローザンヌ大学にいて,パリ大学医学部でも女性の入学を許可することになったので,パリに来たようですね。当時,デジュリンはシャリテ病院の病棟医長でした。彼女がアンテルヌ(インターン)になった時に,ヴュルピアンに相談し,彼は自分の信頼できる弟子がいるところを紹介したのではないかと思います。
岩崎 そこで出会って,デジェリヌとクルムケは結婚したわけですね。
岩田 デジュリンはお金持ちではないので,2人の結婚にはクルムプケの両親が大反対だったそうです。その2人の気が合ったと思うのは,パリではよそ者だったからじゃないですかね。
岩崎 2人ともパリジャンではないから,一緒になったというところですか。
視覚と触覚-病理と臨床
ババンスキー岩崎 当時の医学では,病理学と臨床というのはどのような関係だったのですか。
岩田 フランス病理学の草分けはビシャーです。彼は,顕微鏡を使わないモルガーニ以来の肉眼解剖学でしたので,要するに,解剖学と病理解剖学との間の仕切りがありません。顕微鏡を導入したフランス病理学者の草分けの1人がシャルコーです。この人はフランス人であってパリジャンなのに,目がイギリスを向いたりドイツを向いたりしているのですね。
岩崎 フリードライヒ(ニコラウス,1825-1882)とも仲は悪くなかったと聞いています。
岩田 シャルコーは当初フリードライヒ失調症を認めなかったそうですが,自分が実際に患者をみた後は認めています。
岩崎 別にドイツ人であっても正しいものは正しいと。そういう意味では,シャルコーは幅の広い人間ですね。
岩田 彼は語学力があり,ドイツ語,イタリア語もできたそうです。彼が本当に書いたのかどうかは知りませんが,失語症の有名な論文はイタリア語で書かれています。またシャルコーの下で勉強したアメリカ人はずいぶん多いです。
シャルコーは市民階級ですが,偉くなった後では,実際に患者にはあまり触らないんですね。診察記録を読むと,弟子に反射や感覚を見るよう指示しています。また,シャルコーは視覚的な人だから,触ることよりも見ることのほうをに信じていたのかなという気がします。
それを変えたのが弟子のババンスキー(ジョゼフ,1857-1932)です。ババンスキー徴候にしても,足の裏を擦るなんていう汚いことを平気でやれるのは,当時を考えると普通じゃないですよ。ババンスキーは難民の子で,それが大きな背景にあるのかもしれないと思います。
岩崎 彼の父親はポーランドからの亡命者でしたね。
岩田 ポーランドという国が消滅し,逃れてババンスキーはパリで生まれました。ですから庶民的な背景があったのでしょう。そのためか足を擦るのも平気だったと思いますが,あまり育ちがいいと,いいものが生まれないのかなと考えてしまいます。デジュリンもジュネーブの郵便配達の息子で,資産はないとはっきり言っています。そういう生まれだから,骨身を惜しまず体を動かしたのではないでしょうか,
「ヒステリー」の消滅
岩田 フランス神経学の中で忘れてならないのは「ヒステリー」です。シャルコーが登場するどの本を読んでもヒステリーが出てきます。例えば,ババンスキーがババンスキー徴候を発見したのは,ヒステリー性麻痺との鑑別をどうするかが基本にありました。彼もヒステリーに関してはモノグラフもたくさん書いています。それからデジュリンも同様で,実際に診療をたくさん行なったようです。フランス神経学の初期のレパートリーに,ヒステリーは比重が大きく,その治療法まで進んでいました。しかし現代フランスには残っていません。ピエール・マリー(1853-1940)の時代に消えていったと思います。
マリーは重要な人物ですが,彼も日本ではあまり評価されていませんね。私がパリ留学中に,師匠のロンド先生は回診のたびにさまざまな現象を,「これはシャルコーがこう言った,これはデジュリン,ババンスキーはこう」と言うのですが,その中でいちばん名前があがったのが,1人はご自分の師匠のガルサン先生で,その次はマリーでした。「マリーはこういう不随意運動をこう読んだ」など,彼の名前はほとんど毎日出てきました。
マリーは神経学をマテリアリスティックなものとして確立し,ヒステリーを全部除いてしまったのではないかと思います。
岩崎 本書でマリーの項を読むと,彼は後年にシェフ・ドゥ・クリニークになり,パリ大教授になったのは65歳とありますね,これはずいぶん遅いようですが。
岩田 本当はシェフ・ドゥ・セルヴィス(病棟医長)ですね。マリーはデジュリンが死んでようやく教授になれました。一方,デジェリンはヴュルピアンの弟子で,シャルコーとはまったく関係なく,シャルコーの死後,跡を継いで教授になったのはフルジャンス・レーモン(1844-1910)で,この方は立派な人だったらしいですが,早くに亡くなります。それでデジュリンが出てきました。彼はその当時は国際的にも有名で,解剖学者としても有名だし,パブリッシュという意味では多くの業績があります。今流にいえば,インパクトファクターがすごく高い人ですね。ただ1つの難点は,シャルコーの弟子でないことでした。ただ当時はシャルコーの死後で影響も弱まり,デジュリンが3代目の教授になりました。
イギリスの神経学
岩田 当時,イギリスのクイーン・スクエアのナショナル・ホスピタルには,ジャクソン(ジョン・フューリングス,1835-1911)をはじめとした多くの神経学者たちがおりました。興味深いのは,イギリスでは早い時期から,動物実験や外科学と神経学とを組み合わせていることですね。例えば,ロンドンのUniversity Collegeのホースレー(サー・ビクターA., 1857-1916)は脳外科の先駆けとして有名です。岩崎 この実験への取り組みの早さは,イギリスは生理学をバックにしており,フランスは解剖学や病理学をバックにしている点の違いでしょうか。
岩田 イギリス神経学には詳しくありませんが,研究室との結びつきは早かったようですね。
岩崎 私がイギリス神経学で興味を覚えたのは,学者の個性がとても強いことです。例えばジャクソンが“Brain”を創刊します。その後ガワーズ(サー・ウイリアム R., 1845-1915)が“Brain”には絶対投稿しないと言う。さらにウイルソン(サミュエル A.K., 1878-1937)も非常にユニークな人で,自分で雑誌“Journal of Neuropsychiatry”を創刊しますしね。これは彼の死後に最初の号が出たらしいですが。気にいらないと自分で雑誌を作ってしまいところがおもしろいと思いますね。
また,みなそれぞれ教科書を書いています。当時の学者は,自分の学問を確立して,弟子を育てて,後は雑誌まで作ってしまうというのは本当にすごいと思います。
田代 ガワーズの教科書“A Manual of Diseases of the Nervous System”(1888年)もすばらしいですね。この中に,いろいろな疾患の姿勢や膝蓋腱反射の診方のスケッチなどもあります。しかもそれはガワーズ本人がスケッチしたといいます。そういう意味でもあの本はすばらしいですし,そこに出てくるパーキンソン病患者の絵も,一目でその病気とわかるほど見事に描けており,よく教科書や総説にも引用されていますね。
パーキンソン
 田代 私はイギリス神経学では,それこそシャルコーが認めたパーキンソン(ジェームス,1755-1824年)がどこで医学を学んだかということで,以前から大変興味がありました。
田代 私はイギリス神経学では,それこそシャルコーが認めたパーキンソン(ジェームス,1755-1824年)がどこで医学を学んだかということで,以前から大変興味がありました。
パーキンソン自身が所属したのは,先ほどのナショナル・ホスピタルではなくロンドン・ホスピタル(現在,ロイヤル・ロンドン・ホスピタル)と記録があります。この病院は数年前に設立250年を迎えています。ナショナル・ホスピタルは1860年に設立とありますから,大体150年ぐらいになりますか。ロンドン・ホスピタルでは,必ずそこの出身者のパネルを作って展示する場所があるのですが,パーキンソンのパネルもちゃんとそこにあります。ところが,これも有名な話で,パーキンソン本人の実際の写真はもとより,肖像画もないそうです。私はそこへ行って見てきましたが,そのパネルにもありませんでした。
岩崎 彼はほとんど記録がないですね。多趣味な人で,社会主義者だったそうですが。
政治運動に熱心で,かなりラジカルだったようです。
岩田 それから,化石が好きだったそうです。恐竜(イグアノドン)の化石を最初に発見したギデオン・マンテルという学者はパーキンソンの親友で,彼がいちばん最初にイグアノドンの化石を見せたのがパーキンソンだったと何かで読みました。
岩崎 パーキンソンは,パーキンソニズムという形で名前が残るとは思ってなかったでしょうね。
アメリカの神経学
岩崎 アメリカの神経学はどのような流れを持つのでしょうか。田代 アメリカの神経学は,どこから始まるかということになりますが,大体,ハモンド(ウィリアム A., 1828-1900)とミッチェル(1829-1914)がアメリカ神経学の父となっています。またミルズ(チャールズ K., 1845-1931)はアメリカの最初の神経学教授と言われています。
図1でも示されているようにようにアメリカのミッチェル,イギリスのガワーズと,フランスのシャルコー,マリーの流れはだいたい重なってきます。そこでデニー・ブラウン(デレク,1901-1981)をどこに位置づけるかというのは難しいところですが,彼はオックスフォード大のシェリントン(サー・チャールズ S., 1857-1952)のもとで神経生理を学び,その後ナショナルホスピタル,そしてボストン・シティ・ホスピタルで神経学を研究しています。彼を中心としたボストンの神経学が,アメリカではいちばん栄えた時期がありました。
最初の正式なハーバード大の教授はパートナム(ジェームス J., 1846-1918)で,イギリスのジャクソンのところで教育を受けています。アメリカの神経学は,その前の世代の神経学者はフランスやドイツへと行きましたが,アメリカ神経学の基盤を築いた舞台がハーバード大やマサチューセッツ総合病院,ボストン・シティー・ホスピタルだとすれば,イギリスの影響が大きいのではないでしょうか。その後はデニー・ブラウンが,イギリスとアメリカを行ったり来たりしています。彼はニュージーランド生まれで,それこそ移民ですよね。
岩崎 伊藤先生から,デニー・ブラウンが悪性貧血のB12欠乏について講演したテープを聞かせてもらいましたが,ものすごいなまりなんですね。さきほどきおっしゃった意味での上流階級ではないかもしれませんが,彼の功績は大きいですね。
ドイツ神経学
岩田 ドイツの神経学は,精神医学の中から神経学に進んだ派と,内科の中から進んだ派と2つが並列しています。岩崎 きわめて日本的なのですね。
岩田 その後ドイツでは,精神医学の中で神経学に進んだ人のほうが,主導権を持つようになっていきました。
岩崎 クレペリン(エルネスト,1856-1926)の立場もとてもおもしろいですね。その前には,アルツハイマー(Alois,1864-1915)やニッスル(フランツ,1860-1919)もいます。ハイデルベルグ,ミュンヘンの間で一時期,クレペリンを中心にして大きなグループがあったようです。ネルフェンアルツト(Nervenarzt;神経病と精神病の両方を誇る医師)は今も残っていますね。
岩田 「ノイロプシキアトリー」という言葉はドイツらしくて,今でも神経学と精神医学との境界があまりないような形の方は,めずらしくありません。
岩崎 ドイツでは神経学と精神医学の両方のトレーニングを受けるそうですね。非常に神経学と精神医学が近いところですが,なぜでしょうか。
岩田 それこそドイツ人のものの考え方,観念論があるのではないですか。人間の考えは脳からくるのであって,脳を扱うにはその脳が考えることを研究しなくては考えたと思います。
神経学と精神医学
 岩田 イギリスも,神経学と精神医学とは近いですよね。一方,フランスはまったく離れています。ですから,今の日本の置かれている状況は,フランスのシャルコーの時代とよく似ています。この時すでに,精神医学と神経学とはどう違うのかという議論が起こっています。1877年,パリ大学に精神医学講座が開設されました。この時すでにシャルコーは神経疾患を研究していました。新しい精神医学講座の名前は「精神病理脳疾患クリニック」でしたから,シャルコーを教授に,という案もあったそうです。しかし精神医学と神経学は全然違うものだというので,彼の名前は出ずに終わりました。1870年代ですでにフランスでは,精神医学と神経学はまったく違うということを非常に鮮明に出したわけです。
岩田 イギリスも,神経学と精神医学とは近いですよね。一方,フランスはまったく離れています。ですから,今の日本の置かれている状況は,フランスのシャルコーの時代とよく似ています。この時すでに,精神医学と神経学とはどう違うのかという議論が起こっています。1877年,パリ大学に精神医学講座が開設されました。この時すでにシャルコーは神経疾患を研究していました。新しい精神医学講座の名前は「精神病理脳疾患クリニック」でしたから,シャルコーを教授に,という案もあったそうです。しかし精神医学と神経学は全然違うものだというので,彼の名前は出ずに終わりました。1870年代ですでにフランスでは,精神医学と神経学はまったく違うということを非常に鮮明に出したわけです。
田代 いま日本では,神経学(神経内科)が内科なのかどうかについて,日本神経学会で臨時の理事会を開いて議論されています。しかしアメリカでは,その専門医認定証は今でも「American Board of Psychiatry and Neurology」で,精神医学が先にきます。2つを分けようという話が過去にありましたが,結局,今も認定証のタイトルは分かれていないですね。また神経学のレジデントトレーニング中に必ず,3か月ぐらいは精神医学で学ぶことが義務づけられています。逆もしかりです。
病院医学の確立と神経学
岩崎 レジデントの話から,少し教育についてお聞きします。これまでお話いただいた時代,つまり19世紀ごろの医学教育はどのようなものだったのでしょうか。岩田 ジャクソンも別に医学校出身ではありませんし,19世紀初頭は,病院が中心であって,医学校という形態を持つところはほとんどありません。
岩崎 親から教えられて,という感じですかね。例えばパーキンソンなどは父親が医者ですから,そこで習ったのでしょうか。
岩田 開業医のもとで勉強するというのが,当時の医者修行の一般的な方法のようです。
病院における医学という体系は,フランス革命後に確立されました。それ以前のライデンのブールハーヴェや,ウィーンのヴァン・スウィーテンたちが提唱した「病院医学」は小規模なものでした。その後フランス革命の時に,国家事業として病院医学を打ち出したのは,フランスの興味深いところですよ。それまでは,全部修行ですよ。日本も同様です。
岩崎 本当の徒弟だったわけですね。そういう意味では,医学教育が組織的にシステムとして行われるようになったのは,フランスがサルペトリエール病院から,イギリスだとナショナル・ホスピタルですよね。それから100年以上たっています。
岩崎 ミッチェルの頃は徒弟に近くて,あちこちと自分で好きな先生のところへ留学していました。システムとしての教育はハーバードで受けているようですが。
田代 その後のボストングループですね。
岩田 ハーバードが病院を中心としたメディカルスクールをつくりましたので,ここが最初に病院医学をアメリカ大陸にとり入れたのです。
岩崎 そのころから,神経学は1つの分野として独立したものになっていったと考えていいかと思います。

現代の神経学
岩崎 お話いただいたような流れからみて,現代の神経学はどのような時点にあると考えられますか。岩田 昔のように症候学をきちんととらえる流れはないですよね。私の師匠であるロンド先生はその最期にあたる人だと思うます。つまり,症候学が診断の技術である時代は去って,現象の中で,どうしてこういうことが起こるだろうかと考えながら神経学を学ぶ人がいなくなったということですよね。ですから現代の神経学は,病気の診断,原因のリサーチ,あるいは治療が主流です。症候学は基本的に現象論だと思いますが,現象論がいま下火になってしまった。世界的にそうではないですか。
岩崎 かつては検査が限られて,画像診断などないに等しい時代だからこそ,あのような神経学があったのではないですか。
岩田 今,現象論的な神経学が最もさかんなのは神経心理学の領域です。これは現象を見ないわけにいきませんから,古典的な症候学に近いことをしています。神経心理学の分野ですと未だに,19世紀の論文を読んでいますし,私もそうですが平気で引用しています。しかし,他の領域では滅多にないですよね。しかし,神経心理でケーススタディの論文を書こうと思えば,19世紀の論文を引用せざるを得ないのです。
岩崎 方法論的に変わっていないということですか。
岩田 変わっていない部分があるのです。例えば,イギリスの『ニューロケース(Neurocase)』という神経心理学関係の雑誌では症例報告を主体にしていますが,流れとしては19世紀のそのままのような考え方です。今は病理解剖ではなく,MRIなどの画像を用いてますが,新しい考えを少しあてはめて解釈しているだけのようにも見えます。
岩崎 神経学の雑誌では,1930年代までは長大な症例報告が多数掲載されていましたが,それが今では,神経心理学では生きているということですね。
デジタル化できないもの
岩崎 現代の神経学は世界的な流れとして,方法論的にも,研究の内容も,かなり画一的になってきたといえますね。岩田 今のサイエンスは,データを圧縮して一次元の上でデータを見ようとする傾向が強いですね。要するにデジタル化ですが,ものを測るのはデジタル化することで一次元しかないから,数字しか見えなくなっています。しかし神経学が始まった時には,デジタルなものの見方というのはまったくありませんでした。
岩崎 三次元的なということですかね。
岩田 例えばジャクソンは,時間軸が入ってきたり,頭の中で何がが起こっているのかを概念的なところまで入っていく,つまり多次元的なものを現象から見ていくという考え方でした。博物学に近い形のサイエンスといえるでしょう。神経学にはそういう部分が大きいし,そうせざるを得ない,デジタル化できない部分があったから,20世紀に入ってもそのような形で進んできたのです。
そういう意味では,神経学は古い現象論だけを症候学という名前で呼んだので,それしかないように思われていた時代があったと思います。ただ,サイエンスの中で,そこにあるものすべてをデータとして取り込むというやり方をすると,どうしても多次元的になります。そして今でも科学にはそういう方法で研究する分野があります。例えばフィールドワークがそうですし,考古学や古生物学も同様です。ともかく何かを見つけたら,それを扱わざるを得ないのですから,デジタル化なんかできません。
岩崎 平均化もできないですしね。
岩田 それは1個しかなく,ケースレポートそのものですからね。しかしそれですべてが変わる,どこかでアウストラロピテクスが発見されれば人類の歴史が変わってしまうように。神経学は比較的そのような古い形態をとどめている気がします。
EBMの功罪
岩崎 神経学に限らず,医学そのものが一面的というか,わかりやすく,誰にでも理解できるのがよいという風潮があります。例えば,「わからない」と言ってはいけない,裏に何があるかわからないのは困るというようにです。それは医学・医療がよいほうに向かっているのか疑問になります。田代 確かに今,「エビデンス・ベースド・メディスン」(以下,EBM)が流行しています。しかし,神経学はむしろ,その中に入るものと,そうでないものは絶対にあると思います。例えば血管障害は,その症候,画像,そして治療法と決まったパターンがあれば,EBMが応用できますね。しかし1人の患者さんの観察や症候を重要視をすれば,EBMには入らないものもでてきます。神経学では特にそうでないでしょうか。
岩田 EBMは,新しいことは何も出ない,そこに書かれていないことは全部捨てざるを得ないような世界でしょう。それでは世の中は進んでいきませんから,エビデンスのないところに,われわれは常に発展していかなければならないという役目があると思いますね。ですから,サイエンスの中でEBMは1部分であって,むしろ,エビデンスをもう1つ足すためには,それがないところへ入っていかなくてはいけません。そこにケーススタディは,とても大きな意味を持っていると思います。
岩崎 曖昧さのある安穏なところが残っていなきゃいけないということですね。
岩田 特に若い人たちがあまりエビデンスにとらわれるのは危険だと思いますし,もっと大胆に自分の考えを出していいと思います。そうしないと新しいものは出てこないし,いくらエビデンスといっても間違っているかもしれませんしね。ある病気にこの治療法が効くというエビデンスがあっても,それは理論的な根拠がなければどこかで間違っている,風が吹けば桶屋が儲かる的に見えているものかもしれない。それを本当にエビデンスだと考えるのも危険だ思います。ひょっとすると間違っているかもしれないと,もっと若い人に考えてもらいたいと思います。
「曖昧さ」をサイエンスに取り込む
岩崎 その時に症候学は,どういう立場になりますか。岩田 症候学は現象学ですから,見るたびごとに違うものが見えます。例えばババンスキー徴候も擦っているうちに変わってきますし,今日出ないのが明日出たり,私が陽性でも,誰かは陰性と,そういう曖昧さはものすごく大事なことです。その部分を若い時にちゃんと教育されずに,こうと決まっていると思われのは困りますね。
岩崎 今はそういうものを否定してしまい,再現性のないものはおかしい,サイエンスではないという感じになっていますね。
岩田 先ほどのババンスキー徴候で,人によって違っていた時,どちらかが間違えたという話ではなくて,反射が出る・出ないということがある,これが正解なのです。どうやったら出るようになるのか,出ないようになるのかということの意味を考える素地として,症候学を勉強するのはよいことだと思います。形態学も同様です。
岩崎 例えば形態学でも,顕微鏡で組織の標本を見た時に,「私にはこう見える」ということがあるでしょう。それがサイエンスになるとしばしば否定されるわけです。
岩田 神経病理でも免疫染色をしますね。それは大事なことで,否定するつもりはありませんが,そのはじまりにあったものをもっと大事にしてほしいと思います。例えば,最初にレヴィ小体があったら,これは何だろうかと考えるプロセスが大事なのです。それをせずに最初から結果だけをみて鵜呑みにするような教育では,若い医師にとってまずいことになると思います。
岩崎 教育的には,物事の「曖昧さ」,それが生き物であり人間であるというところをもう少し教え続けないと,機械的になってしまいます。とくに神経学の場合はそのような気がしますね。
岩田 また逆に,曖昧な部分をどのようにサイエンスの体系の中に取り込んでいくかというやり方をきちっと示せば,むしろ他の医学分野より,神経学はおもしろい領域になると思いますね。
悪口は言いたくないですが,医学の分野では物事をデジタル化して一次元でしか考えない,数ですべてを考える風潮があります。それは便利でしょうが,それだけで物事がわかるのかということですね。
岩崎 神経学の底流は,いま急に変わることもないということでしょう。
岩田 次代の進化は,いつも未発達の部分から生まれてきます。発達しすぎたものというのは,必ず進化の行き詰まりです。
岩崎 そのような神経学の流れを次の世代に受け継いでいかなくてはいけません。そういう意味で,本書は非常におもしろいものと思います。私自身,本書から多くのことを学びました。一人でも多くの人が楽しみながら,本書を読んでいただきたいと思います。
――本日はありがとうございました。


