座談会
P-drugをめぐる世界的状況
医薬品の適正使用のために
| 津谷喜一郎氏 (東京医科歯科大助教授・臨床薬理学) | デニス ロス・ディグナン氏 (ハーバード大) |
 | |
| 別府宏圀氏 (東京都府中療育センター副院長) | ジョセフ グリーン氏 (東京大・国際交流室) |
現在,厚生省の薬事関係の組織改変や,新GCPの施行など,医薬品を取り巻く状況に大きな変化が起こっている。医師にとっては医薬品をいかに合理的,適切に使うかが強く問われる時代となったと言えるが,そこには克服すべき多くの問題が存在する。
本紙では,WHO発行の『Guide to Good Prescribing』(日本版タイトル『P-drugマニュアル-WHOのすすめる医薬品適正使用』(医学書院より近刊予定)が,津谷喜一郎氏,別府宏圀氏,佐久間昭氏らにより翻訳されたのを機に,医薬品使用に関する世界的な潮流や教育のあり方について4氏にお話しいただいた。
医学教育の中の臨床薬理学
 津谷 私はいま,別府先生と佐久間昭先生(東京医歯大名誉教授)との3人で,東大とハーバード大との間で行なわれているエクスチェンジプログラム(以下,交換プログラム)の昨年の教材としても用いられた『Guide to Good Prescribing』の日本語訳(『P-drugマニュアル』,医学書院刊)を進めています。
津谷 私はいま,別府先生と佐久間昭先生(東京医歯大名誉教授)との3人で,東大とハーバード大との間で行なわれているエクスチェンジプログラム(以下,交換プログラム)の昨年の教材としても用いられた『Guide to Good Prescribing』の日本語訳(『P-drugマニュアル』,医学書院刊)を進めています。
グリーン先生,この交換プログラムはどのような内容のものですか。
グリーン これは東大とハーバード大とで毎年1回行なわれるプログラムで,両校から学生が参加し,ともにグループ学習や講義,ワークショップを経験するもので,1997年は3回目です。特にグループ学習ではテーマを設定し,現在ハーバード大などで施行されているプロブレム・ベースド・ラーニング(PBL)法(テューターを配した小グループ学習法。あるテーマを設定し,グループディスカッションを通じて問題解決への思考法などを学ぶもの)を用いています。今年のテーマは「医薬品の適正使用」です。第1回は「臨床疫学の基本的な考え方」を,第2回には「予防医学」を取りあげました。
津谷 ロス・ディグナン先生,今年の交換プログラムでは,なぜこの「医薬品の適正使用」が課題に選ばれたのですか。
ロス・ディグナン 私自身の専門は医薬品の使用法で,今年の交換プログラムの担当を依頼されたときに,「医薬品の適正使用を課題にしたい」とお願いしました。このテーマは医学生だけでなく,医療従事者すべてに関係があると強く思っており波及効果も考えて,今回の課題にふさわしいものとして選びました。
医学教育カリキュラムへの統合
津谷 今回の交換プログラムで,学生たちは「薬剤を使用する上での意思決定」について学ぶそうですが,アメリカではセミナー等で,この課題はよく取り上げられるのですか。ロス・ディグナン 最近,国際的にそうした傾向があります。アメリカでは,治療法に関する諸問題点を中心とした議論がさかんになっています。1つの原因は,この『Guide to Good Prescribing』の出版と,本書が注目されてきたことにあると思います。以前に比べて医師は薬物治療の諸問題について考え,その問題を理解するために一貫した努力をしています。また,以前から臨床薬理学が学部の中に存在し,従来の薬理学のみならず処方や薬剤の選択について学ぶ必要があると広く認識されつつあります。
今回,この課題を選んだ理由には,学生にもこのテーマについてのディスカッションに参加する機会を与えるためでもあるのです。現在ハーバード大でも,このトピックを大学のカリキュラムに統合できるように工夫しています。
津谷 日本でも今回の邦訳によってそのようになればと思っています。
ロス・ディグナン ご存じのように,これは新しい考え方で,世界中でも同じようなプロセスを取り入れつつあるところです。現在,マレーシア,フィリピン,インドネシア,オーストラリアなどさまざまな国で,この考え方を大学カリキュラムに統合できるように努力しています。
いかに教育システムに導入するか
ロス・ディグナン ハーバード大のカリキュラムに「プライマリケア・クラークシップ」という科目があります。これは,学生が3年時の中頃から4年時の中頃まで1年間にわたり,毎週1回,コミュニティクリニックや病院のプライマリケア医とともに患者を診るという内容です。「医薬品の適正使用」を学ぶには,このプログラムに1か月ほど取り入れるのがよいと考えています。学生はプライマリケアの問題を理解し始めていますし,臨床にもある程度慣れ,処方についても考え始めていますので,実際にこの問題が自分の学習と関わってくるからです。医薬品の適切な使用については,臨床薬理学だけの問題ではないのです。医学の基本に関わるものであり,どの医師も基本トレーニングとして医薬品をどのように選択するかを学び,自分の医療のレベルを上げなくてはならないのです。
津谷 この『Guide to Good Prescribing』(以下,ガイド)の著者は,オランダのグローニンゲン大学の臨床薬理学のメンバーですが,ヨーロッパで本書がどのように使用されているかをご存じですか。
ロス・ディグナン 毎年,グローニンゲン大で夏期トレーニングコースがあり,内容について講義をし,大学のカリキュラムにいかにこのガイドを統合していくかも教えています。多くのヨーロッパ人がそのコースで勉強しました。南アフリカやアジアでコースを開設したいという人もいます。
来日する1週間前にマレーシアで,各国の医科大学から臨床薬理学者やその他の医学部の人々に集まってもらいワークショップを開催し,このガイドを紹介しました。現在,さまざまな国でこのガイドを使い始めており,医学教育制度に統合する必要があるのか,また統合する方法はあるのかなどを討議しました。国の政策として検討すれば,同じ目的ですべての医科大学での教育が可能となります。
問題解決型の思考法
 グリーン 先ほどお話ししたように,この交換プログラムではPBLの手法を用いています。また今回,学生にはプログラムで勉強する喘息と呼吸器の炎症の2つの臨床課題について,さらに日米の医療制度についての参考資料をあらかじめ読んでおいてもらいました。しかし,実際に使うのは簡単なケーススタディで,当日にその場で学生に渡します。
グリーン 先ほどお話ししたように,この交換プログラムではPBLの手法を用いています。また今回,学生にはプログラムで勉強する喘息と呼吸器の炎症の2つの臨床課題について,さらに日米の医療制度についての参考資料をあらかじめ読んでおいてもらいました。しかし,実際に使うのは簡単なケーススタディで,当日にその場で学生に渡します。
学生たちは提示された症例について,『メルクマニュアル』あるいはその他の教材を自ら読むことで,自分の臨床知識を整理し適切な処方を学ぶことを目的としています。また,病態生理学を理解し,さらに社会的・文化的背景や,政策に関連することまで勉強しなければなりません。
津谷 東大ではPBLを実際の卒前教育に取り入れているのですか。
グリーン 私が知る限り,東大の学生がPBLを経験できるのはこの交換プログラムが初めてです。これは交換プログラムを創設した大きな理由の1つです。日本の学生には馴染みのない方法ですが,すぐにやり方を飲み込んだようでした。
津谷 私が受けた医学教育では,このような教育方法はありませんでした。薬の処方についても同様でしたし,また,例えば臨床検査では「どのような臨床検査があり,どのように行なうか」は勉強しましたが,「目の前の患者さんについてどのような臨床検査をどのように行なうのか」は勉強しませんでした。あるいは,医師としてどう振る舞えばよいのかについて,ほとんど教えられませんでした。
グリーン PBLが日本の医学教育に本当に統合するまでには,教育制度に大きな変化が必要だと思います。
医学教育における有効性
ロス・ディグナン このガイド使用にあたっての疑問点は,学生が今まで受けた医学教育のカリキュラムに関係なく使えるかどうかでした。実際には伝統的なカリキュラムで勉強した学生が,その方法で学んだ場合でもガイドの示す考え方を統合することができ,自分の持っている知識に応用できます。これが大切なことだと思います。PBLは教育方法の1つであり,必ずしもそれだけが最良の方法というわけではないのです。したがって,どの医科大学でトレーニングを受けている学生にもこのガイドは大切ですし,この思考方法を覚えるべきだと思います。津谷 このガイドを最初に読んで驚いたことは,医学教育制度,医療のサービス形態,あるいは文化が異なっていても,共有すべき点が非常に多いことです。日本でも大いに役に立つと思います。
 別府 医薬品の適正使用はとても重要だと思います。特に,日本の政策としても非常に大切で,現在政府は,年間1兆円単位で増加し続ける医療費を減らすことを最重要事項としています。その解決策としての医薬品の適正使用について,医学生が自分の問題としてとらえることができるよう,このようなプログラムを体験させることは非常に重要だと思います。
別府 医薬品の適正使用はとても重要だと思います。特に,日本の政策としても非常に大切で,現在政府は,年間1兆円単位で増加し続ける医療費を減らすことを最重要事項としています。その解決策としての医薬品の適正使用について,医学生が自分の問題としてとらえることができるよう,このようなプログラムを体験させることは非常に重要だと思います。
ロス・ディグナン 先生のおっしゃる通りだと思います。このガイドの編者の1人であるWHOのホーゲルチール氏が,「医学生にこのプログラムを紹介することは予防接種をするようなものだ」といつも言っています。この教材を取り入れることは,日本やアメリカだけではなく,従来から世界中で行なわれてきた医学教育の方法に,医師となった後の処方のあり方について予防接種を加えておくようなものです。医学生時代に従来の意味でのよい教育を受けても,医師としての仕事に慣れてくると,患者を1人ひとり丁寧に診る余裕がなくなり,また自分の医療を適切に批評してくれる人もいません。ですから,医学生時代に,医師として自身の仕事をどうしたら改善できるかという原則を覚えなければいけません。このような考え方は臨床の初期の経験の中で覚える必要があり,その後になると,身につけるのは難しくなると思います。
医薬品の適切な使用をめざして
INRUDの活動
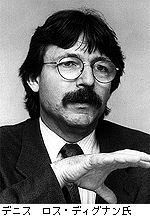 ロス・ディグナン 私の仕事のほとんどはINRUD(International Network for Rational Use of Drug)と関係があります。この組織は医薬品の合理的な使用をめざす国際ネットワークです。正式にはアフリカに5か国,アジアに5か国と計10か国ですが,非公式にはさらに多くの国で活動を行なっています。
ロス・ディグナン 私の仕事のほとんどはINRUD(International Network for Rational Use of Drug)と関係があります。この組織は医薬品の合理的な使用をめざす国際ネットワークです。正式にはアフリカに5か国,アジアに5か国と計10か国ですが,非公式にはさらに多くの国で活動を行なっています。
別府 私は約20か国からなるISDB(International Society of Drug Bulletin:医薬品独立情報誌国際協議会)の日本での活動として,「正しい治療と薬の情報」(The Informed Prescriber:TIP)の編集長をしています。このISDBとINRUDの目的は近いですね。
ロス・ディグナン そうです。INRUDはさまざまな組織にわたっており,1つの組織という概念ではくくれません。事務局はワシントンDCにあり,ハーバード大は,オーストラリアのニューキャッスル大やスウェーデンのカロリンスカ研究所とともに,現在3つあるINRUDの学術的なサポートグループの1つです。1年前から,ISDBとINRUDの間でさらに協力し合えるように話し合いが進んでいます。いま,それ以外にも医薬品使用に興味のあるさまざまなNGOとの間で協力を強める話が進んでいます。
今年の4月,INRUDはタイで医薬品の使用を改善するための国際会議を開催しました。特に,発展途上の国々が,どのように先進国から医薬品のインフォメーションを得て,また今後どのようなトレーニングやプログラムが必要なのかという諸問題を中心に議論しました。ですから,これから数年の間にISDBとの活動がより増えてくると思います。
製薬企業との関係
ロス・ディグナン INRUDでは現在,WHOで1988年に作られた医薬品のプロモーションに関する倫理基準がどのくらい守られているのかを,政府の活動や企業の宣伝,また医師や個人などから6か国で情報収集するプロジェクトを進めています。これは企業を批判するためではなく,むしろ企業の基準がどのくらい守られているのかをチェックし,改良すべき点を見つけるために作りました。このようなアプローチからは,客観的に広告を評価したり,各国がWHOのクライテリアを本当に守っているかもわかります。また,もしWHOのクライテリアが守られていなければ,守る必要があるのか,もし守る必要があるとすればどのように改善したらよいかといった話し合いが可能となります。津谷 例えば,発展途上国ではこのガイドを使ったトレーニングをするときに,企業のほうからの圧力は感じますか。
ロス・ディグナン 先ほどのWHOの倫理基準を用いたプロジェクトから話をしますと,このプロジェクトでは常に科学的,客観的なアプローチをはっきりと示すように努めています。ですから,医薬品がどのように処方されているか,処方せんは必須医薬品リストなどの基本的ドキュメントに基づいているか,もしそうでなければ,なぜかを検討します。検討の結果,1つの理由には,市場からの圧力の可能性があげられますが,医薬品を適切に使用していない理由は他にもたくさんあるのです。そしてさらに,どうしたら現在の医療を改善できるかというプログラムを作ります。これには時々企業にも参加してもらいます。医療を改善することにより,企業が利益を得る場合も多いからです。医薬品の使用法を改善することは,必ずしも使用回数を減らすことや,安い医薬品を使うことではありません。むしろ,いちばん利用効率の高い医薬品を使うことなのです。
多くの国で,企業は当初このプログラムにあまり乗り気ではなかったのですが,最近は以前より積極的に参加するようになってきたと思います。特に,多国籍企業ではその傾向がみられます。企業のほうでも,医療の改善によって利益が得られることがわかってきたのでしょう。自社の医薬品が効果の高いものであれば,そこに利益が起こります。つまり,きちんとした倫理基準を持っている会社は,この医薬品の適正使用の考え方に恐怖を感じる必要はまったくありません。実際に医療を改善したいと考えている企業と,もっと話をしようと努めているところです。
津谷 先ほどの話に関連しますが,どこの国でも医学教育カリキュラムを作り変えるのはなかなか難しいことです。そこで1つの可能性としては,コースまたは講座を新設することがあります。そうしたあり方の1つに冠講座があります。例えば分野は違いますが,東京大学の薬剤疫学講座は寄付講座として,最初の3年間はフランス系の製薬企業ローヌ・プーラン社が費用を出しましたが,現在,5社が費用を分担して運営しています。企業が医薬品の適正使用に関するトレーニングに興味があれば,日本には80の医科大学がありますので,このような講座やコースをどこかに作ることもあってよいと思います。
ロス・ディグナン 消費者である医師がさらに医薬品について知識を得れば,よい製品を作る企業にとって利益になります。ですから,最初から企業が医薬品を上手に使用できるような医師を養成するプログラムに参加できれば,これは素晴らしいと思います。
患者が得る利益
別府 医師と患者の関係については,日本はアメリカよりはるかに遅れています。日本では,患者は自分の治療法について全部医師に任せます。自分で決定することに遠慮しがちです。しかし一方で,「薬をもっと出してほしい」と医師に強い圧力をかける患者さんもいます。ですから,この教育プログラムを応用すれば,医師と患者の関係も改善されていくのではないかと思います。ロス・ディグナン その通りだと思います。私はこのP-drugのガイドの直接の作成者ではありませんが,ガイドをプロモートする人々と親しくしています。その人たちの希望は,各々の国や医科大学で,この考え方を最も適切な方法でカリキュラムに採り入れてほしいということです。必ずしもガイドの通りに行なわなければいけないという考え方ではありません。世界は広いですし,国によって医療の環境は異なり,医師と患者の関係も,医科大学の制度も違います。しかし考え方は「質」を最重視することで,一貫していると思います。
津谷 患者がこの教育プログラムに参加できるような可能性はありますか。例えば,私は医療技術評価の世界的なプロジェクトである「コクラン共同計画」に関係していますが,ここでは消費者が大きく参加しています。消費者が医療・保健の提供者側や教育に関わるというのは大きな意味があります。もし消費者がモデル患者として教育プログラムに参加すれば,学生は患者が一体何を考えているのか,また,医師にどのように圧力をかけるかがわかるでしょう。例えば,日本では通常病院で行なわれる医療だけでは満足せず,民間治療や鍼治療を行なっている患者がたくさんいます。しかし,医師に言わない場合が多いのです。内緒でそういう治療を受けています。
ロス・ディグナン アメリカも同様です。いままでどの国にも,このプログラムに患者が参加することはなかったと思います。とてもいいアイディアですね。特に,先生がおっしゃるように,学生がある決定をするときに何が起こるか,患者と医師はその瞬間にどういう関係にあるのか,患者が強い意見を述べているときに,自身が処方したP-drugが本当に適切であったのか,などのさまざまな場面で学生はいろいろなことを強く感じるでしょう。
P-drugとは何か
P-drugという考え方
津谷 このWHOが発行した『Guide to Good Priscribing』では,薬物治療の論理に基づいて医師が適切に選択した医薬品を「P-drug(Personal drug)」と呼んでいます。この意味について説明していただけますか。ロス・ディグナン 「P-drug」は,医師がよく診る患者の病気を治す医薬品グループのことです。効果や安全性,費用などを改めて考えてから,医師が通常,安心して処方できる薬品がP-drugです。またそれを再考するとき,2番目,3番目に使用する薬品も,当然考慮しなければいけませんから,1つのクラスの中で治療する段階的なアプローチとなります。それが大切なことだと思います。
しかし,私はP-drugについては,思想そのものはよいと思いますが,言葉自体は好きではありません。「drug of choise」のほうがよいと思います。その言葉に関連する別の思想があります。
別府 P-drugを初めて知ったとき,「自家薬篭中のもの」という日本語の表現を連想しました。「自分の薬籠におさめてあるもの」,つまり自分が自由自在に使いこなせる人物や技術のことを表す言葉です。ある特定の分野ですべてをマスターするという意味では,まさにこれはP-drugと同じ意味ではないかと思います。
津谷 自家薬籠に効かない薬や危険な薬が入っていてはしょうがないですね。P-drugとは自家薬籠の中に入れる薬をエビデンスに基づき正しく選ぶ,次いで目の前の患者に上手に使うということですね。
ロス・ディグナン その通りです。
日本の医薬品にまつわる状況
津谷 日本ではここ数年に大きな医薬品スキャンダルがいくつかありました。薬害エイズもそうですし,ソリブジン事件では,臨床試験中および市販後に,その薬品の使用によって15人が亡くなりました。これまでの厚生省の薬務局には2つの機能がありました。1つは消費者の保護です。消費者保護には,無効な医薬品から護ることと,危険な医薬品から護ること,つまり有効性と安全性の2面があります。そしてもう1つは製薬企業の振興・育成でした。
しかし1997年の7月1日から薬務局は「医薬安全局」と名称変更され,そこでは医薬品や医療機器の承認審査や安全対策について担当させ,企業振興・育成については「健康政策局」という,別の局の担当となりました。
ロス・ディグナン とても興味深いことです。このことからどのような変化が現れると思いますか。
別府 行政の組織機構と同時に,医薬品の価格設定方法も変わります。いまは政府が一定の水準に価格を固定していますが,企業からも反対が強く,価格は自由にすべきと言われてきました。このような状況の中でこそ,医薬品の適正使用という考え方は大きな影響を与えるでしょう。いまこそ日本にP-drugの考え方を広めるときだと思います。
このガイドの中には,企業側が受け入れにくい箇所があります。例えば,企業の情報をどう取り扱ったらよいのかなどがそうです。また実際に,企業の圧力によって,政府も医師たちも言いなりになる面もあります。しかし,日本でもこうした圧力に対する医師からのアクションは必要で,このガイドはその有力な武器の1つになると思います。
医薬品の「適正」使用
津谷 本書の日本語訳副題は『WHOのすすめる医薬品適正使用』です。しかし,WHOのいう“rational”(合理的)と日本でいう「適正」という言葉は,別の意味を持っているようです。今回の厚生省の組織変えの前には厚生省薬務局安全課に「医薬品適正使用推進室」がありました。「現場」で薬を適切に使いましょうという考えに立つ部署でした。しかし「合理的」というのはもっと大きなコンセプトで,薬の適切な供給も含めてのものだと思います。そこには,WHOのいう「必須医薬品リスト」のような考えも含みます。ご存じのように,いま日本の市場には,銘柄別品目数で1万3千種の医薬品があります。これでいくら適正使用といっても限界もあります。まず薬の種類を減らすことが必要です。しかし,この問題はとても厄介で厚生省は触れたがりません。あまり価値の高くない薬を作っている会社はつぶれるかもしれないためです。先ほど先生は良心的な多国籍企業は,「医薬品の適正使用」をサポートする可能性があると言われました。革新的な医薬品の開発ができるからです。しかし多くの小規模企業の生き残りは,販売促進にかかっているのです。ただ,こうした世界的な「医薬品の合理的使用」の時代には薬を販売する側の「自由主義」が制限されるというよりも,むしろ,企業も自然と淘汰される時代になったと考えるのも自然なことです。つまり今後,日本でも資本主義のメカニズムが働き,製薬企業の吸収・合併(M&A)がさかんになるでしょう。
一般名と市販名
ロス・ディグナン 医薬品の適切な使用,あるいは合理的な使用の基本となるもう1つの思想は,商品名ではない,つまりジェネリックネーム(一般名)の薬剤を処方することです。患者の治療にどの医薬品を選択するかは,どの「化学品」を使うべきかという視点で学びます。ですから,多国籍企業にもたくさんの一般名による化学品(ジェネリックドラッグ)を作っている会社が多くなってきたと思います。医師の最終的な決定は商品名ではなく「化学品」の質によるものです。津谷 日本ではこれもまた難しいことです。処方せんには商品名を使わなければならず,一般名は使えないのです。日本で処方には目的が2つあります。1つは医師が選択した薬品を患者が受け取ることと,もう1つは保険診療のためにその処方せんが使われることです。現行の制度では,同じ化学品を使用する薬品でも商品名によって別々の値段がつけられています。
別府先生は覚えていらっしゃると思いますが,1995年の第16回日本臨床薬理学会では,「一般名と商品名―商品名は本当に必要か」というファイアサイドディスカッションがあり,さまざまな意見が述べられました。日本の医師が欧米に行ったときに,商品名しか知らない場合は,医薬品についてのコミュニケーションができません。また阪神・淡路大震災のときに,救急の施設で患者が普段使用している医薬品を商品名で伝えましたが,医師がわからない場面が多くありました。阪神大震災は大きな事件でしたから,こういう意見は人々を納得させます。一方,企業は商品名によってこそわが社の製品に責任を持てると考えます。こうした対立を解決する1つの妥協策は,例えば「プラバスタチン・三共」のように,薬品にまず一般名を書き,それから会社名を書くことではないかという議論もありました。
ロス・ディグナン 第一歩として,それはよいことだと思います。アメリカでも,商品名と一般名は大きな問題になっています。もし医師が商品名を書くならば,薬剤師が別の医薬品を選んでもよいと許可する州もあります。一方,患者はある商品名で医薬品を使ってほしいと思っています。しかし,医師が両方を書くのはよいと思います。阪神大震災で起こったような問題を防ぐことができるでしょう。
誰のための適正使用か
別府 名称の問題はもちろん大事ですが,呼称の違いが患者にどのような利益や不利益をもたらすかを基盤に議論すべきでしょう。同一成分でありながら,呼称の違いによって,コストや効果までが異なるとすれば,名称は厳密に区別して使わなければなりません。しかし他方では,複雑な呼称の組み合わせがもたらす混乱,つまり処方ミス,調剤ミス,患者の思い違いなどは極力避けなければなりません。名称によって適正使用が阻まれることがあってはならないということです。もっとも,先ほど津谷先生が言われたように,「適正」という言葉はわかったようでわからない表現です。誰が,誰のために,何を根拠に「適正」と判断して,その薬を選択するのかが不明だからです。ある特定の権威者や委員会が決めたから,この薬を使うというのではなく,現実の診療場面で,どの人に,どの薬を,どのように使うべきかを具体的に考えながら選択していく,そのプロセスこそが大事なのだということをこの『P-drugマニュアル』は教えているように思えます。そういう意味では,本書が卒前・卒後の医学教育に与える影響は非常に大きいと言えます。
津谷 どうもありがとうございました。


